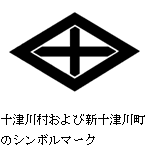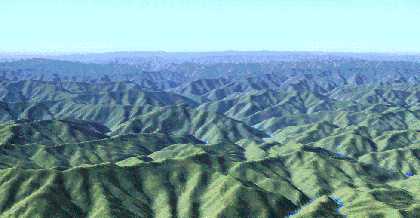
| 杮暥丂乽朶晽塉偺廝棃偲捠夁乿傛傝 |
8寧18擔
丂偵傢偐塉偺偁偭偨梻擔偱偁傞丅
丂栭柧偗偺嬻偼塤偺棳傟偑嬌傔偰懍偔丄幖偭偨嬻婥偑扟娫傪悂偒敳偗偰偄偭偨丅彊乆偵塉傪敽偭偨嫮偄晽偑悂偔傛偆偵側傝丄嬻偼埫塤偱枮偨偝傟偨丅栭偵擖傞偲塉偵傕傑偟偰晽偺惃偄偼傑偡傑偡嫮偔側傝丄擾嶌暔偑側偓搢偝傟傞傎偳偺嫮偄晽偵側偭偨丅
8寧19擔
丂塉偼寖偟偝傪壛偊丄屵屻偐傜偼傑傞偱僶働僣傪傂偭偔傝曉偡傛偆側惃偄偲側偭偨丅
丂栭偵擖傞偲晽偼師戞偵悐偊傞婥攝傪尒偣偨丅偟偐偟丄塉偺惃偄偼偝傜偵寖偟偝傪憹偟丄棆柭偲堫岝偑旘傃岎偆忬懺偵側偭偨丅
丂偁傝偲偁傜備傞扟娫偼戺悈偱堨傟丄憹悈偟偨揤僲愳傗廫捗愳偼寖棳偲側偭偰棆柭偝偊憕偒徚偡傎偳偵崒壒傪敪偟偨丅
丂憹悈偟偨寖棳偼嶳悶傪怤怘偟丄塉悈偺怹摟偟偨幬柺偼懌尦傪偡偔傢傟傞傛偆偵側偩傟懪偭偰扟娫偵撍擖偟偨丅偦偺恔摦偼嶳傪恔傢偟丄寖棳偲側偭偨壨愳傪暵嵡偟偨丅
丂幬柺偺曵夡偲壨愳偺暵嵡偑奺抧偱敪惗偟丄戝奀偺傛偆側怴屛偑偄偔偮傕弌尰偟偨丅
丂搚嵒偑恖壠傪杽傔丄戝攇偺傛偆側戺棳偑恖壠傪廝偆傛偆偵側偭偰丄廧柉偼婱廳昳傗怘椏傪帩偪弌偡梋桾傕側偔恎堦偮偱埮栭偺拞傪旔擄偟偨丅
8寧20擔
丂挬偵側傞偲晽塉偲傕偵廂傑偭偨丅偟偐偟丄宬棳傗壨愳偼憹悈偟偰堨傟丄寖棳偵傛傞怤怘偼巭傓偙偲偑側偐偭偨丅寖棳偼嶳悶傪偊偖傝丄幬柺偺曵夡偼懕敪偟偨丅怴屛偺敪惗偲寛夡偼側偍懕偒丄嵭奞偼偝傜偵奼戝偟偨丅
| 悈嵭帍尨暥傛傝 |
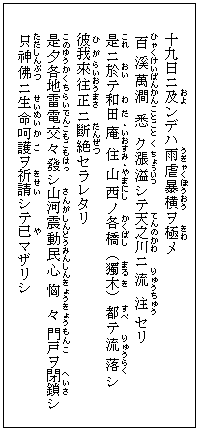
崙搚抧棟堾悢抣抧恾乮拲乯傪巊梡偟偰僇僔儈乕儖3D偱嶌惉丒曇廤
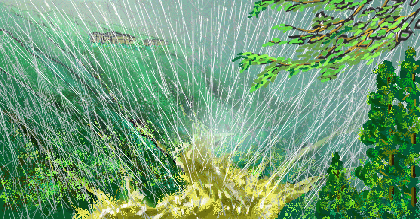


8寧20擔偺挬偵偼彫塉偵曄偭偰偄偨偑丄乽拞嶳乿偺幬柺偑戝偒偔曵夡偟偰椦怴屛偑偵敪惗偟偨丅
乮儅僂僗偑夋憸偺忋偵棃偨偲偒椦怴屛偺夋憸偵側傞乯
廫捗愳杮棳傪暵嵡偟偰惗偠偨怴屛偼偄偔偮傕偁傞偑丄椦怴屛偼嵟戝婯柾偺怴屛偱偁傞丅
丂丂乮拲乯偙偺抧恾偺嶌惉偵摉偨偭偰偼丄崙搚抧棟堾挿偺彸擣傪摼偰丄摨堾敪峴偺悢抣抧恾50000乮抧恾夋憸乯媦傃悢抣抧恾50m儊僢僔儏乮昗崅乯傪巊梡偟偨傕偺偱偁傞丅乮彸擣斣崋丂暯17憤巊丄戞431崋乯
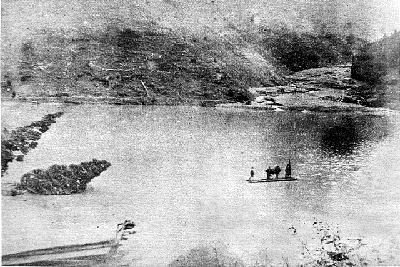 椦怴屛愓偵敵傪晜偐傋偰懳娸偵搉傞
椦怴屛愓偵敵傪晜偐傋偰懳娸偵搉傞丂椦怴屛偼敪惗偺摉擔偺栭敿偵寛夡偟偨偑丄寛夡屻傕幨恀偺傛偆側戝偒悈偨傑傝偑巆傝丄戭抧傗揷敤偼悈杤偟偨傑傑偵側偭偨丅
幨恀偼悈嵭帍暅崗斉傛傝乮幨恀巘拞搰嫪栘偺嶣塭乯
| 杮暥丂乽椦怴屛偺弌尰乿傛傝 |
戝帤崅捗乮廫捗愳嵍娸乯
丂8寧20擔偺挬丄憹悈偟偨廫捗愳偺寖棳偑乽拞嶳乿偺嶳悶傪寖偟偔愻偭偰偄偨丅嶳抧幬柺偺搚嵒偼塉悈傪戝検偵娷傒廳検傪憹偡偲偲傕偵娾斦偺暘棧柺偲側傞婽楐撪偵偼塉悈傗抧壓悈偑怹摟偟丄偦偺悈埑偼枾拝偟偰偄偨娾斦傪堷偒攳偑偡偐偺傛偆偵嶌梡偟偰偄偨丅偝傜偵丄寖棳偑晽壔偟偨嶳悶傪偊偖傝丄嶳抧幬柺偼崱偵傕懌尦傪偡偔傢傟傞傛偆側忬懺偵側偭偰偄偨丅
丂戝朇傪寕偪曻偟偨傛偆側堎條側壒偑愳嬝偵嬁偒搉偭偨丅
乮拞棯乯
丂偦偺屻丄崅捗偺廧柉偼巚傢偸岝宨傪栚偵偟偨丅屛偵偼悢廫偺壠偑楢側傞傛偆偵晜偐傫偱偄偨偺偱偁傞丅
丂摉擔乮8寧20擔乯偺栭11帪偛傠丄寛夡偟偨偲戝惡偱嫨傇惡偑暦偙偊偨丅尦婥惙傝偺抝偑僞僀儅僣傪庤偵偟偰娸曈偵妋偐傔偵峴偔偲丄丂揇悈偺悈埵偼50儊乕僩儖梋傝尭悈偟偰偄偨丅
丂旔擄愭偱偙偺條巕傪尒偨晈恖偼僞僀儅僣偑愳偵塮傞偺傪婼壩偲巚偄丄寛夡傪抦傜偣傞惡傪楈嵃偑媰偄偰偄傞偲巚偭偨丅偦偟偰丄偄傠偄傠側塡榖偑峀傑偭偨丅

揷敤偺旐奞
丂戭抧傗揷敤偲偄偆惗妶婎斦偦偺傕偺偑側偔側偭偨偺偑偙偺嵭奞偺摿挜偱傕偁傞丅
丂偳偆偵偐柦偑彆偐傝廧戭偑巆偭偰傕丄揷敤偺棳幐偵傛傝惗妶庤抜偑幐傢傟偨偙偲偵洎慠偲側偭偨丅
丂偙偺搚抧偵廬棃偺恖岥傪梴偆抧椡偼側偔側偭偰偄偨丅
| 杮暥丂乽峳傟壥偰偨嶳壨乿傛傝 |
丂怴屛偺壓棳懁偱偼寛夡傪怱攝偟丄婽楐偺擖偭偨廤棊偱偼曵夡傪嫲傟偨丅
丂塉偑崀傞偲奺壨愳偺忋棳傗巟棳偼丄拑怓偵曄怓偟偨戺悈傪揻偒弌偟偨丅
丂栭偲傕側傞偲嶳乆偵婖傑傢偟偄壒偑偙偩傑偟丄帪偵偼埆柌偵偆側偝傟傞傛偆偵旘傃婲偒偨丅
丂嶳偼側偍曵夡偟丄愳偼側偍斆棓偟偨丅
丂旐嵭柉偼巚偄擸傒側偑傜傕壗傪偡傞偱傕側偔偦偺擔傪曢傜偟丄巆偝傟偨彮偟偽偐傝偺敤偑偁偭偰傕庬傑偒偺帪婜傪堩偡傞傛偆側偙偲傕彮側偔側偐偭偨丅
丂媬彆暷傗媊漮嬥偺暘攝偑偁偭偰傕堦帪偺婌傃偱偁傝丄崱屻偺惗妶偺栚搑偑棫偨側偄傑傑偱偁偭偨丅
丂嵭奞偺彎愓偼怺偔丄壖彫壆傗曵夡偟偨傑傑偺廤棊偼峳椓偲偟偨宨怓偺拞偵捑傫偱偄偨丅
丂婹偊偨僇儔僗偑憶偖偲偙傠偵偼巰懱偑敪尒偝傟偨丅堦恮偺晽偺拞偵斶偟偔媰偔巰幰偺惡偑暦偙偊傞傛偆偱偁偭偨丅
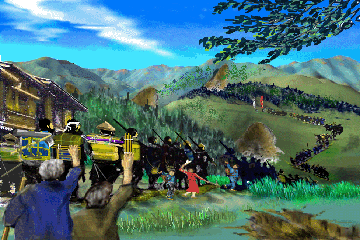
| 杮暥丂乽杒奀摴傊偺椃棫偪乿傛傝 |
丂嵭奞傪傕偨傜偟偨崑塉偺擔偐傜俀儠寧屻丄廫捗愳嫿俇偐懞偺懞挿偑夛崌偱杒奀摴堏廧傪寛掕偟偰偐傜侾儠寧屻偺偙偲偱偁傞丅
丂堏廧幰偼堏廧惪婅彂偺採弌偍傛傃嵿嶻偺張暘傗堏廧弨旛側偳偵杬憱偟偰偙偺擔傪寎偊偨丅
丂夣惏偺廐嬻偱偁偭偨丅
丂堏廧幰堦峴偼戉楍傪偔傒丄廵傪攚晧偄丄愭慶揱棃偺擔杮搧傪実偊偰恑傫偩丅
丂奺帺偺嵍嫻偵偼丄挬掛偐傜帓偭偨旽廫偺峠復傪晅偗丄愒敀偺戝婙傪棫偰偰丄埿晽摪乆偲峴恑偟偨丅
丂増摴偵偼巆棷傪寛傔偨廧柉偑暲傫偱尒憲傝丄恊愂傗桭恖偼壗僉儘傕偺摴傪偲傕偵曕偒丄暿傟傪惿偟傫偩丅
乮拞棯乯
丂堏廧幰偼擇戉偵暘偐傟丄堦戉偼杒廫捗愳懞偺挿揳傛傝揤捯摶偍傛傃屲瀶挰傪宱桼偟丄傕偆堦戉偼彫曈楬傪偨偳傝崅栰嶳偍傛傃嫶杮傪宱桼偡傞丅偙偺俀偮偺摴偼媫曬幰偑嬱偗墖彆暷偑撏偄偨摴偱偁傞丅
丂偙偺栭丄屲瀶挰偵岦偐偆堦戉偼戝搩懞偺暵孨偵廻攽偟丄崅栰嶳偵岦偐偆懠偺堦戉偼栰敆愳懞偺戝屢偵廻攽偟偨丅
丂19擔偼屘嫿偺摶傪墇偊偨丅
丂廫捗愳嫿偐傜戝嶃傑偱偼搆曕丄戝嶃偐傜恄屗傑偱偼婦幵偱偁偭偨丅
23擔偵偼恄屗偵摓拝偟偨丅
丂偙偺娫偳偙偱傕抔偐偄娊寎偲戝偒側惡墖傪庴偗偨丅
丂24擔偵墦峕娵偵忔傝丄杒奀摴偺彫扢峘偵岦偐偭偨丅
| 悈嵭帍尨暥傛傝 |
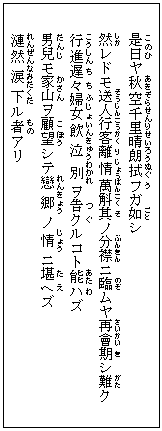
丂偦偺尨場偺戝晹暘偼柧帯22擭偺嵭奞偵偁傞丅
廫捗愳懞塅媨尨偺孲挿憳擄抧旇晅嬤傛傝廫捗愳偺壓棳傪朷傓
壨尨偺傎偲傫偳偼懲嵒偱幨恀偱偼嵒釯偑敀偔幨偭偰偄傞
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2004擭11寧嶣塭