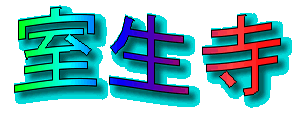
★TOP ★葛飾 ★柴又 ★旅日記 ★雑記帳 ★次ページへ
奥深い山と渓谷に囲まれた室生の地は
古くから神々の坐ます聖地と仰がれていました。

奈良時代の末期にこの地で山部親王(桓武天皇)の
病気平癒の祈願が興福寺の高僧によって行われ
卓効があったことから勅命により
国家のために創建されたのが室生寺です。

建立の実務に当たった修円は
最澄や空海と並んで当時の仏教界を指導する
高名な学僧であり、室生寺は山林修行の道場として
法相・真言・天台など、各宗兼学の寺院として
独特の仏教文化を形成しました。

高野山が厳しく女人を禁制したのに対し
女人の済度をもはかる真言道場として
女性の参詣を許したことから
『女人高野』と親しまれています。

金堂(国宝)は、正面側面ともに五間の
単層寄棟造りコケラ葺きです。
内陣には本尊釈迦如来立像(国宝)を中心に
薬師如来・地蔵菩薩・文殊菩薩・十一面観音が並び
その前に運慶作の十二神将が並べられています。

弥勒堂(重文)
3間四方柿葺の御堂で修円が
興福寺の伝法院を受け継いだものと伝えられています。
本尊厨子入弥勒菩薩立像(重文)と脇壇には
客仏の釈迦如来座像(国宝)が安置されています。

灌頂堂(本堂・国宝)
金堂左手の石段を登ると灌頂堂の前に出ます。
ここは真言密教の最も大切な法儀である
灌頂を行う堂で真言寺院の中心であるところから
本堂とも呼ばれ延慶元年(1308年)の建立です。
| 長谷寺へ | 旅日記へ | 次ページへ |