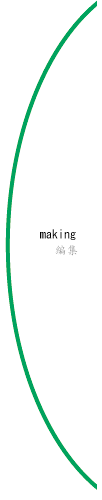 |
 |
1.編集していていちばん面白かったのは定信の5つの庭園のお話。国会図書館に残る絵図と定信や家臣が書き残したエッセイをもとに定信の造園に秘められた奇妙なサイコロジーを読み解いていくところがすばらしくエキサイティングでした。大塚の「六園」についての家臣のエッセイに「井手の蛙を取り寄せ給ひ、池に放ち給へり」とあり、「蛙を取り寄せる??物好きな」、と思っていたら、築地「浴恩園」に設けられた4つの関所(定信は関所マニア!)のひとつ、「山吹の関」から井手の蛙のナゾが解き明かされると言う!本書では図版がモノクロですが、カラーは白河市歴史民俗資料館&白河集古苑のHP、定信庭園コーナーで見ることできます。読み応えのある内容。以前開かれた「定信と庭園展」のコーナーも面白い。展覧会見たかったです。 | ||||||
2.定信はコレクターですが、ヘンなコレクターです。最高権力者で何でも手に入るのに(天敵、田沼意次を見よ!)、定信はけして実物を蒐集しない。カバーの「大仙寺起こし絵」のような模型をつくらせたり、絵師を遣わせて模写させたり、朽ちかけた古建築の瓦や壁片を蒐集したりしている。…とにかく何というか、屈折した回路をもったオジサンなんだよなあ。でも養子にいったり実家が廃絶になって乗っ取られたりと苦労人であったり、「源氏物語」マニアで全巻書写を8回(!)もしてたりと、ほんと教科書からは計り知れないおひとなんでした。 |
||||||||
3.定信はやたら随筆を書いているんだけれど、これも実際に読んでみると不可解なシロモノ。有名な「退閑雑記」にしても1/3くらいが民間療法みたいな話で、江戸の随筆ってそういうものだっていえばそうなんだけど、老中ともあろうお方がが「乳の出が悪いときは○○を煎じ」とかこまめに書いてるとやっぱ不思議デアル。「蛙の声をとどむるは、焙烙にて豆をいり、ほうろくともにその池へいるれば、こえむといへり」。……ね、わけわかんないでしょ。もうひとつ。「あるかたより大蝙蝠をみせぬ。琉球の産といふ。大きさ猫の子ほどありて、よくりうきう芋を喰ふ。両便するの外は、常にさかしまに下がりいるなり。物くらふにもさかしまのままにて食すなり。人々見てさぞくるしかるべしといふ。予ききて、蝙蝠は人を見ていつもわが糞するすがたをなすとて笑ふめりと云てたはれぬ」。キミは星新一か! |
||||||||
4.とにかく、意表をつく資料が意表をつくコネクションで結びついて全く新しい定信像、彼らのもっていた知識体系・世界像が浮かび上がってきます。スクリーチ先生のご本はいつもそうだけれど、構想力が素晴らしい。分厚い本ですが、「物を知るって楽しい!」って思いながら一気に読める本です。ぜひ! |
||||||||
home (c) Gettosha ltd./all right reserved |
||||||||