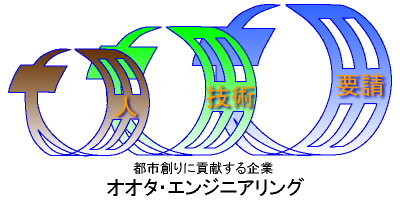わが国ではわずか10年ほど前にスイスの片田舎で生まれた、グロ−バリズムという怪物に襲撃され、国中が苦しみと閉塞感にさいなまれています。
私の会社は1999年2月建設CALS/EC(公共事業支援統合情報システム)を支援する企業を目的として創業後3年経過しました。
”新・中小企業基本法を読む”などいまさらという感もありますが 「新・中小企業基本法」というこの古くて新しい命題を経営者のひとりとして改めて吟味してみますと、 わが国の「大変」からの早期脱出を願わずにはおれません。
1999年の歳の瀬に中小企業基本法が施行されました。昭和38年に制定されて以来、初めての大幅な改正です。
その中身をみると、中小企業の定義をたとえば製造業では資本金1億円以上から3億円以下にするなど、中小企業施策の対象範囲が拡大されたり、創業者やベンチャー企業に対する支援施策を充実させるなど、”まさにグロ−バル時代を反映した”改正となっていることが注目されます。
しかし、今回の改正で最も注目すべき点は、政府の中小企業に対する考え方が根本的に変化したことであります。
これまでは、中小企業=弱者、だから「守るべき存在」として位置付けられてきたのです。大企業と比べて生産性や従業員の所得などに大きな差があり、この差を埋めるべく設備の近代化やスケールメリットの追及に手を差し伸べれれてきたのです。
しかし、新・基本法では、「守るべき存在」から「自助努力する存在」へと中小企業観を変えている。つまり、 ”独立した中小企業者の自主的な努力”を期待しているのです。
極端に言えば、こうした中小企業だけを支援しようというのだ。
「保護する」というより「生き残るところだけ伸ばす」という発想は、まさに自由競争・自己責任の時代にぴったり合っているというわけであり、好む好まざるにかかわらずまさに大競争という大航海時代に突入したわけです。
このような発想は、当社の創業の地である神奈川県中央地区および湘南地区において民間ベースでも、1999年時では、現実のものとなっていました。
日産・いすゞ等の自動車業界の系列取引の崩壊もいい例であります。
下請企業の系列外取引をひどく嫌っていた親メーカーが日産・いすゞの例を出すまでもなく、今では系列外に販売できるぐらいの技術力がないと取引しないと言い出すなど、ここでも様変わりの始末です。
当該地域の話となりますが当該地域では、この中小企業基本法の改正以前から大競争時代という怪物に早くから直面し、企業のリストラと熾烈なコスト削減を余儀なくされ血のにじむ努力をさせられております。
今般の法改正の結論としては、”独立した中小企業の自主的な努力”とは何かということになります。
それはマーケティング活動のことであり、自社の市場がどこにあり、どの顧客を狙っていくのかを明確にすることではな いでしょうか。
つまり、自社の市場を持っているから”独立した企業”であり、自社のターゲットとする市場を開拓するという顧客へのアクションが”自主的な努力”になる。
大競争時代に生まれた新基本法は、自ら経営の本来的な活動に長けた企業を味方してくれことを念じざるを得ません。
今、私たちは建設産業が大変なとき、建設産業が大昔から築いたシステムや歴史に 自信をもつ必要があります。
グロ−バル化の一方で、欧米では日本の建設産業は「勉強や研究をおこたらないで毎回新しい作品をつくる技術開発も含め共通の目標へ協力する体制」だと評価し、「パ−トナ−リング」とよび日本のパ−トナ−リングを他産業にも呼びかける等の動きも見逃せません。
私たちの会社は今後建設産業だからこそできる知的産業であり、情報産業であることを今一度認識し、既存の建設産業はもとより異業種産業のお得意先の方に対するご要望にもそえるように「人」、「技術」、「要請」をキ−ワ−ドにして情報関連事業の進展に努力してまいります。