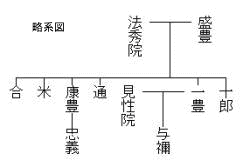|
||||
| 山内家の出自は藤原氏と言うことになっている。平将門を討った俵藤太こと藤原秀郷の流れとされる。 生年については諸説あり、はっきりしない。天文14年(1546)か同15年、同13年ごろの事だと考えられている。父親は岩倉城にあった織田信安の家臣で、尾張国黒田城主・山内盛豊(守豊)。一豊は次男で、十郎と言う名の兄がいたとされる。この他、弟・康豊、そして三人の女兄弟もいた(上略系図参照。ただし、通と一豊の長幼の順については未確認)。出生地についても愛知県岩倉市にある神明生田神社付近か、父が城主をつとめていたという黒田城内とする二説があり、これも一致を見ていないため、一豊生誕地の碑は現在、その両方に存在しているようだ。 父盛豊は岩倉織田氏の家老をつとめる武将だったという。しかし一豊の少年時代、尾張の織田家は諸派に分かれて抗争を続けており、最大勢力を誇っていたのは、織田信長だった。信安も信長によって討たれている。この戦いの中、盛豊と十郎もまた討ち死にしてしまった。父と兄が死んだ時期も未だにはっきりした事がわかっていない。弘治3年(1557)のことだとか、永禄2年(1559)のことだと言われている。 一豊自身の生年も決定的でないことから、「一豊**歳の出来事」という表現には馴染まないが、もっとも年嵩に見ても15歳のときには家族を背負っていかなければならなくなった、ということになる。何にせよ以後数年間は苦難の道のりを歩むことになる。尾張をはじめ美濃や近江を放浪し、一時期は近江勢多城主・山岡景隆に仕えたことがあるとする説もあるが、例のごとく、この時期の一豊の履歴には不明な点が多い。永禄10年(1567)頃に織田信長に仕え、流浪の生活にピリオドを打ったのは確かなようだ。 しばらくの間は特筆するほどの功績もなく信長に仕えていたようだが、天正元年(1573)。朝倉氏と戦った越前刀根崎の戦いで劇的な殊勲を上げている。朝倉家でも剛勇の誉れ高かった三段崎(みたざき)勘右衛門を組討の末に倒し、首級を挙げたのである。勘右衛門は強弓の使い手であったとされ、一豊は顔面に矢を受けながらこれを討ち取ったのだった。一豊の受けた傷は、左目尻から右奥歯にかけて矢が貫通するという、かなりの重傷だった。後日このことが信長の耳に入ると、信長は一豊の家臣に手ずから薬を与え、一豊の看病を怠りなく続けるように厳命したと伝えられる。ただ、「三段崎某」という武将については、『一豊公御武功御伝記』はじめ山内氏側の史料と、朝倉氏側との史料の間で不整合も見られ、このエピソードの信憑性について疑問を投げかける向きもある。一つだけ確からしい事は、この戦の後で一豊が近江唐国(滋賀県虎姫町)四百国の領主となった事だ。 その後、天正5年頃からは信長の直臣から羽柴秀吉の麾下に入った。そして、鳥取城攻めや高松城攻めなど、後に秀吉の経歴を飾ることになる多くの戦に参加している。その間にも、播磨有年(うね・兵庫県赤穂市)七百石、播磨印南郡五百石の知行を与えられている。やがて本能寺の変が勃発。一豊も秀吉の天下取りのために働く事になり、小牧長久手の戦いが終わった頃には、ついに近江長浜城五千石に入った。しかし天正13年(1585)、近江地方で大地震が発生。このとき、一豊夫妻の娘・与禰が崩れた建物の下敷きになって圧死するという悲劇的な出来事が発生した。一豊と見性院(千代)の間には、後にも先にも与禰以外の子はいなかったが、一豊は生涯、側室を設けることを拒み続けた。長浜時代に妾腹の子を拾い子として育てていたという当時のうわさも今に伝えられているが、拾い子はあくまで拾い子らしく、信憑性はあまりないようだ。 その後、一時期若狭へと移封されたが、二万石の領主として再び長浜に復帰。そして小田原征伐が完了して秀吉の天下が完全なものとなった時に、遠江掛川六万石に封ぜられた。この移封は、同じ頃江戸に入れられた家康を監視する目的のものであるとともに、家康が東海道を西上して大坂に攻め上がってきた場合の備えだったと言われる。 豊臣政権下で一豊は、一時期秀吉の甥・秀次の下につけられていた事がある。何事もなければ秀吉の後継者は秀次となっていたはずだが、秀吉が老境に差し掛かった頃、秀頼が生まれた。その結果秀吉は、秀頼を自分の跡取にすえるため、秀次を疎んじるようになっていく。両者の関係が冷え切るまでにはそれほどの時間はかからず、秀次の生活は次第に荒れていった。そして秀吉は、秀次の素行不良を理由に切腹を命じ、秀次一派に対しても徹底的な粛清を行った。しかし一豊は、秀次の腹心ともいえる立場にありながら、ほとんど奇跡的に難をのがれている。謹厳実直を地で行くような一豊の人柄を、誰より秀吉が知っていたためだと言われている。 慶長3年(1598)、秀吉が死んだ。ここで天下取りに向けて蠢動しはじめたのは、秀吉自身が危惧したとおり、徳川家康その人だった。石田三成は豊臣家中の反家康勢力を束ね、これに対抗しようとした。そしてついに武力衝突に至ったのが、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いである。この段階で大坂城に弓を引いて秀吉の遺児・秀頼と対決する形になることを避けたかった家康は、三成を城から誘い出して討滅するためにある企てを実行に移した。「会津の上杉景勝が秀頼に対する謀反を企てている。自分は秀頼の名代として、景勝を討ちに向かう」。対外的にそのように宣伝しながら、大軍を率いて東国へ向かった。 一豊も家康に従軍していたのだが、陣中にあった一豊のもとに、大坂にいた見性院からの文が届いた。文は文箱に入れられ、文箱には封印が施されていた。一豊は封を解かず、これを家康に献上した。箱の中に入っていたのは、三成陣営に属する増田長盛・長束正家が連盟した大坂方への勧誘状と、妻の添え状だった。妻の手紙には、大坂で三成挙兵の動きがあること、そして、自分のことはいいから家康に忠誠を尽くせという内容が書かれていたという。いかにもパフォーマンスじみているが、これは密書による妻からの指示に従ったものだったともいう。密書は使者の傘の緒に忍ばせておいたというが、そこまで行くとかえって作り話めいて見えてくる。なお、当初の三成陣営には、大名の奥方達を人質として手元に置く事で、家康に従軍した大名たちを自陣営に引き込もうとするプランが確かに存在していた。しかし、人質になる事を拒んだ細川忠興室・ガラシャが自害した事でこの方法がかえって逆効果になることを恐れ、露骨な人質工作はそれきりになっていた。見性院に先を見通す確かな目があったとすれば、ガラシャの一件でひとまず自分の身の安全が確保された事を悟っていたとしてもおかしくはない。 見性院の文を見た家康は、ついに三成が動き出したことを悟り、反転西上すべく軍議を開いている。その席上で一豊は、進軍経路上に位置する自分の掛川城を家康のために明渡すと公言した。これによって軍議の流れが決まり、参加していた諸将も、家康に味方して三成を討つ腹を決めた。 一豊はその後に控える関ヶ原の戦場では、手柄と言うほどの手柄を立てていない。西軍の盟主ともいえる毛利軍の抑えに配置されたが、決戦中、毛利はついに動かなかったのである。それでも、戦後には大幅加増の二十四万石で、土佐の高知に封ぜられた。戦前のパフォーマンスが効いたのだろう。決戦直前の一豊の動きを賢しらなものと見る風潮は強いが、最小の労力で最大の成果を上げた一豊と、そして千代の卓見は評価されても良い。 しかし土佐に入ったまでは良かったが、一豊はここで旧領主・長宗我部氏の遺臣、「一領具足」への対応に手を焼く事になる。彼らは長宗我部氏が本拠地にしていた浦戸城に立てこもり、一揆を起こしている。一豊はこの一揆に参加した273名をなで斬りにし、首を大坂の井伊直政に送った。この一件後、長宗我部の遺臣の中でも身分の高かったものは他国に士官の口を求めていったが、下級武士による抵抗はその後もしばらくの間続いた。この問題は一豊の在世中には決着がつかず、山内氏による土佐統治に不満を持つ長宗我部遺臣の中には一豊の暗殺を企てるものまでいたため、影武者を立ててその襲撃に備えたと言われるほどだ。最終的に彼らは「郷士」として山内家に認められる事になるが、明治維新を迎えるまで郷士と郷士以外(上士)の間には厳然とした階級差が存在し続けることになる。坂本竜馬の伝記の中にまで見られる、土佐藩固有の身分差別である。なお、この流れの中で浦戸城は廃城となり、新たに河中山城、後に言う高知城が築かれた。 慶長10年(1605)9月20日、一豊は60歳を一期にこの世を去った。実子はなく、家督は弟・康豊の子、忠義に継承された。 |
||||
| |
||||