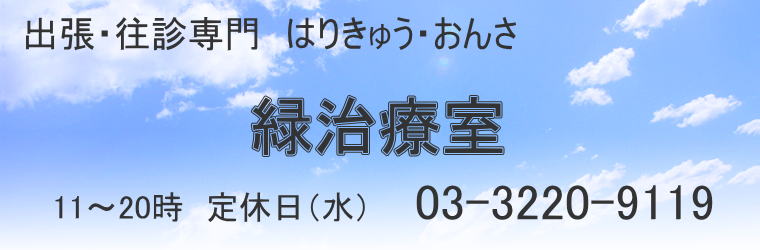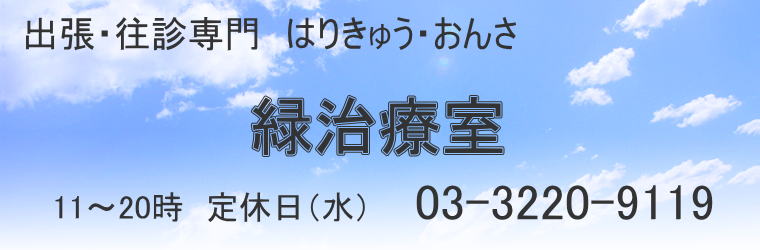|
|
<気と身体>
古来、東洋には万物には気というエネルギーが存在し、その流動と調和により世界が成り立っていると考えられていました。
日本では”気(き)”中国では気(チー)”インドではプラーナと呼ばれています。
そして全てのものがこの”気”と関与し影響しあってます。マクロでは宇宙全体、ミクロでは素粒子に至るまで気の法則に従っています。
人体にも気は存在し、各器官の細胞ひとつひとつから気(エネルギー)は発生し、身体の隅々に渡って流れて調和を保っています。
”気”の不調和は人体では言葉のごとく”病気”となります。
東洋では気の概念を元に世界感や宗教が発展し、医学も体系されました。
現代でも中国の伝統医学(漢方医学)では陰陽五行説を基本に針灸や湯液(漢方薬)や導引などで病気の治療を行っています。インドではアーウルウエ-ダー医学が体系され、ヨガなどによりでプラーナ(気)の流れを調整をしています。
”気”は身体器官だけでなく精神的な影響も及ぼしています。
身体においては気は一定の法則で循環し各器官で流れがあります。
気の流れが乱れたり停滞したりすると身体の不調を生じます。
気持ちが良い(悪い)気が多い(少ない)、気は晴れる(落ち込む)、気が乗る(乗らない)、ひどい状態だと”気が違う、気が狂う”など多くの言葉が昔から使われています。この中でも特に感情を表す表現が非常に多いのです。
人においては身体機能、器官のみならず意識、思考、感情がこの生体エネルギーにも関与されていることが分かります。
具体的に気分がいいと身体を伸ばしたくなり、気分が悪い(気が落ち込んで)呼吸がし難くなり身体は前屈みになります。
体内では気は内部循環と外部との交換を行います。
体幹部を中心として主に頭部、両手、両足、生殖器と6方向に流れています。
気功などでは良く気の廻りをよくする動作を行います。
<気の滞りと不調>
心身に疲労やストレスが溜まると身体の各部に気が滞り、筋肉の緊張を及ぼし一部に筋肉が緊張して硬くなり骨格の歪みを生じます。
さらに物理的に同一姿勢で長時間仕事をしていたり、無理やり身体を動かしすぎたり、睡眠不足が続いたりするとさらにに身体は歪んできます。
普通は自覚できますが中には自身の身体の不調を感じない方もいます。
○ 身体の痛みや凝り、重怠さ。
○ 疲れやすい、やる気がでない
○ 胃腸の調子がすぐれない
○ 深呼吸しにくい。動悸がする。
○ 風邪を引きやすい。
○ イライラする、キレやすい。
○ めまい、顔色が悪い
○ 手足が冷える、浮腫みやすい。
○ 外傷の痛みの治りが良くない。
○ お腹がすっきりしない。
○ 肌があれる。
○ 顔の歪み、O脚、X脚がひどくなる。
(背骨や骨盤の偏位ですので調整すれば一時的に良くなります。)
これらの症状は身体機能が一時的に低下している時で”未病”の状態です。
病院で検査しても異常がないと言われる場合は気の流れが滞り身体の歪みが原因となっています。
長期にわたり気の滞りがあるとやがて器質的な疾患となります。
気の滞りには独特の波動が在って身体の各部位や内臓器官などがその振動(気の質)の影響を受けて症状を現します。
<姿勢との関係>
心身の不調は姿勢によく現れてきます
* 良い姿勢
左右対称でバランスが良い。
腰がよく伸びて反っている。
肩甲骨が内側に入っている。
適度に胸が張り呼吸が楽。
骨盤が上がっている。
* 悪い姿勢
左右の重心が大きく偏る。背骨、骨盤が歪む。
猫背になる。
腰が強張る。
骨盤が下がる。
ふくらはぎが張る、足がむくむ。
腹筋が緊張し胸郭が広がらず呼吸しにくいなど。
<肉体的負荷による身体は歪み>
物理的な面においても人間は二足立位で生活をしているため身体的な構造上、頚、肩、背中、腰、膝に負担がかかる様になっています。、
特に人の頭は重いため、その重さが頚にかかり、腕の負担は肩に、そして上半身全体は骨盤にて支え、両脚で左右のバランスを取りながら身体全体を支えています。
更に背骨は本来、S字状の形で、身体バネの芯となって地面からの衝撃を直接、頭に与えない様にしています。
それ故、頚、肩、腰、膝等に症状が出現し易く、特に同一姿勢位を長時間続けていると各部の負担が強くなり各部周辺の筋の過緊張を生じさせ、凝りや痛みを生じし易くさせています。
また、一部の凝りや痛みの在る筋肉は異常に強張っている事が多く、身体の歪みは、むしろ筋の緊張の偏りと言った方がよいかもしれません。
筋肉は骨に付着しているため筋肉が緊張すれば骨と骨を繋いでいる関節部に負担がかかり、最終的には、身体の基となる脊椎や骨盤の変位になるのです。
従って身体に歪みは、局所的な症状が存在する場合は、一部の筋緊張の偏りが身体全体に係わっている事を現しています。
各筋肉自体は局所において大きく分別していますが治療経験上、筋繊維自体は流れによって連なっていると思われます。
症状と原因が離れた処に在る場合が多く、殆ど脊柱と骨盤が関与しています。
例えば膝ですと大腿四頭筋やハムストリング、頚は脊柱起立筋、腰は腸腰筋という具合に筋の起始は骨盤由来ものが多く在ります。
<身体の硬さ>
身体には、適度な弾力性が必要です。
緊張が強く身体が強張ってしまうと体力、気力とも衰えてしまいます。
特に腰は、反りが伸びやかな程、活発で疲労に対しても回復力も有ります。腰が硬く引けてくると逆に物事に対し消極的になってきます。
精神的なストレスが強く、腰が張ってくるという時は同時に腹筋が緊張して身体が前かがみになり姿勢も悪くなり呼吸も浅くなります。
<身体の歪みを自分で治すには>
歪みの原因は身体の一部の筋緊張の偏りですから、その原因となっている疲労筋を緩めていきます。軽度筋肉の緊張は、其のポイントをご自身で軽く押さえるだけで緩んできます。
筋の緊張が解れてくると症状の起因となってる脊柱の椎骨や骨盤が緩み骨格が元の位置に戻ります。
この際、強い力で身体にに刺激を加えたりする必要は一切無く、調整出来ます。
軽い歪みは、楽な姿勢をとって頭と体を休め、リラックスして意識を呼吸に向けて深く息を吐くことしていると緊張が緩み楽になります。
また軽く身体を屈伸する矯正体操を行う(息を吸いながら左右の手を組み腕を上げて胸、お腹、背中、腰を伸ばす)だけで改善します。
痛みが強い時や局所に炎症を生じてたり、身体の緊張の度合いが強すぎる、また器質的に組織が硬くなってしまった場合などは、時間をかけないと、改善しにくい事も有ります。
身体の不調には必ず原因が存在しています。
外的環境や飲食物、人間関係、そして自身の潜在的な感情の抑圧など、不調に至った時ほど客観的に自分の生活のことを良く知る機会だと思います。
心身とも疲労する事により心か部-骨盤内に筋緊張を起こし胸部及び仙骨周囲筋が硬くなり呼吸がしにくくなります。当然代謝が悪くなり免疫力が低下します。
私達の身体中には以前、飛沫や直接感染したいろいろな菌やウイルスが常在しています。普段免疫力が強い時には活動しないのですが自律神経が機能低下すると免疫力も低下し活動域まで達します。
もちろん悪化すれば急性炎症などにより化膿したり組織破壊や変性も生じてしまいますが不定愁訴といわれている症状で慢性疲労症候群や鬱病、原因不明の関節痛や筋肉炎などにもキネオロジ-テストの反応により感染が関わってい様に思います。
悪性腫瘍においても菌やウイルスが発症の起因になっている場合も多くあります。
<神経系との関わり>
筋-骨格系に歪みがあると神経系にも影響を生じます。
神経系の中枢は脳、背骨の中に在る脊髄からなり、そして末梢神経より成り、その働きより、筋肉を動かす運動神経、五感を司る知覚神経、自らの身体を調える自律神経が存在し、神経の中枢で在る脳と密接に関わり人体を常に統率しています。
身体の歪み、つまり筋の過緊張の偏位、脊椎や骨盤の変位が神経に影響を与え反射的な作用によって様々な異常を身体に生じさせる事になります。
また身体内部、内蔵系の異常が体表に現れ、特定の筋の緊張が歪みの原因となっている場合も在ります。更に精神的な無意識の緊張が筋の緊張として体に現れる場合も在ります。
この場合は鳩尾(みぞおち)から胸郭、腹部、骨盤内にかけて硬くなります。勿論、外傷などの衝撃が骨格系に歪みを生じさせ、後から身体異常をきたす事もあります。
局所的に調子の悪い部は筋-骨格-神経の作用で血行不良を生じ、病巣を造り易くしている場合も多様にあります。
<自律神経の働き>
緊張すると身体は硬くなりリラックスすると緩みます。
緊張しすぎて体の力が抜けず、身体が硬くなってくると眠りが浅くなり、副交感神経が働きにくくなり、心身のバランスが乱れてきます。また、逆に生活にはりがないと交感神経の働きが鈍くなり、身体の自律作用が鈍って抵抗力が弱くなり、体調を崩し易くします。
大切なのは生活の中で適度な緊張、弛緩を持つ事です。
<呼吸について>
吸気は交感神経、呼気は副交感神経と関連しています。
呼吸を改善させるという事は身体のバランスを調え気の滞りを治す目的もあります。
背骨の中には脳から連なる神経の束で脊髄というものが在ります。
この脊髄から更に末梢に神経が繋がっていますが、その各脊椎に領域があり、各領域範囲において様々な働きをしています。
特に内蔵系とは密接な関係と働きが在り、常に脳と連絡を取り合い身体を正常に整えています。各領域を大きくみてみるとおよそ次の様な関係となります。
脳神経(動眼、顔面、舌咽、迷走神経)-眼、鼻、口腔、心臓、呼吸器、肝臓、胃、膵臓、等 (副交感神経系)
胸椎 (D1~3)- 呼吸器、免疫系、等 (交感神経系)
(D4~6)- 循環器系、等 (交感神経系)
(D7~9)- 消化器系、等 (交感神経系)
(D10~12) - 泌尿器系、等 (交感神経系)
腰椎 ( L1~5)- 生殖器系、等 (交感神経系)
骨盤 (S、O)-脊柱の動きを統括、 (副交感神経系)
胸郭は背骨のうちの胸椎、肋骨、そして身体の前にある胸骨によって構成され籠状になっています。呼吸をする事で胸郭が動いて、胸腔か広がったり、狭くなったりします。胸に手を置いてみると胸郭が動くのが確認できます。
深呼吸をすると胸が大きく膨らみ、胸郭が広がります。
身体全体で呼吸が出来ていると全身の筋肉が呼吸とともに可動し、血管が広がり血行血流がよくなり、内蔵の働きが活性化します。また酸素量がふえる事で熱エネルギーが増大し体温が上がり、同時に身体が冷えにくくなります。
大きく息を吸うと身体は極まり、吐くことで緩みます。
呼吸は人間の自律作用と深く関わり身体や精神を安定させるのに最も有効的な方法です。
意識せず、深く大きな呼吸が出来ている時は体調もよく気力も充実しています。
逆に身体が歪み胸筋が硬くなり腹筋か張ってくると横隔膜の動きが制限され、呼吸が浅くなります。
当然,酸素-二酸化炭素の交換量が少なくなり全身の代謝が低下し身体機能の低下を生じます。
特に女性はワイヤーの入った下着など装着することで胸郭の動きを制限してしまいさらに胸筋や乳房、肋間の組織を硬くしていることで自律神経や体温低下による冷え、肩こり、腰痛などの症状を起こしていることがあります。
<胸郭と骨盤>
胸郭と共に呼吸に対し大きな役割をしているのが仙骨です。仙骨は腸骨ととに骨盤を構成している背骨の下に在る三角形の骨です。
骨盤は左右の仙腸関節と恥骨によって支えられていますが、これらの関節が硬くなると全身に影響を与え、身体全体を硬くさせ、歪みを引き起こします。
特に仙尾骨、仙腸関節は呼吸によって胸郭と共に動き、身体を整えています。
治療の際、胸郭と骨盤が調整が中心となります。
人体でも大事な場所です。
<痛みと呼吸>
痛みは呼吸と関係が深く、腰や頚などの痛みは呼吸筋の調整を行うだけで楽になる場合多くあります。
呼吸が深くなると自律神経-交感神経と副交感神経のバランスがとれ酸素供給により過敏になった知覚神経を抑制し痛みが軽減します。
<外因、内因による作用>
病気にはさまざまな原因や要因があります。
分類別にみていきますと大きくは身体の外的要因と内的要因に分けてみます。
外因)
外因には環境の状況や事故なのでの衝撃より物理的な要因があげられます。
環境要因として季候による温度、湿度によるものがあります。
日本は四季の変化が大きく寒さによる冷え、暑さからくる熱中症や脱水、乾燥による粘膜下の障害、湿気による水分代謝不全によるむくみや血行障害など、また最近では大気汚染やシックハウス症候群、花粉などによるアレルギー症状があります。
次に食べ物の問題です。
近年では多種多様の食品添加物(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)、劣化油など使用のファーストフードやスナック菓子、菓子パンなどもあげられると思いなす。
日常コンビニやスーパーや土産店で売られているものの殆どはこの部類です。これらの食品は少量食べてもアナキラフィーショックを起こす以外危険ではありませんが長期間の摂取や常食化、また睡眠不足や体力の低下など解毒作用の低下に伴いアレルギーによる免疫性の炎症を皮膚や粘膜各部に症状を現します。特に低年齢の子供には注意が必要です。
また免疫力低下による感染菌やウイルスの増大による各関節や軟部組織に異常を生じ易くします。
女性の場合は食べ物がホルモン系に関わり作用すると乳房や生殖器などに悪影響を及ぼし女性特有疾患に至りやすいと言われています。
万物には全て固有の波動が在ります。実体の在る物や無い物、場所や空間にも存在しています。もちろん身近にある生活用品や食べ物、ペットなど自身の周りにあるすべて自分を含めてお互い気を干渉し合っています。自分では良いと思って買ったものも実は良くない波動を持っていることも多いです。
できれば自分の周りを良い環境にする事です。
家の中を整理し気持ちの良い居場所を作る事が大事です。それだけでも心身に随分変化があると思います。
内因)
内因としてはストレスによるものが大きいと思います。
ではストレスとはなにか、その原因は何か考えてみる必要があります。
<心の影響>
先にも触れましたが、人は必要以上に精神に抑圧を受けると心も身体も硬くなり、其のエネルギーが凝縮され、限界に達するとエネルギーが噴出し突発的な行動を取ったり、何かに依存的になったり、自分でも自身の欲求を押さえられなくなったりします。
最終的に心身ともコントロール出来なくなって破壊的、自壊的思考に至ります。
また不安も強くなると感情エネルギーが強くなり客観的に考える事が出来なくなります。
これは脳の構造の仕組みにも関わっています。
脳の表面には運動や感覚及び、理性や思考をコントロールする大脳皮質が存在し、脳の中心に近づくに従って生命の基本的維持に必要な領域、大脳辺縁系が存在し、ここでは情動行動(恐れ、怒り、不安、抑鬱、悲しみ、喜び等の感情行動)や本能行動(食欲や性欲等)を司り、その中心には自らの身体を整える自律神経の中枢や代謝を司るホルモンの中枢、視床下部や下垂体が存在しています。
心身とも不安定な時の意識下では、恐怖心や不安感が強く働くため、どうしてもマイナスのイメージが心身に対し強く影響を与え、自律神経に乱れさせ余計に身体が緊張し症状を悪化させる原因となります。
また、イメージが潜在意識に働くと、其の存在力が大きくなるに従って、良くも悪くもイメージが現実化してしまうのです。
調子が悪く日々身体の事ばかり気にしていると神経が其処に集中し、余計に気になって心身を痛めてます。
また不安により身体をいたわり過ぎている場合も無理をし過ぎるのも同じ位に良くない事です。
<気の特性と感情>
気はエネルギーのため自然の物理的法則に従って作用しています。
エネルギーには振動(波動)があり量的強さと振幅の速度があります。
殆どの方はこの気の波動によってご自身の身体と精神(深くは魂のレベルまで)作用されている事に”気”がついていないと思います。
漢方では五情(喜 、楽 、怨、 怒、 哀)、五志(怒、 喜・笑、 思・慮(考)、 悲・憂、 恐・驚 )は五臓(肝、心、脾、肺、腎)に影響を与えるといわれています。
感情は脳内ではいわば本能(欲求)に近い所で作用しています。
感情は大脳辺縁系内(古脳、旧脳)で自律神経やホルモン中枢である視床下部、扁桃体に加え綱様体賦活系が前頭葉(大脳新皮質)に作用し、自律神経系に影響を及ぼし信号を延髄に伝え内臓や筋肉、皮膚など身体全般に影響を与えます。(詳しい作用は専門書をご覧になってください)
感情は体の各部に気(生命エネルギー)の停滞を生じ留まることで周囲筋の緊張などにより血行不良を招き、血液流動不足により酸素、必要栄養素や免疫などが各器官の細胞や神経の作用に障害を与えて自然治癒力低下させ、痛みや免疫機能の弱体化により各種ウイルスや菌が付着し炎症を生じさせてしまいます。また炎症の長期化にあたり時には細胞形成不全や変異などの器質的変化をも生じさせてしまうようです。これがいろいろな病気の機構だと思います。
気のエネルギーは感情や意識によりそのエネルギー量や気の流れに影響を与え変化します。
自然科学での熱力学の法則では
第一法則;どのような変化が起ころうとエネルギーは保存される。
第二法則;エントロピー(普遍的無秩序)の法則に従う。
ストレスなどで感情により発せられたエネルギーは形をかえて発散されていきます。
怒りや憎しみでは何かに対して殴ったり蹴ったり投げたりすることで力学的(ジュールで表せます)変化します。
思いや不安などでは自律神経を介しホルモンなどへの化学的変化を生じさせます。
発散しきれなかったエネルギーは筋内をなど体内に留まりその量的な増大は圧縮され筋肉の緊張(こりや痛みの原因)をもたらし神経反射により内臓機能に不調をも生じさせ各感情により特異の振動を発散します。
また感情エネルギーを抑圧し続けることで蓄積されたエネルギーは抑制が外れて外部に発散されれば社会的にいろいろなトラブルを生じさせ、また内に発散すれば抑鬱や痛みやさまざまな疾患となって自身の心や身体を傷つけてしまいます。
人同士では表面上は感じなくとも必ず心の深部でお互いの気を感じています。
感情的な強い関係は良くも悪くも相互的に持ち併せた感情が作用しあい情や敵意、トラブルを起こします。
全ての感情は振動(波動)の現れです。感情が強ければ強い程、震えを生じます。
強い感情を発したあとは震えを感じた事が有ると思います。
問題が生じたときは自身のの心の深部(潜在意識)を観る事が多々必要かと思います。
-怒り-
骨盤から上腹部から溝打ちにかけエネルギーが上昇し頭部まで達しここで止まります。強く早い波動で一気に動きます。頭部、季肋部周辺臓器(膵臓や肝臓など)に影響すろようです。(頭部顔面などの血流不全、胃の上部、、肝臓、胆嚢、膵臓など)頭、首、肩、背中などに影響をあたえます。抑圧されている感情が大きいと一気にエネルギーが拡大します。あまり強いと理性を失います。時に暴力や暴言的行動、気の振動がつよくイライラした気持ちが所謂貧乏ゆすりのようにあらわれます。
-恨みや憎しみ-
怒りの念が深いと恨みや憎しみになってエネルギーは骨盤底に留まり圧縮されます。普段の振動は早くて細かいですが非常に力が強く、この感情は抑圧されていることが多く表面上は現れませんが何かしら情動が生じると振動が強くなり圧縮されたマイナスのエネルギーを周囲に発散します。(下層次元と共鳴します。振動は早くて細かいですが非常に力が強く)骨盤内臓器(生殖器、腸-肛門)仙腸関節由来の身体各部の関節炎による強い痛みなど生じることがあります。頭部、顔面や頚部にも症状が現れる事もあります。
-強い思い、悲しみ-
おもに胸部の筋緊張による胸郭内の機能低下、呼吸器、循環器に影響します。気管支、喉、肺、心臓、乳房など慢性的な不調があります。胸背部の筋肉の緊張を生じ頚部、背部、腰部の筋肉の痛み、こりなどの症状が生じます。いわば胸が締め付けられるように苦しさを伴います。
考え過ぎや思い過ぎ;腹部全体に作用し胃や小腸、大腸など機能を低下させます。頚、肩のこり(側面に現れやすい)としても現れます。
-不安、心配、恐れ-
主に泌尿器、免疫系に作用するようです。アレルギーによるアトピーや皮膚炎や鼻炎、喘息、免疫不全による関節痛など、また頻尿や膀胱炎、痔や腰や脚など痛み(坐骨神経痛や膝、足など)や足の冷えなどの血行不良にも関係あるようです。
不安は感情のなかでも最も深い所にあります。その根本は自身の存在の消失と思われます。純粋なる愛(自己犠牲に値する)以外のいろいろな感情は不安より生じていると言っても過言ではないと思います。そのためそのエネルギーは強く一度不調に見舞われると長く続きます。
-性に関わること、嫉妬、妬み-
生殖器、乳房など男性、女性特有の臓器に反応します。異性に関わること、男女の関係に留まらず異性の親子関係にも原因を生ずることも在るようです。また憎しみや恨みなども骨盤底にエネルギーを溜めていますので影響されると思います。
気の流れについて書きましたが本来、生殖器に流れる気が下方に流れずエネルギーが頭部に逆流すると性エネルギーが頭に上昇しアブノーマルな状態に至ります。これは目に現れます。そうなってしまうと性に関わる意識が自分自身でコントロール出来ず異常行動をおこします。
感情は経験によって複合的に作用し病的変化も複雑化する事が多くあります。
感情はその量的強さと反対の感情を持ち合わせています。
怒りや憎しみなど敵対する感情はその量的な強さと同様に不安感を持ち合わせています。
怒りやすい人は逆になにかに対し常に不安感や恐れを抱いている事があると思います。
また常に不安感を表に出してる方も同様に潜在的にあることに敵対意識を内在している事も在ります。
また正論や正義でも強い情念的意識を持つと排他的なマイナスのエネルギーを同じ分だけ持ってしまいます。
親しい方を心配するということは一見良いように思われますが心配の元は自身の不安から発していますので相手に対しても自分に対してもマイナスの波動を発してしまいます。無私の状態で祈る事が大事です。
恋人や夫婦間、親子間や社会的な上下関係など、関係に共依存に至った場合、支配する側と支配される側に関係が成り立ってしまい抑圧された感情エネルギーが発生しバランスが取れなくなったときトラブルが生じます。
特に親子間においては世代をこえて問題が継続してしまいます。
良くも悪くも全ての事が原因と結果であり自身のの因縁は自身で請け負うことしか出来ません。
但し、その業は行いによって軽くすることは可能です。
肝心な事は心の奥の自身の感情と向き合いそれをコントロールすることです。
感情の波動はフラットに近づけることが理想です。(抑圧は換えってエネルギーを貯め込みます)
ヨガでは呼吸を限りなく少なく減らしていくことで感情をのエネルギーをコントロールして無に近づけていきます。
まづは心身をリラックスして呼吸を制御することで感情さえもコントロールします。
<脳の機能低下>
慢性的心身疲労や常習的に劣悪な食生活により免疫力が低下すると身体各部の常在菌やウイルスが増殖し活動傾向に至ります。
脳も当然影響を受けてしまいます。キネオロジ-テストでも連鎖球菌の反応が多くみられます。
それにより脳自体も機能が低下に至り、思考力、判断力、記憶力などが低下します。
さらに悪化すると感情、情動、本能欲求が強くなり自己抑制力も低下し依存的性格が強くなる傾向になるように思います。
そうなる本来の自制が利かなくなり被害者意識が強くなり社会的なトラブルを生じたり、自己嫌悪に至ったり躁鬱的な感情変化が生じてしまう事も考えられます。
脳は神経の中枢なので自律神経やホルモンなどのも影響を及ぼすと思います。全身の気の状態ても気の偏りが観られます。
気滞上昇傾向-落ち着きがない、不安心配が強くなる、自分の感情が抑えられない、過呼吸になる。躁的な感情変化
気滞下降傾向-落ち込んで身体を動かし難い、ため息を多く吐く、自己嫌悪に陥る、鬱的な感情変化。
酷くは長年に渡り脳機能低下状態で、かつ強いストレス下に置かれていると感情エネルギ-が増幅しさらに圧縮され心の奥に根付いてしまいます。そうなるとケアには長時間、必要になります。
<身体の緊張>
不調時には必ず身体の強張りや歪みを生じています。
不均一な筋緊張により全身こ骨格に歪みが生じます。
整体やカイロはこの歪みを対象に身体を診ます。
では歪み自体がなくなり全て骨格が整えば良いかと思いますがそうではありません。
特に身体が強張って免疫作用が低下体内在中の菌やウイルスが増殖し感染症状を呈しています。
筋肉の緊張は病巣を拡げさせない様に思います。関節痛の殆どが感染菌やウイルスが関与しています。
また患部の神経に感染があると本人の意思に関係なく周囲筋が異常に緊張している場合があります。
身体の筋緊張は本来、外部からのストレスや炎症時の患部の保護でもあります。
ストレスによって筋緊張をもたらせている場合、大本のストレスが解消出来ていないのに無理矢理筋肉を弛ませ骨格をもどしても後から身体は逆に筋収縮を起こし一時的に痛みを発症させる事が在ります。
好転反応や揉み帰しといわれる中にこのような状況が結構あります。
<身体の治癒反応>
心身の緊張により身体が一時的に硬くなって血行不良になっている状態から治療を行い元の柔らかい躰に戻ろうとする時、必ず身体内に一定の反応が生じます。
筋緊張があると血行障害をおこします。
血流が悪くなると神経に異常を生じ痛みや痺れを起こします。
感覚も鈍くなっったり逆に過敏になることもあります。
過度な緊張は関連部位の運動神経にも影響を与える事もあります。
治療により自律神経が安定してくると筋弛緩され、血流の改善とともに感覚が戻って痺れ、痛みが楽になります。
若干の汗や便の排出(排泄)と共に元に戻ってきます。
この様に身体は鈍く硬くなると、一連の反応を通し自らの体を調整します。
疾患等、発症して短いものは反応も速く治りも良い場合が多いのですが、長期にわたり、硬くなり過ぎたものは反応もにぶく、また、急に過敏反応に転じた場合は一時的に症状が悪化した様になる事もあります。
特に知覚は一定の刺激に対し慣れてしまうと鈍くなります。
長く、調子の悪い事に慣れてしまうと、自身の感覚では、その状態が普通になっている事が多くあります。
一連の痛みや風邪をひく前やアレルギーを起こす前は必ず身体は硬くなり、そして発症します。
体内に溜めていた排泄すべき物質を熱や痛みなど、外に排出させ様とする力が働く為、不快感や苦しさを伴います。
このときは体内に熱が発生するため、息や便などが臭く事もあります。
身体を治すには排泄反応後、発熱後一時的に体力が低下するのでこの時期にしっかり休む事が必要となります。
治療後も心身ともゆっくり休むことが大切です。
|
|
|
|