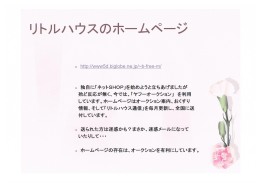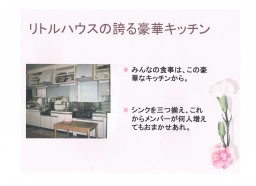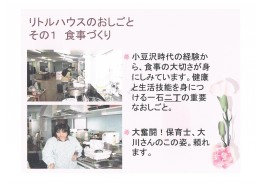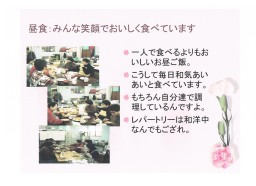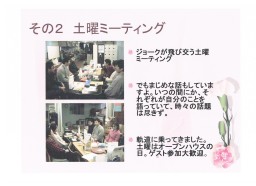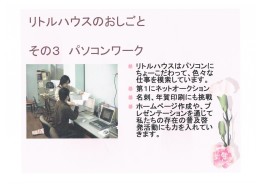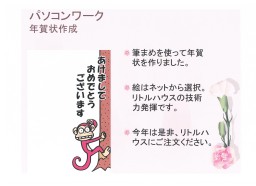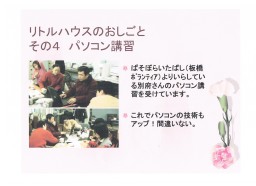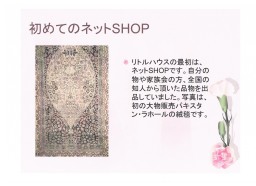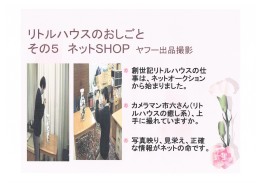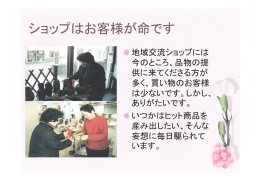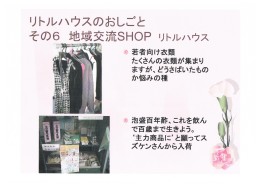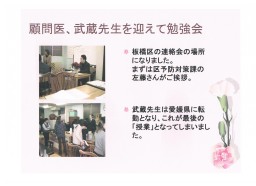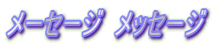NO,95 2011年8月17日発行
過去ログ 2011.5 ラ・ドロン(町田市)よりリソグラフ頂く!(5月17日) 町田市の通所授産施設ラ・ドロンよりリソグラフ(印刷機)を頂けるとのお話があり、簡単な施設見学も合わせて引き取りに伺いました。 この印刷機(写真右)、面白いエピソードを施設長の中村さんが教えて下さいました。共同作業所から通所授産施設(社会福祉法人)新築の移転の際、引越し業者が誤って印刷機を落としてしまい、その補償として来たのがこの印刷機、だそうです。 かなり重く、車への搬入出に苦労しましたが、町田では中村さん、リトルではメンバーの皆さんに手伝って頂き、運び終える事ができました。(梁瀬 光輔)
昨年同様、今年も旅行委員の皆様にはお世話になっています。 今年は4名の方で運営されています。 みなさんの要望を聞きながら、2日間の企画、昼食場所の予約などなど…。 今日は大詰め、バスの座席表を練っていました。 皆さん 撮影に快く 応じて下さいました。 この日、都合で一足早く帰られた中村さんからはコメントを頂きました。 「旅行の前日はお風呂に入って早く寝て体調を整えて少し早く起きて元気で行きましょう。」 予報では石和方面の天気は、大きな崩れはない様ですが…。それぞれの思い出に残る旅行にしたいですね。 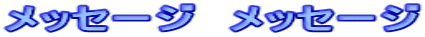
②被災地に 命受け継ぎ 咲く水仙 (作者より…豊) ①藤棚で優雅な香に引き寄せられて、我を忘れ花房の間を泳いでいる虻を見て…。
②命の尊さが、水仙に象徴されていると感じました。 PО法人アドボケイト会第2回役員会3月12日(土) 於リトルハウス pm2:00~ 第1号議案 作業所リトルハウスの報告と利用者の承認 1、共同作業所リトルハウス 事業報告 H22年3月14日~H22年12月11日まで 2、メンバー承認 H22年3月14日~H22年12月11日まで 第2号議案 就業規則の変更、見直しについて 第3号議案 グル―ホームの経過報告 第4号議案 作業所とグループホームの今後 グループホーム ピアホームⅠ、Ⅱの12月~3月までの経過報告、ピアホームⅠには現在5名が入居。Ⅱには3名が入居。ピアホームⅡで1名退所者があったが、後に入居予定者がいることを報告、入居説明会、認定調査などが予定されていると話しました。11月より行なっている非常勤に秋月さんの代替えサポートと食事補助を中心の業務について、全体食事会を月2回、個別食事指導各自月1回ペースが定着、食事の安定や家族のように食事をする楽しさがあり、入居者から好評であること、処遇改善事業については、2月22日付けで決定通知書を受け取り、引き続き、準夜勤手当として支給していくことを報告しました。 次回はH23年5月21日(土)総会開催予定です。 4月13日 お花見&太極拳(赤塚公園) 「寄せ鍋に 諸行無常の 桜散る」 豊子 寄せ鍋、ちらし寿司、千田特製?ライスボール、いちご…。 このほかにゲストの方々からの差し入れもあり、桜の下での食事を、特製甘酒?と共に堪能しました。 しっかり食べた後は、2月に好評だった加藤さんの太極拳でしっかり体を動かしました。(写真↑) 帰りに ニリン草の前で集合写真 ニッコリほっこり^^ お疲れ様でした。 2011.3 2月28日 太極拳 諸々の忙しさから、以前はよく行なっていたスポーツレク(バレーボール)が行なわれなくなっていました。 そこで久々のスポーツレク、今回はピアホーム世話人千田耕平の大学時代の先輩、加藤健二氏をお招きして、太極拳講座を開きました。 DVDやプリントを用いながら太極拳の起源「小寒論」~気・血・水に基づく中国医学~基本(姿勢や呼吸、中程度の緊張でゆったりと)を解説、右の写真のように実際に行ないながら解説して下さいました。 気(き)…「気」の充実 呼吸で酸素供給 血(けつ)…血流の停滞防止 血液サラサラ 水(すい)…水分調節 リンパ液の円滑化 免疫力の向上 ●上記は単独ではなく、関連、毎日の生命活動の根幹となる。 そして、毎日続けないと意味がないのでテレビや新聞を見ながら、靴下をはきながら等「ながら運動」を勧めていました。 例:壁に背をぴったりつけ体の軸をチェックする、 動きそのものは比較的取り組みやすく、ちょっとした動きだけで体が楽になったと話された方がいました。 今回は単発の企画でしたが、新年度も検討したいですね。
新幹線の見える綺麗な日立ソリューションズの社員食堂脇のスペースは、各事業所と社員さん方の熱気でむせ返る程でした。リトルハウスの自主製品(せっけん、アクリルたわし、テッシュカバー)は食べ物ではない為、当初苦戦しましたが、お二人の力で盛り返すことが出来ました。(梁瀬 光輔)
3月17日に、メンバーの菊池忠夫さんが急逝されました。 菊池さんは、リトルハウス開所式の頃からのメンバーで、名刺作成ソフト「名刺郎」を持ち込み、リトルハウス名刺作業の礎を築かれた方です。昨年、お母様を亡くされた後は、一時落ち込まれたものの、再びリトルに通われるようになり、最近ではヘルパー制度を活用、少しずつ生活のリズムを掴んでいるように感じられた矢先、突然の訃報でした。告別式にはリトルハウスSt・メンバー等11名が参列、全員で赤いカーネーションを捧げ、最期の別れをしました。天国でお母様に手渡されている事と思います。 菊池さんのご冥福をお祈りいたします。 以下 お別れのコメントを紹介させて頂きます。 前日まで、通所されておられましたので、にわかには信じられませんでした。折しも、東北関東大震災で多くの方が亡くなられており、生きていることと死ぬことの境は、偶然に左右されているという思いが強まっているさなかでした。菊地さんのそばで、たまたまドラえもんのどこでもドアが開き、それが天国の入り口だったような気がします。ちなみに、菊地さんはドラえもんに似ていたと、私は思います。 リトルハウスの開所式が、通所初日の方でしたので菊地さんの思い出はたくさんあります。開所式の希望に満ちた雰囲気そのままに、うれしいスタートでした。パソコンが得意で、リトルの作業に貢献していただきました。 去年、お母様を亡くされてから、生活に大きな変化がありました。支えが必要な環境だったことは間違いありません。どのようなことが、必要だったのでしょうか?もう少し、話を聞いてあげれば良かった。健康管理の配慮が不足していたのでは?と具体的に悔やまれることもあります。 良い思い出と共に、無念の思いが残りました。合掌 千田 豊子 ・ご冥福をお祈りいたします。A・I ・菊地さんとは短いおつきあいでしたが、ご冥福をお祈りいたします。M・S ・菊池さんいつも電話してくれてありがとうございました。忘れないよ。S・S ・菊地さんとは短い間だったけど楽しかったよ。どうもありがとう。Y・T ・よく名刺の仕事をもってきてくださいましたよね?ありがとうございます。今でも菊池さんがリトルに来る声が聞こえてきそうな気がします。ご冥福をお祈り致します。H・Y ・菊池さん、私達リトルのメンバーを天国で見守っていて下さい。Y・H ・菊池さん、とおくに行ってしまったような気がしますがリトルハウスではともにすごした日々の記憶は忘れていません。天国でお母さんと一緒に暮らして下さいK・N ・菊池さんには色々とかわいがって頂きましてありがとうございます。天国からみんなの事を見守って下さい。大変お世話になりました。感謝致します。ありがとうございました。 ・いつも元気な姿が印象的でした。ご冥福をお祈り致します。E・H
1・20 精神保健福祉連絡会フォーラム 「新しい障がい者制度が変える、誰もが暮らしやすいまち、いたばし」
しかし法の改革となると、その根底となる理念から議論していく為、時間がかかるようです。その間、ほぼ自立支援法の枠組みは、改善を含みつつ固まっております。作業所からの自立支援法移行につき運営側として困難を抱えている当作業所としては、この点につき割りきれない思いが残ります。 それはともかくとして、障害者総合福祉法の制定のために障がい者制度改革推進会議が設置されました。その委員であり、全国精神保健福祉会連合会理事長としてご活躍の川﨑氏から、お話をうかがいました。 会議の目的は、①国連で採択された「障害者権利条約」の批准に向け国内法の制度改革を行う。障害者権利条約については、以前藤井氏の講演で、学びました。 その条約は、国連で審議され、世界共通の基準が設けられたすばらしい内容の物でした。 条約批准するための、国内法の制度改革に含まれるものとして、 ②障害者基本法の抜本改正 ③障害者総合福祉法の制定 ④障害者差別禁止法の制定、があります。 川﨑氏から、②、③、④について、詳しく教えていただきました。 内容詳細は、割愛させていただきますが、感想としては、 「法律を定めるということは、本当にたいへんなこと」だと思いました。何か一部に反対することは、簡単だけれども、構築することは、難しいことです。その法は、障害者のあらゆる場面を、想定し網羅していなければいけないし、差別や、矛盾があってもいけない。現代世界状況にみあった人間学の思想的、倫理的視点から十分論議される必要があります。 法は、神通力を持っているので、障害者のあらゆる困難な場面に、その力は威力を発揮し助けてくれるような法であってほしい。川﨑氏のお話をお聞きし、精神障害者の今の困難な状況に理解が深く、困難を拾いあげ法として取り上げて頂き、それぞれのことを審議していただいていると感じました。何かこれまでは、壁のように感じていたこと、困難を抱えることが当たり前のように思っていたことが、決して当たり前ではいことに気がつきました。差別の中に放り込まれていると、差別の正体がみえなくなってしまうものです。差別の正体は、差別感にもとづいた法が施行されているせいであり、差別が、法により拡大定着していたことに、気がつきました。これまで普通に法だと思っていた法律の中に、制限、制約という形で、精神障害者への差別思想が含まれている法が結構あると思いました。 (具体例:保護者制度、精神科特例、精神保健福祉法の在り方…入院制度・人権保障、医療法と福祉法を分ける等…講演の中から) また基本的な障害の捉え方が、医学モデルから、社会モデルへと変更されました。障害者の社会参加の制限や制約の原因が、障害者個人にあるのではなく、機能障害と社会的障壁との相互作用によって生じるものである。ということです。この考えに基づき、支援の範囲や内容がこれまで以上の良い方向に広がるという川﨑氏のお話を伺い、未来は、きっと良くなると元気づけられました。(千田豊子) 2011.1 2011年を迎えて 皆様 明けましておめでとうございます。 新年に入り寒さが厳しくなり、特に山陰地方の大雪が連日報じられていますが、こちら東京では晴天に恵まれています。私の自宅は、快晴の時は富士山が見えるのですが、連日付近の山々まで良く見え、休日に洗濯物を干しながら眺めていると、否が応でも清清しい気持ちになります。 同じ「改正」でもこちらは「突如として上程され、十分な審議もされずに成立したことは、遺憾であると言わざるを得ない(日弁連会長宇都宮 健児氏のコメントより)」、障がい者自立支援法の改正案(正式名称:「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」)が昨年12月3日、参院本会議で民主・自民各党などの賛成多数で可決、衆院では11月18日に可決されており、改正障がい者自立支援法は議員立法として成立(議員の発議による法律、日本の国会の場合、成立する法律案の大半は内閣提出)しました。 H25年8月成立を目指す「総合福祉法」(仮称)までのつなぎとはされていますが、基本的には1割負担が残ってしまう事、当事者の方々の意見を十分に聞き反映できたか?依然状況としては多くの懸念を抱えた、流動的な状態が続きます。 このような状況の下、リトルハウスとしてはH24年1月を目標に、就労移行継続支援B事業への移行を考えております(基本計画については12月11日の役員会第4号議案をご覧下さい。)NPО人材開発機構の方の協力を頂きながら、移行後も安定した運営を目指すべく礎の年にしたいと考えております。 地域の皆様 リトルハウスを今年も宜しくお願いいたします。 (梁瀬 光輔) NPО法人アドボケイト会第1回役員会12月11日(土) 於リトルハウス pm2:00~ 第1号議案 作業所リトルハウスの報告と利用者の承認 1、共同作業所リトルハウス 事業報告 H22年3月14日~H22年12月11日まで 2、メンバー承認 H22年3月14日~H22年12月11日まで 第2号議案 就業規則の変更、見直しについて 第3号議案 グル―ホームの経過報告 第4号議案 作業所とグループホームの今後 第1号議案について メンバー募集のため11月から通所した時点で1ポイント・12月から昼食を100円とすることを試験的に行っていること、作業所プログラムについては、新しく石鹸作りのための製造機、粉砕機の購入予定を報告しました。 第2号議案について ①常勤・アルバイト職員就業規則について②アドボケイト会就業規則変更について 作業所非常勤Stの忌引き休みについて、非常勤・アルバイト職員には労基法では定めていないので、各事業所に任せているのが通常であるという意見が出ましたが、当法人としてはゆるやかな対応でいいのではないか」と話が出ました。 又、アドボケイト会就業規則内年次有給休暇について『連続した○日間』と記載するのがよいという提案がありました。 第3号議案について ピアホームⅠには現在5名、Ⅱには3名が入居、人事報告としてピアホームⅠ・Ⅱの代替サポート・食事援助を担当する非常勤Stとして秋月美紀さんが11月1日より入職、合わせて了承されました。 第4号議案 作業所とグループホームの今後 H24年1月から就労移行継続支援B事業開始予定、基本計画として①事業内容と利用者計画 ②施設設備 を説明しました。 事業内容としては現行事業、せっけん事業の充実により利用者開拓を行い、15名程度の利用者獲得を目指します。 施設設備として、高島平4丁目に購入可能な土地があり、現在公示待ちです。ここに木造2階建てで就労継続支援B事業として主に石鹸事業、グループホーム6部屋、グループホーム事務室を設置予定です。現在グループホーム・ピアホームⅡは3部屋なのでさらに3部屋の拡張、ピアホームⅡの事務室も作業所と共同の為その設置も行います。土地確保ができない場合、PC講座としてのスペースを別で借り運営を行います。 ●理事会終了後は、おでんやお寿司等を囲んで、理事の方々とメンバーとの交流会が秋月さんの歓迎会も兼ねて開かれました。 2010.12 板橋区就労前研修で学んだ事③ 質疑応答から 職場開拓について 地域…飛び込みや℡、支援センターに入ってもらい紹介 ポイント:「この人ならできるのでは」と思わせる! ・どんなことができる・いいところを売り込む。 ・むやみに就職活動するのではなく、できれば事前に調べる。 (ハローワーク情報・実習等の活用) 求人状況 ・ 知的障害は求人増だが… ・ 精神は求人少ない(統合失調症、うつ、発達障害など様々な状況に加え他障害に比べ勉強不足?) ※ 大企業:社員の中でうつによる休職増加、更に積極採用とはいかず、二の足を踏む状態? 準備不足…求める人材情報不足・ミスマッチ・社内雰囲気の影響? 但し特例子会社等で精神障害を中心に採用する会社も見られ可能性はある。 ポイント:服薬も含め、どれだけ通所施設などで急な欠席(特に無断・長期欠席)がなく、決められた仕事をこなせるかアピール! (梁瀬 光輔) 2010.11 板橋区就労前研修で学んだ事② 採用面接について 面接でよく聞かれる質問…(ポイント:自分の口で語る!) 1、自己紹介 2、職務経歴…入るきっかけ・仕事の内容。※職務経歴書は履歴書よりも重要、職務経歴が無い場合は自己紹介書を提出すればよい。 3、長所・短所…よく出る質問だそうです。 4、志望理由(以前の職の退職理由)…ポイント:自分が応募する会社は何をやっているのか?(例:アパレル企業で「パンを作りたい」?・・・志望企業の業務を把握していない) 5、希望する仕事・給与「言われたらなんでもやります」では駄目。面接官はできるかどうかは別として、自分が具体的にやりたい仕事を(例:清掃、PC等)どれだけイメージしているかを聞いている。 6、将来の目標 7、障害について…ポイント:自分の言葉で説明。障害状況、通院、配慮点(例:視覚障害、PCは読み上げソフト使用、書類はデータで。) 面接で企業がみるポイント ●コミュニケーションスキル・ソーシャルスキル・ビジネススキル ●支援体制(支援センター、家族など) ●障害状況 ※面接同行において支援者に求められる事 ・面接の間は見守る(黙ってしまっても口を出さない、支援者は面接官から促されたら話す)。 ・面接の最後に面接者が答えられなかった部分を補足(本人のセールスポイントを明確に~得意な仕事、性格など)←どんな事ができるのか発信! ・本人のセールスポイントを明確にする(得意な仕事、性格、支援体制) 同行者のビジネスマナー 身だしなみ 男性スーツ/ネクタイ(白いシャツで)袖や襟の汚れや擦り切れ、パンツの折り目に注意。爪、鼻毛、口臭(直前に刺激物を食べない、口をゆすぐ。)…清潔感を! ★クールビズ…あくまでも社内で作業する場合(面接・同行では通用しない!) 女性ナチュラルメーク(ノーメークは×、せめて口紅を)、スーツが望ましい・せめて黒・ベージュ系のジャケットを羽織る、スカートの場合ひざ丈のもの、カラータイツ・生足は×、必ずストッキング着用。ブラウスは白・淡いパープルなものを。 名刺交換…相手の名刺に目の前で書き込むのは失礼(相手の顔に書き込む行為に値する。) 1、部屋に案内されたら席に座って待つ。 2、担当者が入ってきたら席を立ち名刺交換。 3、名刺は机の上に並べる。 4、帰る間際に名刺をしまう。「名刺を頂戴いたします」 ○就労継続の秘訣・・・企業、支援者、家族が相互に協力し早期の課題解決に取り組む。 2010.10 9月18日 中野区東都生協会館3階で行われたie-coopフェスティバルに参加してきました。こちら、初めての試みのようで主催者側も開始までドキドキの緊張感が漂っていました。リトルハウスはせっけんを主に培養土、手芸品を販売しました。受付の向かいという場所的に好条件でしたが呼び込みも自由とのことで、来るお客さんみんなに声をかけていきました。 いらっしゃいませ~ 販売実績はせっけん17個、培養土6個、アクリルたわし5個、テッシュケース1個で合計金額3100円の売り上げでした。コープでもせっけんを販売していたのにこの売上!やはり千田耕平さんの実験コーナーが功を制したのかな? 休憩にはミニゲームをやってフェスティバル自体の盛り上げにも貢献してきました。来年も参加できればいいですね。(木谷 由紀江) せっけん、培養度、手芸品です!
板橋区就労前研修で学んだ事① 9月21日、グリーンホールで区主催の支援者向け講座として、サンクステンプスタッフ(テンプスタッフ特例子会社)工藤雅子さんのお話がありました。現実的な内容を簡潔なお話されていましたので、今月より数回に渡り、利用者の方々にも参考になる内容を簡単にご紹介したいと思います。(梁瀬 光輔) 「社会人」として企業が求める人材とは 基本的なビジネスマナー…(企業側の意見)マナーが身に付いた段階で来て欲しい! あいさつ…大きい声ではっきり「おはようございます」「(お先に)失礼します」 言葉遣い…敬語・丁寧語(です・ます調) 時間を守る…出勤時間5分前 体調管理…食事・睡眠・投薬管理 身だしなみ…服装・頭髪・入浴 報告 連絡 相談(ホウ・レン・ソウ)…コミュニケーション(仕事でわからないこと・不調)を取る。その際話していいかどうか確認し自分から行く。また、仕事が終わったら「出来ました、次はどうしたらいいですか?」…自分からメッセージを発するスキルを! 「社会人」として求める人材 ●コミュニケーションスキル(ホウ・レン・ソウ、あいさつ、言葉遣い) ポイント:自分から発信できる事! ●ソーシャルスキル(身だしなみ・敬語・) ポイント:社会的距離を保つ、 学校では生徒と先生、施設では利用者とスタッフ、といった親しみのある人間関係に比べ、会社は上司と部下、会社≠友人! ●ビジネススキル(具体的には入職時に指導) 指示通りに仕事、集中力、識字力、数操性(電卓は使えるか?)巧緻性(器用さ) パソコン…仕事で使う云々ではなく、採用基準としてチェック (=筆記用具のひとつとして、履歴書にPC関連の資格を書くと有利では?) ※では入職時にどこまで求められるか?文字が書ける=入力、メール対応(仕事の指示などのやり取りがメールで指示が出る場面が増えている為) 2010.09 9月10日11日 「リカバリー全国フォーラム2010」 9月10日(金)11日(土)に文京学院大学本郷キャンパスで「リカバリー全国フォーラム2010」に出席してきました。当事者を交えたトークライブ、「WRAP-WellnessRecoveryActionPlan-(元気回復プログラム)」の考案者メアリー・エレン・コープランド氏による講演、大熊一夫氏による「リカバリーは精神科病院で実現できるか~イタリアでの経験を踏まえて~」の特別講演、分科会が開かれ「リカバリー」をテーマにした議論を行いました。 9月4日~ホットな就労支援者たちの集い♪(墨田区家庭C) とうきょう会議東部ブロックと千葉の就労支援関係者との交流から生まれたまれたこの集い、医療福祉機関、障害者雇用企業などから70名以上の参加者がありました。 (注)IPS(Individual Placement and
Support)…米国で1990年代前半にACTプログラムが展開する中で生まれた、就労支援に焦点を当て開発されたプログラムで、科学的に効果的であると証明された事実や根拠に基づいた援助プログラム (EBS: Evidence Based Plactice)のひとつ。日本語では「個別職業紹介とサポートによる援助付き雇用」などと訳されることが多い。特徴として、症状が重いことを理由に就労支援の対象外としない、就労支援の専門家と医療保険の専門家でチームを作る、職探しは本人の興味や好みに基づく、保護的就労ではなく、一般就労をゴールにする、生活保護や障害年金などの経済的な相談に対するサービスを提供する、働きたいと本人が希望したら、迅速に就労支援サービスを提供する、就業後のサポートは継続的に行なう、がある。~医療法人 福智会 勉強会のページから 2010.07 7・28 実験講座と家族交流会
梅雨も終わりにさしかかりましたが、夜間のゲリラ豪雨(板橋で1時間107mm!)昨年度末よりせっけん作りに力を入れていますが、その関連から油の処理など、外部から講師を招いた、環境にやさしい作業所ならではの企画と、リトルハウス家族会がリトルハウスと連携する形で主催し、H22年度の家族会と合わせて企画致しました。 第1部1:00~2:50 「くらしと環境―地球を守るエコライフ」のテーマで実験講座 講師:里見けい子先生(東京都消費生活講座よりお招きしました。) リトルハウスのせっけん販売も行ないます! 第2部3:05~5:00 家族交流会 ○ 自立支援法についての説明 ○ リトルハウスでの様子 ○ 家庭での様子 ○ 他の家族に伝えたい事 サービス管理責任者研修(就労分野)に参加して 7月2日(共通講義)・8、9日(専門講義・演習)と東京都のサービス管理責任者研修に参加しました。 先日の参院選で「ねじれ状態」となった民主党政権ですが、現政権においては H23年まで旧体系 H25年8月 新法施行 の予定と講義の中で話が出ました。間のH24年はどうなるのでしょう?気になりつつ聞いていました 特に参考になったのは最終日の演習でした。ケアプラン作成における支援内容を「支援内容」「誰が」「いつ」「どこで」ときめ細かくら実行する流れはPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)に沿った支援、この研修のみならず、現在のケアマネジメントが今までより客観的で、誰にもわかりやすい支援を目指している事を実感しました。また、新規事業の立ち上げる(もしくは今までの施設自主製品の売り上げを伸ばす)演習では①商品の設定②施設周辺の地域性③販売ターゲット④コスト⑤工程内容(St、メンバー、ボランティアの役割分担など)について討議しました。これまで地縁への販売に頼りなリトルハウスですが、今後この内容を取り入れて行っていきたいと思います。ケアプランから販売戦略まで、多岐に渡る業務ですが、一方で施設・援助の限界を知り抱え込まないこと、援助者個人のスタンドプレー(職人芸?)ではなくサービス利用者の希望と援助者のすり合わせで行うことが講義などで強調されていました。サービス管理責任者とは、この場合は就労を軸に、対人援助の基本が改めて問われ、実行できる事が求められているのではないか?そう感じながら、会場を後にしました。(梁瀬 光輔) 2010.05 22年度上半期東京仕事財団委託訓練事業PC講座始まる! 5月7日より、今年度のPC講座が始まりました。 8月6日までの約3ヶ月間、ワードやエクセル、パワーポイントを学びます。 今回もリトルハウスメンバーがサブ講師として、講師の先生と受講生の橋渡し役を務めています. 写真の左2枚から察すると、かなり忙しい様子ですね。
5・10の来訪者 AM 益子さん(ハート・ワーク) ハート・ワーク(板橋区障害者就労援助事業団)とは、板橋区に住む障がいのある人が、職業に就き、社会参加できるよう就労支援事業、又、障がい者雇用をすすめる企業に、職務内容にあった方をご紹介している機関です。 どんな紹介文になるか、楽しみですね。 PM 成増高等看護学校より 今年度の看護学生の実習打ち合わせがありました。 今年度は以下の日程となります。 5/31~6/4 6/14~18 6/28~7/2 10/25~29 アドボケイト会総会やPC講座、レクの合間をぬって行なわれます。6月は賑やかな月となりそうですね
2010.04 平成22年度を迎えて
平成22年度が始まりました 今年度もNPO法人アドボケイト会(共同作業所リトルハウス、グループホーム:ピアホームⅠ・Ⅱ)をよろしくお願い致します。
リトルハウスにおいて、就労支援に関る中、感じるのは、就労の前提には社会生活の安定化が不可欠であるということです。どどんなに優れた能力を備えたとしても、2次的に「生活のしづらさ」を抱える精神障害の方々は、コミュニケーション・人間関係でつまづく方が多いように感じます。何か問題が生じると自身は省みず他の人のせいにしたり、場の空気が読めなかったりします。また、ビジネススキルの基本に例えるなら、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)ができていなかったり…服薬、社会制度の活用、地域生活を営む上での課題に取り組む事は個人差こそあれ、欠かせないものです。一方、以前、とうきょう会議の施設利用者向けアンケートに、施設に求めるものは何かとの問いに対し、一番多かった回答は「居場所」でした。就労を望みつつも、その根幹には社会生活の拠点として望んでいることが窺えます。
これまで、多くの共同作業所は、共に障害を支え合い、学び合いながら、15人前後(都Aランクの場合)の多くも少なくもない、昔の大家族程のグループで「居場所」として機能し、通所される方々の生活の営みに関ってきました。間もなく、自立支援法に代わる案が厚労省から発表されると思います。以前に比べ、利用者負担軽減は配慮されつつありますが、今後も多くの方が様々な施設を利用されると思います。その生活拠点としての施設経営を、利用者増減がむやみとお金に反映されない(自立支援法では、利用者の方々の顔がお金に見えてしまう?)磐石の態勢で保障して頂ける法律を、日本と諸外国との比較で言えば、医療費偏重にならない予算配慮を望んでいます。
来年度は、社会復帰施設の経過措置の最終年であり、テレビのアナログ放送が終了となる年でもあります。「地デジ元年」は古き良きものをばっさり切り捨てる年ではなく、活かすような年になればよいな、本年度はその礎となればよいなと切に願い止みません。(梁瀬 光輔) 2010.03 NPО法人アドボケイト会第4回役員会3月13日(土) 於リトルハウス pm2:00~ 第1号議案 平成22年度予算の承認 第3号議案 グループホーム報告、メンバーの承認決定 第4号議案 その他 平成21年度決算、自立支援法について 第1号議案について ほぼ昨年同様の予算を立て、承認されました。 第2号議案について 石けん作りを日々進めています。委託訓練事業PC講座はH22年度上半期は5月7日~8月6日の予定です。 グループホーム、ピアホームⅠ・Ⅱの現況、入退居者、地域ケア会議などについて報告しました 第4号議案決算については残余金の使途について話し合いました。また、自立支援法については理事の方から難しい制度の為、一度学習会を行ないたいという声があり、5月8日(土)4:30~からスタッフ・理事とで行う事と成りました。 ※ 次回 5月29日(土)は法人総会pm2:00~です。 正会員の方はご出席の程 宜しくお願い致します。 板橋区精神保健福祉連絡会学習会 藤井克徳氏(きょうされん常務理事)講演…2月18日 グリーンホール ポスト自立支援法の行方は?精神障害者の行方は? ~権利条約をベースに当事者による政策づくりに向けて~ 連絡会では初めて他障害の方々に呼びかけた学習会でした。 前半は、障害者権利条約は障害分野に関する共通基準として必要、そのためには批准(ひじゅん…衆議院での過半数可決成立が条件、成立により一般法律より上位に位置する。)の重要性を話されました。 特に定義として、「合理的配慮」人が障害の有無に関らず対等の立場に立つ為の配慮を強調していました。 後半では、自立支援法訴訟の終結、障害者制度改革推進本部・推進会議に触れつつ、会場からの質疑応答に答えながら、今後私たちに問われるもの…①学習②考える③伝える④動く(要望書・署名など)を述べていました。 藤井さんは「過去と他人は変えられない、未来と自分は変えられる。」と話されていました(この日出席したリトルハウスメンバーの中にもこの言葉に感動した方がいました)。どんな障害であろうと「生活のしづらさ、所得保障などの不利益」に焦点を当て、医療偏重になりがちな社会と向き合っていく為の心構えを学びました。 2010.02 埼玉県日高市社会福祉協議会・心身障害者地域デイケア施設 デイケアこまのさと来訪(2月16日) 石けん作りのマニュアルDVDを皆で観ています。 作り方を説明。 石けん作り実演の他、リトルのネット作業の見学や情報交換などを行ないました。 最初、まだ試運転の段階で突如メールを頂いたので驚きましたが、更に輪が広がると良いですね。 ↑この状態から粉砕機をかけて、粉せっけんにします! 映レク(2月5日 板橋ワーナー・マイカル・シネマズ)・感想 毎年恒例となったリトルハウスの映画鑑賞。今回は3本の映画に分かれて観ました。 「アバター」 3D画面で目が疲れたという意見と迫力があって良かった意見、ストーリーも単純だという意見とエンターテイメントとして考えると良いという意見に分かれました。アメリカ批判という観点で描かれているのは共通していました。 地球軍優勢からの大どんでん返し? 「カールじいさんの空飛ぶ家」 「涙あり、笑いあり、一生に一度は観てもらいたい」 「カールじいさんが風船で戦ったりするけど、ほのぼのした映画」 「ディズニーらしく夢のある映画、本編前の無声短編映画も良かった。」 「50歳の恋愛白書」 恋愛白書と邦題タイトルが付いていますが、物語の背景には、主人公ピッパ・リーと母の薬物や親子関係・家族関係、夫婦関係の問題を描いていて、いろいろ考えさせられる映画でした。それでいてサラリとしていて、最後は、ハッピーエンドで終わるのがいかにもアメリカ映画らしいですね。 2010年を迎えて・・・粉せっけん製造始まる! 皆様 明けましておめでとうございます。 昨年のリトルハウスは、5月よりグループホーム事業を始めたり、 スタッフの入れ替わりが続いたり・・・と慌しい日々が続きました。世の動きも、政権交代や不況など、様々な動きがありました。 今年は、以前は手作業で実験的に行なってきた石けん作りを、馬主協会さんより援助を頂いて購入した粉せっけんの製造機・粉砕機を使って行ないたいと思っております。 正月気分の抜けない2010年1月7日という日、障害者福祉においてニュースがありました。障害者自立支援法訴訟の原告が政府との間で基本合意文書を交わしました。2005年10月31日に全国の障害のある人と関係者の切実な思いを踏みつぶすようにして成立したこの法律の廃止を政府が文書で表明し、原告と確約をしたのです。 この3年の間に福祉支援の利用をストップして家に閉じこもった人や、将来の展望を見失い福祉の職場から去って行った支援者、そして心中事件などで失われた命など、様々な悲しい出来事が各地で起こりました。その事を思い出すともう少し早く行なえなかったのかと感じました。 合意文書にしても、自立支援医療の利用料は無料にならなかった点について「当面の重要な課題とする」にとどまり、自立支援法原告側からも「本当に合意していいのか」「障害のある者同士が分断される気がする」「合意した後は一体どうなるのか」と意見が分かれた様です。 自立支援法訴訟の原告の方の言葉を借りると「今からがスタート」なのかもしれませんね。 地域の皆様 リトルハウスを今年も宜しくお願いいたします。 (梁瀬 光輔) 2009.12
於リトルハウス pm2:00~ 第1号議案 H21年9月12日~H21年12月12日までの リトルハウス活動報告、メンバーの承認 第2号議案 グループホーム経過について
第1号議案について 馬主協会より援助して頂いた資金を活用して小型せっけん製造機と粉砕機を購入、12月22日に納入予定です。 家族会活動として、生活訓練施設「サンライズ高島平」さんの見学会を来年1月13日(水)pm2時~3時に予定しています。 また平成17年のリトルハウスボランティア講座に来て頂いた時からのご縁で約4年間、手芸ボランティアとしてお世話になった宮原さんが、都合によりボランティア終了となります。 宮原さん、長い間ありがとうございました。 現在の居住者の状況、9~11月までの経過報告として退院促進コーディネーター事業である地域ケア会議、グループホーム連絡会への出席等、報告させて頂きました。 2009.11 こころの健康サポーター養成講座 体験発表 板橋区保健所11月4日) この講座は、精神障害の方やその家族の応援サポーターを養成しようと、区主催のものです。今回は西川さんと市六さん、お二人で行ないました。今年は市六さんの発表をご紹介したいと思います。 僕が入院したての頃は、15年位前で精神科がまだ世の中では聞き慣れない時でした。僕はN病院に20才ごろ入院しました。希望もなく、夢もなく、仕事もなく、友人もいなくなってしまいました。軽い引きこもりでした。初めは個人病院に行き、N病院を紹介され入院しました。抱き合う人、大声出す人、ジュースを盗む人、対人恐怖になってしまいました。先生に話した結果、金曜日、土曜日、日曜日は家へ帰れるようになりました。家にいる日は、大量の薬を飲んでしまいました。1日起き上がれない状態で、その後右手に力が入らずつったり、アゴが開かなくなったりして、今でもその後遺症が残っています。今でも、その副作用は辛いです。 その後3ヶ月の入院を経て、デイケアに行きなさいと言われ、そこで出会った友人に、食事に連れて行かれラーメンをごちそうすると言われ、食べながらアゴが開かないままの状態ですするように、泣きながら食べました。今でもその友人とは親友です。その後、すぐに作業所へ行って見ないかと言われ、家の近くにあったJHC大山という清掃をやっている仕事に入りました。そこで3年間という約束デイケアに通いながら勤めました。年配の方が多くスタッフにも恵まれました。 日曜日現場だったり、JHCをそうじしたり、大山周辺のビルを掃除したり、N病院のデイケアの掃除は恩返しが出来ると一生懸命頑張りました。掃除ばっかりではございません。室内の時はSST(ソーシャル・スキルズ・トレーニングSocial
Skills Training~「生活技能訓練」)や勉強会、内職の仕事、夕方の4時過ぎになるなど充実していました。だんだん対人恐怖も治ってきて、うちとけ込むようになりました。そして月日も早く3年が経ち無事卒業しました。そこで、自分の人生の選択の場面でした。そのまま仕事に就けばよかったのですが、しばらく遊びたいという理由で、デイケアを選択しました。少し後悔でした。ソフトボール、ソフトバレー、料理、習字、絵画など、それなりにおもしろかったです。今となってはデイケアに居てよかったと思います。 しばらくするとリトルハウスが出来るという事で、ケースワーカーの人がそこで勤めてみればと言われ迷わずリトルハウスを選びました。2度目の入院、アパートの外の仕事、エレベーター清掃、グループホームでの生活、色々7年の中でありました。今リトルハウスに通いながら、主に作業は料理、インターネット出品、掃除の仕事など、頑張っています。 この後3つのグループに分かれて受講生さんとの話し合いが行なわれました。お二人とも作業所や発表に関する質問攻め?に一生懸命お答えしていました。 2009.10 NPО法人アドボケイト会第2回役員会9月12日(土) 於リトルハウス pm4:30~
第1号議案 グループホーム職員給料UPの申請に伴う承認事項 第3号議案 グループホーム経過 第4号議案 人事について
障害者自立支援対策臨時特例交付金…経済危機対策を踏まえた平成21年度補正予算において、福祉・介護人材の処遇改善として1070億円に基金の積み増しがされました。法人としては準夜勤を常態とする職員(グループホームなど)の手当を想定し96500円(H21年度助成金見込額)申請した事を説明・報告致しました。 第2号議案について 家族名簿を作成、善意銀行からのイベント情報のお知らせなど、日頃からの連絡に活用したいと思っております。 リトルハウス職員白幡が、健康上の理由で8月末日をもって退職、後任の職員募集をしており今回より、試用期間3ヶ月を設定して募集を行う事となりました。 2009.9 政権交代に寄せる期待と不安 ◆障がい者自立支援法を廃止して、障がい者福祉制度を抜本的に見直す◆ 日本の障害者施策の行方は、まだ暫く時間が掛かりそうですが、希望を決して忘れることなく臨んでいきたいですね。 民主党の理念が変質せず、実現して頂きたいものです 2009.6 NPО法人アドボケイト会総会開催 5月16日 2:00~リトルハウスで行われました。 第1号議案:新役員の承認の件 第2号議案:H20年度事業報告(共同作業所リトルハウス運営事業から) 第3号議案:H20年度会計報告(財産目録、貸借対照表、収支計算書) 第4号議案 H23年度事業計画案および予算案修正の件 役員全員が平成21年6月30日任期満了となり、理事の中野 淳さんが任期満了により退任、新たな理事として、家族の方から菅原孝太さん、先月退職した元St牧野美佐子さんをお迎えしました。他の方々は引き続き重任することが満場一致をもって了承されました。 第2号議案について H20年度における通所の状況、作業状況、行事活動の他、就労支援や家族会活動について報告しました。 修繕費は主に自立支援法移行や現状の課題として相談室の設置があり、スタッフルームに壁やドアを備え付ける形で設置した費用であること、H21年度事業計画案および予算案、H22年度事業計画案および予算案については、グループホーム開設にあたり、必要書類として臨時総会で既に承認済みであることを報告した。また、H21年度よりリトルハウスの会計とグループホームの会計と合わせ一本化した会計を目指すことを説明しました。 第4号議案について H21年度事業計画案および予算案、H22年度事業計画案および予算案については、グループホーム開設にあたり、必要書類として臨時総会で既に承認済みであることを報告、H23年度事業計画案および予算案に相談支援事業が具体的に組み込まれた修正案を提出しました。 新St紹介!白幡 奈央さん 初めまして。6月からリトルハウスの職員になりました、白幡奈央と申します。 封筒印刷に向けて… 板橋区社会福祉協議会の助成を受けて、印刷用のプリンター、購入いたしました(写真右)。使っていなかったPCラックを使い、ロッカー前に専用PCと共に設置しました。 2009.5 PC講座開講!グループホーム始まる! グループホーム、いよいよ始まりました! 心配されていた入居者、現在はⅠが4名、Ⅱは3名(満室)とまずまずの滑り出しです。 新サブ講師紹介 wоrdの方を担当することになりました西川丈博です。 (リトルハウス牧野St送別会) 今年の春のレクはテル「カデンツァ」のランチバイキング。 4月いっぱいでリトルハウスを退職することになりました。 牧野 美佐子 牧野Stは5月より、墨田区の障害者就労支援センターに勤務することになります。 2006.4 新年度 平成18年度を迎えて 新年度4月から、自立支援法が施行されています。すでに、自立支援医療法は、手続きが1月から始まっています。今年度は、自立支援法による新福祉サービス体系が、具体的に姿を現し、リトルハウスも適応を考えざるを得ない年度となるでしょう。リトルハウスのNPO法人取得は、その前提の活動で、ただいま認証への準備を進めています。 現時点で、リトルハウスが可能な自立支援法分類上のタイプは、就労継続支援と地域活動支援センターが、考えられます。随時そのタイプの内容が、明らかになり次第対応していくことになるでしょう。制度の底辺末端部分を支える共同作業所のこれまでの役割がそこなわれずに、強化されて自立支援法上の施設となることができるような法であってほしいし、私たちは、その実態を支える責任を、負っています。18年度運営補助金は、前年同様、板橋区と東京都より各1/2の負担で頂けました。補助金の出方は存続に関わることですが、自立支援法の枠外の共同作業所にとって今後が心配されます。 共同作業所としては、自立支援法は、就労支援が強化されているといわれているが、就労以前の精神障害者への支援が、十分に行われるのか心配です。障害があっても無くてもともに生きる世界、ノーマライゼーションの理念からいって、大多数の就労未満の人への支援を手厚く支援するのでなければ、単に障害者を労働適応の選別機構の 徒然草に、「花は盛りに、月は 完全なものが、最高とはいえない。私達障害者の過酷な試練も、味わい深い人生である。と思える境地を共同作業所で目指しているのです。 「べてる」が、病気を商売としたように、リトルハウスでは、試練もネタに、ミニお笑い作業所として展開されています。 メンバーにとって、実りの多い日々が重ねていけるよう、努力して参ります。(千田豊子) 顧問医山崎先生勉強会(2月28日)「副作用について」 ① ・ジストニア 姿勢の異常 体のねじれ(首・足 後ろ向きに歩く、手のねじれ) ・アカシジア そわそわ/じっとしていられない(激しい揺すり/前後に動く/落ち着かない内面) ・パーキンソニズム ①震え 片足/片手から、小刻み、ひざがガクガク ②筋肉のこわばり 力が入りすぎ ③よだれ 薬 のみはじめ1~2週間で出る、変更時に増減。 ・ 遅発性ジスキネジア(自分の意思に関らず起こる) 口の震え(口腔ジスキネジア),舌の出し入れ(不随運動)眼球回転発作(上転が多い) 〔対策〕副作用止め 長期服用せず、副作用がないと見極め減らす、その増減は主治医とよく話してください。 抗パーキンソン薬(アキネトン/アーテン/シンメトレル) 抗パーキンソン薬が効果がない場合(ピレチア/ジスキネジアに。リボドール/抗てんかん※ただし保健は適用されません。) ② 高プロラクチン血症 ドグマチ―ル・リスパダール 症状(男女共に乳汁分泌)男性 胸のふくらみ 女性 胸の張り、痛み、月経異常 〔対策〕もし副作用がでたら、薬の変更を ③ 肥満 肥満と薬 「よく言われるが・・・」ホントとウソ 例:体重を増加させる薬…ジプレキサ・セロクエル・ルーラン(肥満・糖尿の人には使わない) ドグマチ―ル ヒルナミン レボトミン コントミン ウインタミン 服薬した人全員がなるとは限らない。生活に注意すれば防ぐ事は可能。又は意欲低下による生活習慣の悪化:症状のひとつとも言えます。新薬の場合、錐体外路症状が少ない利点があります。 身体合併症 例:そううつ+高血圧 生活習慣病(糖尿,循環器疾患,肥満,がん,コレステロール)について 予防にお金をかける 食生活 運動(1日30分以上、週2回以上、1年以上) こころの健康 たばこ→やめる(「やめられない」 ひとつの病気、保健で治療可) アルコール 1日20g 休肝日は週2日は必要 ビール コップ1杯 ワイン グラス1杯 焼酎 割って飲む(眠れない 寂しい やる事がないからといって飲まない) 歯8020(80才で20本の歯を)歯周病菌は手足の血管を詰まらせます。タバコは悪化させる 糖尿 体重(kg) 身長(m 循環器病・がん 等 健康日本21より http://www.kenkounippon21.gr.jp/ ※ 事前にあった質問について ①「完治」と「 完治とは病気そのものがなくなる、薬不要の状態を意味します。 例えばガンの場合、ガン細胞を切り取ってなくなった状態を指します。(但し将来を保障するものではありません。) これに対し寛解とは 服薬しながらも症状が無くなった状態を指します。リューマチで薬を飲んで関節の痛みが取れた場合がそうです。 ☆ 部分寛解:諸症状のうちひとつがなくなること。完全寛解:症状すべて ☆ 現在精神病の場合、完治はありません。「寛解」を目指します。 ちなみに 完治の反対は? 完治→再発(例:新たにがん細胞が見つかる) 寛解→再燃(火種がまた大きくなる) ②主治医が信頼できない時があるのですが… 私なりに今まで患者さんから言われたことから考えてみました。 2006.2 再度自立支援法を考える 共同作業所リトルハウスはどうなるのか H15年設立リトルハウスは、都と区から補助金をいただき運営されていますが、 国の法である、精神保健福祉法上で定める、社会復帰施設ではない。共同作業所の成り立ちは、法の整備の遅れを補う形で自然発生してきたものである。自立支援法では、共同作業所は、元々法内施設ではないので言及されていないが、国の法に則った施設は法人でなければならないので、少なくともNPO法人である必要がある。と同時にNPO法人を取りやすくするよう規制緩和もおこなわれている。自立支援法不適合の共同作業所は、自然淘汰されるという話です。(5年の経過措置) リトルハウスは、自立支援法上のどの事業を行える可能性があるのか。 自立支援給付の訓練等給付 就労継続支援 地域生活支援事業の地域生活支援センターなどが候補としてあるが、実際行えるものかどうかは、これからの検討事項である。 労働適正でない者への思想は、果たして健全か 精神障害者にとって自立支援法の体系は、就労支援が強化されたものとなっている。就労支援の強化は、喜ばしいことである。しかしどうしても疑問が生じる。労働適正を、篩い分けしたあと、適正でないものへどのような額の補助金が配分されるものなのか。労働適正たて系列の支柱が、働けないものというスティグマを与えないでほしいと切に願う。訓練等給付では、訓練効果が見込めない人は、そのプログラム適応にならないという話しをきくと、不安になる。 利用料自己負担について(権利としての社会保障が否定されつつある。) 社会復帰施設等の利用に費用負担が生じることについて。 国が、障害に起因して生じる障害者の生活困難に対する支援を提供するにあたり、定率1割負担を設定すれば、必要なサービスの自己規制するしかない状態を作り出す。これは、福祉そのものの考えを問いたくなる。 憲法で保障されている人権思想のひとつである、社会権はどうなっているのだろうか。現憲法には基本的人権が保障されている。基本的人権は、国と個人の関係を規定している。私達は、この人権思想という抽象概念を手に入れるのに、長い歴史を要しそれを維持するのに幾多の闘争を経験してきた。私達は、産まれたときに、何も手にしていないのでは無く、人権を手にしているのである。その基本的人権の内、自由権は、国家権力による個人への不介入を定め、社会権は国家権力による積極的な保障をもとめるものだ。自由主義経済のなかで、自ら生活を支えることができない人々を生じさせ、これらの社会問題に社会保障立法、労働立法、経済立法といった社会法ができた。これらの社会権を基本的人権として規定したものである。 この社会権のなかで憲法25条「生存権」は、社会福祉の拠り所である。 低所得の障害者が、生活上必要な支援が、1割の負担が出来ない為に、利用できず、需要が抑えられるということは、国が税を持って対応するべき対象のものに、自己負担を設定し公的責任の免除を図っているのは問題である。(千田豊子) きょうされん大会国際交流分科会 ナンシーJマーレートさん カナダからの報告 私は1960年代、精神障害の施設で働き「脱施設化」としてグループホームやシェルタードワークショップへの移行を行っていました。しかし利用者はホームを嫌がり路上生活者になる人が出てきました。「専門家の考えることは必ずしも正しくない。」とこの時感じました。仕事能力があっても基盤となる家がないと就けません。コミュニティの中で居場所をと、この25年間大学(現在カルガリー大)で学生教育と障害者の就労の仕事をしてきました。傷害ある方が働くこととは… ①機能回復(作業療法) ②就労の為の能力習得が目的(コミュニティワークショップ) 現状としてワークショップからの就労は難しい。 社会の受け入れやバリアの高さ ③補助付雇用 社会雇用へのプロセス・ビジネス お金(企業に与える・雇用する雰囲気を)プロフェッショナルサポート、ジョブコーチによる専門的評価。 ④やりたい仕事 自分たちで行う。例/ロシア:精神科による共同組合(絵の販売/美術展) 「お金の動き」 ①医療保険(各国削減の動き 高齢者・精神障害のコスト増加) ②福祉による支払い(資本主義化 節減)手を打つかなくなるか。 ③個人による支払い(補助付雇用) 雇用側のサポート 80年代より「ダイレクト・ペイメント」…個人と雇用主に直接払われる。 本人が雇用主(例:ヘルパーを雇う)政府ではなく直接本人に、カナダでは7州導入 日本では施設に支払われますが、カナダでは本人に払われます。 カナダの場合グループホームはなく ワークショップがほとんど、個人が援助を受けながら生活、施設がベースではなく個人がベースなのです。(梁瀬 光輔) 2006.1 2006年を迎えて 皆様のご支援のおかげで、新しい年を過ごしています。 昨年暮れには、共同募金会より、歳末助け合いのお金をいただき、民間助け合いの恩恵を、受けさせていただきました。メンバーの年越し資金とさせていただきました。ありがとうございます。 新年は、明るい話題を、続けたいのですが、自立支援法施行年のせいで、曇ってしまいます。 年明け早々、自立支援医療(医療費自己負担1割)の手続き書類が送られて参りました。 現在の通院医療費公費負担は、ライシャワー刺傷事件に端を発し、社会防衛的な意識から、外来受診費用を、自己負担5%に助成し、未受診者を減らそうということで制度化されました。意図とは逆に,ずいぶんこの制度に助けられました。 今回は、逆に自立支援といいながら、一定条件で1割負担が課せられ、支援を取り払っているようにみえるのですが。支援法なのに、正直乗り越えなければいけないと感じさせられるというのは、笑えない話です。 東京都の医療費助成制度も自立支援医療費に合わせ変更され一部続行の形で、低所得の一定条件を満たせば、無料になることができたのは、唯一の救いですが。 折から外は雪風が吹いています。その厳しさ、冷たさにめげずに、リトルハウスでは、 笑い声が、響きわたっています。 この仲間がいれば、なんとか共に乗り越えていける。 そんな心強さを感じています。 では自己負担自立支援医療費の制度に馴れ、社会適応していきましょう。 お笑い作業所リトルハウス 千田 豊子 非常勤St紹介 このたび非常勤になりました大森秀樹と申します。福祉についての知識は誠に希薄ではありますが、熱意はあると思います。どうぞよしなに、よろしく申し上げます。 顧問医 山崎先生勉強会「病気の型について」(12月27日) 診断カテゴリー「DSV-Ⅳ」…説明:第1~第3軸が多い 第1軸 臨床疾患 第2軸 人格障害 第3軸 身体疾患 第4軸 心理・社会的問題 (第5軸 全体的評価) 1軸+2軸 関係のあるもの ○物質関連障害 外から自分の中に取り込み、精神症状へ アルコール カフェイン(1日20~30杯) ニコチン(2箱以上) コカイン・大麻 幻覚剤 鎮痛剤 抗不安剤(デパス ソラックス ワイパックス レキソタン~30分でいい気分に) ○統合失調症及び他の精神病性障害 頭の神経の誤作動 セロトニン ドーパミン 過剰分泌…幻覚 妄想 興奮 ☆妄想型 30歳以上の女性多い ☆解体型 10代発症多い ☆緊張型 20代男性多い 残遺型(判別不能) ○気分障害(うつ病)・双極性障害(躁うつ病) (適応障害 社会と上手くやっていけない、不登校のように一時的心理葛藤) 〔Drからの提案〕○自分で判断せず主治医に相談 ○自分の病名を知る(病名告知は原則として行われる) ※勝手に本を読んで決めず、言われた病名について調べる。自身の病に興味を持つ。 〔薬について〕 薬局からもらった説明用紙。薬名はなかなか覚えられない、その用紙を見ながら説明してもらえると助かります。「以前貰った赤い、丸い…」と言われても同じような薬はたくさんありますから。 自立支援法へ怒りのメッセージ
精神障害者にとって、障害者自立支援法どのようなものか。 精神障害者の立場から、考えてみたい。 1:病気と障害をかかえる精神障害者にとって、福祉政策の対象になることは、遠い道のりだった。 H5の障害者基本法により、知的身体に精神が加わり三障害同一となり、すべての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられることとなった。精神保健福祉法(H7)に、病気という枠で括られ制限されてきた精神障害者が、病気と障害を抱えるものとして、ようやく福祉政策の対象となった。障害者プラン(H7)は、ノーマライゼーション理念の実現にむけた政策であり、大いに希望を持っていた。現在、新プラン(H15)に引き継がれているノーマライゼーションとは、精神障害者が地域で普通にくらしていくために、障害者と健常者が、同じ条件で生活を送ることが可能な社会への改善、環境づくりを行うことを基本としている。 ノーマライゼーション原理は、障害者が存在してこそ想起される、人の良心を結晶化させた尊い考えだと思う。その原理を支えるものは、障害者の存在であり、ノーマライゼーションを声高に主張できるものは、我々障害者自身であり、それが決して自己利益運動には、ならない点がこの理念のすばらしいところである。健常者?の世界では、格差拡大社会が進む中、過酷な競争社会が繰り広げられているが、だからこそ、その規範にのることができない精神障害者は、能率主義でもなければ、競争でもない共同作業所文化を創ってきた。この流れの中で今回三障害同一の法律で、福祉サービスが受けられるという振れ込みは朗報と思われた。なぜなら自立支援法を、導いた支援費制度は、H15年に発足したものであるが、身体、知的のみの適用であり、精神にもホームヘルプサービスはあったが、量質ともに差があったからだ。H5年以降で、発足した制度にもかかわらず平等ではなかった。 2:こんな経過をたどった精神障害者だからこそ、自立支援法という1つの法律で制度が成り立つことに、期待を寄せるのも当然だろう。しかし、それは、この国の法律の甘いわなだった。三障害同一は、精神障害の特性や事情を無視した一律基準の判断のことであり、実感としてはこれまで僅かに恩恵を受けていた通院医療費5%負担を、10%負担・世帯負担とすること等問題の多いものだった。期待していた生活支援は1割負担の中で「ヌカ喜び」! 3:それでは、この法案に欠けているものはなんなのか。それは、精神障害者に対する共感である。共感が無い人々に持つべき理念もない。ノーマライゼーションは、どこにいったのだろうか。知的と身体に適応していた、支援費制度の財政がパンクした。それを、繕うためにたてられたプランに過ぎず、理念よりも財政が先行してしまった。福祉サービス利用料として、1割応益負担を課す障害者自立支援法は、障害者も健常者社会と同じく、所得のあるものだけが、より良い生活をおくれるという皮肉な一律化となった。 厚生労働省は、労働力を売って貨幣を得られない者はサービスを買えなくても当然であり、それが他の消費者(納税者)と公正に扱うことである。と述べている。税で行われる制度に定率自己負担を持ち込むことも過去に例が無いらしい。低所得であるほど、所得に対する負担比が大きく、重症ほど、所得を得るチャンスが低くなるにもかかわらず、負担が多くなる。 また、就労できるもの、できないもの、介護が必要なものそうでない者の選別化は、理念を失った法では、単なる差別化が影で息づいてしまう可能性がある。注意せねばならない。 就労援助は、私たちの立場から求めてきたものではあるが、同じ文言が、発信者が違うと差別として機能してしまう心配がある。精神障害者を区分けし、訓練による上昇気流の枠組みを課す。そのような訓練による回復という無限の負荷を、与えないでほしい。就労援助は、期待しているものではあるが、訓練という名で、ステップアップして社会に送り込む向上構造の柱のたてかた自体が圧力と言える。私たち精神障害者にとって、過去の時代の、無理解に遡るものと同じだ。外見には、見えにくい生きづらさ、病気の波、外側と内側の心のバランスのとりにくさ、そのような事を理解していただけるならば、就労への困難を改善するメインは、環境の側の改善に力をそそぐ援助でありたい。共同作業所は、地域と共に、そうした環境を提供し探求する場である。 また病気の性質から、変動がはげしく認定のしにくさがあるのではないかと思われるが、そのような病気特性に対し長期間の関わりが必要な部分であるし、就労支援のプランを事前にたてることが、また激しい変動の為に困難な人が潜在的に多い。「プラン」と言う名のレールに乗れる人のみ援助が受けられるのでは如何なものか。気分変動という障害特性を考慮に入れた、援助の必要度の認定の仕方。援助の評価の仕方に、他の障害と異なる視点がほしい。 精神障害者への援助は、モチベーションから始まるところに大きな特徴がある。利用料は、モチベーションを削ぐものである。現に先日のきょうされん全国大会においてその声が出始めている。(今月号・報告レポ参照) 逆に、利用すると、お金が貰える。ポイントが溜まる。だれでもモチベーションは高まります。そんな発想を持って頂きたい。 家族依存の応益負担のありかたは、精神障害者は、所得がないため家族と同居せざるを得ない人が多い。家庭内では、病気の症状もありトラブル事も多い。世帯負担は、親に負担と本人に負い目を負わすものではないだろうか。 精神障害者は、たまたま病気を負った。その苦悩や深刻さを代われるものは無い。しかし援助はできる。誰もがその立場となる可能性はあり、その援助は、実は自分達自身へのものなのだ。 1割負担の医療費:通院医療費は、身体に比べて多額ではないが、ほぼ一生ついてくるものである。標準的障害者は、障害年金を単位に暮らしているが、その所得にとって、医療費はかなりの比率を占めるものである。再発での入院もある。援助の出ない入院の為に蓄えも必要である。 地域で生きる権利:病気を抱えつつ地域で自立して生きる、そのこと自体に生きる価値がある。 私たちは、憲法25条によって、そのことは、権利として持っている。このことを確認し、成立してしまった自立支援法がすべての障害者に、より良い方向に運営されていくことを願って止まない。(文責:千田 豊子) 2005.10 顧問医小川先生家族勉強会「家族が出来る支援について」(9月28日) 1:家族で出来ない事は「出来ない」と割り切る。 2:共倒れにならない(1番柔軟に動けるのは家族) (事前の質問から)ニ-トや引きこもりについてありましたがそれは状態や現象、例えば「せき」と同じで病気・病名ではありません。状況が当てはまったからといって決め付けず、家族で悩まず保健所の引きこもり相談を利用して専門家に話してみて下さい。 いざという時、動ける・頼りになるのは家族なのです。 ※ニートとは元々英国で生まれた言葉、教育や職業訓練等についていない若者を意味します。 3:統合失調症 接し方 1:抱え込まない 2:過剰な介入はしない。 病の特徴 自己と他者(世界)との境界線が不明確 揺らいでいる。境界線が弱い。 →外から聞こえてくる音に「狙われている」と感じるのは筒抜けの様な状態で侵入するからです。 家族が感情的(ヒステリック)介入すると、敏感に反応。呑気に介入すると良い。 しかしどこまでが過剰か…自分で判断できない時に主治医やワーカー、相談できる環境を。 今、失敗できる状態かどうか(そう状態など、病的な高まりなら止める。) メンバーが家族に望むこと 気持ちの尊重 陰性の時やる気がないのではない、出ない。おしりを叩いて作業所に行かせない(そっとして欲しい・口やかましく言わない)→いざ、1番柔軟に動けるのは家族。 切り捨てない発言…大人として認めて欲しい「信頼」 医師は治療を担い、社会資源(福祉・就労)は本人の意思を尊重しつつ各機関(作業所・保健所など)行う。 転機はわからない・どうにかしようと思わず、共通の目標を育む。 この後先生への質問・Stとご家族の方々との懇談会があり、作業所とは違う一面が感じられる話が多く、興味深いものがありました。一方で諸事情で来所出来なかった方もいます。スタッフという名の一方的な援助にならず、ご家族の負担を少しでも軽くする様努めつつ今後もこのような場を積極的に設け、共に歩んでいきたいと考えております。(要約・構成 梁瀬) 2005.8 顧問医 成増厚生病院 小川先生勉強会 「統合失調症の症状と病気との付き合い方」(5月18日)② 〔再発を防ぐためには…薬を飲み続ける事〕 ○もらった薬を自分の判断で勝手に中止すると早くて2,3ヶ月・遅くとも1年以内に再発。 ○調子がいいからといってやめない事。 ?いつまで飲まなくてはならないか? 現在の医学の知識では,「いつまで」と言い切る事は出来ません。症状が重い時は薬は多くなりますが,落ち着いてきたら量は減り,副作用も楽になります。 現在負担の少ない薬がどんどん開発されています。今が辛いからといって悲観せず希望をもって下さい。 〔薬以外の治療〕 精神科の医師は,主に薬を使って病気を治すのが仕事。 リハビリテ-ション:薬以外の治療法・薬物療法と同時に行うのが基本。「健康な部分をのばす」 例 作業療法,デイケア,ナイトケア,生活技能訓練など。 ●作業療法:病ではない部分の心身の維持強化・病の改善-独立心や自己責任,自信をつけていく考えに基づいて行う。作業療法士と呼ばれる専門家が室内ゲームや散歩,絵画,陶芸,料理,木工,園芸などを行います。 ●デイケア(昼間)・ナイトケア(夜):規則正しい生活を送りたい方や仲間を見つけたい方,糖尿病などで食事が心配な方に。なぜなら32条を使えば食事が無料で食べられるからです。料理やゲームのプログラムはありますが疲れたり調子の悪い時休んでもかまいませんし,Stや医師に相談もできます。 生活技能訓練(SST)について 統合失調症の患者さんは上手に買い物ができなかったり,電車に乗れなかったり,又は対人関係が苦手で断る事が苦手な方,本当に助けが必要な時にうまく誰かに助けを求められない方,友人ともっと上手に付き合える様になりたい方,恋愛についてなど,具体的に苦手な事・できるようになりたい事を練習・訓練します。 (質問&その答え) Q:家庭内において相談を受けた時のアドバイスをお願いします。 A:何故そう思うのか「聞く事」です。 近い距離の中大変かとは思いますが,質問して錯覚である事を気付いてもらう,といった感じで最初から結論を言うのではなく,言葉のキャッチボ-ルを通じて,お互いに結論を出してみてはいかがでしょうか。 Q:自分の考えている事が伝わってしまうのでは?例えば資格試験を受けたいのですが答案作成中自分の考えが他の人に伝わりパニックになるのではと考え,受験できないんです。 A:これは「筒抜け体験」と言って代表的な陽性反応のひとつですね。自分の考えがテレパシ-の様に伝わる事はありえません。 ① 伝わらない事を頭で理解する事。②少しずつ付き合う。この2点に注意してみて下さい。 Q:最近感動できる対象が少なくなって感覚・感受性が落ちている気がするのですが。 A:大人になると感覚が変わっていく,その感覚に気付く事が大切であり,そう感じる事はまだ感じる力が残っている証拠だと思います。 障害者自立支援法について質問 平成17年第2回区議会一般質問より 2005年6月5日板橋区区議会議員遠藤千代子 ①今年2月、障害者自立支援法案が国会に上程されました。この法律案は障害者施策全般にわたる見直しを図るもので、障害者、地方自治体、サービス提供事業者など関係者に与える影響は極めて大きいにもかかわらず、制度の詳細が明らかにされておりません。区としても十分な論議と検討をすることが必要なのではないでしょうか、どのようにお考えでしょうか。 法案は身体障害者、知的障害者、精神障害者の一元化や就労への支援の方向は理解できますが、肝心の障害者の生活実態が反映されていなく、本当に障害者の自立に欠かせない制度、負担のあり方になっているのかが疑問です。法律を現実の生活にできるだけ近づける努力が大切だと思いますが、いかがでしょうか。 ②利用者負担の見直しに関して伺います。応能負担から応益負担への転換、サービスの量に応じて定率1割負担を利用者に求めていますが、これは大きな負担となります。特に生活保護を受けていない低所得者の方の負担の増は著しく、サービス利用を抑制せざるを得なくなるのではないかと心配されます。負担の上限は世帯の収入に応じて決めるとされていますが、自立の第一歩は家族の依存から脱却することであり、自立支援ということであるならば、障害者自身の収入に応じて負担を決めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ③評価尺度・基準及び区の審査会について伺います。評価尺度・基準は、これまでの支援費制度のあり方とは根本から違っています。サービスの支給量を障害者本人が選ぶのではなく、医師や専門家が判定して審査会を区市町村に設置するというのです。障害者自身の意思を尊重する観点から、給付審査会のあり方についてご見解をお聞かせください。 ④精神障害者通院医療費公費負担制度について伺います。精神障害者の通院医療費の定率負担が精神保健福祉法32条に定める5%から10%に引き上げられることになっていますが、一気に2倍になるというのはいかがなものでしょうか。急激な値上げは障害者の生活を圧迫することにならないでしょうか。また、こうした公費負担の見直しについては、今年度10月から実施される予定が示されていますが、東京都に対して事前交渉が行われているのかお聞かせください。 ⑤移動介護について伺います。知的障害者や障害が重いほど必要な移動介護についてですが、法案では移動介護は裁量的経費の地域生活支援事業に位置づけられているので、当事者は個別給付のままに残してほしいと求めています。移動介護の法的な位置づけと財政確保についての課題についてお示しください。 ⑥グループホームについて伺います。法案では、重度障害者はケアホーム(共同生活介護)、中軽度障害者はグループホーム(共同生活援助)と障害の程度によって住むところが分類されています。なぜ障害の程度によって住宅が変わるのでしょうか。グループホームでのホームヘルプ事業は認められないとなっておりますが、それではグループホームは入所施設と同じことになってしまいます。どんな障害であっても、住む場所は心の通じ合う居心地のよい場所でありたいものではないでしょうか。 この法案は障害保健福祉施策を根本から変えるものであり、しかも、範囲は広範囲に及んでいます。このような重要な法案を十分な審議時間もないままに、短期間に決めようとするのはあまりにも拙速過ぎると思います。国に対して意見書を上げていただきたいと思いますし、関係機関や当事者の意見をよく聞いて納得できるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○区長 答弁 障害者の自立支援についてお答えします。 ①②現在、国会で審議中の障害者自立支援法、これでは在宅と施設のバランスのとれた負担、サービス利用料や医療費等、所得に応じた負担といった応益の考え方による定率負担の導入を規定しております。この定率負担の導入に対しましては、東京都と特別区がそれぞれ国に対しまして負担軽減措置による障害者の自立支援についての配慮、あるいはサービス利用の抑制にならないように、軽減の措置、経過措置を設けて、費用負担者は障害者本人を基本とするということなどの対応を申し入れたところであります。 ③次に、介護給付、訓練等給付の利用手続につきましては、介護保健制度と同じように審査会の判定をいただいて支給決定することが示されております。現段階では評価尺度・基準及び審査会設置についての詳細が未確定でありますので、その内容が明らかになった段階で検討して対応をしたいというふうに思います。 ④それから、障害に係ります公費の負担の医療であります精神通院の公費厚生医療及び育成医療について、支給認定の手続が共通化されるとともに、1割負担が導入されるということでありまして、その詳細につきましては、現在のところ未確定であります。東京都、特別区がそれぞれ国に対しまして利用者、特に低所得者層の負担が大きく増大するとともに、診療の抑制、中断につながらないように開始時期を含めまして十分な配慮を行うように求めているところであります。 ⑤それから、移動介護につきましては、新制度では定率負担の導入とともに、障害の程度が重い人は介護給付の行動援護の対象に、それから、軽い人、これは地域生活支援事業の対象に位置づけることを明らかにしております。特別区といたしましては、定率負担導入によりサービスの低下にならないように国に要望するとともに、地域生活支援事業につきましては、早急に事業の内容を明らかにして財源を確保するように申し入れをしていきたいと思っております。 ⑥次に、グループホームについてのお尋ねでありまして、新しい制度では障害の程度によりまして、重度の方を対象とした共同生活の介護と軽度の方を対象にいたしました共同生活援助とに分けた形の体系が示されております。新制度への移行の時期につきましては、18年10月から5か年間で順次移行ということで詳細は未確定であります。具体像が明らかになった段階で検討して対応していきたいと考えております。 第2回精神保健ボランティア講座開催 2005.6 第1回運営委員会開催 5月14日、17年度第1回運営委員会を開催しました。議題は次のとおりです。 第1号議案 平成16年度決算について 第2号議案 平成17年度予算について 第3号議案 非常勤職員の採用について 第4号議案 平成17年3月12日~5月14日の経過報告と新メンバーの承認について その他(名刺PR 就職依頼 障害者自立支援法について) 平成17年度最初の運営委員会は、従来の流れの後に時間を取りPRや自立支援法について話し合いました。 「統合失調症の症状と病気との付き合い方」(5月18日)① 〔統合失調症とは?〕 私達の脳の中には、様々な神経伝達物質と呼ばれている物質が存在します。統合失調症の患者さん脳の中では、このバランスが崩れる事によって様々な症状が起こります。簡単に言うと、物事の考え方・感じ方が病気によってうまく働かなくなる事が起こります。 〔症状 陽性症状と陰性症状の出現〕 陽性症状 幻覚や妄想と呼ばれる、健康な状態ならば出てこない症状が現れる事です。 幻覚…実際に存在しない感覚が現れる事。 失調症で一番多いのは幻聴、実際には存在しない「正体不明の声」が聞こえてくる事です。 幻聴は、ただの物音のような事もありますが、患者さんにとってとても辛い時期があります。それは、その内容が患者さんにとってイヤな内容、悪口を言われたり、自分で秘密にしている事が聞こえたりします。また「正体不明の声」が自分に何かを命令し、その命令に従わなくてはいけないと感じるようになる時があります。幻聴は新薬である程度取れますが、どうしても取れない時は「共存」、理解に努めればわかるようになります。その他、(失調症にはあまりないが)幻覚には幻視と呼ばれる幻が見えたり、幻臭と呼ばれる、実際には存在しない匂いを感じる事があります。 妄想…実際にはない事を、本当にあると思い込んでしまう事です。例えば、盗聴器や監視カメラで自分が監視されている、悪の秘密結社が自分の命を狙っている、電車に乗っていたら周りの人が自分の悪い噂をしていると言った等です。妄想は薬で和らぎますが、自分ひとりでは気付きにくい症状です。※自分で気付けば妄想ではない。 陰性症状 今まで(病気になる前)出来たこと・感じた事が病気によって出来なくなる事です。 失調症が長く経過していくと陰性症状の方が目立ってきます。陰性症状には主に以下の症状があります。 自発性の低下 道徳的感情の麻痺 感情をうまく表現できなくなる 表情が乏しくなる イライラしたり落ち着かなくなる みずみずしい感情が鈍ってくる(感情の平板化) 会話 上手くできない、広がりがなくなる 周りの人たちとの人間的な交流が減り(表面的な付き合い)共感できなくなる 思考がまとまらなくなる 学校や職場に行くのが億劫になる 集中力がなくなる 清潔を保てなくなる(歯磨きも面倒くさい) 社交的でなくなり人との交流が苦手になる、人に会いたくなくなる ひとりで1日中ぼんやりする 気力が湧かない ※ これらの陰性症状は、すべての患者さんに現れるとは限りません。 〔症状との付き合い方〕 精神病は、時間が掛かる病気です。薬効も個人差はありますがたいてい2~3ヶ月掛かり、特に陰性症状は長期戦の付き合いが必要となります。 陽性症状は比較的簡単に薬で取る事ができると言われています。最近は良く効いて副作用の少ない薬がありますので主治医と相談しながらきちんと服薬する事が大事です。 そのほか、いらいら感や落ち着かなさ、不眠などがよく起こります。いらいらしたり、落ち着かない感じがする時は、それを一時的に抑える薬がありますので、このような症状がある時は主治医と相談して、症状に効く薬をもらって飲んで下さい。不眠も、よく現れる症状ですが、最近の薬は効きが良い上に安全な薬がほとんどですので、もし、眠れない時には主治医とご相談下さい。また、不眠は症状として出るとは限りません。不規則な生活をしている時はいくら強い睡眠薬を飲んでもよく眠ることが出来ません。 十分な睡眠をとる事は、症状が悪化するのを防いだり、再発を防ぐ為に大事な事ですので、規則正しい生活をするように心掛けて下さい。また、かといって病状が安定していない時に無理に規則正しい生活をすることで、余計に疲れてしまう事があります。いろいろなケースがありますので、もし症状に困ったら、すぐに主治医と相談して下さい。日頃から主治医とよく相談できる関係作りが大切です。陰性が強く、自分ひとりではどうにもならない時はデイケアや作業所などをうまく利用して下さい。(続く) 障害者福祉改革の岐路
「改革のグランドデザイン案」に基づく新たな障害福祉施策体系の構築を背景に、障害者が地域で生活することを支援する「障害者自立支援法案」が、国会に提出されている。「市町村を中心に、年齢、障害種別、疾病を超えた一元的な体制を整備」「地域福祉の実現」などがかかげられ、ますます、障害者施策の拡充、水準の向上、その為の区市町村の役割の発揮が求められている。その法案とは…。
1. 障害者支援費制度の枠外だった精神障害者が、身体、知的と同じサービスを受ける。
注:害者支援費制度平成15年4月に、支援費制度開始
需要の大幅増加:04年度国の補助金、不足額263億円。支援対象者かどうかの判定を受け利用者とサービス提供者の契約による。 応能負担(扶養義務者含む)により、利用料金が決まる。
2. 応能負担から、サービス利用量に応じた応益(定率)負担1割
3. 手続きや基準の透明化、明確化(地域で利用量や頻度に差)
4. ①移動支援サ-ビスの見直し
重度の知的・精神障害など危険回避が難しい人に対する「行動援護」サービス。
危険回避ができない自傷・異食・徘徊の行動障害に対する援助を必要とする者への支援。
②極めて重度の障害者に対するサ-ビスの確保…包括的地域生活支援プログラム(ACT)受け入れ条件が整えば退院可能な72000人の入院患者の退院・社会復帰を今後10年間で進め、重い精神障害をもつことで頻回入院や長期入院を余儀なくされていた人々が、病院の外で質の高い生活を送れるように、医師・心理・福祉など様々な職種の専門家から構成されるチームによる支援。
問題点 応益負担:介護保険は、1割負担しているが高齢者と、障害者では、生活状況が違う。
障害者の場合、働いても共同作業所における福祉的労働の場合が多く、(大抵数千円程度)収入が少ない。障害者年金は2級で、1ヶ月6万7千円、サラリーマンの平均月給より、少ない。
障害を持って生きるための最低限のニーズを満たすことを、益といわないでほしい!
加えて、基準となる収入単位を障害者個人ではなく、家族で考えている。厚生労働省は、サラリーマンの給与体系の中で、収入のない障害者は扶養控除の対象である事を家族負担の根拠としているが、これは障害者自立支援という理念に反するのではないか。と同時に、サービス機関(市区町村)やユ-ザ-、家族の声・実態・要望が反映されないまま審議が不十分のまま進行、不安ばかりが増大しているのが現状だ。 山崎先生勉強会「統合失調症について」(3月29日)
●失調症は何の病?「心の病」って言うけれど=頭の病 頭も体~体の病・行動に現れる。
要因 ①遺伝子の脆弱性+②環境によって起こると考えられる。
①注(遺伝と言っても家族すべてが病気になるとは限らない。又いないからならないとも限らない)
②注(いじめ?育て方が悪い?虐待のような場合を除き「ストレス」と考えられる)
①と②の割合は個人差があるものの、この2つによって起こると現在では考えられる。
※病者の家族がすべてなるとは限らない。また家族にいないからならないとも限らない。
例:幻聴 他には聞こえていないが脳には聞こえている。(=誤作動「陽性反応」)
脳の伝言ゲ-ム化・伝言がないのに聞こえる。
脳の動き(正常)―――――□――――――――□――――――□…
(幻聴)―――――□――――――(例)「ふたつある」――――「ふたつある」…
(「ふたつある」と聞こえる脳の誤作動・実際には聞こえていない。)
治療:薬でその受け取り口を減らし抑える。
●「治る」とは? 幻聴がなくなる・やる気が出る。生活が成り立つ…個人の目標による。
定義:不安や葛藤から開放される事(友人と出掛ける様になる・一人暮らしが出来る。)
参 考
1陽性症状 陰性反応
2山崎先生が考える「治る」段階の例 出来る目標から。
①患者さんの家族が誰かに相談できる。
妄想 感情鈍麻 ②患者さんが病院へ行く。 ③将来が少し考えられる。
幻聴 意欲低下 ④人との交流ができる。※
作業所は④⑤の段階では? ⑤学校・職場に行ける。
思考混乱 ⑥「困った・どうしよう」問題が生じた時に対処できる。
感情不安定など ⑦自立
種類 抗精神病薬 幻覚・妄想 頭の活発な動きを抑える。 抗うつ剤・抗躁剤 抗不安薬 対処的、完全な治療にはならない。 睡眠導入剤 抗てんかん剤… 条件 年齢(若い人・老人) 症状の種類 幻覚・妄想が激しい人 落ち込みが激しくて死にたくなっている人 頭の中が混乱している人 興奮が激しい人 (薬は症状に合わせて使用されている。) 合併症の有無 「新薬に切り替えると薬は減らせるか?」 糖尿病の危険性が高い人は使えなかったり幻覚妄想の激しい人には効果が薄いことも(新薬は弱め)ある、 一概に新薬に変えればいいということではない。 「副作用があると○○さんが言っていたから飲みたくない」 「○○さんは1錠なのに私は2錠?」 →人と薬の量や種類は比較できない。 主治医と相談 ▼精神病 自分の考える力が弱くなる…問題が分らなくなる。 自分の症状を客観的に捉えられず「どこも悪くない」「死んだほうが良い」と非現実的に考えがち。 薬物療法の最優先:薬を飲んで治療を進め調子が良くなってきたらまた現実的に考えられる様になる。 不調の時は自己判断せず、友人・家族など周囲に相談…助言に耳を貸す。 説得・説明は不調時には無効(叱っても病気の心には思うように届かない事もある)。時には厳しく思えても、自身の状態を理解出来ない時に強制入院・手を引いて通院が必要な事もあるが、最終的には本人の状態にプラスになる気持ちを忘れず。 ▼ただ薬をのむだけでよいのか 通院 入院…病気の力が強い時、(点滴・注射 ゆっくり休める) リハビリ SST 作業療法などその人にあったもの、「治療と共にリハも大切」 ▼主治医との関係について ※事前アンケ-トで多かった:主治医に病状聞きづらい「なぜ説明してくれない?」 →「説明して欲しい」事を伝える! Drは時に患者さんが自分の病気と向き合いたいと思っているか、本人から「どんな病気ですか?」「どんな薬ですか?」聞いてくる、その気持ちが芽生えるまでじっと待っている事もあります。それは、自分の病気に興味のない人に説明を押し付けても無駄だからです。 疑問に思ったら自分から聞いてみませんか? 「治療とはDrと患者、お互いの歩み寄り」 ▼コミュニケ-ションスキル…人と上手に付き合う為に コミュニケ-ト=話すこと? ①聞き上手 ②アドバイスばかりしない 人はただ聞いて欲しい時がある。 (例)相談「アドバイスしなきゃ…」?自分にとって良い事が相手にも良いとは限らない。 その話の先が続く様に話を持っていく~自然と答えが出る。 ③他人は自分の鏡 相手:つまらない顔で話を聞いている。→相手も自分もつまらない。 (外来)Drイライラしている=自分もイライラしているかもしれない。 どちらが先という事ではなく、雰囲気はまわりに移る。 コミュニケ-ションが上手くいかない時はこの3点を振り返ってみてはいかがでしょうか。 このあとたくさんの質問がありました。いくつかご紹介したいと思います。 質問:診察時間が3~10分と短い事、その中でどう伝えたらよいか? 伝え方のポイント 山崎先生の失敗談 内科受診時、熱、おなかの不調…時間内で話そうとして言い忘れが気になり話がまとまらなかった事がある。 →診察側としてはメモに書いて貰えると有難い。 →不調時の日記…どのように悪いかわかり易い。 ※長時間の診察は希望すれば可能な場合もある。他に、話を聞いて貰う目的が強い場合は他のStやワ-カ-を活用すると良い。 〔使い分け〕 主治医:症状=病気について 看護師:生活上の困った事(症状~Drに言うべきか?但し薬はDrに) PSW(ワ-カ-):年金制度、生活保護など 臨床心理士:Drにカウンセリングを頼む。自分の悩みや気持ちを整理・解決 質問:人込みや電車、バス、ざわめき 自分の悪口ではと感じてしまう。その対処は。 →ウォ-クマンなど利用して遮断してみてはどうでしょうか。 質問:薬の肝臓への負担について →お酒と併用すると細胞が破壊されてしまいます。どちらも肝臓で代謝するからです。薬の効きが強く・弱くなってしまいます。これは、風邪薬も同様です。またタバコもよくありません。 コ-ヒ-も食後、1日3杯程度なら良いですが、多量(20~30杯)摂取は良くありません。コ-ラも同様です。 質問:多飲水(1日4~6?)について →強迫飲水の場合、治療や入院が必要となります。電解質値が正常だと良いのですが、若いうちからの多飲水は腎機能低下を招きやすくなります。定期採血を行い、血中から調べる必要があります。 ○コミュニケ-ションスキルや診察時のメモなど、参考にしてみてはいかがでしょうか。 ○Stの使い分け…作業所にいるとひと通り聞いている気がする。作業所Stってもしかするとス-パ-マンみたい?(構成 梁瀬 光輔) 増田秀暁氏講演(2月15日 東京障害者職業センタ-) 今回の増田氏の講演(障害者就労支援に必要な視点について ~企業での体験を通して~)の中で何度となく出てきた「自信」という言葉がとても印象に残っています。今までの実績に裏付けられた、福祉的観点でなく一企業体としてのしっかりとした経営方針、戦略に基き運営されていることにより成功するという自信にとても力強さを感じました。 障害者も雇用側の工夫で必ず戦力になるとの信念を持ち、障害を持つ社員の育成を実践されかつ利益を上げているということは本当にすごい事だと思います。「障害特性」を配慮し本人の持っている能力を引き出し、必ずできるようになると信じ待つことの大切さも感じました。 就労となると、どちらかというと何ができるかということに目がいきがちですが、「清潔、体型、服装など社会に好感を持たれるセンスを磨くことも必要」という話はとても頷けるものでありました。「障害者だからこれくらい仕方ないか」という妥協なき厳しさも感じますが、ある意味同じ土俵に立つのであるから当然のことでもあります。もちろん厳しさだけではなく、聴くこと、共感することが大切なのは言うまでもありませんが。 増田氏のHPに障害者雇用を通しノーマライゼーションの達成を目指す為の4つのステップとして 1)障害者雇用の促進 2)障害者の認知の促進 3)障害者の社会的地位の向上の促進 4)障害者に対する社会的受容性の支持、促進 が挙げられています。就労が全てではなく、障害を抱え就労せず生きてゆく生き方もあると思いますが、就労を望む多くの人たちが、背伸びせず無理なく力を発揮でき、お互いが支えあい、認めあえるような場が今後増えてくることを望みます。 また、話の中にもありましたが、支援がその場しのぎのものでなく、大きな視野(養護学校でのさをり織や園芸など実戦的ではない作業、今後につながりのあるプログラムを)持った次に繋がるものになるようにしていけたらと思っています。(牧野 美佐子) 2004.12 特集 1 べてるに学ぶ「おりていく」生き方 東大医学部 本郷キャンパス 鉄門講堂) 11月5日13:00~15:30 上野千鶴子さん司会(ご案内有難うございました) キバヤシ「宴会部長」の替え歌にはじまり、上記テ-マの他べてるが広がって行く為の条件や抵抗勢力についての話から、美しさと毒を併せ持った(盛った)言葉のるつぼと化した会場、その瞑言(めいげん)の一部を紹介いたします。 (向谷地 生良) 東大に足を踏み込むのは究極の落ち方だと感じました。(笑…上野さん「究極は勲章」、更に笑い) 初めて浦河の町に立った時の「落ちぶれた感覚」、そして潔さん達と出会い、秩序、調和などすべて打ち壊され援助とその成果・期待が示されない、次第に腹立だしくなる「壊れていく感覚」。この2つを通じて学んだ事から、一般にソ-シャルワ-カ-は相談を受ける立場とされているが、むしろ相談する立場に立つことを目指すようになった。べてるは誰の現実の中にもあるのでは?普通の事だと思う。私は事実に忠実に行ってきた、さびしい浦河の相談室での自分の社会復帰や失敗・5年間病院を追われた事と潔さん等相談者の現実は等しいと思った。 (早坂 潔) (べてるの家代表)生保と年金で暮らしている。 腹が立つのは相手ではなく自分自身、嬉しいことや悲しいことも。川村先生は治さないけど、生かしてくれる。そして、ひとりの人間として浦河日赤から町の中に出してくれた。(田口さんの)「何かしてあげたい病」は自分が満足できないからしてあげるんだよ。1年のうち2回入院する中で頑張らない事を学んだ。 (河崎 寛)べてるの家爆発救援隊隊長 べてるで行っている「当事者研究」について 病気の仲間達・専門家を交えて自分の病気の体験を語り合う事で人として楽しく生きていける事をみんなで感じ合う。この病気は逆らえない事がわかった、自分ひとりで克服するのではなく、仲間や家族、医師や専門家らと話し合って病気の世界の道案内をする事が当事者研究だと思う。 ※ 河崎さん最近爆発気味について「べてるでは爆発するけど良い奴と言ってくれる。」 東大行く事決定)向谷地さんに℡ 「僕は東大に行くのか?そんな人間じゃない、ムカムカする。」 毎晩東大に行くと同じ事が出来ると思ってしまう。 インスピレ-ション~何でもわかる、夢中。 その状態でべてるへ行く、人と話せない…周りが駄目に見える、自分も。 価値観の変動、喘息もあり入院。 向谷地さんに「苦労した時の首の垂れ方がいい」と言われた。(会場爆笑) (渡辺 瑞穂)べてるの家メンバ-、摂食障害 分析すれば回復につながると専門書など検討、ある程度中味が分ったが「それで?」。それからは、節食する事が何の為に必要か、得られるモノは何かと視点が移った。自己研究を通じ、それまでは自分自身だけが味方だと思っていたが、症状は違えども同じ様な生き詰まり感を抱えたメンバ-とで話しているうちに様々な見方を学び、直接変わった事はないけど、身ひとつでも何とかなる、根拠はないけど「信じてしまえ」と思える様になった。 (伊藤理恵子) 浦河赤十字病院ソ-シャルワ-カ- 向谷地さんは私に何ひとつ指導せず、期待も感じなかったので入職して3ヶ月経った頃聞いてみると「何も期待はしていません。」それまでは人の期待にどう応えるかという事で歩んできたのでショックだったが、そのうちひとりで頑張るのではなく、みんなの力を借りてやっていけばいい、支えるのではなく支えられていると思う様になった。Drのプライドを持ち上げる事に全国のワ-カ-は莫大なエネルギ-を費やしているが、べてるはSt・患者さんみんなでチ-ムを組み回復研究、Drには、実は配慮され続けた不幸、施設にはおせっかいや過援助が多いのでは。 (川村 敏明) 浦河赤十字病院精神神経科部長、治さない、患者さんとじっと座っているDr? 20年前、初めて研修医として浦河に。大事なことはワ-カ-に相談Drにはない現実に「何をするか・出来るか。」一緒に問題を考えていく。Drとしてべてるに必要な条件は楽しむ力。私としては科学的(上野さん解説:伝達可能な知、他人に真似出来る知)、何が最も効果的か考えつつ自身のわきまえを大切に行っている。浦河での経験「先生のおかげで良くなりました。」と言って帰った患者さんで実際に良くなった人はいない。現実は単純ではない、医者の限界を知る。 (田口ランディ)作家、爆発系の父・兄を持つ、べてるに興味 べてるを見ると苦しくなる。引きこもりの末自殺した兄は不幸、幸せな彼をイメ-ジ出来なかった。私は「何かしてあげたい病」自分が何かしたら幸せになれるのでは、自分のせいで人は不幸ではと考えてしまう。 リトルハウスにて振り返り 「早坂さんと同世代、差別・偏見を糾弾しないのは凄い。」「がんばらないで生きるとあったがこの病気に頑張るは禁句」「個性が病と見なされているか。思考のユニ-クさ=治す」「爆発までの思考の形を持っている」「潔どん(上野さんは早坂さんをこう呼んだ)のひと言で場が和む、替え歌面白い」。一方今までの生活の中で病気が知れた事で偏見があり、話を受け入れるのは難しい(辛い)、時折煙草を吸いに席をはずす早坂さんに眉をひそめる人もいて意見が分かれた様です。 この「上っていく」主流の世の中を考えると、べてるの発した言葉に「ホンマかいな」、ある種の辛さ・疑問を感じるのはむしろ自然な事。期待に応えて輝く人もいる様に価値観は人の数だけ存在する。「べてるがなぜ広がらないか」べてるを心の阿片にせず、それぞれの現実に対し、まず言葉の実践・積み重ねではないでしょうか。 渡辺さんの身ひとつでも何とかなる、質疑応答の際、「信頼」について向谷地さんが答えた、嘘でもいいから、ちょっとだけ信頼…。以上の言葉に私は最高の処世術を感じました。福祉施設は曲者揃い、何かと揉め事が多いですから、残念!(要約 構成など 梁瀬光輔) 特集 2 11月6日14:00~ 高島平地域の江口様より紹介頂いたチェロ奏者の須田 千香良氏によるコンサート。 その他テンコ盛りの内容は? ☆ まずは千田の挨拶、ノ-マライゼーションとは障害の有無に関わらず平等な社会であるという説明の後、 リレ-形式によるメンバ-紹介、どうぞ。 (千田)野智さん、あなたにとって作業所はどんなところですか。 (野智)みんなに会えて、とても楽しいところだと思っています。それでは宮坂さんに質問します。 リトルハウスに何を望みますか。 (宮坂)社会性と人間関係のあり方について学ぶところです。それではカズマッチさん、ズバリ目標は? (カズ)社会復帰です。その内容は、3年前から温めている事がありまして、整備士になりたいと思っていまして、本当は4年位前からやめた高校の所の専門学校に通おうかと狙っていましたが、学費とレヴェルが高過ぎるという事もあり、友人から職業訓練校というのがあるのを聞き、やっと決意が固まりました。現在はときわ台にあるワ-キングトライという施設が紹介してくれたパソコン講習に11月8日から通い、そ の後板橋にある訓練校に受験して受かったら通って整備士の資格を取り工場で働こうかと思っています。 うちは父親が自殺しまして、それで病気が重くなりいろいろな場面に会ってきましたが、それをバネにし て生きている訳で、ある意味親に感謝しています。 ひろみさんに質問です。リトルハウスで大変なところはどこですか。 (ひろ)(PCを)初歩から覚えなければいけないところが大変です。 おそばさんに質問します。余暇の時間はどう過ごされていますか。 (そば)音楽が好きでギタ-や電子機器を使って作曲したりします。油絵やアクリル画を描いたりします。気力のない時はテレビを見てゴロゴロしています。 (ひろ)あなたが一番困っている事は何ですか。 (そば)自分のコントロ-ルです。意思した事と成果が結びつかなかったりして、自分の満足に繋がらない事は多々あります。6割がたは達成しているけど4割はイマイチかなあというところですね。 (ひろ)リトルハウスに来て一番変わった事は何ですか。 (そば)友達が出来た事です。 ミズノ君に質問します。来年の今頃あなたは何をしていますか。 (ミズ)来年の今頃は路上生活者になっていると思います。(場内 笑)…後に千田より追加質問、パソコン関連の目標について話す。 神戸さんに質問です。どんな仕事をしていますか。 (神戸)インタ-ネットで物を売ったりお店を開いたりしています。 市六さんに質問します。アルバイトの苦労について教えて下さい。 (市六)清掃の仕事をしていますが暫くの間ご飯が食べられなくなった事があります。 チェロ奏者の須田さんに質問します。僕は皆の前で緊張しますが、演奏する前何をしてらっしゃいますか。 (須田)別に特別な事はしていないです。 (市六)有難うございました。 ※間に合わなかったsihokoさん、懇談の席でネットで自分の出品した服が売れた時うれしいと話す。 ☆白石弘巳(東京都精神医学総合研究所)先生ミニ講演 統合失調症(精神分裂病)の慢性期について。幻覚・妄想が活発な急性期に比べ慢性期は目立った症状は少ないが無理をすると疲れやすく、セルフコントロ-ルが難しい為、自分で「出来る事はきちんとやる事。」がリハビリになる、そのひとつとしての作業所利用を柔らかい口調で話してくださいました。 2004.9 第4回板橋区精神保健連絡会に出席 8月26日、こもね作業所で第4回 ちなみに、行政と板橋区精神障害者施設関係者との話し合いははじめての試みで、行政との協調で、板橋区精神障害者福祉施策を進められればという両者の思いが実ったものです。 区からは、平成17年度で現計画の区切りとなり、平成18年度からは新しく10ヶ年計画が始まり、その試案を検討中との報告がありました。計画に向け、当事者・家族へのアンケートを実施するとのことです。 この機会を利用して、関係者から、質問や現状の訴えがあり、JHC寺谷理事からも助言をいただくなど、活発な意見交換の場となりました。 行政側から、直に、精神保健福祉施策を伺う会として、作業所現場での実態を知ってもらい、施策に反映する良い機会あり、リトルハウスとしては、都区の施策への関心を深めることとなりました。 これを機会に、障害者をめぐる、国の政策を見てみたいと思います。 知的、身体、精神の三障害が、障害者として定義され、平成16年5月改正。地域での基本計画策定を義務化。 ☆ 平成7年精神保健福祉法を基礎に精神障害者に福祉の政策が適応される。 現在は、新障害者基本計画(平成15年から24年度10か年計画)の実施期間ですが、そのうち前期5ヵ年の重点施策実施計画を中心に、精神障害者に関する項目を見てみましょう。 ○ 精神障害者施策の充実○ 社会的入院約72,000人の入院患者について、10年の内に退院、社会復帰をめざすとし具体的に数値が示されている。 1 医療、保健 精神科救急医療システムを全都道府県に整備する。 2 福祉 ①在宅サービス 精神障害者地域生活支援センターを470か所整備する。 精神障害者ホームヘルパーを約3,300人確保する。 精神障害者グループホームを約12,000人 精神障害者福祉ホームを約4,000人 ②施設サービス 精神障害者生活訓練施設(援護寮)を6,700人 精神障害者通所授産施設72,00人分 ③啓発・広報 共生社会に関する国民理解の向上 医療機関・団体との連携による公共サービス事業者に対する障害者理解を促進する。 ④雇用・就業の確保 トライアル雇用、職場適応援助者(ジョブコーチ)、各種助成金等の活用、職業訓練の実施などにより、平成19年度までにハローワークの年間障害者就職件数30,000人に、平成20年度の障害者雇用実態調査において、雇用障害者数を、600,000人にすることをめざす。 地域で当たりまえに暮らすために、自立と社会参加への支援が、具体的数値をあげて示されている。このように、精神障害者を取り巻く環境が、大きく変革前進している時代にいあわせた、共同作業所実施体として、変革期にふさわしく、この法精神が浸透し、心のバリアーを取り除くべき、大胆に地道に取り組んでいきたいと思います。(千田 豊子)
トイレに行くと1時間以上手を洗い続けた中2の頃。薬がきつく口が開きっぱなしだった初めての入院。仕方なく通ったデイケア。そんな長澤さんが力をつけた背景には自分に合った病院(主治医)とクラブハウス、治療と居場所との出会いがありました。特に印象的だったのクラブハウスはばたきスタッフ・ボランティアさんはじめ7、8人はいた相談者の多さです。長澤さんは良くなる条件として治療と居場所を挙げていましたが 居場所に関わる私としてはその多さ=環境をリトルで育んでいきたいと感じました。そして考えます。果たしてリトルの場合はどうかと。 メンバーの質問にも夢を捨てず、能力だけではなく周りとのコミュニケートにも目をとの言葉は、日頃忙しさにかまけ勝ちなスタッフにとっても忘れてはならない言葉でしたね。 彼女を作りたい、ひとり暮らしや結婚したい、資格を取りたい、仕事を持ちたい。長澤さんが話した多くの、当たり前の、されど尊い夢に共感される方は少なくないと思います。 今でも、講演終了後みんなと腕相撲を取っていた姿が目に浮かびます。合間を見て、又来て頂けると良いですね。(梁瀬 光輔) 2004.3 べてる講演会に参加して 千田豊子 コミニュケーションの障害、人間関係を築くのが苦手な病気といわれているにもかかわらず、自分のことをのびのびと語るメンバーに、私は元気をもらいました。妄想をネタにして語るべてるのメンバーは、会場の人が笑っているのを見て、エンタティナーの満足を味わっているように見える。妄想のことで笑っていいのかな?こんな遠慮は、いらない。なぜなら、彼は会場の人に笑ってもらいたくて話しているのが見え見えだから。 べてるの歴史は、“精神障害者の社会復帰”というスローガンさえ、公に言えないくらいの時代の地域状況から始まる。 障害者だけが苦しい生活を強いられているのではなく、 浦河で、一番悲惨なことは、赤十字病院の精神科に入院することと言われていた、その街で、自分たちほど苦しんで生きているものはいないと言いたくなるところを、自分達が奪われていたのは、実は苦労することだった。―という、全く逆の発想です。 病気になって、下降線をたどり、回復という上昇をたどるという図式を想定しての援助ではなく、病気を抱えてしまった人が、自分の人生の主人公になる援助をする。人生の主人公は自分自身だから、その結果についても自分が引き受けるしかないよ。――というわけです。 20年間の向谷地さんの、当事者への深い愛に基づき常識を打ち破り、当事者が主体者となる援助のありかたを実践され示して下さった。べてるの結果は、街ごとの社会復帰にふさわしい、当事者の活動から地域を巻き込んだ事業体となった。べてるに傾倒した人を、「べてらー」というそうです。リトルハウスにも、「べてらー」が生まれそうです 2004.2 顧問医武蔵先生の勉強会 ―お別れ講座になりました― リトルハウス立ち上げから、顧問医としてお世話になっていた武蔵先生が突如愛媛県に転勤となり、図らずも今回が最終講義となってしまいました。 さて、高島平移転後はじめての勉強会は、板橋区精神保健関係機関連絡会とドッキングした開催となり、区内の精神科病院、健康福祉センター、作業所などの医師、看護師、保健師、心理、精神保健福祉士、ケースワーカーの方々が集まり、総勢40名弱の参加となりました。 武蔵先生講演に先立ち、時間を頂戴しリトルハウスの紹介をさせていただきました。そこで、実際の様子をみていただくために、メンバー三人(ネットトリオ)で、ネットショップへの出品の手順を「おめでたい鶴が舞う日の出の花瓶」を使って、参加者の方に向けてデモンストレーションいたしました。皆の注目を浴び緊張の中、まず、デジカメで写真撮影をし、パソコンで競合商品の価格調査(マーケティング)をした上で出品していることを説明しながら、われらが自慢のパソコン(メンバーの自作によるものですよ)を使って、インターネット用ハイパーテキストに変換した上で、無事出品しました。聴衆からはわれんばかりの拍手をもらったネットトリオの市六さん、カズマッチ、水野さん、お疲れさまでした。 武蔵先生講演会要旨 お話の要点をまとめ、報告します。 「薬がたいせつ:なぜたいせつなのか」 人は、必要な情報を選択してみています。情報にフィルターをかけていると例えることができます。これができなくなると、あふれる外からの情報を適切に処理できないため、誤った認知を招き、例えば、自分の回りのことが全て自分と関係があるように思えてくる(関係妄想)などの症状となって現れます。薬(抗精神病薬)は、この感度を下げるように働くと考えられています。アンテナの感度を下げると思えばよいですね。 多くの研究から、服薬を中止すると、再発だけでなく状態の悪化が指摘されています。先生は、患者の状態が悪くなったとき、まず第一に、「お薬が余っていませんか?」と服薬の確認をしています。 「キーパーソンをつくる」 本人とよく話しをすることで、困ったときに誰に相談しているかが分かります。例えば、重要な薬の管理者はだれなのでしょうか? キーパーソンとなる人の存在は大きく、必ずつくっていく必要があります。そして、それは安定している時にこそ準備し、把握しておくことが大切です。また、キーパーソンは複数いることが望ましいと思われます。この病気の親は高齢の場合が多く、親自体が病気を抱えることが多い事情があります。親一人をたよりにしていると大きく崩れることがよくみられます。複数のキーパーソンをつくり情報を共有し、一人が全部をかかえこまないようにすることが大切と思います。 「メンバーの自立」 デイケアーと作業所の守備範囲は違います。デイケアーは医療の一環であり、作業所は、例えれば、会社に行くことに近いものです。作業所に通うメンバーは、自分の状態を医師に自分で語れるようになれるといいですね。作業所のスタッフは医師や医療機関と単に直接繋がっているというのではなく、メンバーを通して繋がることが望ましいです。メンバーが自立し自分のことを正確に話せるようサポートするのが、作業所スタッフの役目だと思います。 お薬Q&A 1 水野さんの質問 Q 就寝直後の電話の記憶が全くありません。 A 睡眠導入剤による前行性健忘です。頭に異常が起きているわけではありません。 服薬後、起きないように。 2 市六さんの質問 Q 何かしようとするとき、指のツッパリがでる。 3 カズマッチの質問 Q 会議中、眠くなり集中できない。 A お薬の服薬時間などを工夫するよう主治医と相談してみましょう。 4 会場から Q 朝起きれないことが多く、朝のお薬を服用すべきか迷う。 2004.1
「僕は進化中」 市六 僕は自分の心が自分でもむずかしい、ではないかと思い込んでいる所もある・・・。 実は僕だけなのではないかと最近うすうす感じてしまう(自分でも自分が怖い時がたまにある)ボケているのかな~。それとも理解されない話しならリトルハウスにきてメンバーと話してしまおうという所もある。 もともと頭も良くないし、話すのも聞くのもこんなにむすかしいとは・・・。 僕だけなのかな~? だけど周りに話しを聞いてくれる人がいてくれて今の自分には助かると言う所もあるし、たすけてーという所もある。 開業してから、もうそろそろ2ヶ月。僕は人と戸惑いながらウソもつけずに進化中。 「こんにちは。はじめまして」 神戸 実奈子 こんにちは。はじめまして神戸実奈子です。人づきあいが苦手で、あまり慣れていませんが、頑張ってやっていこうと思っています。できれば、慣れてきたら回数を増やせていきたいです。よろしくお願いします。 「手芸をして」 山中 広枝 去年の秋10年ぶりに入院して、もう普通に生活できないのではないか、と思うほどにいろいろな症状に苦しみました。退院して母が家族会の人たちとやっていたパッチワークを少しずつやってみるとだんだん作品が出来上がるのがうれしく、いくつもつくりました。 「僕の28年間」 カズマッチ 僕は昭和50年7月2日水曜日に 色々ありましたが、高校はT・K大付属に入学しました!高校2年次に自主退学、その後に大検取得、3年前から生活保護になりました。最後に、絶対社会復帰! 「米調達フリーマッケトを煽動して」 K・水野 人間に欠かせないのはやはりなんといっても食料だ。そして日本人の主食は米だ。オレも日本人、毎朝米を食べている。今年の米の不作のあおりを受けてか、作業所でもなぜか米不足に陥ってる。そこでオレが先頭に立ち、全精力を上げて板橋農業まつりのフリーマーケット(フリマ)で米を買うための資金集めをすることにした。目標額は6,500円だ。ショバ代で1,000円上納しなければならず、オレは前日から気合を入れた。 当日、車2台で移動することになり、オレはリトルハウスまで車を回してやって、スタッフの牧野さんと一緒にフリマの品物を運搬したが、目的地までの行き方が分かる者がいなかった。この作業所は一体どうなっているんだ。おかげで、道に迷いながらの運転で危険な思いを通行人に与えちまったじゃないか。オレはまだ若葉マークなんだぞ。ひよこだ。助手席にいたスタッフの牧野さんには多大な迷惑を掛けたけど、悪いとは思っていない。やっとの思いで駐車場に着いたものの、フリマ会場まではかなりの距離があり、重い荷物を抱えたオレは途方に暮れた。強気なオレは農業まつりで規制された道路を無理に突入したが、なぜだか逆に歓迎されて商品搬入まで至った。オレの日頃の行いがよかったからに他ならない。間違いない。 さて、いざフリマで商品を売るぞとなると、なぜだか周りの空気にオレは馴染めなくなっていた。北風が吹く中、会場の隅っこで昼食を食べた後、売り子をやりたかったんだが、売り子の中に加わることがなかなか出来なかった。一方、スタッフの太田さんは売り子をやらず、なぜか警備員より絶大なる信頼を受けて会場整備に貢献していたので、腹のそこから大笑いしちまった。結局オレはフリマの売り子にはほとんど携わらずに終わったが、当初の目標売上げ6,500円を遥かに上回る14,900円を稼いだんだな。オレのがんばりで我がリトルハウスは米不足から解消された。これで安心して寝られる。 「新転地リトルハウス!!21世紀の劉備 玄徳ここに在り」 松石 隆 2002年12月末、私は、リトルハウスのメンバーとして登場した。私のリトルハウスの第一印象としては、「なんて個性豊かな人材が揃っているなぁ。」と思った。まだ、リトルハウスが小豆沢の地にあった時である。小豆沢時代はどうだったか?私は語る。第一に個性豊富なメンバーがいる。この作業所の最大の特徴だと思う。だが、作業の流れは、だらだらと時間が過ぎていって、終了時間がずれ込んで、帰りが遅くなってしまう。最初の頃はしょうがないことだと思っていた。私の予定がくるってしまう。しかし、今はこの点を改善しつつある。もうひとつ、他の作業所に無いところ、それは、午前中の食事作りである。これは、自給自足という点、生活感のある感じの作業所として、無くてはならないものだと思う。ミーティングも多く、所長中心で行っている。それと、ボランティアの方々に、この作業所が支えられているということを付け加えておく。 2003年10月、リトルハウスは小豆沢から高島平4丁目へと場所が移り、個人的な作業所としてではなく、 そんな中、私の存在はどうでいなければならないのか、常に考えている。私を歴史上の人物で例えると、三国志に出てくる蜀の君主、劉備だと思う。それは何故か?私の最大の長所は優しさである。劉備も武将や国民の人々に優しさを振舞いながらの人生を送った。私の場合は、今のリトルハウスのルールを変えようと、所長に対抗できる意見を多く出している。その訳は、今までの私の人生観、そしてメンバーの意識改革をしようとする事で言っているのである。これは、私の独特の優しさのあらわれである。所長を三国志に出てくる人物で例えると、いろいろな情報を得て、策を考える君主、魏の曹操である。あともう一人、私の2歳年下のメンバー、水野さんである。水野さんを三国志に出てくる人物で例えると、今ある決まりごとを平等や平和的に片付ける(水野さんの書いている文章上では分からないが、実際はこんな性格だと思う。)君主、呉の孫権である。私は、ミーティングをこうゆうイメージを思い浮かべながら、参加している。ミーティングは活気に満ち溢れていると思う。ここでトリビア(トリビアとは、つまらないこと、ささいなことと言う意味であり、つまり、ムダ知識である。)を。実を言うと、政治家は三国志を愛読している人が多い。三国志は、沢山の登場人物、色々なかけひきなどがあって、政治家にとって大変奥深いものがあるに違いない。 最後に。これからのリトルハウスはどうでなければならないのか?あらゆる面でメンバー主体の作業所であって欲しい。それで、所長を始め、メンバーの補助を行ってもらいたい。これにむかうには色々なルールを作ったり、ミーティングを重ねていかなければならない。メンバーの増員も当面の課題である。今いるメンバーがどの様にリトルハウスを利用しているのか、一人一人聞く必要がある。メンバーの意見がこれからのリトルハウスを左右するに違いない。これからも、更なるリトルハウスの発展に期待したいと思う。 おんぼらとしたふれあい ―日本病院・地域精神医学会に参加して― 千田豊子 というわけで発表内容もなんでもありのデパートのような学会で、項目を選ぶのに迷いました。私は、当事者が参加しているもの、作業所関係、お薬関係、を軸に聞いて参りました。総じて、意欲的な取り組みをしている、全国の方々の存在を知ることは、このあとの活動を心強く致します。 リトルハウス運営上の悩みが、個別のものなのか、制度的なものなのか?視野をひろげて―リトルハウスの位置をどこにおき、役割をどうするか?改めてはっきり振り返るきっかけにもなりました。 リトルハウスは、一人ひとりのメンバーの状況に合わせて、さまざまなかたちで社会参加を促し、一歩一歩前進しようとしています。 そのため、ひとつは従来の殻をやぶり、NetSHOPやSHOPを運営し、プライドがもてるお仕事づくりをめざしています。幸い、パソコン上手の力のあるメンバーが集まり、SHOPはうまく回り始めています。 しかし、一歩を踏み出すことをためらっているメンバーのためにも、おんぼらとした気持ちで、3カ月に1度でも、6カ月に1度でも、ふらりとやって来るメンバーがいるような、作業所でもありたいと願っています。 ある専門家からの苦言がありました。作業所ができたできたといっても、通えるメンバーをセレクトし精神障害者の1割2割をカバーして喜んでいていいのですか?作業所に通えないメンバーこそ問題なのではないですか? まずは、どんな方でも歓迎です。リトルハウスにはまっていただければ幸せです。 皆様どうぞお気軽にご見学に来てください。 2003.11 精神障害者共同作業所 『リトルハウス』は、都・板橋区より認可された運営委員会形式によるAランク精神障害者共同作業所です。 平成14年5月、精神障害者を抱える家族が、未来を信じ、障害者の積極的な社会参加を図ろうと立ち上げました。
● 病気を理解する。 ● 皆で話し合い、ひとりで悩まない。 ● 出会いを大切にして、ネットワークをつくる。
1 運営委員会委員 代表 菅谷茂外、地域代表、家族、障害関係者、専門家が加わっています。 2 スタッフ 所長 薬剤師千田豊子を中心に臨床心理士、精神保健福祉士、非常勤の4名体制です。 武蔵先生を顧問医に迎えています。 また、ボランティア組織『ぱそぼらいたばし』の支援を受けています。 主なプログラム
2003.8 独占手記「1人暮らしの落とし穴」(実話です) 松石 隆 6月3日(火)の夜、家に1人でいました。午後8時頃、布団屋のYさんが来ました。ドアのチャイムが鳴ったので、普通にドアを開けて、Yさんに会いました。うちでは色々な布団屋が来るので、家の中に入れても、「生活保護で働いていない。」と話せば、契約をせずにすぐ帰っていくのですが、Yさんの場合は違います。Yさんも同様に家のなかへいれて、生活保護で働いていないことを伝えたのですが、Yさんは、「障害者でも、契約している人がいる。」というので、自分は布団を買う契約をしてしまいました。Yさんは布団を売って20年ということもあって、口が上手いです。布団は約46万円、分割支払手数料が約46万円の37,8%の約17万4千円、合計約64万円の月々約1万円の60回払いでローンを組みました。このとき、自分では払っていけるだろうという気がしました。 その後、Yさんにはお世話になっていたのですが、6月9日(月)に、訪問看護の人が来ました。この布団の事情を訪問看護の人に話したら、「今度の月曜日に主治医とケースワーカーに相談したほうがいい。」と言われ、6月16日(月)に相談をしました。主治医は「最初は払えても、だんだんと生活が厳しくなって払えなくなる日が来る。」と言われ、6月19日(木)に、ケースワーカーの人と一緒に消費者生活センターへ問い合わせてみました。そしたら、「この契約書は不明な点(職場の住所がかかれていない。)があっておかしい。それに布団代が高すぎる。」と言われて、契約の解除の方向へ話を進めてくれました。結局、この布団の契約は無いことになり契約を解除できました。 今思うと、馬鹿馬鹿しい事をしてしまったと思っています。訪問セールスは家の中に入れたら最後です。一人暮らしの人は特に注意してください。自分ではいい勉強になりました。 2003.5 第3回勉強会―顧問武蔵先生を囲んでー 武蔵先生に顧問を引き受けていただき、早、半年以上が過ぎました。お忙しい中、やりくりをしていただき、2ヶ月に1度程度の勉強会をしてきました。 4月よりリトルハウス職員(予備軍を含む)が新体制で臨んでいること、昨年末より新規参加メンバーの定着やメンバー交替、それに伴う新しい親の参加など、今回は参加者の大幅な変化がありました。そのため、まずは、自己紹介からのスタートとなりました。 家族の関わり方 武蔵先生に顧問を引き受けていただき、早、半年以上が過ぎました。お忙しい中、やりくりをしていただき、2ヶ月に1度程度の勉強会をしてきました。 4月よりリトルハウス職員(予備軍を含む)が新体制で臨んでいること、昨年末より新規参加メンバーの定着やメンバー交替、それに伴う新しい親の参加など、今回は参加者の大幅な変化がありました。そのため、まずは、自己紹介からのスタートとなりました。 今回は、武蔵先生よりレジメをいただきましたのでそれを掲載して報告に代えさせていただきます。 家族の関わり方 ● 病者に「共感する」とは ・気持ちを ①「受け止めること」、②「受け入れること」。 受け止め側の表現としては、「うん、なるほど」、「そうか、そう思っているんだね」 ・気持ちを ①「理解すること」、②「親の言葉で置き換えてまとめること」。 受け止め側の表現としては、「~~と思っているんだね」「ということは、~~ということ?」 ● 本当の「共感」を示すには ① 言葉と態度・雰囲気のズレ、②建前と本音のズレが問題となる。 言葉と雰囲気がズレていると、混乱する! 心の動き 言葉では「大丈夫よ」、「心配ないわよ」、「何とかなるわよ」と言いながら、態度・雰囲気では「大丈夫かしら」、「本当は心配」、「どうせダメなんじゃないか」を示すと、内面の不安は、隠しきれない。 必ず漏れ出る。 ↓ 子供は、親の不安・強がり(=本音)を見抜く。 ↓ 親の言葉(建前)に合わせて、親の不安をなだめる役を引き受ける 子供も強がる「うん、私なら大丈夫よ、心配しないで」 親は安心「ああ、親の気持ちを分かってくれた」 あるいは 親の言葉(建前)に納得せず、イライラ、混乱、興奮 「いつもそんな適当なこと言って、口先ばっかり!」 親は混乱「どうして親の気持ちが分からないの! 情けない!」 ● 対応に困った場面では? 分からなかったら、分かったふりはしないこと! 本人の言葉で出てくるまで、待つこと! 常に、親が、言葉と態度を一致させること。 話す内容と心で思っている内容を一致させること。 ●「適切な距離をとること」とは 「子供は、自分とは違う人間なんだ」と、親が理解すること。 ↓ 「親は、自分とは違う人間なんだ」と、子供が理解すること。 「突き放すこと」ではないし、「抱え込むこと」でもない。 ● 統合失調症における情報の取捨選択機能の低下理論 視床下部の、フィルタリング機能(情報の取捨選択機能)の低下 ↓ 自我機能の脆弱性。 ↓ 葛藤や不安を抱える力が低下している。 ↓ one time, one thing. 同時に2つ以上のメッセージを伝えないこと! 「否定」「禁止」「抑圧」ではなく、「受容」「共感」「傾聴」。 「おしつけ」「相手のためを思って先回り」はしないこと。 「あなたのためなのよ」は、ウソ。 2003.4 健康・医療ガイドセンター交流会に参加して わが子の病気をきっかけに、参加してきた健康・医療ガイドセンターの交流会。白石先生を始めとして、精神医療に先進的な取り組みを行っている多くの専門家との交流をさせていただき、『リトルハウス』の大きな支えとなっています。 プログラムは、午前に全体会で家族からの質疑応答。午後は回復者へのインタビューと講演、「ご家族の接し方のこつ」。残りの時間は自由交流となっていました。 午後のテーマは交流会の原点とも言える家族と当時者の接し方についての討論でした。専門家のいう中間的態度の実際はどういうものか?実際の場面の難しさについて家族から数多くの事例について質問が出されました。専門家は親が当事者との接し方に以外に自信がないと少し意外に感じ、親はそう上手くはいかないよとの思いが残ったのではないでしょうか? 相手の立場を理解する。--平凡でもこれが1番の解答でしょうか? 詳細については、『リトルハウス』に資料を保管していますので、お問い合わせください。
2002.9
2002.8 ーE薬剤師を迎えてー 7月27日、先進的に病棟活動をしている○○病院のE薬剤師を迎え、おくすりの勉強会を実施しました。 ○ 向精神薬と抗精神病薬の違いを理解しましょう。 ○ 抗精神病薬の作用は次の3つ ○ 抗精神病薬の力価 ○ おくすりを増やしても症状が変わらないと思うのですが? ○ 飲酒は?コーヒーは? その他、かなり深い内容のお話もありましたがここでは割愛します。最後に、家族の当事者へのかかわり方のお話となりました。家族も子離れして少し距離がおけるようになれるとよいですね。リトルハウスはそのためにもあります。
|