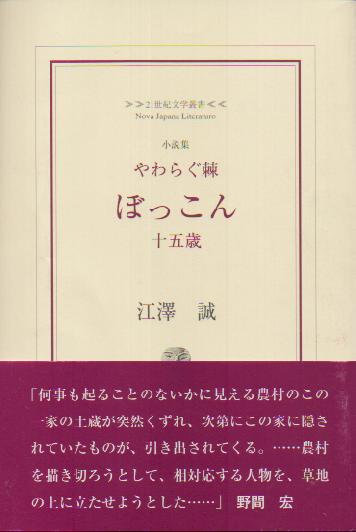 |
A.著作
新日本21世紀文学叢書 小説集 『ぼっこん』(新日本文学会出版部 2002)四六判 213頁(1800円+税)
この小説集には、「やわらぐ棘」「ぼっこん」「十五歳」の3篇が収められています(「ぼっこん」とは、「亡魂」の意味です)。
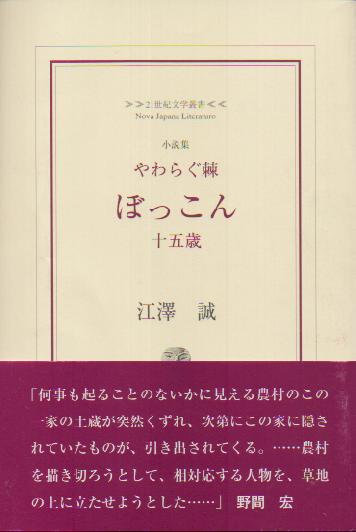 |
「やわらぐ棘」と「ぼっこん」についての評を、帯から転載します。
「やわらぐ棘」の評 野間 宏(作家)
「何事も起ることのないかに見える農村のこの一家の土蔵が突然くずれ、次第にこの家に隠されていたものが、引き出されてくる。……農村を描き切ろうとして、相対応する人物を草地の上に立たせようとした……」
「ぼっこん」の評 針生一郎(美術・文芸評論家、和光大学名誉教授)
「ぼっこんは亡魂で、……祖先の霊がこの川の淵に永生すると信じていたことをつきとめる。……『わたし』は遺伝子操作専攻というのもおもしろく、……護岸工事でぼっこんも住めなくなった、という結末も利いている」
次に、中島誠(文芸評論家)の書評を紹介します。
「本書に収めた3篇は、いずれも時代の移りゆくなかを生きる人間同士の関係の厳しさ、忌まわしさ、また無上の悦びをテーマとしている。3作とも、まさに歴史のなかに生きる人間という環境の物語を見事な短編に仕上げた連環作といえる。……環境とは空間、平面の問題だけではない。環境の変化には時間という大事な要素があって、それを投げ入れると、人間の、のっぴきならない歴史となる。江澤さんの小説は、まさに環境小説なのである。」
本書に関しては、次の誌紙に書評(紹介)が掲載されています。
『税のしるべ』2002.1.28.号
『本の街』2002.3.月号
『新日本文学』2002.3.月号
新日本文学会は解散しましたので、お求めは著者までご連絡いただければ、[1800円+税90円=1890円](送料は当方負担)にてお送りいたします。郵便振替用紙を同封しますので、書籍到着後、その郵便振替用紙でお支払いください。郵便振替の手数料は70円(ATMですと60円)です。
B.正岡子規の大多喜旅行
正岡子規(1867〜1902)は1891(明治24)年3月25日から4月2日まで上総、安房(現在の千葉県)の旅に出ている。子規25歳、大学1年生 (勿論現在とは学制が異なる) の時である。東京から千葉・大多喜を経て外房に出て、小湊、館山から内房の鋸山へとまわり、船で東京湾を渡り東京へと帰ってきている。
そのときの紀行文『隠蓑日記』によれば、千葉から外房に出る際、3月28日は大多喜に泊まっている。その日は雨が降って、子規は大多喜の手前の小さな店で蓑を買い求めた。この蓑をまとっての旅を子規はとても気に入っていたようで、紀行文のタイトルになっているし、東京・根岸の自宅の柱にはその蓑を柱にずっと懸けていた。
子規はまもなく病に倒れるが、病床にあって、この蓑を見ては大多喜近辺の旅を思い出し、随筆『松蘿玉液』のなかで次のように句を作っている。
ともし火は壁上の詩歌を照して雨戸くる音も絶えたるころ家居まばらなる隣近所は静まりかへりて時々打ち笑ふ声かすかに聞ゆ。何とは無く思ひに沈みたる眼を開けば柱に懸けし古蓑に思はず六年の昔ぞ忍ばれける。千葉より小湊に出でんと多喜のほとりに春雨に逢ひて宿とらんも面白からずさりとて菅笠一蓋には凌ぎかねて路の邊の小店にて求めたる此蓑、肩にうちかけたる時始めて行脚のたましひを入れて
春雨のわれ蓑着たり笠着たり
(『松蘿玉液』)
現在、根岸の自宅は「子規庵」として保存されており、蓑は松山の子規記念博物館に残されている。
夏目漱石(1867〜1916)も、1889(明治22)年の夏に房総半島への旅に出ている。子規、漱石とも東京湾を横断しているが、その方向は逆で、漱石は東京湾を船で渡って保田に着き、現在の内房を館山まで下る。あとは房総半島の太平洋側を北上し、銚子から利根川をさかのぼって関宿まで至っている。この漱石の旅行は8月7日から30日までの大旅行であった。交流のあった2人のことだから、子規は漱石の房総旅行に影響を受けていたと考えられる。実際、漱石は房総旅行の紀行文を『木屑録』に著し、子規に贈っている。
当時ごく普通の人は生涯生まれたところから離れて遠くまで出かけることは無かったともいわれているなかで、旅をするということは限られた人にだけ与えられた特権であったわけだが、それにしても当時の文学者(の卵)はよく旅をしている。
これを子規および子規と交流のあった長塚節と夏目漱石についてみてみる。
子規は房総旅行に出た1891年、6月の大学の休みに故郷松山に帰る際に、軽井沢、長野、松本、木曽路を回っている(木曾までは徒歩)。8月に上京する際にも、寄り道して広島、岡山などに遊んでいる(しかも子規は房総旅行の2年前に既に喀血しているというのに)。
1893(明治26)年には、7月19日から8月20まで1か月あまりをかけて奥州旅行に出ている。
1895(明治28)年には3月から5月にかけて日清戦争の従軍記者として、中国に渡っている。
これ以外の年も毎年旅に出ていて、1896年にほとんど歩行ができなくなった後も、体調がいいと人力車を呼んで出掛ける人であった。
長塚節(1879〜1915)は子規が享年35だったのとほぼ同じく36歳の生涯であったが、同様にその生涯は旅の連続であった。例えば1912年(明治45年・大正元年)の旅はすさまじく、旅に出るというよりは日常が旅というほうがぴったりで、その年、元旦を入院先の病院で迎えた節は2月に退院し、『土』の出版にかかわり、3月に旅に出て、京都医科大学で入院、手術し、退院後は帰郷することなく、夏目漱石の紹介状を持って九州大学病院に出向いて診察を受け、そのまま九州・四国・関西各地を回って9月に帰郷している。6か月間の旅というよりは、旅のなかで入院も手術も創作もやってのけ、生活がすなわち旅であったのである。
また、漱石についていえば、先にみた1か月近くの房総旅行の直前、7月下旬から8月始めまでは静岡県方面に旅行に行っている。そして、のちにはロンドンまで行って、「自我」を文学に取り込んで日本の近代文学の鼻祖となる。
こうして見てみると、彼らにとって旅の目的は慰安にあるのではなく、旅は生活そのものであり、創作の場であったといえる。
ところで、『子規全集』(講談社、1978)の「第22巻 年譜 資料」によれば(152頁)、子規が大多喜で泊まった宿は「酒井屋」となっている。私がだいぶ以前に聞いたところでは、この酒井屋が実際どこにあったのかは分かっていないとのことだった。つまり、その後俳句、短歌の大御所となる子規だが、当時はまだ学生であり(といっても帝国大学生だから目立ったのは確かだろうが)、記録には残っていないのである。
私は大多喜中学校在学中、郷土研究部に所属していて、正岡子規の大多喜旅行について調べたことがあり(その研究内容は、市原充『わがふるさと
城下町 大多喜地方風土記』(角川書店、1973)に「子規のミノ・ カサ旅行」として所収)、子規にはとても親近感を持ってきた。
このホームページでは、子規の大多喜旅行の一端と文学者の旅について触れたが、将来何らかのかたちで、わが故郷である大多喜と子規とのかかわりを、子規の大多喜旅行を中心に書きたいと思っている。
後日談
2002年6月8日(土)、大多喜に帰省した際、町なかに自転車で食料品の買い出しに行った。小谷松から桑曽根、上原を通って町なかへと入っていくいつものルートである。新丁(しんまち)では大屋旅館の前を通るので、突然ではあったが、正岡子規の大多喜旅行のことを聞いてみようと思い、ガラス戸を開けて入って行った。
大屋旅館は江戸時代から営業している歴史のある宿である。子規が大屋旅館に泊まったと書いてあるホームページを見たことがあるので、何か手掛かりになるようなことが聞けるかもしれないとは思ったが、先にみたように「酒井屋」に泊まったとしかわかっておらず、子規の投宿先が大屋旅館であるとは考えにくい。しかし、ホームページのとおり、子規が大屋旅館に泊まっていたのであれば、老舗ゆえ何らかの記録が残っているであろう。
声を掛けて、家人が出てくるまで、あたりを見ていたら、壁になんと正岡子規の色紙が飾ってある。小生のように子規のことを聞きに訪ねてくる人がほかにもいるようで、出てきた女将は、この色紙は本物ではなく、訪ねてきた子規の研究者という人から贈られたものであること(本物だったらこんなところに飾ってなんかおけない、と笑っていた)、子規がどこに宿をとったかはわからない、といったことをすらすらと説明してくれた。
懐古談(その1)
大多喜町には重要文化財の渡辺包夫邸があり、テレビ東京の人気番組「開運!なんでも鑑定団」の鑑定士を長年つとめ、先年亡くなられた渡辺包夫氏のお宅である。1849(嘉永2)年に建てられたという。
氏は小生が大多喜高等学校に通っていた頃の美術の先生で、ある時小生の絵をみんなの前で、「おい、誰だ? この左足で描いたような絵は?」と最大限のけなし方をしたのである。東京芸大の日本画科を出た氏であったので、小生の描いた絵は氏のそれと比較すれば、適切な批評であったのかもしれない。
横山大観の薫陶を受けたとの評もあるが、小生は氏を画家としてみたことはない。実際、氏の絵画を1度も鑑賞したことはないし(授業で披露されたことがあったのかもしれないが)、なんといっても、氏は「大多喜高等学校の美術の先生」であって、「画家」ではなかった(あるいは、氏は実作者より批評家であったのかもしれない)。
美術の最高学府を出ながら、田舎の高校で小生たちのようなできの悪い田舎小僧たちを教えているということへの、焦りのようなものがあったかもしれない、と今になっては思うのであるが、当時はそんなことには、思いも至らなかった。東京芸大を出たなどということは、小生など最近になって、「鑑定団」で有名になって知ったくらいなのだから。それに、テレビに出ていると級友から知らされたのも、氏の晩年になってからのことだった。
装いは、いつも三つ揃いに蝶ネクタイで(頭は、ポマードで決めていたと思う)、キザな先生であったが、完全にキザであったので、あまりいやらしい感じはしなかった、と記憶している。
懐古談(その2)
渡辺包夫氏は既に鬼籍に入っておられるのでありのままを書いたが、存命中の恩師となるとそうもいかないだろう。とは言っても、脚色するわけではなく、大多喜高校の英語の教師は実に多彩な方々が教鞭を執っておられた。
石井重郎先生は小生の3年間の在校中1度たりとも笑い顔を見せたことがなかった。教員室などではどうなのかは定かではないが、そこでニコニコしていたら軽蔑の対象にこそなれ、決して尊敬はされなかったであろう。我々は石井先生が自らは笑わずとも生徒を爆笑させるリップサービスにおいて類いまれな才能を持っておられることを知っており、授業でもそれを期待していた。石井先生によれば、吉永小百合は吉永さそりとなり、都はるみは都たるみであり、まだまだいろいろあったが今ではその多くを忘れてしまった。
当時教えていただいた先生で、今では駒澤大学と立教大学の名誉教授の方がおられるのも、いかに質の高い授業を受けていたかの証左である。
お一人は、河内賢隆駒澤大学名誉教授であり、アジア・太平洋戦争における日本軍の蛮行「泰緬鉄道建設」で捕虜となったイギリス人とオーストラリア人の日記の翻訳者として捕虜記録の分野で燦然と輝くお仕事をされている。書はロバート・ハーディ『ビルマ−タイ鉄道建設捕虜収容所 医療将校ロバート・ハーディ博士の日誌』、ウェアリー・ダンロップ『ウェアリー・ダンロップの戦争日記 ジャワおよびビルマ−タイ鉄道 1942-1945』の両書であり(ともに而立書房、共訳)、前者は「日本翻訳文化賞」を受賞され、後者は800ページになんなんとする大冊である。ウェアリー・ダンロップは今日でもオーストラリアの国民的英雄であり、書にはサー・ローレンス・ヴァン・デル・ポストの長文のまえがきが添えられ、あとがきにもサー・ローレンスから河内先生に宛てられた手紙が紹介されている。
もうお一方は、吉野利弘立教大学名誉教授であり、古英語、中世英語の大家であられる。しかし、吉野先生の業績をここで詳しく紹介することは小生にはいかにも任が重い。大学を出られてすぐに大多喜高校に赴任された吉野先生は、当然ながら若々しく、眼光鋭く繰り出してくるシャープな講義は後の業績を既に予感させるものがあった。高校の頃の恩師の方々は、このお三方ばかりでなく、日常における仕草まで鮮やかに蘇るのには我ながら驚きもする。