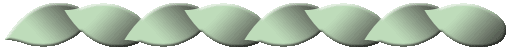
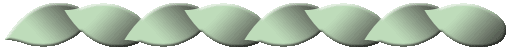
(2000年ごろ八王子マジックグループのHPに記載)
はじめに
ここ10年、いや過去にも私ほどマジックのコンテストに出場した男はいないであろうと思われる。(ギネスブックに載らないか?)その経験上の持論を述べたいと思う。今後多くの若者がコンテストにチャレンジする為の参考になれば幸いである。
1.コンテストの勧め
①コンテストはマジックの友達をつくる
私がマジックを始めたのは約10年前27歳のとき、飲み屋の女の子をナンパするためにデパートで買った四つ玉が最初のマジック道具だった。(いきなりマニピュレーション)約3年間マジックの友達はいなかった。「魔法陣」の堤さんだけが唯一の知りあいだった。(といっても私の名前を覚えてくれたのはここ3年ぐらいであるが。)
私がコンテストに参加するきっかけとなったのは約7年前SAMジャパンが開催した「第1回世界マジックシンポジウム板橋大会」だった。ステージ、クロースアップともに20人を超える参加者があった。初めてマジックのコンテストというものを見ることになる。
ステージコンテストにはアマチュアの実力者達が多数参加していた。FISMで2位になった菅谷さんやYUMIさんも参加していてレベルの高いコンテストであったがコンテスト半ばになると観客はかなり疲れていた。
私は、コンテストは変わったマジックを演じた人が優勝するものと思っていた。
しかし、一人の若手プロマジシャンが登場して、オーソドックスなカード、四つ玉、シルクをきちんとダイナミックに演じて観客の目を覚ました。プロマジシャンのカズ・カタヤマさんである。
私は「きちんとしたマジックは観客に認められる」ということを知った。私も出場してみたいと思うようになった。1年後、コンテストに出場するかどうか迷っていた。やはり恥ずかしいのである。私みたいなのが出場してもし、失敗したら、笑われたらどうしようというマイナス思考が働いた。
藤山新太郎先生に「友達をつくるつもりで出場しなさい」と言われ出場することになった。マジックのコンテストがこれほど緊張するものだとは思わなかった。何回トイレに行ったことだろう。手は汗ばむし、頭の中は真っ白だし、心臓の音が聞こえるし。
いよいよ私の出番。中盤まで結構受けていたが途中で道具を舞台袖に忘れてきたことに気がついた。演技の途中で取りに行ったがテンションは下がりっぱなしであった。しかし、コンテストの後で沢山の人が「コンテストに出てたね。よかったよ。」「面白かったよ。笑顔が良かった」など言われ友達ができたのである。
今から考えればお世辞だったのかもしれないが、参加して良かったと思った。
②マジックが上達する
コンテストに出れば練習せざる終えない。
結婚式やボランティアでやるための練習とは違うのである。
③結果がハッキリする
私は体育会系なので練習は試合に勝つためにあるものと思っている。
マジックをやれば「良かったですよ」と言ってくれるがどの程度なのかわからないしほとんどはお世辞である。その点コンテストは自分の演技は何点で何位とハッキリ数字で出るので目標を立てやすい。
2.日本のマジックコンテスト
コンテストへ参加するには当然申し込みをしなければならない。
今まで私が参加した国内のコンテストを紹介してみよう。
①SAM主催「世界マジックシンポジウム」
私が出場した最初のコンテストでステージ、クロースアップがある。ともに制限時間は10分で越えたら失格。例年8月頃開催されるが開催地が毎年変わるので開催地によって参加が難しいこともあるしコンテストのレベルも違ってくる。賞金あり。コンベンション参加費は2万円程度。SAM会員以外はコンテスト参加費5000円が別途必要。
②EMC主催「マジックマスターズオープン」
EMCが年2回開催しているコンテスト。ステージ、テクニカルアワード、クロースアップトーナメント、団体戦等がある。クロースアップトーナメントは5分の演技を1対1で戦いお客様の投票で決めるというもの。決勝まで行けば5手順必要。賞金あり。
外部からのゲストマジシャンや、レクチャー等は無いが観るだけなら無料というのがうれしい。コンテスト参加は1万円必要。
③不思議クラブ主催 「なにわのマジックコンベンション」
その名の通り関西で開催されるコンベンションで規模はSAMと同じぐらい。ステージ、クロースアップ、2分間コンテストがある。賞金はないがFISM招待やグランプリには海外ゲスト出演等がある。ステージ、クロースアップ共に制限時間は10分で越えたら失格。
④日本奇術会(協会ではない)「全国奇術愛好家懇親会」
2月に行われるいわゆる熱海でゆっくり温泉に入ってうまい物を食べマジックを観ようという会で参加費29,500円(宿泊、食事、おみやげ付き)メインはディーラーブースと言っていいくらいたくさんのブースが参加する。ステージコンテストがあり明確な制限時間は無いが10分以内であればOK。賞金はないが昨年から優勝者はSAMのコンテストに無料招待参加の特典がついた。
⑤マジックランド主催「厚川賞」
毎年12月2日に開催されるクロースアップコンテスト。制限時間は明確ではないが基本的に10分以内。作家の厚川氏が独創性のあるマジシャンを1人選ぶという審査方法で2位以下に賞はない。但し、最近はオリジナリティーよりもパフォーマンスに重点を置くようになった。
おそらく現在日本でもっともレベルの高いクロースアップコンテストで初心者の参加はあまり勧められない。他のコンテストを経験するかよほどの練習をしてからの参加を勧める。
⑥「奇術を楽しむ集い」
3年前までは河口湖で開催されていたが最近は石和で5月に開催されている。参加費、温泉、食事、宿泊込みで18、000円は格安。ステージコンテストで熱海と同じく年輩の参加者が多いが昨年は中学生、大学生の参加あった。1位から3位まで賞があり賞金も出る。コンテスト初参加を対象にした新人賞という賞もある。制限時間6分なので10分で手順を持っている人は組み直す必要がある。
このコンテストはクラブ対抗戦の要素が強く私もクラブ代表として参加したので個人で参加する方法がよくわからない。申し訳ない。
⑦UGM主催「ワールドマジックセミナージャパン」
2年に1度夏に名古屋近辺で開催されるステージマジックコンテスト。制限時間10分で3位まで表彰される。レベルは高くFISM1位の峯村氏を輩出した。
⑧ジョージマジックカンパニー主催「日本海マジックフェスティバル」
2年に1度6月頃新潟で開催。
ステージコンテストがあり3位まで表彰。その他特別賞もある。1位はラスベガス旅行。スタッフのジョージマジックカンパニーの働きぶりに脱帽。コンテスタントはやりやすかった。
⑨日本奇術協会主催「FISM代表選考会」
FISMの前の年末に開催される文字通りFISMの日本代表を選出するコンテスト。ステージ、クロースアップ共に代表者を選出し、協会が参加費旅費等を支給。プロの参加が多いため代表になるのはかなり困難。他のコンテスト等で実績のない場合はビデオ審査がある。
⑩マジックランド主催「箱根クロースアップ祭」
ひとネタマジックコンテストがある。一ネタであればなんでもOKだが一ネタの定義は不明確(一現象か?一手順か?)飛び入りOKで気軽なコンテスト。
3.申し込み
①申し込み時期と順番
さて出場するコンテストが決まったら申し込みをしなければならない。
出場人数が決まっているコンテストは締め切られる前に申し込みをする必要があることは言わずともわかっていると思うが申し込みの時期も考慮する必要がある。
というのは申し込みの順番が出場順になってしまうコンテストがあるのだ。そのようなコンテストで順番が早いほうがよいという人は早く申し込めばよい。但し、中から後ろの順番がよいという人は注意が必要である。コンテストの順番は審査にはあまり関係ない。
もし、順番の損得があるとすれば順番が早ければ
という利点があるが逆に
という不利なこともある。(ですからコンテストの順番は抽選で決めていただきたいと主催者にお願いしたいのである。)
②申し込み時の確認
このほか申し込む際に制限時間、火気の使用、ライトの調整(ジャリを使用する場合等)、舞台の大きさ等気になることは確認すべきである。事前にビデオ審査が必要な場合もあるのでご注意を。
4.手順の作成
①手順構成のポイント
さて、演技の手順を考えなければならない。コンテストによって多少基準は違うが演技30点技術30点オリジナリティー30点客の反応10点というのが多い。この項目を万遍なく得点すれば自然と高得点になる。
まず、スライハンドは必ず取り入れた方がよい。技術点を取りやすくなる。技術点のポイントは無理なことはやらず120%できることを確実にやることである。このほうが審査員に好印象をあたえるしミスは大きく減点されるからである。
オリジナリティーは本当にだれも見たことのないマジックができれば最高だが国内の大会ではそこまで考えなくてもよい。売りネタをそのまま使ったり、人のコピー(もちろん発表された手順)をそのまま演じたりしなければ大丈夫である。(審査員の知識によってはそれでもOKの場合もあるが)むしろ、自分のキャラクターを生かしたり、きちんとした流れの手順を演じた方がよい。
きちんとした手順とは赤いボールが白いボールに変化し、白いボールが白いハンカチになり白いハンカチからハトが出てくる。というように現象につじつまのあった手順のことである。これが最初にこれをやって、次はテーブルから全く関係のない道具を持ってきて演じるようなことではどんなに上手に演じても高得点は期待できない。
エンディングは、これでマジックが終わったなーとお客様に伝わるような現象がよい。必ずしも派手な現象や大きな物を出すことがよいエンディングではない。
②散らかさない
また、無意味に舞台を散らかさないようにすべきである。特に紙吹雪は掃除するのに大変時間がかかり次の演技者に迷惑である。どうしても使いたい場合は大きなシートを持参してその上に散らかすべきである。散らかすことは練習効率も悪くなり、練習場所も選ぶ必要があるので考えるべきである。
③ジャリ
ジャリを使う場合は照明に影響される(光るのである)のであまりおすすめできないが照明係に頼んでみよう。但し舞台が全体的に暗くなってしまうことを覚悟すべきである。
④火気
火を使うマジックは火事にならないように注意すべきであることは常識だが、コンテストをみると火のついたフラッシュペーパーを床に投げつける演技者を見かけるが、必ず空中で燃え尽きさせるか、安全なものの上で燃やすべきである。
もし、火事になった場合(些細な事故でもだが)そのステージで二度とマジックをさせてもらえない可能性がある。少なくともそのステージで火は使えなくなるので他のマジシャンに迷惑である。そのことを十分考えて使用し、消防用の水や消火器の確認等は必要である。
出番前にオイルの調整をする必要がありかなり神経を使うし、気温や空調の関係で火がつかないことが結構多い。場所によっては火を使えなかったり、消防署の検査が必要な場合がある。この消防署の検査が結構面倒でステージがある地区の消防署にわざわざ出向いて道具を見せ安全であることの証明をしなければならない。(消防署の方はマジックをご存知ないのでかなり大変。タネを見せなきゃならないし)
以前FISM予選のコンテストで私が使う道具の説明に3時間ぐらいかかったことがあり、奇術協会の担当の方に大変迷惑を掛けたことがあった。(ダーク広和さんごめんなさい)開催地が遠い場合は検査不可能な場合もあり、可能であれば火は使わない方向で手順を構成することをお勧めする。
⑤音楽
これも基本だが音楽テープ、MDは1本にまとめるべきである。もちろん、頭から録音するべきで使わない曲はいっさい入れない。MDは複数の曲を使っていても1曲にコンバインするべきである。操作のミスで音をとばされる可能性がある。
MDは使えない可能性があるので必ずテープももって行くべきである。テープだけの場合もアクシデントを考えて予備のテープをもっていくべきである。CDはいらない曲が入っている場合が多いので基本的にはNGである。
また、カセットテープデッキは機械によって多少スピードが違うので制限時間の15秒前には終わるように編集しよう。
⑥制限時間
クロースアップは制限時間を注意しよう。ステージは音楽の時間が決まっているのでタイムオーバーはあまりないがクロースアップは言葉やお客様とのやりとりで時間が変わってしまう。練習はストップウォッチで常に時間を計り常に制限時間の30秒以上前に終わるようにすればトラブルにも対応できる。
⑦クロースアップの見せ方、アイテム選択
クロースアップコンテストとはいえ100人以上の観客に見せる場合サロンの要素が必ず必要になってくる。テーブルの上に置いた物は立体的な物でも後ろの人には見えない。テーブルの上に置いたカードは最前列の人しか見えないと思ってよい。
テーブルの上で現象が起こるコインアセンブリようなマジックはコンテスト向きではない。現象は手に持ってできるだけ高い位置で起こす方がよい。できるだけビジュアルなマジックを取り入れた方がよい。
カードやメンタルマジックはよほど演出を考えないとお客さんがついてこない。特にカードは他のコンテスタントも多く使うのでお客さんも飽きてきて半分ぐらいのお客様はカードなど覚えないし複雑なカウントを使った長い手順のカードマジックは見てもくれない。
⑧直前のアイディア
コンテストの数日前に新しいアイディアが生まれることがあるが今回はあきらめよう。直前に変えても十分な練習をしてない手順はやるべきではない。
5.練習方法、ポイント
演技は練習をビデオにとってチェックする。そしてみっともないところを直す。鏡でみるのと違って客観的に演技を見ることができるのである。演技のポイントをいくつか指摘しよう。
登場していきなりマジックを始めないこと。いきなり始める場合はその後間を取ること。まず自分の存在をお客様にアピールし「私はお客様を愛している」という笑顔で自分をお客様に受け入れていただくことが必要。
動作はゆっくりと行う方が見やすい。速い動作の場合でもきちんと動作を止める箇所をつくる。現象が起きている方の足に体重をかける。たとえば右手でカードを出している場合は右足に体重をかけてバランスをとるのである。試しに逆の足に体重をかけて演技してビデオで見てみるとわかる。とてもみっともない。
クロースアップでは後ろのお客様に聞こえるように声を出そう。一流のクロースアップマジシャンは常にはっきりと声が聞こえる。ふつうに話をしていて声が通ることが理想だが最初は大声を出すぐらいのつもりで発声しよう。
6.当日
①忘れ物
さて、いよいよコンテスト当日、忘れ物をしないようにチェックをする。チェックシートを作ることが望ましい。練習で使った道具をそのままバッグに入れたりすると忘れ物をしやすい。
まず、音楽テープ、MD(これを忘れるとどうしようもない)化粧品、アクセサリ、本番用シャツ、ライターオイル、備品(はさみ、セロテープ等)など忘れないように注意する。
そして部屋を出る前もう一度入れ忘れがないか部屋を見回す。
②リハーサル
コンテスト打ち合わせ時間には遅れないようにする。たとえ何も打ち合わせすることが無くても必ず行く。参加しないと失格になることが多い。そのときに必ずキューシートを作成し持っていく。これはスタッフが音響、照明、幕などのタイミングを間違えないようにするために必要である。
コンテストは何十人もの演技がいっきに行われるためノーリハーサルが基本である。よって複雑な要求をすることはできないし、危険である。スタッフへの作業はできるだけシンプルになるようにキューシートを作成しよう
キューシートの例を挙げてみよう。
(1)幕オープン
(2)照明ON
舞台は全照でピンスポットがあれば演技者を追ってください。
照明は基本的にエンディング直前までこのままでお願いします。
(3)音楽スタート。
テープは一本で約7分30秒です。音の大きさがOKであれば
以降いっさいの操作は必要ありません。
(4)演技者が上手から登場します。
(5)前半はカードです(約3分)
(6)カードの演技が終わると音がいったん止まりますが終わりではありませんので
そのままにしてください。照明もそのままにしてください。
(これを書かないとここで音や照明を止められる可能性がある)
(7)後半のハンカチのマジックです。
(8)エンディングはハンカチがたくさんわき出るマジックの後大きな旗を出してポーズを
取ります。
そのときに音が自動的に止まりますので照明を暗転にしてください。
(エンディングのイラストや写真があるとベスト)
打ち合わせ時には音楽テープとキューシート3部(音響、照明、舞台)筆記用具のほかエンディングの道具も持っていって説明するとよい。できれば音が出るかどうかだけでも確認をしてもらうようにしたい。(特にMD)
③楽屋
コンテスタントは平等なので楽屋の上座下座と言うのはないが順番が速い人から出やすい場所を使うようにしよう。そして場所を占領しないように限られたエリアでセッティングし使わない物はカバンにしまうか、整理整頓しよう。
7.本番
①出番前の緊張
いよいよ、コンテストという段階になると緊張してくる。これは誰でも同じである。と思ってよい。緊張をほぐすために柔軟体操をしよう!!これだけで筋肉の硬さがとれてかなり楽になる。緊張で手が汗ばむ可能性がある。ボールの演技には問題ないがカードの演技には影響が出る。薬局でパウダーを購入し手にまぶして汗を調整しよう。
「勝つのではなくお客様を楽しませるのだ」という気持ちで待とう。そして速やかにセッティングできるように準備しよう。
②演技中の緊張
さて演技スタート。
後はもうやるしかない、が緊張で手がふるえている場合は意識して力を抜いてみよう!!ふるえが止まるはずである。
③演技後
さあ、うまく演技できただろうか?
失敗したら、それはスタッフのミスを含めてすべて自分の責任である。次のコンテストで同じミスをしないことである。演技が終わったら速やかにかたづける。散らかした場合はとりあえずほうきで掃く等をして次のコンテスタントの迷惑にならないようにしよう。
友達がきていればかたづけを手伝ってもらおう。(1人で簡単にかたづけられるように手順や道具を考えるのがベスト)そして、スタッフにお礼を言おう。スタッフなしでは演技はできない。裏方様は神様である。
④審査員からのアドバイス
発表後、審査員にアドバイスをいただこう。
審査結果説明会がある場合は必ず参加し、ない場合は審査員を捕まえて聞いてみよう。
もちろん丁寧にうかがいお礼を言おう。(コンテストの審査は重労働である。審査員に感謝。)
8.あとがき
さあ、ざっとコンテストについて書いてみたがいかがだろうか。
とにかくはじめの一歩が大切。最初のコンテストでは入賞はできないと思った方がよい。それでも一度出場してしまえば後は気楽に申し込みできるでしょう。もう一度言うがコンテストに参加すると友達を作りやすい。これはトロフィーよりも大きな財産ではないか。