それからオレたちがどうなったのか....正直言えば多くを語りたくはない心境だ。それは誰もが想像しうる「バリバゴの日常」そのものだったからだ。あまりにも平々凡々とした日々が続いた。二泊三日の強行軍で、東サマールからアンへレスに戻ったオレたちは、語る価値もないようなありきたりでのどかな日々を半年ほど過ごした。
その合間にオレは中国やタイやスリランカを旅し、たまに日本に行き、そして懐かしいねぐらに帰る渡り鳥のような思いでアンへレスに舞戻った。人はそういう弛緩した日々に癒されるのだろうが、オレにはたえられなかった。だから、ときには悪趣味が働き、自虐的な展開を期待して、事前に何の連絡もせずにいきなりバリバゴに乗り込んでみたりした。しかし気の利いたドラマはなにひとつ起こらなかった。この街の「なじみの女」にありがちな、行方知らずや不審な行動などはまったくなく、セシールはいつも不意に姿を現したオレを遠くから目ざとく見つけ
(また、冗談やってるねアイツ!)
とでも言いたげに、店のドアの前で素っ頓狂な顔をして立ちつくし、そのくせ全身にうれしさをこらえきれぬ表情を浮かべながら、久しぶりに会うオレを迎えてくれたのだった。
不在のあいだひとりでどうしていたかなど、野暮な詮索をしたりするのはオレの趣味ではなかった。この街の女どもは、自分のためではなく家族という重い荷を背負い、大なり小なり「プロ」として働く者たちだということぐらい百も承知だった。一方このオレも、「プロの客」としてのプライドがあった。しかも、オレたちはどんなに相性の良さを確かめ合おうとも、ぎりぎりのところで互いに対峙し合う緊張があった。セシールには、この街の女の体臭を匂わす程度に、他の男たちの影が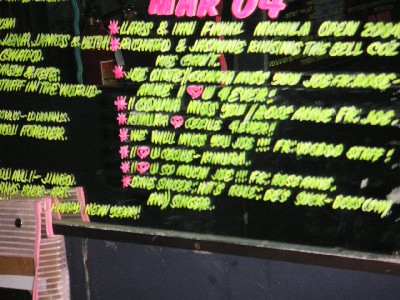 ちらついていた。 ちらついていた。
いつも陽気で冗談が好きな女だった。その冗談は概して心地よかったが、ときには度を過ぎることもあった。タガログ語の「マクリット(makulit)」、つまりしつこさがそこにまとわりついてくると、警戒信号である。彼女のふざけと冗談は収拾がつかないところまでいき、いつしか互いの笑顔は引きつるまでになり、心はささくれて知らず知らずのうちに険悪なムードになった。女はかまわれて喜びを知る五感動物だということか。それでも挑発に乗らず冷静に構えていると、時には本当に喧嘩にもなった。
そのたびに彼女は「もうおしまいね」と捨てぜりふを残して部屋を飛び出し、ホテルと目と鼻の先のステイインにかけ戻った。そうして数時間後には、何事もなかったかのようにけろりとした顔をして、少女のあどけなさでまた部屋のドアをノックし、彼女のひとり芝居は幕を下ろした。少しばかり運がいい男なら、バリバゴのどこにでも起こりうるそんな日常の痴話ばなしを、わざわざここで語る自分が気恥ずかしい。
ある日のことだった。オレは夢の中で不意にあることを思い立ち、それを実験してみたくてその年のクリスマスにふたたび東サマールに行った。その出来事については、いつか語る機会があるかもしれない。その詳細はさておき、この二度目のサマール行きがオレたちの破局につながった。オレたちはクリスマスが明けた翌々日、初めて修復できないほど深刻な喧嘩をした。それは、互いを傷つけ、それ以来今日まで、ただの一度も会っていない.......。
破局に至った喧嘩の原因は、何か。突き詰めれば、それはどうにも乗り越えることの出来ない彼女の境遇の貧しさだった。貧しさがすべての誤解の源になっている。運命としかいいようのない、その生まれ育った環境が、ときには人の期待や信頼を裏切る場合があることを如実に示す、ある事件が起こったのだ。そして彼女は爆発した。
「ええそうよ、何もかも私が貧乏だからこうなったの、それがどうしたというの!」
やるせない思いだったに違いない。出稼ぎに出て、一歳に満たない乳飲み子を年老いた母親に託してバリバゴで働く女、セシール。決して認めたくはなかっただろうその冷厳な境遇を、彼女はあふれ出る涙をぬぐうこともなく、絶叫に近い言葉で開き直って見せた。オレはその言葉を聞きたくはなかったが、彼女の口からその残酷な現実を告白させるほどに追い詰めてしまったのだ.....。その瞬間、風景からすべての音が消え、色を失った。ものすごい剣幕でいきり立つ彼女の姿が、灰色のスローモーションとなって目の前をよぎり、サマールの空に歪んでちぎれた。一期一会。袖すりあったひとりのバリバゴ女と旅行者が重ねた日々は、あっという間に燃え尽きたと思った。オレは次の日セシールをサマールに残して、マニラから日本に戻った。
普通の旅行者になる決意を固め、年が明けてほどなくしてオレはまたひとりでア ンへレスを訪れた。セシールは、迷走したように郷里とマニラの姉の家とを行ったりきたりした。何度もTEXや電話をよこした。ときには、日本に国際電話をかけてきたりもした。しかしオレは、会うことをかたくなにこばんだ。 ンへレスを訪れた。セシールは、迷走したように郷里とマニラの姉の家とを行ったりきたりした。何度もTEXや電話をよこした。ときには、日本に国際電話をかけてきたりもした。しかしオレは、会うことをかたくなにこばんだ。
繰り返すが、ふつうのバリバゴの旅行者に戻る決意にゆるぎはなかった。しかし、セシールはオレがバリバゴにいることを友人から聞きつけて、ひそかに彼女もアンへレスに入り、元のステイインに身をひそめていた。いま自分が目と鼻の先にいることをにおわせながら、オレの気持ちを最後まで探るTEXを何度も送りつけてきた。そのつどオレは、もう新しい女が横にいるからと、つれない嘘を彼女に返した。そしてあるとき、業を煮やした彼女から電話がきた。
「もう、会いたくないのね」
「会っても仕方がないだろ。自分だって分かってるはずだろ」
セシールは、電話の向こうですすり泣いている。
「あなたに、重大な話があるの」
オレは不吉な予感が走った。
「えっ、何の話?」
「どうしてもあなたに言わなければならないことがあるの」
一瞬オレはたじろいで、良からぬことを想像した。心臓が高鳴った。
「聞いてくれる?」
「..................」
「ほんとうに大事な話で、どうしてもあなたに耳に入れておきたいことがあるの」
やけに真剣な口調が、気にかかった。
「ああ、.....なんだい」
「私とどうしても結婚したいという人がいるの。あなたの考えを聞かせて.....」
予期していた話題とは別だった。オレは内心ほっとした。
「考えをあなたの口から聞きたいの、どう思う」
オレはそのとき、こちらの気持ち確かめようとする彼女の小ざかしい狂言だと思っていた。最後の悪あがきにも聞こえた。
「結婚?いい話じゃないか、セシール。君を幸せにしてくれる人がいるなら、そちらに突き進むべきだよ。君がほんとうに幸せになれるのなら、オレも幸せだ。ゴー・アヘッド。そうしたほうが絶対にいい」
的確な助言が、かえって冷たく彼女に響いたようだ。
「私たち、ほんとうにもう会えないのね...」
セシールは、電話の向こうで号泣した。
結婚の話はほんとうだった。太ったアメリカ人の客がいて、オレが店に行くと激しいやきもちを妬いて何度も店を飛び出していたことを彼女の口からきかされた。 そもそも、その相手の方がが先だったのだ。彼はオレが登場する以前から、セシールにアプローチしていた。オレが現れてからほぼ1年もの間、いつも日陰者として我慢し苦しんできたのだった。いよいよオレが撤退するらしいことを知り、この時とばかり身請けを決心したようなのだ。彼女は、男の申し出に結論を出す前に、最後の気持ちをオレに確かめたかったのだ。やめろといえば、彼女は喜んだのかもしれない。そういう決然とした言葉を期待していたのかもしれない。しかし、オレは非情にも他の男のもとに行く道を選択させた。あの貧しさと、どうあがいてもそこから逃れられぬ呪縛の環境を見てしまったオレは、セシールと彼女の子供の将来のために、より確かな幸せを選択する道に押しやったといっていい。彼女は、ファイナンシャルセキュリティ(経済的安心)を求めて観念し、傍らに残された読みきれぬチャンスに飛びつこうとしていた。それは言い換えれば、オレとのへその緒を絶つ痛みの儀式でもあったのだ。 そもそも、その相手の方がが先だったのだ。彼はオレが登場する以前から、セシールにアプローチしていた。オレが現れてからほぼ1年もの間、いつも日陰者として我慢し苦しんできたのだった。いよいよオレが撤退するらしいことを知り、この時とばかり身請けを決心したようなのだ。彼女は、男の申し出に結論を出す前に、最後の気持ちをオレに確かめたかったのだ。やめろといえば、彼女は喜んだのかもしれない。そういう決然とした言葉を期待していたのかもしれない。しかし、オレは非情にも他の男のもとに行く道を選択させた。あの貧しさと、どうあがいてもそこから逃れられぬ呪縛の環境を見てしまったオレは、セシールと彼女の子供の将来のために、より確かな幸せを選択する道に押しやったといっていい。彼女は、ファイナンシャルセキュリティ(経済的安心)を求めて観念し、傍らに残された読みきれぬチャンスに飛びつこうとしていた。それは言い換えれば、オレとのへその緒を絶つ痛みの儀式でもあったのだ。
「私の人生で、かけがえのない人がふたりいる。ひとりは、子供。もうひとりは、あなた。私たちの家族のためにしてくれたすべてのことに感謝しています。さようなら....」
それが彼女の最後の言葉だった。
セシールの結婚を決めたのは、オレだといっても過言ではない。しかし、彼女とオレとの、その最後の電話のやりとりを知る者はいない。だからバー「V」の女たちも、KOKOMOSの従業員たちも、オレが知らぬ間にセシールが他の男と電撃結婚をしたと思い込んでいる。バリバゴに行くたびに、かつての二人の関係を知る者たちは、女に逃げられた惨めな男に寄せるあの特有の憐れみを帯びた視線をいまでもオレに投げ続けている。彼女は、バリバゴの女にふさわしい、したたかな悪女の栄光のイメージを勝ち取りながら、この荒ぶる街を去っていった。オレは、口をかたくなに閉ざしたまま(これでよかったのだ)と自分に言いきかせている。
セシールは、そのアメリカ人の客だった男と結婚してマニラに住んでいると言う。本当か嘘かは知ったことではない。またそれが幸せをもたらしたのかどうかもどうでもいい。今でも彼女はオレの声が聞きたくなったといっては時々電話をかけてくる。もう、彼女がバリバゴに戻る可能性はありえないと信じたい。
注:画像はすべてイメージで、文章の内容とは関係がない
|
 |