|
|
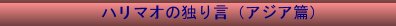 |
|
|
|
2002年4月29日
近頃のオレは病気じゃないかと思うときがある。
現に回りの人間からそういわれ始めている。何の病気かといえば「PC依存症」とでもいえる厄介な病気だ。症状というのはいたって単純だ。暇があれば一日中PCの前に座ってキーボードを叩き、MOを入れ替え、FTPサーバーにアクセスし、ファイルを書き直している...そんな他愛もない病気だ。しかし、周囲に与える戸惑いはなみなみならぬものがある。
天気がいい日も悪い日も、実に朝から晩までPCの前に根を張って座っているという、自分でも原因不明の病いである。世の中のおじさんならば、今頃は会社の上司のゴルフに付き合ったりなどして、ボーナス前の査定にちゃんと見えざる加点をする努力をしているだろうに、このオレはといえばそんなことに費やす時間がもったいなくて仕方がないのだ。
病気というのは、あくまでも相対的な関係の中で、ある不可思議な異常値が観察される場合に疑われるものだが、そういう意味でいえばオレの行動は「異常値」フェロモンを随所で発散させているといえるかもしれない。しかし、オレの絶対的基準で診察すれば、オレのやっていることはちっとも異常ではなく、根拠の明白なすこぶる楽しく健全な状態というほかはない。
いつも睡眠不足で、帰宅も午前様だというのに、家に帰ってすぐやることといえば、まずPCのスイッチを入れてメールチェックをすることなのだ。一日100通近く舞い込んでくる。必要とあらば受信メールに返事を書き、自分のホームページの掲示板を覗き、書き込みを確認してRESやMESを入れたりしている。
年齢のせいだろう、仕事をしていても午後のある時間帯になると急激に睡魔が襲ってくることがある。そういう睡魔にはちょっと抵抗しにくい。また、飲み屋でも10時や11時を回る頃激しい疲れが襲ってきて、ボオーッとしていることがある。おじさん特有のそんな現象が観測されていても、ひとたび帰宅すると、目が覚めそれから最低30分から1時間は必ずPCと対話してからでないと眠れないのだ。
休日というのは、体力のなくなった中高年のためにあるようなもの。感謝して、週末には昼ごろまで寝床でごろごろし、たっぷり睡眠をとってカラダを休め翌週の就業に備えるべきかもしれない。
しかし、オレはといえば休日ほどなぜか早起きしてしまうのだ。朝6時にはもうPCの前に居座ってしまう。阪神淡路島大地震のときにも、4時45分だったか5時45分だったか忘れたけれど、あのときも起きていて、かすかな揺れを東京に自宅のPCの前で感知した。異常値といえるほどの早起きをし、そして深夜の零時か1時ごろまでゴソゴソとPCで何かをしているのである。病気特有の「異常」という意味では、まさにこの長時間ワークそのものがヒトには異常値に映るようだ。
PCのモニターを2時間以上見つめているとカラダに悪い、といわれている。もし本当にそうならば、オレはとっくの昔にPCに起因する癌かAIDSに罹っているはずである。しかし、げっそりやつれるどころか、運動不足が原因で反対に太るばかり...。この肥満は紛れもなくPC依存症の合併症に違いない。
 最愛の恋人:myPCs 最愛の恋人:myPCs
この厄介な病気は、近頃「国際問題」にまで発展しそうな気配である。
PPのオキニたちが、うすうすこの「手の施しようのない病気」に感づいてきたみたいなのだ。これまでは、オレが最近店から足が遠のいているのは、他の店のババエにうつつを抜かしている「パロパロ(浮気)」が原因だろうと思い込んでいたようだ。しかし、どうもそうではないらしいことに感づいてきたのだ。
「あなた〜!いま誰と一緒!?」
昨日までそんな荒っぽい電話を掛けてきたババエが、近頃では
「イカウ(あなた)、またインターネット・カフェにいるんでしょ!」
と、イラだちを隠し切れぬ口調で留守録メッセージが頻繁に入るようになってきた。
競争相手が生身の人間ならまだヤキモチも妬き、恫喝もし、妨害もできようが、「浮気相手」がPPじゃなくてPCだというんじゃどうしようもない。とはいえ、夢中になり方が半端でないので、そのほうが余計やり場のない苛立ちがつのるようだ。
いつかはと思っていたが、ある日最後通牒を突きtけられた。
「あなた、インターネットとワタシとどっちがだいじなのよ!」
フィリピンにいたら考えられもしなかった「花粉症」よりも手ごわい「PC依存症」。原因がそこにある奇異なる嫉妬のケースに、彼女たちが困惑しているようである。
|
|
2002年4月29日
一日のうちに何度か「東南アジア」がオレの脳裏をよぎる。目覚めているほぼすべての時間にオレの脳の活動を完全に支配していると思えるときがある。近頃そんな日が増えてきた。脳がそうであるから、心もきっと脳の赴くままに、黙って従っているはずだ。
足を踏み入れたことのない国は東南アジアでただひとつ、ラオスだけになった。自分でもよくここまで歩き回ったものだと感心する。東南アジアはいまオレの目の前に、うっそうと生い茂る緑と赤茶けたラテライトの土とで工作した、小さな箱庭のように映っている。
箱庭の砂場の何箇所かは綻びて、そこに暗いじめじめとした穴が潰瘍のように開いているのが見える。その小穴の奥には腐敗した生物がいるのだろう、白色や黄色や褐色の蛆虫が、ぞろぞろとうごめきながら出たり入ったりしている。白はファランと呼ばれる欧米人系、黄色は日本人系、褐色は現地の華人系蛆虫だ。
大きな穴はタイのバンコクやチェンマイ、カンボジアのプノンペン、そしてフィリピンのマニラあたりにポッカリと開いている。小さな穴はインドネシアのビンタンや、タイのハジャイ、フィリピンのアンヘレスのあたりに開き、そこにも新鮮な腐食生物が埋もれているのか、新しいいきのいい蛆虫たちが活発に出入りしている.....。
東南アジアに深く関わるようになってもう10年近い時が過ぎようとしている。しかし深くのめりこめばのめりこむほど、自分が蛆虫のように腐食動物のうごめく暗いじめじめとした穴の入り口を覗いてばかりいるような気がする。東南アジアへの興味や情熱がすこし荒れて焦点がずれてきたように思うときがある。
10年前の自分を振り返れば、ペナンやマラッカで活躍していた19世紀初頭の植民地政府官吏サー・トーマス・ラッフルズの生き方に興味をもち、そこからまずマレー文化にとてつもなく惹かれた。マレーという言葉が表題についた書籍は、あのころ片っ端から読み漁ったものだ。やがてそこから文化人類学や民族学にのめりこみ、海のブギス族さながらにマラッカ海峡からパプアニューギニアあたりまでを漂流した。フィリピンにはまり込むきっかけとなったのは、ロンドンで何度も観たミュージカル「ミス・サイゴン」だった。
東南アジア。それは確かに昔も今も箱庭だが、かつてのオレは箱庭のまわりの海も、それを包み込む地球もしっかり見すえていたように思う。それがどうだ。いまは「東南アジアの潰瘍」といっていい暗いじめじめした生臭い小穴に虫眼鏡を当ててまで観察しているていたらくだ。初心に帰る必要がある。
オレの東南アジアの出発点は、シンガポール建国の父として知られるラッフルズその人だった。植民地政府で最後には副総督にまで出世した人物だが、サラリーマン人生としては不遇な人だった。船乗りの子として、地中海に浮かぶ船上で生まれた彼は、決して自慢できる出自でもなかったため、野心家だったわりには出世にも限界があったと思う。スマトラの西海岸ベンクーレンに左遷されたときには、風土病で二人の子供を失い、人生のどん底にあった。
失意の中でラッフルズは、役人以外のもうひとつの顔である博物学者としての才能をいかんなく発揮し、スマトラ奥地で、自らの名を学名に冠する「アーノルド・ラフレシア」という世界最大の花を発見する。
 アーノルド・ラフレシア アーノルド・ラフレシア
その花の画像をオレは今日偶然にもネットの中で発見した。
荒れきったオレのアジアへのまなざしを、もう一度反省するいいチャンスだった。この花を見つめながら、東南アジアとともに暮らしたラッフルズの生きざまを思い起こしつつ、東南アジアの知の漂流の原点に立ち返ってみたいと思った。
|
|
2002年4月28日
とある店のジャネット(仮名)ちゃんが、深夜突然なにかに憑依されたように、ふっと席を立ち、不意にセクシーダンスを踊り始める...まさにその現場に、オレはあるとき偶然居合わせたことがある。
両手を手櫛にするしぐさで髪の毛を後ろにしっとりとかき上げ、その手がバストの両脇に這い降りたかと思うと、今度は親指が、両肩を露わにしたドレスの細いストラップに内側からかかり、それをゆっくり肩からはずしていく...。そこから無邪気な手は横腹を滑って腰に落ち、太ももの内側をなで下ろしている。上体が左右にリズミカルに振れるのに合わせて、ゆっくりと腰は沈み、膝が自然に薄暗がりのなかで大胆に割れていく...。そのみごとな一連の動作が、ライブの曲に乗せてなまめかしく緩やかに繰り返されるのだ。
ジャネットは店一番の巨乳。年齢は不詳だがしぐさが愛くるしく、初めての客にはその明るさが受けてすぐに人気者になる。いつかオレの仕事場の若い女子従業員をふたり連れていったときもすぐに打ち解けてしまった、サービス精神旺盛のジャネット。気がつくと女子社員とオレの間に入って、こちらには背を向け、彼女たちと真正面に向き合いながらなにやらもぞもぞとやっている。
なんだなんだと肩越しに見ようとしたらひどく怒られた。どうやら女子社員の手を奥深く引き寄せて、ジャネットが自慢のバストを触らせていたのだ。
「水のふくろみたいでした」
日本の高等教育機関の最高位に位置するトーキョー大学卒業のA子が、上司であるオレの気持ちをおもんばかって、自ら感想を報告調に手短に述べると、
「すっごくデッカ〜イ」とこれまたケーオー大学卒業のいかにもお嬢様然とした顔立ちのB子が、容姿とはまるで不似合いな言葉遣いで負けじと報告する。
このふたりは、オレがPPのハマリ組みにしてしまった最初の日本人女性たちである。とくにA子からは頻繁に「連れてってコール」があり、この店がお気に入りなのだ。
ジャネットちゃんは賢いババエだ。セクシーダンスをしたその夜も、店はかなり暇だった。全体ムードに乗りが悪くなるとババエたちは睡魔に襲われて、座っているだけでも苦痛になってくる。そんな間延びした空気だったのでわざと「憑依現象」を取り繕ったのに違いない。
回りを見れば残っているのはオレを含む常連の気心知れた客ばかりという安心感もあったのだろう。沈みきった店の空気が、あっというまに盛り上がる。タレントと違い、ずっと立ったままで仕事をしてるスタッフも活気づき、特別な暗さに照明を落としてジャネットのショーに協力する。客もババエもすっかり興奮して、1000円札のチップがどんどんジャネットの巨大な胸の谷間に差し込まれていった...。
ジャネット。ふだんは勿論そんなことはやらないし、店もそのようなショーを売り物にしているわけではない。いつも愛想のいいひとみがきらきら輝いているババエの意外な才能に驚かされた。彼女のスペシャルダンスの迫力はすさまじかった。マニラの「ミス・ユニバース」の舞台を見たことがある人は、想像がつくだろう。突貫級のセクシーダンサーが踊るあの振りである。
どこでそんな芸を身につけたのだろう。もしかしたら昔本国で踊っていたのじゃないかと、誰もが思ったに違いない。オレもあの振りはただものじゃない気がした。この店には黙っていれば、率先して踊りそうなババエが他にも何人かいる。ふだんは大枚のチップをはずむといってもやらないだろう。
この突発的事件のために、そろそろチェックをして帰ろうと考えていたオレは予定にない延長をせざるをえなかった。客が少なかったので、いまいる客の滞留時間を増やして売り上げに貢献しようと、やさしいジャネットが計算したのだろうか...。
場内のざわつきが静まったころあいを捉えて、ジャネットちゃんをべた褒めし、スタッフに「チェック(お勘定)」と言おうとしたら、ジャネットちゃんは「まだ早〜い」といいながらオレを引き止めにかかる。
「これからもっと何んかあんの?あんならもうちょっと居ようかな」
冗談でそういうと、少し酔いかけているジャネットが、またすっと目の前に立ち上がって肩紐に手をかけそれを引き下ろすしぐさをはじめる。
「オ、オ〜、イカウのため、特別あるよ、これから」
そういって、大胆にバストのトップラインあたりまでドレスのラインを引き下げようとした。このときどうやらドレスの肩紐だけでなく、ビニールでできた透明のブラジャーの肩紐までも親指に引っかかったのだろう、ジャネットご自慢の持ち物が頂上まで露出してしまった。
オレはハッとしたが、なんと巨乳の先っぽには肌色のテープが貼りつけてあり、しっかりガードしている。オレは思いもかけぬ発見に心の中でしてやったりと小躍りした。
まだまだ知らない世界があるものだ、帰りの電車の中でオレはつくづくそう思った...。
|
|
2002年4月27日
先日、滅多に行かない浅草のある店に入ったら、二年ほど前によく指名していたババエと偶然出遭った。当方はその店では一見に近い客だったから、気恥ずかしさもあって、節目がちにしてスタッフの案内する席に着いたのだった。オレが店に入った瞬間から、彼女の方がすでにこちらに気づいていたらしい。
「とくに指名はないです」
オレにそう言われて承知したはずのスタッフが、すぐに舞戻ってきて
「以前○○で働いていた△△ちゃんが、ぜひ呼んでいただけないかと言ってるんですが....」
と苦笑している。
名前を聞いてピンときた。オレは少し間をおいて、
「じゃあ場内(指名)だったら」とOKした。
すぐさま、△△ちゃんが薄暗がりから現れ、細いきゃしゃな腕を差し出して握手を求めてきた。日本に来たばかりの荒削りな愛らしさとは違って、髪の毛をショートカットにして、すっかり洗練された都会の美人に生まれ変わっていた。
「よお、ここにいたのか〜」
オレがそういい終わるか終わらないうちに、横に腰を投げ出すように沈めた彼女が少し力を込めてオレの頬に「パチン!」と平手打ちを食らわしてきた。はっとした。生まれて初めての経験だった。そのわずかな隙の一部始終を、店の他のババエにも見られてしまっただろう.....。しかし、そのパンチには悪意らしきものが込められていなかった。
「なんでメインじゃない。スタッフにいうナ、(場内からメインに)チェンジって」
「ここにいるって知らなかったしさ、もう場内って言っちまったヨ」
「も〜、ホントに〜、冷たいなんだから....いつもいつもナ〜」
口をとがらせながらも、それからの彼女は、いる間じゅうずっとオレの腕に抱きついたり、しなだれかかったりして甘えっぱなしだった。いつのまにか、「人前でも甘えるオンナの武器」をみごとに習得していた。
前の店で一時期よく応援してやった。ところが何かのことで疎遠になり、最大のイベントの「サヨナラパーティ」にもオレは顔を出さなかった。オンナを追わない主義のオレとしては当然の行動だったが、面子を重んじるフィリピーナの彼女にとっては決定的な仕打ちに思えたに違いない。それから何度か国際電話ももらったが、それきりでいつしか音信が途絶えてしまっていた。
しかしオレの横で幼児のように甘える彼女に、このときなにやら危険なものを感じた。
これまでの経験で、ある空白期間をおいて再会したババエとはいっそう安定した気心の知れた関係になることが多いことを思い出したのだ。特にプライドの高いババエとの間にいえる。パアっと燃える上がる恋もあるが、そうした分かり合っている自信に裏打ちされた恋というのもあるものだ。
追えば二年も三年もかかるババエでも、半年の空白期間をおくことでなぜか一年で親しくなれそうな気がする。愛情のためだけというより、それは商売のための動機ということも抜きがたくあるはずだが、オンナの側に自分の過去の対応の過ちを反省して、一度去ったものを必死に取り返そうという意識が強く働くからだといえる。
何かと謎の多いフィリピーナ。その付き合いのなかでの「空白期間」が加速装置になり、ときには「キューピット」にもなりうることだけは、やや確信をもっていえる。
|
|
2002年4月26日
新しい出版物のアイデアをこのところずっと考え続けている。
もう長いあいだ東南アジアにかかわってきて、オレもずいぶんいろんなことを知った。知らなくてもいいようなことが山のように増え、オレのなかの「ゴミ箱」も無用ファイルに埋もれ、そろそろ空にしてディスクの容量を軽減しなければなにごとにも発想の切れが鈍くなってしまう危険を感じはじめている。
売れるための出版物を書くにはこうすればいい、というツボならある程度わかる。しかし、その手のもののために膨大なエネルギーを費やして何かを制作し世に出しても、売り切って手に入る金などタカがしれたもの、持ち出す金ほうがはるかに多いのだ。
ひとにぎりのヒット作品を除けは、本の出版とは決して儲かるビジネスではない。それが判っているから、同じエネルギーを使うなら、自分の書きたいもの、出したいものにこだわる方がましだと思っている。
とにかく東南アジアは、日本人のみならず欧米人にとっても人気のエリアで、ドイツやアメリカから毎月かけつけているハマリ組みも少なくない。彼らが交換する情報はじつに明け透けで、しかも洞察力に富んでいて面白い。
しかしそれらを参考にしながら文章を書きためるにしても、「観光だけでは物足りない」し「オンナだけでもつまらない」というジレンマを心の奥にいつも抱えているのは事実だ。そんなことをつらつら考えながら、この東南アジアという底知れぬ興味の対象にどうかかわればいいのか、オレはいまだに悩みながらここまできている.....。
|
|
長いあいだアジアの人々とつき合ってきた。つき合い始めた頃の日本はゆとりも自身もあった。日本式経営がちやほやされ、日本の社会がアジアの模範とされた時代だった。相対的にアジアの人々は低く見られていた。ルーズで小ざかしく平気で口先だけの嘘をつく「遅れたヤツラ」だと思われていた。
あれから二十年近く。最近の日本の社会はすっかり堕落・凋落したかのようだ。何もかもがちぐはぐで、何をやっても自信を取り戻すことができない...。そんななかで、オレはアジアの人間のあいまいさに注目しているのだ。ヤツラのノー天気でチャランポランな生き方は、この無気力な時代を生きのびるには便利な妙薬のように思えてきた。彼らに共通した「貧しさ感」というのも、実は家族を含む一族がまとまって生きていくうえで、有効に働いている。逆説的だが、この貧乏感・飢餓感が、彼らに「幸福」を与えているようにもみえる。
翻ってみれば、実は貧しいのに豊かだと思わされてきた日本人...。最近その「嘘っぽさ」に気づき始めているヤツらも多いが、かといって貧乏になる勇気もなく、まとまろう家族もすでに崩壊してしまっている...。
オレがアジアを徘徊するのは、病に冒された日本人が快復するための「シアワセ探しの手口」を、そこにに求めようという衝動からきているのだ.....。
|
|
■バックパッカーの恋
東南アジアを題材にした「バックパッカーもの」の出版物が増えている気がする。私が東南アジアに興味を持ち、紀行文などを書いているのを知っている、出版社に近い仕事をしているある先輩が、めぼしい本を見つけるたびに私に送ってくれる。その中に、集英社の『バックパッカーは東南アジアをめざす』や同社の『デジタルバックパッカーインドシナうろうろ』、小学館文庫の『アジアの純愛』などのバックパッカーものが、「積ん読」状態になっていた...。
バックパッカーという旅のスタイルは、私のそれとはずいぶん違っている。私のばあい短い滞在でより効率的な情報収集に注力するので、何かトラブルでも起こして時間を無駄することは絶対に避けなければならない。危険回避が、私の旅で最も重視される要素なのだ。
だから旅先では、贅沢をするわけはないがセキュリティの怪しい安宿は避け、時によってはガイドも躊躇せず雇うことにしている。
有り余る時間に恵まれ、次の行動を状況に任せられる自由度の高いバックパッカーの旅行記に、さしたる興味を感じてこなかったのは、そういう旅のスタイルの違いからだった。だからバックパッカーものの旅行記は、先輩にはすまないが、いつももらうたびにページを開くことなく放置してきたのだった。
ところがこのたび、自動車免許の更新があり、空き時間をどうやってつぶそうかと考えたとき、あまり脳みそに負担のかからぬなにか軽い読みものをと思い、気がついたら例の先輩からもらった小学館文庫の『アジアの純愛』を手にしていた。免許更新手続きを済ませ、交付されるまでの空き時間にさらさらと読み流してみた。
旅先でバックパッカーが体験する行きずりの人との淡い恋物語が、匿名で約二十点ほど載せられている。嘘っぽい話もあったが、おそらく実話に近いと思われる切ない物語もあった。
旅先で、人は普段にも増して人恋しくなるものなのか?そして人恋しさの奥には、なぜか男も女も、一様にアバンチュールへの期待が秘められているとでもいいたげな話ばかりだ。いともあっさり惚れちまっては、宿を共にしている...。
これを読む限り、バックパッカーも捨てたもんじゃないし、観ようによっては三日やったら止められない旅のスタイルのようにみえる。
バックパッカーは、安宿を定宿にして数日間から数週間、場合によっては数ヶ月間滞在する。「滞在の気分」が常にそこにはある。安さ重視の旅だから、手ごろな食堂やカフェが見つかれば、そこに通いこむようにもなる。旅行者とはいえ町の人々に顔なじみになり、地域に溶け込んでいく...。地域の人々から見れば、バックパッカーという旅行者は見知らぬ国の文化を背負ってくる興味津々のエイリアンだから、口のひとつも利いてみたくなる対象だ。
同じバックパッカーどうしも、大義名分を背負った家出人のような立場にあるだけに、人恋しくもありまた情報と援助に飢えていることもあり、声をかけあい席を共にしあう...。自由度の高い滞在型だから、出会いを確認し、期待し、待機し、好感を育てたりもできる。バックパッカーは、「出会い」を「恋愛」に無駄なく育んでいく仕組みを内包した、実にうらやましい旅のスタイルだといえる。
しかし、いいことばかりではない。『アジアの純愛』のなかで何人かの寄稿者がそのことを強調している。バックパッカーの多くはフリーターで、為替レートの違いを活用した旅人である。旅を終えて日本に帰れば、ただの失業者に他ならない。定職に着く機会を失った20代〜30代に対する社会の風は冷たい。家族の不安も消えない。バックパッカーはいつのまにか心を癒すように、アルバイトで貯めたわずかなお金を携えてまたアジアへと旅立つ...。
日本でのそうした悩ましいことどもは、旅に出ていればつかの間忘れることもできようが、重苦しい風景や天候が引き金となって思い出すこともあるという。
旅はあくまでも「非日常」の世界で、日常の世界をそれに置き換えることができないということか。(一生旅をして死にたい)と思ってきたが、どうやらそれは叶わぬ夢ということのようだ...。 |
 |