|
1962年・大映京都
スタッフ
原作:水上 勉
製作:永田雅一
脚本:舟橋和郎
川島雄三
監督:川島雄三
撮影:村井 博
照明:岡本健一
音楽:池野 威 |
キャスト
桐原里子:若尾文子
北見慈海:三島雅夫
堀之内慈念:高見国一
宇田竺道:木村 功
藤本雪州:山茶花究
岸本南岳:中村鴈治郎
桐原たつ:万代峯子
堀之内かん:菅井きん
岸本秀子:金剛麗子
木田黙堂:西村 晃
ほか |
物語の舞台は洛北衣笠山にある禅寺・孤峯庵、画壇の大家・岸本南岳が描いた「母子雁」の襖絵が有名で世間では「雁の寺」と呼ばれている。南岳の死後、彼に囲われていた桐原里子は孤峯庵住職・北見慈海の匿女(かくしおんな)になり、寺に住みつく。二人の放逸な暮らしぶり。住職の身勝手な叱責に耐えて、勤行し日々の作務に励む少年僧・堀之内慈念。背が低く、軍艦頭の己が風姿に劣等感を抱く慈念。若狭の乞食谷の阿弥陀堂に捨てられていたという秘められた過去を背負って、孤独な少年僧の心の中に、やがて住職殺しの完全犯罪の思いが…
昭和36年上期(7月)直木賞受賞の「雁の寺」は、翌37年1月に映画化された。巷間、文芸映画の秀作、傑作と言われているが、むしろ異色サスペンスと言うべきかもしれない。勿論、小説と映画は同じではない。自伝的な陰影を色濃く焼き付けた「雁の寺」は、純文学変質論争を巻き起こすほど、単なるエンターテインメント小説ではなかった。監督・川島雄三は、この手ごわい原作をもとに何を描きたかったのか。
「さとは仏じゃ、わしの愛根じゃ」と言っては匿女・里子との愛欲に溺れる慈海の浅ましい狂態を覗き見る慈念。慈海に愛撫される里子に対する母性思慕と、慈海に対する嫉妬が混ざり合い絡み合って、やがて殺人へ…。襖絵の母親雁の絵をむしりとって、慈念は寺を出奔する。里子はひと月たって実家に帰った。原作はここまでである。ならば、あまりに唐突で、蛇足のようにも見える、観光スポットと化した「雁の寺」を撮ったラストの部分は何を意味するか。川島にとって「雁の寺」を描くのが目的ではなく、宗教の欺瞞性と寺や僧侶らの堕落をシニカルに描くために「雁の寺」の原作が必要だった、と考えれば納得いくのではないか。「雁の寺」の物語部分は白黒で、今現在(昭和36年当時)の寺の有り様をカラーで表現したのも、そのためであろう。さらに、里子のその後を見せるという意図があったのではないか。寺の売店の後ろ向きのおばさんは、間違いなく里子なのだ。日本軽佻浮薄派と自称していた川島監督の真骨頂、単なる文芸映画にはしなかった、と私は見る。お気に入りの小沢昭一を出演させんがためでもなく、批評家から低俗娯楽画の作り手と言われて来たことに対する屈折した意趣返しのサービス精神でもない。
水上勉は福井県大飯郡本郷村岡田で生まれた。父は宮大工の水上覚治、母はかんである。四男一女の次男坊。他所での仕事が多い父が送金を怠りがちなため、一家は母かん一人の農作でなんとか糊口を凌いだという。口減らしのため、9歳で京都市上京区の臨済宗相国寺塔頭瑞春院の徒弟となるも、住職・山盛松庵に若妻・タツがあって女児・良子の子守をさせるなどの行為が、僧侶に対する幻滅を生み、仏門に対する希望を失って寺を脱走するに至る。仏門にあるものは戒律によって妻帯できぬと信じていた純粋無垢な9歳の子にとって、住職の姿は破戒そのものに映ったであろう。ここに「雁の寺」の原体験がある。その後、相国寺玉竜庵に入った後、衣笠山等持院徒弟となるが、後にここも飛び出すことになる。
この原体験は「作者は『書いているうちに和尚殺しの行為がイヤになってきた』とそのころの心境をのべている。『私の人生でわすれられない、恩義をうけた人、親切にしてくれた人などを、無断でさらってきて、作者は、大それた殺人現場へ顔をならべさせているのだ。このう |
|
|
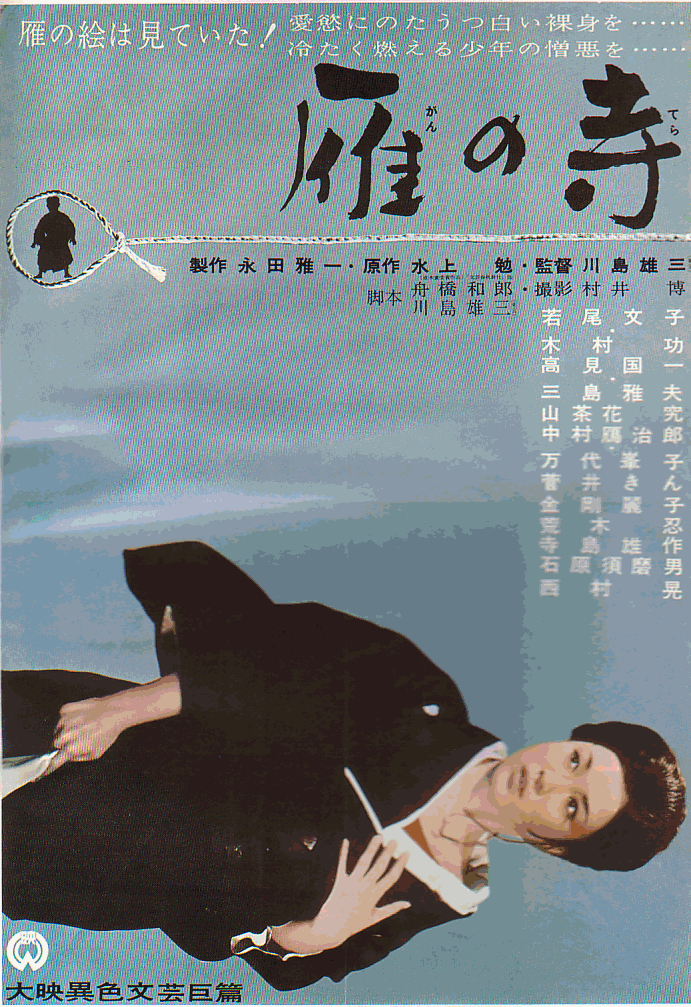
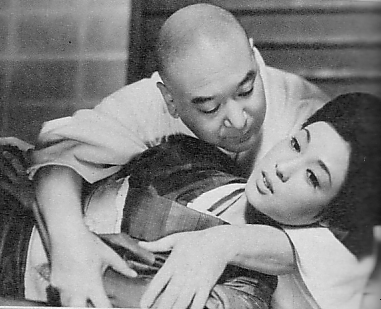 住職と愛妾と小坊主の愛欲がからまる 住職と愛妾と小坊主の愛欲がからまる
明治大学映画研究部の論客・川島雄三は1938年、松竹の第一回助監督公募で採用され映画界に入った。「洲崎パラダイス・赤信号」(56・日活)、「幕末太陽伝」(57年・日活)、「貸間あり」(59年・東宝)は、彼の三大傑作であると私は考えている。特に「幕末太陽伝」は大大傑作で、この一作のみで川島雄三の名は映画史上に不滅であろう。空中にほうり上げた羽織を下でさっくりと着てしまう颯爽とした佐平次役のフランキー堺、遊郭回りの貸本屋を演じた小沢昭一、バイタリティーあふれるお女郎の左幸子とともに、私には忘れ難く、何回見ても見飽きない作品である。
咋年6月10日、NHK・BS2で放送の「映画監督・川島雄三」は、彼の作品理解のために有意義な一編。若尾文子がナレーターを務めた。 |
次回公開作品未定!
館内改装予定のため
次回の作品は未定です
急告
改装の目途が立ち次第
次回公開作品を
お知らせ致します
近日 大公開!!! |
|
|
|
しろめたさは、永遠にのこるかもしれぬ』と水上勉は語っている(略)」(作家・近藤信行「情念と業を主題に−水上勉」から抜粋)ほどに、私小説的雰囲気を濃厚に宿しながら人間心理の深奥に迫る優れた文学作品を紡ぎ出した。
住職を殺した33年(昭和8年)はどんな年だったか。前年、1月28日・第一次上海事変勃発、3月1日・満州国建国を宣言、5月15日・五一五事件。翌年、2月23日・関東軍が熱河省への侵攻を開始、3月27日・国際連盟脱退の詔書発布。殺人直後の12月23日には皇太子(明仁)が誕生している。
慈念が「死にたくなる」軍事教練は、1925年4月公布の陸軍現役将校学校配属令により、中等学校以上の学校に現役将校が配属されて始まっている。軍靴の響きがいよいよ高くなる中、学校教練は頻繁かつ厳しさを増していただろう。教練を嫌う慈念に教師・宇田竺道は「教練も作務の一つと思えば修行だ」と言う。人殺しの訓練が修行になるとはどんなこっちゃい、禅坊主は阿呆か、と映画を見ながら思ったことを覚えている。
慈念と比較するつもりはないが、七歳で父親が死去し、臨済宗の慈恩寺などに預けられて少年時代を過ごした仏教学者の古田紹欽氏の話を聞こう。
「慈恩寺には師匠(宜堂和尚)のほか、私のような小僧が十人いました。喜捨で食べるものを得て、命をつなぎます。喜捨がなかったなら、托鉢に出て、町を一巡します。それで集まった三円五十銭で、米二升と、麦三合か四合を買って、約一週間、師匠、小僧の十一人が養われるのです」「米が二合ぐらい、麦が一合ぐらいで、それを三升ほどの水で炊きます。だから、ほとんど水ばかりで、食べようと思って見ると、天井が映っているため、天井粥といっていました。でも、静かにすくえば、沈んでいる米がすくえます。寺では僕が一番年下で、兄弟子から順番にすくっていくから、僕の時にはほとんど米がなかった」「当時、履物というと草鞋(わらじ)ですから、それに破れた白足袋を履いて、衣をつけて、托鉢に回る。一番寒い一月には寒修行といって三十日間、回りました。白足袋は盆と正月に信徒から一足ずつもらったのです。それを履きつぶすと、履くものがない。だから、寒修行の時は足袋を履かず裸足でした。手も足もひびだらけでしたね」「でも、苦労とかいう思いはしなかったなあ。このように生きていくのが、出家をした限りは当然だと思いました。学校もよく休んだ。寺に何かあると、行けない。それでも、禅寺というのは修行の道場だと、子供心にも自覚してました」「僕はね、人間はやっぱり苦労しなければならないと思う。自分の経験でつくづくとそう思いますよ。いまはみんなめぐまれ過ぎています。だから、不足ばかりいうんだ。どこまで行っても。ありがたさとか感謝とかいう気持ちが希薄になり、何かをしてもらうのが当たり前になってしまっている。日本がある程度、繁栄をしてきたからいいが、これからどうなるのか。精神的には非常に寂しい思いをするでしょうね」(1998年1月24日付、大阪読売から)
古田氏はその後、旧制松江高校をへて東京大学文学部印度哲学科に入学。大学院時代に鈴木大拙に出会って生涯にわたり師事、仏教学者として大成した。
「雁の寺」は書き足され、孤峯庵を出奔した後、慈念は北陸路から近江の山寺までさすらって、落命する。
水上勉原作の映画作品
●越前竹人形(63年)監督・吉村公三郎
●五番町夕霧楼(63年)監督・田坂具隆
同 (80年)監督・山根成之
●越後つついし親不知(64年)監督・今井正
●飢餓海峡(65年)監督・内田吐夢
●波影(65年)監督・豊田四郎
●湖の琴(66年)監督・田坂具隆
●あかね曇(67)監督・篠田正浩
●はなれ瞽女おりん(77年)監督・篠田正浩
●父と子(83年)監督・保坂延彦
●色蛇抄(83年)監督・伊藤俊也
|
(2002.06.01)
|
|
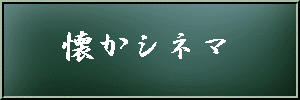
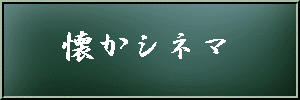
![]()