焼き物雑感その6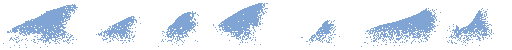
焼いた岩魚の塩焼きを大杯に入れ、そこになみなみと日本酒を注ぐ「岩魚の骨酒」を作るには、岩魚を囲炉裏で気長に焼き枯らしていくことが勘所であると山の古老に聞いたことがあります。
一番上に示した桃山志野の陶片ですが、虫眼鏡でよく観察すると、薬の表面の部分とボディーの部分の間にもう一つの層が厚く形成されていることがわかります。
例えば、灰釉の場合、塩基成分である木灰は中性成分(粘土質原料)を溶かす溶剤として働くと共に、ボディーの粘土をも溶かして中間層を形成します。この中間層がなければ、素焼きの表面にガラスをくっつけたような状態になり、薬が剥離してしまいます。よく、焼き締めの自然釉は「薪の灰が付着したもの」といわれることがありますが、実は「付着したもの」ではなく、灰のアルカリが粘土を溶かして「粘土と灰が解け合ったもの」という方が正しいのではないかと思います。
さて、志野釉はほぼ長石単身の薬です。釜戸長石を例にとるならば、約77%の珪酸と14%の酸化アルミニウム、4〜5%の酸化カリと酸化ナトリウムなどが主成分です。圧倒的に酸性成分が多く、温度さえ上げてやれば、溶けるには溶けますが、ボディーと解け合った中間層を形成させるには、しっかり焼き上げなければなりません。
さらに、この中間層の発達が薬の立体感となってあらわれます。ただ溶かしただけでは、ぺたっとしたタイル状の扁平なものになってしまいます。立体感を出すために、濃度のちがう薬を嫌らしいほど二重がけしたり、鬼板をがばっとかけて立体感を出そうとしているものも見かけますが、志野としては・・・。
左に挙げた各務賢周氏の志野茶碗は、「穴窯を焚く」のページで紹介した窯で焼かれたものです。穴窯でしっかり焼成されたことにより、中間層がしっかり発達し、奥行きのある釉調に仕上がっています。また、「卯の花垣」を思わせる造形(個人的には「卯の花垣」よりも躍動感がありいい形をしているなあと思っています)、高台の削りにも非凡な才能がうかがえます。これこそ、「本当の志野」といえるものだと思います。
焼き物好きも年を重ねてきて、対外のものは手に取ると寸法がわかるはずなのに、この茶碗は実寸よりも一回りも二回りも大きく見え、寸法を測ってびっくりしました。轆轤引きの躍動感と薬の立体感がそうさせているのではないかなと思います。
以前、志野が好きなのに、コレクションの中で圧倒的に志野が少ないのは、本当に納得することできる志野が少ないからかも知れないというようなことを書きましたが、この志野茶碗は本当に納得できるものの一つです。
下の加藤康景氏の志野ぐい呑みも、薪窯でしっかり焼成され、見せかけではない志野の美しさが表現されています。これ以上溶けてしまってはガラス光沢になってしまうというぎりぎりのところを見切って、薪の投入を終えているところに技を感じます。
これまで現代作家志野をかなり見ましたが、なかなかいい志野には巡り会うことができませんでした。しかし、各務賢周氏と加藤康景氏の志野はかなり高レベルにあり、この二人は間違いなく美濃陶芸を背負っていくものと考えます。
子どもの頃、岩魚釣りを終えて家に立ち寄ると、「税金、税金」といってにこにこしながらびくの中から2番目に大きな岩魚を塩焼きにして骨酒を作ったあの山のおじいさん。山仕事の合間を見ながら、岩魚を釣っている小学生の私の様子を見守っていてくれたこと本当は知っていました。
酔っぱらったおじいさんの隙を見てつまみ食いしたあの岩魚の味は、ガスオーブンの魚焼きで出せるかなあとふと思うことがあります。
桃山志野の陶片
釉調から、高根古窯群のどこかの窯で焼かれたものであると考える。
各務賢周志野茶碗
径11 高9.7
派手な造形技法を使っているわけではないのに存在感のある茶碗である。釉薬調子、造形が見事にバランスをとっている。
同高台
茶碗正面に入れられたたてべらのタッチといい、この高台の削りといい、賢周氏の非凡なセンスを感じずにはいられない。
加藤康景
志野ぐい呑み 径6.7 高5.3
薬を貫く赤の発色が美しいグラデーションをなしている。
各務周海蕪絵色紙「ぼくは絵はようかかんでねえ。」と周海氏は語るが・・・