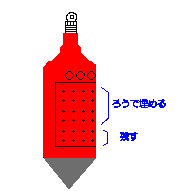| この釣りの原理を考えるとアミエビのこませを撒いてその中にハリのついた疑似エサであるウィリーを漂わせるわけですから一体どの程度のこませを撒いたら良いかを考えることは大切なことです。 基準としては約15mほどのしゃくりの動作を2回行ってビシの中のアミエビが空になる程度ということですがしゃくり方や潮の速さによってはそれよりも早くなくなってしまうことも当然考えられます。 また識者によっては「1回のしゃくりでアミエビが2粒出れば上等、ハリの数以上出しては駄目」という意見をもっている人もいてこの基準を否定する意見の人もいます。つまり20粒のこませの中に4本のハリのついた仕掛けが入るのと5粒のこませの中に4本のハリの仕掛けが入るのでは魚が間違えてハリを食う確率はどちらが高いかということです。 当然後者のほうであるというわけです。こませを多く撒きすぎると魚はすぐに満腹になってしまいウィリーのついたハリを食わなくなるというわけです。 そこで一度潮が澄んでいるときに水面下5mぐらいにビシを沈めてどの程度こませが撒かれているのかご自身で観察して見ると良いと思います。1回で5粒なんてとんでもなく、自分の想像よりももっと多くのこませが撒かれていることに気がつくと思います。たとえ上窓を全部閉めたとしてもかなりのこませが出ていることに驚くでしょう。 このようなこませの量についての説を信じるにしても信じないにしても市販されているビシの状態では完全なコントロール(一番少ない量にあわせる)はできないわけでここでチューンナップが必要になるわけです。 ウィリーこませしゃくりでは金網のアンドンビシではこませが出過ぎてしまうのでプラスチック製のサニービジがベストであると言われています。 そこでサニービシの80号を例にあげて改造(チューンナップ)の仕方を説明します。 サニービシには周りに細かい穴が6列で72個あけられており、これをロウソクのロウを使って埋めるわけです。
|