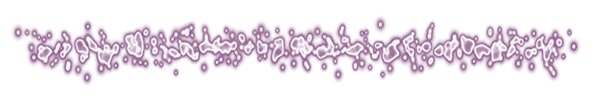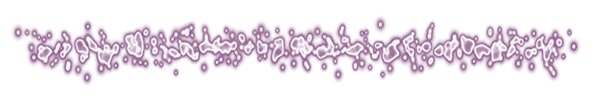
戦場のピアニスト
舞台は第二次世界大戦さなかのポーランド。ユダヤ人ピアニストが
ドイツ占領下で生き延びるという実話に基づいた話。
監督はロマン・ポランスキー。自身ユダヤ人で母を亡くした体験が
だっぶっているらしい。
この映画を見ながら2,3感じたことがある。
ナチとユダヤ人との関係をテーマにした映画だがこれほど淡々という
のか客観的にというのか、そんな描き方をした映画は知らない。
憎悪、恐怖、悲しみそして愛というのがナチがらみの映画表現の
定番だがそれらとはいささか距離置く。
感覚的には乾ききった石ころの上を歩いているとでも言うのか、不思
議な気分で映画を見ていた。縦列に並ばされたユダヤ人の中から
適当に何人かを引っ張り出し、腹這いにさせ頭に銃を突きつけて
事務的に殺していく。普通こうした場面を見ると嫌悪感がつきまとうの
だがなぜか一切の感情が入り込む隙もないくらい何も感じない。非
人間的な事をするものだと頭の中で考えているだけ。
全体に説明っぽい表現が少ない。列車で家族が強制収容所に連
れて行かれるときにピアニストだけが何の前触れもなく列車に乗る
一群からはじき出される。ある意図があって助けられたのだが、そのあ
たりを監督はくどくどと説明しない。離ればなれになった家族のことを
どう思っているのかもほとんど説明がない。 家族と別れナチの手から
逃げる。それを救う地下組織も極めて淡々と描かれている。
ラストシーンでなぜドイツ人将校がピアニストを助けたのか、ピアノの
音色に惑わされたか、そんなこととは関係なしに初めから命を救うつ
もりだったのかなどなど。
観客の感情移入を拒否した映画のように思えた。
いまイラク問題に世界が揺れているとき、戦争が民衆にもたらす
悲劇をぼんやり考えていた。
人は人に対しこのように何の感情もなく接することが出来るということ。
その一方で、見ず知らずの人を、命がけで救おうとする地下組織の
人たち。何が彼らを分けているのか。
こんな映画を見せられるとホロコーストは所詮日本人の手には
負えないものに思えてくる。そこいらに転がっているかわいそうとか
信じられないとかいった薄っぺらい感情で処理するにはあまりにも
重すぎる問題のようだ。
ま、人によって見方が随分違うのだろうけれど。
(2002.2.19)