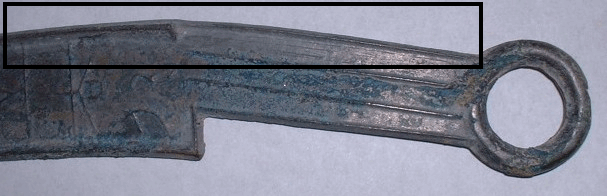質問1:真贋のポイントを教えてください。
回答1:正直な所、非常に難しい質問です。
今まで一番感じるのは、購入先で「何かの本に載っている書体だから真正品」という
売り方をされている古文銭に真正品はない、と言う事です。
半両銭、五銖銭以前の古文銭は製法より基本的に「一品一様」と考えて良いと思います
ので、同じ製作、書体の物が複数あったら疑った方が正解でしょう。
特に珍品と言われる品物の場合、同一品の存在が確認された場合は、経験上×でしょう。
一番大切なのは、古文銭に限らず、基本的には本物と言われている物を「よく見る」と
言う事で、真贋両者を並べると、何が違うのかが明確になります。
真贋についての解説資料例としては、2004年4月10日に販売開始された
「真贋古銭対照譜」は画期的な教科書の一つです。
さて、真贋のポイントは、貨幣の材質(色)、大きさ(重さ)、形状、書体、製作方法等
で判断する事になります。
貨幣の材質(色)
古文銭は基本的に青銅製で作られていますので、それ以外の材質の場合は注意が必要です。
当時は精錬技術が低く、主成分の銅以外に、錫、鉛がかなりの比率で含有されています。
従って、純銅に近い材質の場合は、近世の製作と考えて良く、最近の贋作の多くは純銅製
の物が多数存在します。純銅以外には、真鍮(下記)や鉛等で製作される事が多い様です。
 |
六字刀(真鍮製、贋物)
|
貨幣の大きさ(重さ)、形状
製作されて二千年以上も経過している事による金属の腐食(錆)等により、見た目よりも
軽くなります。しかし、具体的に減少する数値については、貨幣の状態により変化する為に
判断基準としては非常にあいまいであり、薬品等による処理で意図的に軽量化させたもの
もあり、重さだけの判断では不充分です。
貨幣によっては、形状に特徴がある物があります。一例として五字刀の場合を紹介します。
五字刀の場合、背側の柄部分の郭は一度切れるという特徴があります。
(三字刀の場合は切れない)
真正品
|
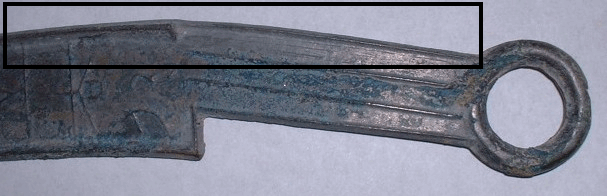 |
贋物
|
 |
貨幣の書体、製作方法
文字の書体には歴史があります。象形文字より変化していく過程(年代)により、同じ
文字でも異なり、その貨幣特有の文字もあります。(詳細についての説明は省きます。)
刀幣、布幣の多くは、小刀で一気に文字を掘る様な製作方法であった為、文字、線は
ほぼ均一な太さの直線状になります。従って、文字、線が細かに波打っている場合は、
注意が必要です。
多くの古文銭は石範、陶範等の型により作られている為、貨幣の表面は平面になっており
当時の鋳造温度も低かった(銅純度が低く、比較的低い温度で鋳造できた)為、気泡や
鋳肌あれも少なく、滑らかな表面をしています。
現在贋作の多くは、製作の容易な砂型を用い、しかも高温で鋳造する為、表面(鋳肌)に
違いを残します。多くは、ルーペ(5〜15倍程度)で現品の表面(鋳肌)を見れば判別
可能ですが、あまり状態の良くない物や、錆がある物、表面を磨いた物、薬品で処理した
物については判別できない場合があります。
贋物の製法としては他の古銭と同様の製作法が多い様です。
・本物を型取りして作る
本物より大きさが小さくなるという特徴があります。
本物が持っている特徴(書体や表面の状態等)がそのまま一緒に鋳写されますので一見
すると非常に似ている物となります。
・新しく型を作る
有名な古銭書や、文献、資料に似せた物を製作、あるいは、収集家好みの変わった書体
で製作されます。
しかし、拓図のみを元に製作される為、拓に表れない部分は想像や、類品で製作される
事になり、形状等に真品と相違が出てしまいます。
・改造品
比較的に入手が可能な真品を一部改造し、珍品に見せます。
文字を様々な方法(漆、泥、彫り直し等)で変化させます。多くは本体部分と追加部分
に相違がありますので、ルーペで拡大する事によって判別ができます。
ケイ刀五百の真贋比較例

|

鋳肌は平坦
|

鋳肌がざらざらしている
書体が甘く太い
|
左:本物 右:贋物
重量:20.0g(本物)
24.4g(贋物)
|
本物(五百 詳細)
|
贋物(五百 詳細)
|
贋物のレベルにも様々あり、稚拙な贋物については上記の例ですぐに判別できますが、
近年は収集家を対象にした「非常に精巧な贋物」も多く登場しています。
真贋の判断も年々困難な物が登場してきていますし、単品のみ見ただけではわからない
場合がほとんどです。しかし、本物と二つ並べて比較すると明確に違いがわかります。
最後に、今回紹介した内容は多くある中の一例に過ぎません。
今回紹介した内容は比較的にわかりやすい特徴ですが、通常は様々な手法を用いて贋物を
本物らしく見せています。
やはり、他に所有している人の現品と比較したりして、数多くの貨幣に触れる事が大切
であると思います。
質問2:半両銭は「秦の始皇帝により作られた」と習いましたが、本HPではそれ以前より作られて
いた、とありますが?
回答2:戦国時代の秦人墓中より半両銭が出土した事により、戦国時代より半両銭が作られていた
事が判明しています。
代表例
四川省青川、秦人墓(前306年の木札と一緒に七枚の半両銭出土)
陝西省西安、窖蔵銭(戦国時代に蓄えられていたもの、約千枚の半両銭が出土)
半両銭は、戦国時代に作られた半両銭、秦統一によって作られた半両銭、漢により作られた
半両銭に分類されます。製作期間からみて、秦統一によって作られた半両銭が最も少ない事に
なりますが、詳細が不明な物も多く、今後も研究が必要です。
|