今月の特集題 和解
![]()
| 佐々木義夫 |
日本では、多神教国家と評せられる位TPOに合わせて様々の宗教を信じますし、夫婦が別々の宗教を信じている例は多いと思います。このことから、宗教に限らず何事も相互に理解し妥協することが家庭生活の円滑化に不可欠であると先人が説いているところです。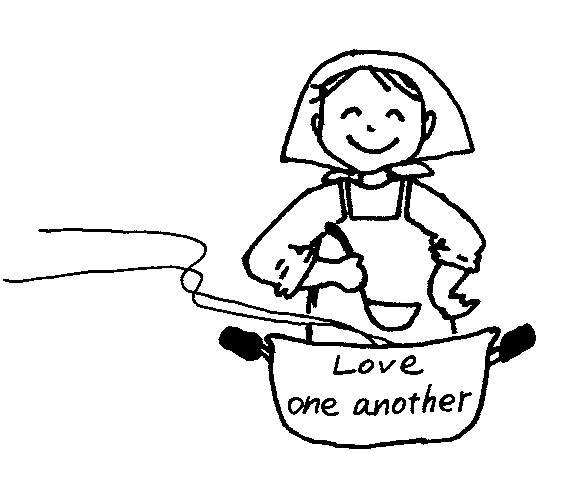 そのことは頭では理解していても、我家庭では二人とも頑固で後に引かない性格から、宗教上の対立が頻繁にありました。その辺をつまびらかにしないと表題の主旨について大方のご理解が得られないと考え、恥を忍んで敢えて記述させて頂きます。 そのことは頭では理解していても、我家庭では二人とも頑固で後に引かない性格から、宗教上の対立が頻繁にありました。その辺をつまびらかにしないと表題の主旨について大方のご理解が得られないと考え、恥を忍んで敢えて記述させて頂きます。私の両親は信心深く朝夕神仏にお祈りしていました。従って子供心にも大人になれば同様にするものと思っていました。 家内と結婚して二か月位の頃、大病し、家内の必死の看病、肉親の祈り医師の適切な処置、自分も生きねばと必死に祈って何とか克服できました。従って家内は命の恩人であり、又、神仏のご加護のお陰で今日があると思っています。しかし、再発の怯え等からくる心の葛藤は長く続き、子どもが生まれても、事ある毎に神仏に頼り長い祈りになっていました。これが家内の理想としていた一家団らんの場が作れず、又、滋賀県に赴任中の時には子どもも初期反抗期の頃で、家内は相当悩み最終的にキリスト教に救いを求めた主因と思います。 受洗にさいして相談はありましたが、私には学生時代に読んだ旧約聖書に大きなつまずきを感じていたので猛反対しました。それでも家内の決意は変わらず受洗し、以後東京に復帰し越谷の官舎に居住して越谷教会にお世話になるようになっても、互いにソッポをむいた(私はそう思っていました)生活をし、それは家内が大病し召されるまで続きました(ただ私には家内の看病で治癒したと同様、私も家内の病気を克服させるという思い上った気持ちがありました) 家内が召された後、自分の愚かさと憎悪感から教会に通うようになり、皆様の暖かい励まし等を受け教会に対する親近感を感じながらも、キリスト教を理解しようとするより罪悪感の方が先に立っていました。 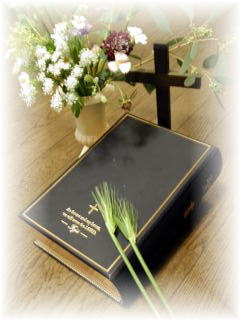 一昨年、石橋先生と相談させて頂き一年間自分なりに熟考の末、新約聖書の内容ならば受容できそうに思え、同時に壮年部の皆様の助言も踏まえ、受洗することがせめてもの家内の意に沿うと考えて、石橋先生に申し出て現在エフェソの信徒への手紙について受講中で、キリスト教への理解も少しずつ深まりつつあります。 一昨年、石橋先生と相談させて頂き一年間自分なりに熟考の末、新約聖書の内容ならば受容できそうに思え、同時に壮年部の皆様の助言も踏まえ、受洗することがせめてもの家内の意に沿うと考えて、石橋先生に申し出て現在エフェソの信徒への手紙について受講中で、キリスト教への理解も少しずつ深まりつつあります。その中で石橋先生は「純子さんはご主人のことを心配して一緒にお祈りしたこと、末期には息ができることが感謝ですと述べたこと」等をお話下さり、又、第五章に「…妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい」との文面にふれ、対立していても心は繋がっていたことが分かると共に、生前腹をわって話をすればもっと早く和解できただろうと改めて家内を思慕しています。そして、家内の到達した境地(極めて高い山ですが…)を目標に石橋先生のご指導を頂きながら自分なりの努力を続けていきたいと思っています。 |
| (ささき よしお) |
| 棚橋千恵美 |
私は今、川端由喜男先生にギリシャ語を学んでいます。ギリシャ語原典の言語には日本語訳の聖書に現されない意味があることを丁寧に教えてくださり、その度に新しい発見をしています。「和解」という言葉の意味を考えてみました。一般的に和解とは、争いをしている当事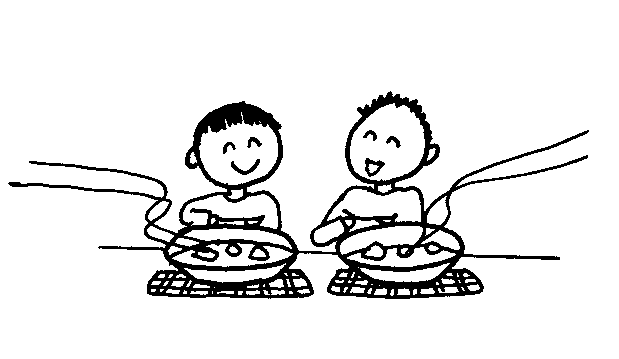 者同士が互いに譲り合い争いを止め、その関係が修復されることを言います。ギリシャ語で「和解」(カタラゲー)とは「取り替える、交換する」という意味があります。聖書は、イエス・キリストの死と復活によって神と人間との敵対関係が、正しい関係に回復されたことを「和解」と考えています。十字架の上で神の子イエス様の命と罪人である私たちの命が交換された、神の聖さと人間の罪との交換が成されたと言うことです。 者同士が互いに譲り合い争いを止め、その関係が修復されることを言います。ギリシャ語で「和解」(カタラゲー)とは「取り替える、交換する」という意味があります。聖書は、イエス・キリストの死と復活によって神と人間との敵対関係が、正しい関係に回復されたことを「和解」と考えています。十字架の上で神の子イエス様の命と罪人である私たちの命が交換された、神の聖さと人間の罪との交換が成されたと言うことです。聖と罪との交換、まさに大逆転の世界、神から一方的に与えられた恵みの世界に生かされていることを思います。 和解ということでは、人と人との関係においても考えさせられます。和解というのは一つになることでもあります。「実に、キリストはわたしたちの平和であります。二つのものを一つにし、御自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律ずくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは、双方を御自分において一人の新しい人に造り上げて平和を実現し、十字架を通して、両者を一つの体として神に和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。」エフェソ書2章14〜16節。神の和解を受けた私たちは既に一つと見なされています。私たちが努力する前に既にキリストにおいて一つとされているのです。教会の中にあっても人間関係に悩むことがあります。しかし、教会の交わりは、互いに譲り合って何とか上手くやって行こうというような人間の努力によるものではないと思うのです。「それで、わたしたちは、今後だれをも肉に従って知ろうとはしません。」(第二コリント5章16節)。 人を知るということは難しいことです。知るということの中には愛するということが含まれる  からです。しかし、キリストにおいて知ることができます。一人ひとりの内に生きておられるキリストに目を向けるとき、その人を生かしてくださる神に目を向けるとき一つとなります。私たちは今、大逆転の恵みの世界に生かされています。罪ある者が聖なる者とされ神の前に立つことが赦されています。神が私たちを一つのものとして見てくださる、一つとされていることを感謝します。共に、神から与えられた恵みを伝えて行くことができますように、共に御名を讃え、賛美し、礼拝することができますように、祈ります。 からです。しかし、キリストにおいて知ることができます。一人ひとりの内に生きておられるキリストに目を向けるとき、その人を生かしてくださる神に目を向けるとき一つとなります。私たちは今、大逆転の恵みの世界に生かされています。罪ある者が聖なる者とされ神の前に立つことが赦されています。神が私たちを一つのものとして見てくださる、一つとされていることを感謝します。共に、神から与えられた恵みを伝えて行くことができますように、共に御名を讃え、賛美し、礼拝することができますように、祈ります。 |
| (たなはし ちえみ) |
 |
| 越谷教会月報みつばさ2005年11月号特集「和解」より |