 |
また、243年に書かれたある書物には旧暦(ユリウス暦)の春分にあたっていた3月25日に天地創造が始まったと考え、太陽が創造された第4日め(3月28日)を「義の太陽」イエス・キリストの誕生の日だと記されています。
クリスマスを盛大に祝うという風習はローマ帝国の農耕の神サトゥルヌスのお祭りから受け継がれてきたものと思われています。当時サトゥルナリア祭の期間中は、仕事はすべて休みとなり人々はどんちゃん騒ぎに明け暮れていました。主従の立場を逆転したりもしたそうです。現在の世俗のクリスマスの陽気な面はこのお祭りの伝統が影響しているのかもしれません。 |
 |
さてその頃、未だ辺境の地ガリヤやその北の果てでは「ユール」と呼ばれる冬至のお祭りがありました。アルプス以北のヨーロッパにおける冬の厳しさは、私達の想像を絶するものがあります。一年の半分近くは日も短く、作物も育たない不毛の期間、彼らは神を祭ることで勇気づき冬を越してきたのです。特に一日の大半が闇に包まれる冬至の時期には、さまざまな悪霊がうろつく恐ろしい期間と考え、悪霊をなだめる為、「ユール」を祭りました。蜜の酒を乾杯し、豊穣の女神フレイヤに生贄のブタを捧げました。また、暖炉では「ユールログ」と呼ばれる大きな薪を燃やし続け、数々の儀式が行われました。その影響が、キリスト教が伝わってからも受け継がれているのです。
|
 |
キリスト教とローマの文化が地中海沿岸からヨーロッパ全土に広まっていく過程で、いろいろな古代のお祭りが混淆し、現在のクリスマスの原型が形成されていきました。キリスト教を伝えた宣教師たちも敢えて古来の習俗を根絶やしにはせず、むしろ積極的に取り込んでいったのです。
|
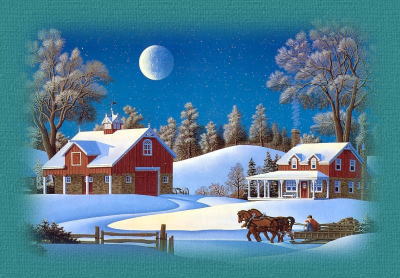 |
このお祭りの要素が色濃く残った為に、日本をはじめとしたキリスト教以外の人々にもクリスマスが普及していったことは否めません。そして、冬至の祭りはヨーロッパだけでなく、インド「マカラ・サンクランティ」のお祭りや、日本の神社での「一陽来復」の祭り等、世界各国にあった為、その冬至を特別な日とする万国共通の想いが宗教を越えてクリスマスを祝うという風潮に表れているのかもしれません。
たとえクリスマスがどんな形であっても、神の御子を下さったことを神様に感謝する心を大切にしたいものです。 |



