| いま来たりませ(『讃美歌21』229番) |
四世紀にミラノの司教アンブロシウスが作ったラテン語の賛歌《Veni, Redemptor
gentium》を、マルティン・ルターがドイツ語で翻案。曲もグレゴリオ聖歌の旋律をもとにルターが編曲したと言われています。
ドイツで何百年も愛唱されたクリスマスソングで、かのJ・S・バッハもこのメロディを好み、「オルガン小曲集」第1番(BWV599)ほかいくつものカンタータで用いています。原曲よりもバッハの曲で聞き覚えのある人のほうが多いかもしれません。
※マルティン・ルター(Luther,Martin)
 1483年生-1546年没、ドイツ出身、ドイツの宗教改革者 1483年生-1546年没、ドイツ出身、ドイツの宗教改革者
ニックネームは「うそつき博士」、父ハンスは農民出身で、のち鉱夫となって成功する。初め法律家を志し、エルフルト大学で学ぶが、修道院に入り修行することになり、ローマ教会の司祭、ウィッテンベルク大学神学教授となる。
1517年に贖宥状を批判した95ヵ条論題を発表して宗教改革の口火を切り、教皇に破門される。1521年ウォルムスの国会で皇帝カール5世に追放される。1522年新訳聖書をドイツ語に翻訳、ルター教会を組織し布教活動を行う。
|
| 「起きよ」と呼ぶ声(『讃美歌21』230番) |
作詞作曲は十六世紀後半のドイツの牧師・神学者フィリップ・ニコライ。ペストが流行する中、アウグスティヌスの『神の国』を読んで慰めを与えられ、この讃美歌を作ったと伝えられています。
キリストの来臨を待ち望むこのコラールはドイツでは「コラールの王」と呼ばれ、バッハも有名な「シューブラー.コラール集」第1番(BWV645)ほか、いくつもの編曲を書いています。ニコライは《あかつきの空の美しい星よ》(『讃美歌21』276番)という公現日の讃美歌も残しており、こちらも「コラールの女王」と呼ばれる名曲です。
|
| 久しく待ちにし(『讃美歌21』231番) |
日本のクリスマス礼拝でもよく歌われる、中世から歌い継がれてきた有名な待降節の讃美歌です。東方正教会で九世紀に作られた詩《Veni,Veni,Emmanuel》を再構成した歌詞に、十五世紀フランスのフランシスコ会女子修道院で歌われていた聖歌のメロディをつけたものです。
|
| 天のかなたから(『讃美歌21』246番) |
 宗教改革者ルターが自分の子どもたちのために作ったと伝えられている、ドイツのクリスマスソング。曲は16世紀初めの流行歌のもので、言ってしまえばルターによる替え歌です。ルター白身はこの歌を讃美歌として作ったつもりはなかったらしいですが、じきに礼拝でも愛唱されるようになりました。バッハなど多くの作曲家が、この讃美歌による編曲を残しています。 宗教改革者ルターが自分の子どもたちのために作ったと伝えられている、ドイツのクリスマスソング。曲は16世紀初めの流行歌のもので、言ってしまえばルターによる替え歌です。ルター白身はこの歌を讃美歌として作ったつもりはなかったらしいですが、じきに礼拝でも愛唱されるようになりました。バッハなど多くの作曲家が、この讃美歌による編曲を残しています。
|
| エッサイの根より(『讃美歌21』248番) |
これも15、6世紀から知られていた中世ドイツのキャロルです。もとはライン地方のカトリック信徒が歌っていたマリア賛歌でしたが、教会音楽家ミヒャエル・プレトリウスが自分の編纂したプロテスタントの歌集に収録する際、これをイエス中心の歌詞に改めました。以後もカトリック、プロテスタントの別なく世界的に愛唱されています。「エッサイ」は旧約聖書に出てくるルツとボアズの孫でダビデ王の父。つまりイエスの先祖にあたります。
|
| 生けるものすべて(『讃美歌21』255番) |
 歌詞はギリシャ正教会の礼拝で5世紀頃から歌われていた式文『聖ヤコブ典礼』に基づきます。曲は北フランスで17世紀頃教会旋法(ドリア旋法)で作曲された宗教的バラードのものです。 歌詞はギリシャ正教会の礼拝で5世紀頃から歌われていた式文『聖ヤコブ典礼』に基づきます。曲は北フランスで17世紀頃教会旋法(ドリア旋法)で作曲された宗教的バラードのものです。
19世紀にイギリスのジェラード・マウルトリーによって英訳され、この曲との組み合わせで発表されてから、英語圏で盛んに歌われるようになりました。
|
まきびとひつじを(『讃美歌21』258番)
後半の「ノエル、ノエル」のくり返しが印象的な、イギリスの伝統的キャロル。歌詞の原型は15世紀頃から知られていましたが、メロディはもう少し時代が下り、18世紀頃に生まれたとみられています。19世紀前半のキャロル集に収録されてから、世界的に普及しました。
|
| いそぎ来たれ、主にある民(『讃美歌21』259番) |
 カトリック、プロテスタント問わず世界中で親しまれている有名なクリスマスソングです。古い『讃美歌』では《神の御子は今宵しも》というタイトルで訳されていました。 カトリック、プロテスタント問わず世界中で親しまれている有名なクリスマスソングです。古い『讃美歌』では《神の御子は今宵しも》というタイトルで訳されていました。
歌詞はラテン語の古い聖歌《Adeste fideles》。曲は18世紀、フランスに宗教亡命していたカトリック信徒のイギリス人ジョン・フランシス・ウェードが記録していたものですが、誰が作曲したかは分かっていません。
|
| いざ歌え、いざ祝え(『讃美歌21』260番) |
もとはシチリアの船乗りが歌っていたマリア賛歌だったと言われています。ドイツの作家ヨハンネス・D・フアルクが1819年に1番の歌詞を、その同労者ハインリッヒ・ホルツシュアーが1829年に2番・3番をつけて完成したこの讃美歌は、ドイツをはじめ英米にまで広く普及しました。
|
 |
| もろびとこぞりて(『讃美歌21』261番) |
これも誰もが耳にしたことのある、定番のクリスマスソングです。詞はイギリスの牧師フィリップ・ドツドリッジが1735年の末に書いたもの。曲はヘンデルのオラトリオ《メサイア》の数か所からヒントを得て、後世に作られたと言われています。
|
| 聞け、天使の歌(『讃美歌21』262番) |
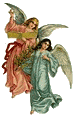 フェリクス・メンデルスゾーンが1840年に作曲した男声合唱曲(作品68の2)と、18世紀にジョン・ウェスレーの弟チャールズ・ウェスレーが書いた詩を、イギリスの音楽家ウィリアム・カミングズが組み合わせて生まれたクリスマスソングです。この歌も、古い『讃美歌』の《あめにはさかえ》というタイトルで覚えている人が多いかもしれません。 フェリクス・メンデルスゾーンが1840年に作曲した男声合唱曲(作品68の2)と、18世紀にジョン・ウェスレーの弟チャールズ・ウェスレーが書いた詩を、イギリスの音楽家ウィリアム・カミングズが組み合わせて生まれたクリスマスソングです。この歌も、古い『讃美歌』の《あめにはさかえ》というタイトルで覚えている人が多いかもしれません。
|
| あら野のはてに(『讃美歌21』263番) |
18世紀に作られたとみられる、近世フランスのクリスマス民謡。作者不詳ながら世界中で歌われており、日本でもよく知られています。くり返しで歌われる「グロリア・イン・エクセルシス・デオ」は、「ルカによる福音書」2章14節の天使の賛美「いと高きところには栄光、神にあれ」のラテン語訳です。
|
| きよしこの夜(『讃美歌21』264番) |
オーストリアのオーベンドルフに、貧しさのあまり壊れたオルガンの修理もままならない小さなカトリック教会がありました。1818年、このままではクリスマスミサも満足に上げられない、と困った助祭ヨーゼフ・モールは、窮余の末に自分で新しい讃美歌を作詞。地元の小学校教師をしていた教会オルガニストのフランツ・グルーバーに、ギター伴奏で歌えるよう作曲を依頼しました。
 この急ごしらえの曲がどういう経緯かオーストリアからドイツのカトリック圏に広まり、気がついたら作者も知らない間に「新しく見つかったチロル地方のキャロル」として出版されていました。歌そのもののみならず、制作のいきさつまでが世界中に知られている讃美歌も、「きよしこの夜」ぐらいのものでしょう。現在でも、この歌を歌わなければクリスマス会が終わらないというほど、なくてはならないクリスマスソングとして親しまれています。 この急ごしらえの曲がどういう経緯かオーストリアからドイツのカトリック圏に広まり、気がついたら作者も知らない間に「新しく見つかったチロル地方のキャロル」として出版されていました。歌そのもののみならず、制作のいきさつまでが世界中に知られている讃美歌も、「きよしこの夜」ぐらいのものでしょう。現在でも、この歌を歌わなければクリスマス会が終わらないというほど、なくてはならないクリスマスソングとして親しまれています。
ちなみに、観光名所になっている「きよしこの夜教会」は後世建てられた記念堂で、当時の会堂は洪水で流されてしまったそうです。
|
| 天なる神には(『讃美歌21』265番) |
19世紀アメリカ・マサチューセッツ州の牧師エドマンド・H・シアーズの詩に、同時代の作曲家リチャード・ウィリスの曲がつけられています。一般よりも、どちらかと言えば教会の礼拝で好んで歌われている讃美歌です。
|
| ああベツレヘムよ(『讃美歌21』267番) |
 |
| ベツレヘムの遠景 |
フィラデルフィアの聖公会司祭フィリップ・ブルックスは1865年に聖地旅行をしていましたが、クリスマス前夜、静まり返るベツレヘムの町を郊外の丘から眺めているうちにインスピレーションを得、のちに一編の詩を書き上げました。1868年、教会オルガニストのルイス・H・レッドナーが、クリスマス礼拝用にこの詩に曲をつけてくれと依頼され、苦心のすえ本番の朝までかかってようやく曲を完成させたのがこの歌です。現在では《天なる神には》と並ぶアメリカ生まれの代表的な讃美歌となりました。
|
| みつかいうたいて(『讃美歌第二編』216番) |
16世紀のイギリス民謡《グリーンスリーヴズ》は、古来さまざまな詩をつけて歌われてきました。もちろんクリスマスヴァージヨンもいくつか残っていて、『讃美歌第二編』には19世紀イギリスの讃美歌作家ウィリアム・チャタートン・ディックスの詩がつけられたものが収録されています。
|
| さやかに星はきらめき(『讃美歌第二編』219番) |
会衆讃美というよりも独唱で朗々と歌い上げるほうが似合うこの讃美歌を作曲したのは、19世紀前半のフランスの歌劇作曲家アドルフ・シャルル・アダン。もとはカポー・ド・ロクモールによるフランス語の詩がついていましたが、英語圏では19世紀にジョン・S・ドワイトの作った詩《O
Holy Night!》が有名で、日本でもこちらのほうが親しまれています。
|
|
  |