トナカイは北ヨーロッパ、シベリア、アメリカの北極圏に分布する、大きな角とふさふさの毛皮が特徴の、シカ科トナカイ属の大形哺乳類です。意外なことに「トナカイ」は日本語。漢字だと「馴鹿」と書きます。
もちろん聖書には出てきませんが、クリスマスと言ったら決して外せない動物のひとつです。サンタのそりは八頭のトナカイが引いていると言われますが、トナカイは犬のような整然とした集団行動が苦手で、実際に八頭だてのトナカイぞりなんか仕立てた日には、空を飛ぶどころかマトモに走らせることもできないそうです。また、トナカイは雌雄ともに角を生やしますが、クリスマスの時期に角が生えているのはメスの方。したがってあのそりを引いている、立派な角を生やしたトナカイたちは、全部メスのはずだそうです。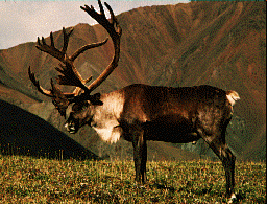
ラップランドなど北極圏ではなくてはならない家畜で、角も毛皮も骨も有効に利用されます。かってはトナカイ乳もしぼられていました。肉は独特のトナカイくささがありますが、栄養素が豊富に含まれています。もちろん現地にはトナカイ料理を出すレストランもあります。国内でも青森県岩崎村の「サンタランド白神」などで食べられるそうです。
|
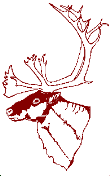 |
| トナカイと言えば忘れてはいけないのが、「真っ赤なお鼻のトナカイさん」こと赤鼻のルドルフ。ルドルフが誕生したのは1939年、シカゴのデパート「モンゴメリー・ウオード」の宣伝用小冊子に、専属コピーライターのR・L・メイが、サンタのそりを引く9頭目のトナカイの詩を書いたのが最初でした。この詩が好評を博し、数年後には単行本まで出版されました。49年にはメイの義理の兄弟J・D・マークスの作詞作曲でテーマソングも作られ、レコードが発売されるとこれも大当たり。全世界で歌われるまでになりました。それ以後もしばしばアニメ化されるなど、今なお世界一有名なトナカイの名をほしいままにしています。 |
ではどうしてサンタクロースのそりをひくのがトナカイになったのでしょうか?
|

|
| それは、1822年のクリスマス・イブにアメリカの詩人“クレメント・ムーア” という人が、自分の子供達に「クリスマスの前の夜」という詩を書きました。
その詩が世界に広まり、皆に親しまれるようになり、それからサンタクロース の乗り物は“トナカイが引くそり”が当たり前となったそうです。 |
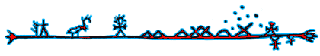
|