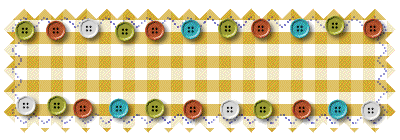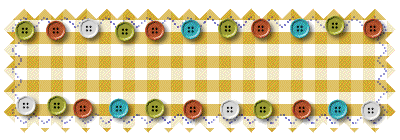白亜紀の恐竜たち・・・・
多様化した恐竜時代、百花繚乱
白亜紀(1億4400万年〜6500万年前)の地球は全体的に温暖で、植物は多様化し、それに伴って食べる草食類も多様化していました。また、植物連鎖の関係は、その草食類を捕食する肉食類まで多様化したのです。これまでに知られている恐竜の2/3は白亜紀時代のものです。
多様化した恐竜時代・・・・
白亜紀はそれ以前に比べて、すべての生物が最も繁栄、多様化した時代です。草食恐竜では、カモノハス竜類・角竜類・堅頭竜類のすべて、肉食恐竜では、コンプソグナトゥスを除くコエルロサウルス類が白亜紀に出現したものです。ジュラ紀に繁栄した竜脚類は、数の上では減少したものお、残った種が繁栄しました。
<被子植物の繁栄と新しい恐竜>
以前は裸子植物がメインでしたが、白亜紀になると花をつける植物が多く見られます。カモノハシ竜類と角竜類は、これまで見られなかった多数の集まった歯をもっていて、効率よく植物を咀嚼させられるようになりました。地域分布としては、北半球が被子植物がよく育っていたようで、このような恐竜が繁栄していたようです。しかし、南半球は被子植物の出現が遅れたらしく、それを食べたと思われる恐竜はあまり知られていないそうです。
<大陸移動と恐竜分布>
大陸移動は、恐竜の繁栄にかなり影響があったと考えられています。恐竜は分裂した大陸の中で独自の進化を進め、多様化されてきたのです。それは海によって隔たりがあり、交じり合うことがなかったからと思われます。たとえば、現代のガラパゴスやオーストラリアなど、長く海で囲まれてきた所では、その島にしかいない独自に進化した動植物がいます。
<巨大になった恐竜たち>
白亜紀は温暖で過ごしやすく、食物も沢山あったことから、どんどん体が巨大化し、また肉食恐竜などは、捕食するために競って体が巨大化していったと思われます。これは、捕らえるべき草食恐竜が巨大になったため、自らも大きくならないと捕食できなかったからです。
恐竜は恒温動物か変温動物か、いろんな説があり、今はむしろ変温であった説が重要視されています。大型化すると体重の割りに表面積が少なくなり、体温が下がりにくくなります。慣性恒温性の状態になって、体温が安定するのです。中国で発見された羽毛恐竜は逆に恒温性をもった恐竜で、体を小さくしても羽毛等で体温を調節し、下がるのをふせいだと考えられています。
アフリカ・恐竜の墓場、失われた世界・・・・
アフリカ・ニジェール
1990年、世界最大の砂漠・サハラを横断して化石の発掘を計画したチームがありました。ヨーロッパを南下し、地中海を渡り、砂漠を横断、指し語はニジェールまでという壮大な旅でした。
当初の目的は、魚の化石発掘でしたが、遊牧民の一人が沢山の骨が散らばっているところに研究員を連れていったのが、この偉大な発見のはじまりでした。そこには誰も見たことのない恐竜の化石が沢山顔を覗かせていたのです。それまでアフリカで発見されていたのはカモノハシ竜類のオウラノサウルスのみでしたが、ここで、何十種類にもおよぶ化石が発見されたのです。白亜紀には超大陸パンゲアが分離してアフリカが独立した大陸になったことから、それ以後恐竜は独自の進化を遂げたのでした。そのため、この血で発見されたものは他のどんな恐竜ともちがう形をしたものが多いのです。
先の発掘で手ごたえを感じたシカゴ大学のポール・セレノ氏は、1993年、再びニジェールの地にもどり、再発掘を始めました。露出していた巨大な骨を掘り進めるとそこには新しい竜脚類が埋っていたのでした。この恐竜はジョバリアの命名されました。現地の遊牧民の神話に出てくる「ジョバール」にちなんだそうです。このそばで、肉食恐竜も発見されました。その形はアロサウルスにいくぶん似ているようでもありました。この恐竜はアフリカロベナトールと名づけられました。アフリカのハンターの意味を持ちます。
1997年、三度の発掘調査が行なわれました。
そして1億1000万年前の地層から、奇妙な獣脚類の化石を見つけたのです。ワニに似た頭と背中の棘を持つスピノサウルス類とよばれる魚食恐竜の一種です。この変わった恐竜はスコミムス(ワニに似たもの)と命名されました。
この場所からそう遠くないところから、新しい草食恐竜が発見されました。それはあごの形が類を見ない竜脚類でした。あごには小さな歯がぎっしりとはえ、およそ1000本はあったようです。この恐竜はニジェールサウルスと命名され、ディプロドクスの遠い親戚の位置に数えられました。これまでジュラ紀の終わりにはディプロドクス類は死に絶えたと考えられてきましたが、今回の発見により、ニジェールサウルスのような子孫が生きていたことが解明されました。
この発見地あたりには、長さ2メートルもあるような頭骨も見つかっています。「スーパークロコ」の愛称で呼ばれているこの頭骨は、全長13メートル、体重8トン以上と推定されています。
恐竜の化石は全世界、様々な地区で見つかっています。アフリカ・南アメリカ・オーストラリア・インド・・・。また、アジア・北アメリカ・ヨーロッパにも、まだ沢山の化石が眠っていることでしょう。インドでは新種の肉食恐竜が、そして中国でも保存状態のよい恐竜や鳥類の化石が見つかっています。古代と現代をつなぐ鍵になっている化石・・・・その神秘の世界はまだほんの一握りしか明らかになっていないのです。これからの更なる発見を期待しています。
大恐竜時代・・・白亜紀の巨大生物たち・・・・
ジョバリア
竜脚類エウサウロポーダ類
(全長)21メートル
白亜紀前期
アフリカ・ニジェール
生体模型(下側)
筋肉の発達・骨に入り込んでいる空気袋・皮膚の様子などを復元。骨はダチョウに良く似ていて、それを参考に復元。
1999年、アフリカ・ニジェールで発見された大型の竜脚類。白亜紀のなかでは原始的な竜脚類であります。ここでは亜成体から成体まで数頭分発見されているので、それを元に復元されています。
ジョバリアの首は比較的短く、頚椎12個、胴椎13個、前足は後ろ足より短くなったいます。
マラウイサウルス
竜脚類ティタノサウルス科
(全長)10.5メートル
白亜紀前期
アフリカ・マラウイ
アフリカ・マラウイで発見された小型の竜脚類。ゴンドアワナ大陸を中心に、白亜紀最後まで生息していた竜脚類でもあります。
ティタノサウルス科は今まで白亜紀後期でしかみつかっていなかったが、マラウイサウルスの発見で前期にも生息していたことが明らかになりました。そしてこの科ではもっとも原始的な恐竜とされています。
スコミムス
獣脚類スピノサウルス科
(全長)11メートル
白亜紀前期
アフリカ・ニジェール
1998年、アフリカ・ニジェールで発見された大型の肉食恐竜で、名前の由来の通り、「ワニに似たもの」の特徴をもっています。ティラノサウルスに近く、全長11メートルと巨大です。エジプトのスピノサウルスやイギリスのバリオニクスと同じ仲間です。頭骨は、吻部が非常に長く、幅が狭く、高さが低いのが最大の特徴です。また背骨の上に伸びる棘突起は仙椎のあたりが高くなっています。前足は短いのですが頑丈に出来ていて、3本の大きなかぎ爪があります。頭骨の特徴から、魚などを食していたと想像されています。
アフロベナトール
獣脚類テタヌラ類
(全長)9メートル
白亜紀前期
アフリカ・ニジェール
19993年、アフリカ・ニジェールで発見され、今までにこの1体しかみつかっていません。アロサウルスに類似していますが、高さが低いこと、多くの骨がより細かいこと、吻部が狭く、歯が薄くナイフ状であること、目の上に突起がないなど、異なる点も多々あります。
3本のかぎ爪のある前足は頑丈で、後ろ足は大腿骨が頚骨より長いことから、あまり速く走れなかったと想像されています。尾の後半は、突起の連結によってつながっているたね、よく曲がらなかったとおもわれます。
アクロカントサウルス
獣脚類カルカロドントサウルス科
(全長)12.5メートル
白亜紀前期
アメリカ・オクラホマ州
北アメリカの白亜紀を代表する大型肉食恐竜で、首から尾にかけての背骨の棘突起が非常に長いのが特徴です。1950年、部分骨格が見つかった当初は、アロサウルス科に入れられていましたが、その後の研究で1996年、カルカロドントサウルス科に含まれるように変更されました。ところが1990年第に完全骨格が発見され、再度検討された結果、当初のアロサウルスのほうが近いのでは・・・と考え直されています。
ティラノサウルス
獣脚類ティラノサウルス科
(全長)11メートル
(頭骨の長さ)140センチ
白亜紀後期
アメリカ・サウスダコタ州
恐竜といったら真っ先に名前が浮かぶのは、このティラノサウルスかもしれません。それぐらい有名な恐竜でもあります。ティラノサウルスは有名の割りに発見数は少なく、今一番完全な形のものは、アメリカ・シカゴのフィールド博物館にある、愛称「スー」と呼ばれているものでしょう。スーの発見を堺にいくつか発見され、現在は20体ほどが発掘されています。そのひとつ、1992年、「スタン」と呼ばれているものが、今回展示されていました。この頭骨には穴があいていて、怪我をしたのが治ったようです。かなりの大怪我でも生き残ったたいした生命力の持ち主だったようです。