南関東地域には約3,300万人、実に日本人の約1/4の人が生活しています。
又、この地区には政治・経済・文化などあらゆる機能が集中しています。
それだけに南関東で大地震が起こると大災害になり、日本そのものがマヒしかねません。
地震防災、災害対策の重要性が痛感されます。
※下記の()内の発生確率は平成17年1月12日に政府地震調査委員会が公表したもので30年以内に地震が起きる確率です。
南関東では次のタイプの地震が予測されています。
1.南関東直下型地震
南関東の地下では、北米プレート・フィリピン海プレート・太平洋プレートが三つ重なっていて、お互いにこすれたり衝突したりするため絶えず地震が起きています。
M6クラスの地震も2〜3年に1度の割で起こっていますが、震源地が首都圏の真下なだけに、震源地が浅いときは大災害になる恐れがあります。
2.相模トラフ沿いの地震(最大0.9%)
1703年の元禄関東地震(M8.2)、1923年の関東大震災(M7.9)がこのタイプで、M8クラスの巨大地震がおよそ200年の周期で発生しています。
このタイプは、前回の巨大地震発生後70〜80年経ったあたりからM6クラスの地震が発生するようになります。
現代はその活動期に入ったところかもしれません。
伊豆半島を乗せたフィリピン海プレートが神奈川県西部地区に衝突しています。このため、この地区のプレートにはひずみがたまりやすく、断層も沢山できていて、地震の起こりやすい条件を備えています。この地区では、M7クラスの地震が約70年の間隔で発生していて、最近では1923年に起きています。
4.房総半島沖の地震
房総半島沖で相模トラフと日本海溝が出会い、そこで三つのプレート(北米プレート、フィリピン海プレート、太平洋プレート)が境を接しています。このため、この場所ではそれぞれのプレートに複雑な力がかかっており、大地震がよく発生しています。そのとき、海底の変動によって大津波もよく発生していますので注意が必要です。
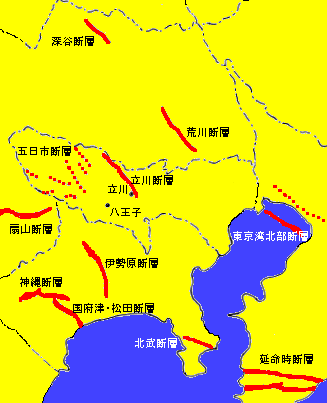
5.駿河トラフ沿いの地震(東海地震)
駿河湾に深い谷があります。これが駿河トラフで、御前崎沖で西南西へ曲がり、南海トラフにつながっています。
この二つのトラフからフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈みこんでいて、そのとき陸のプレートを引きずり込んでいます。
駿河湾を挟んだ伊豆半島と駿河湾西岸の距離が毎年少しずっ狭まっているのがその証拠で、引きずり込まれた陸地はいつか一気に跳ね返り、大地震を起こすと予測されています。
これが東海地震で、静岡県は震度6から7の激しい揺れに、南関東も震度5程度の揺れが予想されています。