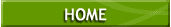2004.3.15
「『峠』(司馬遼太郎著)について」
司馬遼太郎の『峠』を読んだ。2度目である。半年前に読んだばかりだが,どうしてもまた読みたくなったのだ。
河井継之助……教科書には絶対に出てこないので,あまり馴染みのない名前かもしれない。彼の最大の魅力は,何と言ってもその“生き方”だ。日本の歴史上,信じられないような困難に見舞われた人物は数多くいるが,加えて彼ほど複雑な立場に置かれた人物も稀だろう。
継之助は江戸時代末期,越後長岡の人である(ちなみに,長岡は戦前に山本五十六,戦後に田中角栄を出した。また,小泉首相の所信表明演説で有名になった“米百俵”の話も,長岡藩の故事である)。長岡藩は譜代大名だった。つまり,古くから徳川に仕えていた“忠臣”である。
さて,幕末になると,にわかに江戸幕府は危うくなってきた。そして,恐らく日本史上3本の指に入るであろう大事件が起きる。ペリー来航である。幕府は困った。困り果てた挙げ句,出した結論は「諸大名に意見を求めるべし」。これで幕府はますます権威を失墜させた。
一方,国論は真っ二つに分かれた。「開国」か「攘夷」(外国を追っ払う)か。最終的に日本は「開国」するのだが,そこに至るまでの論争が凄まじかった。人も多く死んだ。吉田松陰・井伊直弼・坂本龍馬……数え上げたらきりがない。
そんな政争の中で,最もしたたかだったのは薩摩藩と長州藩だった。両藩とも当初は確かに「攘夷」を唱えていた。しかし,外国と戦ううち,それは無理だということをいち早く悟った。悟るが早いか,藩の方針を「攘夷」から「倒幕」へと一変させた。「開国」とは言わなかった。諸藩が猛反発するからだ。でも,「倒幕」を達成した瞬間,彼らは「開国」派に転ずるつもりだったし,事実そうした。彼らにとって必要だったのは「攘夷」運動のエネルギーであり,そのエネルギーを転用して最終的には新政府を作り上げたのだった。
話がそれた。継之助が長岡藩家老となった当時,薩長はいよいよ官軍となり,東進しようとしていた。江戸に進出し,徳川の息の根を止めようとしたのだ。同時に官軍は北陸にも兵を出した。北陸の諸藩を説得しつつ,会津を目指すつもりだった。
問題は長岡藩である。長岡藩は譜代であり,徳川に対して恩義があるが,時勢は官軍にある。時勢を背負って来るものには誰も敵わない。継之助にもそれは分かっている。官軍に味方すれば,きっと生き残れる。藩の存続のためには,この方法が最良だろう。しかし,それは同時に恩義ある徳川に弓を引くことでもあった。果たして武士としてそれができるかどうか。
継之助が考え抜いて出した結論,それは当時としては奇想天外のものだった。「武装中立」……現代ならともかく,当時の日本にこういう発想があり得たのかどうか。『峠』では,このアイデアは彼がスイス人と面会した際にヒントを得たことになっている。周知の通り,スイスは永世中立国である。日本の中で長岡藩のみが“独立国家”となり,官軍と幕府軍との間を取り持つ役目をする。これを彼は可能だと信じていた。
継之助はとにかく金を集めた。最新の武器を買い揃えるためだ。彼が奔走し,長岡はガットリング砲(今で言う機関銃)等,小藩らしからぬ軍備を整えた。
結論を言うと,長岡藩の主張は受け入れられなかった。武装中立は夢と消えた。官軍にとって,味方をせぬものはすべて賊軍であり,賊軍=幕府軍だった。
官軍はどんどん東進してくる。長岡藩は幕府軍として戦うしかなくなったが,その瞬間,長岡藩の命運は定まった。
長岡藩の戦いは壮絶を極めた。戊辰戦争の中で,この中越ほど凄まじい戦いはなかったかもしれない。文字通り長岡は火の海となった。1868年5月,長岡城陥落。同7月,継之助等が長岡城を一時奪還するも,すぐに再び落城。足に銃弾を受けた河井は会津へ落ちようとしたが,その怪我が致命傷となり,8月16日,山中で静かに息を引き取った。享年42歳。
継之助の選択は正しかったのか。地元では,長岡藩を火の海にした張本人として,彼をよく思わない人も多いと聞く。しかし,私が心ひかれるのは,そのリーダーシップと行動力だ。彼の周りには常に“抵抗勢力”があふれていたが,彼は決して怯まなかった。怯むどころか,進んで批判の矢面に立ち,初志を貫徹した。この激動の時代,立場の難しい藩の舵を取れる人物は,自分以外にない……彼は自分の本分をよく理解し,小藩・長岡のために身を粉にして動き続けたのだった。
河井継之助……現代人も大いに勇気づけられる人物である。だが,彼はひたすら悲運であった。
「改革者というものは多くは美名が残らない。むしろ悪名が残る。古来,そうである」と司馬遼太郎は言う。確かにそうかもしれない。そして,継之助こそ例外ではなかった。 |
|
|
|