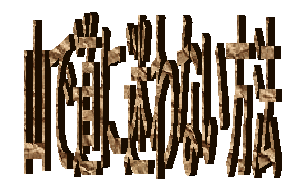
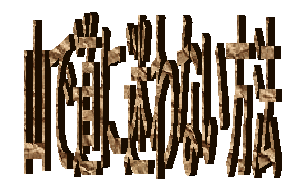
![]()
道に迷った経験はどなたにもあるでしょう。迷わない方法を考えてみました。
大事な情報です。そして思い込みを避け冷静になること。
石などを置いておきます。
![]()
もし道に迷ったら
ただし安全な場所で、火事の危険がないように焚き火をしなければいけません。
![]()
さて東西南北はどうやって決められたのでしょうか?
地球は地軸を中心に自転しながら、
太陽のまわりを円軌道で移動しています。地球上のどこにいても太陽の昇る方向が東、
しずむ方向が西と決められました。南北は古代中国人が発明した方位磁石で決められました。
方位磁石は磁北(磁南)を指し、地軸を差す真北とはずれています。横浜
では約6°40’西方向にずれています。
このずれの角度(偏角)は次の式により計算できます。
D=7
°22'.82+21'.01φ-7'.36λ−0.197φ2+0'.587φ・λ−0'.197λ2 (西偏)φ
=緯度−37°N 、λ=経度−138°E現在の地図は緯度経度の座標系によってあらわされて、ほとんどは上が真北です。
この座標系は今まで各国でまちまちでした。それは地球が完全な球でなく、
各国で異なる楕円体式を採用したためです。しかし人工衛星の軌道データから
解析した結果、地球は当時よりも扁平であることが判りました。
これをもとに座標系の原点がきめられ世界測地系(WGS86)が生まれました。
米国やカナダを始めとする多くの国は既に採用しています。
日本では昨年(2001年)の国会で現状の日本測地系(TOKYO)から世界測地系
(WGS86)に変更することが決まりました。今年の4月から施行されますが、
国土地理院の地図は昨年11月発行分から既に世界測地系が併記されています。
これにより日本の全ての地点の緯度経度が現在に比べ南と東にそれぞれ
約7〜14"ずれます。もちろん明石にある日本標準時の地点(135°E)や「日本のへそ」
のモニュメントなども約400m移動することになります。
![]()