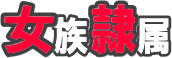
1日目(日曜日) 午後3 美猫淫謀
モダンな作りのモザイク模様のタイルが張られた塀に囲まれたマンションの前、閑静な街のたたずまいとは無縁な白と黒のツートンカラーのミニパトが停車していた。その側で先ほど後部座席から降り立った小柄な少年が、車内にいる二人の婦警さんにぺこぺこと頭を何度も下げていた。
一見すると、何かよからぬ事をした中学生が、家までミニパトで護送されてきたようにも見える。
「すいません、送ってもらっちゃって」
「いいのよぉ、正樹様のお世話はあたし達の仕事なんだもんっ!」
助手席からヒラヒラと手を振って答える黒髪の婦警さん。
少し垂れ目がちの優しげな美貌はほんのりと桜色に染まり、その胸元のボタンは乱れ、首筋に幾つもキスマークがついている。
そんな相棒とは対照的に、運転席に陣取る金髪ショートカットの婦警は、その華やかな顔立ちに遠慮の無いむすっとした表情を露骨に浮かび上がらせている。
「はっ、そりゃいいわよねぇ、まどか!あたしが運転してる間ずっ〜〜と正樹様と乳くり合ってたんだもんねぇ」
コツコツと白い手袋に包まれた指先がイライラとした様子でステアリングをノックしている。
まだ出会って半日も経っていないが、すでに普通の人たちの数十倍以上の濃密な時間を過ごした正樹は、目の前の不良婦警さんの怒りが頂点に達すると何をするかわからないことを重々承知しているため、急いでご機嫌をとろうとする。
「れっ麗華さん、あのですね…」
「いやねぇ麗華ちゃん、乳くり合ってたなんてぇ、もう恥ずかしい、ちょっと正樹ちゃんの大事な所を撫でてあげていただけじゃないのぉ、もうエッチなんだからぁ、いや〜ん」
だが、冷や汗を流す正樹を無視して火に油を猛烈な勢いで投入するまどか巡査。
予想に違わずピクピクと引くつきだす麗華のこめかみ。
「まぁ、ちょっ〜とそれだけじゃ収まらないからお胸とかお口とかぁ…アソコも使っちゃったけどぉ…麗華ちゃんは運転手さんだから正樹様にご奉仕できないでしょ」
ニコニコ笑いながらそっと自分のスカートを押さえる黒髪の婦警さん。
もちろんその瞳には何の罪悪感もありはしない。
「………っく」
麗華の真っ赤な唇がピキピキっと吊上がり、ハンドルを握る手が小刻みに震え出す。
ミニパトの外からそんな二人の様子を見ていた正樹の額からダラダラと汗が流れだす。
こっこれは良くない…兆候だよね…
確かに交番から正樹の住むこのマンションまで、運転する麗華さんをよそにまどかさんが後部座席に移ってきて、「えへへへ、正樹ちゃ〜ん」と抱き締められ、なし崩し的にエッチな事をしてしまっていたのは事実だ。
その間、麗華さんは無言で運転してたけど、時折バッグミラーにうつる瞳がまるで猛獣のように光っていたような…
あうぅ、あの時にまどかさんの柔らかい肢体に溺れて麗華さんのことを忘れてなければ…
今更後悔したって後の祭りだ。
あううぅ…どっどうしよう…
中学生の思い悩む問題とは到底思えない内容で、頭を抱える正樹。
そんなハーレムの主人の眼前では、能天気な下僕が一人さらに油をじゃんじゃん放り込んでいた。
「麗華ちゃん、あらぁ、どうしたの黙り込んじゃってぇ、ねぇねぇ、麗華ちゃんってばさ」
うりうりっと隣に座る野獣と化しつつある同僚の肩口をつつきまわす。
その度に、まどかの豊満な胸元からはつい先ほどまで少年に愛されていた名残香が漂い、狭い車内に溢れかえっていく。
「………まどか」
麗華の唇からまるで禍々しい息を吐き出すように低い声が漏れる。
「なぁに?麗華ちゃん」
にっこり向日葵のように笑う相棒。
その無邪気な笑顔に、ご主人様を独り占めされていた金髪の婦警さんは軽く忍耐を放棄してブチ切れていた。
「あんたねぇ!いい加減に……んっ!!むぐぅ」
ニコニコ笑うまどかの頭につかみかかろうとしたその矢先…
麗華の怒鳴り声が、突然掻き消える。
理由は簡単、罵声を吐き出そうとしたその唇が無理やりふさがれていたのだ。
「むむっ…んっ…んんっ」
絶妙のタイミングで麗華の口をふさいだのは、運転席の窓に顔を突っ込んだ正樹の唇だった。
少年は両手で婦警さんの頬を押さえ、その唇を無理やりふさぐと舌を絡ませる激しい口付けを与え続ける。
「んんっ…んふぅ……あん…っっ」
少しもしないうちに、ぎりっと吊り上っていた美女の眉が徐々に落ち、その瞳がトロンと惚けたものにかわっていく。
ルージュの引かれた唇の間に差し込まれた少年の舌は、口腔内で優しく麗華の舌を絡めとり慣れ親しんだ深い口付けを与えていく。
「あふぅ…んんっ…ちゅ…くちゅ」
つい先程までの怒りも忘れ、強気な婦警さんは少年に与えられる舌の感触に夢見心地な様子で脱力しながら、一心不乱に交じり合った唾液を啜り取っていた。
「んんっ…んちゅ…まっ…正樹…様ぁ」
やがて、つつっと唾液の糸を引いて中学生と美貌の婦警さんの交じり合った唇が離れていく。
「……あっあの、落ち着きましたか?」
この数時間で学んだ暴走する麗華のコントロール法をいかんなく発揮した少年は、すこし恥ずかしそうにはにかんでみせる。
そんな様子を、ぼーとした瞳でみつめる金髪の婦警さんは、まだ自分の唇に残る少年の感触に浸るように、指先で濡れた唇をなぞりながらため息と共に返事をする。
「ほんとひどいんだから…こんな技に身につけちゃってさ、正樹様の卑怯者」
その台詞とは裏腹に満更でも無い様で、満足気にシートに体を預けている。
そんな麗華の様子を見ながら正樹はほっと内心で胸を撫で下ろしていた。
ふぅぅ、どうやら落ち着いてくれたみたい…よかったぁ
またあのバリバリと電撃が走る警棒を振りまわされたら大変なことになるもんなぁ。
麗華さん怒ると何するか判んない人だし。
などと思いながら、なんとか山場を乗り切った少年は、二人に気づかれないように再度嘆息する。
「やるぅ、さすが正樹様、もう麗華ちゃんもメロメロねぇ」
そんな正樹の気苦労などお構い無しに茶々をいれるまどかは、にっこり笑うと緊張していた正樹が無意識のうちに触っていた腕輪に目線を注ぐ。
「ねぇねぇ、これもその腕輪のせいなのかしらぁ?」
「え?……どうなんでしょう?僕にはよくわからないです」
正樹はそう言いながら、もう一度自分の腕にしっかりと巻かれた例の腕輪を見つめなおす。
一部が黒く焦げ付いた腕輪は、交番で床に落ちていた手錠の鍵を見つけた時にまどかが拾ってくれ、また丁寧に巻きなおされていた。
その時、正樹は例によって例のごとく自分の力の秘密を黙っていることに耐えられなくなり、二人の婦警さんにことの真相を話していたのだ。
全てが済んでしまってから真実を打ち明けることほど卑怯なモノはないが、それでも自分が少しでも楽になろうとしたのか、それとも婦警さん達の心が救われることを本気で願ったのか自分でも分からなかったが、正樹はできる限り詳しく話していた。
もっとも、当然の如くすでに正樹の力に堕ちてしまった二人の美女は、そんなことなどどうでもいいように少年を押し倒し、話もろくに聞いていない様子だったのだが…
「本当なら、最初に話すことだったんですけど…ごめんなさい」
腕輪をいじっていた正樹は俯いて思い出したかのように再度頭を下げていた。
今回に関しては、正樹に非が有った上に無理やりの連行と、最初から話してもあの状況で素直に聞いてくれるとは思えなかったのだが、そこは自分の力が一番悪いと信じてしまっている正樹ゆえ、何度も謝り続けていたのだ。。
「高梨正樹!」
そんな頼りないご主人様の様子をみた麗華は、キスの余韻を吹き飛ばすように、ばんっとハンドルを叩くと活を入れるように怒鳴りつける。
「はっはい」
正樹は思わず背筋を伸ばしてミニパトの横でしゃちほこばる。
その胸元に、窓から乗り出してきた麗華が白い手袋に包まれた指先をぐいぐいと押し付け説教するようにまくし立てだす。
「あのね、正樹様、あたしもまどかも正樹様の力がどうとかは興味ないわ、大事なのは正樹様が何をしたいかって気持ちよ!いいわね!わかってる?」
「はっはい」
その剣幕に押されてガクガクと頷いてしまう。
どちらかと言うと、大事なのは僕の意思ではなく、僕の力のせいで虜になってしまった麗華さん達の意思のような気がするんですけど……
などとは恐ろしくてとても言えない。
「でしょ!今キスしてくれたのだって、正樹様の力のせいじゃなくて正樹様本人の意思でしょ?正樹様がしたいと思ったことをすればいいのよ、私たちはそれを助けるだけ、たとえなんであろうとね!そうでしょ、まどか?」
「そうですよぉ、正樹様ぁ、あたしたちは正樹様専用のお巡りさんとして日夜ご奉仕する所存ですぅ」
助手席のまどか巡査も独特ののんびりしたテンポでそう言うと敬礼をしながら嬉しそうに賛同する。
「そう言う訳よ」
うんうんと頷く少しどころかだいぶいっちゃってる瞳の麗華。
その瞳は正樹がやるんならなんでもOKよ!っと爛々と燃え上がっている。
そう言う訳ってどういう訳?
などと聞き返そうものなら、ご主人様の心意気を教え込むために何時間でも説教されそうだった。
「わっ…わかりました」
すっかり論点のずれた会話に呑まれて頷く正樹に、少年の魅力の下僕になった麗華は満足げに微笑む。
「わかればよろしい、じゃね正樹様おやすみっ」
そのまま運転席側の窓から身を乗り出し、少年の頬にちゅっとキスをすると、すばやくミニパトを発進させる。
「あぁん、麗華ちゃんずっこいぃ、あたしも正樹様にお休みのキスぅ」
「あんたは黙ってる!…じゃね、また明日、正樹様ぁ」
助手席で騒ぐ黒髪の相棒を乗せたミニパトは、正樹の目の前からファンファンと事件でもないのにパトランプを回しながら突風のように姿を消していた。
「まっ…また明日って…」
頬に残った美女のぬくもりを感じながら、呆然として立ち尽くす正樹の目の前で、走り去ったミニパトが跳ね飛ばしていったゴミバケツの蓋がカラカラ無常な音をたてて転がるだけだった。
「ただいまぁ」
マンションの玄関の扉を開けると、正樹の口から自然とその言葉がこぼれ出る。
引っ越してきたばかりの頃は、まだ違和感のあったその台詞も、この家の持ち主の叔母さんによる手厚い保護を受けているうちにすっかりと馴染むようになっていた。
「あれ?」
だが、いつもなら正樹の保護者にして、とっても美人でスタイル抜群の叔母さんが出迎えてくれるはずなのだが、今日に限って玄関先は誰もいない。
「?…おかしいな」
昨日も特注だという腰の辺りまでスリットの入った扇情的なチャイナドレスで抱きついてきて、その白く艶やかな太腿をたっぷりと正樹に堪能させてくれていたのだ。
正樹は、閑散とした玄関を見つめながら小首をかしげていた。
「冴子さん?」
正樹の声が空しく響き渡る。
正樹といる時はサービスと色気たっぷりの叔母さんだが、一歩外にでればバリバリと仕事をこなすやり手のキャリアウーマンの冴子さんは、仕事の都合から度々海外への出張や夜をおしてのプロジェクトなどがある時が多かった。
しかし、どんな場合でもまず正樹に連絡を入れてくれていた。
今日も昼に突然の呼び出しで会社にいってしまったが、その後正樹の携帯には冴子さんから連絡が一切なかったということは、いつも通り夕飯前には帰ってくることだと思っていたのだが…
「忙しすぎて僕に電話するの忘れてるかも…」
もし冴子さんが聞いたならば、目を潤ませて「そんなことをあるわけないじゃない」と泣きながら声を震わせるだろうことを口にする罪作りな少年。
「どうしよう…今日は帰ってこないのかな?」
正樹はそう呟きながら、横のシューズボックスを覗き込む。
田舎に住んでいた時は、誰がいるかなんて靴を見れば一目瞭然だった。
しかしながら、いかんせんまるでちょっとした小部屋ほどもある玄関に備え付けられた木目調のラックには冴子さんの靴だけでも見えるだけで数十足。
まるでブティックのショーケースのように並べられており、帰宅しているのか正樹にはてんでわからなかった。
「う〜ん、冴子さん?…まだ帰ってないんですかぁ?」
部屋の奥に向かって声をかけながら、正樹は履きなれてきた新品のシューズを脱ぐと、自分の割り当てのラックにきちんとしまい、本屋から図らずも万引きしてしまった例の本を小脇に持って居間の方に歩きだす。
「おかしいな……冴子さん?いないんですか?」
しかし、正樹がスリガラスの一枚扉を開けたときに、その疑問はすぐに氷解していた。
美味しそうな夕飯の匂いがすぐに漂ってきていたのだ。
濃厚でクリーミーな匂いから、おそらく今夜のメニューは正樹も大好きな冴子さん特製のシチューだということが推測できる。
そして微かに聞こえる楽しそうな鼻歌。
「冴子さん?」
正樹はパタパタと駆け足で居間を抜けると食卓から一望できるダイニングキッチンを覗き込む。
「ふふ〜ん〜♪」
そこには、普段着にエプロンをつけた冴子さんが、楽しそうに鼻歌交じりに鍋の味見をしているところだった。
すらっと驚くほど長い脚に、丸みを帯びたヒップに張り付く短めのスカート、そして均整のとれたプロポーションと背後からでもわかる豊満で見事なバスト。
その細い腰の後ろではエプロンの結び目がアクセントのように揺れている。
髪の毛が料理の邪魔にならないように、その額には大きめのヘアバンドがつけられ前髪を後ろに流していた。
そんな冴子さんのしなやなか白い手が、シチューを取り分けた小皿を艶やかな唇にそっと運んでいく。
「う〜ん……ばっちりね、ふふふふ♪」
切れ長の瞳を細めてそう言うと、にこっと唇を笑みの形にして満足気な吐息をもらす。
そんな新妻のように初々しい美貌の叔母さんの様子を正樹はまるで惚けたようにじっと見ていた。
毎朝見かけるパリッとしたスーツを着こなすやり手のキャリアウーマンの格好や、夜になるとベッドの中に忍び込んでくるランジェリー姿の色っぽい冴子さんも素敵だったけど…
こんな風に料理している冴子さんも可愛くていいなぁ。
などと思いながら正樹は、背をむけて歌うように楽しげに料理を続ける若妻のような冴子さんの側にフラフラと歩み寄っていた。
「ふふ〜ん♪」
だが、背後から忍び寄るように近づく正樹に気がつかない冴子さんは楽しそうに料理を続けている。
おそらく昼に別れた時の格好のまま急いで仕事に行き、帰ってくるとろくに着替えもせずに夕飯の仕度を始めたのだろう。
黒の魅惑的なストッキングと淡いグリーン色のスリッパというアンバランスな格好の冴子さんが、忙しげにキッチンを動きまわる度に、黒のカットソーの上から羽織ったエプロンの裾がヒラヒラと跳ねるように動きまわる。
「あっ、いけないアスパラガスが…」
ひらっとエプロンの裾を翻し、美貌の叔母さんは素早く手馴れた様子でアニマル模様の可愛げな鍋掴みを手にし、湯がいていたアスパラガスをザルに移し出す。
「ふぅ、後は、正樹くんの大好きなドレッシングを作って……ん?」
その時、冴子さんはやっと背後の人の気配に気がついたようすで、何気なく後ろを振り返る。
「あっ!」
「たっ…ただいま、冴子さん」
いつもとは違う叔母さんの家庭的で素敵な姿に見とれていた正樹は、黙って見つめていた事を隠すようにあわてて帰宅の挨拶をする。
「あら、正樹くん、帰ってたの?……おかえりなさい」
瞬間驚いたように瞳を見開いた叔母さんは、すぐにそれが彼女の大切なご主人様であることに気がつくと、にっこりと柔らかい笑みを浮かべて出迎えの挨拶を口にする。
「ごめんね正樹くん、料理に夢中で気がつかなかったわ」
アニマル模様の鍋掴みを手に嵌めたまま、口元を隠すように照れ笑いをする冴子さん。
おそらく先程までの鼻歌まじりのクッキングの様子を見られていたことが恥ずかしかったのだろう、微妙にその頬が染まっている。
「いえ、いいんですよ」
正樹もなぜだかその照れが伝染してしまったかのように、若妻のようなエプロン姿の冴子さんを見て頬を染めてしまう。
「あの後、正樹くんはどうしていたの?泪のところにずっといたの?」
「あっ…あの…あの後ですか?」
なぜかアニマルプリントの鍋掴みで口元を隠し上目使いにこちらを見つめる美貌の叔母さんの視線にドギマギしながら、正樹は裏返った声をだす。
その途端、正樹の背中に本日何度目か分からない冷や汗がどっと流れ出す。
あわわわ、どっどうしよう…
麗華さんとまどかさんのことですっかり忘れていたけど…僕、冴子さんの親友の泪さんとも……
ぱっと脳裏に浮かぶのは、色気たっぷりの濡れ光る唇を笑みの形に変え、カウンターの上でシャム猫のように淫らで挑発的なポーズを取る泪さんの姿だった
「ねぇ坊や、我慢できないでしょ、ふふふ、お姉さんが気持ち良くしてあげるわよ……ほらおいでなさい」
年下の少年に誘惑の台詞を吐きながら、四つん這いで突き出した丸みを帯びたヒップを揺り動かし、しなやかな指先でおいでおいでと手招きをしている。
あぁ…泪さん…とってもエッチな格好です……
「正樹くん?どうしたの?」
「はひぃ!」
こちらをみて怪訝な顔をする冴子さんの声で現実に連れ戻された正樹は、二、三度瞬きをするとフェロモンたっぷりのコーヒーショップのお姉さんの妄想を振り払う。
変わりに思い出されるのは、楽しそうに新しく仕入れたコーヒー豆について語り合う冴子さんと泪さんの二人の姿だった。
そして、少し悲しげな瞳でもう誰も座ることの無い婚約者だった人の椅子を見つめる泪さんと、それを優しく見守る冴子さんの姿。
きっと二人はかけがえの無い親友なんだろうってことは、今日のお昼の様子で始めて目にした正樹にも簡単に予想がついていた。
そんな二人に…
あああっ、どうしよう僕…もうとんでもない極悪人だよ…
まだ人生経験が豊富とは言えない正樹にとって、人と人の関係は簡単には計り知れないモノだったが、それでも二人の関係は自分なんかが間に入って壊してはいけない大切なものだったのがはっきりとわかる。
どうしよう……
思わず目をつぶって自分は何も知らないことにしてしまいたくなってくる。
正樹だって正直に全部打ち明けるのが正しいことばかりだとは限らないことは知っているが、それでも目の前の自分を信じてくれる大切な冴子さんに嘘だけはつきたくなかった。
たとえその結果が嫌われることになるとしても…
ごくりと決意を固めた少年の喉が鳴る。
「あっあの…冴子さん、僕…今日…」
小脇に抱えた雑誌を握り潰しながら、正樹は震えた唇を開く。
しかし決意をこめたその声をわざと邪魔するように、冴子さんが涼やかな声だす。
「あら、本を買って来たのね?それで遅くなったんでしょ」
「え?…はい、ちょっと本屋に…でも、それだけじゃなくて…」
うまく気をそらされた感じになってしまった正樹は仕切りなおしとばかりに、例の経済雑誌を近くのテーブルの上に置いて、もう一度心の中の勇気を奮いたたせようとする。
「冴子さん、僕…」
「ふふふ、いろいろあったみたいねぇ、まぁわたしもちょっとばかり大変だったけどね」
だが、そんな気がせいている様子が傍目でもありありとわかる少年を巧みに焦らすように含みをもたせ、笑みを浮かべる冴子さん。
「??仕事が大変だったんですか?」
「ふふふ、そんなところよ」
本当の所は、仕事は早く終わったのだが、家に帰宅すると予想外の訪問者がマンションの前で待ち構えておりそのせいで食事の仕度が遅れていたのだ。
もっとも彼女はそのことはまだ目の前で悶々としている正樹に伝える気はさらさらない。
なにせこれからすぐに分かるのだから……
「さてと、テーブルに座って少し待ってて、もうすぐできるから」
わざと話を打ち切るようにそう言うと冴子さんは正樹に背中をむけ、先ほどザルにあげたアスパラガスを冷水に浸そうとする。
「あっあの…冴子さん…その」
そんな叔母さんの背後で正樹はまるで所在無げにうろうろしながら、言葉を選んでいた。
どっどうしちゃったんだろ?冴子さん?
いつもなら抱き締めてくれたり、お帰りのキスをしてくれたりと大変なのに…今日はなんだかそっけない…なにより、なんだか僕の話そうとしていることをわざと邪魔してるみたいな……
だからと言って、自分からキスしてくださいなんて言い出せない正樹は、悶々としながらキッチンで働く冴子さんの後ろで立ち尽くす。
そんな正樹の目の前で、冴子さんの腰に巻かれたエプロンのフリルが、左右にぴょこぴょこと可愛らしく揺れ、美味しそうな匂いが立ち昇る。
「どうしたの?テーブルに着いて待っていてくれていいのよ」
「うっうん」
ちらっとこちらに切れ長の瞳を向ける冴子さんは、釈然としない様子で立つ少年を席に着くように促して、魅力的な腰を動かしながら手早く料理を皿に盛り付け出す。
だが、正樹はぼーと突っ立ったまま、そんな冴子さんの後姿を眺め続けていた。
どうしよう?泪さんのこと……
心を決めたつもりなのに、タイミングを上手くずらされたためか、楽しそうに料理をする叔母さんの後姿を前にすると言葉が口から沸いてこない。
それどころか、目の前で魅力的に揺れる充実した腰を見ているうちに、胸の奥の葛藤を無視して下半身にドクドクと熱い血液が集まりだしてしまっていたのだ。
あうううぅ…ぼっ…僕って……
そんな自分を意識してますます気が滅入ってしまう正樹だったが、体は毎日たっぷりと教え込まれた素敵なお姉さんの香りと媚態に敏感に反応してしまう。
「あら?どうしたの?お手伝いしてくれるのかな、正樹くん?」
冴子さんは、いまだにこちらを見つめて立ち尽くす甥っ子の方に振り返ると、不思議そうに小首をかしげて見つめるが、やがてその切れ長の瞳が大きく膨らんだズボンにたどり着くと合点がいったように微かに頬を染めて微笑みを浮かべる。
「あっ…こっこれは…」
「ははぁ〜ん、正樹くんは夕飯じゃなくて、他にも食べたいモノがあるみたいね…う〜ん、でも、もう少しまってもらえるかしら?すぐに食事の用意してあげるから…その後でたっぷりね♪」
淡い色のルージュが薄く引かれた唇がにっこりとその美貌を彩ると、冴子さんは何事もなかったようにキッチンに顔を向け、料理の続きをはじめる。
「あうぅ……はっ…はい」
カクカクとまるで機械仕掛けの人形のように頷く正樹だったが、一向にキッチンを去ろうとしなかった。
それもそのはず、目の前で楽しそうに料理にいそしむ美しすぎる叔母さんから目を離すことができなかったのだ。
エプロンのレースを翻すきゅっとしまったウェストに、切れ目の入った短いスカートが張り付いた魅力的なヒップ。
そして黒いストッキングに包まれたスベスベの美脚が、すらりとまるで官能的な芸術品のように伸びている。
その全てが、背後に控える少年の飢えた目を引き付けてやまないことを知っているかのように、なめかしく扇情的に揺れ動き、まるで触ってくださいと誘惑しているようだった。
「…冴子さん…」
正樹は、あまりにも魅力的な叔母さんの後姿に視線を釘付けにしたまま、囁くような熱い声を人知れず吐いてしまっていた。
正樹の頭の中は、もうすでに目の前で腰をふりながら料理に没頭している美貌の叔母さんの抜群のプロポーションで一杯になりつつあった。
泪さんのことを話すタイミングを待っているという建前が、正樹の股間でドクドクと高鳴る性欲を経由するうちに、いつのまにか毎晩味わっても味わい尽くすことない極上の美肉の記憶に置き換えられていく。
そう、あの服を剥けばその下には、しっとりとした最高級の絹のような手触りと弾力を持った甘く香る最高の美肌があるのだ。
ねっとりと絡みつくような甘いキスに、いつも正樹を包み込んでくれる優しい抱擁。
知ってしまっているだけに、さらに欲しくなる甘美で気持ちの良すぎる麻薬のような少年のためのだけの美女。
毎日毎日貪り尽くしたために、目をつぶらないでも思い出せる冴子さんの柔らかな肢体が、すでにズキズキと痛いほど大きくなっている正樹の下半身を更に刺激する。
「ん?どうしたの?」
だが冴子さんは、背後から突き刺さるそんな少年の性欲に狂った視線に気がついていないのか、こちらに背を向けたまま朗らかな声をだす。
「あっ…そっその…」
正樹は、はうっと顔を伏せながら、それでも下半身から湧き上がるジンジンと焦げ付くような飢餓感に背中を押されて声をだす。
「ぼっ僕…がっ我慢ができなくて…あうぅ…そっそうじゃなくて、冴子さんに言わないといけないことが……でっでも…その前に…っっう…」
「ふふふ、わかってるわ、もうお腹ぺこぺこなんでしょ、よいしょっと…あとはサラダを盛り付けるだけよ、待っててね」
だが、冴子さんは正樹のじれたような声を聞き流すと、手早くさっと鍋の中のシチューの具合を確かめ、木製のサラダボウルの中の野菜にドレッシングを馴染ませだす。
「そっ…そうですか…その…わかりました、待ってます」
正樹ははうぅっと涙のでそうな声をだすと、もじもじと自分のズボンの盛り上がりを隠すように上着をひっぱり、冴子さんの姿を極力見ないようにじっと下を向いて待つことにする。
「そう、いい子ね」
そう答えた冴子さんは、磨き上げられた鍋の表面にうつる背後の少年の姿を見つけると、まるで甘いお菓子を舐めるように、唇を卑猥に舐めて妖艶な笑みを浮かべていた。
ふふふふ、正樹くんたら可愛いいんだから、もう今すぐにでもご奉仕してあげたくなっちゃう…………あん、いけない、はやく夕飯の準備しないと……
思わず少年の愛らしい姿に魅せられていた美貌の保護者は、数秒後ようやく自分が料理をしていたことを思い出すと、期待に胸を高鳴らせながら少年のために考えた献立を次々と用意していく。
しかし、手際よく仕事をこなしながら、やはり気になってしまい、ちらちらと切れ長の瞳を鏡のようになった鍋の表面についつい走らせてしまう。
そこには俯きかげんで立ち尽くす小さなご主人様の姿があった。
「ふぅ…もう、しかたのないご主人様ね」
冴子さんは小声でそう呟きながら困ったように指先を顎にあて思案顔になると、やがて涼やかな声で背後をうろうろしている少年に声をかける。
「ねぇ正樹くん、悪いんだけど大きなお皿取るの手伝ってくれるかしら、ほら、この上の棚にあるのよ」
「はっはい」
なるべく冴子さんを見ないように下を向いていていた正樹は、あわてて返事をするとばっと顔をあげる。
そこには、キッチンの上のキャビネットに手を伸ばそうと、シンクの縁に片手をついてぐいっと背伸びをしている冴子さんの姿があった。
カットソーから伸びた白く細い腕がキャビネットの枠にギリギリ届いているが、つま先だちになった姿勢は今にも倒れてしまいそうなほど安定が悪くあぶなっかしい。
そしてなにより、きゅっと引き締まったヒップにつられて短いスカートの裾が持ち上がり、黒のストッキングに包まれた魅力的な太股と絶妙な曲線を描く美脚をあますところなく見せつけるという、ある意味あぶなっかしい格好でもあった。
…さっ冴子さん…あぁもう少しで見えそう…あぅ…駄目…駄目だ
正樹は、思わずしゃがみこんでそのイケナイほどに持ち上がっているタイトスカートの内側を覗き込みたくなる衝動にたえると、「お願い」っとこちらに視線を送る美女の後ろにあわてて歩み寄る。
「んっ、ありがとね、それじゃ腰のところ支えてくれるかしら?もう少しで届きそうなの」
冴子さんは前髪を押さえつけるヘアバンドからこぼれた黒髪を一房垂らしながら、背後に立つ少年にそっと柔らかく丸みを帯びたヒップを押し付ける。
「はっはい」
正樹は、自分の腰に押し当てられるエプロンのレースに飾られた冴子さんのウェストにドキマギしながらなんとか腕を伸ばすと、そっと触る程度で手を添える。
「んっ、あれっ、もうちょいなのに……あん、正樹くんもっとぎゅっと押さえてくれないと安定しないわよ」
「はい、こっ…こうですか?」
その声に背中を押されたのか、正樹は目の前のほっそりとした腰に添えた手に力をいれる。
手の平に服越しでも伝わる柔らかな大人の女性の肌の感触。
ますますドギマギする正樹のことなど気にする様子もなく、冴子さんはシンクの端に手をつき、伸び上がってさらに正樹にもたれ掛かるように背筋を反らす。
「んっ、もう少し…しっかり持っててね、正樹くん、んしょっと」
手を伸ばす美女の柔らかな肢体が正樹にぐいぐいとのしかかってくる。
ちょうど丸みを帯びたお尻が少年の下半身を押さえつけ、驚くほど細い腰がまるで欠けたピースを嵌めたようにぴったりと腕の中に納まっていた。
途端に、今まで以上の欲望が美女の腰に押さえつけられた下半身から沸きあがり、ぐんぐんとズボンの前を押し上げる。
だっ駄目だ…こっこんな時にぃ…
だが、あせる正樹の股間は本人の意思とは正反対に立ち上がり、今すぐにでも目の前の美女の柔肌を食い尽くそうと硬くなっていく。
あわわわ…おっ落ち着かないと…そうだ今日の午前中だって散々見たし触ったじゃないか…いっ意識することなんてないはず……だよね…
だが、連想ゲームのように、思わず今日一緒に買い物をした時のあのいやらしく淫らな休憩の光景が次々と思い出されていく。
とろっと濡れた半開きの口唇、汗に濡れ、たわわに弾む豊かな乳房、肉を打つ音が響き渡るトイレの個室。
あっ…しっまた、よけいに大きくなってくよ……とほほ、僕、泪さんのことを話そうと思ってたのに…
心とは裏腹に、正樹の中学生らしい肉欲に飢えた手は目の前で揺れ動く魅力的な美女の腰の上をしっかり這いまわり、いつのまにかその姿勢は、まるで後背位で美女を貪るように、がっちりとその腰を抱きかかえ、タイトスカートに浮かび上がるヒップの割れ目にズボンの膨らみをぐいっと押し当てられてしまっていた。
…あぁ…さっ冴子さん……ごめんなさい…僕もう……
このスカートの奥には、あの魅力的で気持ちの良い叔母さんの白い尻肉と甘い蜜壺があるのかと思うと、正樹は理性を保っていられなかった。
思わずズボン越しに肉棒をこすり付けるようにスカートのヒップラインに擦り当て、猿の玩具のように腰を揺らしだしてしまう。
「きゃっ……こら!正樹くん何をしてるの、もうぅ、だめよ、ふざけちゃ」
天井近くのキャビネットにようやく手を差し込んでいた冴子さんは、慌ててもう片方の手でシンクの縁を掴み直し不安定に揺れる体勢を整える。
「ごっごめんなさい…でも…でもぉ…冴子さんのお尻…とってもスケベなんだもん、冴子さんが悪いんだからね」
すでに理性ではなく下半身の欲望に体の制御を譲ってしまった正樹は、言い訳にならない言い訳をしながら猛然と目の前の美女に背後からぴったりと抱きつき腰をカクカクと動かしてしまう。
「あっ、ちょっと、こら、危ないでしょ」
「冴子さんっ、冴子さんっっ」
正樹はまるで駄々っ子のように大好きなお姉さんの名前を呼びながら、その柔らかくグラマラスな肢体にむしゃぶりつくように腕を回し、丸みを帯び肉感的なラインを描くスカートのお尻のラインに腰を擦りつける。
「あん、もう甘えん坊ね、正樹くんは」
しかたないわねぇと言わんばかりにため息をつく美女。
しかし、そう言いながらも少年が自分を求め抱き締めてくれることに喜びを隠しきれず、雌奴隷らしく毎晩調教された蜜壺からは淫らな水をにじませていた。
「でもね、今度から、我慢できない時は先にちゃんというのよ、いいわね」
まるで幼子に言い聞かせるように冴子さんはそう言うと、そっと上に伸ばしていた手を下ろし、両手でシンクの縁をつかむと背後から抱き締める少年の体に大きなヒップを突き出すように与えてやる。
「でも、冴子さんも悪いんです…こんなに綺麗で…素敵なんだもん、すぐに我慢できなくなっちゃうよ」
正樹は欲望に狂った瞳でそう言いながら、もぞもぞとエプロンの脇から手を差し込んで行く。
レースのついた布地が盛り上がり、潜り込んだ正樹の両手がまるで地面の中を潜行するミミズのように美女の体を這い回ると、大きく張り出した豊かな胸元めがけて突き進んで行く。
「正樹くん、そっそんな……あっっ、あひぃ…おっお胸もんじゃ…んんっ」
大事なご主人様に誉められ思わず頬を染めて長い睫を震わせた美女の胸元で、少年の手がもぞもぞと貪欲に動き回りだしていた。
「冴子さんっ、冴子さんっのおっぱい」
エプロンを大きく突き出す淫らな形の重そうな膨らみに、正樹の手がまるで飢えた狼のように貪りつくと、たぷたぷと揺らしながら形が変わるほど捏ね繰り回し執拗なまでに揉みしだく。
「あんっ、もうっ…正樹くんったら、そっそんなに激しく…だめ…お料理途中なのにぃ…」
自分の大事なご主人様に可愛がってもらっている。
そう思うと冴子さんは背後からエプロンに手を突き入れられ巨乳を鷲掴みにされながら、我慢できないように欲情に満ち震えた声をだしてしまう。
その瞳はすでに半分焦点を失い、いまにも背中から抱きつく愛しい少年に全てを任せてしまいそうになっていた。
「ね、夕飯が終わったら…お胸好きにしていいから…あっ…お料理させて…あん、だめぇ」
切れ長の瞳を妖しく潤ませ切れ切れの声をだす冴子さん。
なにせ彼女のたった一人の大事な主人に言い寄られているのだ、頭ではまず食事の準備をしなくてはと思うのだが、すでに堕ちてしまった体はトロっと甘い蜜を零しだしていた。
「だったら冴子さんは料理しててください」
こちらはすっかり欲望に狂った中学生が、勝手なことを言いながら大人の女性の香りのする背中にぺったりと張り付いていた。
しかもその手は自分の保護者の叔母さんの豊かな乳房を両手でタプタプと揉み、腰をグリグリと押し付けている。
「でっでも…こっこんなんじゃ料理できない…あひぃ…」
黒のカットソー越しでは我慢できなかったのだろう、もっと美女の重量感に溢れたバストを味わおうと正樹の手が今度は上着の内側に入り込んでくる。
「んはぁ…」
乱れたエプロン姿の美女は、背後から少年に抱きつかれたまま、まるで熱病にかかったように、肩を寄せて小首をふる。
「ああっん、正樹くん、つっつまんじゃ…んひぃ…あっなにを…」
もそもそと服の内側で動き待っていた指先がさらにその欲求を満たすべく、今度は美貌の叔母さんの上着を剥いてしまおうと、エプロン越しに捲り上げる行動を開始する。
ここ最近、経験を多少は積んだ正樹の指先はまだ危なっかしい所はあるが、着実に作戦をこなすだけの技術を身につけていた。
「だっだめぇ、ぬっ脱がしちゃ……」
いやいやと紅潮した美貌をふる冴子さんの胸元では、あっけなくエプロンが胸の谷間に寄せ集められる。
さらに、少年の手は容赦なくその下のカットソーとブラをぺろんっと捲り上げると、瑞々しく実った果実のような豊かな双球と、控えめに硬くなった胸の頂をぶるんっと露わにしていた。
「綺麗ですよ、冴子さん」
正樹は、頬を染め荒い息を吐く冴子さんに背後から抱き付き、そのうなじに鼻先をうずめチロチロと舌を這わせていく。
もちろん前に回された両手では、よれたエプロンを谷間に挟んだ艶ややかな美乳をむんずと掴み、円を描くように揉みしだきまくる。
「まっ正樹くん…んはっ…あひぃ…お料理冷めちゃう…から…ああっ」
まだ年端もいかない小柄な少年に抱き締められ、いいように弄ばれる美女の口元からは、言葉とは裏腹に耐え切れない快楽がもたらす唾液の雫が一筋流れ落ちていた。
その胸元で揺れる弾力のあるバストには少年の指がめり込み、淫らな肉が詰まった双球を、激しく擦りあわすように揺り動かしていた。
理性を何処か遠い所に忘れてきた正樹は、白く匂い立つような冴子さんの首筋に舌を這わせ、極上の前菜を舐めしゃぶりながら、耳元に微かに聞こえるような声をだす。
「僕といるときはエプロンの下は何も着ちゃだめって約束だったよね?……雌奴隷の冴子さん」
その言葉が、届いた途端、僅かばかりの抵抗をしていた肉感的な叔母さんの体が力をなくし、瞳から最後の理性がすっと消えて行く。
「あんっ、そっそうです、正樹くん……いえ、正樹様……私はご主人様の奴隷よ」
代わりに現れたのは主人への隷属を誓った奴隷の瞳。
「いつでも、正樹様のお好きなように」
トロンと蕩けた瞳で、美貌の叔母さんは背後から抱きつく彼女の主人に、その抜群の肢体をゆっくりと預けていく。
「冴子さん……」
「正樹様…」
抱き締められたままゆっくりと後ろを振り返る冴子さん。
そこには、美の女神のように麗しく、少年を包み込むような嫣然とした美貌があった。
正樹は欲望のままに、女神の柔らかなバストに指をめり込ませて抱きつきながら、ゆっくりと近づいてくるその類まれな美貌に心を奪われていた。
…こんな綺麗な人が、僕の奴隷なんだ…
言葉一つで何時でもその魅力的な肢体を捧げる、少年によって調教された忠実な雌奴隷。
今さらながらその事実が、正樹の心をざわざわと乱していく。
「正樹様、お口を頂くわよ、いいかしら?」
見惚れるような優美で淫らな大人の笑みが接吻の許可を求めてくる。
「うん…うん、うん」
正樹は目の前の美貌に心を奪われたまま、ごくりと生唾を飲み込んで何度も肯定の声をだしていた。
「ふふふ、可愛い御主人様」
次の瞬間、しっとりと濡れた薔薇の花びらのような高貴な唇が、少年の唇にそっと重なってくる。
「んっ…んんっ……」
極上の蕩けるような果実が正樹の唇を覆いつくしていた。
正樹はその甘く糖蜜のような美女の唇を味わいながら、しっかりと抱きついた腕に力をこめ、冴子さんの素敵すぎる体を恍惚とした意識の中で感じていた。
今、自分の腕の中には、あの冴子さんがいるのだ。
いつもテキパキと仕事をこなすバリバリのキャリアウーマンとして活躍し、家では家事でもなんでも完璧こなすスタイル抜群、容姿端麗。
そんな最高のお姉さんが、いま自分の腕の中で頬を染め長い睫を震わせ、キスをしてくれている。
それだけで、ズボンの中で固く大きくなった肉棒が暴発しそうになっていくた。
「冴子さん…んんっ…あふぅ」
「んんっ…あふぅ…んっ…ちゅっ」
やがて貪り合うように何度も重なり合う唇の間から、肉感的で柔軟な美女の舌先が、ぬるっと口腔内にもぐりこんでくる。
すぐさま官能的な踊りを踊るように、大人の美女とまだ中学生の少年の舌は激しく絡み合っていた。
ぴちゅくちゅ ちゅるるっ にちゅにちゅ
粘着質で淫らな音と、喉の奥で篭るようなうめき声だけがしばらくキッチンに響き渡る。
正樹は存分に甘い舌を啜り、とろっ絡み合った唾液を送り出すと、舌を尖らせ美女の口腔内を舐めまわす。
「はんっ…んんっ…んぐぅ…んふぅ」
とろとろと重なり合った唇の間から交じり合った唾液が流れ落ち、どちらからともわからない微かな喘ぎ声が際限なく繰り返される。
くちゅ ちゅく にゅちゅ じゅるっ くちゅ
「はうっ…んんっ…さっ冴子さん……唾液…飲んで……んんんっ」
「は…はいっ……んっ、んぐぐぐぐっ…んはぁ…おいし…んんっ…んちゅ…ちゅちゅっ…じゅるるっ…もっ…もっとくださいぃ…あふぅ…ちゅく…じゅるるっ」
正樹は、年上の美貌の叔母をしっかりと抱き締め、思う存分その麗しい唇をついばみ、その半開きの唇の中に舌を使ってどろっと唾液を流し込んでやる。
さらにコクコクと少年の唾液を嚥下する美女の白い喉の下、スポンジケーキのような柔らかい胸を揉みしだき、指の腹で木苺のような乳首をグリグリ押しつぶすように扱き責めたてていた。
「んはぁ…正樹様…んんっ…あふぅ…くちゅっ」
お互い一ミリでも深く繋がろうと唇を交える顔を動かす度に、その隙間から空中で何度も絡み合う妖しい舌の蠢きが見え隠れする。
「これ以上は、もうっ……お胸がぁ…んんっ…あふぅ…もう駄目よ」
「冴子さん…ねぇ…もっと、もっと…」
年上のお姉さんの唇がそっと離れても、正樹はまだまだ物足りない様子で唇を突き出すように幼い顔を寄せていく。
まだまだ貪り足りなかった。
もっともっとこの美女の綺麗な唇に吸い付き、その甘く魅力的に動く舌を味わい尽くしたい。
正樹の心の奥から、この類まれな美貌と艶やかな肉体をもった腕の中の麗女を体の隅々まで味わいたいという欲求が留まることなく溢れだしてくる。
その美しいモノを独占し自分の色に染あげたいという独占欲に突き動かされるままに、少年はさらに美女をしっかりと抱き締め、その豊満な美乳を捏ね回しながら必死に口付けをねだっていた。
「ねぇ、冴子さん…冴子さんっ〜」
「ふふふふ、こら、もうっ、そんなに舐めちゃ、お姉さんのお顔がドロドロになっちゃうでしょ…あんっ」
飢えたように突き出される少年の舌に、その端正な横顔をチロチロと舐め上げられ唾液まみれにされながら、冴子さんの切れ長の瞳が優しくしかし何処か楽しそうな雰囲気で細められる。
「ふふふふ、本当に甘えん坊なんだから……ねぇ、ところで…」
その時、自分の被保護者の少年にタプタプと乳房を揉まれ、その美貌を唾液に汚される冴子さんの濡れた赤い唇から少年にとって衝撃的な言葉が発せられる。
「……泪にもこんな風に甘えちゃったの正樹くん?それともケダモノみたいに犯しまくっちゃったのかな?」
「え!」
突然の冴子さんの台詞に、後ろからしがみ付いた姿勢のまま、正樹はピキッと固まってしまう。
「ふふふ、驚いてる、驚いてる」
固まってしまった少年を満足げにみつめる意地悪なお姉さん。
「ごめんね、正樹くんがそのことを私に言いたがってるなぁってわかってたんだけど…ふふふ、もじもじしてる正樹くんを見てたら可愛くって、ついつい、ね」
そう言って首を後ろに捻じ曲げると、冴子さんは自分の肩口に乗っている真っ赤になったままの少年の頬を先程までのお返しと言わんばかりに舌でペロンっと舐め上げてやる。
「あっ…あのぉ…なっなっ…なんで…」
事態が未だに把握できていない少年は、それでも美女の剥き出しの巨乳はしっかりと放さずに、もたつきながらもなんとか声をだす。
そんな正樹の様子に冴子さんはますます楽しそうに目を細めながら、整った鼻筋を擦りつけるようにして美貌を摺り寄せ甘く囁くように教えてあげる。
「教えてもらったのよ、本人に……ねっ泪」
…まっ…まさか……
ちらっと動いた冴子さんの視線の先。
そこには……
「そういうことよ、坊や」
キッチンの入り口の壁際に、もたれかかる様に立っている一人の美女。
緩やかなウェーブのかかった長い髪、濡れたような黒い瞳、色っぽい肉厚の唇にその左下のホクロが特徴的なフェロモンたっぷりの美貌。
急カーブを描いて盛り上がる豊満なバスト、細くくびれた腰から豊かなヒップへのシェイプアップされた見事な曲線、そしてスラッと長く綺麗な美脚。
理想的な曲線を描くグラマラスなボディライン。
その全てが男性を虜にしてやまない魅力的な大人の色香を存分に漂わせている。
「るっ泪さん」
今日の昼間、正樹の魅力に堕ちた蠱惑的な喫茶店の女オーナー、桐生泪の姿があった。
「どう、びっくりした?」
背後から正樹に密着されバストを鷲掴みされた姿勢のままの冴子さんは、してやったりと言わんばかりの声をだし、ふふんと面白そうに小鼻をならして自慢気だった。
「なっなんで…あの…その…」
すっかり年上の美女たちに翻弄されることが定着しつつある少年は、あわわっと口を開いた顔のまま頭に浮かんだ単語をそのまま声に出し続ける。
「あらあら、坊やもう忘れちゃったの?言ったでしょ今日のお昼に…今日からは私も坊やにたっ〜ぷりスケベなことを教えてあげるわ、ってね」
ちゃめっけたっぷりに泪はウインクすると、その魅惑的なヒップラインを左右に揺らしながら正樹のほうに歩み寄ってくる。
メス猫のようにしなやかに歩く魅力的なフェロモン美女は、ブラウン系の落ち着いたセーターとロングスカートに、なぜかお店でもないのに片側の肩を通すタイプの黒のエプロンを身につけている。
「あの…でも…その…」
「よろしく指導してあげてね、泪」
「ふふふ、おまかせよ、冴子」
いまだにあわあわと慌てる正樹にはお構いなしに、落ち着いた様子のカフェのオーナーと年若い保護者はお互いその美貌をにっこりと微笑みにかえると正樹の方に視線を集める。
「ふふふ、そんなに困らなくても大丈夫よ、ちゃんと冴子には説明してあるわ…私が坊やに本気で夢中だってね」
「そう言うわけよ正樹くん、私が仕事から帰ってきたら泪が待っていてね、それでいろいろ聞いちゃったの……まったく帰りが遅いから心配してたのよ、変なことで正樹くんが気にしてるんじゃないかって、ね、泪」
「ええ、坊やったらなかなか帰ってこないんだもの、じれったかったわよ」
再度、視線を絡ませあい頷きあう二人の年上の美女。
それだけで大概の男なら昇天してしまうほどの強烈な色気と魅力を含んだ二つの視線。
既に美女達の間で、正樹の知らないうちに自分の運命がかかったやり取りが行われていたのだろう、知らぬは御主人様である本人ばかりなのであった。
「あの…その…」
勿論そんなことは想像もできない正樹は、腕の中の美人の叔母さんの予想外の反応について行けずただ意味の無い言葉を繰り返す。
「それでね、私の仕事の遅いときは泪にもお手伝いさんとして来て貰おうと思うんだけど…どうかしら?」
「…え?泪さんが?」
ようやくこの時になって背後から抱き締めていた冴子さんを解放した正樹は、事態を徐々に飲み込みつつ先ほど耳から入ってきた言葉を反芻する。
「…お手伝い?…ですか?」
きょとんとした顔で、すぐ側で嫣然と微笑む泪さんと、正樹の手が離れて少し寂しげな冴子さんを見比べる。
「そうよ、お手伝いさん、駄目かしら?泪なら信頼できるし、正樹くんのことをいろいろわかってくれると思うんだけど…ねぇ、だめぇ?」
事の成り行きについていけてない正樹をしぶっていると勘違いしたのか、冴子さんはくるっと後ろを振り返ると今度は自分から少年を抱き締めて甘えるような声でおねだりする。
「ねぇ正樹様ぁ♪」
乱れた時か、感極まった時にしか言わない様付けで正樹を呼びながら、冴子さんは悪戯を楽しむ猫のように正樹の首筋に鼻先を摺り寄せる。
「あら、坊やは私を雇うことに反対なのかしら?…う〜ん…そうだわ……どう?今夜はお試し期間ってことで、私の仕事ぶりを見てもらえないかしら?それで坊やが満足するようなら正式なお手伝いさんで採用ってことでどう?」
冴子さんに抱き締められる正樹の顔が横からくいっと秀麗な指先に持ち上げられる。
「ふふふ、もちろん、坊やの大好きなコトのお手伝いだってして上げるわよ、私を雇って損はさせないわよ、ぼ・う・や」
まるで匂い立つ薔薇の花のように妖艶に微笑む泪は、そう言いながらそっとその瑞々しい美貌を年端もいかない少年に寄せていく。
「ぼっ僕は、反対なんて…んぐぅ」
ようやく頭の回り出した正樹の声をふさぐように、真っ赤な唇が重なると、ねっとりと絡みつくような舌が踊りこんできていた。
ぬちゅ くちゅ ちゅるるる
まるで血を啜る魔性の花のように、淫らに妖しく蠢く泪の舌が少年の口腔内に侵入すると、ねっとりと口の中を舐めまわし、口蓋を舌先で擦るように愛撫し、湧き出す唾液を激しく吸引する。
「んんっ…んぐぅ…んんっ」
思わず目を見開く正樹の眼前には、震えのくるほどの美貌が迫り、長い睫の奥に見える潤んだ宝石のような瞳が「どう坊や、あたしのキスは?最高でしょ」と囁きかけてくる。
くちゅくちゅ ちゅるるる じゅるるる
ねじ切るように激しく正樹の舌が吸われ美女の口の中に引き込まれると、トロトロと蕩ける口腔内でたっぷりと包み込まれ、絡まった舌ごと飴玉を溶かすように舐めしゃぶられる。
「うぐっ…うううっ」
優しく諭すような冴子さんのお姉さん然とした口付けとは異なり、泪のそれは妖しげな魅力に彩られ男を恍惚とさせるキスだった。
「んはぁ…ふふふ…ほら、もっと舌を出してごらんなさい…んふ、そうよ、吸ってあげるわ、坊やのお口、ほら、あ〜んして……そうよ…んんんっちゅるるる」
白く細い指先が正樹の頬をそっと両側から押さえつけ、半開きになった口に再度ねっとりと濡れた赤い唇が覆いかぶさって行く。
とろっと唾液を垂らした甘美な砂糖菓子のような舌先が、少年の口の中を先ほど以上に丹念に舐めまわし、唾液ごと舌をバキュームする。
じゅじゅじゅじゅ じゅるるるる
まるで水をたっぷりと含んだスポンジから水気を啜り取るような卑猥な音が流れ出し、泪の白くほっそりとした喉がコクンコクンと交じり合った唾液を飲み干していく。
「んふっん…んぐんぐ」
「あぅぅ…ぅぅぅっ」
頬を押さえられ、顎を上げた姿勢のまま年上の美女の激しい口付けに溺れる少年は、ただ目を見開いたまま時折体をピクピクと動かす以外は、その絡みつき蕩けるような口付けの虜になっていた。
もっとも動こうにも、もう一人の魅惑的な肢体と美貌の持ち主である彼の叔母さんが、しっかりと抱きついて放してくれないのだからどうしようもない。
「ふふふふ、正樹くん…どう、新しいお手伝いさんの具体は?お掃除にお洗濯、料理に…正樹くんの性欲処理までなんでもこなせるのよ?」
そう言いながら、少年に抱きつく冴子さんのしなやかな腕は、ズボンの盛り上がりの上を這い回り、服の上から果物の皮をむくように爪の先でカリカリと優しく掻き乱していた。
「あっ…あふぅ…いい…ですぅ…うぐぅ……っっ」
正樹は、頬を染め嬉しそうに目を細める冴子さんに返事を返そうとするが、その言葉のほとんどはスケベなお手伝いさんの艶やかな口腔内に飲み込まれ、かわりに桃色の吐息と蛭の様にねっとりと蠢く舌の愛撫を送り込まれていた。
くちゅ ちゅくっ ちゅるるっ ちゅ ちゅ
「んふ、んんっ…好きよ…あふぅ…坊やのお口の中、お姉さんが綺麗にお掃除したげるわ…んんっ」
長い睫を瞬かせる泪は、まるで発情した淫らなメス猫のように美しく淫らな美貌を何度も左右に傾け少しでも深く正樹の口の中を味わい口腔内を舐め回そうと、接吻と言う名の口の交わりに没頭していた。
「正樹くん、ほら、もっと顔を上げてあげて…そうよ、あん、汗が垂れてるわよ、んっ、ちゅ」
そして冴子さんも、エプロンからこぼれでている豊かなバストを惜しげもなく少年を抱き締める肉の枷として使用しながら、嬉しそうに滴り落ちる汗や唾液を顎先から舐め取って泪をサポートしている。
「泪さん…んんっ…冴子さん…あぅ…んぐぐぐっ」
「んんっ…いいわよ、坊や、ほらもっと私のお口の中に…んふぅ、美味しい」
「ちゅちゅ、んっ…正樹くんのお耳好きなの、あはっ…もう真っ赤にしちゃって、ふふふ、これならどうかしら…はむ」
くちゅ ちゅちゅちゅ くちゅ ちゅくっ
やがて台所には、二人の類まれな美女とその間でサンドイッチ状態で抱き締められ白く艶やかな肌に溺れる少年との、睦み会う音だけが主旋律となっていつまでも響き渡り続けていた。
誤字脱字指摘
6/16 JUM様 ミグ様 9/20 H2様 10/22 あき様
ありがとうございました。
6/16 JUM様 ミグ様 9/20 H2様 10/22 あき様
ありがとうございました。