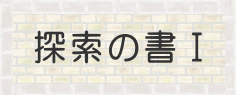
「凶王の迷宮」
そう呼ばれていたダンジョンがある。
はるか昔、古き神々の力が色濃く残る時代から存在していた魔の迷宮。
自らを「凶王」と名乗った魔王が創造した地下深く地獄まで伸びる悪の要塞。
その存在は、近隣の諸国を恐怖に陥れ、恐るべき混沌と殺戮を撒き散らす災悪の源とされていた。
勿論、人間達がそのダンジョンをただ黙って見ているわけがなかった。
幾つもの国の軍隊が、聖なる力をもった騎士達が、そして名うての冒険者達が、元凶たる凶王を倒すべくダンジョンに踏み込んでいき……
そして、だれ一人として帰って来なかった。
凶王が召還した無数の魔物、巧妙に張り巡らせた死の罠、そして難攻不落の迷路がいかなる英雄も退け続けていたのだ。
だが、聖なる剣や、研ぎすまれた槍、究極と呼ばれた神聖魔法でさえ倒せなかった凶王でさえ、時代の流れには勝てず、やがて訪れた古き神々の時代の終焉とともに、いつの間にか迷宮からその姿を消していた。
そして、光の女神達が統治する新しい時代の訪れと共に、かつて「凶王の迷宮」と呼ばれたそこには……
ただ、難攻不落のダンジョンだけが残されていた。
主のいないダンジョンの中に取り残されたのは、如何なる英雄も屈服させた死の罠と、遙か昔に呼び出され放置された魔物達。
「凶王の迷宮」
そう、ここは倒すべきボスキャラも居なければ、得られる栄光すらない、時代に取り残された場所。
最高難易度のモンスターとトラップだけが残る、世界最難関にしてもっとも無意味な、過疎のダンジョンなのであった。
「あぁん、暇あぁっー」
う〜〜ん、とベッドの上で背伸びをする女の子。
背格好は15、6歳ぐらいだろうか、緑色の不思議な色彩の髪の毛がさらっと流れ、その驚くほど整った美貌にかかっている。
貴族か王族の血をひいていると思わせる高貴な光を放つその肢体を惜しげもなくさらし、むっ〜とかわいらしく欠伸をしている。
だが、この緑の髪の美少女が王族の血をひいていない事は、誰が見ても一目瞭然だろう。
何故なら、そのしなやかに伸びる背中に、ぴょっこりとコウモリの様な黒い翼が生えているのだから。
その翼は間違いなく、彼女が人間ではなくモンスターであることを教えていた。
「ひまぁひまぁ、ひ〜〜〜まぁ」
そんな黒い翼を持つ健康的な美少女モンスターは、うにゅっと口をまげ、ベットの上でクロールするようにバタバタと手足を動かす。
すらりと伸びた腕はまるで白い陶磁器のように輝き、短めのスカートから伸びた脚は驚くほど長く、ちらちらと瑞々しい太腿の奥を覗かせていた。
「ひまぁなのぉ〜」
大きめのベットの上で、そんな可愛らしい女の子が、はしたない姿で転げまわっていると……
「うるさいよ、レン!暇なのはわかってるわ」
続きの隣の部屋から紫の長髪の美女が、ひょこっと顔を出す。
レンと呼ばれたベッドの上で転げまわる少女より三つ程年長だろうか、切れ長の瞳に、意志の強そうなトパーズ色の瞳、そして小ぶりの整った顔。
思わず叱られてみたいと思う男性が群れをなしそうな、きつめの美貌の持ち主だった。
その端整な顔にかかる薄い紫色の髪は、頬に沿って切り揃えられ、長く伸ばされた後ろ髪が背中の辺りで一つに束ねられリボンと共に揺れている。
ベッドの上で悶えていた緑髪の少女を睨む彼女は、だれが見ても涎を流しそうな完璧なスタイルの上から、エプロンをつけ、手には厚手の鍋つかみをはめた極めてアットホームな格好だった。
だが、そんな彼女も、人間ではなかった。
きゅっとくびれた腰のあたりから、長くしなやかな蝙蝠の羽が生え、まるでスカートのようにその魅惑的な太腿を覆っている。
「なによぉ、ラフィーネ姉さんだって無駄な事してんじゃん、料理なんて作ったって私達には食べられないのにさー」
暇々と言いながら転がっていた少女 レンは、ふんと可愛らしい鼻に皺をよせ、唐突に隣で膨らんでいるシーツの塊を蹴っ飛ばす。
「もう、ミルもいつまでも寝てないで起きなさいよ」
ゴロンっと丸まったシーツが転がると、そこからピンクの髪の毛の女の子が転がりでていた。
「うにゅぅ、痛いぁい、うわ゛〜〜ん゛」
ゴロゴロとシーツから転がりでたのは、髪と同じ色のピンクキャミを着た、抱き締めたくなるほどの小柄な可愛らしい女の子。
そして、その背中には、ぴょこぴょこと動く小さいながらりっぱなコウモリの翼。
「馬鹿レンがあたいを蹴った〜あぁ、蹴ったぁ〜」
グズグズとぐずるミルと呼ばれた女の子は、ツインテールに結わえられたピンク色の髪の毛をゆらし、自分に蹴りをかました緑髪のレンに果敢にも掴みかかる。
「なに!やるき、このぉ」
「むきぃ馬鹿レン〜」
二人の少女がベッドの上でもつれあい倒れこむと、お互い髪の毛をひっぱりあい、ゴロゴロと転がりだす。
レンの長い足がミルの小柄な身体をはさみつけ、負けじと小柄なミルもその尖った犬歯で、かぷりとレンの剥き出しの肩にかぶりつく。
「いたたた、かっ噛むんじゃないのッ、このぉ」
「ふがふがぁ、ふ゛ぁ、ふ゛えぇ〜ん゛」
ミルのほっぺがむにゅっと引きのばれ、みるみるうちに大きな瞳からぽろぽろと涙があふれだす。
「このこの、どうだ!」
「ばぁが〜〜、レンのばぁが〜」
バタバタと上下になりながら、さらに激しく転がり回る二人の少女。
「はぁ、もういつもいつも……やめなさいったら、二人とも」
エプロン姿のラフィーネと呼ばれた女性が呆れきった声をだすが、ベッドの上でくんずほぐれつの姉妹二人は一向にやめる気配はなく、むしろさらに白熱していく。
「あらら、また喧嘩してるのね、おやめなさい、おちびちゃん達」
その時、おっとりとした声とともに、四人目の人物、艶やかな黒髪の目の覚めるような美女が部屋の中に姿を現していた。
深い闇の様に潤む黒い瞳に、肉感的に濡れるしっとりとした真っ赤な唇。
豪奢な顔立ちと、それに負けず劣らずの見目麗しい白く透き通る肌を持つ優雅なボディライン。
大きく開いたドレスの胸元からは、重量感たっぷりに突きだされたバストの谷間が披露され、驚くほど高い腰の位置まで深く入ったスリットからは麗しい白い太腿がチラチラと覗いている。
まさに完成され成熟した大人の女にしかだすことのできない、匂い立つほど濃厚な誘惑のフェロモンを漂わせる極上の美女だった。
そして、そんなフェロモン美女の、体の線を強調した漆黒のドレスの背中からは、ベッドの上で絡み合う二人の少女よりも大きく、しなやかなで、ビロードの生地のように滑らかな蝙蝠の羽がマントのように生えていた。
「ひぐぅっ、レイラお姉ちゃん、聞いてよ、聞いてよぉ、馬鹿レンったらね、あたいのこと蹴るんだよ、ひどいよぉ」
「なによ、あんたがグースカ寝てるのが悪いんじゃない」
「あらあら、おやめなさい二人とも、あんまり悪さしてると……姉さん、怒っちゃうわよ」
おっとりとした声でレイラと呼ばれた妖艶な美女がにこやかに微笑む。
見た目は優しげな女神そのものだが、その奥に隠された真実を知るレンとミルは、ひっと息を飲み、しぶしぶといった感じでお互い離れる。
「ふふふ、それでいいわ、無駄にお腹を空かすことないでしょ」
「……は〜い」
「それはそうだけどさ、でも、もう300年も人間様なんてこないじゃない!あぁもうお腹すいた〜〜」
レンは可愛らしい小鼻をすんすんと鳴らしてむくれると、ベットの上にへたり込み滑らかなお腹の辺りを撫で回す。
「確かに、そうねぇ、最後に人間様を頂いたのは何時だったかしらぁ」
魔性の魅力を持つレイラは、ベッドの上で駄々をこねる少女達をじっと見つめ、やがてゆっくりと指先を動かし肉厚の唇にそっとつけると、小首をかしげて遙か昔を思い出していた。
そう、まだ、この「凶王の迷宮」が華やかだったあの頃を……
レイラ達は、卓越した美貌と貪欲で淫蕩な性格で知られる、サッキュバスと呼ばれるモンスターの四姉妹だった。
彼女達が住むのは、「凶王の迷宮」でも最下層に近い一室。
いや正確には住んでいると言うより、囚われていると言ったほうが正解だろう。
はるか昔、凶王によってダンジョン内に召還された彼女達は、ここで迷宮に入り込む人間達を殺し、ダンジョンを守るように言いつけられていた。
簡単に言えば生きたトラップのような物だ。
最初の頃は、もうこの世の天国だった。
凶王を殺すためダンジョンに毎日山のように人間達がやってきて、食べるモノに困る日なんて一日だってなかった。
しかし、何時の頃か凶王が去り、ダンジョンに人間が訪れなくなっていた。
だが、彼女達を含め召還されたモンスター達はダンジョンに縛れたまま解き放たれることなく、この誰もこない侘しいダンジョンの奥で侵入者を待ち続けなければならなかったのだ。
最初の100年は、時々残された財宝の噂を聞いて入り込んだ冒険者もいたが、今ではもうそれさえも皆無。
たまに、盗賊や旅人が間違えてダンジョンの中に迷い込むことがあるらしいのだが、迷宮の最深部にいる彼女達の部屋に来る前に、たいてい入り口近くに配備された他の飢えたモンスター達の餌食になっていた。
そのためサッキュバスの姉妹の飢えが満たされることは、この300年一度たりと無かったのだ。
そう300年もの長きにわたり一度も……
「ほんと昔はよかったわぁ、逞しい人間様のアレを両手にもって舐めまわしたものよ……はぁ、もう一度でいいから人間様を味わってみたいわねぇ」
レイラはそう言うと、頬を染め懐かしそうに瞳を潤ませ、クネクネとその身を身悶えさせる。
「大丈夫よ姉さん、信じてればまた人間様が来てくれるかもしれないじゃない」
次女のラフィーネが、鍋つかみに包まれた手にぱんっと拳を叩きつける。
「うん、だよね、人間様のために私達だっていろいろ用意してるんだもん」
長女のレイラを勇気付けるように、緑髪のレンもこの300年ぎゅるぎゅる鳴り続けているお腹をそっと押さえて言葉を紡ぐ。
「うん、いつか人間サマ、また来てくれるよぉ、ねぇそうだよねぇ、ねぇ」
そんな姉達の様子に末の妹のミルが、幼い瞳に涙をいっぱいにため、枕元においてあったシャレコウベをひっぱりだし、まるで人形を可愛がるように優しく撫で話しかけていた。
「ええぇ、そうね、きっと人間様は来てくださるわ……そう信じましょう」
飢えに耐えながらそれでもへこたれない、けなげな妹達を見ながら、レイラはウェーブのかかった黒い髪を、指先ではらい、そっと目じりにたまった涙をぬぐう。
そして、大切な妹達に、絵になるほどの魅惑的な美しさで気丈にもにっこりと微笑むのだった。
「姉さん」「レイラ姉さん」「お姉ちゃん」
ひっしと抱き締めあう四姉妹。
このダンジョンに召還されてから幾星霜、飢餓にもめげず姉妹仲良く手を取り合って生き抜いてきたサッキュバス達の姉妹愛がそこにはあった。
「きっと、きっと人間様がまた来てくださるわ」
ところで、この300年の間、サッキュバス四姉妹達は、その美しさも魅惑的なスタイルも、そして麗しい姉妹愛も変わることなく生き続けてきた。
が、しかし、その中で変化した物が一つだけあった。
それは彼女達の獲物であり食料でもある人間についての考え方だった。
そう、あまりにも長く餌である人間を待ち続ける彼女達の中で、もう人間は「様」付けで呼ばれる、念願のもう一度でいいから巡り合いたい至高のご馳走になっていたのだ。
なにせ最後に人間の精液を啜りとったのは、もう300年前、味さえ思い出せないほど遥か昔のことなのだ。
その時は、まだ人間がこんなにも来なくなるとは思っていなかったので、あっさりと精液をすすりとり、カラカラになるまで搾りつくし殺してしまったのだ。
ちなみにその時の人間の頭蓋骨は、今、四女のミルが大事に抱きかかえているシャレコウベで、何度も撫で回しているうちに角がとれツルツルに磨耗してしまっている。
そんなこんなで、その最後のご馳走をあっさりと吸い尽くしてしまったことを悔やんでも悔やみきれない四姉妹は、人間様を殺すなんてなんてもったいない、人間様は捕まえて生かさず殺さず大切に味わないと……っというモンスターにあるまじき信念に変化していたのだった。
「さてっと、料理の練習の続きしないとね」
一通り、毎日の日課のような美しい姉妹の抱擁が済むと、次女のラフィーネは、エプロンの端をひらりと翻し、隣の部屋に入っていく。
そこにはダンジョンの部屋の一部を改良して台所が設けられており、鍋やら釜やらが置かれ、グツグツとスープが煮立っていた。
「なかなか上手にできたわ、これで人間様さえ来てくれれば、絶対素敵なおもてなしができるのに……」
凛とした美貌のラフィーネは背中に垂らした紫色の髪の毛先をいじりながら、つい癖になった独り言をつぶやいてしまう。
サッキュバスである彼女達にとって、食事は人間の欲望を啜り取ることだけであり、目の前にある料理はどれも食べることすらできない、ただのオブジェに過ぎないモノだった。
それでも彼女が一生懸命練習を重ね人間用の料理作り続けているのは、まだ見ぬ人間様が来た時のためだった。
何せ人間というのは、食事を食べないと空腹で死んでしまうらしいのだ。
それどころか、美味しい料理を食べさせると元気になっていつも以上にたっぷり精液を吐き出すらしい。
そんな話を、噂好きのニンフ達から聞いたラフィーネは、もう200年以上こうして報われないお料理修業を続けてきたのだ。
「くよくよしてても始まらないわね、よし!人間様のためにもっと美味しい料理の訓練をしないと」
きゅっと唇をかみ締めると、ラフィーネはお玉を手にとってボロボロにすりきれた「お料理百科」のページをパラパラとめるく。
「ふむふむ、精力のつく料理は……」
一方、緑髪の三女のレンは「はうぅ〜」と大きな欠伸をして、またゴロンとベッドに横になっていた。
ちらりと視線を動かすと、末っ子のミルは相変わらず人間のシャレコウベを後生大事に抱え込み、いい子いい子と撫で回している。
長女のレイラは大きな鏡台の前でいつか来る人間のために扇情的なポーズの練習に余念がないようだった。
この300年、毎日毎日見飽きた光景だった。
「ほんと、ひまぁ」
何せ彼女たちはダンジョンの最下層に近い部屋に固定用モンスターとして召還された身、ダンジョンから出ることどころか、この部屋から一歩も外に出ることすらできないのだ。
だらーっとだらけた姿勢のレンは、白磁のような腕を伸ばし、ベッドの脇に置かれた「人間の正しい飼育方法」と書かれた本を手に取るとペラペラとめくりだす。
この本は、彼女達の上の階に住んでいる下半身が蛇のモンスター、ラミアによって書かれた「凶王の迷宮」に住むモンスター達の中で大ベストセラーの一冊だった。
なんでも著者のラミアは、幸運な事に迷い込んだ盗賊の少年を捕まえ、大切に育て毎日新鮮な精液にありついているのだそうだ。
裏表紙には、幸せそうに笑うラミアと、彼女の長い蛇の下半身に巻きつかれ、チロチロと伸びた舌で頬を舐められている人間の少年の写真がついている。
来月には「人間との正しい繁殖方法」の本も出版されるらしい。
「はぁ、人間様ぁ、いいなぁ、私も……」
レンは裏表紙の写真の人間をみつめながら、脳内で隣にいるラミアを自分と置き換えてみる。
「はぅ」
それだけで、レンのスカートの内側の秘肉が甘い液体を分泌し、体中が火照りだしてきていた。
こんな健康そうな人間をずぅ〜と飼って、毎日、新鮮な精液をしぼりとれたら……
300年の間、飢え続けたサッキュバスの彼女にとってそれはもう最高の時間になるだろう。
「あぁ、人間様の他に何もいらないんだけどなぁ……んっ」
いつのまにか、程よくふくらんだ形のいい胸の先端がきゅっと尖り、日の光を浴びていない真っ白な太腿がもぞもぞとじれたように動き出してしまっていた。
「もう我慢出来ないよぉ」
レンは鼻にかかった声でそう言うと、本を持つのと逆の手を、そっと枕の下に潜りこませる。
そこには半固形状のスライムを加工してつくったプルプルとふるえるレンの秘蔵のスライムバイブが……
「あれ?ないない?」
いつもこの本の少年の写真を見ながら、自分を慰めるのに使っていた道具がなくなっている。
その時、
「はぁん、んっ……いいわぁ、ああっん」
鏡台前でポーズをとっていたはずの長姉のレイラが艶っぽい声をあげ、その肉感的で抜群のスタイルをくねらせていた。
「あ!ちょっとレイラ姉さん、あたしのスライム使わないでよね」
姉の黒いドレスのスリットからむっちりとつきだした太腿の間で見え隠れして、ねちょねちょと蠢いているのは間違いなくレンの秘蔵の品だった。
「あぁん……ごっごめんねレン、ねっ…姉さん、我慢できなくてぇ…あんっ」
妖艶を絵に書いたような陶酔した表情で、レイラは黒髪を頬に張り付かせながら悩ましげに喘いでいる。
その長く見事な脚の付け根の辺りから、ぐちゅぐちゅと淫らな音が響き渡り、それにあわせて突き出された水餅の様な豊満なバストがたぷんたぷんと柔らかそうに揺れていた。
「レイラ姉さんもこの前、同じスライムバイブ買ったでしょ?」
レンはベッドの上で胡坐をかくと、口を尖らせる。
「あぁ、あれ?あれね…その…姉さん、ちょっと使いすぎたみたいで…スライムちゃん動かなく…ふぁぁ……あんっ」
鏡台に両手をついたレイラはウェーブのかかった黒髪をゆらし、腰をくねらせビクビクと背筋を痙攣させ色っぽく喘いでいる。
それにあわせて四姉妹の中でも最も大きく艶やかで肌触りの良い蝙蝠の羽が、ふわっと気持ちよさそうに広がっていく。
「ええぇ!もう駄目にしちゃったの?買ったばかりじゃない」
レンは緑宝石のような輝きを放つ瞳を見開いて、姉妹ながら思わず見とれてしまう姉の淫蕩な姿に大声をあげる。
「うん、ホントだよ、ほら、これお姉ちゃんの」
その声に答えたのは、胸元にシャレコウベを抱いた妹のミルだった。
ベッドの横に置かれた屑篭から、なにやら干からびた寒天のようなものを取り出し、レンの目の前に突きつける。
「げげっ、ほっ…本当だ…もう、しおしおになってるぅ」
それはレイラが、レンと一緒に買ったはずのスライムバイブだった。
すでに素材のスライムは昇天してしまったのだろう、精気も枯れ果てた見るも無残な姿になっていた。
「こら、レンちゃん、女の子がそんな言葉使いしちゃ…だめ、だめよ…あんっ、きっ…気持ちいい…んあぁ…もっと…中をぐちゅぐちゅして…あぁん」
濡れた舌をだして妖艶に喘ぐレイラは、まったく悪びれていないのか、それとも天然なのか、自らの熱い肉膣の中で蠢く妹のスライムをきゅっと締め付けると、むっちりとしたお尻をピクピクと震わせている。
「あの調子じゃ、レンのスライム半日ももたないねぇ…えへへ、ごしゅうしょうしょさまぁ」
ミルはピンク色のツインテールをゆらし意地悪そうな笑顔をつくると、ベッドの上でボーゼンとしているレンに笑いかける。
「そっ…そんなぁ、あれ、お気にだったのにぃ…あたしのこの疼きはどうすればいいのよぉ」
涙目になったレンはばふっと枕に顔をうずめると、バタバタと脚を動かす。
「もう最悪っ」
ミルの「にひひ」っという笑い声と、レイラの「あんあんっ」という喘ぎ声を聞きながらレンがよよよっとわが身の不幸を嘆いていると……
ドンドンドン
おもむろにサッキュバス達の住む部屋のドアがノックされ、野太い声が聞こえてくる。
「スイマセン、お届け物デス」
「………」
長女のレイラはサッキュバスらしく貪欲にスライムの与える快感を貪るのに夢中で反応してない。
さらに数回叩きつけるように鳴り響くドアと、それに続けて野太い声が響き渡る。
「スイマセン、お届け物デス」
「……」
次女のフィーネは鼻歌交じりに厨房でクッキングにいそしんでるし、四女のミルはもともと出る気がないのかそっぽを向いてシャレコウベ相手におままごとの最中だ。
「スイマセン、お届け物デス」
野太い声は馬鹿の一つ覚えみたいに、同じ台詞を繰り返している。
レンは悲劇の主人公をきどってベッドに倒れこんでいたが、だれも反応しないのでしぶしぶ起き上がっていた。
「…は〜い」
もう何よ、と口を尖らせながらポリポリと頭をかき、ドアまで歩いていく。
部屋のドアには、昔は毒針やら石化の罠やらの非道なトラップがついていたが、人間様にケガがあっては大変と今ははずされて久しく、簡単な鍵がかかっているだけだった。
「はいはい、ご苦労様です」
ガチャリとレンが無用心にドアを開けると、そこにはダンジョンの廊下の天井に頭がつきそうなほど巨大なトロールが一匹、鼻息もフゴフゴさせてぼけっと立っていた。
みるからに愚鈍そうな顔に、醜悪な肢体。
力だけが取り柄のモンスターとして召還されたこのダンジョンの住人の一人だ。
「あの、こで、お届け物デス」
そう言うと、トロールには小さな、しかしレンには一抱えもある包みをどさっと渡す。
「うわっと…また沢山ね、よいしょっと…はい、これお代よ」
レンは受け取った包みをテーブルまで運ぶと、かわりに部屋の棚に並べてあったエリクサーを一瓶トロールに手渡す。
「どっも、ども」
トロールは渡された小瓶を大切そうにしまいこんでいる。
「それから…これは、サービスね」
レンはトロールから見えないようにちらっと嫌そうな表情を浮かべるが、すぐににっこり微笑むと、その巨体にしなやかな肢体を押しける。
「ウヒ」
トロールの腐ったチーズケーキのような匂いを発するデコボコの顔が、真っ赤に高揚し、下半身を覆う毛皮が巨大な一物にむくむくと押し上げられていく。
「ふふふ、これからも、よろしくね」
レンは、どんな男でも手玉にとるサッキュバス特有の蕩けるような微笑を浮かべながら、トロールの醜悪な顔に、瑞々しい唇をそっと添える。
それと同時に、犬歯がちらりと覗く年頃の美少女の唇の間から、甘い吐息とともにピンク色のブレスが吐き出される。
「ウウゥッ」
美しい少女に抱きつかれたトロールは、顔の筋肉をだらしなく弛緩させ、気持ちよさそうな呻き声をあげていた。
「いっちゃっていいのよ」
淫らな笑みを浮かべるサッキュバスの白い指先が、毛皮に包まれもっこりと盛り上がった下半身をさっと一撫する。
「アウゥウゥ、イググゥ」
たったそれだけで、トロールの巨体がビクビクビクとふるえ、下半身を覆う毛皮の奥でいきりたっていた一物から、精液を噴水の様に迸らせていた。
「えっ…エガッタぁ…アアァ」
トロンっと目じりをさえげて、はぁはぁと荒い息を吐くトロール。
夢見心地なのだろう、足元も定まらず今にも腰が抜けてしまいそうになっている。
「そう、よかったわ、またよろしくね」
レンは手早くトロールの巨体から離れると、毛皮からボタボタと垂れ落ちている精液に極力触れないように慎重に地面に降り立つ。
「まっ、また御用があればいつもでオデに言ってグデ」
トロールはゲヘゲヘっと笑いながらどんっと胸を叩いている。
「ええ、そうするわ、じゃあね」
レンは胸の谷間を寄せるサッキュバス秘伝の悩殺ポーズでにっこりと微笑み、素早くドアをバタンと閉めていた。
「たくもぉ、手にかかっちゃったじゃないのぉ…うわぁ、臭いがついたぁ」
ドアが閉まるやいないや、レンはげんなりとした様子で、タオルを取り出しゴシゴシとふき取っていく。
性欲と理性を併せ持つ人間ならいざしらず、性欲しかない同じ闇の眷属のトロールの精液はサッキュバスにとって腹の足しにもならないのだ。
だからといって、無下にできない理由があった、それは……
「あらあら、見てこれ、いい肌触り、これでシーツを新調しましょう、きっと人間様喜んでくださるわ」
長女のレイラが届いた包みをあけると、そこから光り輝くローブを取り出し広げてみせる。
「この薬草、新鮮でいいな、うん、おいしいサラダが作れそうだ」
いつのまにか厨房から戻ってきていた次女のラフィーネが、薬草やらスパイスなんかを選り分けている。
「ねぇねぇ、この宝石もいいよ、ほら、ぴか〜って光って、きっと人間様も気に入るよ」
四女のミルは光の魔法のかかった宝石を丹念に並べると、宝石箱にしまっている。
トロールの宅配便が届けた包みの中には、この凶王の迷宮の特産品である魔法のアイテムが山のように詰まっていた。
彼女達のような高レベルのモンスターは各階や部屋毎に召還され、勝手に移動することもままならないが、ワンダリングモンスターとして召還されたトロールやゴブリンなど一部のモンスターは、自由に迷宮内をさ迷うことが許されていた。
迷宮が賑やかだった頃は、雑魚として狩られるだけだった彼らだったが、今では迷宮内の経済活動の主軸として欠かせない存在となっていたのだ。
ダンジョンのそこかしこで無限といってよいほど湧き出るアイテムを収集して回れるのは、自由に歩きまわれる彼らワンダリングモンスターだけであり、その特性を活かして各階、各部屋を繋ぐ物流ネットワークとして重宝されている。
今ではゴブリン運輸とトロール大型便、ジャイアントバット特急運送、それにフロストジャイアントの冷凍宅配便などがしのぎをけずっているのが現状だった。
そして、サッキュバスの四姉妹もご多分に漏れずワンダリングモンスター達の運送ネットワークのお世話になっていた。
幸運にも彼女達の部屋に置かれていた宝箱の中には、高い価値と効果のある様々なエリクサーが配置されていたらしく、定期的に湧き出すその秘薬を元手にダンジョン内の色々な物を集めていた。
勿論、その目的はいつか来る人間様のために必要だと思ったからだった。
大ベストセラー「正しい人間の飼育方法」に、人間は日の光がなければ弱ってしまうと書かれていれば、太陽の輝きをはなつ魔法の輝石を集め、人間はすぐ年をとって死んでしまうと聞けば若返りのポーションを集めたりもしていた。
他にも派遣メイド業が大当たりしているフェアリー達から裁縫を習い、最高級の魔法のローブを仕立て直しベットのシーツを作ったりと、人間が喜びそうな環境を整えていたのだ。
もっともそのせいで、ダンジョン内に入り込んだ数少ない冒険者達が手に入るアイテムがほとんどなく、余計に難攻不落の最高難易度の迷宮として寂れてしまっていることに気がついてはいなかったのだが…
そんな悪循環に気がつかないサッキュバス達は、いつか来ると信じている人間様のために今日もせっせっと歓迎の準備に余念がなかったのだ。
「はぁぁ、もう、いっつもあたしにトロールの相手をさせるんだもん、やんなっちゃう」
レンは手をよく拭くと、口やかましく新しいアイテムを鑑定している姉妹達をよそに、包みの下に押し込まれていた新聞をばさっと広げる。
「ダンジョン・ニュース」と銘打たれたそれは、愚痴やウンチクが大好きなノーム達が暇に任せて発行している凶王の迷宮内専用のミニコミ紙だった。
「なんか面白い事ないのかなぁ……あっ!ほら23階のハーピーさんとこ体力回復の泉を部屋に引いたらしいよ」
レンは今週のトピックのページを机に広げる。
「あら、ホント、何々…人間様も喜ぶくつろげる癒しのスペース作りだって、考えたわね、ねぇレイラ姉さん、うちも作らない?」
妹の指し示す紙面を読んだラフィーネが、きらきらと輝くローブに頬をあて幸せそうに夢想している長女に意見する。
「う〜ん、でもねぇ、この前ヒーリング効果のある石版で床をフローリングにしたばかりでしょ?それに姉さんは泉よりも温泉の方がいいわぁ〜、ほら最下層にマグマ溜まりがあるでしょ、そこからお湯をひいてぇ…人間様としっぽりと…」
ぽっと頬をそめて憂いを帯びた瞳を潤ませる長女のレイラ。
「はい、は〜い、あたいは毒の沼がいい〜、ピリピリしててきっと人間サマも気に入るよぉ」
テーブルに載せられた新聞をうんうんと悩みながらやっと読み終えたミルが元気良く話しに加わってくる。
「馬鹿ね、人間様は毒には弱…あっ!!あああああぁぁ!」
その時、レンがあんぐりと口を開いてすっとんきょうな声をあげる。
「なに?どうしたの?…あっ!」
毒の沼はやめたほうがっと引きつった笑いをしていた次女のラフィーネも、神秘的な紫水晶のような瞳を見開いてレンと同様紙面のある一点をみつめたまま唐突に静止する。
「あらあら、二人ともどうしたの?ラミアさんがまたお子さんでも産んだのかし…ら…」
おっとりとしたレイラの口調が、まるで軟着陸する綿毛の様にゆっくりと止まっていく。
三色の異なった輝きをはなつ美しいサッキュバス達の視線の先は、ガリ版印刷でつくられたダンジョン・ニュース紙の一面にデカデカと書かれた文面に釘付けになっていた。
「どしたのぉ?みんな固まって……むぅ…えっと……ダンジョンないに…久しぶりのシンニュウシャが…あり…モクゲキしょ…ショウゲンでは…人間の…一団の模様って、えええええ!人間サマが来たのぉぉお?」
ミルが頭を悩ませながらなんとか見出しを読み終え大絶叫をあげるのと同時に、時を忘れて硬直していた他の姉妹達も歓声をあげる。
「嘘ぉ、信じられない、50人以上だって、人間様が50人も!!うひゃぁ、ねぇねぇ、しかも一晩で地下6階まで突破だって、きゃぁ、がんばって人間様ぁぁ、愛してるぅ」
レンは口元に手をやってピョンピョンと飛び跳ねながら大声をあげる。
その度に、ミニのスカートが捲りあがり健康的な太腿と下着が見えているが、今は気にしてはいられない。
「でもぉ、ここまで来てくださるかしら、ほら、前は15階のマンティコアの方々に全滅……」
レイラが、はうっと悩ましくため息をつきながら、ほっそりとした見事な腰をくねらせる。
「レイラ姉さん、縁起でもないこと言っちゃ駄目よ、それにほら見て、人間様の一団の隊長は真っ白な鎧を着込んだ勇猛な戦士だって書いてあるわよ」
ラフィーネが指差すそこには、印刷は荒いが特派員のビホルダーが念写した写真がついていた。
「ほんとだ、すご〜い〜」
そこにはローブをまとった魔法使いやフルプレートを着込んだ騎士達をひきつれ、抜き身の剣を掲げて歩く豪奢な鎧姿の人物が映っている。
「まぁ凛々しいお姿ですこと、きっと英雄の血をひいてるのねぇ…あぁこんな殿方の精液を舐めしゃぶれるんだったらもう死んでもいいわぁ」
長女のレイラはうっとりとした瞳で紙面をみつめ、豊満な胸を抱き締めるように身悶えだす。
「姉さん、よだれ、よだれ」
「はっ…やだ、わたしったら♪」
何はともあれサッキュバス四姉妹は、心の底から興奮と期待に打ち震え、どうか無事に人間様がこのダンジョンの最下層にある自分達の部屋まで来てくれますようにと邪神に祈るのだった。
それから3日後。
いつもは静かな凶王の迷宮は、この300年来の活気に満ち溢れていた。
月例のサバトや黒ミサどころか、年に一度の凶王聖誕祭も真っ青の大盛り上がりだった。
ワンダリングモンスター達はダンジョンに入り込んだご馳走に群がるように我先にと殺到し、移動できない固定モンスター達もあらん限りの手段を用いて、てぐすね引いて人間達を待ちかまえる。
ダンジョンのあちこちには、この騒ぎに便乗しようとお金に汚いどぶドワーフ達が出店をかまえ、いたるところに「回復ポーションありマス」やら「ご休憩はこちらの部屋で」等の文字が書かれた極彩色の看板が立ち並んでいた。
そんなお祭り気分で盛り上がる迷宮の一角、最下層付近のサッキュバスが暮らす部屋でも、ご多分に漏れず人間様ご一行を迎える準備がちゃくちゃくと進んでいた。
「号外、号外っ」
猛スピードでダンジョン内を飛び回るジャイアントバットにまたがったグレムリンの配達員が、ミルが綺麗な造花で彩ったサッキュバス家の戸口の隙間に号外紙を放り込んで飛び去っていく。
「ねぇねぇ、ラフィーネ姉さん、号外が来たよ、号外」
戸口の前で人間様にと宝石を使って首輪を作っていたレンは、急いでダンジョン・ニュースの号外をひっぱりだすと忙しなく居間へと駆け出し、テーブルに広げる。
もう今日だけで6回目の号外の発行だ。
「すごいわ、もう20階を突破よ、これはもしかしたら、もしかするわね」
料理の手を休めて、ラフィーネがスリッパをパタパタ言わせながらテーブルに座る。
この数日、サッキュバス四姉妹の期待はいやがうえにも高まっていた。
それもそのはず、凶王の迷宮が最盛期の時でさえ、普通の冒険者なら10階程度で全滅していたこのダンジョンを、白い鎧の戦士に率いられた一団はもう20階まで突破していたのだ。
地上に近い上方の階層にいる比較的強力なモンスター達の大半は、すでに人間をくわえ込んで飼育しており、この一大イベントに参加していない者も多かったのが幸いしているかもれない。
それでも、ダンジョンに配置されていたはずの魔法の品々や回復の場所などは、モンスター達によって勝手に移動させられており、その中で雲霞の如く押し寄せるワンダリングモンスター達を相手にしての20階突破は快挙といえるだろう。
…と言うのがイモータルキングにして「ダンジョン・ニュース」編集長の博識なリッチの意見だった。
しかしながら、一般の読者、もといモンスターにとって大事な事は……
「あぁ…また一人やられちゃったんだって…ううぅぅ」
レンは「20階突破」の見出しの下にかかれた「スキュラの少女、大活躍」の記事を読んで、緑色の瞳一杯に涙をためる。
「ほんとねぇ、10階を超えた頃からどんどん減ってるわ」
そっと黒いレースのハンカチで目元を押さえながら、レイラが鼻声を出して悲しげに呟く。
その潤んだ瞳の先には、嬉しそうにピースサインをするスキュラの年若い少女と、彼女の下半身から生えた蛸のような沢山の触手に体中を絡みつかれ捕獲された騎士の青年の白黒写真がデカデカと載っている。
「…ええと…スキュラのミストリアさんは、部屋に迷い込んだ騎士の青年(推定21才)をお得意の触手攻撃で見事ゲット、「こんな素敵な人間様を手に入れられるなんて幸せです、お母さんとお姉ちゃんと3人で仲良く分け合って可愛がっていきたいと思います」と本誌記者に元気に答えると、人間の青年を大事に抱え幸せそうに笑顔を振りまき去っていった……っだって、いいなぁ」
レンはそう言うと「はうぅ」っとため息をこぼして、未練がましく写真の中で泣き笑いのような表情で蛸足に絡みつかれている青年騎士を指先で撫で回す。
「もうこれで残り20人もいないよぉ〜、あうあぅ」
テーブルに顎先をのっけたミルは、指を咥えて目の幅で涙をぽろぽろ零す。
それと同時に、彼女の小さなお腹もきゅ〜っと鳴っていた。
「そうねぇ、最初は50人以上いらしたのに…はぁ…こんな最下層に召還された凶王様を恨みますわぁ」
長女のレイラも控えめにお腹を鳴らしながら、うるうると潤んだ瞳でレースのハンカチをそっとかみ締める。
「でもさ、まだ、殺さなかっただけいいじゃない、もしかしたらスキュラの所から逃げ出せるかもしれないし、ね?」
このご時世、捕らえた人間を逃がすような大馬鹿はいないのはわかりきっていたが、それでもラフィーネは姉妹達を元気付けようと声を張りあげる。
今頃、この件の青年騎士は300年以上飢えに飢えたスキュラの母娘達によって精気を搾り取られ続けているのだろう。
「だよね、あの馬鹿オーガどもよりずっとマシよね」
レンも頷くと、嫌なことを思い出したといわんばかりに、秀逸な眉をひそめ、こぼれでた涙をさっとふき取る。
先日、愚鈍なことで知られるモンスターのオーガが群れを成して人間達を襲い、その際貴重な人間の騎士をその場で殺して、あろうことか死体を細切れにして捨てしまったのだ。
レンもミルもこの事件には目を真っ赤にする程泣き続け、ラフィールも怒りをおさえるために台所で鍋の底を一晩中磨いていた。
そして、長女のレイラは見ず知らずの人間のために、喪服を纏うと心から祈りをささげ冥福を祈ったのだった。
人間を襲うのがモンスターの性とはいえ、このダンジョンでは絶滅危惧種の人間を食べることもなく、ただ殺して悪戯半分に捨てた行為は、モンスターとしてのモラルにかけるとしてダンジョン内でも物議をかもしだしていた。
特にダンジョン開闢以来、一番奥深くで待機し続け出番がまだ一度も無い女悪魔のバルログ女爵は文字通り烈火のごとく怒り狂い、件のオーガ達を呼び出し炎のムチであたりかまわずシバキまくったらしい。
なんでも、殺された騎士が、長い間、男日照りで飢えていたバルログ女爵のハートにクリティカルだったらしく、彼が来るのを地獄の業火を轟々と燃やして待っていた矢先の事件だったのだ。
噂では、禁断のネクロマンシーを使い死んだ青年を蘇生させ、今は怒りもおさまり寝室に騎士と二人でこもりきりだとか。
「そうね、さぁ、みんな泣くのはやめて祈りましょう、どうか人間様が無事にこの階層に来られるように」
「そうね、姉さん」「…うん」「は〜い」
レイラがそう言うと、姉妹たちは銘々返事し、そっとテーブルの上で両手を組むと、彼女達の信仰する邪神に祈りを捧げるのだった。
「どうか人間様がつつがなく無事にこの部屋に来てくださりますように…イヤアヤハストゥール、ウルウング……」
もっとも祈りをささげるその邪神は災厄と呪詛を司る神様なので、効力の方は妖しいが……
そんなこんなで、凶王の迷宮は上へ下への大騒ぎな日々が続いていたのだ。
さらに5日後。
この世界でも最高難易度を誇るダンジョン、凶王の迷宮に久しぶりに訪れた人間の一団は残すところたった数人となっていた。
「ダークエルフの女傑一族、3人の魔法使いを捕虜に」やら「ウィンデーネの誘惑魔法で騎士陥落」とか「ケルベロスお手柄だワン」などの記事とともに、次々に人間の一団はその数を減らしていた。
それでも白い鎧を着た隊長らしき若い戦士を筆頭に、人間たちはなんと40階を超え、今までになくダンジョンの最深部近くまで到達していたのだ。
これには「ダンジョン・ニュース」紙のリッチ編集長も異例の英雄宣言をだし、エンシェントドラゴンが主催する権威あるブックメーカーのオッズも大荒れになっているらしかった。
「姉さん、新しい号外きたよぉ」
戸口の前で新聞が届くのを朝からジッ〜と待ち続けていたレンは、特急配達係のグレムリンから号外を受け取ると、いつものように一目散にテーブルに走りより広げる。
「見て見て、もう45階だって、信じらんないぃ、この2つ上だよ、ああぁん、もう人間様の足音が聞こえるような気がするぅ」
興奮のあまりクラクラと失神しそうになるのをこらえながら、レンは夢見る乙女のようにその可愛らしい美貌を染め黄色い声をあげる。
「でもほら、見て、もう残り2人に減ってるわ、他の人間様は、アラクネの蜘蛛の糸と、インプの群れに捕まったって書いてある」
ラフィーネの指差した先には、満足そうに舌なめずりをする蜘蛛の脚をもつ妖艶な美女が、屈強な戦士の喉もとに舌を悩めかしく這わせている写真があった。
さらに、その下には神官戦士らしき少年が、無数の小さな女悪魔にもみくちゃにされながらダンジョンの奥に連れて行かれる光景が添付されていた。
「しょ…しょんなぁぁ」
残るは、白い鎧のリーダー格の人物と、彼の側近らしき騎士だけだ。
あと2階下ればこの部屋のある階層に着くとは言え、ここはダンジョンの最下層付近、強力なモンスターが履いて捨てるほどいるのだ。
そしてどのモンスター達も自分達と同様に、ダンジョン・ニュースの号外を読んで千載一遇のチャンスとばかりに目を爛々と輝かせて待っているのは間違いない。
「最低でも、堕天使のセラフさん達の部屋を通らないとここには来れないわね」
ラフィーネはもうプロ級にまで達した料理の腕前でつくった、焼きたてのシシカバブの串を片手に持ちながら、クールな美貌をひそめる。
これは結構大問題だった。
堕天使セラフ達の部屋はちょうど上の階から階段をおりたベストポジションにあり、普通なら避けては通れない場所なのだ。
しかもその部屋の中は、欲望に忠実で見目麗しく強力な力を持つ堕天使達が八枚の羽を広げて待ち構えているのだ。
セラフ達もこのダンジョンの他のモンスター達同様、飢えに飢えていた。
なにせこの300年、堕落させる相手の人間が一人も現れていないのだ。
きっと、あの光り輝く柔らかな羽に包みこんで、未来永劫甘く心地よい言葉を囁きつつ、欲望の限りを人間に尽くさせて堕落させるためならなんだってするだろう。
そんな甘美で肉欲に満ちた堕天使達の誘惑に抵抗できる人間が少ないのは、同じ誘惑のプロであるサッキュバス達にはよくわかっていた。
「あうぅ、もう、もう少しなのにぃ、がんばって、私達の人間様ぁぁ」
レンはぐすぐすと小鼻をな鳴らす。
「そうだね、ここまで来てくれたんだ、あとひとふんばり、がんばれ!人間様」
ラフィーネもレンに同調すると、お互いぎゅっと拳をにぎりしめ「えいえいおー」と声をあげる。
「ふふふ、でもねぇ、こんな近くまで来ていただけただけでも幸せに思わないといけないわぁ、レンちゃん、ラフィーネ」
そんな妹達の期待に釘をさすレイラだったが、露出度の高いお気に入りの黒のドレス姿に、どんな男性でもイチコロで虜にできる魔界一の香水を振り掛けている気合の入れようは、実は一番人間の訪問を期待しているようだった。
そんな言動不一致の姉の様子をジトーっとした目で見つめるレンとラフィーネだったが、長女であるレイラを怒らせた時の恐ろしさを知っているだけに、黙って肩をすくめあう。
「ねぇ、ねぇ、レイラ姉さま、みて、みて、これつくったのぉ」
その時、先ほどから床にひろげた白い布に、一生懸命なにかを書いていた末っ子のミルが、クレヨンで汚れたほっぺをふきながら、姉達に自慢げに完成品を見せ付ける。
そこには角ばった汚い人間用の文字で「カソゲイ、にんげんサマ」とデカデカとかかれていた。
「あら、よくできわねぇ、えらいわミル、でもね、間違えてるわよ」
にっこりと微笑みながらレイラは四女のぴょんぴょんと飛び跳ねるピンク色の頭をなでてやる。
笑顔は女神のようだが、その瞳の奥は全然笑っておらず末の妹でも容赦ない。
こと人間関連の事になるとモンスターとしての地が出るレイラだった。
「ひぃ…あうぅ、あうあう」
何処を間違えたのかわからないミルは、姉の瞳の奥の剣呑な光りを浴びながら、言葉につまり必死に手旗を何度も見返している。
「あははは、ミルのばぁか、こんな汚い字じゃ人間様もあきれて帰っちゃうわよ」
そんな末の妹の様子にレンが大声で笑いながら、さっとミルの手からお手製の手旗を奪い取る。
「カソゲイって何よ?過疎のゲイ?あははは、へんなのぉ」
「う゛〜〜」
文字の間違えを教えてもらったのは嬉しいのだが、やはりレンに言われるとレイラとは違う感情がこみ上げてくるミルだった。
「あははは、ミルの馬鹿っ、人間様の文字も書けないなんて、ほんとダメダメよねぇ」
「うう゛ぅ〜〜」
ミルのふにふにとした頬が物凄い勢いでふくれていき、それに比例するように大きな瞳に涙がたまっていく。
「ちょっとレンもうやめときなさい、ミルがせっかく作ったんだから」
しかし、ラフィーネの静止の声など聞く様子もないレンは、調子に乗って悪戯っ子のように笑いながらミルお手製の旗をパタパタと振りまくる。
「カソゲイ、カソゲイっだって、あははははは」
せっかくレイラの静かな怒りから気を効かして妹を助けたのに、これでは元の木阿弥だった。
「レンのばがぁぁぁ」
案の定、どうやら堪忍袋の尾が切れたらしい小さなサッキュバスは、幼い蝙蝠の羽をパタパタと動かしながら、レンのお腹めがけて体当たりを敢行する。
「きゃあぁ」
突然の特攻攻撃にレンはミルをお腹に抱きかかえたまま倒れこむと、ゴロゴロと床をころがり戸口まできてようやく止まる。
「いたたたっ…たくっ、なによ」
「ううぅ〜」
手足を絡めるようにして、倒れこむ二人の少女。
この300年いつも見られる姉妹のたわいもない喧嘩の光景だった。
しかし、そんな二人を見つめる姉達の視線はいつもと違い驚愕に見開かれ、まるで今にも心臓を止めてしまいそうなほど固まった表情を作っていた。
「??…どうしたの姉さん」
「ふにゃ?」
したたかに打ち付けた腰をさすりながら顔を上げるレンとミル。
そこでようやく幼い妹達は、姉達が向ける目線の先が自分達ではなく、その後ろ、そう彼女達の背中にあるドアの方に向かっていることに気がついた。
また号外が来たの…いえ、それなら姉さんたちはこんな顔はしない…じゃぁ何が…!!
「えっ…まっまさか…」
期待と、そしてそれ以上の緊張に包まれながらレンがゆっくりと首を後ろにむけたその先には……
まぎれもなく、300年ぶりの最高のご馳走、人間様が立っていた。
「あ…ああぁ…にっ…にんっ」
ようやく硬直から回復したラフィールが自らの唇を震える手で覆いながらゆっくりと戸口にたつ人影を指差す。
「しっ…信じられない…ほんと…なのね」
その隣でレイラも、目を閉じたら全てが消えてしまうと言わんばかりに目を見開き、凝視していた。
そこには、間違いなく彼女達が待ち焦がれた人間様が立っていたのだ。
まだ成人はしていない少年といった趣の顔立ちと小柄な体つき、見た目はレンより少し年下に見える。
金色の髪と、スカイブルーの瞳、そして端整な顔立ちは人間の中でもだいぶ上出来の部類に入るつくりなのは間違いない。
そしてなにより南の海のように深い蒼色の瞳は、強靭な意志を持った人間独特の高い理性の光りが輝き、幼いながらも凛々しく、まさに英雄の気迫に満ちていた。
見た目はまだ成人していない少年でも、この迷宮の最下層部まで辿り着いたのだ。
相当な手練、いや、歴代の英雄クラスの力をもつ類まれな戦士なのだろう。
そう、彼女達の主食にして最高のご馳走、人間の男性、しかもとびきり極上の存在だった。
幾多の戦いを潜り抜けた鎧はあちこちが傷だらけで、肩当も砕け散り、返り血に無残に染まっている。
しかし、その鎧が元は真っ白く美しいものであったことは容易に想像できた。
間違いない、たった一人きりだけど、あの人間の一団を率いていた白い鎧の戦士なのだ。
「にっ…人間様…本当にいらしてくれたんだ、はうぅ」
「ゆっゆめ?レン?これゆめ?」
その足元で腰を抜かし座り込んだまま、しっかり抱き締めあったレンとミルが、ぽか〜んと口を開けながら、この信じられない訪問者を見上げていた。
しばらくの間、サッキュバスの四姉妹にとっては感激の、そしてこの部屋に足を踏み入れた白い鎧の若き戦士には絶望の空気が流れる。
「ちっ、ここもモンスターの巣か」
白い鎧の戦士は、優しそうな顔に似合わずそう吐き捨てると、モンスターに反応して青白く輝く魔法の剣を構え直す。
そして、足元に潜んできた女の姿をしたモンスター達から間合いをとるためにジリッと後退っていた。
「あっ…かっ帰らないで、人間様」
しかし、それを勘違いしたレンは、思わず涙の雫をとばしながら、戦士の足にしがみつく。
「うわっ、はっはなせ」
慌てた白い鎧の戦士は、レンの細い腕を振り払うと、さっと剣を構え直す。
「レン、人間様に手荒なことしてはけませんわ……申し訳ありません、無作法な妹で」
いちはやく会合のインパクトから復帰したのは、やはり老練なサッキュバスである長女のレイラだった。
娼婦のような魅惑的なドレス姿に包まれる極上の肢体を印象付けるようにくねらし、相手に緊張感を与えない絶妙な歩幅で歩み寄りだす。
「わたくし、この部屋の守護をまかされております四姉妹の長女、レイラと申しますわ、以後お見知りおきを、若く雄々しい人間の戦士殿」
レイラは、脈打つように広がる黒髪を翻し、白い鎧の戦士に向かって優雅に一礼する。
勿論、腰のあたりまで入ったスリットから艶やかな白い太腿を覗かせ、淫らな曲線を描く大きなバストの柔らかな膨らみを強調する事は忘れていない。
その様子に白い鎧の戦士は、年相応に微かに動揺したようだったが、ここまで激戦を潜り抜けてきただけあって、そうやすやすとは懐柔されることはなかった。
「貴様らサッキュバスだな、そうそう騙されるものか、寝首をかこうとしてもそうはいかない」
チャリッと剣の柄を握り直し、四匹の美しい人間の姿をもつ凶悪なモンスター達を警戒する。
「ふふふ、はじめまして若き戦士殿、あたしは次女のラフィーネ、貴方様のおっしゃる通りあたし達はサッキュバスよ、だからといって毛嫌いしないで欲しいわ、ほら見てあなたの為にご馳走だって用意してるのよ」
そう言いながら次女のラフィーネが優雅に身を翻し、さっとテーブルの方に手をかざすと、そこにはちょうど並べていた豪華な料理が湯気をたて陳列されていた。
「ふん、見えすいた罠を」
白い鎧の戦士は疲れ切った飢えた青い瞳をちらりとテーブルに視線を走らせるが、すぐにサッキュバス達のほうに注意を戻す。
だが、そのほんの数瞬の間に、ラフィーネはその位置取りを変え、戦士とレイラの反対側から回りこむような見事なポジションに移動していた。
300年のブランクがあるとはいえ、最高難易度のダンジョンの最下層を任されたモンスターだけのことはある動きだった。
「ねぇ人間様ぁ、私は三女のレン、えへへ、よろしくね」
「あたいはミルだよ、ほら人間サマ熱烈カンゲイなの」
床に横たわったままのレンとミルは、いつのまにか可愛らしく両手をとりあい草原に佇む乙女のような姿で座ると、ハタハタと「カソゲイにんげんサマ」と書かれた手旗をふっている。
可憐な頬を火照らせ熱い眼差しで見上げる美しき姉妹の姿は、敵意などいっさい感じられない正真正銘の愛情のこもった美少女ぶりだった。
「ええぃ、もう騙されるのか、このダンジョンでお前らのようなモンスターに仲間を何度奪われたか!」
だが、ここに来るまで艱難辛苦、すっかり人間……もといモンスター不信に襲われているらしい人間の戦士は、その幼いけれど凛々しい顔をきっと引き締め一寸の油断無く構える。
「あら、そんな騙すだなんてことありませんわ、戦士殿、せめてお名前だけでも聞かせていただけませんか?」
レイラは涙に濡れた寂しそうな上目つかいで戦士を見つめながら、悲しげな声をだす。
勿論、騙すことがないと言う事自体、真っ赤な嘘だ。
四姉妹達だって不意をつかれなかったら、すぐにでもこの若者を取り押さえ待ちに待ったご馳走を堪能していたところだろう。
だが残念な事に、このすこぶる極上で美味しそうな若者の後ろでは、ドアが開け放たれたままになっていたのだ。
ダンジョンの部屋に縛られたままの彼女達にとって、もし若者が一歩外に踏み出して逃げ出してしまえば、それで全て終わり、300年間待ち続けたこの最高のご馳走を逃してしまうのだ。
瞬時にそれを悟ったレイラが、妹達に目線でそれとなく伝えつつ、人間の注意が後ろの空いているドアにいかないように話し掛ける作戦をとっていたのだ。
「そ、そうだな……よし、いいだろう、お前達に聞きたいこともあるしな、俺の名は、ルクス・ブラックムーア、グレイホーク王国の第三位王位継承者だ」
レイラの策略が功を奏したのか、相変わらず油断を見せない光をスカイブルーの瞳にたたえたまま、若き戦士ルクスは名乗りをあげていた。
「まぁ、王族の方なんですの?……あぁ美味しそ…」
思わず本音がちらりとでてしまうレイラは、その美貌にかかる黒髪を払うふりをして、唇から滴り落ちそうになった涎をぬぐう。
「信じられない、王子様がきてくれるなんて……」
ラフィーネも思わず目の前の待ち望んだ人間を抱き締め、たっぷりと熱いキスとともに大好きな唾液をすすりあげたい誘惑に必死に耐える。
ただでさえ、人間というだけでも希少価値が高いのに、その中でもさらに高貴な血をひく王族の生まれだなんて凶王の迷宮華やかし頃でも、めったに口にすることができなかった一品なのだ。
「おっおっ王子様ぁああ、はふぅ〜〜」
レンはすっとんきょうな裏声を出すと、感激のあまり軽い貧血になってしまい、妹のミルに抱きついてなんとか姿勢を保っていた。
「はわわわっ」
そんなレンに抱きつかれたミルといえば、邪神様からのあまりにも素敵なプレゼントにもう感動の涙と涎をはしたなく垂らしながら、言葉もなくルクスと名乗った戦士を見上げていた。
一方、グレイホーク王国の若き王子ルクス・ブラックムーアは、背中の蝙蝠の羽を除けば人間、それも極端に美しい女性にそっくりな四匹のモンスターをみつめ思案していた。
実際の所、この若い王子はサッキュバスと相対するのは初めてだった。
目の前にいる四匹のモンスターは、竜族のように強力無比なブレスは吐かないし、巨人族どものような恐ろしい怪力も無い、それどころか牙も鉤爪もないければ、雷や炎をあやつる強力な魔法の力も、一撃で人間を殺す死の呪いさえもっていない。
あるのは、ただ人間を誘惑する力だけと宮廷魔術師から聞いていた情報を思い出す。
苦痛や恐怖なら十分わかるが、ただ誘惑するだけとは……
なんだ、何も恐れることは無い、非力なモンスターじゃないか!
頭の中に事前に詰め込んできたモンスターの知識を反芻し、ルクス王子は内心ほっとする。
なにせ今までの敵が敵だった。
雄たけびをあげて襲い掛かるゴブリンやオーガの群れ、闇の中から這いよるゴーストども、狡猾なスペルを唱えるオークメイジ達、まさに連戦に次ぐ連戦、休む暇もなく戦い続けてきたのだ。
さらにダンジョンの各所には、漆黒の剣と楯をかまえ魔法をキャストしながら切りかかってくるトロールのダークナイト、地獄の炎を吹き上がらせるアークデーモン、硬い鱗をもちマグマよりも熱いブレスをはく強力無比なドラゴンといった信じられないくらいの恐ろしいモンスター達が待っていたのだ。
それに比べ、今目の前にいるのはたった四匹の、ただ人間を誘惑するだけの、なんともお粗末な特技しかないモンスターなのだ。
このダンジョンの死地を潜り抜けてきたルクスにとって恐れる程の敵ではない。
いざとなったら魔法剣の錆にしてやるまでだ。
残念がら、まだ経験の浅い幼い男の子である王子には、美女の誘惑がどれほど恐ろしいものか、この時まったく知る余地もなかった。
「お前らに聞きたいことがある、邪なレッドドラゴンのザゴールはどこにいる?」
ルクスは、今までに人語を解すモンスターに何度も聞いてきた質問をくりかえす。
「ザゴール?だれそれ?知ってる?」
「うんにゃ?」
レンとミルはまだ床に横座りになって手と手を取り合う姿勢のまま、お互いフルフルと首をふる。
「聞いたことないわね」
ルクスに気がつかれないように、ジリジリと間合いをつめているラフィーネも小首をかしげ即答していた。
「……そうか」
その応えに目に見えて落胆するルクス。
「あら、赤竜のザゴールちゃんでしょ、あのガキ大将の…たしか700年前だったかしら、まだこのダンジョンにわたしが来る前に何処かのウイザードに封印されたと聞いてますわ、ルクス様、あの子、また何か悪さをしましたの?」
だが、肩を落とすルクスの耳に思いもかけない言葉が聞こえてくる。
「知っているのか?ザゴールを!そうだ700年前に封じられたザゴールだ!今は?今は何処にいる?奴がまた現れたのだ…そして、ミスタラ公国の光り、ユリアーナ姫をさらって、どこだ、奴はこのダンジョンの何処にいる?」
そう、あれは今から一ヶ月ほど前のことだった。
ハイランドでも西方に位置するグレイホーク王国の国境付近で、同盟国のミスタラ公国の皇女、ユリアーナ姫の馬車が襲われ連れ去られてしまったのだ。
ユリアーナ姫の美しさは近隣諸国にも知れ渡っており、ルクスもその姿を初めて見た時から幼い胸をドキドキとさせ初恋に落ちていた。
そんな美姫を襲いかどわかしたのは、突然上空から現れた邪悪なレッドドラゴンとその眷属の竜人ドラゴニュート族の群れだった。
レッドドラゴンはブレスを撒き散らし護衛の騎士団を壊滅させ、ドラゴニュートどもがユリアーナ姫とその侍女達、それに選りすぐりの女近衛兵達を全てさらっていってしまったのだ。
グレイホークの賢者達は、生き残った騎士の話からそのドラゴンが700年前に封印された赤銅色の鱗をもつレッドドラゴンのザゴールと呼ばれる邪悪なドラゴンであることを突き止めたのだ。
だが、なぜユリアーナ姫をさらったのか、その目的や、なにより何処に去っていたのか皆目検討もつかなかった。
そんな時、ザゴールの眷属のドラゴニュート族が、遙か昔に打ち捨てられた伝説のダンジョン、「凶王の迷宮」に入っていくのを見たと言う情報が偶然にもルクスのもとに舞い込んできた。
昔から、王ではなく、王に祝福される英雄になりたかったルクスは、これは一世一代のチャンスが来たと身震いを隠せなかった。
なにせ悪のドラゴンに攫われた愛しいお姫様を助けに難攻不落のダンジョンに立ち向かう…まさに英雄の王道。
ルクスは、姫への愛と、英雄への功名心、そして同盟国の危機をすくう狭義心に突き動かされ、すぐさま剣をとると、グレイホーク王国中に呼びかけ腕に覚えのある者たちを集め、ユリアーナ姫救出部隊を編成し、凶王の迷宮に挑んだのだ。
もともと、グレイホーク王国ではルクスは幼いながらも強靭な意志の強さで知られる王子であり、努力に努力を重ね困難にぶつかるその姿に、彼を慕ってくれる力強い仲間も多く、そして何より自分も英雄になるべく必死に訓練を繰り返し剣の腕に自信があった。
しかし、潜っても潜っても赤竜ザゴールどころかその手下のドラグニュート族にも遭遇せず、変わりに恐るべきモンスターと罠によって大切な仲間を次々と失い、もう今は王子一人きりなってしまったのだ。
「どこだ、どこにいる、奴をザゴールを倒さねば、ユリアーナ姫を助けないと…仲間がうかばれん」
ギラリと光る魔法剣の先を、レイラに付きつけるルクス。
「まぁこわい……でも、残念ですわね、ザゴールちゃんでしたら、ここにはいませんわよ、確かあの子のお家は北にある火吹き山のダンジョンですもの」
レイラは、にっこりと温和な笑みを浮かべながら、眼前の切っ先をちょんちょんとつつく。
「へ?……ここではない?」
そんな話初めて聞いたぞっと言わんばかりポカンとした顔を浮かべるルクス。
「あらあら、可愛いお顔……ふふふ、そうですわよ、火吹き山の赤竜ザゴールと言えば、昔は…そうねぇ1000年ほど前は有名でしたのよ」
四姉妹の仲で最も古参なレイラは、嫣然と微笑みながら相手に安心感を植えつける柔らかな口調で答える。
「そんな馬鹿な、奴の眷属のドラゴニュートがここに入るのを見たと……」
魔法剣を持つ手をカタカタと震わせるルクスは、騙されるものかとブンブンと首を振りながらあらんかぎりの叫び声をあげる。
「ああ、それならリザードマンと見間違えたのかも、ほら同じトカゲの鱗で人型だし、あれなら迷宮の入り口付近の沼地に住んでるから」
レイラと反対側からラフィーネがやれやれっと言った感じで声をだす。
「そっそんな…間違いだったなんて………こんな最下層にまで来たのに…いや、嘘だ、嘘に決まってる…」
あまりのことに注意力が緩慢になっているルクスは、二匹のサッキュバスがこれ幸いとさらに間合いをつめにじり寄っていることに気がついてなかった。
「なんのために…こんなダンジョンの奥まで…みんなを犠牲にして…」
その脳裏には次々と散っていた仲間たちの顔が浮かんでは消える。
「どうか、先に行ってください!ここは俺が!」そう叫んで女蛇ナーガの蛇体の中に消えた切り込み隊長スタームの最後のニヒルな笑み。
「危ない王子っ」と叫びルクスの身代わりに死霊の女騎士デュラハンに深い闇の中に連れ去られていったクレリックの少年フリントの決死の表情。
ルクスと共にダンジョンを探索した素晴らしい仲間の最後が次々と思い出される。
そして、ルクス王子の剣の師匠にして良き理解者、剣豪ソス卿が堕天使達を引止めるためルクスを逃がし扉を閉ざす瞬間、最後に初めて見せてくれたあの笑顔。
その全てが、入るダンジョンを間違えちゃった♪ という初歩的ミスでまったく無意味になるなんて…
「そんな馬鹿な話…あってたまるか……みんな…」
皆、死体すら残らない悲惨な最後を遂げたのだ。
何故か「お婿さんゲット〜」やら「坊やめくるめく世界に連れてってあげてよ、おほほほほ」という叫び声をモンスターどもが残して消えていったのが気になるが……
「くそ、くそぉ…姫を助けるはずが…ユリアーナ姫」
思わず涙がスカイブルーの瞳からこぼれそうになるが、ぐっとこらえて剣の柄を握る小さな王子。
意思の強さだけなら同い年の男の子には絶対負けないだろう王者の強さだった。
そうだ、せめてユリアーナ姫が火吹き山のダンジョンにいることを、姫の故郷であるミスタラ公国に伝えなければ……
なにもせず、ここで朽ち果てては死んだ仲間にも申し訳ない。
「あのさ、その姫様達なんだけど、もう攫われてけっこうたつんでしょ?じゃあ手遅れかも」
ラフィーネは意気消沈する人間の王子に気取られないようにチラリと姉のレイラと視線を合わせると、ルクスの注意をそらすため話しかける。
「なっ何をいう…なぜ、なぜだ!」
またしても希望を刈り取られ怒るルクスは、ラフィーネの目論み通りレイラに突きつけていた青白い光りをはなつ魔法剣の切っ先を、ラフィーネの方にむけて詰め寄る。
「んっ?ああっ、ルクス王子達人間は知らないのね、ドラゴニュートってね男しかいないのよ、それで、女を繁殖のために攫っちゃうわけ、多分そのお姫様も侍女の方々もみんな今頃ドラゴニュートの幼生を孕まされちゃってると思うわよ」
突きつけられた切っ先を恐れもせず、ラフィーネは王子の青い目をみて、事実を淡々と話す。
実際今頃、攫われた姫君達は竜人ドラゴニュートの巣穴に持ち帰られ繁殖用メス家畜として日々、犯され孕まされ幼生を産み続けていることだろう。
「そっ…そんな…そんなこと……」
若き王子は、唖然としてラフィーネを見つめる。
「本当よ、ドラゴニュートって半分爬虫類なだけであって、交尾もとってもねちっこいし、冷酷だし、人間の女の子じゃとうてい正気ではいられないでしょうね、それにトカゲだけあってバカだからお姫様を捕虜にってことも考えつかないと思うわ」
ラフィーネには、彼らトカゲどもが王であるドラゴンと同族以外の生き物を大事に扱うとは到底思えなかった。
おそらくドラゴニュートにとって捕まえた女は全て、自らの子種を注ぎ込む穴と肉袋をもった繁殖用の道具にしか見えていないだろう。
そんな奴らの巣穴が王族のお姫様達が耐えられる環境であるとは思えない。
最もずる賢いレッドドラゴンが何かのたくらみをもって暗躍しているという可能性も捨てきれないが、そんなことまで王子に教えてあげる必要は今はない、なによりラフィーネの狙いはただ一つ、王子の注意を扉からそらし捕獲することだけだ。
ラフィーネはご愁傷様ね、というような冷淡な口調でわざとそう言いきると、軽く両肩をあげるゼスチャーをする。
「きっ…貴様ぁぁああ」
やり場のない怒りに駆られたルクスが、その激情にかられるまま無防備にラフィーネにむかって詰め寄ろうとした。
その時、
「はい、ぎゅうっですわぁ……うふふふ、つかまえましたわよ、わたしのかわいいルクス様」
いつのまにか後ろに回りこんでいたレイラがルクスの体をそのたおやかな腕で抱き締める。
小柄なルクスは、頭をむにゅっとレイラの豊満な胸に包まれ、くるみ込まれていた。
「なっ…しまった…くそぉ」
油断したといえ、そこは、この凶王の迷宮を最下層までおりてきた歴戦の戦士のルクス、すばやく反応すると、美女の姿をしたモンスターの抱擁から逃れようとする。
しかし…
「駄目よ、ルクス王子、オネーサン達から逃げちゃ」
これまたいつの間にか、ルクスの耳元にかがみこむようにして涼やかな顔を近づけたラフィーネが、ふっと耳元に息を吹きかけると、若い戦士の体はまるで自分の物では無いように動きがとれなくなっていた。
「ぐぅう…パラライズブレスかっ…くぅ」
モンスターの特殊な攻撃に対する抵抗術は十分に訓練してきたはずなのに…涙を浮かべて悔しがるルクスの顔に、そっとラフィーネは美貌をすり寄せ、人間の匂いを美味しそうに嗅ぎながら、さらに丹念に息を吹きかけていく。
「まぁ悔しくて泣いちゃってるの?ふふふ、本当に可愛いんだから…でもね、レイラ姉さんの抱擁とあたしの吐息から逃げられた戦士は今まで一人もいないのよ」
「そういうことですわ、ルクス様、でもルクス様は大分お元気みたいですし…念には念をいれさせていただきますわ」
背後から愛しい人を抱き締めるように優しく手を這わせるレイラの背中から、ゆっくりと漆黒の翼が広がっていく。
「わたしの接吻と抱擁を、どうぞ堪能してくださいませ」
にっこりと微笑む蕩けそうなほど優しげな微笑、その艶やかな唇がそっと後ろからルクスの頬に触れる。
「あうぅっ、やっやめろ」
それだけでもう、ルクスの顔の皮膚は火照りだし、体の芯がドクドクと脈打ちだしていた。
これがサッキュバスの誘惑の力なのか…まっ負けてなるものか…
昔、王城お抱えの宮廷魔術師から聞いた話を思い出し、若き王子は理性という名の弓をひきしぼろうと身構える。
「ふふふ、硬くならなくてもいいですわルクス様、あなたのレイラが優しくしてさしあげます」
背後から抱きつく妖艶なレイラは、白くしなやかに動く指先を揺らめかすと、そっと彼の顎先を動かし、おもむろに王子の唇を奪っていた。
「なっ…んぐぅつ」
「はふぅ…んんっ…ちゅく」
ルクスの口に到底同じ生き物とは思えない、柔らかくそれでいて甘美な唇が押し付けられる。
それと同時に、ねっとりと唾液を滴らせる貪欲な舌が彼の口の中に潜り込もうと吸い付いてくる。
「んぐぐぐっ」
ルクスは必死で歯をくいしばり、その淫らな攻撃から逃れようとする。
ルクスにとってキスと言えば生前母上が寝る前にしてくれたお休みのキスと、彼の愛しいユリアーナ姫に接見した際に許された手の甲にしたことがあるぐらいだった。
そんなまだ初心な王子にこの攻撃は恐ろしいほどに有効だった。
「ふふふ、無駄ですわ、ルクス様」
唇を吸いながら、何故か器用に声をだすレイラ。
その言葉は嘘ではなく、ちょっんと美女の舌先がルクスの歯にあたっただけで、まるで己の意思とは関係なく彼の口はあっさり開き、飢えたサッキュバスの蠢く赤い舌をやすやすと口内に迎え入れていた。
「ふぐぅ…ううぅ…んんっ」
「んんっ…さっ…最高ですわぁ…んっ…こ、この舌、人間様、人間様のお口っ…んっ…美味しいっ…んふ」
そこからはもう妖艶なレイラの300年たまりたまった性欲が爆発したかのような、激しすぎるディープキスの嵐がはじまっていた。
じゅるっと音をたてて潜り込んだ長い舌は、手当たりしだいにルクスの口の中を嘗め回し、歯の間から口蓋までベロベロとしゃぶり尽くしていく。
「ふぐっ…ううぅっ」
若い戦士の舌はあっという間に淫蕩なサッキュバスの舌に絡め取られ、まるでキャンディーのように舐めまわされ、ぐちゅぐちゅに交じり合い、犯されていく。
「あふぅ…ルクス様、もっとぉ、もっとお口を開けてくださいませ…じゅるる、んちゅ、じゅるるっ」
黒髪の美女レイラの人を惑わす匂いに包まれながら、ルクスは際限なく口腔内を蹂躙され続けていた。
それは口の中から広がり、まるで体中に絡みつくようにルクスを簡単に篭絡し、到底人間同士では得られない恍惚感を与えてくれる。
「はふぅ…んんっ…じゅるるぅっ…いいですわ、いいですわ…んんっ、人間様のベトベトの唾液、んぐ、最高ですわぁ」
頬を染め興奮しながら深い接吻を繰り返し、王子の唾液を極上の飲み物のように喉を鳴らして飲み干すレイラ。
そのしなやかな背中から広がった蝙蝠の翼が、まるで夜の帳がおりるように若い王子の姿を包み込んでいく。
やがて漆黒のマントの中で、妖艶な美女の顔と虜にされた戦士の顔だけが浮かび上がり、何度も顔の位置をかえながら深い深い口づけを繰り返す。
その絡み合う口の中では、若い戦士の唾液と一緒に、その精気もじゅるじゅると美しいサッキュバスの喉の奥に吸い込まれていた。
「……姉さん!レイラ姉さん、独り占めはだめよ、ちょっと姉さんってば」
その時、このままでは大変と思った姉妹達が急いで姉の耳元で大声をだす。
すでに意識を失いぐったりとするルクスをゆっくりと蝙蝠の羽で包み込み、骨の髄までむしゃぶり尽くそうとしていたレイラは、妹の声にようやく冷静さを取り戻していた。
「んっ、あら…ごめんなさいね、姉さん夢中になっちゃって」
恥ずかしそうに頬を染めているのだが、それでもまだ、肉厚の唇から伸びた真っ赤な舌先は戦士の口の周りを名残惜しそうにねっとりと舐め回していた。
「もう、姉さんばかりずるいよぉ、私もぉ」
はぁはぁと欲情した牝犬のように荒い息をつくレンの瞳は、瞳孔がきゅっと細まっている。
「そうよ、レイラ姉さん、あたし達にもわけてくれなきゃ」
次女のラフィールももう我慢できないのだろう、いつもは料理の味見をしている端整な口元からはトロリと欲情の唾液が滴り落ち、長い脚をもじもじさせながら、姉の蝙蝠羽をひっぱっている。
「あうぅ、ミル、もう、もう」
四女のミルに至っては、床にぺたりと座り込み、切なそうに下着の上から胸と脚の間を撫でまわしながら、火照った顔で姉を見上げていた。
「ふふふ、ごめんなさいね、でも、ほら邪魔な物は全部とれたわよ」
レイラはそう言いうと、愛しそうにルクスの首元に鼻先をこすりつけながら、閉じられていた大きな黒い蝙蝠の羽をゆっくりと開く。
そこには、先ほどまで小柄な王子が身に纏ってた白い鎧がグズグズに溶け落ちており、下に着ていた薄絹の軽装だけになっていた。
その絹の服もボロボロとほとんど剥がれ落ちている。
「ちょっちょっと!レイラ姉さんったら、もう少しでルクス王子まで溶けちゃうとこだったじゃない!」
ラフィールは普段は姉に対して使うことのない怒った口調でそう言いながらも、目の前に現れた人間の瑞々しい裸体に目を奪われていた。
レイラの「黒き翼」といえば、包み込んだ男性を極上の快楽のまま身も心も文字通り溶かすことで有名だった。
蝙蝠の羽の内側の微細な羽毛から分泌される甘い香りの粘液は、ゆっくりと獲物の神経を麻痺させ心地よい陶酔感とともに精気を奪い溶かし消化してしまう。
遥か昔に一度、レイラがその黒い翼を虚空に広げて聖騎士一個小隊をまるごと包み込みあっという間に平らげてしまったことさえある事をラフィーネは知っていた。
「ふふふ、まぁいいじゃない、ほらレン、そこのテーブルを少しどけて、わたし達のご馳走をおきましょう」
レイラは興奮しすぎて羽の制御ができなかったことなど素知らぬふりで、妹達に指示をとばすと、テーブルの上の人間用の料理を脇にどかし、その横に精気を吸われ麻痺しているルクスを横たえる。
「ううぅ…おっ俺は…」
レイラの抱擁と口つけで軽く意識を飛ばしていたルクスは、その振動でどうにか正気を取り戻すと、まだ痺れのとれない体を無理に動かそうとする。
だがテーブルの上に囚われた彼の体は、パラライズブレスと「黒き翼」の影響が残っているのかうまく動かすことができない。
そんな王子の体に、サッキュバス達がしなやかに絡みつき、甘い肉の拘束という枷に捕らえていく。
「だめよ、ルクス様」
「そうよ、逃がさないわ」
両脚は、妖艶な美貌のレイラと、涼やかな顔立ちの美しいラフィーネによって捕らえられ、
「ふふふ、もう夢みたい、人間様がここにいるんだね」
右手は、ルクスより少し年上の年頃にみえる美少女のレンに抱き締められる。
「はやく、はやく、食べたいよぉ、ルクスお兄ちゃんを食べていい?いい?」
そして左手は、ハァハァと舌をだしてうずうずしている幼く可愛らしい少女のミルによって掴まれていた。
「はっはなせ…はなしてくれ…俺は姫を助けなくては…ユリアーナ姫ぇ」
ルクスは彼が颯爽と救出するはすだった姫の名前を呼びながら、痺れの残る体を無理やり動かそうと必死に抵抗を試みる。
だが、何故か体がピクリとも動かず言うことをきいてくれない。
痺れが残っているが、それでもいつもなら王子の体は、彼の強靭な意志に従ってくれるはずだった。
それがなぜか、まるで王子の意思とは無関係に、体の方が拘束されるのを望むかのようにピクリとも動かないのだ。
馬鹿な!何故だ!相手のサッキュバス達の力は人間の女性と大差ないはずなのに、何でそれが振りほどけないのだ。
これがサッキュバスの力…なのか…
ルクス王子が愕然とした時には既に遅く、意思とは関係なく王子の肉体は美しく四姉妹の魅惑的な力に屈していたのだ。
男を虜にするためだけに存在する絶世の美貌と淫らで美しい肢体、その女の魔力が男であるルクスの肉体から抵抗の力を奪ってしまっていたのだ。
理性ではわかっている、この目の前にいるのは姿形が美しいだけのモンスターなのだ。
その心中は、彼の憧れのユリアーナ姫にとうてい及ばない邪悪な魂が渦巻いているに決まっている。
この心を蕩かす妖艶で可愛らしい魔性の美女達の中にあるのはただ一つ。
伝え聞く通り、ルクスをいたぶり、さんざん弄んだあげく、魂まで食らい尽くすことだけなのだ。
悔しげに顔を歪める王子の横には、脇にどけられれた豪華な料理が置かれている。
そして、自分もまるでこれから食されるメインディシュのようにテーブルの上に乗せられているのがその証だ。
「くうぅ、くそぉこんな所でぇ、こんな所で」
なんとしても逃げなければ、そう、このモンスター達から逃げ、ミスタラ公国に姫の所在を伝えなければならない。
そう解っているのに、彼の腕や足は言うことをきいてくれず、それどころか、あってはならない事なのに心の一部さえサッキュバス達のさらなる攻めを持ち望んでいる。
そう先ほどの、あのキスのように…
あれは、もう蕩けるように、ふわふわとした気持ち良さで…
いかん!
「くうぅぅ、くそぉぉぉぉ」
スカイブルーの瞳に力をこめるとルクスはぎりっと奥歯をかみ締め、渾身の力を奮い起こして四肢に纏わりつくサッキュバス達の誘惑を再度レジストしようと試みる。
だが、
「ふふふ、とっても元気でいいですわ王子、ちょうど食べごろって感じですわね」
そっとレイラの指先が太腿を撫でただけで、ガクンっとルクスの力が抜けてしまう。
「ねぇ、姉さん、もういいでしょ、ねぇ、ねぇ」
「我慢できないよぉ、あぁっ、とってもいい匂い」
「はぁはぁ、一口だけでも、ねぇ、はやく、はやく」
ラフィーネもレンもミルも、目の前に置かれた極上のご飯に涎を垂らし、頬を紅潮させながら、今にもむしゃぶりつこうと家長であるレイラの声をウズウズと待っている。
「ふふふ、そうね、ではいただきましょうか?」
レイラも心臓を高鳴らせながら、そんな可愛い妹達に微笑みかける。
次の瞬間
『いただきま〜す』
300年ぶりの食事の合図とともに、四匹の飢えた魅力的なサッキュバスの姉妹は一人の若い戦士の体に覆いかぶさっていた。
「やっ、やめろ〜〜、うわぁぁあああああ」
餌食となった若き王子の叫びは、柔らかな美女達の白い肌に埋め尽くされるように微かに途切れ、やがてバタンと閉じたドアによって二度と外に漏れ聞こえることは無くなっていた。
<2へ>
小説リストへ
誤字脱字指摘
2/10 あき様
ありがとうございました。
2/10 あき様
ありがとうございました。