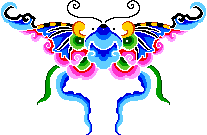
-
Musica di Giacomo Puccini
Libretto di Luigi Illica, Giuseppe Giacosa
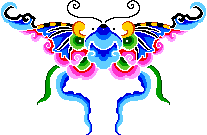
2004年9月9日 NHKホール
生前のプッチーニゆかりの地、トーレ・デル・ラーゴ プッチーニ・フェスティバルのプロダクション『蝶々夫人』の引越公演。今年(2004年)は『蝶々夫人』初演100周年にあたり、今回の上演はミラノ スカラ座での初演失敗を受けて改訂されたブレッシャ版が復元・採用されている。
野外公演であるトーレ・デル・ラーゴのプロダクションをNHKホールで上演ということは、若干の変更が加えられていることが想像されるが、演出のステファノ・モンティのコンセプトは、「日本」というより、幻想の国で、装置はまったくリアリズムを追求しない象徴的なもの。衣装は、蝶々さんがレビューの衣装風の無国籍で、他の日本人はスズキも含めて、歌舞伎の影響?なのかキモノというかドテラのような巨大な衣装で着膨れている。それに対して、ピンカートン、シャープレスらアメリカ人は、革ジャンでパンク風。ピンカートンは、サソリを表した衣装とも聞いた。すると彼の餌食になるのが蝶というのはよくわかるが、まさか他の日本人は「虫」なのだろうか?ヤマドリなどは、あきらかに「芋虫」のようだった。
別に舞台上のニホン、ナガサキが写実的でなくてもいっこうにかまわないのだが、個人的に趣味のよい衣装コンセプトとは思えなかった。また、ところどころ背景の小舞台に日舞の踊り手らしき人物が現れて踊っていたが、ここだけ本物の和風というのは、一貫性としてどうなのだろう?(蝶々さんも、なぜか足元だけ、草履を履いているのだが…)トーレ・デル・ラーゴでは、この部分はあったのだろうか?もっともけしてこの日舞の導入は、それ自体としては、しっとりとした趣があり、プッチーニの音楽と相容れていたと思う。
第一幕の蝶々さんとピンカートンの結婚式では、ヒロイン登場までを引っ張るかダレさせるかは、演出・演奏の腕の見せ所だと思うのだが、今回は、冒頭のピンカートン、シャープレスのやり取りと、その後の芋虫のモブシーンに関連性が感じられず、どうもしっくりこなかった。特に後者に関しては、見た目は華やかだったが、もう少し動きを活き活きとしたものにできなかっただろうか。あまりに着膨れていて、動けなかったのかもしれないが…。
ソリストについては、シャープレスのファン・ポンスは、今回は可もなく不可もなくといったところ。
ピンカートンのファビオ・アルミリアートは、今旬のテノールの力をみせてくれて、ひじょうによかった。ビデオなど映像で見たところ、やや優等生的な歌唱が気になっていたのだが、生の舞台では、イタリアのテノールらしい強さと伸びやかさがあった。高音がやや細くなるが、テノールとしての爽快感、臨場感は十分味あわせてくれる。特に、近年払底しているテノーレ・ロブストとして、彼を生で聴けただけでも、今回の公演は価値があったといえるほど。難を言えば、若々しく不良っぽいスタイルに似合わず、大変誠実そうなピンカートンに見えてしまったことか。
いよいよ登場するヒロイン、蝶々さんを歌うダニエラ・デッシーは、相変わらず美しく、清楚な第一印象がまずよい。十五歳のリアリズムを求めるのは、無理とはいうものの、とにかく悲劇のヒロインとしての陰影が備わっている。
ただ、第一幕を聴いたところでは、かなり声を抑えた感があったのが、少々気になってはいた。愛の二重唱も、私生活でもおしどり夫婦のデッシー、アルミリアートに期待していたほどの熱っぽさは感じられず、ちょっと控えめな印象。
第二幕に入ると、少女だった蝶々さんが一気に大人の憂いに満ちた大人の女になり、さすがにデッシーの本領発揮となった。現在、これだけ情感たっぷりと「女」を歌えるソプラノは、他にそんなに多くないだろう。一幕で気になった抑えた発声、表現も段々熱が入ってきて、『ある晴れた日』は感動的な熱唱だった。
ところが、折角盛り上がってきたところで、この日アクシデントが発生してしまった。
ミラノ オリジナル版では「花の二重唱」と美しい間奏曲の後、幕を下ろさず、物語が続くことはよく知られていることであり、このトーレ・デル・ラーゴのプロダクションはそれに準じてか、当初の予定では、二幕の幕が下りた後にすぐ三幕が始まる予定だった。
ところが、一度下りた幕がなかなか上がらず、「舞台装置のアクシデント」という場内アナウンスがあり、15分の休憩が告げられた。15分が過ぎてもなお幕は上がらず、「予期せぬアクシデントでダニエラ・デッシーは体調不良となりましたが、日本の聴衆のために三幕も歌います」というアナウンスがあり、ようやく35分後に三幕が始まった。
この件に関しては、後日、関係者の方からの証言がより、ウールの衣装の毛をデッシーが吸い込んでしまい、喉に障害を起こしたためと判明した。まさに「予期せぬアクシデント」であり、短時間で立ち直り、舞台に戻ってきてくれたデッシーに感謝したい。
こうして始まった第三幕だが、第一幕−初めての恋に胸躍らせる少女、第二幕−情念と信念の塊となった女、そして母へと変貌した蝶々さんは、この幕では信じていたものを失った悲劇と、それでも最後まで誇りを捨てることのない、人間の尊厳を体現する存在となる。好調とは言えないながら、この幕でのデッシーの表現力は素晴らしく、特に「母」としての心情が見事に最後のアリア「可愛い坊や」に込められて、筆者も含め、場内の涙を誘っていた。深紅の照明の中で、切腹して果てた白い蝶のイメージは忘れがたい。
また、この幕では、妻の体調への気遣いもあったのか、アルミリアートが一層の熱唱を聴かせ、「さようなら、愛の家」が素晴らしかった。あまりに熱く誠実だったので、不実なピンカートンのイメージとかけはずれていたくらいに。
以上、ちょっと奇妙な演出と舞台上のアクシデントがあったものの、イタリア・オペラの「声」に浸る上演としては、十分楽しめた。演出も、日舞との共演のアイデアをもっとつめるなどすれば、ずっと上質なものになることが予想される。
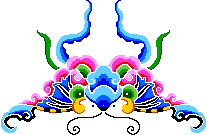
指揮 : アルベルト・ヴェロネージ
管弦楽 : 読売日本交響楽団
合唱 : プッチーニ・フェスティヴァル合唱団
演出 : ステファノ・モンティ
美術 : アルナルド・ポモドーロ
衣装 : ギジェルモ・マリオット
配役
蝶々さん ダニエラ・デッシー
ピンカートン ファビオ・アルミリアートョ
シャープレス ファン・ポンス
スザンナ ロベルタ・カンツィアン
スズキ ロッサリーナ・リナルディ
ゴロー ルカ・カザリン
ボンゾ リッカルド・ザネッラート
ヤマドリ/ヤクシデ マルコ・カマストラ
ケイト マリア・チョッピ
役人 フェデリーコ・ロンギ
Copyright © 2004 Natsu. All right reserved.
2004年10月18日