|
|
再び主イエスのくだります日 |
|
|
再び主イエスのくだります日 |
「病院から電話よ。ユイちゃんの容体が急変したって。すぐ行ってあげて」
管理人夫人の声を耳に残し、朝、礼拝堂で祈っていた私は、すぐさま入院中の娘のもとに急いだ。いつもにましてエレベーターがのろい。その狭い空間に私の心臓の音だけが無闇に響いていた。
その日は、私にとって新しい人生の船出、特別な日となるはずだった。大学卒業後、三年間勤めた高校教諭を辞し、牧師となるために飛び込んだ神学校。その全課程を終えて迎える、卒業式と祝賀パーティー。
エレベーターのドアが開いた。ガラス越しに医師と看護婦が、ちっちゃな娘の胸を押さえて心臓マッサージをしている。蘇生を図り、電気ショックを試みる。なんとか息を吹き返してくれたら、と祈り見守るうちに、いつしかその思いは変わっていた。(もういい、十分だ、やめてくれ!)
変わり果てた娘のもとに通されたとき、私も妻も、あふれる涙をとどめることができなかった。
「主よ、この幼い魂を、あなたの御手にゆだねます」
牧師である義父の祈りが、治療室の冷たい壁を突き抜けて、天に昇ってゆく。
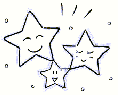
それなのに、私は、冷笑する運命の中にひとり取り残されたかのように立ち尽くしていた。白い闇に包まれて、何もかもが真っ白になってゆくようで、自分が今、目覚めているのか夢を見ているのかもわからない。
「わずか一才半で、どうして……」
その思いが頭の中をぐるぐる回り続ける。そのとき、何か遠い所から、心の奥に響いてくる言葉があった。
「すべてに感謝。すべてに感謝……」
それは、耳慣れた聖書の言葉だった。
「でも、これだけは、感謝できない」
それが本音だった。それでも、その言葉は響き続けていた。
一年半前の情景がよみがえる。
待ち望んでいた娘の誕生。しかし、娘は体中に管をつけられて、保育器の中にいた。呼吸ができず、酸素を送り続ける。強い副作用の伴う薬を投与され、胃腸からの激しい出血。この状況で使える薬は、あと一種類だけ。最後の賭けのような投与。なんとか一命を取りとめるも、保育器から出るめどは一向に立たず、水頭症の疑い、未熟児網膜症の危険もあった。
「イエスさま、たとえ何があろうとも、私はあなたをあがめます」
祈り続けたある日、そう言えたとき、すべては変わり始めた。心に平安が訪れ、娘の容体は好転し、奇跡的に退院できた。あれから、もう一年半……。
あの日のように、私は神に語りかけていた。
「たとえ何があろうとも、私はあなたをあがめます」
いつしか、「わずか一才半で」という思いは消えて、心に感謝があふれ始めた。
「一年半も生かしてくださって、感謝します。親として、貴重な、かけがえのない、ほんとうに幸せな一年半でした」
親が子を失う。それが、どれほど大きな痛みを伴うものなのかを、私は知った。
「神は、実に、そのひとり子(キリスト)をお与えになったほどに、世を愛された」(聖書)
それほどの犠牲を払ってまで、神は、私たちを救おうとされた。限りない痛みを越える、限りない愛で。
神は知っておられた。子を失うことの痛みを。だから、私も越えて行ける。この痛みを宝に変えて……。
担当医からの説明があった。死因は呼吸不全。病名は先天性横隔膜神経麻痺。生まれつき、肺を伸縮させる横隔膜を動かす神経が麻痺していたのだ。しかも、普通は、左右のどちらか一方だけ動かないものなのに、娘の場合は、どちらも動かなかった。私は尋ねた。
「それではどうやって呼吸をしていたのでしょう」
「肩で息をするようにして、肺を伸縮させていたのだと思います。しかし、それは、体力のない乳児にとって、二十四時間、いつも、百メートルを全力疾走しているようなものだったと思います」
担当医の言葉に、私は思い出した。娘が冬でも背中に汗をかいていたことを。
「たいへんだったんだ。よく、あの小さな体で、がんばったよ。えらかったなあ」
ちっちゃな、ちっちゃな自分の娘を、ほんとうに、ほめてやりたかった。百メートルを全力疾走か……。そのとき、確かに心に響く声があった。
「おまえの娘は、わたしが与えたいのちを全力で走り尽くした。さあ後は、おまえが、残されたいのちのかぎり、全力で走り抜く番だ」
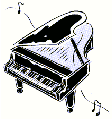

卒業祝賀パーティーの席で、友人たちは、腫れ物に触るように私に接していた。「卒業、おめでとう」と言ってあげたい。でも、娘さんを亡くしたばかりで、おめでとうなんて、やはり言えない……。
そんな中、私は卒業の辞を語っていた。
「私は今、ほんとうに神に感謝しているのです……」
心には「すべてに感謝」の言葉がなおも響き続けていた。語り終えたとき、会場の空気が変わった。
帰途の車中、義父が語ってくれた。
「ほんとうに、いい式だった。私も半年で最初の娘を亡くしている。しかし、それから天国が近くなった」
娘の告別式では、妻が、讃美歌の好きだった娘のために、ピアノの弾き語りをすることになった。
「……召さるる幼な子 み国にて み空の星と輝きつつ 主の御冠の玉とならん……」(讃美歌458番)
涙で歌えなくなるかな、と見守っていたが、最後まで歌いきった妻の顔には、満面の笑顔があった。
その夜、娘のいない、その思い出だけが残るわが家は、痛いほど寂しかった。妻と二人。沈黙を破り、電話のベルが鳴った。妻の友人からだ。彼女は、娘の死を聞いて、「神さま、どうして、そんなむごいことをされたのですか」と感情を抑えられず祈っていた。すると、背後から 「神をおそれよ」との声が響き、思わず振り返ると、幻が見えたと言う。それは、私の妻が、笑顔で讃美してる姿だった。妻は幾分興奮して語った。
「今日の告別式で、ユイちゃんのために歌ってたとき、笑顔があふれてきたの。それが幻で見えたのかしら」
驚きと、神をおそれ敬う思いが二人の内にあふれた。
「神さまって、ほんとにおられるのね……」
受話器を置いてもなお興奮さめやらぬ妻は、友人との対話の一部始終を話してくれた。
「あるんだね、そんなことが」
「ほんとね」
「でも、今日の告別式も、正直、驚いたよ。きっと涙で最後までは歌えないって思ってたのに、歌い終えたら、満面の笑顔だもの」
「うん。歌ってたとき、ユイちゃんが、今、イエスさまと一緒にいて、とっても幸せなんだって、肌で感じるように実感できて、ユイちゃん、ほんとうによかったねって。それで、なんだか、うれしくて、うれしくて、笑顔があふれてきて、まずい、葬儀に笑顔は似合わないって思ったんだけど、もう抑えられなくって」
「とても、いい歌だったよ。……み空の星と輝きつつ 主の御冠の玉とならん、か。ユイちゃんも、天国で、星みたいに輝いてるのかな」
「きっとそうよ。月の船にでも乗って、ユイちゃんの星まで行けたらいいのに」
「月の船に乗って!?」
「そう、せめて、月に一便でも出てくれればいいのに。天国のユイちゃんの星行き、月の船」
「あったらいいねえ。……でもこれで、少なくとも天国に行く楽しみはひとつ増えたね」
「どんな楽しみ?」
「イエスさまに会えるだけじゃなくって、ユイちゃんにも会える楽しみ」
「はやく会いに行きたいなあ」
「でも、あまり急がないでもらいたいねえ」
「そうね、おたがいに」
娘の葬儀の夜に、夫婦がもう笑い合っていた。
「そうそう、式の後で聞いたんだけど、あのヨシくんがね、式の最中に、言ったんだって」
「なにを?」
「『あっ、ユイちゃんが、イエスさまといっしょに、お花畑で花をつんでる』って」
まだ3才にもならない幼い無垢の魂を通して、天国を垣間見たようだった。神は語りかけられた。
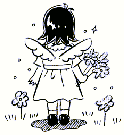
「心配することはない。おまえの娘は、今わたしと共にあって、幸せなのだよ」
もはや私たちにとって、そこははるか彼方の遠い世界ではなかった。現実に手を伸ばせば、ふれることができるほど、 天国は近くなった。
Illustration by S.Abe