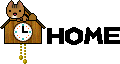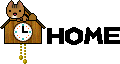
このたび、うちの父親の還暦祝いに、両親と一緒に沖縄に行って来ました。
旅行会社のツアーに参加しての2泊3日の旅行の体験談なぞを書いてみようと思います。
乱文ですが、読み進めていただければ幸いです。
尚、文中にリンク張っているところでは、旅行中に撮影した写真を見ることができます。
そして1日分ずつ印象に残ったところをピックアップしてあります。
1日目昼過ぎに沖縄到着。バスに乗って沖縄南部観光に。
南部地方は第2次世界大戦の際に被害の大きかった一帯です。
それだけに悲しいお話も・・・穏やかな風景に物語が随所に散りばめられている感覚。
切なくて、苦しい。戦争はやっぱりない方がいい。
心苦しさから一転して、夕食はアメリカンスタイルのレストランでした。
夕食後にはホテルサンマリーナへ。リゾート気分満喫のとても綺麗なところでした。
2日目
ひめゆりの塔 石碑の真下に悲劇の場所の地下壕の入り口があります。
隣接している資料館に行くと、戦争反対を切に感じることでしょう。
資料館内部では被害者の方々の写真が壁一面に飾られています。
見ていると、とても切なくなります。(写真は撮っていません。切なすぎて・・・)摩文仁の丘
平和の礎2次大戦の際、沖縄戦で被害に遭われた方々のお名前が御影石に彫られてあります。
日本人だけでなく、アメリカ兵や朝鮮・台湾の方々のお名前もあります。
ここは平和祈念公園となっており、一見すると広い、綺麗なところなのですが、海に面した
場所に先の御影石の石碑がたくさん建てられてあります。
他にも他の都道府県ごとの沖縄戦戦没者慰霊碑も同じ公園内にあります。
公園で楽しそうに遊んでいた子供達と、石碑の悲しみとが夕日混じりの中に同居していた空間でした。朝もはよから観光観光。
まず万座毛に行って団体写真を撮影した後に名護パイナップルパークへ。
パイナップルをしこたま食べさせていただいた後、沖縄本島最北端の辺戸岬へ。
昼食は海洋博記念公園のそばで琉球宮廷料理のお茶漬けのようなものをいただきました。
車酔いが激しかったのでちょっと幸せ。
その後、海洋博記念公園に入り植物園を堪能。ランが綺麗・・・
つくづく熱帯の植物は温帯では栽培が難しいことを実感。そりゃそうだ。
しかしツアーのためスケジュールが過密。すぐにやんばる亜熱帯園へ。
夕方には那覇市内のパシフィックホテルに行きました。
夕食を取った後に国際通りに行ってお土産を物色してきました。
疲れた・・・
|
|
非常に綺麗な岬です。命名は琉球王国の王様だとか。 |
|
|
パイナップルがたくさん植えられています。
(他にも県内にいくつかパイナップルパークはあるんだそうで。) 途中の展示では沖縄県におけるパイナップルの栽培に関する話もあります。 ハブとマングースの決闘も見ましたが、本当にマングースが勝ちました。 |
|
|
沖縄本島最北端です。海の向こうには鹿児島県が見える。 |
|
|
ここは一日がかりで見に行きたい場所です。ていうか行かせて。
入園は無料ですが、各パビリオンは一部(?)有料です。 今は園内を一部改装(?)しています。 |
|
|
ヘゴの原生林が壮観です。
シダ科の植物の原生林なので、かなり珍しいです。 |
3日目首里城を見た後に沖縄南部観光に行きました。
前日に両親と行った壷屋(やちむん−焼き物工房が並ぶ通り)経由国際通りを散策した後、昼食。
昼食後は初日の戦跡巡りから一転して、観光地巡りに。
船の下がガラス張りになっているグラスボートに乗り、珊瑚礁を見ましたが・・・珊瑚がかなり死んでいました。
グラスボート乗り場の近くの海岸で、工事を行っていたのでそのせいかな?と思ったのですが、それにしても・・・なんか悲しい。
玉泉洞王国村に行き、鍾乳洞をみました。その後は琉球舞踊の「エイサー」も行われていたのでちょっと堪能。
そしてとうとうこの後は那覇空港へ向かい、沖縄を離れ東京に戻りました。
やはり東京は桜の季節。空気も冷たかった・・・
|
|
赤い柱が印象的です。守礼の門は発掘作業のため正面からの撮影が大変困難です。
印象的だったのが17世紀の国王の印が漢字とアラビア文字が同居していたこと。 交易範囲の広さを感じますね。 |
|
|
那覇市のメインストリート、かな。元は戦後の市場・商店街からとか。
たくさんお土産やさんがあるので店選びで迷います。でもふつうのお店もあります。 牧志公設市場は国際通りからちょっと入ったところにあるので一度足を運んでみてはいかが? 市場近くで売っていたブラジルのお菓子(パイにチーズが入っている)が美味しかった。 |
|
|
鍾乳洞の中は非常に蒸し暑かった。地上に近いところだからかな?
気になったのが鍾乳石が灰色をしていたこと。乳白色じゃなかった。なぜだろう? あと、通路を造るために鍾乳石がざくざくと切断されていたのがなんとなく悲しかった。 「王国村」部分では琉球の伝統芸能や工芸を行っています。 |
感想観光地ごとにお土産屋がたくさんありました。すぺしゃるさんくす
それだけならいいんだけど、かなり商魂たくましいんですよね・・・みなさま。
非常に印象的だったのが、街路樹の木の種類が全然違うこと。やはり亜熱帯。
教科書でしか知らなかった植生の違いを肌で感じたこと。貴重な体験。
でいごの花もみたし、蒼い海も堪能したしで風景にはとてもとても満足。
どうしても気になったのが、お土産攻撃だけでしたが、あとはなかなか楽しい旅行でした。
あと、生の紅イモは沖縄以外には植物検疫の関係で持っていけませんのであしからず。
昔は果物も持っていけなかったのよね・・・という話を授業で聞いたことがある。甲子園の土とか。
閑話休題。
小学校の時に沖縄戦の話を本で読んだとき、涙が止まらなかった。
実際にその場所を訪れたときに、切なくて胸が締め付けられた気分だった。
いつになっても、消えない傷。いつまでも忘れてはいけない事。
美しい自然の流れと歴史の傷跡とが調和しつつ、それぞれ自己主張をしている。
そこで生活している人は、とても「強い」という印象を受けた。
「傷」を知っているからこその「強さ」−屋根の上のシーサーがそれを護り、物語る。
そんな場所でした。
こんどはゆっくりまわりたいな。
父・母、たくさんのともだち。いつもありがと。
先生方・研究室のメンバー。いつもすまないねぇ。
阪急交通社さま。添乗員さま。
沖縄バスのガイドさんと運転手さん。本当にありがとうございました。