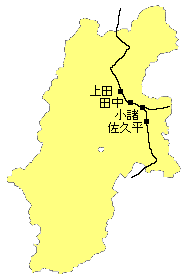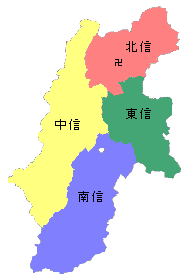
道祖神といえば、どうしても長野県のローカルな話になりがちですので、県外の方が読まれることを考えて、ひとこと書いておきたいと思います。
長野県は、大きく4つの地域から成り立っています。かつて長野県は「信州」と呼ばれていましたから、「信」の字をつけて「北信・東信・中信・南信」という4つの地域名になっています。
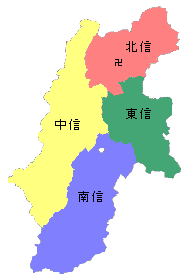
[1] 安曇野・松本・塩尻
中信の、松本と大町の間のあたりを安曇野(あづみの)と言いまして、「道祖神といえば安曇野、安曇野といえば道祖神」というくらい、全国的に知られた名所となっております。以前はこのあたりの平野全体を、広い意味で安曇野、または安曇平と言ったのですが、平成十七年(2005)、合併によって安曇野市ができました。
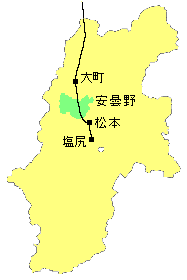
安曇野を訪れた人は、雄大な北アルプスと、どこまでも続く田園地帯に、きっと心を奪われることでしょう。のびのびとした景色の中で、日常のつまらないことを忘れ、ふと道祖神に目をやると、優しく微笑んでいたりします。なるほど、安曇野ほど道祖神が絵になる場所はないと言えましょう。
[2] 諏訪盆地・辰野・高遠
安曇野に次いで道祖神が多いのは、南信の、諏訪・辰野地方だと思います。東京から中央線で来ますと、富士見・茅野・諏訪・岡谷・辰野とつながっていますが、このあたりに道祖神がたくさんあります。(高遠は合併により伊那市の一部になりました。)
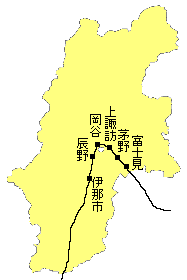
安曇野とはちがい、諏訪は狭苦しい盆地です。人々は頑固で気性が激しく、山がちの狭い土地にひしめきあうように暮らしています。そういった厳しい風土にたたずむ道祖神は、安曇野のものとは雰囲気がまた違って見えることでしょう。
[3] 佐久平・小諸・東御
安曇野・諏訪に続いて、三番目の道祖神の名所を挙げろと言われたら、東信の佐久平を挙げたいと思います。ここは、かつての中山道や北国街道が通っていたところであり、現在でも旧街道沿いに、たくさんの道祖神が見られます。(上田市まで行くと数が減ります。)