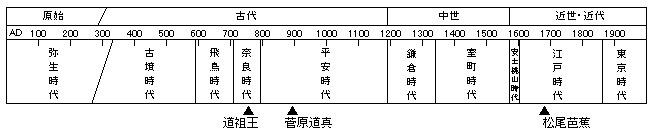松本市 岡田 松岡。文字碑「道陸神」。
<どうそじん・どうろくじん・みちの神>
「どうそじん」は漢語ですから、中国大陸から伝わったものと思います。
奈良時代には、道祖王(ふなとのおおきみ、?〜757)という人物がおりました。万葉集に歌が残っているほどの人物ですが、続日本紀(しょくにほんぎ)によれば、道祖王は756年、第45代 聖武天皇の遺言により皇太子となりましたが、第46代 孝謙天皇によって廃太子にされ、さらには獄死したと伝えられています。なお、道祖を「みちのや(=道の親)」と読むべきとする説もあります。いずれにせよ、奈良時代までには「道祖」という語が中国大陸より伝わっていたという証拠になりましょう。
平安中期(930年台)に書かれた「和名抄(わみょうしょう)」という辞典によれば、その昔、中国に旅の好きな人がいて、死後に道祖神として祭られた、と伝えられています。(彼は古代の皇帝の息子だった、旅の途中で死んで道祖神として祭られた、という説を聞いたことがありますが、出典を知りません)
「道祖」は「道徂」、みちをゆくことだという説があります。旅人たちは、道の神に、旅の安全を祈ったことでしょう。なお、道陸神(どうろくじん)という言い方もあります。陸の字には「道」という意味があるのです。

松本市 岡田 松岡。文字碑「道陸神」。
陸の字には、「六」という意味もあります。それで「道六神」と書かれることもあるようです。仏教の六道(りくどう)輪廻(りんね)の思想と習合したのではないか、と推測できるのですが、確かなことは分かりません。
現代では、「みちの神」の意味から、交通安全の祈願に建てた道祖神も見かけます。

安曇野市 堀金 下堀。平成十年(1998)。円形中区。
<たむけの神>
旅立つ人に、餞別(せんべつ)をあげる習慣がありますが、餞別のことを手向け(たむけ)とも言います。
かつては、旅の安全を祈って、道祖神に手向けをしたと言います。具体的には、小さく四角に切った紙や布を、道祖神の所にまき散らしたのです。この紙や布のことを幣(ぬさ)と言います。
「このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに」(現代仮名)
ご存知、小倉百人一首の中のひとつです。かの学問の神様・菅原道真(845-903)の歌です。このたびの旅行では、幣(ぬさ)を用意してこなかったので、代わりにもみじの葉を手向けにした、という光景を詠んでいます。まさに道祖神のことを詠んでいるのでしょう。
江戸時代、松尾芭蕉(1644-1694)の「奥の細道」には、道祖神の招きにあって、旅に出ることにしたという記述があります。はたして芭蕉は、みちのくでどんな道祖神を見て歩いたのでしょう。(ちなみに芭蕉は、口癖のように「道祖神が呼んでいる」と言っては、旅に出かけたと伝えられています)

秋田県 にかほ市 象潟町。東北地方の道祖神。