
辰野町 上平出。円形中区。首をかしげた様子が可愛らしい。仲の良さをよく描いていると思う。
握手(あくしゅ)像は、男女が握手をしている図です。長野県内全域で見られます。

辰野町 上平出。円形中区。首をかしげた様子が可愛らしい。仲の良さをよく描いていると思う。
よく見ると、肩に手を回しているものもあり、肩組み握手像と言ったりします。

山形村 小坂殿。櫛型中区に懸魚。寛政八年(1796)。
富士見町から原村にかけて、男女が向き合って手をにぎる仲むつまじい像が、多く見られます。これを「向き合い像」と呼ぶ人もいます。

原村 中新田。龕灯中区。享保十九年(1734)。割れて修復した跡がある。
ところで、孔子(前551〜前479)の論語に「天子南面」という言葉があります。皇帝は南を向いて座るという意味です。そのとき、日が昇る東方を「上座」、日が沈む西方を「下座」と言います。
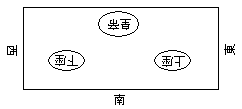
ちなみに舞台関係者や音楽関係者も、ステージの右側・左側などと言わずに、上手(かみて)・下手(しもて)という言葉を使うでしょう。そのほうが、舞台俳優たちは混乱せずに済むからです。
道祖神の場合、上座に男神、下座に女神が描いてあることが多いです。ひな人形とは反対です。ひな人形も、昔は道祖神と同じように並んでいたのですが、昭和天皇のとき、西洋のように男が下座に立つお写真が世に広まったため、ひな人形もそれにならって男が下座に並ぶようになったと伝えられています。
(現在でも、京都など一部の地域では、昔ながらに道祖神と同じ並び方のひな人形があるそうです。)