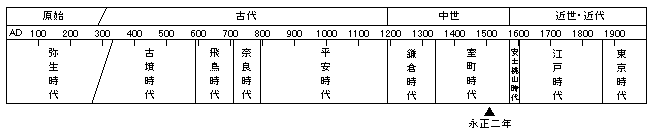
永正二年(1505)ごろの、歴史的背景も考えてみたいと思います。ただ道祖神を見て歩くだけでなく、その背景を考えるのが、石像物めぐりの楽しいところなのです。
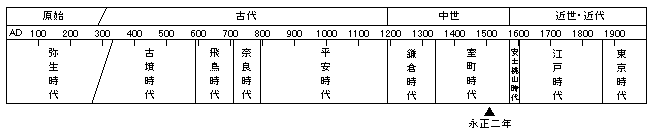
室町時代は、日本の歴史の中でも特に政情が不安定だった時代だと思います。学校の社会科で習うキーワードを挙げますと、
・惣の結成。
・地侍の出現。
・土一揆の頻発。
・応仁の乱。
農民たちは、惣(そう)という村落共同体を作って暮らすようになりました。惣の掟(おきて)にしたがって自治が行なわれるようになったのです。
地侍(じざむらい)は、幕府や守護大名に属さない、地方の武士のことです。自前の荘園を持ち、農民を指導するようになりました。
やがて農民や地侍は、土一揆(つちいっき)を起こすようになりました。幕府に徳政令(=借金の棒引き)を出すよう求めたのです。自分たちの暮らしを自分たちで守るという意識が高まっていたのでしょう。
そして応仁の乱が起きます。もとは将軍家の相続争いだったようですが、京の都が戦場となったため、首都機能が麻痺しました。これにより、幕府の支配はまったく地方に届かなくなり、戦国時代へ突入してゆきました。
・・・以上のように、室町時代は「地方自治が育っていった時代」だと言えるでしょう。村落による自治で、何よりも大事なのは「結束」です。立派な石像が建てられるのは、村の結束が固い証拠なのです。永正二年の道祖神は、かなり立派ですから、きっと村の結束が固かったであろうと、容易に想像できます。
現代でも、村で石碑を建てることが、けっこう行なわれていると聞きます。


松本市 四賀 西宮。平成五年(1993)。「開道記念」と書かれた道祖神。裏には、道路の建設に尽力した人々の名が列挙されている。