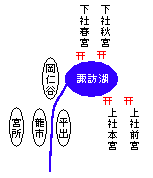
永正二年の道祖神が疑われている理由のひとつとして、「500年前、沢底のような片田舎に、こんな優れた道祖神が生まれるはずはない」という声を聞きます。しかし、応仁の乱で京都が戦場になり、文化が地方へどんどん流出していった時代背景を考えると、このような作品が地方に生まれたとしても、おかしくはないと思うのです。
では、この時代の地理的背景は、どうなっていたのでしょうか。鎌倉時代の歴史書として有名な「吾妻鏡(あづまかがみ)」には、ほかでもない源頼朝(1147〜1199)が、諏訪大社に戦勝祈願をしてもらったので、そのお礼として、諏訪上社に平出・宮所を、諏訪下社に龍市・岡仁谷を寄進したと、記述があります。
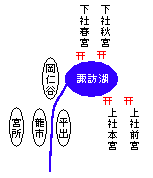
このような、神社に寄進された土地を“社領”と呼びます。「龍市」は辰野のこと、「岡仁谷」は岡谷のことでしょう。「平出」「宮所」という地名は、今でも辰野町内に残っています。
諏訪上社には「廻湛(まわりたたえ)」という祭事が、春と秋の年二回おこなわれたといいます。これは、神使(=神の使い)の一行が、各地を巡回して祭事をおこなうものでした。おそらくは、諏訪大社勢力下の各地を“定期訪問”するという意味があったのだと思います。
伊那地方の巡回ルートは、上社前宮(茅野市)を出発し、辰野町→箕輪町→南箕輪村→伊那市、と南下して、最後に辰野町に戻って沢底で祭事をし、帰っていった、と言われています。
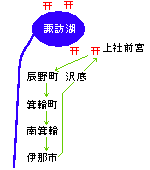
なぜ最後に、沢底で祭事をやる必要があったのでしょう。巡回が終わったら、まっすぐ帰れば良いような気がします。
永正二年の道祖神がある場所は「入」という集落で、現在でも「入村」と呼ばれています。かつては諏訪から伊那に入ってくるための玄関口だったのでしょう。現在では、沢底と言えば辺境の地ですが、昔は諏訪と伊那を結ぶ交通の要衝だったのです。
そう考えると、伊那谷を巡り歩いた神使一行が、最後に沢底で締めくくりの祭事をしたのも、なんとなく理解できます。500年の歳月を耐えるような、立派な道祖神がこの地に建てられたとしても、不思議ではないような気がしてくるのです。