
諏訪大社 上社本宮のすぐ隣りにある、鷲峰山法華寺。織田信長が本陣をはった場所である。ここで明智光秀を愚弄したため、本能寺の変につながったと伝えられている。 徳川の幕藩体制では、辰野町は伊那=高遠藩の飛び地になりました。それで現在でも、辰野は諏訪地方ではなく伊那地方の一部になっています。幕府側としては、わざと飛び地を置いたり、直轄地を置いたりして、互いを監視させる狙いがあったのだと思われます。
中世には広大な社領を持ち、勢力を誇っていた諏訪大社ですが、織田信長の侵攻によって、ほとんどの社領が失われてしまいました。

諏訪大社 上社本宮のすぐ隣りにある、鷲峰山法華寺。織田信長が本陣をはった場所である。ここで明智光秀を愚弄したため、本能寺の変につながったと伝えられている。
徳川の幕藩体制では、辰野町は伊那=高遠藩の飛び地になりました。それで現在でも、辰野は諏訪地方ではなく伊那地方の一部になっています。幕府側としては、わざと飛び地を置いたり、直轄地を置いたりして、互いを監視させる狙いがあったのだと思われます。
辰野町と諏訪市には、現在でも境界未定の部分があります。それが沢底です。地元の人の話によると、「さわそこ」は、昔は「すわそこ」といって、諏訪の底という意味だった、と言います。辞書を引きますと、底という言葉には「果て」の意味があり、ここが諏訪の境界、という意味です。
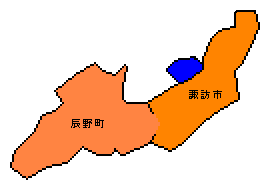
境界の諏訪市側には、板沢(いたざわ)という集落があります。あきらかに辰野町側にあり、ここが諏訪市だと言われても信じられない場所です。かつて諏訪(高島藩)が、伊那(高遠藩)に対する軍事的警戒のため、設置した集落だと言われています。


左:諏訪市側、湖南 板沢の道祖神。福寿草の里として知られる小さな集落。
右:辰野町側、沢底 岩花の道祖神。こちらの集落は滅びてしまった。今は廃墟が一軒あるのみ。
おもしろい言い伝えがあります。昔、一番どりが鳴くのを合図に双方から馬で出発し、出会ったところを国境(くにざかい)に定めよう、ということになりました。
ところが諏訪側は、にわとりを早く鳴かせて早く出発したので、峠を越えてずっと先のほうまで領地にすることができました。それで今でも辰野町側に、集落が食い込んでいるのだと言われています。
諏訪と高遠のあいだには、どうも宗教的な謎があるような気がして仕方ありません。
古事記の「国譲り」の神話によりますと、出雲でアマテラスの使者と戦って敗れたタケミナカタが、諏訪まで逃げてきて、「ここから出ませんから許してください」と命乞いをしたことになっています。
ところが諏訪には、「もともとモレヤという神がいたのに、タケミナカタがやってきて争いとなった。結果、モレヤはタケミナカタを祭る神官の一族になった」という言い伝えがあります。実際、このあたりには守屋(もりや)という苗字の人がたくさんいます。
さらに高遠には、「聖徳太子と戦って敗れた物部守屋(もののべのもりや)の一族が、高遠まで逃げてきて、この地に祭られている」という言い伝えがあります。実際、高遠には守屋神社があります。

伊那市高遠。守屋神社。
そして、ここが一番分からないところなのですが、諏訪大社は、守屋山(標高1650m)という山を御神体にしているのです。高遠の守屋神社も、おなじ守屋山を御神体としています。どうしてそんなことになってしまったのか、まったく分からないのですが、神話と史実が入り混じった、複雑な事情があるのかも知れません。
守屋山の頂上には、守屋神社のほこらがあるそうですが、これを、諏訪側の人々が谷へ突き落としてしまうのだそうです。それで、高遠側の人々は、鉄柵を作って守っているのだそうです。なんだか、根深い宗教対立があるように感じます。