
井月の肖像{『井月全集』より引用}
その前半生は謎のままだが、後半生は、最新の資料研究によってかなりのところまで分かってきた。決して放浪しに来たわけではなく、また三十年間ずっと伊那谷にいたわけでもない。従来の井月のイメージは、そろそろ改めなければならないと思っている。・三十年ちかくも信州殊に伊那の地を放浪して、[中略]行きだをれになり、[中略]死んだのであります{『人犬墨』43~44頁}・旅から旅へとさまよった井月さんは、後半生の三十年を伊那谷で過ごしました{『郷土読み物 井月さん』25頁}・ふらりと伊那の谷に来て、[中略]およそ三十年間、この地を離れず、その生涯を終わっている{『井月真蹟集』2頁}
井月の肖像{『井月全集』より引用}
そして井月は、泊めてもらったお礼のつもりなのか、俳句を書いて置いていった。今なお、伊那谷のあちこちの家から俳句の発見が続いている。・小さな古ぼけた竹行李と汚れた風呂敷包みを振り分けにして、時々瓢箪を腰にぶらさげてトボトボと牛より鈍い歩調で歩いてゐたものです。而も滅多に余所見をしないのが特色でありました{『人犬墨』48~49頁}・井月が伊那の地に於ける生活状態は怎うであったかといへば、全然一処不在の浮浪生活で、彼処に一泊此処に二泊、気に入れば三泊も五六泊もする。[中略]要するに、行き当りばたりであった。然し井月の立ち寄る家は[中略]殆んど一定してゐたやうでる。[中略]名望家とか、旧家とか、謂ゆる知識階級或は特に俳諧に趣味のあるやうな処許りに限られてゐた。[中略]そしてグルグル同じ区域を廻って歩いたのであった{『井月全集』344~345頁}
俳句の好きな旦那衆は、井月を厚くもてなしたという。
井月の俳句{筆者所蔵品}
井月のことをよく思わない人も多かった。汚らしい姿をしていたからである。・おとな達一般には「先生々々」と言はれてゐたやうである{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号14頁}・まづ盥を差出し足を洗ってもらい必らず座敷に招き入れました。[中略]そして好物の自家醸造の黄金水に肴、次に汁物と次々と御馳走しました。[中略]程良い処で硯紙を用意して御願いすると黙考すること暫く、草稿もせず例の達筆で認めると言う詩句書道の達人{『伊那路』昭和62年3月号139頁}・井月は酒が好き、ことに熱燗が好きであった。親椀一杯の酒が毎晩のオシキセ、それを喜んで、「ああ井月カンぢゃ、千両、千両。」といって、楽しさうに飲んだ{『伊那路』昭和39年3月号126頁}・瓢箪に酒をつめてやると「千両々々」で帰った{『井月全集』372頁}・強酒ではなかったやうだ。[中略]強ひれば可成り飲んだが、[中略]直ぐ泥酔して倒れた結果が、下痢やら寝小便で、祖母や母が迷惑をしたものである{『井月全集』346頁}
《どんな人物だったのか》・汚れた、だらしない風をしてゐると「井月のやうだ」といった。[中略]乞食のやうな人が通ると「井月のやうな人が通る」といった{『井月全集』372~373頁}・おそろしく垢によごれてゐたばかりでなく、ひどい虱がわいてゐた{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号2頁}・井月が来ると、たいへんでしたよ。まず玄関で、着ているものを全部脱がして、通りに沸かしてある風呂にはいってもらう。そうしないと、井月の着物はシラミの巣だからね。その着物は、私たちが盥の中で熱湯を注いで虫退治をして、井月には、別に用意の新しい着物を着せたんですよ。それから、はじめて座敷へ通して挨拶{『伊那路』昭和46年8月号309頁}・有名な虱の問屋で、何処へ行っても婦人などから極端に嫌はれた{『井月全集』345頁}・多くの細君は怖気をふるって居留守を使ったものである{『高津才次郎奮戦記』11頁}・そこのお婆様は、「天気がいいで、井月が来そうだから戸じまりをしておおき」とお嫁さんにいったと伝え聞く{『伊那路』昭和62年3月号133頁}・僅かに軒下で酒食を与へて戸を閉ぢてしまふといふやうな処もあって、相手どころか、気味の悪い乞食として忌み嫌った{『井月全集』345頁}・井月を別名乞食井月或は虱井月といってゐました{『人犬墨』47頁}
容姿については次のように伝えられている。「赤銅色」は日焼けした肌の色のこと。村から村へ歩き回っていたから日焼けしていたのだろう。・あの学問と文字と俳諧は何処で誰に学んだのであらうか。[中略]わざわざ無点の孝経を取寄させて自ら点をつけて教へた事や[中略]、唐詩などを諸処で揮毫して居る事や、その他彼の句や文によって漢籍を飜展した人であることは容易に頷かれる{『井月全集』398頁}・玉篇から特に難字を抜き出して問うたとき、「ははは、これは字引から出して試すのだな、これは」と言って、悉く正答した{『高津才次郎奮戦記』38頁}・井月が字を書く時や、印を押す時は酒のあとでも必ず端坐して苟もせず、そして人の居ぬ所で書くやうにした{『井月全集』371頁}・刀剣にはとても詳しく、学問の深い方だ、と聞いています{『漂鳥のうた』32頁}・「井月が、村の若者達に九尺柄の槍をつかって見せた」と云ふ口碑を聞いた。槍を手にした井月、いつもトボトボの彼に似もやらず、くり出す槍の穂のひらめきは電光の如くであった。それを見た人々はいづれも「さすがだ」と驚嘆したさうだ{『俳人井月』119頁}・碁も打ったが、決して汚い打ち方をしない{『高津才次郎奮戦記』13頁}
無口・無表情で、何を考えているのか分からない人と思われていたようだ。・彼は痩せてはゐましたが、骨格の逞しい、身長は私の父と比較して五尺六七寸ぐらひあったらうかと思ひます。[中略]頭の禿げた髯も眉毛もうっすらした質でありました。眼は切れ長なトロリとした少し斜視の傾きを持ち、[中略]鼻も口も可成り大がかりで、[中略]顔面は無表情の赤銅色で、丸で彫刻のやうな感じでありました{『人犬墨』44~45頁}・井月の色の黒さや時鳥{『井月全集』361頁。伊那市西春近の有隣の句}
かなり無頓着な人だったようで、数々の奇行が伝わっている。・彼は元来、極端な沈黙家であったばかりでなく、口をきいても低音で、而も舌がもつれて何を言ふのか明瞭に分ったことが少かった{『井月全集』346~347頁}・井月は来る時も往く時も別段に挨拶もしなかったと。[中略]人が居なくても黙って上り込み又黙って出て行ったりした{『井月全集』369頁}・あの人に限って、いつも顔色を変へた事がない{『井月全集』372頁}・井月ばかりは、平常すら酔てゐるのか醒めてゐるのか、時として死んでゐるのか、生きてゐるのか訣の分らぬことさへあった{『井月全集』347頁}
松尾芭蕉の『幻住庵の記』に「空山に虱を捫て座す」という一節があるから、もしかしたら、それを文字通り実践していたのではなかろうか。お金にも無頓着で、一文無しでも全然平気だった。・祖母が古い綿入羽織を着せてやった。[中略]三日許り遊んでの帰途、井月に出逢うたが、着せてやった筈の羽織を着てゐない。不思議に思ふて如何したのかを聴いてみると、乞食が余り寒さうに見えたから呉れてやったと平気なので、祖母も殆んど呆れてゐた{『井月全集』354頁}・古い夏羽織と袴とを贈った。夫から数日を経て、[中略]偶然井月の奇行を発見したのである。それは夏羽織を掬ひ網に代用して頻りに水溜りの雑魚を漁ってゐるのであった。[中略]試みに何をしてゐるかと尋ねてみた。『イヤ好い雑魚がをるので某家の土産に掬うてゐる』と平気な答へであった{『井月全集』358頁}・午後の五時頃「トボトボ」出掛けるので、今時分何処へ行くかと見てゐれば、[中略]萱原へ坐り込んで、何を見てゐるのか考へてゐるのか、日が暮れても動く様子がない。そこで塩握飯と酒を持せてやったが、握飯を一つ食うて酒を飲んで寝てしまうた。寒からうと云ふので[中略]空俵を頭から被せてやったが、身動きもしない、[中略]翌朝[中略]、空俵はあったが井月は居なかった{『井月全集』355頁}・或時井月が来て、落ちてる柿の葉を拾ひ、しきりに着物で擦って埃を落してゐる。何をするかと見て居たら、やがて家に入って妻女の前へそれを出して、「ハイお土産」{『井月全集』368頁}・河べり[中略]に井月が坐ってゐる[中略]。何をしてゐるのかと近寄って見れば、襤褸の襟の辺から虱を摘まんで前の石の上へ並べてゐるのである。[中略]如何にも悠々緩々と採っては並べ、並べては見てゐると云ふわけで、私も小半時見てゐたが人が居るとも感じぬらしい{『井月全集』354頁}
無頓着でありながら、次のような話も伝わっており、こだわりは強かったのだろう。プライドも高かったのかも知れない。・高遠の市へ井月が行くといふので、[中略]一文もなくて市へ行くのはといって笑ったら、即座に「一文の銭がなくても千両と人にいはれて心せい月」{『井月全集』371頁。井月と霽月(=雨上がりの月)をかけた洒落であろう}・火山峠山麓に[中略]紋十婆茶屋と云ふのがあった。[中略]或る時井月が例によって立ち寄った。老婆は待ってゐたと云はぬ許りに[中略]酒債の仕払ひを請求したのであった。[中略]井月は[中略]白紙を取り出し、[中略]一句を題し大形の印を捺して老婆に与へ、「さて良き証文が出来た。是なら私が死んでも屹度取れる」と云うたのである。老婆は[中略]不満ながらも其時一椀の粥を供養し、さて立ち去る時に、「最う来なさんな」と云うたが井月は後振り返って、「また来るよ」の一語を遺して、トボトボ去ったとのことである{『井月全集』360~361頁}
伊那谷の農村部で、普段から袴を着けているような人は、きっと井月くらいだったのだろう。村を歩けば変に目立つ存在だったに違いない。・袴だけは怎んなに汚れてゐても、裾がち切れてゐても、着けてゐた{『人犬墨』46頁}・どんな時でも袴は穿いて居たさうで子供が之を見ると「せんげつせんげつ」と呼んださうだ{『井月全集』373頁}
井月は、いったい何者で、なぜこんな暮らしをしていたのだろうか。また、若いころは何をしていたのだろうか。・五六人の友と小学校の帰り道に、偶ま井月の「トボトボ」とやって行く後姿を見つけたので、その腰にぶら下げてゐる瓢箪を擲石の手練で破ることに相談一決した。そこで大小手頃の石を盛んに擲ったが中々うまく当らない。悪太郎の吾々も少し焦れ気味で一層盛んにやってゐる中に、誰のが当ったか後頭部から血が流れ出した。が、井月は振り向いても見ず歩調も変らぬ。私はこの時非常な恐怖を感じたので、一生懸命後の方へ逃げ出した。すると、他の友達も私の後から逃げて来た{『井月全集』352~353頁}
長野県図(井月にゆかりがある主な場所)
明治二十年に数え年の六十六歳で没したのなら、逆算すれば文政五年の、午年生まれということになる。これを裏付ける次のような記事もある。・わぬしはいづこよりぞと問へば、こしの長岡の産なりと答ふ{『井月全集』284頁。『越後獅子』の序文に}・塩翁斎柳家井月居士 明治二十年三月十日示寂[中略]越後国長岡藩士族井上勝蔵ト申者、発句師柳家井月行年六十六才歿{『俳人井月』135頁、龍勝寺の過去帳に}
生家については、長岡市の千蔵院のそばに、井上という家があったらしい。刀研ぎの仕事をしていた下級士族と思われ、「刀剣にはとても詳しかった」という説と合致するように思われる。・未年の梅月が井月を一つ上の午年だと言って居た{『井月全集』406頁}
・長岡の町内中を、井上姓はないかと足を棒にしてさがしまわった。[中略]「たしかに観音様と田中さんの間に小さい細長い屋敷があったけど、[中略]あの家は下方のものだが、藩の方々の刀の磨師だったという事です。何んでも男の子が多くて、五、六人か七、八人もあったらしいが、誰一人家の跡をたてるものがなくて、一人前の手頃になるとどこへ行ったのか、出奔してしまったという事です」{『伊那路』昭和62年4月号194~195頁}
《江戸へ出る》
長岡の千蔵院。「千手の観音さま」として親しまれている。
人殺しをしたかどうかについては、今のところ検証する手立てがないし、軽々に事実と判断するには重すぎる問題であり、後考を待ちたい。「一斎」というのは、昌平黌(昌平坂学問所、東京大学の前身)の儒学者・佐藤一斎のことだろうか。井月は江戸で学問をしたのだろうか。・井月は確かに長岡藩士で、本名は井上勝之進といい、「十八のとき友をあやめ、兄に連れられて江戸に行った」と、あるとき、自ら語らざるを得ずして語ったと、とある確かな筋から聞いた{『高津才次郎奮戦記』85頁}・井月はよく幻住庵の記を書いたが、その文中の「奥州」を、有隣が「オクシウ」と読んだので、井月が「アウシウ」と直したが、有隣がなかなか承知しない。そのとき井月が「これでも俺は一斎の門人だからな」と最後に言い放ったという{『高津才次郎奮戦記』73頁}
俳句は、関為山(月之本為山)という江戸の有名な俳諧師に学んだという。・一斎の門人であるために唯一貴重な文献『升堂記』や『書生寮姓名簿』に記載されている名前から、井月(井上克三・勝造・勝之進・井上姓のつく名からの推測・長岡出身・高田出身など)を探した結果、見当たりません{『伊那路』2000年9月号346頁}
井月に妻がいたかどうかについては、次のような説がある。・桂雅が井月から貰ったものの中に、俳句は「為山」についたという意味の書きものがあったという{『伊那路の俳人たち』126~127頁}・為山の肖像画は早稲田大学古典籍総合データベース所蔵『青柳集』にある。
しかし俳句というものは、いくらでもフィクションで作ることができるのであり、それだけをもって事実とするのは慎むべきである。妻帯の裏付けとなる資料が他に出てこない限り、俳句作品からの想像にすぎないからだ。・妻帯したことの有無については、「妻持しこともありしを着衣始」の句があるから、恐く持ったことがあるのであらう{『井月の句集』略伝11頁}
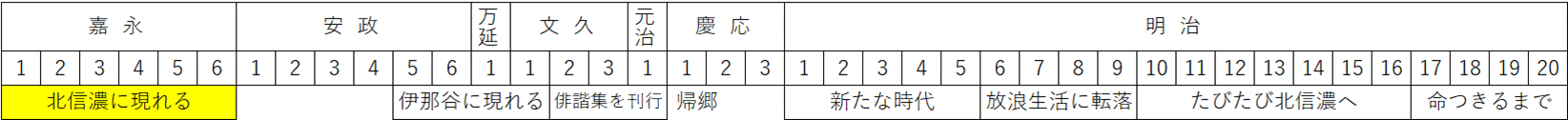
嘉永元年というのは、あくまで高巣の揮毫帳が起筆された年であり、井月の訪問が嘉永元年だったとは確定できない。なお、高巣の別号は「山敬」といい、のちに元治元年に井月が刊行した『家づと集』に載っている。・嘉永元[中略]中野市の石田正芳氏所蔵『高巣風雅帳、仮題』に「泥くさき子供の髪や雲のみね 井月」をこの年から数年のうちに揮毫{『新編井月全集』626頁}
北信濃の足跡で、はっきり年がわかっているのは次のものである。・山敬 姓石田 中野市安源寺の人。別号高巣{『長野県俳人名大辞典』384頁}・縞がらのはっと眼立や単もの 山敬{『井月編俳諧三部集』146頁}
木鵞は善光寺大勧進の役人。井月とどのような関係だったのだろうか。・嘉永五[中略]長野に於て吉村木鵞の母追弔詩歌を一枚刷にせる中に井月の「乾く間もなく秋暮れぬ露の袖」の句見ゆ{『井月全集』401頁}・嘉永六[中略]「稲妻や網にこたへし魚の影」の一句を載せたる、木鵞編句集「きせ綿」長野にて開版{『井月全集』402頁}
小布施町の豪商・高井鴻山と井月が交流していたとして、それが嘉永の頃かどうかは分からない。鴻山の家から出たという廃紙・短冊が、いつの時期の筆跡なのか、今となっては確認のしようがない。つまり、鴻山の紹介で木鵞の家を訪ねたという説は、想像の域を出ないものと思われる。・木鵞 吉村隼人[中略]大勧進納度役人、当時ノ名家也{『仏都古今雅人名士録』54頁}・高井鴻山[中略]の紹介を持って、大勧進に勤めている吉村隼人の家を訪ねた{『郷土読み物 井月さん』11頁}・高井鴻山の許に[井月が]厄介になって居たであらうことは、かつて、私が、鴻山の家から出た廃紙、短冊のうちに井月の筆跡を四五枚見つけたところから、「であらう」と考へたのである。当時の高井三九郎[=鴻山]の名は、天下に籍甚たるもので、志士、画家、詩人、剣客、あらゆる人々が[ここ、文脈が跳んでいる]途を小布施にとった者は、必ず鴻山の許に厄介になって居る。また、彼は、それらの訪問客を好んで、よく待遇した{『俳人井月』8頁}
つまり『きせ綿』は、ゆたか・はる雄という旅の二人組に、あたたかい綿入れを着せてあげようと、「諸君子のめぐみ」を集めるために作った本だったと考えられる。「勧進帖」とあるから、投句料を徴収し、二人への寄付金としたのだろう。ゆたかについては資料がなくて不明だが、はる雄は、江戸から来た「広田精知」という若き俳人である。・ゆたかはる雄の両子姨山の月見んとひさしく我草庵に杖をとどめ良夜も心の侭に過しおのがさまざまこしかたを語りあふ折ふし葉末をはしる露の音に次つぎ募るものからひとつ給伝の高吟を思ひ出てうらやむ両子の嘆息もむべにしてまたおかしく不図衣更勧進帖といえる事を吹すさぶ秋風のさとふで終へよう真冬心出たるを聞とがめそはよき幸なりとて序を乞ふ事頻にやまざれば遠近親疎の隔なく猥に秀句を梓にのぼせ馬のはなむけにせんとおこがましくも筆をとりて諸君子のめぐみをともにねがふ事とはなりぬ 信北鶴が里の片辺り 素月庵木鵞誌{長野県立図書館 関口文庫所蔵『きせ綿』序文}
はる雄は、嘉永のころ行脚俳人として北信濃にやって来て、善光寺の桜小路(現在の桜枝町)に住んでいたようだ。井月より六歳年下。若いながらもすでに著書がある秀才だったのだろう。そして、「為山門」とあるから井月と同門。つまり井月は、はる雄という同門の行脚俳人を支援するために、投句料を支払って『きせ綿』に投句したと考えられる。・春雄 俳 嘉永 桜小路 行脚シテ来テ此所ニ住シ、俳諧別世界三冊、其他ヲ著シ、后東都ヘ帰リ、改メテ語石庵精知ト称ス{『仏都古今雅人名士録』51頁}・精知(広田氏)[中略](文政十一年生)。東京の人。[中略]四時庵、のち、語石庵と称した。月の本為山門{『明治大正俳句史年表大事典』98頁}・はる雄(精知)の肖像画は早稲田大学古典籍総合データベース所蔵『画入ちり紅葉集』にある。
つまり嘉永六年の時点で、井月はまだ雲水(行脚俳人)になっておらず、江戸に家があったということになる。だとすれば、井月は諸国をさまよった末に信濃へやって来たのではなく、江戸から信濃へやって来たと考えたほうが自然に思える。行脚でなければ、単なる旅行者として来たのだろうか。たしかに当時、善光寺参りは、伊勢参りと並んで人気の旅行コースであり、参拝という名目ならば、わりと自由に旅行ができたらしい。笹ゆれてのち薄くなる霞かな 在ヱド 茶友
いなづまや網にこたへし魚のかげ 井月
たばこ盆持て川こすすずみかな 素交
{長野県立図書館 関口文庫所蔵『きせ綿』に}
のちに井月は、次のように回想している。・旅行には身元証明書とも言うべき「往来手形」が必要だったが、寺社参詣を理由にした旅行の場合は発給されやすかった{『江戸の旅行の裏事情』5頁}
信濃路で仏といえば、第一に善光寺だろう。「信濃にやって来たのは、善光寺のありがたさを慕ってのことだった。その後、伊那谷に足をとどめることになった」と言っているように思われるのである。・古里に芋を掘て生涯を過さむより、信濃路に仏の有がたさを慕はむにはしかじと、此伊奈にあしをとどめしも良廿年余りに及ぶ{『井月編俳諧三部集』239頁、『余波の水くき』の跋文に}
《北信濃の俳人たちと交流》
善光寺。今も昔も多くの参拝客でにぎわう。
『家づと集』は、のちの元治元年に井月が北信濃で作った本。その序文を書いた梅塘は、井月にとって北信濃における一番の恩人だったと考えて間違いない。大勧進の木鵞のところよりも、むしろ宝勝院の梅塘のところで世話になっていたのではなかろうか。・梅塘 純徳 月精舎 俳 茶[中略] 宝勝院ノ住僧ニテ、贅沢ヲ極メ貧乏ノ果ハ建具ヲ焚ヲ薪トセシト云フ奇僧、井月ノ家つと集ノ序ヲ書ク{『仏都古今雅人名士録』7頁}・肖像画は早稲田大学古典籍データベース所蔵『画入ちり紅葉集』にある。
このうち、梅塘・双鵞・木鵞は長野市の善光寺周辺の人、菊雄・潮雨・潮堂は中野市の人、嬌雨は長野市川中島の人。したがってこの時期の井月の活動範囲は、善光寺を拠点に、北は中野方面まで、南は川中島まで、ということになりそうだ。月の朧花に譲りて明にけり 信濃 梅塘{『井月編俳諧三部集』43頁}
花散て何処やら寒き月夜かな 菊雄{同書43頁}
門柳人の見るたび太りけり 鵞友{同書43頁}
恋猫や終には潜る枳殻垣 潮雨{同書43頁}
月花のためとこらへつ二日灸 シナノ 嬌雨{同書66頁}
ちりもなき畳を掃くや五月雨 ゝ 双鵞{同書66頁}
けふ明日と立日思ふや羽ぬけ鳥 ゝ 潮堂{同書66頁}
すずしさや灯並ぶむかふ河岸 ゝ 木鵞{同書66頁}
信濃の俳人の筆頭に梅塘が載っており、やはり井月の第一の恩人だったと考えてよいだろう。三番目に載っている鵞友については、次のような資料がある。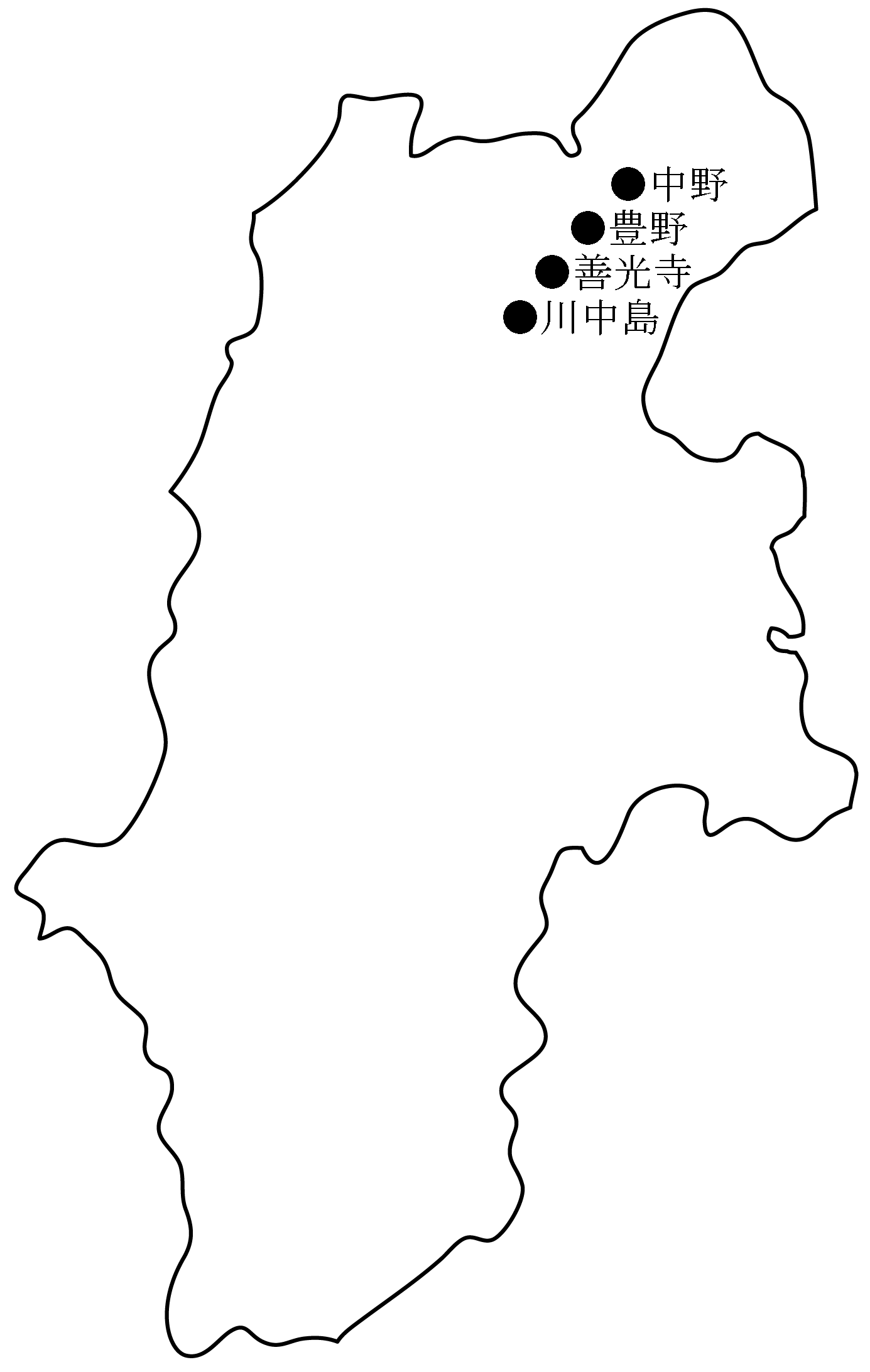
この句は井月の『越後獅子』に載っている句と同じであり、したがって鵞友と鵞雄は同一人物と考えて間違いない。峯村鵞雄という寺子屋師匠で、井月より五歳年上。・鵞雄句集[中略]門柳人の見るたびふとりけり{『一茶ゆかりの白斎と文虎』171頁}
豊野は善光寺と中野の中間地点。井月は、豊野の鵞雄の寺子屋「寒岳園」に滞在したこともあったのだろう。なお、鵞雄との交流は晩年まで続くことになる。・鵞雄 豊野町[現在の長野市豊野]石の人。[中略]文化十四年[中略]出生。[中略]白斎の寒岳園二世をついだ。[中略]弘化四年寺子屋を開き、明治六年まで近隣の子弟を教育した{『長野県俳人名大辞典』149頁}・鵞雄の肖像画は早稲田大学古典籍総合データベース所蔵『画入ちり紅葉集』にある。
中野市安源寺の高巣(=山敬)が『越後獅子』に載っていないのは、なぜだろう。高巣と井月が交流したのは嘉永ではなく、もっと後の『家づと集』刊行の頃だった、ということなのだろうか。後考を待ちたい。・潮堂 中野市間山の人。[中略]小蓑庵碓嶺の高弟。江戸に出て小蓑庵の執筆をつとめたが、行脚に出、諸国を巡った。嘉永以来の俳人番付や俳書にその名が頻繁に登場する。明治初年、長野県庁の設置とともに営繕掛、のち地券掛をつとめ功績があった。同十三年間山に帰り、□泉学校の創立役員として尽力。[中略]編著すこぶる多く、世人「本屋潮堂」と称した{『長野県俳人名大辞典』652頁。□は環境依存文字}
精知は、井月の人生を解き明かすためのキーマンと思われる。今のところ精知以外に、北信濃と伊那谷と井月を結びつける人脈は見つかっていない。・見に起る雨も花まつたより哉 イナ 精知{『井月編俳諧三部集』48頁}
つまり、嘉永七年(安政元年)から安政四年までの四年間の足跡が、何も伝わっていない。北信濃から伊那谷へ直接向かったのなら、何かしら長野県内に足跡があってもよさそうなものだ。この期間、信濃を離れていたのではなかろうか。宝勝院の梅塘のところを去ってゆくときのエピソードが、元治元年刊行の『家づと集』に載っている。・嘉永六[中略]木鵞編句集『きせ綿』[中略]に[中略]井月句載る{『新編井月全集』627頁}・安政五[中略]この頃には伊那に来ていたか。中沢村高見[中略]田村梅月のこの年調製「発句書抜帳」[中略]に井月選出の印あり{『新編井月全集』627頁}
「捨べきものは弓矢なりけり」は、武士をやめることを言っているのだろう。「入道の姿」は、松尾芭蕉が着ているような「道服」のことと思われる。つまり、羽織・袴の武士の格好をしていたはずの井月が、旅の俳人の姿になって挨拶に来た、と言っているのだろう。これこそ、井月が正式な行脚俳人になって旅立って行った、その瞬間の様子ではなかろうか。あるいは一旦江戸へ帰って身辺整理をしてから、行脚へ旅立って行った可能性もある。・捨べきものは弓矢なりけりといふこころに感じてや、越の井月入道の姿となり、前年我草庵を敲てより此かた、鳫のたよりさへ聞ざりしに{『井月編俳諧三部集』91頁、『家づと集』の序文に}
《この章のまとめ》・初虹や裏見が滝に照る朝日{『井月全集』11頁。栃木県日光市}・行く雁や笠島の灯の朧なる{『井月全集』17頁。宮城県名取市}・松島一景 塩竃のけぶりも立て朝ざくら{『井月全集』32頁。宮城県松島町}・象潟の雨なはらしそ合歓の花{『井月全集』64頁。秋田県にかほ市。芭蕉が訪れた最北の地}
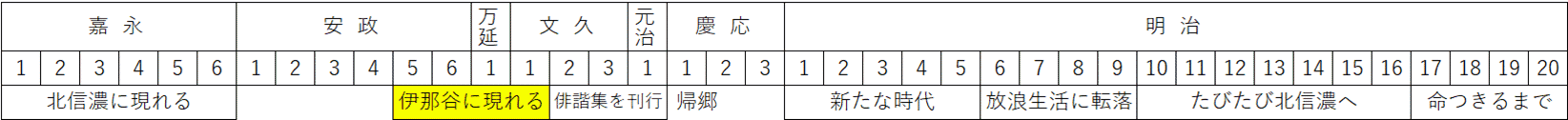
井月が選出したという梅月の句は、文久二年刊行の井月の最初の俳諧集『紅葉の摺もの』(まし水)に、実際に収録されている。・伊那峡へ入った時は、安政五六年、即ち彼の三十七八歳の時までしか今の所遡れない{『井月全集』401頁}・安政五[中略]中沢村[=駒ヶ根市中沢]田村梅月の此の年調製「発句書抜帳」中「桜木は葉にくもりしや杜宇」の句を井月選出の印あり{『井月全集』402頁}・梅月氏は近処の子供に寺小屋式の読み書きを教へてゐた{『井月全集』362頁}・梅月の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』にある。
つまり井月は、「俳諧集の作成」という明確な目的を持って、伊那谷にやって来たのだろう。決して放浪しに来たのではない。・桜木は葉にくもりしや杜宇 タカミ 梅月{『新編井月全集』490頁}
当時、プロの俳諧師になろうとする者は、行脚修行をした。行脚で出会った人たちから俳句をもらい集め、俳諧集を刊行したのである。そういう実績を積み重ねることで、一人前の俳諧師として認められるようになっていったのだろう。
上空から見た伊那谷。天竜川を中心に河岸段丘が広がる。
安政五年は、あくまで梅月が「発句書抜帳」を起筆した年であり、井月の訪問が安政五年だったとは確定できない。安政六年の可能性もあることに注意すべきである。・故根津芦丈翁は[中略]自らの体験も加えて行脚のやり方を説き、「行脚には、乞食行脚、上り端行脚、座敷行脚などと幾通りもある」などとその実際を説明し、基本は師匠の許状と添書とをもらって出て、旅まわりをするのが通常であると言っている{『伊那路』昭和63年11月号607頁。芦丈は、井月と交流があった馬場凌冬という俳諧師の門人}
井月の伊那谷出現が、安政五年ではなく安政六年だったとするならば、中川村四徳の桂雅の家で詠んだ「羽二重の袂土産や蕗の薹」の句が、伊那谷における井月の最初の活動痕跡ではなかろうか。「その後つけ加えられたものだろう」とあるが、なぜそう推測されるのか、根拠は示されていない。安政六年に井月が四徳に来ていたと考えて、なにか不都合があるのだろうか。・安政六年の晩春に、[中略]「こだま石の里独り案内記」または別名「四徳八景案内記」というものが書かれている。この案内記の作者は四徳の俳人の先達的な立場で活躍した「桂雅」である。[中略]末尾の井月の句はその後つけ加えられたものだろうと推測される。[中略]羽二重の袂土産や蕗の薹{『四徳誌』355~357頁}・桂雅[中略]井月より一六才年上[中略]、すでに松本・諏訪・下伊那・遠州・三州の俳友と交わる俳人であった。[中略]庄屋をつとめたことがある{『中川村誌』下巻416~417頁}・桂雅の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』にある。・梅月と桂雅は親類関係{『伊那路の俳人たち』118頁}
野月は安政七年の正月に喜寿祝いを行い、そこに井月が参加したようだ。無口な井月だったが、寺子屋師匠が相手ならば学問の話がはずんだであろう。「衆吟評募集通知」は、おそらく投句募集のチラシを作って配ったのだろう。・安政七[中略]正月二十七日同地[=駒ヶ根市中沢]野村野月喜寿祝帳に、井月へ返礼の品目を書けり{『井月全集』402頁}・野村野月の安政七年正月二十八日に祝った喜寿の控帳に「額面一、半切菊一、井月江」の文字がある。その他同年頃の衆吟評募集通知等に狂言寺井月評と記したものが遺ってゐる{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号9頁。なぜか二十七日ではなく二十八日に改められている}・野月 駒ヶ根市中沢の人。[中略]寺子屋を開き、近郷の子弟を教えた。元治元年十二月没{『長野県俳人名大辞典』860頁}
桂雅の蔵の棟木に揮毫した文面は、残念ながら伝わっていない。安政七年は万延元年と改められ、さらに万延二年は文久元年と改められた。・安政七[中略]南向村四徳小松桂雅方蔵の棟木に大書す{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号47頁}
葎窓は、朝夕庵野外という人物が文久二年に刊行した『寄傲集』に「雲客」として載っており、つまり行脚俳人。その野外も、武蔵から来た行脚俳人。・文久元[中略]十二月南向村[現在の中川村]四徳小松桂雅方にて桂雅、葎窓の連句を書く{『井月全集』402頁}
そして精知も、江戸から信濃へやって来た行脚俳人であった。つまりこの時期、井月のような行脚俳人が何人も伊那谷に来ていたのであり、井月だけが特別な存在ではなかったのだろう。逆に言うなら、当時の伊那谷は、井月のような行脚俳人が飛び込んでいけるような風土が整っていた、ということになる。・手づさびや菊打かざす下り坂 雲客 葎窓{飯田市立中央図書館所蔵『寄傲集』に}・きのふは旅けふは松棚居[=中川村田島の斧年という俳人]のすすめに庵を設られし野外叟はおなじ武蔵野においたちおなじ伊那にとどまるもふかき因なるべし 掬ひあふこころすずしき清水かな 精知{『寄傲集』に}
井月の句に十点満点が付けられている。「秋混題水車吟」がいつ行われたのか、はっきりしないが、この時点で井月は人からの選句を受ける側だったのであり、まだプロの俳諧師になりきっていなかったのではなかろうか。・井月、烏孝、菊麿、桂雅、雅卜、米月等が会して運座会[中略]を行った折の句を井月が上書して、井月がかねてから敬慕していた朝夕庵野外先生の評を受けた「秋混題水車吟」が残されており、当時の俳人が、井月を交えて句会を楽しんだ様子を細々と伺い知る事ができるのである{『四徳誌』353頁。なお菊麿・米月の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』にある}
・「秋混題水車吟」は、井月筆蹟で、朝夕庵[中略]選のようである。[中略]句の下の数字は点数である。
すみ切らぬ此河かみの砧かな (10) 烏孝
あしの葉にとまり流るる蜻蛉哉 (10) 桂雅
いへぶんのなき空相や赤蜻蛉 (10) 井月
夕隈のきれた処へ後の月 (10) 桂雅
此晴を独で見るや後の月 (10) 烏孝
山寺に入日を残す紅葉哉 (10) 菊麿
{『井月の俳境』147~149頁}
すでに道服をやめ、武士の姿に戻っていたようだ。そのほうが肌になじんでいただろうし、関所や番所の取り調べを通過しやすかったのかも知れない。・初めて伊那へ来た頃は、紋附黒羽二重の小袖に白小倉の袴菅の深阿弥笠といふやうな、まるで尾羽打ち枯らした芝居の浪人染みた物凄い出立ちであった{『井月全集』345頁}・初の頃の井月はぶッさき羽織に袴を穿ち、樫の木刀をさして居た{『井月全集』373頁。なお、井月の木刀は現存する。『手紙で読み解く 井月の人生』243頁に写真を載せておいた}・初め逢った時は史山と云う男と一緒だったし、黒の小袖を着込んで大小をはさんでいた{『流浪の詩人 井月の人と作品』6頁}
『たびぶくろ』の刊行年は不明だが、安政五年に没した西馬という著名俳人が序文を書いている。西は九州から東は奥州までもれなく行脚しており(『たびぶくろ』の本文を見ると松前の人が載っているから、蝦夷地にも行っていたのだろう)、つまり史山は、安政以前に相当の行脚修行の実績があったと思われ、井月より格上の俳諧師と考えてよいだろう。・雲衲史山はるばると東都に携へ来れる一嚢あり。風伯が背負て寒中にはしり長汀子が荷ひて市場に遊べるたぐひにあらず。これを紐ときてこまやかに見るに西は瓊浦のみるめ東は金華山の砂子迄もらさず拾ひ入し福やかもの也。そをむなしく吾弊庵の柱に掛おかむよりはやく同好の手をやとひて玉藻をつらね真砂をえらぶにしかじとかの括嚢咎なしの一言をうち誦して筆をさしおくのみ。惺庵西馬{史山編『たびぶくろ』序文、岡山市立中央図書館所蔵}
戌のとし弁慶庵にて 穂芒も月も親子の記念哉 史山
おなじく 笠石に寂をしれとや秋の風 井月{『手紙で読み解く 井月の人生』251頁。「親子」とあるが、史山と井月が親子だったわけではない。芭蕉の弟子・広瀬惟然が、妻子を捨てて仏門に入った、という逸話に寄せて詠んだ句であろう。「笠石」は弁慶庵の庭にある笠塚のこと}
井月の最初の俳諧集である『紅葉の摺もの』(まし水)を見ると、東海方面だけでなく、京都や大阪の俳人も載っているから、関西方面まで足を延ばした可能性が高い。かつて史山が刊行した『たびぶくろ』には、京都の堤梅通、八木芹舎、大阪の藤井鼎左、岸田素屋など、トップクラスの俳諧師が何人も載っている。史山が井月を案内し、紹介することも十分可能だったであろう。
弁慶庵。岐阜県関市。
・文久二年壬戌三月十五日 堤梅通花下宗匠御免許ニ付花御会相勤候{『二条家俳諧 資料と研究』202頁}・まし水や河原ながるる花のちり ラク 梅通{『新編井月全集』475頁}
文久二年といえば、尊王攘夷運動が吹き荒れていた頃である。横浜では生麦事件が発生、京都では勤王派による暗殺事件が横行、寺田屋騒動もこの年。治安悪化に手を焼いた幕府が京都守護職を置いたのもこの年。そんな物騒な折に、のこのこと俳句をもらいに行ったりして、大丈夫だったのだろうか。
東海・関西方面の足取り。『紅葉の摺もの』を元に作成。
・大阪御天守台に初て昇りて 是がその黄金水かほととぎす 柳の家井月{『井上井月真筆集』41頁}・素屋 岸田氏。[中略]大阪の人。[中略]旧幕時代大阪城代に仕えたという{『近代俳句のあけぼの』第二部191頁}・名月や酌とり眠るゑんのさき ナニハ 素屋{『新編井月全集』476頁}
ただし、井月が詠んだ大阪城の俳句は、晩年の筆跡で書かれており、次のような説もある。
大阪城の金明水井戸。かつては黄金水と言ったらしい。
晩年半年とは、いつのことなのだろうか。明治維新後、大阪城の跡地は陸軍の訓練場として使われたというから、なおさら観光で登ることができたとも思えない。・此の句は大阪城趾の廃墟に立った時に、豊太公の盛時を偲んだ追想句である。[中略]晩年半年位い伊那を去ったことがある。其の帰り土産の句として所々に此句を書いた短冊がある。晩年作でたどたどしい筆蹟であることはたしかだ。若い時に一度旅行した関西の風光を慕い、再び老の杖を曳いたものらしい{『俳人井月探求』57頁}
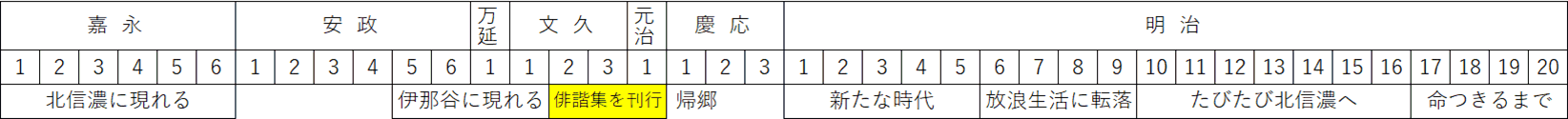
手紙には「閏月廿日」としか書かれていないが、野月は元治元年に没しており、その前の閏月は文久二年閏八月が該当する。井月の最初の俳諧集である『紅葉の摺もの』(まし水)は、文久二年の九月に刊行されている。よってこの手紙は、その製作依頼に行くときに出されたものと考えて間違いない。・両三日中には飯田え罷越、早々出来候様右連中へ御取持御願申心得罷在候。十三夜前には配呈仕度、又々其節は罷出御厄介に罷成可申候間、何分よろしく奉希上候。此度は梅月君え別書差上不申候間、尊君より宜奉願上候。[中略]閏月廿日[中略]野月老人様[中略]従四徳反哺庵{『井月全集』320頁}
「后の月」は旧暦九月十三日の名月のこと。だから手紙に「十三夜までにはお配りしたい」と書かれているのだろう。東海・関西方面への行脚を記念する句なのだろうか。「松風」からは、須磨の松風村雨堂や、源氏物語の明石の君が連想される。井月は、敬愛する松尾芭蕉の足跡をたどって須磨・明石まで足を延ばしたのだろうか。もっとも、これは俳句作品からの想像にすぎないから、断定は避けるべきであろう。・后の月松風さそふひかりかな 雲水 井月{『新編井月全集』502頁}
そもそも井月が伊那谷に現れたのは、精知に俳諧集の製作を依頼するためだったのではなかろうか。はじめからそのつもりで、伊那谷で俳句をもらい集めることにしたのではなかろうか。何の人脈もない土地へ、何の目的もなくやって来たとは考えづらい。のちに井月は、次のように回想している。
『紅葉の摺もの』(まし水){筆者所蔵品}
つまり、「最初は飯田に杖を曳き、そのあと高遠」だったと、井月自身が言っているのだ。井月の伊那谷における最初の足跡は、駒ヶ根市中沢にあると言われてきたが、失礼ながらそんな鄙びた山里をはじめから目指して来たとは思えない。それよりも、「まず北信濃で接点があった精知を頼って飯田城下に現れ、そこから北上して、中川村田島あたりで街道をそれて四徳へ入り、折草峠を越えて駒ヶ根市中沢へ、東伊那へ、高遠城下へと活動範囲を広げていった」と考えるのが自然ではなかろうか。・抑拙叟御当郡江曳杖の最初は、今を去る事拾有五年、飯田におゐて紅葉の摺ものの挙あり。高遠にては、越後獅子集をあむ{『井月全集』515頁、明治九年に書かれた『柳の家宿願稿』に}
『井月全集』の編者である高津才次郎氏も、次のように考えていたようだ。
『紅葉の摺もの』を元に作成した初期の井月の足取り。
北信濃から伊那谷へ直接やって来たのではなく、嘉永七年~安政四年の「空白期間」にどこで何をしていたのか分からないが、いったん長野県外へ出て、美濃から飯田へ入った可能性はゼロではない。この高津氏の説、一考に値すると思われる。・高津氏は飯田附近、南向村[現在の中川村]四徳方面に、[井月の]最初の交友が多かった為め、あるいは美濃路より入ったのではないかと疑を存して居られる{『俳人井月』131頁}
《精知の人脈》茸がりや山ふところの小酒もり イイダ 圭布
つり鐘に打つけて見る木のみ哉 巴丈
聞た名のしるしおほせず菊畠 欣祇
我ばかり日かげに立歟紅葉狩 赤峨
入相や時雨しあとの松に風 素星
いなづまや竹にすずめの十ばかり 梅枝
うら門やもみぢにゆるす片扉 素仙
夕日さす紅葉にすむやかねの声 稀星
家路へはつづらをりなり葛の花 穂浪
もみぢのみ夕日さすかと思ひけり 鳩山
丘に来て朝寒き鵜の雫かな 精知
菩提樹のふる葉ちる日や杜宇 タジマ 坂雅
あは雪やしばしそれにも松のかげ ゝ 石坡
立ながら姿やつるるかかしかな ゝ 完斎
鐘過て茶の水くむや春の雨 シトク 樵雨
水鳥のふまへて立や山のかげ ゝ 柳遊
わらぶきの家に過けり梅に月 ゝ 米月
朝ゆふた髪にちりつく桜哉 ゝ 雅卜
山はまだ花の香もありほととぎす ゝ 思耕
山寺に夕日をのこすもみぢ哉 ゝ 菊麿
床ひとつ持まわしけり松の月 ゝ 三休
朝な朝な日かげひろがるわか葉哉 桂雅{四徳の人}
雲行にまかせてまふや秋の蝶 清暉{田島の人}
珍客の□このむしぐれかな 烏孝{四徳の人}
葉の染る樹よりおこりて月の雲 斧年{田島の人}{『新編井月全集』497~502頁。末尾の桂雅・清暉・烏孝・斧年には、あえて地名が書かれていない。つまりこの四名は、井月と共に制作した側の人たちと思われる。□は環境依存文字}
「文久三年」と書かれているが、この説は改めなければならない。飯田市立中央図書館に『未の春』(末の春)と題された精知の歳旦帳が収蔵されている。未年は安政六年か明治四年だが、幕末に亡くなっている人物が載っており、つまり安政六年の刊行と特定できる。・語石庵精知[中略]文久三年頃飯田へ来り裏町に住んで版下を本業とし家内は貸本家を営む{『伊那の俳人』116頁。裏町というのは扇町の奥まった一画}
桂雅・烏孝については、次のような資料がある。よき人のよくなじみけり花の山 シトク 桂雅
とし暮てめでたき老の白髪哉 烏孝
{飯田市立中央図書館所蔵『未の春』歳旦帳に}
つまり桂雅・烏孝は、かねてから飯田俳壇とつながりがあった人たちで、そこへ北信濃から精知がやって来て、交流が始まったのだろう。もしかしたら井月は、精知の紹介で四徳へ出入りするようになったのではなかろうか。さらに烏孝については、次のような資料もある。・この二人は、天保時代の初期[中略]頃に飯田方面に出て、多くの俳人[中略]に交わり、俳諧の道を学び、それを四徳にひろめたのではないかといわれている{『四徳誌』349~350頁}
すなわち、中沢の野月と四徳の烏孝は師弟関係だった。それで井月は、折草峠を行き来して交流していたのだろう。もちろん梅月と桂雅が親類関係だったこともあるだろう。・烏孝[中略]上伊那郡中川村四徳の人。[中略]精知とは特に親しかった{『長野県俳人名大辞典』74頁}・石原の善作[=烏孝]は高遠藩中沢郷の野村清兵衛[=野月]に学び、手習い師匠を兼ねた{『志登久誌』274頁}
しかし『紅葉の摺もの』を見ると、宮田の俳人は山圃一人しか載っていないし、街道筋の伊那部・赤穂・飯島などの俳人は一人も載っていない。つまり山圃は、宮田宿や街道筋の俳人を一人も紹介せず、遠く離れた中沢の梅月を紹介したことになり、とても不自然に思える。山圃と梅月が俳友だったことを示す資料も未見。・菊つくり稲つくるとは見へぬなり ミヤダ 山圃{『新編井月全集』484頁}・井月は、伊那谷でまず街道筋の宮田に山浦山圃を訪ね、そこで中沢の俳友、田村梅月を教えられる{『中川村誌』下巻416頁}
このうち、青坡・圭布・梧芳の三名は下伊那の俳人で、間違いなく井月は俳句をもらいに行っている。氷りつく靄の雫やうめのはな イナ 青坡
老たりと見られて嬉し花のかげ 圭布
原中をながるるほどや忘れ霜 梧芳
あそぶ日のこころあてあり春の雨 我蝶
静さはいろにこそなれさく桔梗 蒼芦
{長野県立図書館 関口文庫所蔵『きせ綿』に}
圭布は別号を圭斎といい、阿智村の宗円寺の住職。ただし井月が現れたころには飯田城下に移り住んでいたものと思われる。井月より十五歳年上で、当時の飯田を代表する俳人であった。『紅葉の摺もの』『越後獅子』に載っている。・青坡[中略]下条村吉岡の人。[中略]栗矢村の井原九右衛門の長男に生まれ下条村吉岡の新井家をつぐ。農閑に句作、手習師匠をつとめた。文久三年七月十日没{『長野県俳人名大辞典』541頁}・武栗葵悠の両子息{青坡追善『おち穂集』(筆者所蔵品)序文に}
梧芳は泰阜村の人で、おそらく手習い師匠。『紅葉の摺もの』に載っているが、その後の井月の俳諧集には載っておらず、つまり一度訪ねただけの付き合いだったのではなかろうか。・蕉花堂圭斎[中略]伍和村宗円寺[中略]第十三世住職となり、[中略]明治維新前より飯田常磐町旧野村邸内に閑居、[中略]明治二十年六月[中略]享年八十一歳{『伊那の俳人』83頁}・圭布[中略]下伊那俳壇の名士である{『長野県俳人名大辞典』289頁}
あとの二人、すなわち我蝶・蒼芦は上伊那の街道沿いの俳人だが、『紅葉の摺もの』に載っていない。この事実は、初期の井月が「飯田から北上し、中川村田島あたりで街道をそれて四徳に入り」という説を裏付ける傍証と思われる。・梧芳 本名牧島俊蔵[中略]泰阜村唐笠の人{『長野県俳人名大辞典』334頁}・唐笠村 牧島塾{『泰阜村誌』上巻384頁}
蒼芦は辰野町の長久寺の住職。井月より七歳年上。『一棹庵蒼芦撰奉額句集』(筆者所蔵品)には、長久寺がある宮木のほか、平出・上平出・沢底・横川・渡戸の人たちが載っており、つまり辰野町でかなり広く勢力を持っていた俳人なのだろう。井月の『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』のいずれにも蒼芦は載っていない。・我蝶 飯島町田切の人。[中略]聖徳寺十三世住職[中略]。三十二、三歳の頃眼を患い、横浜の外人医ヘボン[ローマ字で知られる人物]に治療をうけ、豪商田中平八[天下の糸平]の家に滞在した。この時左眼が失明している。[中略]明治二十四年一月没。六十九歳{『長野県俳人名大辞典』147頁}
ただし井月は、蒼芦のところを訪ねなかったのではない。訪ねて行ったが門前払いをくらったらしく、それ以来、辰野町方面には寄り付かなくなったと思われる。・蒼芦 辰野町宮木の人。[中略]文化十二年辰野町平出に出生。[中略]宮木の長久寺十八世住職{『長野県俳人名大辞典』607頁}
《生涯の友》・宮木宿長久寺の現住蒼炉子を訪ふに飯焚の女ひたすら留守のよしを断りて更にとりあはざるに座敷にて囲碁の音しければ一句を残して去ぬ 花に客しらで碁をうつ一間かな 井月{『井上井月真筆集』24頁}
伊那市美篶末広の梅関は、井月より六歳年下。のちに井月は梅関のところで生涯を閉じることになる。つまり梅関は、最初期から最後まで井月の面倒を見てくれた人なのだろう。遠近のかねや野わけの吹だるみ 大シマ 梅関{『新編井月全集』483~485頁。「大シマ」は、現在の伊那市美篶のうち上大島・下大島を合わせた呼び方。梅関は伊那市美篶末広の人だが、『みすゞ』現代編34頁の図によると、文久三年に上大島村から末広村が分離している。『紅葉の摺もの』は文久二年の刊だから「末広」と書かれていないのは当然、ということになる}
雲はづれはづれて月にふけにけり アヲシマ 柳川
不二見へぬ日に藻の花の白みけり 火山 若翠
伊那市美篶青島の柳川は、井月より八歳年下。井月の俳諧集や歳旦帳などには、必ずと言っていいほど柳川の名が載っている。つまり井月にとって生涯の支援者だったと考えられる。・塩原梅関 俳人。[中略]明治三十三年没、享年七三歳{『井上井月研究』335頁}・梅関の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『信陽俳諧名家集』にある。
駒ヶ根市東伊那の若翠は、井月より十七歳年下。やはり井月の俳諧集や歳旦帳などに、必ずと言っていいほど若翠の名が載っており、柳川と並んで井月にとって生涯の支援者だったと考えられる。・翁柳川 明治時代の俳人。天保元年[中略]生れ、[中略]井月には作句の指導を受けたが、また井月の為には良き後援者でもあった{『長野県上伊那誌4人物篇』89頁}・柳川の肖像画は伝わっていない(御親族に確認済み)。
《第二俳諧集『越後獅子』》・下平若翠 俳人。天保十年火山村[中略]に[中略]生れた。生涯俳句に親しみ、[中略]昭和七年四月九十四歳で歿した{『長野県上伊那誌4人物篇』222頁。井月の門人の中で最も長命だったと思われ、『井月全集』刊行のときも存命だったはず。しかし惜しいことに、若翠と井月の交流を物語るエピソードはほとんど伝わっておらず、後掲の書簡があるのみ}・此度珍敷掛物持参被致候間御みせ申上度、[中略]当人持参の掛物は御両所の内ならではとぞんじ候間、何分御取持御買入の程伏而奉希上候。代料の処は当人に御相談可被下候。柳の家井月拝 若翠君 吐月君 尊下当用{『井月全集』311~312頁。井月が若翠らに掛軸の購入を勧めた書簡。ちなみに吐月は『長野県上伊那誌4人物篇』542頁に馬場伊三郎という名で出ており、東伊那の村長にまでなった人}・若翠の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』にある。
前作『紅葉の摺もの』の刊行から、わずか八か月後であり、ずいぶん立て続けの刊行のように思われる。その中に、次のような不穏な連句が載っている。
『越後獅子』{筆者所蔵品}
「ぬれ衣」とあるから、井月に何らかの嫌疑がかかっていたようだ。しかし、そんな不名誉なことを、なぜ井月はわざわざ自分の本に載せたのだろうか。そして、どんな嫌疑だったのだろう。身にかかりし去年のぬれ衣も着更る日とはなりにければ
晴たれば声猶高しほととぎす 野笛
雫重げに見ゆるわか竹 井月
{『井月編俳諧三部集』73頁}
この記事は“聞き書き”であり、資料としての確かさに疑問があるが、しかし「二年もつづいた」からこそ、連句にも「去年のぬれ衣」と書かれているのだろう。そういう細かい点が合致しているのだから、まったくのデタラメとも思えない。隠密(スパイ)かどうかはともかく、コソ泥や食い逃げといった類ではないのだろう。次のような資料もある。・文久年というと[中略]、藩では井月に隠密の疑がかかって居り、しきりに内偵を進めていた。こんな時期が二年もつづいたという{『伊那路』昭和49年3月号87~88頁}
『歌の中山吾妻物語』は、幕府を批判した小説であり、勤王派の志士たちが好んで読んだらしい。そんなものを筆写したとなれば、不穏分子の嫌疑がかかってもおかしくない。・高津氏の書簡より「歌の中山吾妻物語」写本別便貴覧に入れます。これは井月の作ではなく写したものらしく而して原作者は未詳 写したのは多分文久頃四徳滞在中かと思ひます。ともかくかう云ふものを写すことに彼が勤王の心持ちの動いたことは想像されます{『俳人井月』142頁}・これもいくばくかの酒銭となった筈で、ほとんど筆耕ともいうべきものである{『井月真蹟集』74頁}
一介の行脚俳人にすぎない井月に、しかも嫌疑がかかっている井月に、なぜ藩の重臣が序文を書いてやったのだろう。・岡村菊叟[中略]寛政十二年九月九日信濃国高遠に生る。[中略]藩の砲術総師範となる。[中略]天保十一年藩の執政となり[中略]齢六十にて致仕したれど維新の際再召されて藩政に参与せり。[中略]和歌、俳諧を嗜み古学に志す{『千曳の巌』巻末に}・菊叟の肖像画は『千曳の巌』のほか、『長野県上伊那誌4人物篇』86頁にある。
一読して不自然な文章だ。まだ見たことのない土地なら、「名物は何か」「家族はどうしているのか」などと問うのが普通だろう。それなのに菊叟は「特に問い聞くべき点もなかった」と言っており、実にそっけない。・文久三年のさつき行脚井月、わが柴門を敲て一小冊をとうで序文を乞ふ。わぬしはいづこよりぞと問へば、こしの長岡の産なりと答ふ。おのれまだ見ぬあたりなれば、わけてとひ聞べきふしもなし{『井月編俳諧三部集』29頁、『越後獅子』の序文に}
「あかし文」とある。井月はこの『越後獅子』によって、身の証しを立てることができ、ぬれ衣は晴れたのだろう。なお『越後獅子』は、広田精知ではなく井月本人の筆跡で書かれている。井月にかけられた嫌疑を晴らすための「あかし文」なのだから、井月本人の字で書く必要がどうしてもあったのだろう。・足をそらに国々をかけ巡りたるあかし文なれば、これもかの角兵衛がたぐひならんかと、此小冊に越後獅子とは題号しぬ 鶯老人{『井月編俳諧三部集』29~30頁}
「補助」「荷担」の八名は、井月と共に『越後獅子』を製作した側の人間と考えられる。『越後獅子』は、井月一人の力で作り上げたものではなく、多くの仲間たちに作ってもらった本だった、と考えなければならない。特に、末尾の野笛は「ぬれ衣」の連句を詠んだ張本人だ。どんな人だったのだろうか。ひはひはと咲ととのひぬけしの花 補助 斧年{『井月編俳諧三部集』81~82頁。なお三休・雪庭の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』にある}
苗代や寒さを分る風のふく 烏孝
薄雲の押へて低し花の家 清暉
さそはれて誘引かへすや翌日の花 三休
柳には斯は冴まじ梅に月 桂雅
田一枚もって嬉しやはつ蛙 荷担 雪庭
士峰ばかり残して雪は消にけり 紫川
朝霧に世に山はなし不尽の山 野笛
文久二年刊行の『紅葉の摺もの』には、野笛を含め、駒ヶ根市東伊那の人が二十三名も載っている。つまり当時、井月は東伊那にかなり大きな人脈を築き上げていたと考えられる。その東伊那の名士である野笛が、「ぬれ衣」をかけられて窮地に陥った井月を助けるために、一肌脱いでくれたのではなかろうか。用水路や通船の事業を成したということは、相当な財力と手腕を持った人物と考えられる。高遠藩の重臣に働きかけることも、あるいは可能だったかも知れない。・野笛は伊那村[=駒ヶ根市東伊那]の人 名は唐沢市作{『井月全集』135頁}・唐沢市作 利水家。文政四年頃伊那村[中略]に生れた。[中略]用水路の開鑿にまた天竜川通船に、この時代の事業家として活躍している。明治二十九年十一月七十余歳で歿した{『長野県上伊那誌4人物篇』125頁}
つまり桃五は、越後出身で京都に定着した行脚俳人。井月とどういう関係だったのか、後考を待ちたい。・越の桃五は年頃俳路に巡遊してもの広う取聚めたる句ども笈浚と題してはじめ次ぎのまきはとく編集せしが此ほど宮古に杖を停め{桃五編『笈浚集』三編(安政六年刊)序文。「宮古」は岩手県の宮古市ではなく「都」の当て字であろう}
だとすれば、井月は「ほととぎす・・・」の句にどんな意味を込めたのだろうか。おそらくは「嫌疑が晴れ、ぬれ衣を脱ぐ日がきた」という喜びを、遠回しに詠んだものと思われるが、これは俳句作品からの想像に過ぎないので、本当のところはわからない。・因深き井月叟の帰郷を祝して 行戻り明りひきけり花木槿 野外{『井月編俳諧三部集』68頁}
「翁」とあるから、芭蕉の名を借りて作句の心得を説いたものと思われる。プロの俳諧師としての権威付けのために、秘伝書を持ち歩くようになったのではなかろうか。・句の姿は青柳の小雨にたれるがごとくにして、折々微風にあやなすもあしからず。附ごころは薄月夜に梅の匂ひるがごとし。情は心裏の花をも訪ね真如の月をも観ずべし。翁 文久三亥皐月 雲水 井月陳人{『伊那路』昭和57年2月号52頁}・此教示世に珍しき伝なれば尊むべし。なほ他言他見をゆるさず。文久三亥 皐月 雲水 井月道人{『伊那路』昭和57年2月号54頁}
井月は『俳諧正風起証』を伊予の俳人から授かったという。・こうした秘伝書めいたものは、当時の俳人の多くが伝え持っており、俳諧の宗匠としての権威を保つための小道具としても利用されていた{『伊予の俳人たち~江戸から明治へ』60頁}
おそらく前年の、東海・関西方面への旅のときに、尾張あたりで米海に出会って、『俳諧正風起証』を授かったのだろう。ただし米海がどんな人物だったのか、資料がなくて不明である。伊予の桃地氏といえば、松尾芭蕉の母方の家系であろうか。・俳諧正風起証と申は行脚米海が授也{『井月全集』315頁}・「伊予の行脚米海桃地氏、由緒ありて伝授之」[中略]「尾州一日市場、石田源助号豊屋素陽」[中略]井月と関西方面との交渉を語る稀覯の[中略]資料であらう{『井月全集』316頁}
文久三年十一月、井月は駒ヶ根市中沢の野月の息子・鶴鳴に、芭蕉の弟子・向井去来の『柿晋問答』という俳論書を見せたという。プロの俳諧師として、こういった俳論書を持ち歩いていたのだろう。奉納裏に文久三亥菊月吉祥日、高遠領高見邑玉留屋甚四郎、行脚井月執筆とあり
世の中を手に乗て見る稲穂哉 梅月
照降もなき三ヶ月の友 井月
[中略]
{『井月全集』150~151頁。玉留屋は梅月の屋号}
文久三年十二月、飯田の広田精知が『とくさかり』という俳諧集の初編を刊行しており、その巻末を見ると、『秋混題水車吟』で選者をした朝夕庵野外の句と並んで、井月の句が載っている。先輩俳諧師と肩を並べるようになったのだろう。・文久三[中略]十一月、中沢高見の野村鶴鳴家に泊まり、古今名士の話をした際、携行の『柿晋問答全』を見せる。鶴鳴はこれを書写{『新編井月全集』628頁}
同じく文久三年の冬、中川村四徳の烏孝が『百家このみ袋』を刊行している。四徳近辺・下伊那・諏訪の俳人が似顔絵つきで載っていて、画風から諏訪の著名俳人・岩波其残による似顔絵のように思われる。烏孝・井月・精知による連句が載っているが、残念ながらこれら三名の似顔絵はない。苫舟に初冬らしきけぶりかな 井月{飯田市立中央図書館所蔵『とくさかり(阿智)』巻末に。刊行年は書かれていないが、阿智の武栗が序文に「集名の儀木賊苅と被成ては如何[中略]十二月」と書いており、初編と思われる。一方、同館所蔵の『とくさかり(諏訪)』には、諏訪の岩波其残という俳人が序文で「去年の冬とくさかりてふひととぢをものしてまたことしつづきの巻を[中略]元治はじめのとし」と書いており、つまり続編と思われる。よって『とくさかり(阿智)』は前年の冬、すなわち文久三年十二月の刊行と推定できる}
うき芝を根にして厚き氷かな 野外
ほかに井月の俳句も載っている。萩のつゆ居ごころしまる夕べ哉 烏孝{飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』に。『井月全集』150頁}
たておくれたる窓の月代 井月
秋もはや捨餌あらそふ鵜の痩て 精知
文久四年は元治元年と改められた。六月、伊那市長谷市野瀬の稲荷社に、井月は俳額を奉納している。井月のすぐ前に載っている春月という人物が発起人。遠山の初雪見する日和かな 雲水 井月{飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』に}
この仕事をしたあと、伊那谷に別れを告げ、北信濃へ戻って行ったと考えられる。・于時元治元年甲子六月吉日 行脚 井月書
[中略]
笠をとる宿のはづれや夕桜 春月
松風を押へて藤の盛りかな 判者 井月
{『伊那路』2004年4月号136~139頁}・井月は、元治元年六月にこの俳額を書き上げて、すぐ長野市善光寺へ赴き、約百日滞留、合著句集『家つと集』を出した。[中略]活発な文学活動を始めていた意欲的な時期であった{『伊那路』2004年4月号140頁}
・西村春月[中略]俳額奉納の元治元年[中略]には二二歳であった。この若さで発起催主の一人となり、活発に俳諧活動を展開していたらしいことは驚きである{『伊那路』1996年5月号204頁}
これは、第三俳諧集である『家づと集』の序文である。狂言寺というのは井月の別号。「風談日を重ね」とあるから、梅塘の宿坊に井月は泊まって、親しく語り合ったのだろう。しかしずっと滞在していたのではあるまい。夏に再会し、秋までに「諸家の玉葉」を拾い集めたと書かれている。つまり、北信濃のあちこちへ、俳句をもらいに出かけていたと思われる。「家づと」は手土産のこと。梅塘は、この俳諧集を手土産にして故郷へ錦を飾りなさいよ、と言っているのだろう。・今年水無月の末、暑いと堪がたき折から、笠を脱、杖を置音に昼寝の夢さめ、誰ぞと問へば、狂言寺とことふ。いつも替らぬけなげさに風談日を重ね月を越て、秋も良碪の音の遠近に澄わたるころ諸家の玉葉を拾ひ集め、梓にものして、古郷へ錦を餝るの家づとにすすむる事とはなりぬ。元治甲子菊月 梅塘{『井月編俳諧三部集』91~92頁}
『越後獅子』とは違って、『家づと集』には地名が細かく書かれており、特に長野市・中野市あたりの俳人が数多く載っている。井月自身の筆跡で版下が書かれており、製作は長野市長沼の彫り師に頼んだようだ。
『家づと集』{筆者所蔵品}
では、夏から秋までのおよそ百日間で、どこまで俳句をもらいに行っていたのだろうか。まずは戸隠方面へ行ったであろう。・長沼 鎮築橋本 塚久刀{『井月編俳諧三部集』166頁}
「清水」は夏の季語だから、梅塘と再会を果たした六月(水無月)のうちに、さっそく行ったものと思われる。それから、秋(旧暦七月~)には中条方面へ行ったであろう。戸隠山に詣でて みな清水ならざるはなし奥の院 井月
{『井月編俳諧三部集』160頁}
中条は山あいの地域なのに、井月は舟の句を詠んでいるので違和感があるが、当時運航されていた“犀川通船”の様子だろうか。信州新町まで行けば船着き場があったという。出後れて泊る舟あり荻の声 井月
影冷かにすめるゆふ月 雲鈴{長野市中条の人}
{『井月編俳諧三部集』161頁}
『家づと集』の序文は晩秋(旧暦九月)に書かれているが、完成は冬(旧暦十月~)にまでずれ込んだのではなかろうか。なぜなら、冬に詠んだと思われる連句が載っているからである。残る蚊や汚れの眼立ひとつ衣 三ツ丸{山ノ内町夜間瀬の人}
簾の向を替るゆふ月 井月
{『井月編俳諧三部集』159頁}
東信方面へも行ったようだが、いつのことなのだろう。日のささぬ垣も有けり冬構 康斎{長野市中条の人}
俵ながらに水かける炭 井月
{『井月編俳諧三部集』163頁}
鴨の啼田もはさまりし隣かな 悦燕{長野市七二会の人}
時雨をさそふ風呂の柏木 井月
{『井月編俳諧三部集』164頁}
ひとくくりに「サク」とされている人たちに、実際に会いに行ったのかどうか疑問が残る。長野市や中野市など北信濃の俳人について、かなり細かく地名が書かれているのに、「サク」は大雑把すぎるからだ。はつ蝶や見る間に羽のちから付 サク 雪麿{佐久穂町の人}
二三人羽織も脱で水いはひ 庭雨{小諸市の人}
淡雪やふる間につとふ軒雫 雲石{佐久市の人}
ひらかぬは人目兼てや懸想文 可錬{小諸市の人}
誰が来て摘だ濁りや池の芹 物外{佐久穂町の人}
松竹のそよぎに昇る初日かな 長クボ 烏扇{長和町の人}
休む間は余所の田植を見歩行ぬ ワダ 一徳{長和町の人}
{『井月編俳諧三部集』125~126頁}
『家づと集』を完成させ、越後へ帰って行く井月に対して、梅塘は送別の連句を詠んでいる。「渡り鳥の井月さん、来年もこの宿坊に戻って来なさいよ」といった意味だろう。・信濃なる追分原を過る 焼石を見ても寒きにけぶる山 史山{『井月編俳諧三部集』154頁。浅間山の溶岩流跡を見たのだろう}
井月は、「信州名物の蕎麦を味わわずに、越後へ帰っていくのは心残りです」と言っているのだろう。そして『家づと集』の最終ページには、次のような井月の句が載っている。送別{『井月全集』145~146頁。なお『井月編俳諧三部集』では160頁から157頁に跳んでおり、乱丁と思われる}
来る年も巣は爰ぞかし行乙鳥 梅塘
花にこころの残るそば畑 井月
これからが自分の最盛期だ、と言わんばかりの意欲と野心にあふれた句だ。「いとなつかし」には、帰郷の心境を含ませているのだろう。・しほらしくもいとなつかし ちりそめてから盛なりはぎの花 井月{『井月編俳諧三部集』165頁}
《帰郷》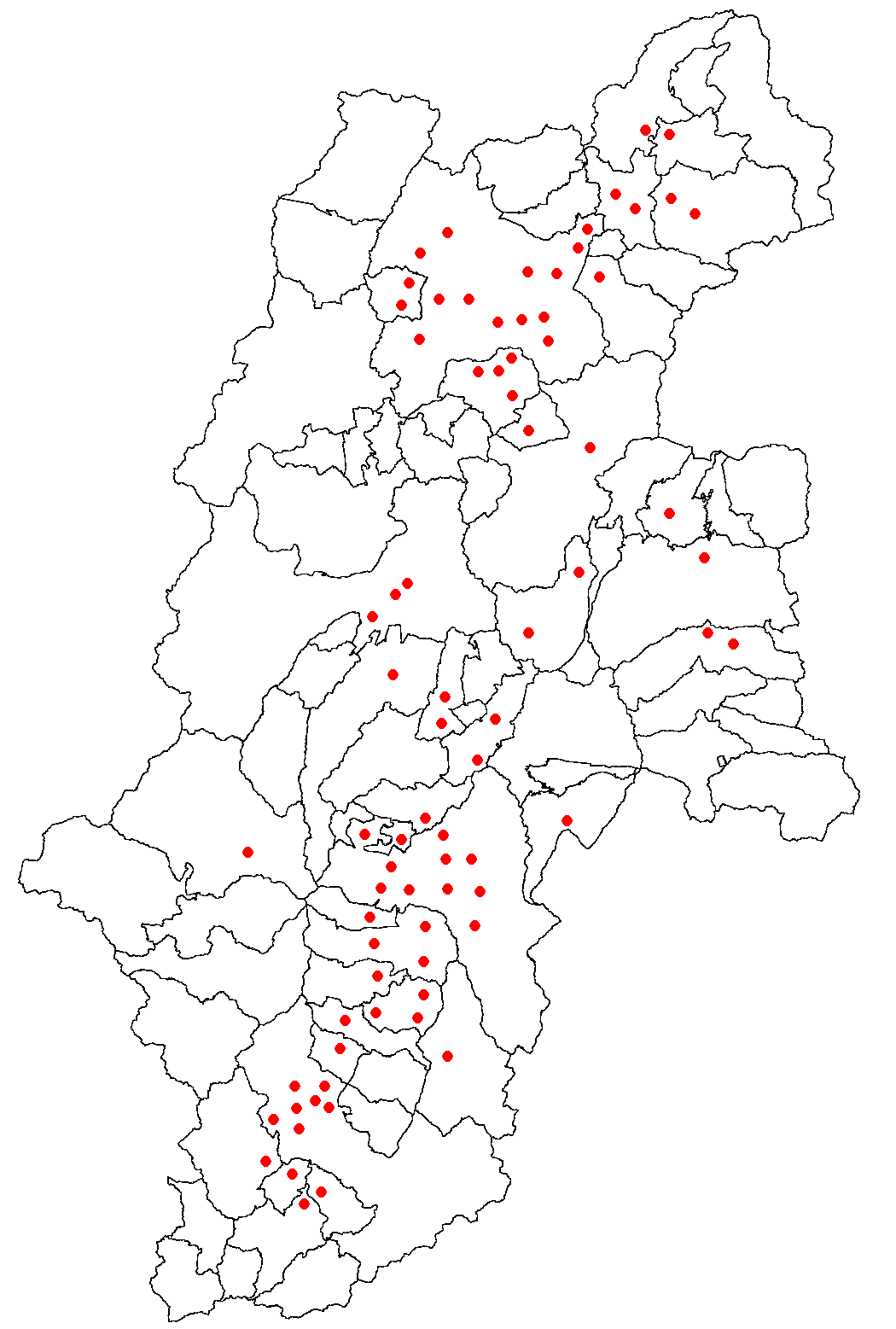
『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』に載っている俳人を地図にプロットしたもの。
『家づと集』について触れられていないが、梅塘が「古郷へ錦を餝るの家づと」だと言っているのだから、井月の帰郷は『家づと集』刊行後と考えるのが妥当と思われる。・飯田におゐて紅葉の摺ものの挙あり。高遠にては、越後獅子集をあむ。其後古郷へ帰り母の喪を果して{『井月全集』515頁}
まず、元治二年の新春を井月は長野市中条で過し、歳旦帳を刊行した。
『家づと集』刊行後の井月の足取り。
残念ながらその内容は伝わっていないが、「歳旦帳」とは新春を祝って作る刷りもののことで、おそらく中条の俳人たちから一句ずつもらい集めて刊行したのだろう。そういうものを作ったということは、伊那谷だけでなく北信濃にも活動拠点を作ろうとしていたのかも知れない。つまり、ゆくゆくは北信濃と伊那谷を股にかけて手広く活躍しよう、という遠大な構想を持っていたのではなかろうか。・元治二[中略]正月[中略]井月及び同地方俳人の句井月板下翠山培樵画歳旦帖二種印刷{『井月全集』402頁}
井月・康斎・其祥の三人で始めた連句に、途中から月信・甫山という親子が加わったようだ。このうち甫山は、当時十九歳の若者だったはずで、井月と戯れて詠んだという連句が伝わっている。長閑さの余りを水の埃りかな 井月
下駄も草履も交る摘草 康斎{長野市中条の人}
凧の糸しばし柱に持すらん 其祥{長野市中条の人}
笛面白くまはる飴売 井月
灯の見える端村の月の差かかり 康斎
碪の音の風にとぎるる 其祥
彼岸頃走りの栗の実入よく 月信{長野市中条の人。神職・手習い師匠}
用なき脊戸に独彳 其祥
暮かかる私道の拾ひぶみ 康斎
思ひの外に積る初雪 井月
川千鳥雲助唄に立さわぎ 甫山{月信の息子}
やくざ古手のうれる此頃 其祥
{『井月全集』152頁}
元治二年は慶応元年と改められた。井月は秋に、善光寺方面・飯山方面の俳人たちと交流したようだ。井坊の頭をはるの月夜哉 甫山{『井月全集』373頁。「春の月夜にうかれて、井月さんの頭を叩いてみましょうか」「涙の雨に、カエルが手をついて喜ぶでしょう」「無口な井月さんは、堪忍袋の口を縫ってこらえるでしょうね」といったところだろう。甫山は、井月のことがよほど印象に残っていたようで、ずっとあとの大正八年ごろ、消息を絶った井月を尋ねてはるばる伊那谷まで来て、墓参りをしたという}
空の涙に蛙手をつく 井月
糸柳こらへ袋の口縫て 甫山
・枯柳軒にさびたる碇かな 井月伊那谷へ戻ったのはいつなのか、はっきりしない。駒ヶ根市東伊那には、慶応二年七月に奉納された井月の門人たちの俳額があるというが、井月本人が関わったかどうかは未解明である。
{慶応元年仲秋刊、羽田墨芳追善『かきね塚』(筆者所蔵品)に。なお筆者所蔵品には刊行年が書かれてないが、糸魚川歴史民俗資料館所蔵の写本には「慶応元乙丑年仲秋」と書かれている。墨芳は善光寺大門町下堀小路の人。千葉県鋸南町で客死}
・動かせばうごく手摺や散る柳 井月
{慶応元年八月刊、伊藤知月追善『さくら草集』(石川県立図書館所蔵品)に。知月については『飯山町誌』540頁に記事があり、飯山市飯山の人}
慶応三年六月、飯田の広田精知が刊行した『とくさかり』に井月の句が載っている。遅くともこのときまでに伊那谷へ戻っていたのだろう。・駒ヶ根市東伊那の火山部落にある名社、高烏谷神社の里宮にある、古い神楽殿の俳額がある。この俳額は、慶応二年丙寅七月十九日に、井月の門下の俳人の俳句を集めて献額したものであって、上伊那郡の南部地域の俳人三十数名の俳句が墨書されている{『四徳誌』357頁}
伊那市長谷のほうにも、このころの足跡があるというが、やや疑問が残る。・いける間の花をながめて桐火桶 雲水 井月{国立国会図書館所蔵『とくさかり』に}
慶応四年の一月、京都の伏見・鳥羽で戊辰戦争が勃発する。・慶応三[中略]長谷中尾、伊東家、屋号上の屋に「竹雪還暦祝集」を遺す{『新編井月全集』630頁}・「竹雪還暦祝集」(仮題)という筆書きの一冊[中略]に、諸家の歌句に並んで、井月の句が自筆で書いてある。[中略]すずしさや月を自在のまつ一木 井月{『伊那路』2004年5月号193~194頁。ただし掲載写真を見ると、幕末のころの筆跡かどうか疑問。そもそも還暦祝いは正月に行われるのが普通だが、「すずし」は夏の季語}
このとき井月は、宮田村の俳人・山圃の家に滞在していたようだ。
三角帽をかぶって攻めかかる新政府軍{筆者所蔵の絵葉書より}
ただし、山圃の年齢には疑義が存在する。・明治元[中略]宮田村山浦山圃六十賀の句あり{『井月全集』402頁}・山圃ぬしの六十歳のことほぎをのぶる 積年の弱みも見えず筆はじめ{『井月全集』117頁。「筆はじめ」は新春の季語だから、明治元年ではなく慶応四年の一月なのだろう}。・山浦山圃 幕末より明治初期の俳人。文化六年宮田村に生れ、[中略]酒造店を営みつつ俳諧を嗜んだ。[中略]又俳画を能くした。[中略]元治元年[中略]水戸浪士の伊那通過の際に、彼が高遠藩士岡村元蔵の命乞をして助けた話は有名である。[中略]明治十四年五月七十三歳で歿した{『長野県上伊那誌4人物篇』451頁}・山圃の写真は『長野県上伊那誌4人物篇』451頁のほか、『伊那路』2025年11月号411頁にある。
もし山圃が八十歳を越えて生きたとすれば、井月が詠んだ「積年の・・・」という六十賀の句は文久元年以前に詠まれたことになり、「明治元年(慶応四年)に井月は山圃の家で六十賀の句を詠んだ」という通説が崩れてしまう。後考を待ちたい。・多くの俳句仲間が73歳で亡くなったはずの山圃に賀句を贈っている。それも喜寿(77歳)を過ぎて傘寿(80歳)のお祝いにである{『伊那路』2025年11月号411頁}
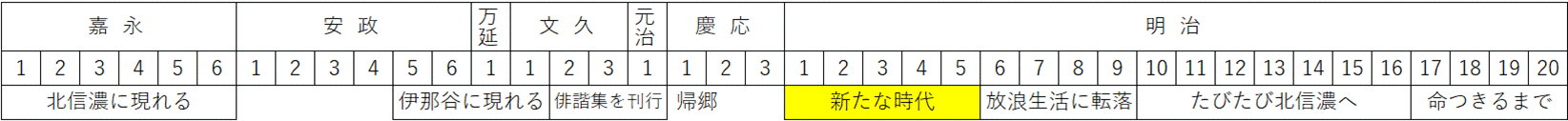
次のような手紙も伝わっている。「大島より」とあるが、下伊那郡松川町の大島宿ではなく、大島村(現在の伊那市美篶上大島)から出したものではなかろうか。・古郷へ帰り母の喪を果して、又々昔のなつかしみをおもひ、明治元辰の冬より、此辺りに遊て常に御懇恤を蒙る{『井月全集』515頁}
「はつ雪」は冬の季語であり、「元治元辰の冬より、此辺りに遊て」という井月の回想と季節は合致する。あて先の青島村は、明治八年に美篶村に編入されており、それ以前に出された手紙なのだろう。つまり明治元年と考えても矛盾はない。ただ「久々に又御当国へ参り」とあり、越後帰郷から信濃へ戻ったことを言っているのだから、慶応年間の手紙という可能性もある。後考を待ちたい。・愚房も久々にて又御当国へ参り申候。不相替御引立の程奉希上候。[中略]はつ雪や小半酒も花ごころ[中略]大島より 井月草 青島村 柳川雅君{『井月全集』331頁}
これは、明治二年に井月が刊行した歳旦帳に、伊那市美篶上大島の神官・富岡守胤が添えた和歌である。井月は明治元年の暮れに守胤の家に滞在し、歳旦帳を作って新春を迎えたらしい。これが井月にとって、伊那谷での活動再開の第一歩だったのだろう。もしかしたら、長岡のいくさが終結するのを待って、活動を再開したのかも知れない。・井月ぬしこたび我里訪来りて何くれものして年を迎ゆ 諸ともにつかへまつるも君がためなけや鶯よろづ代までに 守胤{『井上井月真筆集』118頁、「巳の春」歳旦帳に}
鶯老というのが、岡村菊叟(忠輔)の別号である。かつて『越後獅子』刊行のとき、序文を書いてくれた菊叟を頼って、井月は高遠に来たのではなかろうか。そして、高遠城下のすぐ近くの、美篶に滞在していたのではあるまいか。和歌を詠んでくれた富岡守胤は、岡村菊叟と師弟関係にあった人物である。・沫雪を花にしてなけ梅の鳥 鶯老{『井上井月真筆集』118頁、「巳の春」歳旦帳に}
『越後獅子』刊行のころは「越の長岡の産」と公言していた井月だが、明治維新後は、出身を語りたがらなくなったであろう。新政府軍の追及の手が及ぶのを恐れ、はっきり長岡藩と言わず、ただ越後とか、あるいは高田藩などと言っていたのではなかろうか。・富岡守胤 神官。[中略]美濃国土岐郡釜戸郷に[中略]生れ、[中略]上大島村(現伊那市美篶)に来て住み、[中略]高遠藩士岡村忠輔にも皇学と歌学を学んだ{『長野県上伊那誌4人物篇』279頁}・守胤の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『信陽俳諧名家集』にある。写真は『長野県上伊那誌4人物篇』279頁にある。
明治二年の歳旦帳の巻末は、次の一句で締めくくられている。・郷里をはっきり云はなかった{『俳人井月』132頁}
・越の高田より信濃へ趣く途中 雪車に乗し事も有しを笹ちまき 井月{『手紙で読み解く 井月の人生』225頁写真。幕末の筆跡ではなく、明治初期の筆跡と思われる。なお、この句が書かれた短冊の裏面には、井月ではない筆跡で「越後高田藩人 行脚」と書かれている}
・辟世窟の吟
鶯お聞程明て庵の窓 富岡 半中
梅が香運ぶ風の折々 越後高田 井月{『井月全集』432頁。辟世窟は伊那市東春近の医師・那須竜洲の家。竜洲は『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』に載っておらず、つまり井月と竜洲の交流は、明治以降と思われる。竜洲の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『信陽俳諧名家集』にある。半中がどういう人なのかは不明}
この句は、行き当たりばったりの、人任せの生き方をした井月を象徴するかのような句と思われがちだが、そうではないように思えてくる。「戊辰戦争で世の中がひっくり返ってしまいました。目出度い正月になるかどうか、あなた方にお任せするしかありません」といった、かなり切実な意味が込められているのではなかろうか。・目出度さも人まかせなり旅の春 井月{『井上井月真筆集』118頁、「巳の春」歳旦帳に}
その広田精知だが、明治二年に一旦東京へ帰っているのではないかと思われる。・浪よけの松は曲りてはるのかぜ 精知{『井上井月真筆集』118頁、「巳の春」歳旦帳に}
精知の著作物である『古今発句類題書画 春』(筆者所蔵品)には、諏訪郡富士見町の五味寥左という俳人が漢文による序文を付けている。そこには「東京四時庵主人休杖於曽濃原」とあり、四時庵は精知の別号の一つ。精知の家はずっと東京にあって、飯田に定住していたのではなく、行ったり来たりしていたのかも知れない。また「曽濃原」とあるから、飯田市だけでなく阿智村の園原にも、精知の活動拠点があったのではないか、という疑問も生じる。・築地商社 秋もまだおくひまのなき扇かな 精知{『東京繁華一覧』明治二年己巳十月梓行 東京浅草御蔵前 萬屋庄助版}・明治二己新刻 語石庵精知輯 閑樹園菊雄校『古今発句類題図画 春』{明治己巳年十一月 浅草御蔵前片町 萬屋庄助}
駒ヶ根市の火山峠には、井月の門人たちが明治二~三年ごろに建てたという芭蕉の句碑がある。井月本人が碑の建立に関わったかどうかは不明だが、すでに東伊那方面で「社中」あるいは「連」と呼べるような門人組織を作り上げていたのではなかろうか。・明治二[中略]七月[中略]日枝神社奉額揮毫{『井月全集』403頁}・富県村福地の村社に井月選句自筆の奉納額がある。[中略]酒を飲んでは一二句書き、また飲んでは寝てしまふ、と云ふやうなことで一向出来上らぬ。四五日目には村の世話役から大変な苦情が出て来たが、[中略]漸く八日目の晩に出来上った{『井月全集』358~359頁}・霧晴れや実りをいそぐ朝の冷 雲水 井月 明治二巳歳七月{『伊那路』平成元年5月号251頁。日枝と冷えを掛けた洒落であろう}
・火山峠芭蕉の松[中略]根本に芭蕉の句碑が建ててあることからこの呼び名がある。[中略]この句碑は[中略]俳人井月の門人たちが建立したものである。[中略]明治二、三年頃の建立とされている{駒ヶ根市教育委員会による立て看板}
このほか明治二年の動向としては、「慶応」「巳己」と記された書道作品が存在する。そもそも「巳己」は誤りで己巳と書くべきだし、己巳は明治二年であって慶応のはずがない。たとえ泥酔していたとしても、こんな誤りを書くだろうか。明治維新を認めたくない旧幕府側の人たちが「慶応」を使い続けた、という話を耳にしたことがあるが、定かではない。
芭蕉の松と句碑。駒ヶ根市東伊那火山峠。
「応需」とは、求めに応じて揮毫すること。井月は家々を歩き回って、こういった揮毫をしたり、句会を開いたり、「引墨」といって俳句の添削指導をしたりしながら、伊那谷のあちこちに門人を増やしていったのだろう。句会の様子が伝わっているが、旦那衆だけでなく、若者たちも参加していたようだ。・慶応巳己夏日応需 雲衲井月{『井月真蹟集』203頁}・慶応四巳己水無月 井月道人{『井月真蹟集』205頁}
《新たな仲間たち》・夕方になると、近隣の俳諧好きが集って来て、井月を先生に、句をはじめるというわけ。そのあとはいつものことで酒盛り。いつだったか、そうした集まりのとき、私の作った句を、当夜第一といって井月がほめてくれたんですよ。天といいましたかね。十五、六の娘のときのことなので、ほんとにうれしかった{『伊那路』昭和46年8月号309頁}
筍苞は、伊那市狐島の人で井月より二十歳年下。のちに凌冬という名で上伊那地域に大きな勢力を築くことになる著名俳人である。植ものの囲ひもとれて春の雨 筍苞
心までかくあら玉のはつ日かな 蔵六
くもるのもひと気色なり春の月 五声
黄鳥の声に川こす日和かな 山好
{『伊那路』2001年1月号22~23頁}
蔵六は、駒ヶ根市赤穂の寺子屋師匠で井月より五歳年下。のちに松崎量平という学校教師になり、数多くの教え子を育てた人物として知られる。なお、井月の代表作である「降とまで人には見せて花ぐもり」という句は、この蔵六の家で詠んだものと伝えられている。・馬場凌冬 明治の俳人。天保十三年[中略]生れ、明治元年[中略]名主役、明治六年円熟学校を起し、自ら教鞭を執り、[中略]明治十二年伊那村戸長となった。その家を見ると、祖父は如苞、父は如竹といってともに俳諧を嗜んでおり、凌冬の後年の斯道における活動は、この家庭的環境に負うところが大きいことがわかる。俳号は始め筍包[正しくは苞]、のち凌冬といった。[中略]既に十四歳のとき、当時この地に来遊中の空羅と対吟してその指導を受けている{『長野県上伊那誌4人物篇』328頁}・凌冬の句の手ほどきをしたのは井月であって、常に井月を先生、先生と敬重し、経済的援助をしたことなども聞いている{『高津才次郎奮戦記』84頁。しかし俳句の手ほどきをしたのが井月だという説は、ちょっと考えにくい}・凌冬の写真は『長野県上伊那誌4人物篇』328頁のほか、『呉竹園遺稿』にある。肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』『信陽俳諧名家集』『俳諧百家集』にある。
・松崎蔵六 教育者、俳人。文政十年二月伊勢松坂に生れ、[中略]出京の砌り母が病臥したので上穂(現駒ヶ根市)の安楽寺を頼って、ここで成人した。後この地に家塾を開いて慈父の如く教え、門戸大いに振って教えを受けた者千余人と言われる{『長野県上伊那誌4人物篇』389頁}・亀の家蔵六は本名松崎量平、伊勢の松坂に生れ、父が江戸に出て火に遭ひ帰郷の途上、赤穂で病没、蔵六は此の間に成長し赤穂で幄を垂れた{『井月全集』275頁。前掲の説とは微妙に異なっている}・蔵六の写真は『長野県上伊那誌4人物篇』389頁にある。・蔵六の妻が「今日は光前寺祭なれば降らねばよいが」と語られたとき、厠より出てきた井月が「大丈夫大丈夫」と連呼しながら筆をとってかの有名な「降るとまで人には見せて花曇」と記された。蔵六は「こうなればよいが」と語ったがその日ついに降らなかったという{『駒ヶ根市誌』現代編下巻207頁}
余談になるが、この「降とまで・・・」の句はとても評判になり、はるか岐阜県恵那市明智の女性から、井月のところへファンレターが来た、という話も伝わっている。
花曇りの光前寺。駒ヶ根市赤穂。
明治三年の歳旦帳に話を戻そう。五声は、伊那市西春近の人で井月より二十数歳も年下の若者。造り酒屋だった。・ことの葉種の飜れてや、美濃の関屋を打越て、尾張間近き山田やは、明智の里の旅籠にて、婦世帯がよしと呼、あるじはもとよりしきしまの、道にこころの有磯海、浜の真砂と手にふれし、数の玉藻を撰分て、降とまでの愚詠をさばかり愛で給ひし甘吟の、おのれがもとへ来る事も、彼の明王の利益によれるものか{『井月全集』271~272頁「花曇の自讃」}・此の句に感じて歌を送ったといふよし女につき、[中略]姓は山田、[中略]薬種商の娘で入夫[中略]に死別し、独身で居たが乳癌を患ひ[中略]明治十五年十二月二十一日に没した。時に年四十三。同家は郷宿といって村役人が泊ったり[中略]といふやうな、さうした御用を課せられた家でもあり、[中略]井月が旅籠屋と誤り書いたのもその為であらう{『井月全集』272~273頁}・井月はしばしば訪れて、よし女とも親しんだものらしい。漂鳥井月に纏わる微かな艶聞でもあろうか{『漂鳥のうた』9~10頁。しかし井月は訪れていないだろう。訪れていたなら「旅籠」などという誤りは書かないはず}
山好は、伊那市東春近の人で井月より四歳年下。門人というよりも、年の近い友人だったであろう。その後の井月にとって最も近しい支援者となる。・加納五声ぬしの新酒披露を寿ぐ 味ひは水にかのふて今年酒 井月{『井上井月真筆集』69頁。「加納」と「叶ふ」を掛けた洒落であろう}
明治三年の歳旦帳の巻末は、井月の句で締めくくられている。・飯島山好 伊那市東春近、殿島渡場の人。明治三十七年に七十九歳で没した{御親族の話に基づく}・陶渕明山好神 狂言寺和尚筆{『井月真蹟集』43頁。よく支援してくれる山好のことを、井月は「山好神」とふざけて崇め奉っているのだろう}・山好の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『信陽俳諧名家集』にある。
歳旦帳にふさわしく若菜摘みを詠んだ句で、みずみずしい露の玉が籠からこぼれる様子であろう。もしかしたら、俳句をもらい集めて作ったこの歳旦帳を「若菜の籠」に見立てているのではなかろうか。「みなさんから集めたみずみずしい俳句で、籠がいっぱいになりましたよ」といったところか。・露ちるや若菜の籠の置所 雲水 井月{『伊那路』2001年1月号23頁}
「飯田に頼んだ版木製作が遅れていて、私も奔走ばかりに時間を費やしています。昨年の冬にも二度飯田に行って、お金も二両渡して、早春(旧暦一月)には出来上がるように頼んだのですが、あちこちの注文が立て込んで、遅延して困っています。先方(=飯田)からあなたのところへ知らせがあるはずですので、知らせがあったら山好氏のところへご連絡ください。挿絵を刷り上げて校合もしなければなりませんので、あなたのところへ送るように伝えてあります」といった内容である。・飯田版木相後れ、旁奔走のみに暇費を消光、[中略]昨冬も両度飯田へ参り、金子も貮両相渡し出精いたし候て、早春には出来いたし候様にと呉々頼置候へ共、[中略]諸方の注文混雑、[中略]彼是遅々いたし困入候。[中略]先方より貴所様迄申遣候筈に付、[中略]便り御座候はば乍憚山好子迄一草御差出被下候様奉願上候。[中略]口画摺り上げ校合も御座候事故貴所様迄差送り可申やう申置候[中略]正月十三日 井月拝 山圃雅兄尊下{『井月全集』307~308頁}
明治二年・明治三年の歳旦帳には、この「屠蘇と声・・・」の句が載っていないから、明治四年の歳旦帳なのだろうか。未見なので分からないが、はじめて草庵というものを持った井月が、正月の客をもてなしている様子だろう。・山好、竜洲、吉扇などの取持により奥村藤兵衛の土蔵を仮住居として、明治三年より四年におよび、四年三月十八日に光久寺にて[中略]開庵披露が行なわれた{『東春近村誌』936頁。明治三年ではなく明治四年の三月十八日だと特定できる資料がどこかにあるのだろうか}・上殿島区渡場の、現在の「中正館」の近傍で[中略]、門弟山好の家から二町ばかりの所に小庵があって、そこで十日間ばかり門弟たちと寄り合って、井月が句会などをしたことがあるそうだ。三年前に六十五歳で死んだ、当時小娘だった井上いわという「あばたの子」が、頼まれて飯焚きをしていたことを覚えている{『高津才次郎奮戦記』56頁。この記事が書かれたのは昭和二年で、そこから逆算すると、いわという少女は当時十一歳か十二歳だったのだろう}・屠蘇と声かけて手間どる勝手かな 又「坐敷かな」歳旦摺に「草庵に春を迎ひて」と題す{『井月全集』116頁。}
井月の草庵が存在したのは、「明治三年より四年におよび」とあるから、わずか一~二年間のことなのだろうか。しかし後述するが、井月は明治六年まで草庵にいたはずで、つまり「明治三年から四年間」だったと考えられる。決して短くない期間、井月は伊那市東春近を拠点に暮らしていたのだろう。・来る十八日弥開庵披露書画展観会興行仕候間、[中略]山好方へ早朝より御来臨、御取持の程偏奉希上候。[中略]弥生十四日{『井月全集』318頁。山好の家に集合して、光久寺へ向かったのだろう}・来る十八日於殿島光久精舎不論晴雨開庵披露、席上俳諧並書画会興行仕候間被仰合早朝より御来臨御取持の程、伏而奉希上候。[中略]弥生十五日 [中略]当日展観張出し御恵投可被成下候{『井月全集』317~318頁。「御恵投」とあるので、仲間たちが書画を持ち寄って、展観会の収益を井月に寄付しよう、という企画だったのだろう}
つまり、伊那市東春近に住まいを持ちながら、宮田村の職場にも寝泊りしていたのだろう。天竜川を渡って行ったり来たりしながら、暮らしていたのではなかろうか。・明治になって宮田村が置かれると、湯沢友右衛門が宮田村戸長になった。[中略]書記は、越後の国長岡出身の柳の家井月といふ俳人で、湯沢家に逗留して、初代書記として勤めたと言ふ{『伊那路』昭和39年3月号126頁}・湯沢友右衛門 名主。文化十年宮田村南割に[中略]生れた。[中略]俳句を好み亀石と号して句作した{『長野県上伊那誌4人物篇』459頁}・和宮内親王が将軍家茂に降嫁されることになった。[中略]湯沢友右衛門は高遠領七十三ヵ村の人馬大引回しを命ぜられて上松・元山[正しくは本山]間を駈けている{『宮田村誌』上巻792頁。つまり高遠藩を代表する大名主だったのだろう}・明治四年[中略]戸長[中略]の選任は[中略]七月三十日までに済ませ、[中略]湯沢元彦が任命された{『宮田村誌』下巻20頁。つまり実際の戸長は湯沢友右衛門ではなく、息子に代替わりしていたのだろう}・亀石方へ来る度に一度に米一合与へる約束で、[井月は]絶えず来ては風呂敷の四隅を縛っては持帰った。或時手づかみにして与えたら、怒って受取らなかったといふ{『井月全集』370頁。米一合というのが、井月と結んだ雇用契約だったのだろう。「契約なのだから、手づかみではなくちゃんと一合を量って渡してほしい」という抗議の表れと考えられる}
《草庵建設計画》
天竜川にかかる殿島橋。水害で何度も流され、何度も架け替えられた歴史がある。
まず「翠柏園」がどこを指すのか未解明。「あるじ山好」とあるから山好の家だろうか。あるいは山好らがあっせんしてくれた井月の草庵(土蔵)のことを翠柏園と言っているのだろうか。井月の晩年の日記にも翠柏園が二度出てくる。後考を待ちたい。・春近開庵勧請文 爰に行脚井月杖を当国に曳て、さつころ春近なる翠柏園に頭陀をおろす。あるじ山好是が為に大に席を設けて弥生の会宴ありしより、四方の好士此所に集ひ彼処に寄りて風流益行る。近辺の社中尤多きが中に、下牧の五声父の風雅を継で頗る隠徳仁恕の聞へあり。一日月に語りて曰く、我家近きほとりに一つの空地有、是に一小庵を結び、新に祖翁の像を安置し、常に江湖慢遊の風子をさそひ、永く俳諧の道場たらしめむとおもひども、力の足らざるをいかにせむ。幸なる哉、子が社中翁講の催ありとききぬ。此秋に当り蕉堂勧化の一念を発起して草庵開基の志あらば、彼の地を以て永く寄附せんと。茲におゐて月雀躍としてよろこび、其地を計りみるに、凡百有余坪あり。草堂蝸廬の地には広しといへども、往来の都合煩はしき程にもなく、絶景佳境といふにはあらねど、西に駒峯あり東に天竜の流れを帯たり。眼に見ゆるものみな涼しと翁のすさび玉ひしかの岐阜川の景色には劣るとも、凩の日に笠の破れ繕ひ、時雨の夕に蓑の濡たるをほさむにはまた便りなきにしもあらずと、頓てことのよしをおのれにかたり、山好五声にこころざしを同うして風流の礎に荷担し、一心帳の魁たれと、しきりに勧むることの切なるに、稲舟のいなとも言れず、されど四方の風士数多が中に、ひとりさし出て嗚呼なりと人々の指さし笑ひ玉はんも面なきことなめれど、そは私の一小事、二三子が計る処は万代不朽のいさほにして、翁への追善これに増たる供養はあらじと、纔の楮幣を投じて勧進のいと口を開き、なを四方の君たちに乞ふてちからの足らざるを補ひ玉はれかしと、月にかはりてひたすら希ふものは兜が城の片ほとりに住る逸俳士雨香にぞ有ける{『井月全集』476~477頁}・この「勧請文」の要旨は、西春近(現伊那市)下牧の加納五声[中略]が、芭蕉堂建立のため百余坪の土地を寄附し、そこに堂守兼庵主として井月を住まわせようとするもので、俳諧愛好者に建築費勧進を乞いたいとするもので、案文浄書ともに井月ながら、兜が城(高遠城)下の雨香なる逸俳士の名を借りたのである{『井月真蹟集』20頁}
ところで、芭蕉忌の催しとは、どんな内容だったのだろうか。
井月が草庵を建てようとした、伊那市西春近下牧の風景。
これらの資料が明治四年のものかどうかは不明だが、十月十二日の芭蕉忌に、伊那市東春近殿島の吉扇の屋敷を借りて開催したようだ。「御宝前」「衆評」とあるから、たぶん座敷の床の間に芭蕉像とか芭蕉句の掛軸を飾って拝んでから、句会をおこなったのだろう。「紙や筆が必要なのでお金を貸してください、すぐ高遠まで行って買い求めてきます」といった意味のことが書かれている。・来月翁忌を御宝前にて御興行被下度、上部、赤木、下牧、表木社中申合出頭可仕候間、何分共御世話の程伏而奉希上候。[中略]九月二十七日[中略]飯島吉之丞殿{『井月全集』299~300頁。東春近の飯島吉扇という名主の家に宛てた手紙}・衆評の義に付、鳳良子より御咄申上置候通り何か当日入用紙筆の類調進に付、御都合次第にて貮百疋程拝借仕度、直様今日高遠へ出向、夫々相求申度、右御返納は終会の節迄と御承知可成下候。[中略]十日 飯島吉扇君{『井月全集』297~298頁。鳳良という人物については未詳}・此程より申上候通り、来月十二日を目的、何を申も○の事せめて紙筆の用だけ御工風偏奉希上候也 柳君足下{『井月全集』298~299頁。柳君は柳哉という人物で、吉扇の息子}・我道の神とも拝め翁の日{『井月全集』100頁}
実際に駒ヶ根市赤穂方面からも、芭蕉忌(時雨忌)の催しに関する書簡が見つかっており、「殿島におゐて」と書かれているから、やはり伊那市東春近の吉扇の家のことを指していると思われる。・吉扇は[中略]東春近村上殿島渡場の大庄屋である。[中略]仰天するほどの大屋根であった。間口十三間、奥行八間という。[中略]遠くから見れば、とても民家とは思われない。[中略]吉扇亭には近隣に聞こえた牡丹園があった。前庭に色とりどりの牡丹が咲き乱れていた。[中略]花の時期には遠方からも風流人が集まってきた{『漂鳥のうた』131~136頁}・飯島吉扇の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『俳諧百家集』にある。柳哉(飯島幾太郎)の写真は『長野県上伊那誌4人物篇』22頁にある。
『春近開庵勧請文』には「一心帳」という言葉が出てくる。寄付金集めの趣旨に同意し、仲間たちが心を一つにして記入する帳面、といったところか。要するに“寄付金帳”と思われ、誰が何円、誰が何円、というふうに記帳してもらったのではなかろうか。次のような書簡もある。・毎度御無心ながら紙筆の料二十五銭程、当月殿島におゐて時雨会済まで恩借仕度[中略]十月二日 井月敬書 泉柳君 紫水君 玉机下{『井月全集』475頁。泉柳・紫水は駒ヶ根市赤穂の人}
「帳びらき」は、各地の門人たちに記帳してもらった寄付金帳を、集計してみることだろう。ただし日付に疑問がある。もし「五」ではなく「壬」ならば、「閏六日」ということになり、明治初期だとすれば「明治三年の閏十月六日」が該当する。十月十二日の「翁講の催」で門人たちに「一心帳」を配り、翌月の閏十月に集計したと考えて矛盾はない。だとすれば、『春近開庵勧請文』は明治四年ではなく、明治三年の三月十八日以降、十月十二日以前に書かれたことになる。後考を待ちたい。・勧化の義に付明日帳びらきいたし度、[中略]いろいろさし行、御はなしも拝眉万々可申上候。[中略]五(或は壬?)六日 井月{『井月全集』302頁}
「当連」とは、東春近の門人たちのこと。「馬入庵」は山好のこと。「東春近の門人たちは、とても恥ずかしいのですが先生方のレベルに付いていけるのは山好ただひとりです。刷り物の作成などに労力をさかなければならず、衣食も良くなく、自他のことに忙しく、思うようにならず、いずれ先生方にお願いするしかないと思います」といった内容である。「先生方」というのは、伊那市西春近の五声と、弟の有隣のことか。援助をお願いしたいと言っているのだろう。・当連至極愧入候得共、四点句勝にて六印以上の秀才微く、馬入庵一人御両公に随従可仕心入には御座候へ共、摺物一会等々弊労に拘り居鳥渡衣食の附はたよき程に不参、自他の所に混雑いたし、[中略]随分面倒なれば思ふ様に不参、何れ先生方に御願申より外無之と奉存候。[中略]折節ほととぎすを聞て 我友は川のあなたぞ時鳥{『井月全集』313~314頁}
越後から戸籍を移すにしても、あるいは寄留者として伊那に留まるにしても、一旦越後へ帰って「送籍」あるいは「鑑札」を持参しなければならない。しかも、井月は宮田の戸長役場の書記という職にあり、こういった法令を遵守させる側の立場だった。・第九則 他の管轄地に引移る時元の庁より送籍するには其当人より元住所の組合並戸長に其由を届け長副連印し其庁に届け其庁之を受け其庁聴き知るの証を押し当人に渡すべし・第十二則 全戸引移らず又は一時公私の用にて寄留するものは其本貫管轄庁の鑑札を持参し寄留地戸長に通し其寄留する所の庁に名前書を添へ鑑札を差出し其庁之を受け即ち其庁の鑑札と引替遣すべし{明治四年四月五日布告、明治五年二月一日施行の戸籍法。筆者所蔵品より引用}
精知の場合、かねてから東京に「四時庵」という住まいがあったと思われ、だから飯田をひきはらって帰京するのも容易だったであろう。しかし井月の場合は、若いころの江戸の住まいがそのままあったとは考えにくく、伊那谷にとどまって生きるしかなかったのではなかろうか。・語石庵精知 初めは四時庵と号し、後に語石庵と号す、[中略]滞飯十有余年沈滞せる峡谷俳壇に活を入れたる功績は特筆に値すべく明治五年頃帰京す{『伊那の俳人』116~117頁。諏訪郡富士見町の五味寥左が明治五年に刊行した『俳諧三千題早引略解』の人名録に「精知 語石庵 飯田」とあるから、たしかに明治五年までは飯田にいたのだろう}
日付は「文月十七日」となっている。明治四年の十月十二日の芭蕉忌に寄付金集めをしたのなら、この書簡はその後に書かれたと考えられ、明治五年の七月ということになる。「来月さし入には当所出立」とあるから、八月に出発したいと計画していたのだろう。・是非早速故郷北越迄罷越、戸籍送証持参不致候而者宿願不相叶義に候の間、来月さし入には当所出立仕度、[中略]当所御暇乞の印小摺にても一葉御取持に預り持参いたし度、[中略]御助力の程偏に奉願上候。[中略]野口連御当所連八手福与福しま川手邊の心得に御座候。何分右の思召にて御集句の程幾重にも相願上候。廿日過には参堂仕候[中略]文月十七日 尚々餞別会にては如何申事も咄し候へ共、摺物の方為筋に可相成哉とも被申候間、此段は何れにても宜敷候{『井月全集』332~333頁。伊那市手良の桂月という人物に宛てた書簡だという}
「御左右も不被下」とあるから、仲間たちの反応は冷ややかで、誰からも音沙汰がなかったのだろう。先述の東春近といい、この手良といい、どうも井月が思うほど協力的な人ばかりではなかったのかも知れない。・先達而手良郷にて送別会御取持相成其節御案内申上候処、各様方の内一円御左右も不被下候間{『井月全集』335頁}
この「中沢」には注意が必要。現在の駒ヶ根市中沢だけでなく、東伊那まで含む広い地域を「中沢郷」と言ったのである。東伊那大久保の、中村新六という「カッパの妙薬」で知られる名家の屋敷を借りて、盛大に開催したものと思われる。・此度中沢にてちらしの通大会開筵に相成、玉名猥に加入御取持の程相願度候。被仰合当日早天より御来臨の程奉待上候[中略]九月二日 尚々諸方の珍蔵書画展観にそなひ度候間、御所蔵の銘品御持参奉希上候{『井月全集』335~336頁}
実に一一三名もの名前が載っている。もちろん、これらが全員出席したとは思われず、井月の知人・友人の名を片端から入れただけであろう。ただの送別会ではなかったようで、例によって仲間たちが書画を持ち寄って展観会を開き、その収益を井月の旅費にあてよう、という算段だったと思われる。・柳廼家送別 書画展観会 九月八日九日・補助 五声・巴水・米花・山好・稲谷・沽哉・庭泉・良盛・蔵六・軒柳・市雪・我蝶・菊の家・一瓢・飛山・鵠斎・歌丸・吐月・松花・可明・圭雅・南春・工尺・有孝・貫一・中皐・春庭・三子・亀寉・耕斎・春寉・蘭堂・鶯娯・啓賀・万来・有丈・柳台・墨草・筍苞・柳川・玉斎・禾圃・文軽・李山・布精・昌寿・富山・山石・玉月・如雲・吉扇・有実・竜洲・二竜斎・三友・文交・永眠・雨香・升女・梅園・鳳雲・亀石・笹直・桃秀・山圃・寉子・山雪・揺扇・里丈・裳水・梅芝・鶯雅・松風・魯暁・峰雲・梅枝・鳳良・竜賀・呉竹・附石・胡外・一風・星月・梅竹・牧雄・蛙石・碧堂・一盃・与雄・若翠・狄仙・玉椿・月松・栗園・原ヶ島・素雄・白岱・如帆・柳春・いし女・桂月・吉平・海寉・自友・露寉・松月・里鶏・星一・現章・池月・有隣・南枝・曳尾・諸先生席上揮毫・四方之君子不論晴雨早天より御賁臨御取持之程偏奉希上候 但各御さし合の御方は展観御望可被下候会幹 中村其楽 中村源造 中村小平 中村如渕
会主 中村新六
《大赤字を出す》・明治五壬申秋送別会{『井上井月真筆集』91頁などに}・柳家連{『井上井月真筆集』58頁などに。井月は、自分の社中のことを「柳家連」と呼んでいたらしい}
「かかる設席三日に及べど」とある。二日間の予定だったはずだが、三日間に延長したのだろう。「諸賓の賁臨時に中らず」とあるから、思ったより参加者が少なかったと思われる。「二百有余の珍膳佳肴の饗応も空しくなりて」とあるから、用意した料理が無駄になってしまったようだ。ついには借金の淵に首をくくらなければならないような状況となったらしい。越後へ帰るどころではなくなっただろう。・さきの年己れ送籍取に遥々と、思い立しも行秋の菊花の宴をこころに込め、大久保なる中村亭に於て、餞別書画の大一座、[中略]かかる設席三日に及べど[中略]諸賓の賁臨時に中らず。二百有余の珍膳佳肴の饗応も空しくなりて、夢なら覚よと甘心しても、惑ひは晴ぬ永雨に、会主は端から自算用、足ざるは足ずとしては置ぬなり{『井月全集』515~516頁}・心の目算忽ち変じて意正に茫然たり。[中略]そも先年中沢に会莚を開くも[中略]送別会興行の雑費不少終に借金の淵に首縊るとか申如く成行き[中略]帰郷の手段一策も無之{『井月全集』292~293頁}
十両といえば大金である。明治維新後、貨幣単位は「円・銭・厘」になったはずだが、庶民の間では「両・分・文」という言葉がまだ通用していたのだろう。「五声君は、七両二分と記帳しているので、五両をお引き受けください」という意味のことが書かれている。これは寄付金帳のことではなかろうか。草庵建設のための寄付金を、送別会の赤字補填に流用しようとしていたのなら、のちのち大きな問題になったと思われる。・就ては拾両の所二人にて割合差出候事にては即金に差出し可申との事に付、何卒其思召にて、五声君は御記帳七両貮駄の廉も御座候へば、五両金御引請、残る五両の処梅竹君蝸石君にて御心得被下候様偏奉希上度、此段御承知被成下度候{『井月全集』303頁。梅竹・蝸石は五声の親戚}
山好と、なにか行き違いがあったようだ。「月迫」は月末(ここでは歳末)の支払いが迫ること。・行違ひ等不都合、東西奔走月迫山好待入、夫故別而混雑、年は同所にて一昨日迄何方へも不参、[中略]今日とても冬の儘草庵に蝸居、[中略]例の拝借金の処は、段々御迷惑筋の処は御察申居候へ共、何とも小生以参外御両公様え拝顔ならでは分り兼候義に御坐候[中略]正月七日[中略]無いそでをなをふる雪の歳暮かな{『井月全集』304~305頁。蝸石へ宛てた手紙}
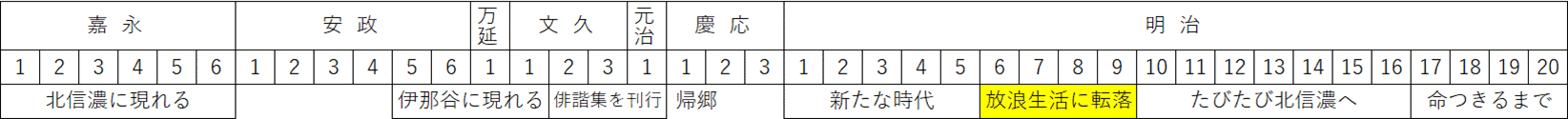
送別会の失敗後、明治六~七年ごろの様子を伝える書簡と思われる。「昨年貴館を発し」と書かれており、伊那市西春近の五声の家に立ち寄ったようだ。そして今は、駒ヶ根市赤穂(上部、正しくは上穂)で毎晩楽しく酒を飲んでいる、と言っている。・炎暑之時節益無御障事、[中略]其後者乍存御無沙汰多罪[中略]昨年貴館を発し上部社中へ投じ候処殊の外取扱よろしく、毎日夜席を設け俳酒盛大凡出席三十人近きに及ぶ。[中略]柳の家が為体寒中の薄衣[中略]既に殿島連の実意少きを詰て書を那須氏に投じ説諭を山好に勧むといへども、[中略]更に其甲斐なし[中略]草庵開基の志よりして送別興行の雑費不少終に借金の淵に首縊るとか申如く成行き、[中略]昨冬は向寒の出立残暑と同うし、[中略]追々厳寒に逼り終に命を中沢に落さんとせしも、曽倉なる竹村某が深き情により寒気凌防の実を得今日に及ぶといへども、帰郷の手段一策も無之、貴君へ御預け申置候勧化帳の上にて何程づつか受納いたしたる其所彼所の言訳を立、将又半を分て旅費に当て{『井月全集』291~293頁。加納五声あての書簡}
ところで、書簡には「勧化帳の上にて何程づつか受納いたしたる其所彼所の言訳を立」とあり、寄付金帳から流用してあれこれに使っていたことがわかる。東春近の門人たちが騒ぎ出し、那須竜洲・飯島山好らが事態の収拾にあたったことも書かれている。さらに井月は、「越後への旅費を、寄付金帳から出したい」と言い出している。どうやらかなり金銭にルーズなところがあったのだろう。・竹村熊吉(1846-1913)事業家[中略]中沢本曽倉に生れた[中略]。明治8年奈良屋製糸所を設立した。中沢村長を努めた。中沢郵便局[中略]を建設開局し、初代局長として大正2年まで務めた。傍ら竹村松風として俳句に親しみ[中略]井月の生活上の庇護者でもあった{『中沢区誌』456頁}・熊吉氏の言うのに──私も一時は一寸熱心に句作して井月に見て貰ったものだが、点が辛いというよりも、わからんことを言って滅多に採ってくれない。たまたま直したものは丸で別のようなものにされているというようなわけで、ウンザリして止めてしまったと言っていました{『伊那路』昭和51年9月号339頁}
「活計に道を失ひ」とあるから、宮田の戸長役場の書記の仕事もすでに辞めてしまったのだろう。また、俳諧師としての仕事も干されていたのではなかろうか。『井月全集』の略年譜(403頁)を見ると、明治六年の活動痕跡が一つも記されておらず、仕事を干されていたと考えて矛盾はない。・厳暑の節、[中略]其後は打絶御疎音申何共多罪、[中略]活計に道を失ひ住居不定の仕合、此壱両年は下牧にも出向不申、[中略]五声君に預け置候勧化帳の内、金高の分、利足等勘定に廻し候へば、余程に可有之候間、身右一勘定御願申、右の内何程か借用いたし候而{『井月全集』294~295頁、伊那市西春近赤木の現章という人物に宛てた書簡}
同じ明治七年四月、東京の俳諧師・関為山らが「教林盟社」という俳人結社を設立している。・美しくつよみ持けり糸柳 井月{『俳人井月 幕末維新 風狂に死す』249頁。北相木村の厄除観音堂に明治七年四月十七日に奉納された俳額}
もしかしたら井月は、南佐久から秩父山地を突っ切って、東京へ行ってきたのではなかろうか。道中、多摩川や奥多摩で詠んだと思われる句も存在する。これらの季語は晩春~初夏で、新暦四月~五月の旅だったと考えて矛盾はない。・結社之儀何卒御許可被下置候様奉願上候[中略]明治七年四月 訓導 橘田春湖 仝 鳥越等栽 仝 関為山[中略]願之通聞届候事 明治七年四月十八日 宍戸大輔御印{『教林盟社起原録』より。この四月十八日が、正式に教林盟社が新政府から認可された日と思われる}
・武の玉川に遊て 徐に柳のかぜや小鮎くみ{『井月全集』15頁}・玉川 夕士峰も朝不尽も見てさらし搗{『井月全集』47頁}・むら暑き広沢山や閑子鳥{『井月全集』56頁。広沢山は奥多摩町にある}
明治七年七月、井月は伊那市東春近で俳額を作成しており、その撰者は関為山(月之本)となっている。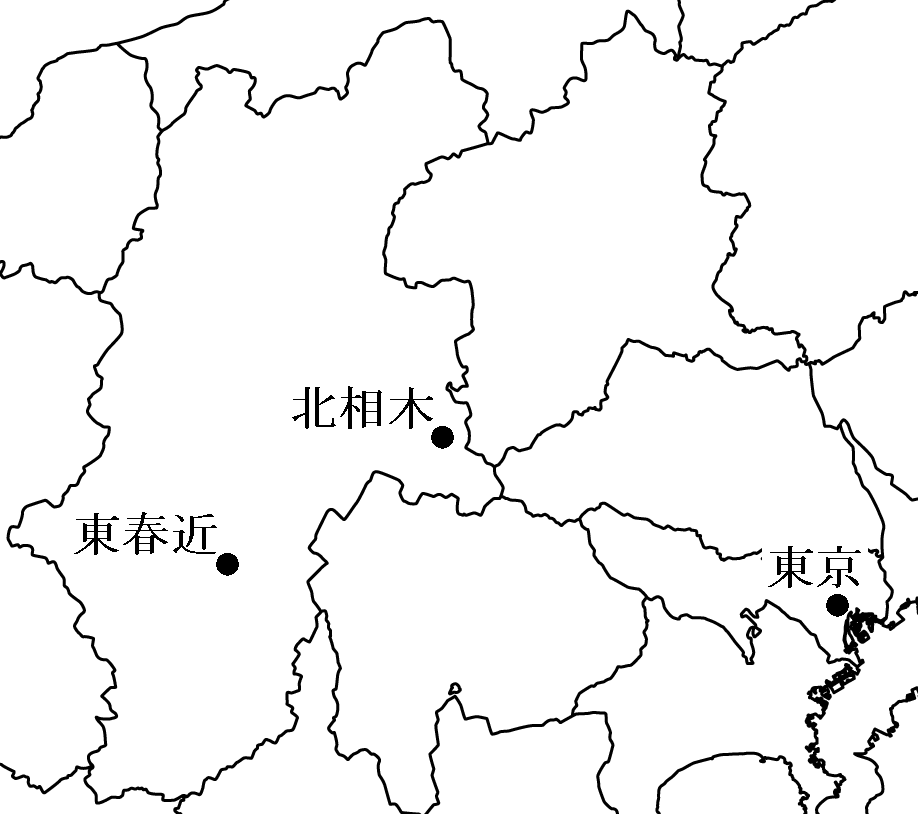
以上を総合すると、「教林盟社設立の知らせを聞いた井月は、如雲という人物の名を借りて東春近の人たちから俳句を集め、投句料を旅費にし、師である関為山に会いに行き、選句を依頼した」という推測が立つ。いまを時めく東京の関為山の選句を取り付けたとなれば、井月の信用も少しは回復したに違いない。井月なりに、再起をかけて頑張ったのだろう。・延寿会揮毫俳額[中略]月之本撰[中略]明治七甲戌年七月 柳廼家書{『伊那路』昭和63年11月号638~639頁}・本村風客飯島如雲[中略]盧[正しくは廬だろう]を結び、雅客清遊の処とする。明治七年騒客柳の屋井月この亭に遊び推賞して鵆菴と命名する。[中略]如雲俳句を募り東都月の本為山宗匠の撰評を得山圃老人の画を添え扁額を□間に掲げ延寿会の盛宴を張り衛の幽声を賞した{『東春近村誌』938頁。□は環境依存文字}
『春近開庵勧請文』に「下牧の五声父の風雅を継で」とあるから、五声の父と井月が交流していたのは確実で、つまり井月は、教林盟社設立の前年の明治六年の時点で、すでに東京の為山たちの動向を察知していた可能性が高い。教林盟社の発足の日に合わせるかのように東京へ向かうことも十分可能であっただろう。・関為山・橘田春湖・鳥越等栽が教導職に任ぜられ、「本月三日於教部省訓導拝命仕候。此段為御知申上候。痩骨も数には入し霞哉」という通知を出した写しが、当時下牧で酒屋を営んでいた加納与右衛門の記録「永代萬蔵記 三」の明治六年六月の頃の上欄に記されている。この手紙は、加納与右衛門あて直接の手紙かどうかわからぬが、このような情報が、いち早く僻遠の一有識者に伝わっているのは興味をひかれるところである。ちなみにこの与右衛門は、井月と風交あった加納五声の父に当たる{『伊那市史』現代編901頁。「痩骨も・・・」は鳥越等栽の句で、『教林盟社起原録』(長野県立歴史館所蔵品)に類句が載っている}
《新天地を模索し始める》・曽倉の桃源院の経堂の額に[中略]父の句が載っていましたから、父に聞くと父は井月が勝手に作って入れたのだ……といっていた{『伊那路』昭和51年9月号339頁}・霞松氏の報ずる所によれば、この連句は井月一人の作であり、他は悉名を連ねたのに過ぎぬさうである{『井月の句集』140頁}・本曽倉連にて中曽倉奉額催、ちらし出来[中略]就ては鳳名猥に加入仕候。不悪御海恕可被成下候。且御近辺御取立御補助の程宜奉希上候也{『井月全集』321頁。勝手に人の名前を使い、投句料の取り立てをしてくれ、補助を出してくれ、というのであれば、ずいぶん図々しいように思われる}
明治九年は、俳諧師・書道家として最も脂がのっていた時期と思われ、大いに活躍している。・明治八[中略]五月、富県井上題治郎、下島真治方にて大幅揮毫。晩夏、早川漫々の『俳諧雅俗伝』を長谷杉島、久蘭堂の求めで書写{『新編井月全集』632頁}
特に、明治九年三月に奉納された伊那市手良の清水庵の俳額は大作で、何日も泊まり込んで作ったものだという。保存状態もよく、井月の技の輝きを今に伝えている。厳しい放浪生活を生き抜くことができたのも、やはり優れた書道の技があったればこそなのだろう。・丙子は九年、井月は五十五歳であった。筆にも脂が乗っている。この年の井月はなかなかの活躍ぶりである。春の清水庵にはじまり、福島の富哉家にて、社中禾圃の追善連句、火山宮下家の襖、下牧有隣家の筆入れ、四徳思耕家の棟木などを揮毫した。上牧菊園の句集序文を書き、十一月富哉方にて歌仙、十二月手良田畝と半歌仙と、晩年の井月としては充実した年であった{『漂鳥のうた』168頁}
・清水庵の奉額揮毫には施行主の家に泊まりきりで十日間を要したそうだ{『井上井月真筆集』162頁}
同じ明治九年三月に、中川村四徳の思耕という人の家で揮毫した棟木には、次のようなエピソードが伝わっている。
清水庵の俳額。伊那市手良。
しかしこの時期、頼りにしていた大事な支援者を、立て続けに失っている。かつて宮田の戸長役場の書記の仕事を世話してくれた亀石は、明治八年に亡くなった。また、土地を寄付してくれるはずだった五声は、明治八年か九年に、二十七歳の若さで亡くなってしまった。・土蔵の建てまへの日、飄然井月が来たので、棟木へ祭詞の揮毫を頼んだ。井月も快諾はしたが、祝ひ酒に泥酔して書くことが出来ず、仕方がないので白木の儘上げてしまった。二三日過ぎてから再びやって来て前日の欠礼を詫び、今日書くと云ふので急に足場を造ってやった。仰向きの姿勢で書いた「天長地久 千歳棟 万歳棟 福寿財棟 明治九年三月二十九日、小沢松次郎代井月書」の大文字が頗る立派なもので、今は有名になってゐる{『井月全集』365頁。思耕の肖像画は飯田市立中央図書館所蔵『百家このみ袋』に載っている}
井月は、今後のことを真剣に考え始めたのだろう。明治九年に『柳の家宿願稿』という長文を記している。・湯沢友右衛門[中略]明治八年三月六十三歳で歿した{『長野県上伊那誌4人物篇』459頁}・「五声は二十七で死にました」[中略]八年九月から九年十二月の間に没したのであろう{『漂鳥のうた』89~90頁}
「草庵の再興」とある。つまり新たに建設するのではなく、かつての東春近の土蔵のようなものでいいから、住まいを得たいと思っていたのだろう。そのためには、越後へ帰って戸籍を持ってくる必要があるので、旅費を捻出するために投句と投句料をお願いします、と言っているようだ。・柳廼家井月寸楮を以、宿願之次第を諸君の机下に述て、広大無量の仁恕を仰ぐものなり。[中略]今より古郷へ罷越、送籍持参の其上からは、草庵蝸廬の再興をはかり、月雪花に望みを遂れば、生て巨万の長者も祈らず、死して蓮の台も願はず。[中略]扨夫に付其御社中諸君へ御頼み申、外でも御座りませぬ、[中略]送別投吟の思召を以て一組づつの入花をさへ給はらば、忽に錦を古郷へ餝るの僥倖にして、亦豈俳諧の狐福なり{『井月全集』515~516頁、『柳の家宿願稿』に}
「兼ねてから教林盟社とは交流があるが、思うようにならない。越後へ戸籍を取りに行きたい、あるいは東京で活躍してみせる」といった意味のことが書かれている。・既に東京第一[大]区七小区、桶町廿七番地関為山宅、教林盟社仮本社にて公務俳用共に取扱ふと云、兼而通行有之間上京拝命の志は有といへども任せぬをこそ浮世と申せば是又其序を知らず、今や愁眉を開くにおゐては戸籍拝命を両手に握り、東京北越に美名を顕はし[中略]懸まくも、賢き君の拝顔を祈るはくだを巻ならず{『伊那路』1998年10月号386頁、『柳の家宿願稿』に}
「東京教林盟社よりの報にて」とある。井月は、どこでこういった通知を読んだのだろう。伊那市西春近の有隣(五声の弟)など、伊那谷の俳人たちが何人も教林盟社に入会しているけれども、いつ入会したのか、はっきり分かっているのは伊那市美篶の柳川で、明治九年二月からである。柳川の家で、井月は東京から送られてくる情報を見る機会があったのだろう。・東京教林盟社よりの報にて、諸国在々におゐても、夫々結社可致の旨申来り、[中略]中々面白き事に相成候{『井月全集』473~474頁。東京へ出て行かなくても、地方で結社を率いて活躍する道が開けた、面白くなってきたぞ、と言っているのだろう}
「布教」とある。教林盟社は、俳人結社でありながら宗教団体でもあった。松尾芭蕉を「神」とし、俳諧によって人民を教化することを目的としていたのである。かねてから芭蕉を信奉していた井月は、その活動に大いに賛同しただろう。・筑摩県信濃国伊那郡美篶村青嶋耕地[中略]俳名柳川 右入社の上は布教弘道専心懸可有之候事 明治九年二月 教林盟社{『画俳柳川菊日和』57頁。教林盟社の会員証}
『教林盟社起原録』の末尾には、幹部の名が記されている。そこに、広田精知が「社宰」の一人として載っている。井月はどう思っただろうか。「いつか俺だって・・・」と思ったのではなかろうか。・方今教部ノ所嚮 国体ヲ知リ人民ヲ教育スルニ堪タル者挙テ以テ教導職トナス 愚案スルニ世ニ俳諧師ナル者アル枚挙スベカラズ 就中芭蕉派ナドト唱フル者専ラ道学ニ心ヲ寄セ人倫ヲ正ウシ今日ノ事務ニ明ラカナルモノ亦鮮シトセズ{芭蕉派の俳諧師を「教導職」に任命し、人民の教化にあてようという教部省の考えが記されており、関為山・橘田春湖・鳥越等栽の三名が任命された}・今般私共同志之者申合[中略]教林盟社ト唱[中略]結社仕度[中略]当分東京第一大区小七区桶町廿七番地居住関為山宅ヲ右盟社仮本社ト致シ{関為山の住所が詳しく書かれている。井月はこれを見て『柳の家宿願稿』に丸写ししたのだろう}・兼テ規則ノ通来ル五月中社費其外適宜御差出被下度此段依頼候也{以上『教林盟社起原録』より}
明治九年の秋、関為山らと共に、広田精知は姨捨山へ月見に来ている。もし、このことが井月の耳に入っていたとすれば、「精知のように活躍したい」という気持ちがますます膨らんだのではなかろうか。あくまでも推測だが。明治九年二月
教林盟社々長
橘田春湖
鳥越等栽
関 為山
仝社宰
河村石叟
青山菊雄
中村是三
広田精知
松平呉仙
間宮宇山
土沢沙山
小野素水
{『教林盟社起原録』巻末より}
その広田精知は、東京で大成し、数々の俳諧集を刊行している。だが、これらすべての本に井月の句は含まれていない。・明治九年[中略]十月三日、東京の月之本為山が画家服部波山、俳人五休、精知らとともに姨捨に観月、雅会を催した{『姨捨山の文学』425頁。十月三日というのは新暦だろう。旧暦に直すと八月十六日。仲秋である}
『開化附合集』明治8年刊、序文は関為山
『俳諧開化人名録』明治9年間、序文は関為山
『開化附合集(明治附合集・俳諧自在古今集 乾)』明治12年刊、序文は橘田春湖
『明治発句図画秋津集 春』明治12年刊、『古今発句類題図画 春』の再刊、序文は青山菊雄
『明治発句図画秋津集 夏』明治13年刊
『明治発句図画秋津集 秋』明治14年刊
『明治発句図画秋津集 夏』明治15年刊
『明治附合集 三編(俳諧自在古今集 坤)』明治16年刊、序文は鳥越等栽
『明治発句題砂子集(俳諧明治五百題)』明治17年刊
『明治発句続題砂子集(俳諧明治新五百題)』明治19年刊
『明治発句図画秋津集 拾遺』明治19年刊
『明治発句続々題砂子集(俳諧明治八百題)』明治20年刊(遺作であろう)
『俳諧博物撰 夏』明治20年刊(遺作であろう)
教林盟社では、辰野町出身の小野素水という俳人も幹部として活躍していたが、しかしどうも井月との接点が見つからない。井月が伊那谷に現れた安政のころには、素水はすでに江戸へ移り住んでいた。したがって伊那谷で素水と井月が交流したはずがない。江戸で交流していたとしたら、『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』に素水の句が載っていてもよさそうなものだが、載っていない。井月の俳諧集に素水の句が載るのは、ずっとあとの明治十八年の『余波の水くき』である。
精知が刊行した本の数々{筆者所蔵品}
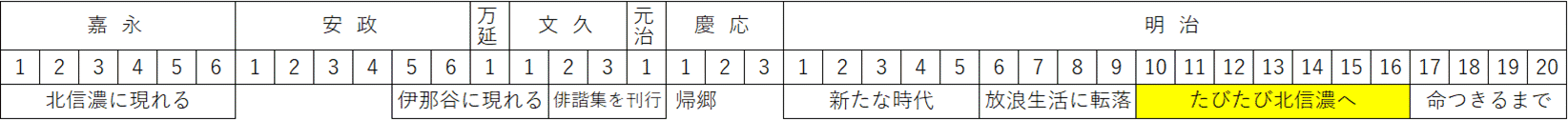
「当所 井月」と書かれており、つまり文音(手紙による投句)ではなく、実際に長野市豊野まで行って詠んだと考えるしかない。「これからはツバメのように、毎年ここへ来て長寿をお祝いしますよ」といった意味に解釈できる。俳句からの憶測は慎まなければならないが、井月は、これから北信濃と伊那谷を行き来して暮らそうと考えていたのではなかろうか。・年毎にめでたく来啼乙鳥哉 当所 井月
{明治十年、峯村鵞雄の還暦の句集『むつびぐさ』に。長野県立図書館所蔵品}
これは、伊那市福島の竹圃の父・三畝の七十賀集に載っている句で、井月と並んで鵞雄が載っていることからしても、井月が北信濃からもらって来たと考えざるを得ない。次のような資料があり、不明字の□□は「嘘と」だと思われる。・明治丁丑第十月(十年)七十賀集[中略]
曇るとは浮世の□□今日の月 鵞雄
みな人のうらやむ老や花の宿 井月
{『伊那路』昭和39年3月号99~100頁}
次のような資料もある。明治十年の旧暦二月二十九日、北信濃から伊那谷へ戻ってきたときのものと思われ、たぶん長旅で足袋がボロボロになっていたのだろう、駒ヶ根市東伊那の歌丸(宮脇歌雄)という学校教師から、足袋の代金を恵んでもらったと思われる。・曇るとは浮世の嘘と今日の月 明治十年 手子塚神社奉納額
{『一茶ゆかりの白斎と文虎』172頁。鵞雄の句として載っている}
明治十年に、伊那・駒ヶ根の俳人たちと詠んだ連句がいくつも伝わっている。北信濃に活路を求めながら、伊那谷の俳人たちとも上手く付き合っておきたい、といったところであろう。・記 一 足袋一足 右代料の内弐十銭正請取申候也 丁二月廿九日 柳の家 宮脇先生玉下{糸魚川歴史民俗資料館所蔵品。『井月全集』326頁には「十二月」となっているが、筆者の解読では「丁(ひのと)二月」であり、明治十年に井月が書いた領収証と考えられる。『手紙で読み解く 井月の人生』120頁に写真を載せておいた}・宮脇歌雄 明治初期の教育者、神職。弘化三年伊那村(現駒ヶ根市東伊那)に生れた。明治五年十一月高見村の善法寺に、伊那村と共同の淳開学校が開設した時教員となった{『長野県上伊那誌4人物篇』420頁}
同じころのものだろうか、凌冬の妻・那美女と詠んだ連句もある。明治十年弥生雪嶺亭に於ゐて興行
木母寺の秋寂しくもたたき鉦 井月
松ふく風の肌をこそぐる 寉子[=雪嶺、殿島学校の教師]
{以下略。『井月全集』433頁}
明治十年夏於呉竹亭興行[=凌冬の家]
撫子や咲ぶりに名のあやまたず 凌冬
馴て村なく湿るうち水 井月
{以下略。『井月全集』433頁}
明治十年九月初旬於呉竹亭興行[中略]
粟の穂や雀がつけば又撓む 凌冬
夕日てかてか月になる空 井月
{以下略。『井月全集』436頁}
明治十年丁丑初冬赤穂駅埜溝素人亭におゐて興行[中略]
蝶に気のほぐれて杖の軽さかな 井月
立場の屋根にのぼる陽炎 祖丸
{以下略。『井月全集』443頁}
「まだら」というのは、那美女が明治十三年まで使っていた俳号。つまりこの連句も、明治十年前後のものと考えて矛盾はない。白骨湯治中
瀬音のみ友として居る夜寒かな まだら
やせたる月の遅き山の端 井月
滾々と素湯は泌るに虫鳴て 凌冬
照降なしに売る挽下駄 竹斐[凌冬の門人]
{以下略。『井月全集』443頁}
松本市安曇の白骨温泉へ、凌冬夫妻らといっしょに湯治へ出かけたのだろうか。あるいは、那美女が白骨温泉で詠んだ句を発句にして、伊那で連句の会を開いただけなのかも知れない。これについては後考を待ちたい。・始め俳号をまだら女と言ったが[中略]八木芹舎の門に、夫凌冬とともに入門してから那美女と称した{『長野県上伊那誌4人物篇』327頁}・馬場凌冬[中略]明治十三年、一切の役職を譲って、妻那美女[中略]とともに再度上洛し、芹舎に就いて本格的な俳諧修行をした{『長野県上伊那誌4人物篇』328頁}
《明治十一年》・軍務を解て再び古郷へ帰給ふ有隣子に謁して 命有て互に花を見る日かな 井月拝{『井上井月真筆集』24頁}
このころの井月は、道を歩けば村の子どもたちから石を投げつけられるようになっていた。・上もなき老の白髪やふじの山 井月{『伊那路』2000年1月号2頁}
「私が十歳位の頃」とあるが、「私」とは『井月全集』の編者の一人である下島空谷という人物。明治二年生まれの人である。・私が十歳位の頃、五六人の友と小学校の帰り道に、偶ま井月の「トボトボ」とやって行く後姿を見つけたので、その腰にぶら下げてゐる瓢箪を擲石の手練で破ることに相談一決した{『井月全集』352頁}
「十歳」が満年齢なのか数え年なのか分からないが、石を投げつけたのは明治十一年~十二年ごろの出来事、ということになるだろう。ほかにも次のような話が伝わっており、井月は村の子どもたちにいじめられたようだ。・明治二年[中略]八月十八日、信州は伊那の村里、中沢村原集落に[中略]生まれました{『文人 空谷 下島勲』1頁}
きっと、歯を食いしばって耐えたであろう。伊那谷を出たいと、何度も思ったに違いない。・母から、前の街道をゆっくり歩いてゆく井月の後を追って、せいげつやい、せいげつやいとはやしたてたといふ話を聞いた覚えがある{『井月全集』増補改訂版の序}・あるときは大勢の通せんぼうにあう。井月は決して逆らわないで、いつまでも止めるのを待っている。もしくは遠回りして行く{『高津才次郎奮戦記』13頁}
明治十一年といえば、井月の師匠・関為山が亡くなった年である。・雇ひ小僧の万太と云ふのが、突然後から石を頭に擲げつけた。その瞬間体をブルブルと振はせて、歯ぎしりをしながら恐ろしい眼つきで振り向いた。が、何も言はず徐ろにまた元の姿勢に向き直った{『井月全集』353頁}
為山の死去によって、「東京へ出て活躍したい、教導職を拝命したい」という井月の夢は、大きく遠ざかったであろう。東京が駄目となれば、越後へ戸籍を取りに行くか、あるいは北信濃に活路を見出すか、どちらかしかない。・一一 戊寅 為山歿、一月十九日、享年七十五{『新選俳諧年表』284頁}
竹圃・富哉は、伊那市福島の人。井月は二月に連句を行い、それを携行して北信濃へ向かい、三月には下長井(現在の長野市中条地区)に到達していた、と考えられる。「俳諧正風起証」は、文久のころ行脚俳人の米海から授かった秘伝書であり、まだ大事に持っていたのだろう。・明治十二己卯年如月於井田斎興行 俳諧之連歌 三吟 井月、竹圃、富哉[中略]附合ったのは伊那峡の人々だが本巻は北信の蔵者の家から出た。井月が携行したものか。[中略]井田斎は竹圃の家{『井月全集』181頁}・明治十二[中略]三月上水内郡下長井久保田盛斎方にて「俳諧正風起証」を書く{『井月全集』404頁}
井月が草庵にしようとしたお堂。
結局、お堂を草庵にしたいという希望は実現しなかったようだが、越後へ戸籍を取りに行くつもりはあったようだ。書簡に次のように書いており、たしかに井月は長岡の出身だったと思われる。・一の瀬庵の義に付、[中略]直さま開庵披露の上、入庵の手つづき万端御相談被下度{『井月全集』327頁。長野市中条五十里市之瀬にある観音堂}・お堂には庫裏と呼ばれる部屋があり、囲炉裏も設けられ暖房や簡単な煮炊きに酒の燗などができたようである{『中条村の神さま仏さま』16頁。井月が住み着くには十分な設備があったであろう}・あし沼堂当時明き有之よし、右庵も一のせには劣るまじき位のよし、愚老は何方にてもよろし{『井月全集』327頁。市之瀬の観音堂が駄目なら、芦沼の大日堂でもよいと考えていたらしい。現在、大日堂は地域センター(集会場)に建て替えられている}
次のような資料もある。三月に中条を訪れた井月は、四~五月(旧暦では夏)までいたのだろう。・長岡迄送籍取に参り候而は如何{『井月全集』328頁}
ただし「跡の月」の句があって秋の季語。季節を先取りして詠んだのだろうか。後考を待ちたい。・1879(明治12)年初夏、上水内郡下長井(現長野市中条)の俳句愛好者らの句に点を付けたもの・右 甲乙 柳の家井月(印)
雲の間のはやき歩や夏の月
松原の中にをがむや跡の月
{信濃毎日新聞2022年3月10日}
「晩夏」とあるから飯山市瑞穂を訪れたのは旧暦六月である。・水沢老人の遠行をいたむ けふの日や泪を包む汗拭ひ[中略]水沢老人──下高井郡穂高村[現在の木島平村穂高]の人、名は源吾右衛門明治十二年歿{『井月全集』48頁。つまり明治十二年の夏に訪れたのだろう}・千草子の愛児を先立給しを悼 いふ事の汗にまぎるる涙かな[中略]千草──下高井郡穂高村字中村、山本八十右衛門{『井月全集』47頁。これも同じころのものではなかろうか。季語は「汗」で、やはり夏である}・明治十二卯晩夏梅春亭おゐて興行{『井月全集』188頁}・梅春[中略]飯山市瑞穂小菅の人。[中略]明治四十四年没。七十四歳{『長野県俳人名大辞典』738頁}
このほか飯山での足跡としては、明治何年のことか分からないが、次のような記事がある。・明治十三辰年春四月於真居庵興行[中略]真居庵──梅春の家{『井月全集』191頁}・明治十三年下高井郡木嶋村[現在の飯山市木島]某方にて幻住庵記を屏風半双に書す{『俳人井月』132頁}
伊藤知月については、慶応元年の追善集『さくら草集』に井月が投句しており、その縁をたどって、息子の知淡のところを訪れたのだろう。ちなみに教林盟社が刊行した『花桜集』(明治十年)、『時雨祭集』第二冊・第三冊(明治十二年・十三年)に知淡の句が載っており、会員として積極的に参加した人らしい。・伊藤知月[中略]の子知淡は父の感化を受けて俳諧をつぎ、[中略]井原井月の当地に来るや連句を催し大正八年七十四歳にて歿した{『飯山町誌』540頁。「井原」とあるが井上井月のことだろう}
明治十三年は、伊那谷に戻ってから松尾芭蕉の『幻住庵記』をいくつも書いている(『井上井月真筆集』130頁~)。「芭蕉さまのように、ささやかな仮住まいが一つほしいだけなのに」と心に念じながら、ひたすら書いたのだろう。暑
なほ暑し降そこねたる雨の跡 梅薫{中野市江部}
うりをむかせる片かげの椽 井月
入船を待る小挙の手を明て 潮堂{中野市間山}
寄りさへすれば石の番持 文康{中野市上今井}
木の間洩る月の光のあざやかさ 喜逸{中野市新保}
棚田の水の落果る音 白淵{中野市三ツ和}
{以上『井月全集』206頁}・潮堂[中略]明治初年、長野県庁の設置とともに営繕掛、のち地券掛をつとめ功績があった。同十三年間山に帰り{『長野県俳人名大辞典』652頁。つまりこの連句は明治十三年以降のものと考えられる}
暗記するくらい何度も読み、何度も書いていたに違いない。そのうちの一つに「東京教林盟社中」と署名している。東京で活躍したいという夢も、まだまだ捨ててはいなかった。・中沢村本曽倉の竹村熊吉氏は、[中略]曽て井月の饑寒の難を救ったこともあり、また俳諧も多少学んだと云はれてゐる人である。或る時廻って来たので酒を飲ませて、何か書くかと聞けば、書くと云ふので唐紙を提供した。[中略]一盃飲んでは書き、二盃飲んでは書いたものが[中略]芭蕉翁の幻住庵記である。無論記憶の儘を書いたもので、その頭脳の確かなのに驚いたとのことである{『井月全集』363頁}
だが、井月自身が入会していた証拠は見つかっていない。教林盟社に関係する刊行物には次のものがあるが、どれにも井月の名はない。「俺も関為山の門人だった」という意味で、「社中」と書いただけではなかろうか。・明治十三庚辰年晩秋浦埜氏の応需 東京教林盟社中 柳の家井月書{『井上井月真筆集』135頁}
・『真名井』明治7年刊《明治十四年》
・『花桜集』明治10年刊
・『時雨祭集』明治11年刊
・『時雨祭集』明治12年刊
・『時雨祭集』明治13年刊
・『時雨祭集』明治14年刊
・『青柳集』明治17年刊(為山追福)
・『結社名員録』明治18年刊
九月、伊那市狐島の凌冬が、円熟社という俳人結社を作った。これは教林盟社の分社であった。井月としては面白くなかっただろう、自分こそが教林盟社で活躍したかったのに、若い凌冬が活躍を始めたのだから。・山圃の死んだのは明治十四年五月でその時の井月の弔句は「東西も分らぬ雁の名残かな」{『井月全集』370頁}
この円熟社は、やがて上伊那地域に一大勢力を成すことになる。井月は苦々しく思ったであろう。そんなこともあってか、凌冬と井月の仲は険悪になったらしい。・分社委任証[中略]
時明治十四年九月 教林盟社々宰長
少講義 鳥越等栽
同 橘田春湖
仝月番領舗
権訓導 小野素水
分社円熟社々宰長
試補 馬場学之亟[=凌冬]
{『伊那市史』現代編901頁}
この「粗相」をしたのが円熟社設立の前なのか後なのか分からないが、関係が悪化したのは事実と思われ、井月は次のような手紙を書いている。・凌冬と井月は仲違ひしたやうである。その原因はなみ女の句集を井月が粗相をして汚した為とも、凌冬が当時としては珍しい生鯖を楽しみにしてゐたのを、不在中に井月が食べたからだと語った人もある{『井月全集』275頁}・ある日井月は、馬場家の改築祝いに招かれて、例によって好物の祝酒をふるまわれ、[中略]つい酔い痴れて、不覚にもたれ流してしまった。新しい畳は台無し、[中略]その後の井月は、馬場家では門前払いであったとか{『伊那路』昭和46年8月号309頁}
「墨附あしく」は、冷遇されたという意味。伊那市狐島を訪ねていったところ、凌冬は留守で、妻女に門前払いにされた、といった意味ではなかろうか。・狐島へ御尋申上候処、御留守にて、甚墨附あしく{『井月全集』334頁}
教林盟社の二代目代表・橘田春湖が判者(選者)になっている。催主の月山は『紅葉の摺もの』のころから井月と長い付き合いがある人物だし、揮毫した鳳雲は『越後獅子』『明治二年の歳旦帳』『明治十一年の歳旦帳』に挿絵を付けてくれた人物。ほか、のちに井月の戸籍を世話することになる梅関の句も載っている。なぜ井月に仕事を依頼しなかったのだろう。まさか井月をのけ者にして作ったのだろうか。それとも、井月が伊那谷を留守にしていたのだろうか。・催主
予貧ぼう故美服をまとひし事な□□□
心には錦まとはすかみぶすま 月山
教導職訓導拝命の時
あふがばや扇もそへて道の風 判者 小築庵 春湖
茲歳明治十四十一月良辰奉額
{清水庵の「井月が参加していない俳額」に。□は筆者が判読できなかった字}
・両吟百二十句
此の句帖は[中略]有隣[中略]と井月とが明治十五年三月一日春の雪、各々三十句、梅の花各々三十句、合計百二十句を連作的に詠み続けたもので両者各々の筆で隔行交ぜ書に認めて居る{明治十五年の三月一日は、旧暦に直すと一月十二日。新春を祝って詠んだものと考えられる}折人も思案顔なく梅の枝 有隣
振袖の花盗人や楳屋敷 井月
{以下略。『井月全集』123~124頁}
このころの井月の様子を伝える記事が伝わっている。・明治十五年三月一日於不狐亭興行
俳諧鯉鱗行 両吟 有隣 井月初鶏や常に似合ぬ太き声 有隣
若水汲の歩行井の端 井月
{以下略。『井月全集』194頁}
よく知られている「頭は禿げて髯もうっすらした、色黒の井月」とは、ずいぶん違った印象に思える。長きにわたる放浪生活で疲弊していたのだろうか。・明治十五年[中略]、天竜川の殿島橋[中略]の袂で、前々から見聞きしていた「井月」に出合った。三月末の夕方で人通りもない路を歩いていた「井月老人」は、着物は汚れ草履(あるいはわらじ)も長く伸びたものを履いており、以前に見かけたより一そう前屈みで、弱々しい足どりであった。[中略]面と向かって初めて見た「井月」は、髪も髯も伸び青白い老顔のように見えた{『伊那路』昭和62年3月号137頁}
・寒岳園白斎追善句集
{中略}
臑で見る芝居は殊に大当り 井月
きれぬできれる棒の脇ざし 柳翠{以下略。『井月全集』446頁には「明治十五年序十六年六日版」とあるが誤り。実物には「明治十五午年五月上旬浣」とあり、序文に「明治十六年六月」と書かれている。つまり明治十五年に刊行したものであり、白斎という俳人の三十三回忌にあたる明治十六年に合わせるため序文には明治十六年と書いたのであろう}
俳句ならば文音(郵送などによる投句)の可能性もあるだろうが、連句の文音は、次の人へ、次の人へと手紙を転送する必要がある。住所不定の井月のところへ、北信濃からそのような手紙が回ってきたとは考えにくい。井月が実際に北信濃へ行って参加したと考えるのが妥当である。・奥山の名もふれ行や氷うり 井月
{『井月全集』423頁には「奥山の名を」となっているが誤りである}
井月は御開帳をお参りして、それから長野市豊野の鵞雄のところへ足を延ばしたのではなかろうか。伊那市東春近の山好の家には、次のような話が伝わっている。・明治十五年の開帳は西南役後の好景気で賑わい、[中略]「毎夜球灯を点じ、暗夜も白日の如く、最も見事」であった{『善光寺史研究』436頁}
たびたび北信濃へ行っていたはずの井月を、あえて善光寺参りに連れて行ったのだから、何か特別な行事のときと考えるのが妥当。すなわち明治十五年の御開帳しか考えられない。井月は、初夏のうちに伊那谷に戻ったと考えられる。・山好が井月を善光寺まで送って、お参りを済ませると、「ここまででいいから」と言って井月は去っていた。ところが山好が伊那に帰り着くと、井月のほうが先に帰り着いていたので驚いたという{山好の家に伝わる話。筆者の独自取材による。このとき山好は、奥さんを同伴していたのではないか、という話もお聞きした。きっとあちこちを見物して、井月よりも戻りが遅くなったのだろう}
明治十五年の秋、ついに井月は越後へ帰る決心をしたらしい。『暇乞の訳』と題した手紙がある。・明治十五午年麦秋 応需 柳廼家井月 拝書{『井月真蹟集』143頁の『幻住庵記』に。麦秋は初夏の季語}
まず明治五年の送別会の失敗のことが書かれていて、「此三五年」とあるから、明治八年~十年ごろのことなのだろうか。・暇乞の訳
嚮に大久保中村新六……挙に依て故郷へ帰……の燕も崩れ簗……なりしより、赤穂のまこ……餅となり、下寺社中のとり持も飲喰とともにひゐきの曳たをしとやら、明樽ともち寄の…重筥と居残り客の始末も無。其後呉竹園のあるじ、おのれが門下を鼓舞して、散しほの柳の家を越路に押遣むとせられしも、時至らざりしにや、思い絶て此三五年は更にぼう然たりしに、今とし中沢連に人有て、帰郷の沙汰を深切に説諭せられしを、再三おもひ廻して拙吟をものし侍る
立そこね帰りおくれて行乙鳥 柳の家
{『井月全集』274頁。実物は駒ヶ根市立博物館に所蔵}
この、亀石の家に暇乞いに来たときの話が伝わっている。・暇乞 立そこね帰り後て行乙鳥 井月{『伊那路』2025年1月号21頁に写真を載せておいた。明らかに晩年の筆跡である}
「誰か知人が」とあるが、山好のことだろう。・書記をやめてからずっと後に、羽織袴姿で、越後へ帰るからと挨拶にきた。このときは誰か知人が、善光寺まで送っていったといふ{『伊那路』昭和39年3月号126頁}
「お詣に同伴するといって」「井月を誘って」という部分に違和感をおぼえる。このとき井月は、『暇乞』と題した俳句をあちこちに贈り、世話になった人たちに別れの挨拶を済ませ、明らかに帰郷の意思を持って旅立ったはずだ。山好のほうから善光寺参りに誘ったとは思えない。・まかれた井月 厄介な井月を国元へ送り帰すべく、お詣に同伴するといって東春近村の[中略]山好が善光寺まで行き、翌朝宿屋を立つ時、酒の中毒でか震へる手先で草鞋の紐をぐずぐず結へて居る間に、山好は、茲まで来れば越後へ帰るだらうと思って、こっそりまいて帰村した{『井月全集』365頁}・ある年の秋、上伊那郡東春近村の山好という者が、井月を誘って越後路へ送り返そうと長野まで来た{『高津才次郎奮戦記』11頁}
この記事にある「楽二」という人物については、次のような資料が伝わっている。・下高井郡延徳村桜沢[現在の中野市桜沢]に、景斎と云ふ俳諧師がゐた[中略]。景斎の母親は[中略]、ある日の夕方[中略]、一人の乞食坊主を拾って来た[中略]。家内の者は、畑から拾って来た井月と言ってゐた。景斎は[中略]この頃、俳諧師らしい好みの離れ座敷を新築した。井月とあって話してみると、尋常の俳諧師でないことがわかったので、この新しい離れを彼に与へた[中略]。ある夜、「先生一筆願ひませうかな」と景斎が出した短冊に、井月も気軽に筆をとって、「貸すはずの提灯できて花の宿」としたためた[中略]。景斎の部落には楽二と云ふ宗匠がゐて、村の青年はたいてい俳諧をやった。井月が景斎のところへ拾はれて来たと云ふので、たちまち村の青年たちが集まるやうになった{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号2頁}
井月が中野市桜沢で拾われたのは、楽二が帰郷した明治十五年以降のことと思われ、『暇乞の訳』が明治十五年の秋に書かれたという推定と矛盾しない。・楽二[中略]明治十一年四月東京に行き、花見ののち『奥の細道』をたどり、冬には松島、羽黒山を一見、秋田で越年。翌年春再び松島に遊び北海道に渡り、千島で越年、十三年には佐渡に渡った。[中略]明治二十四年[中略]没。六十一歳{『長野県俳人名大辞典』883頁。井月より九歳年下の俳諧師だったのだろう}・楽二[中略]明治十五年春、帰郷。信州下高井郡延徳村桜沢区{『明治大正俳句史年表大事典』61頁}・卯の花の白き心を手向哉 楽二{明治十五年五月、峯村鵞雄刊『花の滴』に}
桜沢からは、富士山の形をした山が三つ並んで見える。越後富士(妙高山)・信濃富士(黒姫山)・戸隠富士(高妻山)の三山で、どれが一番とは言えない見事な風景だ、と言っているのだろう。・三つ組やどれとも言ぬ春の富士{『伊那路』2025年2月号63頁}
《明治十六年》
中野市桜沢から見える三つ組の富士。
酒でしくじって、身ぐるみはがされたことが書かれている。伊那谷ならば、お金がなくても俳句の一つも書いてやれば、みんな酒を飲ませてくれただろう。ところが北信濃ではその手が通じなかった。このあと井月は、おそらく荷物を景斎の家に置きっぱなしにしたまま、明治十六年の五月ごろに伊那谷へ逃げ戻ったのだろう。・青年たちは、井月に俳諧の指南をしてもらった御礼に、衣服一着を新調して贈った。新しい衣服を着た井月は、ある日一寸外出をしてくると言って出かけた。しかし夕方になっても帰らず、翌日も、翌々日も帰らなかった。あとできくと、隣村の茶屋で、終日酒をひっかけた井月は、嚢中無一物、その新調の衣服をぬがされてしまった。その後幾日たっても井月は帰らなかった{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号2頁}
「葉にすてられて」の句は、善光寺でまかれたことを言っているのだろう。恨みを込めたような句だが、しかし山好と絶交になったわけではなく、その後に書かれた井月の日記を見ると、たびたび山好の家に立ち寄っている。・翌年の五月頃、携行した竹袋や印章類は失くして又ひょっこり南へ戻り、中箕輪村松島で昼食を済し、その夕方嚢中僅に三百を持って東春近村の随布亭に姿を現し、「はい御免よ」「先生か」「ハイ私ぢゃ千両、千両」「越後へ行ったさうだが」「それが行かんぢゃ。ハイこれが土産だ」といって出したのが左の句である。
秋経るや葉にすてられて梅もどき{『井月全集』367~368頁}
「旧四月」とあり、新暦なら五月ごろだ。「五月頃ひょっこり南へ戻り」という記事と合致している。「讃岐屋」は、伊那市坂下の稲谷という俳人の家で、円熟社の幹部。明治十六未年旧四月 日改 坂下讃岐屋
出口から名の二つある清水かな 稲谷
其行先の道に居る鷭 富哉
弁当の早い時分に茶屋ありて 其伯
勧めに来ても直の出来ぬ駕 井月
{『井月全集』304~305頁}
明治十年~十六年に井月が訪れた場所。
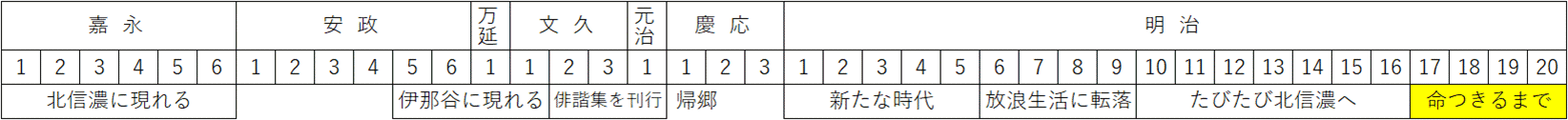
「湯沢家」というのは、かつて井月に書記の仕事を世話してくれた宮田村の亀石の家。井月が出発の前に「暇乞」の挨拶に行った家である。逃げ戻ったのは五月頃と言われているが、たぶん合わせる顔がなかったのだろう、十月の末になって、ようやく帰還の挨拶に訪れたものと思われる。・後、十月も末といふころ、単衣物一枚で、ぶるぶる震へて、また湯沢家へ帰ってきた{『伊那路』昭和39年3月号126頁}
「去年の冬」とは明治十五年に善光寺でまかれた後のことか、それとも明治十六年にぶるぶる震えて宮田村に戻ってきた後のことか。「命の覚束なさ」は、単衣物一枚で凍死しそうな様子、「人々のあやしく沙汰し」は、井月が置き去りにされて身ぐるみはがされたと噂しあう人々のこと、「いづれの頃にくり立しにや」は、どこから順を追って話したらよいだろう、という意味。「花のさく日」に浮かれて無銭飲食、「もと来し道にたどりつつ」は、伊那谷へ逃げ帰ってきたこと、「旅ごろも耻つつ」は、新しい衣服をとられてボロ一枚になった自分を恥じていると思われる。・去年の冬は命の覚束なさを 人々のあやしく沙汰し申されけるに こたびいづれの頃にくり立しにや 西上人のの給ひける 花のさく日は浮れこそすれ もと来し道にたどりつつ そこはかとなく行暮て 旅ごろも耻つつ花の宿りかな 井月{『井上井月真筆集』24頁}
《戸籍を作る》・晩年の井月は乞食も乞食、余程極端な状態であったらしい{『井月全集』345頁}・当時、井月なんて何が目あてであのような惨めな暮しをしているのだろう、首でも縊るか水にでも這入ってひと思いに死んだ方が増しであろうに……などというのを耳にしたことがありました{『伊那路』昭和51年9月号343頁}
井月は文政九年ではなく文政五年生まれのはずだが、死亡日は合っている。・柳の家井月戸籍謄本
文政九年十二月廿一日生 養父 塩原清助 戸籍編製ノ際、漏籍相成居リ候間加籍願済ニ付明治十七年七月二十五日入ル明治廿年三月十日死ス{『伊那路』2000年10月号364頁}
当時、戸主は徴兵が免除されたため、徴兵逃れのために分家を作ることが、かなり行われていたらしい。・聞く処によると、徴兵除けの復籍した者の跡へ、填補の形式か何かで入籍したものであるとのことであるから、戸籍上の年齢は勿論都合上の年齢である{『井月の句集』略伝19頁}・梅関には男子が無く、長女に養子を迎へ、次女の処へ伊那町上牧の某が入籍して分家戸主となった。徴兵のがれの為に戸主となったのである。所が[中略]気に入らなくて、某は又同町野底の某家に婿入しようとしたが、戸主が他へ入籍は協はぬので、井月を塩原清助の名でその分家の戸主に祭り上げたのである{『井月全集』410頁}
梅関の家には、離れの小屋があり、井月はときどき泊まりに来ていたという。・徴兵のがれ あの手この手(ある雑誌の記事より)
[中略]他家に入籍するが、絶家、廃家を再興して戸主になること{『澤底区誌』396頁}
《最後の俳諧集》・終戦直後、生家を頼って疎開したという尾津よし子おばあさんは、井月が住んだという、草屋根の小屋を修繕して住まわせて貰ったという。[中略]井月が肩に吊して歩いたという行李と、その中に印、はんこというもの等有ったという{『伊那路』昭和62年3月号135頁}・離れは玄関の間と奥の二た間があった。二た間とも広さは、六畳ぐらいであった。[中略]井月はこの離れに本を置いて、俳諧の座を開いていたという話を聞いている。その離れは茅葺であったので萱の傷みが激しく、[中略]昭和二十年、離れを本家が取り壊した{『井上井月研究』88頁}・隠居屋には、井月は家人の知らない中に不定期に泊まっていたという。[中略]八畳二間八坪、土壁で専門の大工が作ってあり、壊すのに容易でなかったという{『伊那路』2011年9月号361頁}
原稿は完成していたようだ。・もともと日記帳として拵へたものでなく、[中略]伊那峡の風交者の句を選抜して摺物にする稿本であったらしく、多分採句を兼ねて行脚中、携帯して諸家の句を収集すると共に、行程と寄泊した所等を書込んだものであらう{『井月全集』223頁}
しかし、もはや井月自身の力では、刊行することができなかったのだろう。・井月筆の「大奉書一枚摺口画入諸家投吟集」と題する、半紙十七枚を横長に二ツ折に綴ぢた句帳が有る。表紙両側に「明治十七年秋八月」「柳の家井月控」と記し{『井月全集』379頁}
見かねた梅関は、明治十八年の秋、六波羅霞松という若い俳人の手を借りて、井月のために『余波の水くき』という俳諧集を作ってやったのである。・諸家の御玉吟を伺ひ、生涯の風流を催し大摺物を企候処、春去秋来てに今満願に至らざるは、全く金銭のたしなき故とこそ{『井月全集』310。なお『伊那路』1998年11月号454頁に「この書簡は明治十七年の旧暦十月十二日の書簡」とある}
『余波の水くき』{筆者所蔵品}
『余波の水くき』の序文は、仲たがいしていたはずの凌冬が書いており、和解したのだろう。事実、井月の日記には凌冬の家を訪問したことが書かれている。・越後の国の人井月雲遊の□を信濃にとどむる事茲に年あり。この頃此土地へ入籍して、鬼籍にいるも亦寔にこころを決めたるとなり。其心をさだめたるより思立て年ごろ交り深き人々の句を乞得て小冊をものし、名残の水くきと冠らせ、永世不朽の交りを期せんとの志となん。その志を助けて霞松梅関の両士四方に奔走し、遂に桜木にちりばめて、事の成るに至れり。[中略]明治十八年季秋 呉竹園凌冬{『井月編俳諧三部集』177~178頁。『余波の水くき』の序文。□は環境依存文字}・霞松[中略]越後に生まれたが維新の際彰義隊に属したため捕えられて高遠藩に預けられ[中略]昭和九年三月三日没。九十歳{『長野県俳人名大辞典』111頁。逆算すると『余波の水くき』製作のときは四十一歳の若手俳人だったであろう}
『余波の水くき』の巻末は「落栗の座を定めるや窪溜り」という井月の句で締めくくられている。北信濃と伊那谷を転がり続けた井月だったが、ついに伊那谷に居場所を決めた、という意味が込められているのだろう。・狐島呉竹園訪。あるじ婦夫在庵{『井月全集』454頁。明治十七年二月三日の日記。呉竹園は凌冬の家。つまり『余波の水くき』刊行の前に和解していたと考えられる}
なお『余波の水くき』には、なつかしい広田精知が東京から句を寄せているが、翌年(明治十九年)に井月より先に亡くなっている。・古里に芋を堀て生涯を過さむより、信濃路に仏の有がたさを慕はむにはしかじと、此伊奈にあしをとどめしも良廿年余りに及ぶ。取分親しかりける人々の、むかしを思ひ出して夜寒を語る友垣に換るものならし。明治十八酉の行秋 落栗の座を定めるや窪溜り 柳の家井月{『井月編俳諧三部集』239~240}
筆者は常泉寺を訪問し、墓地を全部見て回ったが、精知のものと思われる墓は無かった。「関東大震災のあと、墓地がずいぶん縮小したので、もう無いでしょう」という話もお聞きした。東京で大成した精知の墓は跡形もなく、一方、伊那谷に埋もれた井月の墓が今なお人々に大事にされているのを見ると、何とも皮肉に思える。・稲の香やひと穂ふた穂のはしりより 精知{『井月編俳諧三部集』182頁。「稲」は「伊那」に通じる。つまり「井月さんの俳句は、伊那谷に現れたころから香り高いものでしたね」と言っているのだろう}・十九 丙戌 精知歿、九月一日、小梅静泉寺に葬る{『新選俳諧年表』294頁。東京都墨田区の常泉寺のことと思われる}
しかしこの句は、明治十四年に広田精知が刊行した『明治発句図画秋津集 秋』に「宵闇や月のなき間は星明り 素水」という形で載っている。つまり、井月のために詠まれた句ではない。以前に詠んだ句の中から、適当なものを送ってよこしたのだろうか。あるいは『余波の水くき』の編集者が、既存の俳諧集の中から拝借して載せた可能性もある。後考を待ちたい。・宵闇や月のなき間を星明り 素水{『井月編俳諧三部集』182頁}
ところで、『余波の水くき』の序文は、もともと駒ヶ根市赤穂の蔵六が書く予定だったらしい。だが、何らかの理由で蔵六ではなく凌冬が書くことになったのだろう。ちなみに、明治十九年あるいは二十二年に蔵六は凌冬の円熟社に入っている。・喰太りして声高し稲すずめ 蒼芦{『井月編俳諧三部集』209頁。とても井月のために詠んだ句とは思えない。井月は痩せ男だったと伝えられている}
《井月の最期》・柳の家井月ぬしは、はやくより風雅に遊びて、殊に蕉翁のみちを慕ひ、月花に情を移し、降雪の越のふる里ふり出て、此信濃路に杖を曳きけるより、いくばくの年月を経ぬる。いなにはあらぬ伊奈郡みすずの里に笈をおろして、落栗の吟あり□。年頃親しき友の集めて一巻のそめぎぬとなしぬるは、寂栞さびし寝覚の友垣にせんとの結構ならんかし。亀の家蔵六述 柳の家の占居を祝して 百までも踊る秋あれ稲雀{『井月全集』286~287頁。渡り鳥のツバメだった井月さんは、伊那に定住するスズメになりましたね、百歳までもお元気で、といったところだろう。□は難読字}・円熟社の発足当時は、社員四十名未満のものであったが、明治十九年[中略]には、赤穂の松崎蔵六(当時郡書記で坂下居住)[中略]など、五十数名が加入した{『伊那市史』現代編903頁}・呉竹園遺稿の奥書に拠れば、明治二十二年に蔵六は凌冬に入門したことになって居る{『井月全集』286頁}
明治十九年の夏、井月は戸籍上の娘のために婿探しをしている。娘の将来を心配したか、あるいは、もうじき自分が力尽きることを予感していたのだろうか。・明治十九年六月十八日(陽暦七月十九日)晴天なり。井月、川井(松本辺の弓師と云ふ)来り茶振舞ふ{『俳人井月』134頁、駒ヶ根市中沢の梅月の日記。『余波の水くき』完成後も歩き回っていたことを裏付けている}
そしてついに明治十九年の十二月、駒ヶ根市東伊那の田んぼの中で、井月は行き倒れになって発見されたのだった。まだ息があったので、戸板に載せられ、村から村へと運ばれて、伊那市美篶の梅関のところへたどりついたという。・柳の家井月、此度聟養子□ひ請度、[中略]娘は塩原折治二女当丙十九歳也{『井月全集』325頁。□は環境依存文字。折治は梅関の本名。丙は明治十九年。この書簡には「亀の鳴事も有しを夏の月」などの句が添えられており、つまり夏に書かれたと考えられる}
たらいまわしにされたような印象を受けるが、これは村伝いに病人を送り届ける「村送り」だったのではなかろうか。ただし、次のような異説がある。・時は明治十八年師走某の日、(高津氏によれば明治十九年)信州上伊那郡伊那村[現在の駒ヶ根市東伊那]の路傍乾田の中に、身は襤褸を纏ひ、糞まみれとなって倒れてゐる井月を発見した。[中略]村人数名が戸板に載せ、[中略]火山峠を越え、隣村富県村字南福地の某地点に置いて帰ったのである。[中略]竹風老人はまた村人三四人を頼み、[中略]河南村字押出の六波羅霞松氏の処へ担ひ込んださうである。霞松氏は[中略]また若い人達の肩を借りて三峰川を渡り、美篶村末広の太田窪、塩原梅関氏方へ送り届けたのである。[中略]茲で腰も立たず、口もきけぬ悲惨な病躯を横たへてゐた{『井月全集』348~349頁}
・富県村の[中略]露鶴翁から聞いた所では、[中略]幾日か静養した後、美篶村へ行って死にたいと云ふのでその義弟宮下三子と二人で送ったが、[中略]「川天白」の辺で井月は固辞して一人となった。そして彼が三峰川を渡り終る迄堰土堤に二人は見送って居たといふ{『井月全集』406頁。つまり井月が自力で川を渡ったというのだ。『伊那路』昭和62年4月号198頁に「当時三峯川は押出から対岸へ並べ石や二本丸太の粗末な橋であった」とある}
次のような話も伝わっている。
上伊那クリーンセンター付近の三峰川。このあたりを渡ったのだろうか。
竹風は伊那市富県の人。井月の遺品をもらったという。・井月が伊那村[駒ヶ根市東伊那]で野倒れになって、南福地に送られて来て逢ったとき微かな声で、「竹風ヤイ……己れは明日死ぬぞ……辞世は三枚ある、どれでも出せ」云々と、譫言のやうに言うた{『井月全集』367頁。一旦は死を覚悟したのだろうが、静養して持ち直したのだろうか}
この芭蕉像は、芭蕉忌の催しのときに使っていたのだろう。あるいは、草庵に安置するためのものだったのかも知れない。・一、芭蕉陶像一体 一、七部集一部(井月の朱註入り) 一、歳時記一部 一、自著一部(中折紙四枚綴にて、雅俗の言葉を分けたもの){『井月全集』366~367頁}
病床にありながらも、井月はまだ死ぬわけにはいかないと思っていたようだ。伊那市美篶の六道地蔵尊に俳額を奉納しようと計画していたのである。もはや身動きもできない体なのに、俳諧師としての執念は持ち続けていたのだろう。井月の代わりに、梅関が俳句を集めに出かけていったと伝えられている。・病床といってもそれはお粗末なものであったといふ{『井月全集』407頁}・ここの納屋で六十六年の数奇の生涯を閉ぢた{俳句雑誌『科野』昭和22年3月号12頁}・離れはなかったで、納屋にいたというだけど、くわしいことはわからないでねえ{『漂鳥のうた』251頁。昭和二十年ごろ取り壊された「離れ」のことをご存知なかったのだろう}・竹林の前の赤い屋根が坂田兼七のあき馬屋で、ここに戸板で運ばれ息を引き取った{『漂泊の俳人 井月 回想の句画書文集』17頁}・井月が寝起きした[中略]家は、八畳と六畳のバラック。いまは耕耘機などの農機具置場になってしまっている{『俳句あるふぁ』1996年2・3月号32頁。しかし、井月が寝泊りに使っていた小屋は馬屋でもバラックでもなく、茅葺・土壁だったはず}
結局井月の具合は良くならず、明治二十年の三月十日、静かに息絶えた。・二十年二月十日([新暦]三月四日)晴天なり。六道地蔵尊奉額面につき、梅関と云ふ人、井月病気に付き句貰ひに廻るとのことにて入花三銭{『俳人井月』134頁。駒ヶ根市中沢の梅月の日記。井月が亡くなる六日前の出来事である}
亡くなる間際に筆を持たせてもらい、「何処やらに鶴の声きく霞かな 井月」としたためたという。これが絶筆となった。数え年で六十六歳の生涯だった。・命日は河南村龍勝寺の過去帳によって二十年三月十日、旧暦の二月十六日であることが確かめられた{『井月全集』406頁。なお、明治の後半に「井月」という名の俳人が活動しているが(例えば『伊那の俳人』36頁)、それは横井井月という飯島町日曽利の人。井上井月とは別人だから注意を要する}
ただし異説もある。・臨終の二時間前、俳友霞松氏一盞の酒を勧めて一句を乞ふ。井月頭を左右に打振り出来ぬよし答ふ。強て筆を把らしめしにこの句を書けりといふ{『井月全集』9頁}
井月の人生はこれで良かったのだろうか。誰にも分からない。だが、最後まで自分の生き方を貫いたのだ。俳諧一筋に、あがいて、あがいて、あがき続けた人生だった。井月の墓には、今日も酒が供えられている。・梅関の三女なる老婦に私が質した所に依ると、師走の三夜に病みほうけた井月が門口に倒れて居たので、早速家の中に入れて介抱する事五十余日、死亡の前日坂下[中略]から饅頭を買って来て分けてやった。翌朝九時頃、食べ物を持ってこの人が病床[中略]を訪れると、井月は昨日の饅頭を胸の上に持ったまま仰向に眠って居た。声をかけるとパチリと一旦眼を開いて、再び閉ぢた時はもうこと切れた時であったと言ふ。この人の半紙では、その頃は井月を訪ね寄る人も無かった{『井月全集』406~407頁}
《この章のまとめ》
井月の墓。伊那市美篶末広。
・駒ヶ根に日和定めて稲の花 井月 東京市外田端 芥川龍之介氏蔵{『井月の句集』巻頭写真に}
そんな芥川の協力もあって『井月の句集』は作られたようで、本が完成したときの喜びを詠んだ俳句もある。・鯉が来たそれ井月を呼びにやれ{『芥川竜之介俳句集』114頁}・井月の瓢は何処へ暮の秋{同書117頁}・井月ぢゃ酒もて参れ鮎の鮨{同書126頁}
・井月の句集成る 月の夜の落栗拾ひ尽しけり{『芥川竜之介俳句集』128頁}
のちに芥川は、『庭』という短編小説に井月を登場させており、単なる興味で終わらず、かなりほれ込んでいたのかも知れない。
『井月の句集』{筆者所蔵品}
『井月の句集』には、高浜虚子・内藤鳴雪・寒川鼠骨・小沢碧童の四人が巻頭句を寄せている。・「蛙が啼いてゐるな。井月はどうしつら?」──これが最期の言葉だった。が、もう井月はとうの昔、この辺の風景にも飽きたのか、さっぱり乞食にも来なくなってゐた{『現代日本文学大系43芥川龍之介集』190頁、大正11年『庭』より}
『井月の句集』の跋文は、芥川が書いている。・井月賛 丈高きをとこなりけん木枯に 虚子・井月句集に題す 秋凉し惟然の後に惟然あり 鳴雪・井月句集に題す 露けさを米貰はずに帰られし 鼠骨・井月の句集成る。翁と著者下島先生とは世を隔つと雖も同郷の人、因縁のふかさ、ありがたさ、なみだこぼるるばかりなり。空がはれゆき日影さす雲 朝の光り消えゆき日影さくる身 碧童{以上、『井月の句集』巻頭より}
『井月の句集』は空谷による自費出版で、発行部数もわずかだったようだが、その後、昭和五年の『井月全集』にも、平成三十年の『新編井月全集』にも、芥川の跋文が脈々と受け継がれている。・空谷下島先生の「井月の句集」が出るさうである。何しろ井月は草廬さへ結ばず、乞食をしてゐたと云ふのだから、その句を一々集めると云ふ事は、それ自体容易な業ではない。私はまづ編者の根気に、敬服せざるを得ないものである{『井月の句集』跋文より}
・井月の墓前にて 山頭火
お墓したしくお酒をそそぐ
お墓撫でさすりつつ、はるばるまゐりました
駒ヶ根をまへにいつもひとりでしたね
供へるものとては、野の木瓜の二枝三枝
伊那市美篶末広、井月終焉の地にある山頭火の句碑。
「井月の伝記 ~命つきるまで歩き続けた俳人~」令和7年(2025年)公開
一ノ瀬武志
井月の個人研究家として執筆・講演多数。著書に『手紙で読み解く 井月の人生』など。