気付いたところを列挙していきます。井月資料室へ戻る
P.30 L.10 「出席者百三十人」→「出席者百十三人」 (円形の参加者名簿を数えてみると113人である) P.34 L.4 「春近し」→冬の季語。 P.90 脚注L.1 「家づと集 巻末に出ている一句」→ 巻末は誤り (巻末の句は「ちりそめてから盛なりはぎの花」) P.98 脚注L.3 「鷲雄」→「鵞雄」 (新編P.331 L.3を参照。五版P.424 上段 L.1が間違っている) P.141 L.4 「ちりそめて…」→ 詞書「しほらしくもいとなつかし」を追加 (井月編俳諧三部集P.165、家づと集の巻末) P.205 L.9 「新し」→「新らし」 (井月編俳諧三部集P.74) P.206 L.11 「持つ」→「もつ」 (井月編俳諧三部集P.76) P.210 L.10 「踊り」→「踊」 (井月編俳諧三部集P.78) P.211 L.2 「島原」→「嶋原」 (井月編俳諧三部集P.78) P.217 脚注L.2 「母袋」→ 地元では茂田井と表記する (日下野学校史P.64 L.3) P.233 L.8 「五位鷲」→「五位鷺」 (五版P.163 L.8) P.241 脚注L.2 「彦兄」→P.414脚注L.2には「彦児」とある (高遠藩の刀工、野溝彦右衛門のことらしい) P.267 L.9 「込あふ」→「込合ふ」 (五版P.197 L.1) P.273 L.3 「おどか」→「のどか」 p.283 L.9 「がっちゅう」→「びっちゅう」 P.288 L.12 「口の口」→「□の□」(不明字を表す四角形に) (五版P.529 L.11) P.301 L.12 「賑やかな」→「賑かな」 (五版P.435 上段 L.18) P.304 L.5 「支度」→「仕度」 (五版P.436 上段 L.15) P.312 L.9 「蒔きちらし」→「蒔ちらし」 (五版P.439 下段 L.3) P.319 L.4 「じゅうしょく」→「ちょうばみ」 (二つのサイコロを使った遊戯、双六か丁半のことであろう) P.323 L.12 「誉らるる」→「誉らるゝ」にすべきか? (五版P.444 上段 L.3は「るる」だが) P.327 L.7 「ふぶきの」→「ふゞきの」にすべきか? (五版P.445 上段 L.15は「ふぶ」だが) P.330 L.7 「つづく」→「つゞく」にすべきか? (五版P.446 上段 L.16は「つづ」だが) P.332 L.1 「ひじ」→「すね」 (五版P.530 L.5) P.347 脚注L.5 「る弓」→「弓」 (五版P.218 頭注L.2) P.352 L.5 および L.7 「甲の表紙には」「乙には」→ どこが甲・乙か分からなくなった (時系列で並び変えたので仕方ないが、「ここまで甲本」「ここから乙本」 「ここは丙本」などと書いてあると、原典と照合したいときに助かる) P.354 L.2 「頭註を」→頭註ではなく脚注になった (版を改めたため仕方ないが、ひとこと註を入れたほうがよい) P.357 L.12 「掛乞達の」→連句なので一字下げが必要。 P.367 L.14 「如月七日」→ゴシック体に。 P.379 脚注L.3 「池上四郎 境の屋号大輪亭」→西春近諏訪形では? (新編403 脚注L.10) P.396 脚注L.22 「煮かけ 手打ちうどんを煮込んだもの」→ これでは煮込みうどんになってしまう (正しくは、煮込んだ汁物をうどんにかけた料理、であろう) P.403 脚注L.10 「池上四郎 西春近諏訪形」→ 伊那市の境? (新編P.379 脚注L.3) P.412 L.11 「十二日」→ ゴシック体に P.414 脚注L.3 「彦児」→「彦兄」? (新編P.241 脚注L.2 なお五版P.461に註はない) P.426 L.1 「大久保とあるを→「大久保」とあるを (カギカッコが足りない。五版P.467 下段 L.10も同様の誤り) P.468 L.5 「ア、うれしやと」→「アゝうれしやと」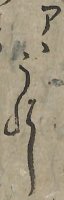 P.473 『まし水』(仮題)→ 『紅葉の摺もの』 (実物を見ると、あざやかな紅葉の挿絵が添えられており、井月自身、柳の家 宿願稿の中で『紅葉の摺もの』と呼んでいる。新編P.463 L.6)
P.473 『まし水』(仮題)→ 『紅葉の摺もの』 (実物を見ると、あざやかな紅葉の挿絵が添えられており、井月自身、柳の家 宿願稿の中で『紅葉の摺もの』と呼んでいる。新編P.463 L.6)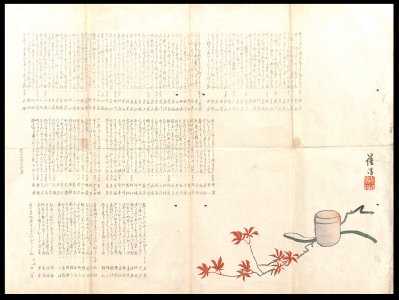 P.480 L.2「夜の□は」→ 不明字は、繋? 栞? 染?
P.480 L.2「夜の□は」→ 不明字は、繋? 栞? 染? P.497 L.2 「キンサハ」→「オンサハ」 P.503 二段目 L.10 「山村」→ 上伊那郡ではなく、下伊那郡(飯田市鼎)であろう。 P.503 四段目 L.6 「口沢」→「恩沢」 P.510 L.8 「権造」→「権蔵」 (五版P.296 L.3も間違っている) P.510 L.13 「候へし処」→「候へし所」 (五版P.296 L.9) P.515 L.6 の円)。頂戴仕度 →「。」は不要か? (五版P.301 L.14にも「。」があるが、文脈からして不要) P.520 L.14 「遺し」→「遣し」 (五版P.307 L.13) P.539 L.10 「一の瀬」→ 地元では「市の瀬」「市之瀬」「市ノ瀬」と表記している。 (「中条村の石造文化財」には市の瀬。「中条村の神さま仏さま」には市之瀬。 路線バスの表記は市ノ瀬。) P.568 L.11 「ぎく」→「ざれく」? -------------------------------------------------- 全集に未収録の連句 鴨の啼田もはさまりし隣かな 悦燕 時雨をさそふ風呂の拍木 井月 染むらを直さす絹の隙とりて 原逸 (『家づと集』より。なお井月編俳諧三部集P.164では「絹」ではなく「箔」となっている) -------------------------------------------------- 全集に未収録の発句 「美しくつよみ持ちけり糸柳 井月」 (俳人井月幕末維新風狂に死すP.249 南佐久郡北相木村の奉納額にある) 「籠礼仏参を観て 鬼面を脱して見れば笑顔哉 井月」 (一ノ瀬所蔵の奉燈句にある) 「料理場の客止礼や花七日」 (井上井月真筆集P.108) 「我宿の貯酒やほとゝぎす」 (井上井月真筆集P.108) 「小簾に半面美人杜宇」 (井上井月真筆集P.108) 「絶間なく客の入来る牡丹かな」 (井上井月真筆集P.108) -------------------------------------------------- 全集に未収録の類句 (井上井月真筆集・井月真蹟集・井月全集五版に載っていて、新編井月全集にないもの を挙げる。なお、表記が違っても読みが同じものは、類句と見なしていない。) P.35 L.13 「遅き日や」→「長き日や」 (井月真蹟集P.69) P.37 L.9 「開け放つ」→「明て置」 (井上井月真筆集P.13) P.37 L.11 「春風や」→「長き日や」 (井月真蹟集P.69) P.41 L.10 「霞かな」→「初旭かな」 (五版P.502 L.18) P.44 L.4 「瀬多の茶屋」→「瀬多の店」 (井上井月真筆集P.16/井月真蹟集P.15) P.49 L3 「時にとりての余り順」→「ときに取ての錺り順」 (井上井月真筆集P.115) P.59 L.11 「朝風呂好きな」→「朝風呂好の」 (井上井月真筆集P.2) P.64 L.2 「花の兄」→「梅の花」 (井上井月真筆集P.114) P.64 L.9 「香かな」→「匂ひかな」 (井上井月真筆集P.99/井月真蹟集P.175) P.67 L.6 「莚かな」→「宿りかな」 (井上井月真筆集P.24) P.69 L.4 「散る花や若い女の」→「花散や若い女の」 (井上井月真筆集P.113/井月真蹟集P.199) P.87 L.8 「余所になぐれて」→「余所へなぐれて」 (井月真蹟集P.211) P.96 L.11 「村雨の」→「村雨も」 (井上井月真筆集P.41 および P.112) P.97 L.6 「蚕玉祭の」→「蚕祭りの」 (一ノ瀬所蔵の真蹟による。蚕は「神虫」と書く) P.107 L.1 「見え透く鮎の」→「見えつゝ鮎の」 (井上井月真筆集P.37) P.117 L.9 「日覆となるや」→「日除に成や」 (井上井月真筆集P.32) P.124 L.2 「たのみがひなしあきの風」→「たのみ甲斐なき一葉かな」 (井上井月真筆集P.45/井月真蹟集P.181) P.125 L.14 「名月に」→「名月や」 (井月真蹟集P.15) P.150 L.5 「白菊の」→「白菊は」 (井上井月真筆集P.63) P.168 L.6 「頼まれて庵の留守や」→「たのまるゝ菴の留守居や」 (井上井月真筆集P.88) P.176 L.7 「不断来た」→「ふだん来る」 (井上井月真筆集P.80) P.178 L.14 「富士は今年の」→「富士も今年の」 (井月真蹟集P.31) P.181 L.6 「酒の香の」→「酒の香も」 (井上井月真筆集P.100) P.188 L.7 「誰見ても」→「誰がみても」 (井上井月真筆集P.102) -------------------------------------------------- その他 ・ページ番号が片側に連番で書かれているが、ふつうに両側に書いたほうが 参照しやすいと思う。
P.497 L.2 「キンサハ」→「オンサハ」 P.503 二段目 L.10 「山村」→ 上伊那郡ではなく、下伊那郡(飯田市鼎)であろう。 P.503 四段目 L.6 「口沢」→「恩沢」 P.510 L.8 「権造」→「権蔵」 (五版P.296 L.3も間違っている) P.510 L.13 「候へし処」→「候へし所」 (五版P.296 L.9) P.515 L.6 の円)。頂戴仕度 →「。」は不要か? (五版P.301 L.14にも「。」があるが、文脈からして不要) P.520 L.14 「遺し」→「遣し」 (五版P.307 L.13) P.539 L.10 「一の瀬」→ 地元では「市の瀬」「市之瀬」「市ノ瀬」と表記している。 (「中条村の石造文化財」には市の瀬。「中条村の神さま仏さま」には市之瀬。 路線バスの表記は市ノ瀬。) P.568 L.11 「ぎく」→「ざれく」? -------------------------------------------------- 全集に未収録の連句 鴨の啼田もはさまりし隣かな 悦燕 時雨をさそふ風呂の拍木 井月 染むらを直さす絹の隙とりて 原逸 (『家づと集』より。なお井月編俳諧三部集P.164では「絹」ではなく「箔」となっている) -------------------------------------------------- 全集に未収録の発句 「美しくつよみ持ちけり糸柳 井月」 (俳人井月幕末維新風狂に死すP.249 南佐久郡北相木村の奉納額にある) 「籠礼仏参を観て 鬼面を脱して見れば笑顔哉 井月」 (一ノ瀬所蔵の奉燈句にある) 「料理場の客止礼や花七日」 (井上井月真筆集P.108) 「我宿の貯酒やほとゝぎす」 (井上井月真筆集P.108) 「小簾に半面美人杜宇」 (井上井月真筆集P.108) 「絶間なく客の入来る牡丹かな」 (井上井月真筆集P.108) -------------------------------------------------- 全集に未収録の類句 (井上井月真筆集・井月真蹟集・井月全集五版に載っていて、新編井月全集にないもの を挙げる。なお、表記が違っても読みが同じものは、類句と見なしていない。) P.35 L.13 「遅き日や」→「長き日や」 (井月真蹟集P.69) P.37 L.9 「開け放つ」→「明て置」 (井上井月真筆集P.13) P.37 L.11 「春風や」→「長き日や」 (井月真蹟集P.69) P.41 L.10 「霞かな」→「初旭かな」 (五版P.502 L.18) P.44 L.4 「瀬多の茶屋」→「瀬多の店」 (井上井月真筆集P.16/井月真蹟集P.15) P.49 L3 「時にとりての余り順」→「ときに取ての錺り順」 (井上井月真筆集P.115) P.59 L.11 「朝風呂好きな」→「朝風呂好の」 (井上井月真筆集P.2) P.64 L.2 「花の兄」→「梅の花」 (井上井月真筆集P.114) P.64 L.9 「香かな」→「匂ひかな」 (井上井月真筆集P.99/井月真蹟集P.175) P.67 L.6 「莚かな」→「宿りかな」 (井上井月真筆集P.24) P.69 L.4 「散る花や若い女の」→「花散や若い女の」 (井上井月真筆集P.113/井月真蹟集P.199) P.87 L.8 「余所になぐれて」→「余所へなぐれて」 (井月真蹟集P.211) P.96 L.11 「村雨の」→「村雨も」 (井上井月真筆集P.41 および P.112) P.97 L.6 「蚕玉祭の」→「蚕祭りの」 (一ノ瀬所蔵の真蹟による。蚕は「神虫」と書く) P.107 L.1 「見え透く鮎の」→「見えつゝ鮎の」 (井上井月真筆集P.37) P.117 L.9 「日覆となるや」→「日除に成や」 (井上井月真筆集P.32) P.124 L.2 「たのみがひなしあきの風」→「たのみ甲斐なき一葉かな」 (井上井月真筆集P.45/井月真蹟集P.181) P.125 L.14 「名月に」→「名月や」 (井月真蹟集P.15) P.150 L.5 「白菊の」→「白菊は」 (井上井月真筆集P.63) P.168 L.6 「頼まれて庵の留守や」→「たのまるゝ菴の留守居や」 (井上井月真筆集P.88) P.176 L.7 「不断来た」→「ふだん来る」 (井上井月真筆集P.80) P.178 L.14 「富士は今年の」→「富士も今年の」 (井月真蹟集P.31) P.181 L.6 「酒の香の」→「酒の香も」 (井上井月真筆集P.100) P.188 L.7 「誰見ても」→「誰がみても」 (井上井月真筆集P.102) -------------------------------------------------- その他 ・ページ番号が片側に連番で書かれているが、ふつうに両側に書いたほうが 参照しやすいと思う。
トップページへ