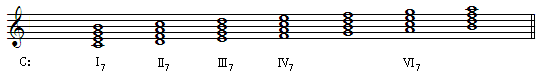
本書では、属七・導七・減七以外を「副七」と呼ぶことにします。
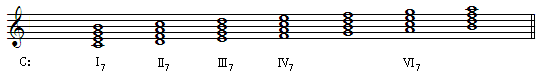
基本形、第一転回、第二転回、第三転回があり、数字のつけ方は属七などと一緒です。ここでは II を例にして示しましょう。
を例にして示しましょう。
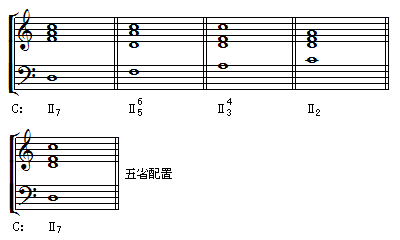
副七の中で、最も使用頻度の高いのは II 、次いで IV
、次いで IV で、ほかのものは時々見かける程度です。次の和声を読んでみてください。
で、ほかのものは時々見かける程度です。次の和声を読んでみてください。
副七には導音はありませんが、第7音は進行規制音です。ただし属七と違い、副七の第7音は、前の和音から「予備」すべきと言われています。
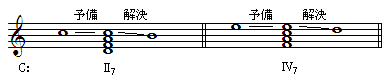
やむをえず正しい進行ができない場合も、決して跳躍はせず、保留した後に解決するのが良いのです。
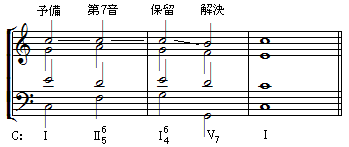
なお、副七の第7音は予備すべき音なので、ほかの声部に置き換えることができません。属七とは微妙に扱いが違うのです。
 V
V VI | II
VI | II VII
VII I
I [全] | II
[全] | II VII
VII I
I I | IV
I | IV V
V I [全]
I [全] V
V I | IV
I | IV II
II V [半] | I IV
V [半] | I IV V
V I | II
I | II V
V I [全]
I [全] | V [半] | I
| V [半] | I IV
IV V
V | I II
| I II | I
| I V
V | I [全]
| I [全]