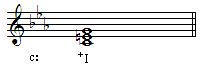
変質和音をどういう記号で示すか、人によってさまざまだと思いますが、本書では、先人たちが残した和声学書の中から、具合のよい記号を選んで使うことにします。
<ピカルディーの3>
短調の終止の I は、第3音を半音上げることがあります。これを「ピカルディーの3」と言い、おもに変終止で使われます。本書では + を付けて示すので、「プラスI度」と読めば良いでしょう。
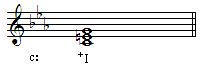
<ドリアの6>
短調の IV は、第3音を半音上げることがあります。この半音上がった音は、教会旋法の一種である「ドリア旋法」の第6度音にあたるので、「ドリアの6」と呼ばれます。
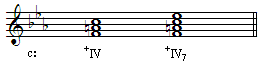
和音記号は「プラスIV度」「プラスIV度の七」と読めば良いでしょう。なお + の記号は、フランス和声では導音を示す記号として使われています。 IV
IV は、第3音が導音のようになっている属七の形、と見ても良いでしょう。
は、第3音が導音のようになっている属七の形、と見ても良いでしょう。
<ナポリの6>
短調の II は、根音が半音下がることがあります。これを「ナポリの6」と言います。本書では、N
は、根音が半音下がることがあります。これを「ナポリの6」と言います。本書では、N という記号を使います。
という記号を使います。
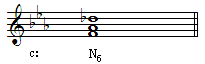
<増六諸和音>
短調の第6度音の上に、増6度音程を含む和音を使うことがあります。古くは「イタリーの6」「ドイツの6」「フランスの6」と呼ばれてきましたが、本書では、これらを「増六諸和音」と総称します。
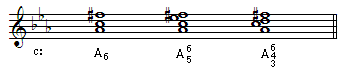
本書では Augment (ドイツ語で「増加」の意味) の頭文字をとって、A と書くことにします。それぞれの和音記号は「増六」「増五六」「増三四六」と読みます。
増六諸和音の機能はサブドミナント(S)です。根音が何か考える必要はなく、ただドミナント(D)へ進むものとおぼえれば良いでしょう。
次の和声を読んでみてください。
<増五の和音>
第5音を半音上げて使うことがあります。特に長調の I, IV, V に多いのですが、本書では ` を左上がりに付けて示すことにします。
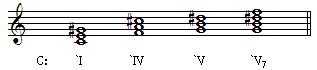
変質和音は、まだほかにも、いくらでも考えられますが、古典和声の範囲内では、以上を知っていれば充分だと思います。なお、変質音はいずれも進行規制音であり、半音上がった音はさらに上行し、半音下がった音はさらに下行するのを原則とします。
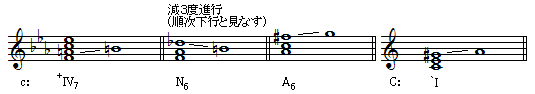
やむをえず正しい進行ができない場合も、決して跳躍はせず、とどまって半音進行するのが良いのです。
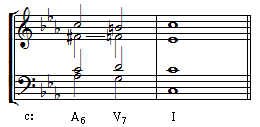
逆に、半音進行がほかの声部にまたがると「対斜」といって、避けるべきとされています。
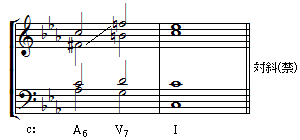
今後、借用和音や転調など、臨時記号が数多く出てきますが、対斜はやはり避けるべきとされています。(対斜が許される場合については、後の「禁則について」を参照してください。)
 IV
IV VII
VII I | IV
I | IV A
A V [半] | I
V [半] | I IV N
IV N V
V | I IV
| I IV
 I [変]
I [変] I
I N
N | I
| I V [半] | I
V [半] | I
 IV
IV VII I | A
VII I | A V
V I [全] | VI IV |
I [全] | VI IV |  I [変]
I [変] A
A | I
| I V | I
V | I  IV
IV V
V | VI [偽] | N
| VI [偽] | N I
I V
V | I [全] IV
| I [全] IV |
|  I [変]
I [変]