あ 甘酒(あまざけ)
あらばしり
おり酒(おりざけ)な 中取り(なかとり)中汲み(なかくみ)
生酒(なまざけ)
生貯蔵酒(なまちょぞうしゅ)
生詰酒(なまつめさけ)
濁り酒※(にごりざけ)
日本酒度(にほんしゅど)か 掛米(かけまい)
粕歩合(かすぶあい)
活性酒(かっせいしゅ)
活性清酒(かっせいせいしゅ)
寒造り(かんづくり)
生一本(きいっぽん)
貴醸酒(きじょうしゅ)
生もと仕込(きもとしこみ)
原酒(げんしゅ)
高酸味酒(こうさんみしゅ)
麹(こうじ)
麹蓋(こうじぶた)
高濃度酒(こうのうどしゅ)
酵母(こうぼ)
甑(こしき)
古酒(こしゅ)
は 発泡酒(はっぽうしゅ)
火入れ(ひいれ)
火落菌(ひおちきん)
老ね香(ひねか)
冷卸し(ひやおろし)
槽(ふね)さ 酒林(さかばやし)
酸度(さんど)
酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)
酒母(しゅぼ)
醸造アルコール(じょうぞうアルコール)
新酒(しんしゅ)
精米歩合(せいまいぶあい)
総米量(そうまいりょう)
増醸酒(ぞうじょうしゅ)
ま 醪(もろみ) た 樽酒(たるざけ)
杜氏(とうじ)
長期熟成酒(ちょうきじゅくせいしゅ)
斗瓶取り(とびんとり)
斗瓶囲い(とびんかこい)や 山廃仕込み(やまはいしこみ)
あ
甘酒(あまざけ)
もち米の粥に米麹を混ぜ、60度前後で一昼夜放置して造ったもの。別名として、「一夜酒」、「なめ酒」とも呼ばれる。
あらばしり
醪※(もろみ)を搾った時に最初に出てくる白濁した部分。味は若く荒々しい。
おり酒(おりざけ)
タンクの底に沈殿した麹※(こうじ)と酵母などを集め、白濁したままにしておいたもの。
か
掛米(かけまい)
仕込の際に、通常三度にわけて醪(もろみ)を増量するときに使用する蒸米のこと。
粕歩合(かすぶあい)
原料の白米に対する搾り終えた後の酒粕の割合。通常25〜30%が多いが、吟醸造りの場合、低温で米を溶かさないように発酵させるため、30〜40%を超えるものがある。
活性酒(かっせいしゅ)・活性清酒(かっせいせいしゅ)
濁り酒※(にごりざけ)で出荷の際に加熱、殺菌していないもの。酵母菌が生きており、多くは炭酸ガスを含んでいる。
寒造り(かんづくり)
11月頃〜3月頃までの寒い時期に行われる酒造りのこと。寒い季節は酒造りに好条件が揃っており、醸出される酒の品質も最良である。
生一本(きいっぽん)
単一の製造場のみで醸造した純米酒である場合表示できる。
貴醸酒(きじょうしゅ)
仕込の際に水ではなく、清酒を用いて長期熟成させた清酒。味わいは濃醇な甘口。
生もと仕込(きもとしこみ)
酒母※(しゅぼ)を造る際に、蒸し米、麹、水を半切りという桶に入れ、米を櫂棒で摺りつぶす「山卸し」という作業を行い、天然の乳酸菌を増殖させる昔ながらの手法。
原酒(げんしゅ)
搾り立ての日本酒を加水調整(アルコール分1%未満の加水調整を除く)しない清酒。アルコール度数が18 〜20 度程度の高めとなります。
高酸味酒(こうさんみしゅ)
一般の清酒は黄麹菌を使用するが、これは白麹菌などを使用して造った清酒で名の通 り酸味が強い。
日本酒には、この他仕込みにお酒を使ったもの、紅麹菌を使ったものなど、多品質のタイプがあります。
麹(こうじ)
カビの一種で、清酒には「黄麹菌」が使われ、米のデンプンを糖化させている。
麹蓋(こうじぶた)
麹造りの際使用される道具で、杉で出来た底の浅い長方形の箱。手間がかかるがその分丁寧な温度管理が出来る。主に吟醸造りの際に用いられる。
高濃度酒(こうのうどしゅ)
アルコール度数を24〜36 度と高くした清酒。
酵母(こうぼ)
麹によって生じた糖分をアルコールに変える働きをするもの。日本醸造協会が培養、頒布する協会酵母や自家酵母などがある。
甑(こしき)
原料米を蒸す大きな蒸籠。
古酒(こしゅ)
一般的には三年以上熟成させた清酒を指す。ただし、酒造現場では醸造年度(7月1日〜翌年6月30日)が変わるとそれ以前に造られた酒は全て古酒と呼ぶ。これらは、酒造年度(BY=ブリュワリー・イヤー )別に分けられ、10BY(平成10年製造)、13BY(平成13年製造)というように表示される。
さ
酒林(さかばやし)
杉の葉を束ねて球状にしたもの。軒先にかけて酒屋の看板としたもの。
酸度(さんど)
味の濃淡をみるために使われる数値。現在の清酒は平均1.3〜1.5で、これより少ないと淡麗、多いと濃醇とみられる。
酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)
酒造りに適した米。特徴として大粒で蛋白質、脂肪が少なく、心白が大きく、吸水率が良いといった事があげられる。条件として現在29府県に31品種が指定されている。代表的なものに「山田錦」「五百万石」「雄町」など。
酒母(しゅぼ)
酒類の成分であるエチルアルコールは酵母※(こうぼ)という微生物の働きによって生成されるが、その酵母を純粋に大量 培養した粥状のもの。
醸造アルコール(じょうぞうアルコール)
デンプン質物質や含糖質物から醸造されたアルコールをいう。
吟醸酒、本醸造酒に使用できる醸造アルコール量は、白米の重量の10%以下(白米1トンに対し100%アルコール116.4リットル)に制限されている。
新酒(しんしゅ)
その年(7月1日から翌年6月30日まで)に造られたお酒。熟成が進んでいないため特有の若い香り(新酒ばな)が残っているのが特徴。一般に12月〜2月に販売される。
精米歩合(せいまいぶあい)
白米の玄米に対する重量の割合。例えば精米歩合60%の場合、玄米の表層部を40%削り取る事をいう。
総米量(そうまいりょう)
1本の酒を仕込む際に白米の量。
増醸酒(ぞうじょうしゅ)
白米1トンにつき、2.400L(アルコール分30%に換算した数量)の調味アルコールを添加したお酒。これは第2次世界大戦後に酒造用米が不足したために造られ、現在でも造られている。収量が約三倍になることから三倍増醸酒、三増(さんぞう)とも呼ばれている。
た
樽酒(たるざけ)
木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒。樽の材料として、杉、なかでも吉野杉が最高とされている。
杜氏(とうじ)
酒造りの総責任者。蔵の管理、帳簿管理、醪の仕込と管理などを行う。
長期熟成酒(ちょうきじゅくせいしゅ)
3〜10年、あるいはそれ以上の期間を経て熟成した清酒。
斗瓶取り(とびんとり)・斗瓶囲い(とびんかこい)
袋吊りにて搾った最良の部分を一斗(18リットル)入りの瓶に入れたもの。その蔵にとって最高級の清酒。
な
中取り(なかとり)・中汲み(なかくみ)
醪※(もろみ)を搾る際、タンクを上から「あら・中・せめ」と3つに分け、その中の部分を搾った清酒のこと。
生酒(なまざけ)
搾り立ての日本酒を一切加熱処理していない清酒である場合表示できる。
生貯蔵酒(なまちょぞうしゅ)
搾り立ての日本酒を加熱処理せずに貯蔵し、出荷時に一度だけ加熱処理をしたものに表示できる。
生詰酒(なまつめさけ)
搾り立ての日本酒を加熱処理後貯蔵し、程良く熟した頃に出荷したもの。
濁り酒※(にごりざけ)
醪を目の粗い布で漉しただけの清酒で、白く濁っている。この中で出荷の際に加熱、殺菌していないものを活性酒ともいい、酵母や酵素が生きたままです。
日本酒度(にほんしゅど)
清酒の甘辛をみる数値。+の値が高いと辛口、−値が高いと甘口という事になる。しかし総体的なバランスで味わうと必ずしもそうでないため、あくまでも目安程度である。
は
発泡酒(はっぽうしゅ)
炭酸ガスを吹き込んだ清酒。一般的にアルコール分は低く8%程度。
火入れ(ひいれ)
濾過した新酒を60度程度で加熱殺菌すること。酒の中の酵素を殺し、熟成度、香味などの調節を計るために行われる。
●火落菌(ひおちきん)
火落菌という菌が清酒に繁殖すると白濁、酸の生成、特異臭といった現象が起こり、飲めなくなる変敗現象。古くは貯蔵中の6月〜9月にかけ起こっていたが、現在では技術の進歩により、ほとんどみられなくなっている。
老ね香(ひねか)
熟成が必要以上に進んだ場合、色が濃くなったり、味わいや香りに異変が起こったものを指す場合の表現。
冷卸し(ひやおろし)
かつては樽詰めの際に加熱処理をせず、生のまま詰められたのが由来。夏場の熟成を経て秋口に入り生詰めされる清酒のこと。
槽(ふね)
発酵を終えた醪(もろみ)※を袋に詰め、それを積み重ね上から圧力をかけ、清酒と粕に分離する道具。
ま
醪(もろみ)
清酒の製造工程で、酒母、蒸し米、麹、仕込水を混ぜたもの。
や
山廃仕込み(やまはいしこみ)
生もと※(きもと)の行程から「山卸し」を廃止したもの。
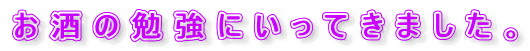 |
2004年5月末日、日本酒の造りがオフシーズンに入っているので、業界では各地で交流や情報交換などの勉強会が行われています。ママになった香織は久しぶりに、パパと二人で行ってきました。@日本閣 マチダヤ主催 |
 「飛露喜」蔵元 廣木健司さん。 「飛露喜」蔵元 廣木健司さん。 |
 ジョン・ゴントナーさん。アメリカ人の日本酒伝道師。英語で書いた日本酒の本3冊や、「日本人も知らない日本酒の話」の著者。雑誌等でも有名です。 |
 福島県会津坂下町「天明」蔵元 曙酒造 鈴木孝教さん、明美さんご夫妻。 |
 2004年7月14日に行われる第7回しずく会にゲスト出席してくれます。 |
 写真家 名智健二さん。 写真家 名智健二さん。 |
 静岡「磯自慢」蔵 社長 寺岡さん。 |
 福島県「國権」蔵 細井さん。「天明」明美さんの紹介で撮影させてもらいました。 福島県「國権」蔵 細井さん。「天明」明美さんの紹介で撮影させてもらいました。 |
|