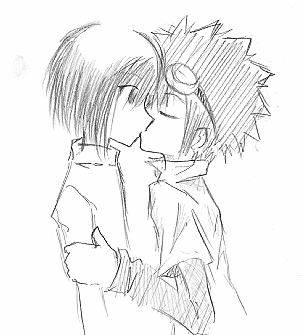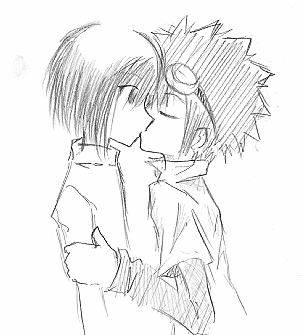「賢、好きだ。」
お台場小学校のパソコンルーム。たまたま、僕と大輔は早くそこに来ていた。
突然の告白だった。僕は大輔の思いに戸惑う。無論、嬉しかった。でも、後ろめたかった。すぐに返事をしたい。「僕も好きだ。」と・・・。
だけど・・・。
「ごめん、少し考えさせてくれないかな・・・。」
「お前は、俺のこと好きじゃないのか?」
「そんなことない。大輔のこと、好きだ。」
「じゃあ、何でだよ・・・。」
「それは・・・。」
返答に詰まる。僕には大輔に隠していることがあるのだ。
「好きだ・・・。お前が好きなんだよ。」
大輔は繰り返す。そして、僕の唇に自分の唇を押し当てる。
僕は、驚く。今まで、大輔が、こんな行為に出た事がなかったから・・・。
大輔の舌は僕の歯を割って侵入してくる。僕は、思わず舌を絡めてしまう。腰に力が入らない。
大輔の思いがその熱いキスで流れ込んでくる。
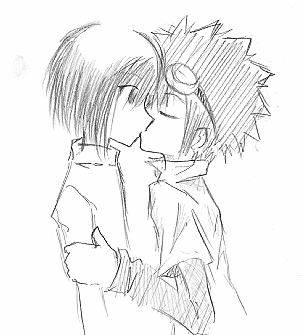 ここまで思ってもらえる事が嬉しくて・・・。
僕は、キスに溺れてしまってこれから言わなければならないことをなおざりにしてしまう。
少しだけ、少しだけなら・・・。
キスに溺れていたい。
その時だった。
「ごめん、お楽しみ中だったのかな。」
クスクスと笑いながら入ってくる。
「高、石・・・。」
僕は愕然とした。
「ごめんね。大輔君。一乗寺君。」
高石は、唇を微笑みの形にする。しかし、目は笑っていない。
僕は顔を強張らせた。
僕は数ヶ月前から高石と肉体関係を持っていた。そう、最初は何が何だか、分からないうちに犯され、今度は、このことを周囲に人間に言わないことと、引き換えに、僕は高石と肉体的な関係を絶ちきる事ができないでいた。自分でも情けない。しかし、僕は、知られたくなかった。僕が不純同性行為という穢れた行為をやっていることなど、誰が人に言えるだろう。特に大輔には・・・。大輔が知ったらきっと・・・。
「何だよ。タケル。」
大輔がムッとした顔をした。
「悪気はなかったんだ。許してよ。」
言って笑う。僕は、その後、自分がどうなるかは、容易に想像ができたが、高石が、大輔に僕と彼との肉体関係のことを告げるのではないかと恐怖し、焦った。
ここまで思ってもらえる事が嬉しくて・・・。
僕は、キスに溺れてしまってこれから言わなければならないことをなおざりにしてしまう。
少しだけ、少しだけなら・・・。
キスに溺れていたい。
その時だった。
「ごめん、お楽しみ中だったのかな。」
クスクスと笑いながら入ってくる。
「高、石・・・。」
僕は愕然とした。
「ごめんね。大輔君。一乗寺君。」
高石は、唇を微笑みの形にする。しかし、目は笑っていない。
僕は顔を強張らせた。
僕は数ヶ月前から高石と肉体関係を持っていた。そう、最初は何が何だか、分からないうちに犯され、今度は、このことを周囲に人間に言わないことと、引き換えに、僕は高石と肉体的な関係を絶ちきる事ができないでいた。自分でも情けない。しかし、僕は、知られたくなかった。僕が不純同性行為という穢れた行為をやっていることなど、誰が人に言えるだろう。特に大輔には・・・。大輔が知ったらきっと・・・。
「何だよ。タケル。」
大輔がムッとした顔をした。
「悪気はなかったんだ。許してよ。」
言って笑う。僕は、その後、自分がどうなるかは、容易に想像ができたが、高石が、大輔に僕と彼との肉体関係のことを告げるのではないかと恐怖し、焦った。
 「がんばってね。大輔君。」
そう言って、高石は、笑う。
(どりあえず、最悪の事態は避けられた。)
「ちょっと出てるから。ごゆっくり。」
高石はニッコリ笑って出ていった。
その笑顔は一見、親切。だが、その裏に見え隠れする不穏なものは僕しか知らない。
改めて、僕達は向き合う。
「悪い。急かしちまって。」
「ううん。大輔の気持ち嬉しい。」
「俺、待つから。いつまででも待つから。」
大輔のひたむきな思い。それは嬉しかった。
しかし、今の僕にはその思いに応える自信もないし、その資格もない事が歯がゆい。
「ごめんね。」
その後、僕達は、デジタルワールドでいつも通り、作業をした。
作業終了後。
メールが入る。
”今日、家に行くから・・・。逃げないでよね。”
僕は高石の方を見た。メールを打った本人は、何食わぬ顔で仲間達と笑顔で会話を交わしている。僕の視線などお構いなしという風に。
それから、僕は、仲間達に別れを告げ、家に帰る。いっそのこと、塾にでも逃げ込んでやろうとも思ったが、そんな抵抗など、彼にとってはほんの些細なものすぎないことは十分思い知らされてきた。逃げれば、逃げるほど、苦しまなければならないのは、目に見えている。
家に帰る。幸いと言っていいのか、母は生憎、パートによる不在。
僕は、誰も居ない家に上がり込む。そして、自分の部屋で待っていた。恐怖の呼び鈴が鳴るのを・・・。
今日、僕は高石に見られてしまった。高石は、僕と大輔を見て、何を考えていただろう。正直疑問だらけだった。そして、あの笑顔が不気味でたまらなかった。高石に今日のことを追求されるのだろうか。高石は怒っているのだろうか。僕は罰せられるのだろうか・・・。どっちにしても、あんな所を見られた以上、ろくなことにならないのは分かりきっている。
ピンポーン。
僕は溜め息をついて玄関に、向かい戸を開ける。
「よく、逃げなかったね。」
「僕は逃げない。」
「そうだね。逃げたら苦しいのは君自身だからね。」
そう言って、高石はクスリと笑った。
「今日はお母さん、いないんだ。」
僕は頷く。
僕は高石を自分の部屋に入れる。
「お茶、持ってくる。」
部屋を出ようとする僕の手を高石が掴んだ。
「何するんだ。」
「分かってるでしょ。僕がお茶を飲みに来たんじゃないってこと。」
「あ・・・。」
僕は、その場に座り込んだ。
「聞き分けがいいじゃない。」
「君が誘ったの?」
「な、にを?」
「とぼけないでよ。」
「君は大輔君を誘ったの?」
僕は首を振った。
「嘘。」
「だから、あれは・・・。」
「あれは、何?」
高石は、獲物を追いつめるように、じわじわと僕に質問を浴びせる。
「どっちでもいいけど。」
「でも、君が大輔君の欲望を掻き立てたのは容易に想像できるけどね。」
「そんなこと、ない。」
「だって、一乗寺君、触わって下さい、犯して下さいって顔、してるもの。」
「やめろ・・・。」
僕は静かに言った。
「ほら、その顔。」
「違う・・・。」
「何が違うの?」
「違う・・・。」
「で、君は、大輔君のキスに嬉しそうに、応えてたんだね。」
「ほんと、いやらしいね。僕とあれだけのことしておいて、大輔君を誘惑して騙そうとでも思った訳?」
「違う。」
違う・・・。僕は大輔が好きだ。だから・・・。
でも、大輔を騙した事実には変わりがない。その上、大輔を求める欲望も一人前で、キスに溺れてしまっていた。
自己嫌悪・・・。
「最低だね。一乗寺君。」
高石は笑った。
言いながら、僕の服を剥ぎ取っていく。
「やっ・・・。」
そして、僕の顎を掴むと僕の唇に自分の唇を重ねる。僕が逃げようとすると、顎を掴む手に力が入る。
「大輔君とは喜んでやってたくせに。」
そして唇を押し当てる。
「がんばってね。大輔君。」
そう言って、高石は、笑う。
(どりあえず、最悪の事態は避けられた。)
「ちょっと出てるから。ごゆっくり。」
高石はニッコリ笑って出ていった。
その笑顔は一見、親切。だが、その裏に見え隠れする不穏なものは僕しか知らない。
改めて、僕達は向き合う。
「悪い。急かしちまって。」
「ううん。大輔の気持ち嬉しい。」
「俺、待つから。いつまででも待つから。」
大輔のひたむきな思い。それは嬉しかった。
しかし、今の僕にはその思いに応える自信もないし、その資格もない事が歯がゆい。
「ごめんね。」
その後、僕達は、デジタルワールドでいつも通り、作業をした。
作業終了後。
メールが入る。
”今日、家に行くから・・・。逃げないでよね。”
僕は高石の方を見た。メールを打った本人は、何食わぬ顔で仲間達と笑顔で会話を交わしている。僕の視線などお構いなしという風に。
それから、僕は、仲間達に別れを告げ、家に帰る。いっそのこと、塾にでも逃げ込んでやろうとも思ったが、そんな抵抗など、彼にとってはほんの些細なものすぎないことは十分思い知らされてきた。逃げれば、逃げるほど、苦しまなければならないのは、目に見えている。
家に帰る。幸いと言っていいのか、母は生憎、パートによる不在。
僕は、誰も居ない家に上がり込む。そして、自分の部屋で待っていた。恐怖の呼び鈴が鳴るのを・・・。
今日、僕は高石に見られてしまった。高石は、僕と大輔を見て、何を考えていただろう。正直疑問だらけだった。そして、あの笑顔が不気味でたまらなかった。高石に今日のことを追求されるのだろうか。高石は怒っているのだろうか。僕は罰せられるのだろうか・・・。どっちにしても、あんな所を見られた以上、ろくなことにならないのは分かりきっている。
ピンポーン。
僕は溜め息をついて玄関に、向かい戸を開ける。
「よく、逃げなかったね。」
「僕は逃げない。」
「そうだね。逃げたら苦しいのは君自身だからね。」
そう言って、高石はクスリと笑った。
「今日はお母さん、いないんだ。」
僕は頷く。
僕は高石を自分の部屋に入れる。
「お茶、持ってくる。」
部屋を出ようとする僕の手を高石が掴んだ。
「何するんだ。」
「分かってるでしょ。僕がお茶を飲みに来たんじゃないってこと。」
「あ・・・。」
僕は、その場に座り込んだ。
「聞き分けがいいじゃない。」
「君が誘ったの?」
「な、にを?」
「とぼけないでよ。」
「君は大輔君を誘ったの?」
僕は首を振った。
「嘘。」
「だから、あれは・・・。」
「あれは、何?」
高石は、獲物を追いつめるように、じわじわと僕に質問を浴びせる。
「どっちでもいいけど。」
「でも、君が大輔君の欲望を掻き立てたのは容易に想像できるけどね。」
「そんなこと、ない。」
「だって、一乗寺君、触わって下さい、犯して下さいって顔、してるもの。」
「やめろ・・・。」
僕は静かに言った。
「ほら、その顔。」
「違う・・・。」
「何が違うの?」
「違う・・・。」
「で、君は、大輔君のキスに嬉しそうに、応えてたんだね。」
「ほんと、いやらしいね。僕とあれだけのことしておいて、大輔君を誘惑して騙そうとでも思った訳?」
「違う。」
違う・・・。僕は大輔が好きだ。だから・・・。
でも、大輔を騙した事実には変わりがない。その上、大輔を求める欲望も一人前で、キスに溺れてしまっていた。
自己嫌悪・・・。
「最低だね。一乗寺君。」
高石は笑った。
言いながら、僕の服を剥ぎ取っていく。
「やっ・・・。」
そして、僕の顎を掴むと僕の唇に自分の唇を重ねる。僕が逃げようとすると、顎を掴む手に力が入る。
「大輔君とは喜んでやってたくせに。」
そして唇を押し当てる。
 「ふあぁぁ・・・。」
高石の舌が、僕の口内に割り込んで、口内を弄んだ。
「あはぁふあぁん。」
すでに腰に力が入らなくなる。
「こうやって大輔君にもサービスしてたの。」
「ちがぁ・・・。」
「やりたいくせに。」
「誰でもいいんでしょ。」
「違う・・・。」
高石は露になった僕の上半身に舌を這わせる。
「ふあぁぁ・・・。」
高石の舌が、僕の口内に割り込んで、口内を弄んだ。
「あはぁふあぁん。」
すでに腰に力が入らなくなる。
「こうやって大輔君にもサービスしてたの。」
「ちがぁ・・・。」
「やりたいくせに。」
「誰でもいいんでしょ。」
「違う・・・。」
高石は露になった僕の上半身に舌を這わせる。
 「やぁ・・・。」
思わず、僕は短い嬌声を上げる。
「ほら、もう、感じて・・・。」
突起の部分を軽い甘噛み・・・。
「やぁん・・・。」
自分の意思とは関係のない声。
「この声で大輔君を誘惑するのかな。」
「あはぁん・・・。」
「大輔、して下さい、僕を犯して下さいって。それは効果絶大だね。」
高石がクスクス笑った。
「大輔は、そんなこと・・・。」
「じゃあ、あれは何だったのかな。」
高石は指で刺激を与えつつ、言葉で僕を追いつめていく。
そして、僕の太股に手を這わせ、奥まで、指を忍ばせる。
「あっ・・・。」
「ここ、もう、ぐしょぐしょだよ。今日は二人目だものね。淫乱賢君。」
「やだ・・・。」
「嫌なの?良いくせに。」
「やめて・・・。」
「やめてって言って僕がやめたことあったっけ?」
僕は口を噤む。
「そうそう、賢君は良い子だね。」
そう言って、僕の中を指で犯す。
「やぁぁぁん・・・。」
痛い・・・。異物感が全身に広がっていく。
「いたぁぁぁ・・・。」
僕は叫んだ。しかし、高石は、その指を中で動かす。
くちゅくちゅと粘着質な音がそこから響く。
「やだぁぁぁぁん。」
「やぁぁぁん・・・。」
その内、痛みが麻痺してきて、知らず知らずのうちに身体が犯される事に慣れてくるのだ。
そして・・・。
「あはぁぁぁん・・・。」
「ふあぁぁぁん・・・。」
知らぬ間に、僕はいやらしいとしか言えない声を上げていた。
「ふあぁぁん。」
「鳴けるじゃない。こうやって誘惑しないの?大輔君をさ。」
「ちがあぁぁあん。」
「違うんだ。」
高石はクスクス笑いながら僕の中で動いた。
「あはぁぁん・・・。」
「やだぁぁあ・・・。」
「大輔君も可哀相だね。こんな淫乱を好きになっただなんて。」
高石は大輔の名前を口にしては、戸惑う僕を煽った。
「君は穢れてるんだよ。大輔君と釣り合わないじゃない。」
僕はハッとした。
そうだ・・・。僕は穢れている。どんなに大輔に優しくされても、「好きだ」と言われても僕は大輔に応えることはできない・・・。
絶望。
「今気付いたの?良かったね。気付いて。危うく大輔君を傷つけてしまうところだった。」
気付いて、高石はこともなげに言い放った。そして、指を動かしたまま。
「やぁぁぁん・・・。」
「あはぁぁん・・・。」
「ほんとに、僕にこんな声を上げているなんて、大輔君が知ったらどう思うだろうね。淫乱賢君。」
「おねがい、もう・・・。」
涙が止まらなかった。そうだ・・・。僕は一生大輔にこのことを隠していかなければならない。ぬくぬくと大輔に甘えることなどできる筈がないのだ。
「大輔君を見れない身体にしてあげるよ。」
そう言って、高石は僕の中に入ってきた。
全身を貫かれるような痛みに襲われた。
「やぁぁぁぁ。」
僕は叫んだ。
「いたぁあぁぁ。」
高石は僕の中で目茶苦茶に動いた。
「いやぁあぁぁん。」
「やぁぁぁん。」
しかし、いつからだろう。僕は、挿入されることに慣れた身体になっていたらしく、無意識に腰を動かし、嬌声を上げて、高石のそれを求めていた。
「あはぁぁぁん。」
「ふあぁあぁん。」
淫らな行為に溺れていく。僕の身体がいやらしくなる。
僕であって、僕でないような、でもそれは僕自身なのだ。
「クク、ホラやっぱり淫乱賢君だ。」
僕は高石に犯されながら、なくなる意識の中で、大輔と淫らな行為に及んでいる妄想をしていた。
ああ、僕はこんなことしか考えられなくなっていたのか。
本当に淫乱だ。高石の言う通りだ。僕は淫乱だ・・・。
(折角、告白してもらったのにな・・・。)
僕は高石に囚われている。高石の愛撫に、高石の身体に囚われてしまっている。
これは弱い自分が招いた、あまりにも惨めすぎる結果だった。
果てる寸前、高石が僕の耳元で囁いた。
「君は逃げられない。どこへも。」
その瞬間、大輔の笑顔が走馬灯のようによぎる。
(ごめん。大輔。君の気持ちには応える事ができそうもない。)
「やぁ・・・。」
思わず、僕は短い嬌声を上げる。
「ほら、もう、感じて・・・。」
突起の部分を軽い甘噛み・・・。
「やぁん・・・。」
自分の意思とは関係のない声。
「この声で大輔君を誘惑するのかな。」
「あはぁん・・・。」
「大輔、して下さい、僕を犯して下さいって。それは効果絶大だね。」
高石がクスクス笑った。
「大輔は、そんなこと・・・。」
「じゃあ、あれは何だったのかな。」
高石は指で刺激を与えつつ、言葉で僕を追いつめていく。
そして、僕の太股に手を這わせ、奥まで、指を忍ばせる。
「あっ・・・。」
「ここ、もう、ぐしょぐしょだよ。今日は二人目だものね。淫乱賢君。」
「やだ・・・。」
「嫌なの?良いくせに。」
「やめて・・・。」
「やめてって言って僕がやめたことあったっけ?」
僕は口を噤む。
「そうそう、賢君は良い子だね。」
そう言って、僕の中を指で犯す。
「やぁぁぁん・・・。」
痛い・・・。異物感が全身に広がっていく。
「いたぁぁぁ・・・。」
僕は叫んだ。しかし、高石は、その指を中で動かす。
くちゅくちゅと粘着質な音がそこから響く。
「やだぁぁぁぁん。」
「やぁぁぁん・・・。」
その内、痛みが麻痺してきて、知らず知らずのうちに身体が犯される事に慣れてくるのだ。
そして・・・。
「あはぁぁぁん・・・。」
「ふあぁぁぁん・・・。」
知らぬ間に、僕はいやらしいとしか言えない声を上げていた。
「ふあぁぁん。」
「鳴けるじゃない。こうやって誘惑しないの?大輔君をさ。」
「ちがあぁぁあん。」
「違うんだ。」
高石はクスクス笑いながら僕の中で動いた。
「あはぁぁん・・・。」
「やだぁぁあ・・・。」
「大輔君も可哀相だね。こんな淫乱を好きになっただなんて。」
高石は大輔の名前を口にしては、戸惑う僕を煽った。
「君は穢れてるんだよ。大輔君と釣り合わないじゃない。」
僕はハッとした。
そうだ・・・。僕は穢れている。どんなに大輔に優しくされても、「好きだ」と言われても僕は大輔に応えることはできない・・・。
絶望。
「今気付いたの?良かったね。気付いて。危うく大輔君を傷つけてしまうところだった。」
気付いて、高石はこともなげに言い放った。そして、指を動かしたまま。
「やぁぁぁん・・・。」
「あはぁぁん・・・。」
「ほんとに、僕にこんな声を上げているなんて、大輔君が知ったらどう思うだろうね。淫乱賢君。」
「おねがい、もう・・・。」
涙が止まらなかった。そうだ・・・。僕は一生大輔にこのことを隠していかなければならない。ぬくぬくと大輔に甘えることなどできる筈がないのだ。
「大輔君を見れない身体にしてあげるよ。」
そう言って、高石は僕の中に入ってきた。
全身を貫かれるような痛みに襲われた。
「やぁぁぁぁ。」
僕は叫んだ。
「いたぁあぁぁ。」
高石は僕の中で目茶苦茶に動いた。
「いやぁあぁぁん。」
「やぁぁぁん。」
しかし、いつからだろう。僕は、挿入されることに慣れた身体になっていたらしく、無意識に腰を動かし、嬌声を上げて、高石のそれを求めていた。
「あはぁぁぁん。」
「ふあぁあぁん。」
淫らな行為に溺れていく。僕の身体がいやらしくなる。
僕であって、僕でないような、でもそれは僕自身なのだ。
「クク、ホラやっぱり淫乱賢君だ。」
僕は高石に犯されながら、なくなる意識の中で、大輔と淫らな行為に及んでいる妄想をしていた。
ああ、僕はこんなことしか考えられなくなっていたのか。
本当に淫乱だ。高石の言う通りだ。僕は淫乱だ・・・。
(折角、告白してもらったのにな・・・。)
僕は高石に囚われている。高石の愛撫に、高石の身体に囚われてしまっている。
これは弱い自分が招いた、あまりにも惨めすぎる結果だった。
果てる寸前、高石が僕の耳元で囁いた。
「君は逃げられない。どこへも。」
その瞬間、大輔の笑顔が走馬灯のようによぎる。
(ごめん。大輔。君の気持ちには応える事ができそうもない。)