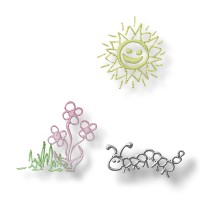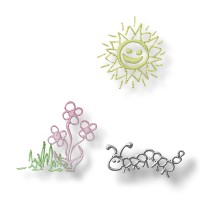「ひなたぼっこと子犬」
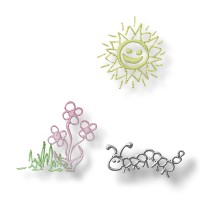 「翔一君、ここで、ボーっとしてると気持ちいいね。ほんと。」
真魚は菜園の手入れをしている翔一を眺めながら言った。
「俺が言ったとおりだろ。真魚ちゃんもさ、春休みだからって、いつまでも寝てないで、たまには、早起きしてさ、菜園の野菜に挨拶してみてよ。」
3月下旬の平日の10時を回った頃だった。真魚と太一は、春休みで、太一は、いつも、この時間帯は、友人と空き地に遊びに出かけていた。義彦は、春休みといえど、卒論研究の打ち合わせで大学に顔を出さざるを得なかった。
美杉家は、翔一と真魚の2人だけである。
翔一は、いつも、美杉家で一番に起きて、家事をするのだが、真魚はというと、春休みということもあり、義彦もいないせいか、ついつい、昼まで眠ることが多かった。
今日は、翔一がそんな真魚を起こし、ひなたぽっこをしようと誘ったのである。
「だって、春休みだとさ、ついつい、朝寝坊しちゃうんだよね。ほらっ、寝る子は育つって言うじゃない。」
「真魚ちゃんのは、寝過ぎっていうんだよ。」
「そっ、そうかな・・・。」
「そうなの。たまには、早く起きて、午前中に気持ちいい空気吸うのが俺はいいと思うよ。真魚ちゃん、寝るのも早いんだしさ。」
真魚は、最近の高校生にしては、寝る時間は早い方なのである。それは春休みとて変わりはしなかった。10時には布団に入り、11時頃には、就寝しているのである。
「そっ、そうだね・・・。」
先程から翔一のペースにはめられているようで、真魚は思わず苦笑した。それでも、そんな自分が真魚は思わず微笑ましいとすら思えてくるのである。
そんな中・・・。
「クーン、クーン・・・。」
犬の鳴き声が、翔一と真魚の耳に入った。
翔一と真魚は顔を見合わせて、鳴き声のする方向に目をやった。みると、茶色の雑種と思われる子犬が美杉家の門から入り、鳴いているのである。まだ、生後数ヶ月といったところであろうか。首輪をしているところを見ると飼い主がいるのだろう。
翔一は、子犬を抱き上げた。
「どうよ〜。真魚ちゃん、可愛いじゃない。」
翔一は嬉しそうに笑った。
「ほんと。私も抱かせて。」
翔一は、真魚に子犬を手渡した。真魚は、服に僅かに爪を立て、真魚にしがみつく、子犬を愛しいそうに眺めた。
「この子、大人しいね。それに人なつっこい。それとも、私のことが好きだったりして。」
「え〜、真魚ちゃんより、俺の方になついてると思うよ。」
翔一のその言葉に、真魚はムッとした。
「何で、そう思うわけ?私に抱かれて気持ち良さそうじゃない。私になついてるのよ。」
「そうだっ、ちょっと待ってて。」
翔一は、真魚の抗議をサラリと受け流し、台所へ向かった。
少しして、翔一が、手に、ミルクを入れた紙皿を持って戻ってきた。
「ほら、ミルクやろーなぁ。」
翔一が縁側にミルクを置くと子犬は、真魚の腕からスルリと抜け、ミルクを飲み始めた。
「あー、翔一君、物で吊るなんてズルイよっ。」
真魚が翔一に抗議をはじめた。
「だって、お腹空いてると思ってさ。」
そう言って翔一はエヘヘと笑った。
「子犬ちゃーん。真魚お母さんだよ〜。」
「じゃあさ、俺がお父さんっ。」
翔一が言った。
「ほら、お父さんがミルクをあげたんだよ〜。」
翔一も負けじと言った。
その時、真魚は、思わず、ドキリとして。
(私がお母さんで、翔一君がお父さん・・・。これって・・・。)
色々な想像が真魚の頭を巡り、真魚が顔を思わず熱くなった。
”翔一君と私が・・・。”
”結婚・・・。”
「真魚ちゃん、真魚ちゃん・・・。」
気が付くと、翔一が自分の名前を呼んでいた。
「あっ・・・。」
「翔一君・・・。」
「さっきから、真魚ちゃん、ボーッとしてどうしたの?」
真魚は、少しの間、自分の思考の世界に閉じこもっていたらしい。
「えっと・・・。」
「そのっ・・・。」
(私、何考えてたんだろ・・・。)
先程考えていたことを思いし返真魚は動揺を隠そうと必死だった。真魚は、再び顔が熱くなる。
真魚は動揺を隠そうと必死だった。
翔一は不思議そうな顔で真魚を眺めた。
「あの〜。」
その時だった。
美杉家の門を人の良さそうな中年の女性が顔を覗かせていた。
「すみません。その犬うちの犬なんです。」
「あ・・・。」
2人は同時に声を出した。
ついさっき、お父さんと、お母さんなどと名乗った矢先のことであったので。
「申し訳ありません。お宅にご迷惑かけてしまったようで・・・。」
「そっ、そんなことないですっ。ねっ、翔一君。」
「あっ、はい。とっても楽しかったです。」
翔一はニッコリ笑った。
「あの、また、こいつと遊びに行っていいですか?」
翔一が言うと・・・。
「はい、いつでもいらしてください。この子もきっと喜びます。」
そう言って女性は微笑んだ。
こうして、子犬は、飼い主に手渡され、帰宅していった。
「何か、ちょっと、寂しくなったね。」
「そう?」
真魚が寂しそうな顔をしている割には、翔一は何てことない顔をしていた。
「翔一君は寂しくないの?あの子犬のこと可愛がってたじゃない。」
「だって、あいつ、近所だろ。また遊びにいけばいいじゃない。あの人も来ていいって言ってくれたわけだし。それに、俺達、お父さんと、お母さんだしねっ。」
翔一の言葉に真魚は、また熱くなった。そして、その言葉がくすぐったくもあり、嬉しくもあった。
「そうだねっ。」
真魚はその時、心からの笑みを見せた。
そして思った。
(あのわんちゃんには感謝かな。)
こうして、春の喉かな一時は過ぎていった。
「翔一君、ここで、ボーっとしてると気持ちいいね。ほんと。」
真魚は菜園の手入れをしている翔一を眺めながら言った。
「俺が言ったとおりだろ。真魚ちゃんもさ、春休みだからって、いつまでも寝てないで、たまには、早起きしてさ、菜園の野菜に挨拶してみてよ。」
3月下旬の平日の10時を回った頃だった。真魚と太一は、春休みで、太一は、いつも、この時間帯は、友人と空き地に遊びに出かけていた。義彦は、春休みといえど、卒論研究の打ち合わせで大学に顔を出さざるを得なかった。
美杉家は、翔一と真魚の2人だけである。
翔一は、いつも、美杉家で一番に起きて、家事をするのだが、真魚はというと、春休みということもあり、義彦もいないせいか、ついつい、昼まで眠ることが多かった。
今日は、翔一がそんな真魚を起こし、ひなたぽっこをしようと誘ったのである。
「だって、春休みだとさ、ついつい、朝寝坊しちゃうんだよね。ほらっ、寝る子は育つって言うじゃない。」
「真魚ちゃんのは、寝過ぎっていうんだよ。」
「そっ、そうかな・・・。」
「そうなの。たまには、早く起きて、午前中に気持ちいい空気吸うのが俺はいいと思うよ。真魚ちゃん、寝るのも早いんだしさ。」
真魚は、最近の高校生にしては、寝る時間は早い方なのである。それは春休みとて変わりはしなかった。10時には布団に入り、11時頃には、就寝しているのである。
「そっ、そうだね・・・。」
先程から翔一のペースにはめられているようで、真魚は思わず苦笑した。それでも、そんな自分が真魚は思わず微笑ましいとすら思えてくるのである。
そんな中・・・。
「クーン、クーン・・・。」
犬の鳴き声が、翔一と真魚の耳に入った。
翔一と真魚は顔を見合わせて、鳴き声のする方向に目をやった。みると、茶色の雑種と思われる子犬が美杉家の門から入り、鳴いているのである。まだ、生後数ヶ月といったところであろうか。首輪をしているところを見ると飼い主がいるのだろう。
翔一は、子犬を抱き上げた。
「どうよ〜。真魚ちゃん、可愛いじゃない。」
翔一は嬉しそうに笑った。
「ほんと。私も抱かせて。」
翔一は、真魚に子犬を手渡した。真魚は、服に僅かに爪を立て、真魚にしがみつく、子犬を愛しいそうに眺めた。
「この子、大人しいね。それに人なつっこい。それとも、私のことが好きだったりして。」
「え〜、真魚ちゃんより、俺の方になついてると思うよ。」
翔一のその言葉に、真魚はムッとした。
「何で、そう思うわけ?私に抱かれて気持ち良さそうじゃない。私になついてるのよ。」
「そうだっ、ちょっと待ってて。」
翔一は、真魚の抗議をサラリと受け流し、台所へ向かった。
少しして、翔一が、手に、ミルクを入れた紙皿を持って戻ってきた。
「ほら、ミルクやろーなぁ。」
翔一が縁側にミルクを置くと子犬は、真魚の腕からスルリと抜け、ミルクを飲み始めた。
「あー、翔一君、物で吊るなんてズルイよっ。」
真魚が翔一に抗議をはじめた。
「だって、お腹空いてると思ってさ。」
そう言って翔一はエヘヘと笑った。
「子犬ちゃーん。真魚お母さんだよ〜。」
「じゃあさ、俺がお父さんっ。」
翔一が言った。
「ほら、お父さんがミルクをあげたんだよ〜。」
翔一も負けじと言った。
その時、真魚は、思わず、ドキリとして。
(私がお母さんで、翔一君がお父さん・・・。これって・・・。)
色々な想像が真魚の頭を巡り、真魚が顔を思わず熱くなった。
”翔一君と私が・・・。”
”結婚・・・。”
「真魚ちゃん、真魚ちゃん・・・。」
気が付くと、翔一が自分の名前を呼んでいた。
「あっ・・・。」
「翔一君・・・。」
「さっきから、真魚ちゃん、ボーッとしてどうしたの?」
真魚は、少しの間、自分の思考の世界に閉じこもっていたらしい。
「えっと・・・。」
「そのっ・・・。」
(私、何考えてたんだろ・・・。)
先程考えていたことを思いし返真魚は動揺を隠そうと必死だった。真魚は、再び顔が熱くなる。
真魚は動揺を隠そうと必死だった。
翔一は不思議そうな顔で真魚を眺めた。
「あの〜。」
その時だった。
美杉家の門を人の良さそうな中年の女性が顔を覗かせていた。
「すみません。その犬うちの犬なんです。」
「あ・・・。」
2人は同時に声を出した。
ついさっき、お父さんと、お母さんなどと名乗った矢先のことであったので。
「申し訳ありません。お宅にご迷惑かけてしまったようで・・・。」
「そっ、そんなことないですっ。ねっ、翔一君。」
「あっ、はい。とっても楽しかったです。」
翔一はニッコリ笑った。
「あの、また、こいつと遊びに行っていいですか?」
翔一が言うと・・・。
「はい、いつでもいらしてください。この子もきっと喜びます。」
そう言って女性は微笑んだ。
こうして、子犬は、飼い主に手渡され、帰宅していった。
「何か、ちょっと、寂しくなったね。」
「そう?」
真魚が寂しそうな顔をしている割には、翔一は何てことない顔をしていた。
「翔一君は寂しくないの?あの子犬のこと可愛がってたじゃない。」
「だって、あいつ、近所だろ。また遊びにいけばいいじゃない。あの人も来ていいって言ってくれたわけだし。それに、俺達、お父さんと、お母さんだしねっ。」
翔一の言葉に真魚は、また熱くなった。そして、その言葉がくすぐったくもあり、嬉しくもあった。
「そうだねっ。」
真魚はその時、心からの笑みを見せた。
そして思った。
(あのわんちゃんには感謝かな。)
こうして、春の喉かな一時は過ぎていった。