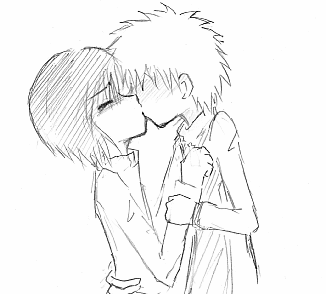
『終身刑』
憂鬱だった。体調も悪かったのだが、憂鬱の原因はそれだけではない。
今日はテストで昼までだった。昨日の徹夜のテスト勉強による寝不足が体調不良の原因だった。一刻も早く帰って寝ようかとも思ったが、明日もテストはある。家に帰ったら全くやらないまま眠りに落ちて朝になるのはまずいと思ったので2、3時間教室で勉強して帰ることにした。それに約束もあったので家に帰るとキリが悪いような気もしたからだ。そして、その約束こそが本当の憂鬱の原因だった。それは一方的な約束だったから・・・。
約束の時間まであと30分・・・。僕は教室の時計をぼんやり見ていた。
今日は、というか今日もといった方が正確であろう。僕は高石に呼び出されていた。目的は分かりきっている。僕はそのことを考えるだけで、屈辱感と羞恥心に襲われる。高石の思い通りに反応するこの身体も嫌いだったし、それを拒絶できない意志薄弱な自分の内面にも自己嫌悪を抱いていた。
今日は体調悪いから・・・。しかし、断ったらどうなるだろう・・・。高石のことだ、何をしでかすか分からない。一見、人当たりのよい優等生。天使のような笑顔で周囲に笑いかける高石。だが、彼の魔性の顔知っているのは僕だけなのだろうか。
どうするかはっきり決める事ができないまま、僕の足は高石の家の前で止まっていた。何で、来てしまったのだろう。僕は自分の足を呪った。その時、寝不足がピークに来たのか、僕の思考回路は停止していた。
「賢。」
誰かが 僕の名前を呼んでいる。誰?聞き覚えのある声だった。
「賢。」
二回目の声で僕の意識は現実に舞い戻った。
「高石・・・。」
目の前には金髪で青い瞳の(僕にとっては)悪魔が僕を見下ろしていた。
その姿に僕は愕然とした。
「君、玄関で倒れてたんだよ。」
「テスト勉強で寝不足ってわけ?昨日もしたからね。あの後ちゃんと勉強したんだね。エライ、エライ。」
高石は冷やかすように言って、手を叩いた。
彼は僕がテスト中で眠る事もできないのを承知で僕を呼び付ける。高石は、せっぱ詰まった人間を抱くのが良いらしい。
「今日は・・・。」
僕の言い訳高石は唇で塞ぎ、言わせないようにする。
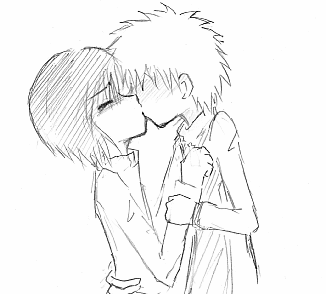
「ん、ん・・・。」
高石の舌が僕の口内を弄ぶ。僕は涙を溜めて、吸い付いた唇を離そうとして腰を引いた。しかし、高石は手でがっしりと顎を捕まえ逃れる事ができなかった。次第に僕は身体の力が抜けていった。
だ液の音とともに高石は唇を離した。
「賢は忠実だね。でも、ほんとは今日は断ろうとか考えてなかった?」
高石は口を歪ませた。
図星だった。僕はその問いに思わず顔を背けた。
「本当にポーカーフェイスが下手だね。賢は。」
「僕を裏切ろうって考えてたわけだ。」
高石の口調は穏やかだが、顔が笑ってない。青い瞳が僕を射抜く。
こういう時の高石は一番恐ろしい。
不意に高石は僕のシャツの中に手を伸ばし、滑り込ませた。
「やめて。」
拒絶の言葉を吐いてみる。声が震えているのは自分でも分かった。その一言が僕なりの精一杯の勇気だった。
しかし、そんな勇気を出したところでどうなるというわけではないのだ。
言いながら、高石は僕のうなじに口付ける。

「やぁ・・・。」
その声に僕は我に返る。最低だ・・・。こんなことするのは最低だ。
「やめろ・・・。」
僕は高石の手を振り払おうとした。その行為自身自分でも予想外だったので驚いた。驚きとともに後悔に念に襲われた。やばい。高石を怒らせる・・・。
「何、良い子ぶってるわけ?ほんとはしたいくせに。」
高石の口調に苛立ちが見え隠れしている。怒っている。明らかに・・・。
「そんなに、無理矢理にされたいんだ。それでも僕は構わないけどね。」
高石は笑った。しかし、目は冷たく僕を見据えている。逃げられない・・・。
「やめろ・・・。」
抵抗の真似事をする僕を難なくベッドに押さえつけた。バスケをやっているだけあって、細い身体の割には、その手にはかなりの握力があり、僕は簡単にねじ伏せられた。高石は僕の手首を捻った。
「痛い・・・。」
「君が素直じゃないからだよ。」
「ほんとはいやらしい声出したいくせに・・・。」
高石は笑いながら言った。
「そんなこと、思ってない・・・。」
高石は、僕のズボンのジッパーを下ろし、手を滑り込ませた。僕のを探り出し、それに手で触れた。
「やぁぁ・・・。」
誰にも触れられたことがないそれは、異常な反応を示し、僕はそこから液体を放出し、体中を震わせた。
「触わっただけで、こんなになるなんて、やらしい。」
高石はクスリと笑った。僕はその顔を見て、羞恥心に襲われ、顔が熱くなった。
高石は僕の放出した白く、粘着質な液体を指になぞり、それを僕に見せる。
「君のだよ。ホラ。」
僕はその液体から目を背けた。これが自分のものだなんて考えたくもなかった。自分が汚れているのを認めたくなかったから。それは意味のない最後の虚勢・・・。
「何で見ないの?」
高石は僕の髪を掴み自分の方を向かせた。

「っ・・・。」
目の前に晒される、卑猥の象徴みたいな液体・・・。
「何恥ずかしがってるわけ?今更。」
「だって、君が・・・。」
「触わられただけで、こんなの出している君がそんなこと言うわけ?」
「それは・・・。」
僕は言い返せないで口篭もった。
高石はクスクス笑っている。
「素直になった方がいいよ。これ以上僕を苛立たせないためにもね。」
言いながら、高石の青い瞳は凍てつくような冷たい光を放っていた。
高石は僕の中に指を二本入れる。痛みが全身を襲う。
「いたぁ・・・。」
「その内、喘ぐくらい気持ち良くなるから。」
言いながら高石は容赦なく内部を突いた。他人開かれ、抵抗すらできずに、侵入されるこの屈辱的なこの行為に、僕は、恐怖と情けなさで涙が止まらなかった。
「お願いだから、やめてぇ・・・。」
僕は懇願した。しかし、高石の指は僕に痛みを与えた。
「やぁぁん・・・。」
「あはぁぁぁ・・・。」
「やぁぁ・・・。」
その内、僕の声はだんだん、痛みじゃない、別の声に変わったような気がする。それは自分の意識の中の無意識が命令して出している声なのだろうか。だとしたら僕の深層心理は高石との行為を肯定している?
そんな筈ない、いや、そんなことがあってはならないのだ。
高石は指を抜いた。
僕のそこはぐしゃぐしゃになって自分身体の一部であってそうでないような感覚がした。
「お願い、やめて・・・。」
僕は涙声で言った。
「君の涙は誘ってるとしか思えないのだけど。」
逃げようとする僕の腰を掴んで高石は自分のを露出して入れる。指の時とは比べ物にならない激痛が走る。
「やぁぁぁぁ・・・。」
僕は無我夢中で喚いた。それでも高石は僕の中で身体をえぐるように動いた。引き裂かれんばかりの痛みだった。
「痛ぁぁぁ・・・。」
「君が逃げるからだよ。」
僕と高石の放った液体が交じり合い、太股に飛び散る。高石は僕が失神する度に激しい刺激を痛みを与えて、イカセナイようにした。
「今日は簡単イケルと思わない方がいいよ。」
それでも意識が遠ざかり、叩き起こされる感覚を何度も味わう。そのまま苦痛から逃れられないまま、僕達は行為を終える。
高石は僕の耳元で囁いた。
「少しでも逃げようと考えたどうなるか分かったでしょ。」
悔しさと情けなさで涙が止まらなかった。僕は一生高石という檻に閉じ込められたままなのだろうか。
それは僕に与えられた罰。
僕は終身刑に処された。いつ逃れる事ができるか分からない終身刑。