「そんな処で――」
声を掛けられて見上げると、白い女の人が居た。
「そんな処で丸まって居たら、お巡りさんに連れてかれるよ」
何だろう、ふざけてるんだろうか。
右手を差し出して。何かに気付いて引っ込める。
「ああ、ごめんごめん」
そう言った彼女の右手には白いライオンの人形が着いている。
やっぱりふざけてるんだろうか。
「お腹空いたからさ、ご飯食べに往こう」
「何ですかあなたは。ふざけてるんですか?」
言ってしまった。
左手を差し出した彼女の表情は変わらない。けれど、何かを考えるように視線が動いている。
「あ……」
少し、後悔した。
「ごめんなさい」
怒られると思って咄嗟に出た言葉だった。それなのに、
「うん、巫山戯けてるのかもね。さ、往こうよ」
そう言った白い女の人の、笑顔が優しくて。綺麗で。すがるように手を伸ばし
止まった。
わたしは。
「わたしは」
そう、わたしは。
「行けません。死神だから」
そう、この手で大切な人の命を刈り取った。
「あ?」
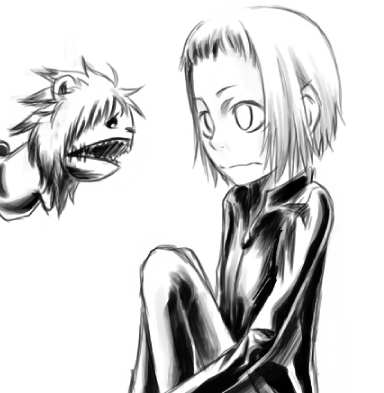
目の前に突然迫った白い物体が声を発した。
「ただの人間の小娘が何言ってんだ」
白い女の人の右手に着いたライオン。
それが喋っている。ように見せたいんだろうけれど、声は彼女の声。
「俺の目に映るお前の魂は人間の物でしかない。この梅さんなんかは本物だぞ。大昔は門の魔女とも呼ばれた半妖ま」
そこまで言って、五月蝿いよ。と人形の口が塞がれた。
ふざけてるにしても凄い。実は路上芸人なのかもしれない。ちょっと、売れそうに無いけれど。
「ね、死神ちゃん。何があったか私には判らないけどさ」
白い人形の口を押さえて、白い女の人が言う。
「言うまでも無く君は人間でしょ。それも綺麗な、とても綺麗な魂が私には観えるんだけどな」
この人は、何も知らない。
わたしが綺麗なはず無い。何も知らないくせに、可哀想にと腫れ物に触るように優しくしてきた大人達と一緒。馬鹿みたい。馬鹿みたい。何も知らないくせに。馬鹿みたい。
そんな同情はいらない。
嘘つき。
嘘つき。
「うそ――」
「お。あらあら、君はおばあちゃん似なんだね」
うそ……
「私がいるから出てきたのかなー?」
「梅さん。飯」
「五月蝿いよ、くま」
この人は。
「往こう。死神ちゃん」
この人の笑顔は他の大人たちの笑顔とは違う。
ふざけてるのかもねって言った。ほんとに心からたのしくて出る笑顔。自分のための笑顔。似ている。顔は全然違うけれど。
「ディヴィです」
「でぃび?」
「わたしは死神なんて名前じゃない。ディヴィです」
最初に話し掛けてきた時から、ずっと笑ったままの顔。それが一層の喜びを表して。
誰かのためにあるわけじゃないのに周りを照らす太陽のような、そんな笑い顔で。
「私は白。もちだ、しろ」