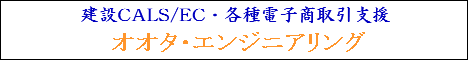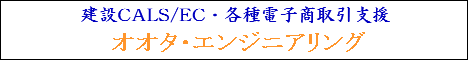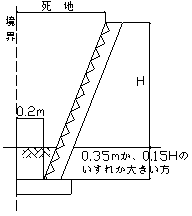擁壁・法面目次
はじめに
今、我が国では行政改革や規制緩和が様々な形で進行する一方、
消費者のニーズも多様になり私たち都市造りに携わるものもその変化には
目を見張るものがあります。
このような変化に対しても当社はこれらの情報をいち早くキャッチし、
お客様に最新の設計や工法をご案内致し都市造りに貢献します。
当社技術陣は規格設計・許認可取得・施行に関して30年の経験を
要した人材で、土地の資産価値の減少の下落が止まらぬ今、
どのような些細なご相談でも受けたわまります。
擁壁・法面の処理
(1)法 面
1. 切土法面の勾配・小段
- 切土法面=5M以内1:1 5M超1:1.5
- 小段=3〜5M毎、1〜1.5M幅、U字溝設置
a. 法面勾配
b. 法面処理
2. 盛土法面の勾配・小段
- 小段=1M以内1:1.5 5M以内1:1.5〜1.8 ,5M超1:1.8〜2.0(地山の段切り1:3)
- 小段=3〜5M毎、1〜1.5M幅、U字溝設置
a. 法面勾配
b. 法面処理
3. 法面保護と管理
自然法面を残置した方が修景、安全、コスト面等でよい場合もある。
4. 緑地等の必要面積への算入
5. 造成法面の植栽
法面は従来、外来の牧草種子の吹付や芝張等による植栽が行われてきた。
これらの方法は比較的安価であり、施工方法も研究開発されていて降雨等による
法面侵食防止にも効果が認められてきたが、持続性・計画性・管理費の点で問題がある。
また、住宅環境をより豊かにするため常緑高木樹脂(シイ,タブ,カシ等)による植栽が検討され
採用されている例がある。
ただし、最近では行政機関において従来の工法(法型枠、芝張等)による法面処理方法は、
行政移管後の管理コスト増大から敬遠される傾向にあるので、十分な協議が必要である。
この場合、行政に移管すべき土地で道路残地が生じる場合は、設計時点において、
如何に民有地として処理するかを検討しておく必要がある。
最近のはなはだしい例では、道路用地に面した法面や道路残地を
モルタル覆工させられた例がある。
昨今のガーデニングの普及により、むしろ民有地として管理させた方が有利な場合があり、
計画設計上留意すべき事柄である。
(2)擁 壁
1. 基本検討
a. コストと有効平地の兼ね合い
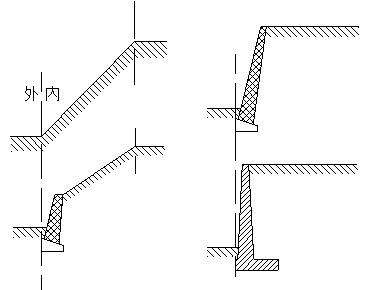
b. 任意擁壁(切土部2M以下、盛土部1M以下)
1ヵ所に集約せず、任意擁壁の範囲内の分散配置の方がコスト的に安い。
c. 認定擁壁(切・盛土共に3M以下)
- プレキャストコンクリート擁壁の検討(景観に留意する必要がある)
- CP型枠ブロック擁壁(整備基準,景観に配慮した製品・・当社推奨品)
d. 修景(環境及び商品性)と擁壁
擁壁の圧迫感を回避するための材質の検討。
また、北下りの場合の北傾斜法については日照も考えて擁壁工法を選定。
e. 法令上の規則
- 宅地造成等規正法
- 建築基準法
- 基準書(建築省,国鉄,公団等)
- 崖条例
- 指導要網
- 自治体開発担当者と協議
- 宅地造成等規制区域については、
「宅地造成に関する工事の許可申請」(第8条)が必要である。
- 宅地造成等規制区域外の場合も規制法に準じた指導をされることが多い。
- H=2M以上の擁壁は「工作物確認申請」(建築基準法88条)が必要で、
建築主事と協議して許可を得る。
※ 宅地造成等規制法による許可を受けなければならない擁壁については
適用しない。
2. 細部の検討
a. 擁壁のころびと宅地の条件
- 北傾斜地における日照の確保
- 死地の解消(別掲:検討資料参照)
b.石積擁壁
| H(m) |
死地面積(擁壁幅1mについて) |
| 1 |
0.2+(1+0.35)×0.3=0.605m2 0.18坪 |
| 2 |
0.2+(2+0.35)×0.3=0.905m2 0.27坪 |
| 3 |
0.2+(3+0.45)×0.3=1.235m2 0.37坪 |
| 4 |
0.2+(4+0.60)×0.4=2.040m2 0.62坪 |
| 5 |
0.2+(5+0.75)×0.5=3.075m2 0.93坪 |
c.コンクリート及びCP型枠式直擁壁 (擁壁幅1mについて)
死地面積0m20坪
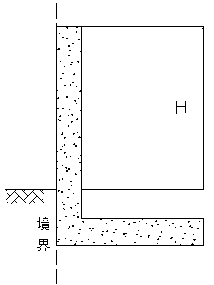
d.プレキャスト直擁壁 (擁壁幅1mについて)
死地面積0m20坪
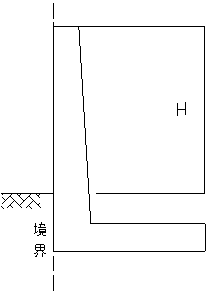
※ 直擁壁にすることで死地を解消(あるいは減少)できるが、
以下、直擁壁の損失について考察する。
3.メリット
- 有効平地となった死地面積を開発地全体としての戸数増加に利用すれば、
- 一戸当りの有効平地面積は同じだから土地需要者はより安く
同一平地面積の宅地が購入できるようになり特に土地売買単価が
高い物件においては、供給者及び需要者にメリット。
- 宅地有効面積が増え、供給者及び需要者双方にメリット。
- 有効平地となった死地面積を個々の宅地においてガーデニング等の
有効利用をはかり、宅地としてのグレードアップを実現できる。
- 擁壁の根入れ部分をめぐる隣地との間に境界や管理トラブルが発生しない。
4.デメリット
- 土地価格に着目すると近年の土地価格下落の傾向から、擁壁の形態の
如何にかかわらず土地価格は不変ととらえられる傾向にある。
よって他の擁壁に比べて工事費のかかる直擁壁は土地価格の原価を増加させる。
要は開発区域の周辺環境にマッチした整備基準(景観,居住性,グレードに相応)
策定に配慮することになる。
- 開発地全体としての戸数の増加が各種負担金の増加、公共公器施設の
イニシャルコスト・ランニングコストの増加等につながる可能性がある。
- 直擁壁のため住宅地全体について圧迫感が生じてしまう。
5.当社提案
当社はこのようなメリット・デメリットに対して十分な検討を行い、
許可認定,供給側,需要側のそれぞれの立場に配慮した設計や提案を行います。
土地診断はもとよりエンドユーザーの居住後のグランドカバーやガーデニングに対しても、
様々なアドバイスや提案を行える企業です。
ブロック積擁壁の積方
CP型枠ブロック擁壁の設置例
- 表面には様々なバリエーションを用意
- 周辺環境に無理なく溶け込む
- 多用途(門扉・カーポート・塀・擁壁に対応)
1〜3Mの認定擁壁
タイプ毎の標準にて施行可
- 擁壁の勾配がないため敷地を100%活用できます
- 間知石など練積み擁壁は擁壁に勾配をもたせなくてはなりません。
擁壁が高くなるほど、有効敷地面積の割合が少なくなり、
貴重な土地が無駄になっていました。
|