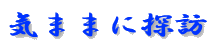 [若宮さん] (1)
[若宮さん] (1)<<<Home Next>>>
 ■若宮さん (佐良志奈神社=さらしなじんじゃ)
■若宮さん (佐良志奈神社=さらしなじんじゃ) 長野県千曲市若宮
佐良志奈神社の由来
一説には仁徳天皇の皇子、允恭(いんぎょう)天皇が皇子「黒彦の命」に、命じて創建したとも言われています。 冠着山の尾根八王子山に祀ったが、887年の地震で千曲川に崩落して、現在の場所に祀られたと言われている。
1450年に本殿火災により古文書が消失し詳しい創立年不明ですが、433年頃といわれています。
当時「延喜式内神社」は更級郡には11社ありその中の1社であった明治15年郷社になる。
社殿の名称は明治の町村合併に際し、「更級(さらしな)村」の名を許される根拠となりました。
※「延喜式内神社」とは当時「官社」とされていた全国の神社一覧である。延喜式神名帳に記載された神社を、「延喜式の内に記載された神社」の意味で延喜式内社、または単に式内社(しきないしゃ)、式社(しきしゃ)といい、一種の社格となっている。 元々「神名帳」とは、古代律令制が平安時代の康保4年(西暦867年)に施行された三大式の一、延喜式が在るが、其の中の延喜式神名帳に記載された神社を特に「延喜式内社」と呼ぶ。
 氏子は黒彦村、若桜宮村(現在の若宮地区)、柴原村(現在の芝原地区)、中でも黒彦村は戸数が多く市も立ち栄えていたが1542年、1597年、1612年のたび重なる水害に遭い当時は山側に流れていたが、氾濫により現在の位置になり、黒彦村が水害で移住分村し右岸が現在の上徳間と五加o、左岸は1部 河原となり田畑化され、黒彦村跡に1970年代に県の住宅供給公社により新たに大規模な「黒彦団地」が造成され、黒彦団地と若宮地区、芝原地区、の3地区を「若宮」と呼んでいます。
氏子は黒彦村、若桜宮村(現在の若宮地区)、柴原村(現在の芝原地区)、中でも黒彦村は戸数が多く市も立ち栄えていたが1542年、1597年、1612年のたび重なる水害に遭い当時は山側に流れていたが、氾濫により現在の位置になり、黒彦村が水害で移住分村し右岸が現在の上徳間と五加o、左岸は1部 河原となり田畑化され、黒彦村跡に1970年代に県の住宅供給公社により新たに大規模な「黒彦団地」が造成され、黒彦団地と若宮地区、芝原地区、の3地区を「若宮」と呼んでいます。志賀直哉の小説「豊年蟲」にも登場する神社で、 地元では「若宮様」と呼ばれて親しまれています。
※豊年蟲=オオシロカゲロウ 佐良志奈神社の鳥居付近の千曲川大正橋の街灯にオオシロカゲロウの群生飛来を見ることがあり散歩に来た「志賀直哉」が見たと思われます。大量発生した年は豊年になるとされ豊年蟲と呼ばれています。
◆若宮
若宮 芝原 黒彦団地(旧黒彦村跡)




◆案内図
しなの鉄道戸倉駅 徒歩15分
長野道 上信越道 更埴IC 車20分
