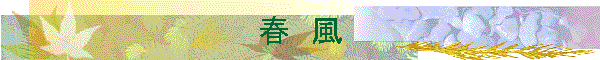…―――
それは、間もなく訪れる春の薫りを告げる、柔らかな風の吹くある日の出来事…。
§
…ぱたぱたぱた…と軽やかな足音が邸内に微かに響く。
それはここ一月ほどの間に聞き慣れた音。
足音の主の心を表しているかのように、その音はいつも明るく、そして心地よく耳に届く。
内裏でのその日の朝の務めを終え、一旦、自らの住まう左京一条の邸へと帰宅した泰明は、寝殿へと続く渡殿の途中で捉えたその音に、ふと足を止めた。
そうして、自分の意識を捉えた気の持ち主の気配に惹かれるように、足音の消えた方へと琥珀の双眸を向ける。
足音の主は、どうやら庭へと降りていったようだった。
自分の今いる場所から左手の方、この邸の南側に広がる庭園の奥まった辺りから、何やら楽しげな暖かい気配が伝わってくる。
―――
どうやらまた、「彼女」が何かを思いついて動き回っているらしい。
あちらの邸にいた時は、手習いや行儀作法などを身につけるのに忙しかったせいもあってか、時折「散歩」などと称して無断で独り、邸を抜け出していた事を除けば、大抵は部屋で大人しくしていたようだったが、こちらへ移ってきてからは、何かとくるくるとよく動き回っているように思える。
…まあ、本来の「彼女」の性質からすれば、今の方が「らしい」とも言えるのだが。
ふっと胸に浮かんだ面影に、遠くを見透かすかのような澄んだ瞳が、僅かに和む。
そのまま、泰明はそのひとの気配のある方へと足を向ける。…と。
そのすぐ傍をととと、と小さな女童(めのわらわ)がすり抜けた。
胸の前に掲げた小さな両手の中には、何かを包んでいるらしい料紙を携えている。
自分へ向けられている泰明の視線に気がついたのか、紅梅匂いの襲ねの衵(あこめ)姿のその童女は通り過ぎざま、ちょこんと小首を傾げるようにして彼に挨拶した。そして、淡い桜色の振り分け髪を肩の辺りでふわふわと空に散らしながら、先に足音のした方へと元気に走ってゆく。
だが、その賑やかな動作に反して、少女の足元からはほんの僅かな音すら聞こえない。
「…お師匠の式神か」
その後ろ姿を見遣りながら、いつの間に住み着いたのだろう、と泰明はふと考える。
邸の主の主義が「来る者は拒まず、去る者は追わず」というものだったので、気がつくとあのような何かの精や式神が住み着いて、邸のあちこちをうろついていることは日常茶飯事だった。
ただ、近頃…特にここ一月ほどの間に、ああして引き寄せられる輩が急に増えてきている。
師に言わせれば、恐らく今、この先の庭にいる筈の「彼女」は、どうやらそのようなものをよく引き付ける質、らしい。そしてそれは師ばかりでなく、そのひとの本質を知る者ならば自ずと判る事だ。
…「彼女」は全てに愛される存在、なのだから。
あちらの邸に「彼女」が住まっていた時は、自分がかなり強力な結界を張っていた為、そのような者達は近づこうにも近づけなかっただけなのだろう。
―――
故に、恐らく原因の一端は、今ここにいる「彼女」にあるのだろう。…が。
と、そんな事を考えていた泰明の傍を、また小柄な影が通り抜けた。
今度は角結いの牛飼い童だ。
濃い紫色を帯びた結い髪を靡かせつつ、殆ど足音を立てずに、その手に水の入った桶のような何やら大層な荷物を抱えて、やはり先ほどの女童の消えた方へと走ってゆく。
重さを感じさせないその動きは、やはり式神のもの。
…それもこれ程増えてくると、師はそうして「彼女」に懐いてくる精に、半分面白がって片端から形を与えているのでは、という気がしなくもない。
今し方目の前を通り過ぎた、初めて見かける二人の式神の行く先を泰明は見つめ
―――
その行く先に近い辺りにもう一つ、「彼女」とは別の、慣れ親しんだよく知る人の気を微かに感じ取る。
知らず、形の良い唇から吐息が洩れる。…それはどちらの気配へと向けられたものなのか、彼自身にもよく判らない。
「…今度は一体、何をしているのだ」
ぽつりと独りごちると、泰明は自分もその童の後を追った。
§
寝殿を通り抜け、黙々と歩いていた泰明の目に、中庭を望む透渡殿に立つ見慣れた一つの人影が映る。
白い狩衣を無造作に羽織り、艶のある青みがかった黒髪も背で緩く一つに束ねたまま、くつろいだ雰囲気で佇んでいるそのひとは、紛れもなくこの邸の主であり、彼の師でもある人物だ。
その陽の光に蒼く透けるような双眸は、何処か面白そうな表情を湛えて、正面に広がる庭の奥…柔らかな風にはらはらと花びらを散らす梅の木の辺りに向けられている。
そして彼の人の視線を追った先には、三つの人影。
梅の木の下にしゃがみ込むようにして、肩を越す程の長さの朱鷺色の髪の少女が、先に見かけた二人の式神に話しかけながら、何やら地面を掘り返しているようだ。
様子から察するに、植物の種か苗でも植えようとしているらしい。
…それをどうして師があのように妙に楽しげに眺めているのか、いまいちよく判らなかったが、当面の問題はそこではなく、何故今、そのひとがこの邸に居るか、という事の方だろう。
―――
泰明がそのまま真っ直ぐに近づいていくと、相手もやはり彼の気配にはとうに気がついていたらしい。
ゆっくりとこちらを振り返ると、その端正な面立ちに柔らかな笑みを浮かべる。
「お帰り、泰明」
「お師匠。何故ここに…」
労うかのようなそのひとの静かな声音に比べ、対する泰明の自らの師へと呼びかける口調はやや固い。
よく透る声には問いかける風は無く、何処か呆れにも似た色が滲み出ている。
「此処は私の邸だからね」
「…そうではなく。今日は陰陽寮の方で仕事があった筈ですが」
飄々とした晴明の様子に溜息をつきながら、低い声で泰明がそう返す。
そんな彼の前で晴明はにっこりと穏やかに笑って見せた。
「固いことを言うものではないよ、泰明」
「………」
お師匠は柔らかすぎる、とでも思っているのかどうかは解らなかったが、それ以上会話を続けても無駄と言わんばかりに、泰明は何も答えなかった。
大体、彼の師がこの様な調子ではぐらかす時は、いつも雲か霞のようにその思惑は掴み所がないのだ。
何か考えあっての事か、それとも単なる気紛れか…判断の難しい所だったが、それでもこんな具合で晴明が出仕しなかったり、ふらりと雲隠れする度に後始末を任せられた事が何度となくある身としては、苦い思いを感じざるを得ない。
思わず溜息を洩らしたとしても、仕方のないことだろう。
―――
一方、晴明は、黙りこんでしまった彼の横顔にじっと視線を注いでいた。
師である彼にしてみれば、そもそも泰明が内心でどんなことを思っているのかなどすぐに判ってしまうのだが、近頃はそれが随分はっきりと表情に表れるようになってきている。
…そう、それは彼があの少女と出逢ってから…。
…―――
と、その時、泰明に向けられていた瞳が、視界に捉えたものに僅かに細められた。
同時にその奥に揺れていた面白がるかのような光が、俄に鳴りを潜め、ふっと表情が和らぐ。
そこに浮かぶのは、慈しむかのように穏やかな、柔らかな…微笑。
「…随分、髪が伸びたな」
思い出したかのようにぽつりと紡がれた言葉に、一瞬、泰明は訝しげな顔をし…ややあって、それは何と答えればよいのか戸惑っているような表情へと変わる。
晴明からかけられた言葉に籠められたものが何であるか、理解してはいるが、どのように反応すべきかわからないといった様子だ。
…困惑した風情でその場に佇む泰明の髪は、吹く風にさらさらとたなびいていた。
それはある時を境に急に伸び始め、いまや綺麗に結っていてもその長さは以前の腰の位置をとうに超えている。
晴明はそんな彼の姿の意味するものを思い、一層、その微笑を深くすると、彼から再び庭の方へ、ゆるりと視線を移す。
…その先には、二人の式神に囲まれて先ほどと変わらず佇む、優しい気配を纏った朱鷺色の髪の少女の姿。
“もうそろそろ、ひと月になるか…”
独り言のようにふっと心の中で呟き、晴明は何事か考えるように軽く瞳を伏せる。
…泰明がかの少女を自分の元へ迎えたいと言ったのは、まだ雪深い睦月の頃。
それから必要な段取りを踏み、先頃漸く、邸へ正式に少女を迎え入れたというのに、自分が把握している限りでは、ここの所、泰明は休む暇もなく出仕している。
他方、彼女はと言えば、そんな彼にあからさまに拗ねたり文句を言ったりするでもなく、実に健気にその帰りを待っていたりするのだ。
―――
ここにいれば毎日逢えるから淋しくないのだ、とは当の少女の弁。
だが。
“…少しくらい仕事に手を抜く、という事を覚えればもっと楽であろうに”
普段よりも少々青ざめて見える、生真面目で何処か不器用な愛弟子の横顔にそんな感想を零し、晴明は内心で苦笑すると、右手に握っている檜扇をぱちり、と鳴らした。
「泰明、午後は出仕には及ばぬよ」
唐突な晴明の言に、泰明は不審そうに首を傾げる。
「…?しかし」
「後の事は心配はいらないよ。この際、二、三日休んで暫く、ゆっくりするといい」
反駁しかけた彼に、穏やかながら逆らい難い声音で継がれた言葉に気圧されるように、泰明は一瞬、口を噤んだ。
何故、晴明が急にそんなことを言いだしたのか、その意図が泰明には判らなかった。第一、これまで仕事を申しつけられることはあっても、特に理由もなく仕事を休め、などと言われたことなど無い。
だが、よいね?などと更に念を押されると、この場は頷くしかない。
何とはなしに眉根を寄せたまま、わかりました、と一言頷く泰明に、晴明は緩やかな笑みを浮かべると、そうそう、神子姫に宜しく伝えておくれ、と言い残して優雅な仕草でその場を立ち去っていった。
§
「…あれ?泰明さん?」
晴明の姿が渡殿の向こうへと消えた後、当初の目的であった庭へ降りてゆくと、その気配を感じたのか、そこにいた少女
―――
あかねはくるりと振り返るなり、驚いたように目を丸くした。
今朝、出仕していく泰明を見送ったのだから、当然と言えば当然の反応だろう。
あかねは慌てて立ち上がると、傍にいた式神にちょっとごめんね、と囁きかける。
すると二人は心得たように、辺りに散らばる自分達の運んできた道具を手に取ると、すうっとその身を空気に溶け込ませるようにして、その姿を消す。
後に残るのは、飛び去っていく小さな紫色の胡蝶と、ひらりと舞い落ちる梅の花びら。
それを見送ると、あかねはぱたぱたと軽く手から土を払い落とし、傍まで近寄ってきていた泰明の方へと駆け寄ってきた。
そして彼の顔を見上げて、首を傾げる。
「どうしたんですか?こんなに早く…」
「お師匠に二、三日休めと言われた」
「晴明様が?」
釈然としない為か、どことなく憮然とした面持ちでそう答える泰明に、あかねはきょとんとした様子で首を捻る。
そんな少女の表情を見ながら、泰明は軽く腕を組むと小さく息をついた。
これ以上、考えてみても仕方がないと思ったのだ。
そして、ふっと先ほどまであかねがしゃがみ込んでいた辺りの地面へと、視線を落とす。
「…―――
それよりもあかね、一体何を植えていたのだ?」
「えっ?」
不意に問いかけられた為か、一瞬意味を取り損ねたらしいあかねが聞き返す。
しかし、泰明が何やら興味深げな色を瞳に滲ませて、小さな若葉が幾つか植わっている地面をじっと見つめていることを悟ると、菫です、とにっこりと笑った。
「すぐ傍の道端に生えてて踏まれそうになってたから、気になって。何だか窮屈そうだったし、広い処に移してあげた方が綺麗に花が咲くかなって」
「花が窮屈そうだ」などとは、いかにも彼女らしい感じ方だと思いながら、泰明はあかねへ視線を移す。
あかねは再びしゃがみこむと、菫を植え替えた辺りの土をぽんぽんと軽く叩いて、丁寧に指先で均しはじめた。
「…それにね、たくさん増えて、毎年春に花が咲いたらいいなって思ったんです」
ややあって楽しげな様子でそう言うと、咲いたら一緒に見ましょうね、とあかねは綺麗に微笑って見せる。
その言葉に、何を思ったのかふっと泰明が笑みを零した。
「毎年…か」
「…?」
不意に隣から零れ落ちた言葉に、不思議そうに振り返ったあかねがこちらを見上げているのが視界の端に映る。
「…いや。それならば私も、お前と一緒に見るのを楽しみにしている」
ゆっくりと、噛みしめるかのように紡がれた言葉に、あかねが破顔した。
それは少しの翳りも無い、純粋な喜びを映した…笑み。
彼女の微笑に惹かれるように、泰明の笑みも深くなる。
まるで当然のことのようにさらりと毎年一緒に見ようと言うあかねの言葉が、驚くほど自然にするりと胸に染み込んでくる。
言葉自体の意味だけならば…或いは他の者が言ったのであれば、恐らくはたわいないものとしか感じないだろうと思えるのに、一片の疑いも無く、共に在る日々が続くのだと信じさせてくれる言葉。
たとえ一時離れることがあったとしても、必ず「此処」へ還ってくるのだと。
――― 自分の元へ。
そんな事を考えてしまうのは、それだけ強く、自分がそうあることを望んでいるから、なのだろう…。
そして泰明は緩やかに瞳を伏せる。
…あの雪の日。
それまで何処かで踏み切れずにいた願いを胸に、晴明の元を訪れた自分に、師であるそのひとは蒼く透ける双眸に全てを悟っているかのような、穏やかな優しい光を湛えてただ、頷いた。
――― 何かを望み、叶えたいと願ってもいいのだと。
そして“こんな事は生涯言えぬだろうと思っていたが”と苦笑しながら優しい眼差しで自分を見つめ、ぽつりと呟いた。
“私は、いつもお前にとっての幸せを願っているよ。…息子である、お前の…”
――― “幸せ”。
それは、生まれたばかりの自分に晴明が告げた言葉を思い出させる。………『幸せを知れ』、と。
まだ、あかねと自分が神子と八葉としての務めを負っていた頃。
北山の天狗の元で「幸せ」を「知らぬ」と言った自分に、それは今、不幸せだという意味ではないのかと訊いて、安心していた彼女。
そして「幸せ」というものがどんなものなのか知らない…そう、判らないというのなら、これから少しずつ感じてゆけばいいのだと。
“そんなに苦しそうな顔をしてるんだもの。あなたは、ちゃんと何かを感じてる。だから幸せも心も必要ないなんて言わないで”
まっすぐに自分を見つめながら、そんな事を言って彼女は微笑んでいた。…今と、同じように。
…――― 「幸せ」…そう、自分は確かにいま、幸せなのだろうと思う。
本来なら出逢う事すら叶わなかった…遠く、世界を隔てたひとと出逢い。
誰よりも愛しいと思ったその少女が傍にいて。
その笑顔に自分自身が満たされ、癒されてゆくのを感じながら、今…共に時を過ごしている。
そうして傍らでその声を、笑顔を、温もりを感じ、同じ時を刻みながら、幾つもの思い出と溢れる想いを積み重ねてゆくのだろう…。
―――
微かな吐息と共に、柔らかな表情を浮かべてゆっくりとその瞳が開かれる。
陽に透けて金色に輝く双眸が真っ直ぐに見つめる先には、彼を囚えて離さない愛らしい微笑み。
そこへ何処からか、微かな甘い花の薫りと共に涼やかな鳥の鳴き声が風に運ばれてくる。
ふわりと頬を撫で、髪を梳いてゆくかのようなその風は、包み込むように柔らかく、仄かに暖かい。
…そしてまた、生命の萌え出づる季節が巡ってくる。
仄かに薫る淡紅の花びらを乗せた、新しい温かな息吹を連れて。
――――― 運命と出逢った、あの季節が。
FIN.
陸深 雪様<Copyright(c)
Yuki Kugami. 2002>
月晶華:http://www.geocities.co.jp/Playtown-Queen/3188/

|
[涙のひと言]
陸深様が“2002年
New Year企画”として
特別配布しておりました3部作の中のラストを飾る作
品です。
あらゆるものに愛され慕われるあかね、ふたりを父親
として見守る晴明、そして泰明とあかねふたりの間に
流れる穏やかな時間…そんな三人の様子が伝わって来
て、ホッと温かい空気に包まれる作品です。
陸深様素敵な作品をありがとうございました。
|
★陸深 雪様のサイトへは『リンクのお部屋』からどうぞ★
戻る
|