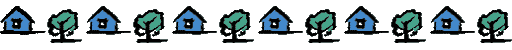
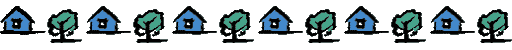
最終話 再びプノンペンそして帰国
朝まだき5時にチェックアウト。6寺10分には、暗い中ホテルを出る。ベトナムとカンボジアに来てから、朝暗いうちに起きて行動し移動する毎日が続いた。ガイドの几帳面な性格もあって、万が一にもというよりこちらでは万が100くらいの確率で起るらしいが、飛行機に乗り遅れてはいけないということで、今朝もまた早起きとなった。オーバーブッキングということもあるが、早めにスタンバイチケット(空席待ち)を売ってしまうことがあるので気をつけなければならないという。
地元の人々の朝は早い。真っ暗闇のなかで、朝のコーヒーを飲む習慣のある客のために営業を始める喫茶店らしき店があり、ぼんやりと薄ら明かりをともして寝ぼけている。
真面目を絵に描いたようなコン君が、気を利かせて空港に早めに着こうとしたのに、なんとシエムリアッップの空港はまだ開いていなかった。日本でいえば田舎町の駅のような小さな空港だから、中のようすが見える。ほどなく空港に入れたが、今度はチェックインカウンターの女性は来たが、コンピューターを作動させるキーを管理する担当者がまだ来ていないということで、しばらく待たされた。空港利用税を徴収する係りの女性も眠そうな顔をして現れた。ボックスの中で、化粧を整え始めた。折角早起きしたのに、という気になったが、いずれにしてもカウンターの一番前に並んでいるのだから、乗り遅れることだけはなさそうだった。
間もなく、チェックインが始まり、すぐ搭乗ゲート(といっても空港施設の出入り口)前のロビーに出る。すべてが10メートル四方の中でのできごとだ。そういえば、荷物検査もセンサーによるボディチェックもない。日本からの団体客が、集りはじめた。最近特にアンコールワットは人気だそうである。きのう、寺院の急な石の階段を昇り降りしていた客とツアーガイドの顔も見える。
飛行場が、ガラスごしに丸見えだ。待合室で少し感傷的な気持ちになった。ベトナムも含めて、今回の旅は充実していた。すべてが私の好奇心を満足させてくれたと確信している。私は持ち歩いていた自分の著書『スーはきっと踊りつづける』(1998年工作舎)を、お礼の気持ちでコン君にプレゼントした。コン君は、今年ふたたび日本の大学に留学する準備をしているのだと、初めて私的な事情を私に打ち明けた。一緒にいる間ずっと、コン君はガイドとしての自分の立場を越えて私に接近しようとはしなかった。ひとりで食事をするのもさびしいので、一緒にどうかと私は何度も誘ったのだが、生真面目な彼は注文を取りにくるときまでは一緒のテーブルにいるが、やがてトイレに行く風を装ってさっとどこかに姿を隠した。それが私には少し不満だった。
「うれしいです」
私が中表紙にサインをして彼に手渡すと、彼は少し驚いた表情をして、それから本当にうれしそうに微笑んだ。心の中と表情とがピタリと一致していたように見えた。ガイドと雇い人の関係を超えてこのとき初めて私はコン君に深い友情を感じた。
「日本ではカンボジア難民を支援する会の人々が留学の手続きをしてくれています。私はただしっかり勉強していればいいといわれています」
コン君の日本留学を支援する人々は、東京の高等学校の教師グループだという。彼の誠実さが、大きな支援グループの心を捉えていることをはじめて知った。まもなく、ボーイング737−400機の機体がゆっくり目の前の滑走路に着陸した。プノンペンからのVJ320便。きのう乗った便だ。これが折り返し、われわれの乗るVJ321となる。客が降りきるのを待って、ちょっと一呼吸おいてから、まるで電車にでも乗るような軽い気分で飛行機のタラップに向かって歩いていった。
飛行機は朝日に輝くトン・レサップ湖の上空を通り、再びプノンペンに向かった。飛行機の中で、プノンペンでの半日の行動計画を簡単に確認した。まず、王立芸術大学を訪れること。さらに、私の著書の舞台となった「サムダッチ・ソーテールゥ通り界隈」をもう一度散策する。さらに、「スバイポペ寺院」をもう一度。また、寺院の裏手にはカンボジア独特の高床式の家がたくさんあったはずだから、もしかして30年近く経過した今でも残っているかも知れない。ぜひそのあたりに行ってみたい。残された時間が残り少ないとなると、最後の悪あがきか欲望はどんどん膨らんで行き、コン君に無理なお願いが増えていく。しかし、コン君は通常の観光客とは勝手の違う「案内」の要請に並々ならぬ気配を感じ取ってくれ、(まかせておいてください)と言いたげな表情でうなづいていた。
プノンペンの「ポチェントン空港」から、私たちはすぐクルマで王立芸術大学に向かった。朝の日差しはもうかなり強く、車の窓を締め切ってクーラーをかけなければいられなかった。途中プノンペン工科大学の前を通過した。
「フランス人が運営している大学(institute of technology)です」
カンボジアもベトナムと同じく長い間フランスの植民地だった。いまでもその名残が随所に残っている。国の失業率は統計を取るのも無意味なほど高い。高卒者の約30%が大学に進学。大卒者の10%も就職にありつけないのが今のカンボジアの就職事情だ。
ベトナムでも同じだったが、大学の工学部を出てもそうしたエンジニアの卵たちを吸収する産業が国内にない。高度な技術者はみなアメリカやヨーロッパで学ばなければ通用しない。就職を考えれば工科大学の卒業生の前途は明るくはない。そんな中で、人気の筆頭は経済大学や経営大学だ。カンボジア最大の難関校は、プノンペン国立経営大学「Cambodia National Institute of Management」だ。ここを卒業し英語か日本語を話せれば、高給を保証してくれる「外資系企業」に就職ができる。カンボジア人は自分でビジネスを起こすことにも熱心だ。
「いまのカンボジアにはどんなビジネスでもあります。まだ市場が育っていないだけ。アメリカや日本にあってカンボジアにないものは、銀行からカードでお金を引出すATMだけですね」
コン君は自信たっぷりに言った。われわれのクルマは、幹線道路から一本外れた土ぼこりの舞う道を走り出した。市内だというのに、貧しい人々が住むこの地区のインフラはまだまだ未整備だ。かなり置き去りにされている感じだ。道の名前が「キム・イルソン通り」だという。プノンペンには「毛沢東通り」というのもある。インフラ整備の資金を、この国は他国の援助に頼ってきた。だから、国交が怪しくなったり、断絶したりすると、道路や建物の建設が途中で中断し放置される。政治情勢が不安定なカンボジアを象徴するように、そんな場所が市内にいくつもある。
「ほんとうに、もったいないです」
広い土地が無駄になり、その上に無残な工事の残骸が野ざらしになっている。急に土ぼこりにまみれたバラックが延々と続くエリアに入った。あきらかにスラムと思われた。
「ここは、トゥォールコック通りといいます。カンボジアの人々で知らない者はいません。有名な売春街です」
コン君の説明に、私は驚いた。その手の商売をする場所は、怪しげなネオンが煌く場所と思い込んでいたからだ。ここはまるで違う。軒を連ねているのは今にも倒壊しそうな薄汚れた小屋だ。衛生状態も最悪だろう。悲惨なものを見た。「向かって左側がベトナム人居住区。反対側がカンボジア居住区です」
住み分けがきちんとできているという説明だが、目に映る光景は左も右も同じだ。両国人が同じ商売をし、張り合うようにして客を取りあっているというのか。クルマの中からカメラを向けると、入り口の外の椅子に腰掛けている女が、さっと中に身を隠し堅く扉を閉ざす。何度やっても同じ反応だ。危険はないのかと、心配になって聞いてみた。
「大丈夫です、私たちがいれば」
コン君はさりげなく答えた。
確かに、ガイドとクルマによって移動すれば、昼の間カンボジアはどんな場所でも入って行けるし、どんなものにカメラを向けても安全だった。ガイドは、われわれが想像する観光案内人以上の権力を持っているようにも見えた。夜は危険だと言われるが、そうかもしれない。カンボジアでは長い内戦の間に、一般市民の中にまで拳銃などの銃器が浸透してしまった。警察官も、夜影に乗じて「アルバイト」をするので信用できないといわれる。しかし、コン君は苦笑いをした。
「警察官の制服を着た泥棒がたくさんいます。なんだかんだと言い掛かりをつけて、金銭を巻き上げる。犠牲になるのは観光客だけでなく、私たちも同じです。必ずしも警官が悪いということではありません」
説得力のある話だ。そういえば日本でもかつて「警察手帳」を悪用した愉快犯の事件があり、世間を騒がせたことがあった。
トゥォールコック通りを抜け出ようというとき、クルマは急にハンドルを左にきり、門の間を滑るように王立芸術大学のキャンパスに入った。ここが目的の場所だと知って愕然とした。売春街のはずれに、カンボジアが誇る芸術家を養成する名門の大学があるとは想像もしていなかった。
突き当たりのホールでは、韓国からの団体旅行者が貸切で民族舞踊の公演を鑑賞していた。いつもは練習場になっているというホール。この時間生徒たちはどこで練習をしているのだろうと見回すと、左手奥のピロティのような場所の2階に集まっている。色とりどりの練習服を着て、先生の指示に合わせて手の指や足腰を反らせている。上着はレオタードのようなものだが、下は袴のようなもののすそをよじって股の間に通して結ぶ独特の衣装だ。そばに付いている先生といっても、ついこの間までは生徒だった人々で、二十歳を越えたばかりの年齢だ。私は、思わずシャッターを切りまくった。おそらく小学生から中学生の始め頃の年頃の「大学生」だろう。ふと目線を上げると、校舎の窓からこちらに向かって手を振っている子供たちがいる。彼女たちは「教科の勉強」の時間なのだろう。
キャンパスには、それ以外に民族楽器を練習する長屋のような場所がある。小部屋ごとにさまざまなグループが練習をしている。珍しい楽器があり、どうやって音を出すのか食い入るように見ていた。先ほどのホールに戻ってみると、コン君の知り合いの女性がそこにいた。カンボジアで最もアプサラが上手な女性と認められた、いわば「ミス・アプサラ」のパラー(OUK PALA)さんだった。日本のテレビ局が彼女を取材するために来るとき、コン君がいつも通訳をしてきたので、二人は知り合いになっていた。
パラーさんは、1979年生まれ。踊りの勉強を始めたのは11歳(1990年)のときだった。1993年にはシハヌーク王の娘ノロドム・ボパテビー妃(現在の文化大臣)から上述の「トップ・アプサラ」の賞賛を得た。1996年カンボジアの元観光大臣と結婚し、アプサラの踊りを一時中断し、一児をもうけたが一年後の1997年、離婚した。もともと有名な女性だったが、その離婚劇で、さらに話題となった人だ。まだ21歳。いま彼女は再び踊りを始め現役に復帰している。
芸術大学のあと、私たちはブランチを摂ることにして、モニボン通りの方に向かった。ベトナムのレストランで紹介されたプノンペンに出来たばかりの新しい日本レストラン「銀河」に行くつもりだった。開店は11時30分という表示が表に出ている。コン君が掛け合ってくれ、一時間早いが、開けてくれた。カウンターと、個室の座敷がいくつかあって、私たちは座敷を選んだ。きれいなカンボジアの女性がメニューを持ってきた。日本でいえば大衆的な日本食が置いてあった。日本料金より少し安い。こちらの水準で言えば、かなり高額だ。コン君は、600円ほどの値段の天丼を申し訳なさそうにして頼んだ。ドライバーも、メニューが全くわからないのでコン君を真似て天丼を頼んでいた。
コン君が女性になにやら話しかけている。女性は、前の店よりここのほうが少し給料がいいので、気に入っていると話しているという。ただ、座敷でひざを曲げてサービスしなければならないのがきついとのことだ。なるほど、半腰になったりひざを曲げたりして何かすることは、カンボジア人の生活にはないことだろう。
そこを出て、私たちはプノンペンの初日に回れなかった「観光スポット」を駆け足で回った。まず王宮。中に迎賓館や、シアヌーク王の住居、シルバーパゴダなどがある。シルバーパゴダは、床に銀のタイルを敷き詰めた寺院だからそのように呼ばれているのだが、中にエメラルドを彫った仏像があり、正式な名称は「エメラルド寺院」というのだそうだ。建物の外の写真撮影は許されるが、中は禁止で、建物の入り口でカメラを預けなければならない。
それから、ポルポトの残虐行為を目の当たりにする「トゥルールレン犯罪博物館」を駆け足で回った。元フランス式の高校(リセ)の校舎だった場所だ。教室を二つに仕切り、それぞれを犯罪人の留置や拷問の部屋に作り直していた。1979年ベトナム軍が解放したとき、小部屋のベットに14の遺体が腐乱した状態で残っていたらしく、そのときの遺体の写真が引き伸ばされ壁にかかっている。この14人は、ポルポト勢力の幹部と目されており、ポルポト政権末期に「政敵」として捕らえられ拷問されていたらしい。ベトナム軍による解放が近いと知ったポルポト軍が、退散する直前に「口封じ」のために殺害したものと思われている。この14人の墓標が、ここ犯罪博物館の中庭にある。
「ポルポトの不可思議なことが多すぎます。なぜ、証拠になるようなこのような写真をたくさん残したのか。1975年4月からプノンペン市民を地方に追いやって略奪を繰り返すのですが、時計だったら時計、鍋だったら鍋を一箇所にまとめて保管する奇妙な癖がありました。クツも、左足だけを集め一まとまりにし、右足の山とは別なところにありました。奇妙な蒐集の癖があったのです。それにしても、どんな理由で同じ民族をこれほど殺害しなければならなかったのか、いまでもカンボジア人は知りたいと思っています」
生まれる直前に、ポルポトに父親を殺され、生涯父親の存在を知らずに生きていく運命を背負わされたコン君が、淡々とした口調でそう言った。
それから、われわれは「ワット・プノム」を一回りし、その周辺にあるタマリンドの木などを撮影した。通常の入念に準備された観光ツアーでは、こんな回り方をすることはまずない。狭いプノンペンの街中だから、思いつきであれこれ回ってもたいしてイラつくこともない。なにせ、車の中はエアコンが効いているので快適のだから。
ふと思い立って、私はコン君にインターネットカフェのような場所はないかと尋ねたら、あるというのでそこに向かった。確かにコピーの出力サービスやPCのDTP編集機を貸し出すサービスなどの店が建ち並ぶ一角があった。窓ガラスに「Internet」の文字が見える。そのひとつに飛び込んで、日本にメールを送り、自分のホームページにアクセスしてみることにした。コン君も、日本に留学していたときにはコンピュータを専門にしていたので、面白がっている。意外と接続は快調だ。モデムのスピードも56Kで、思ったより速い。あいにく日本語環境が整っていないので文字化けしてしまうが、接続には問題がない。10分使ってUS1ドル。通りすがりに利用するサービスとしては安い。
日がかなり傾きかけてきた。もう出発の時間まで残された時間は少なくなってきた。私は、もう一度川沿いとスバイポペ寺院の方に行ってみたいと頼んだ。まぶしい黄色の王殿が「チャンチャヤ(Chan Chaya)殿」。水祭りのとき、シアヌーク王はここに座ってボートレースを観戦する。いまは、のんびりと浮浪者がハンモックに揺られて昼寝している。恋人だろうか若い男女が欄干に腰をかけて話している。川を背にしてチャンチャヤ殿の左のほこらが庶民に人気の「プレアン・ドンカー(Prah Ang Dong Kar)」である。偶然、結婚したばかりの男女が、ウエディング衣装のままここにお参りしている場面に出会った。ほこらの回りの浮浪者やこじきの群れの間を縫って、彼らは狭いほこらに入り手を合わせていた。こじきの老婆が、私に向かってなにかしきりに言おうとしている。「きれいだね」と言っています。コン君はこじきの言葉を通訳した。濁った老婆の目の奥に、かすかな祝福の思いが漂っている。チャンチャヤ殿の右のほこらは「タードンボーンデック(Ta Dombang Dek)」という。なぜか、こちらの人気はいまひとつだ。
それから、私はまた思いついて、かつてチェンポーン先生が歌劇「ラカンバーサ」の練習に使っていた建物があるはずなのでそこに行ってみたいとコン君に頼んだ。記憶によれば、5階建てで、2階に先生の事務室があり、5階部分が歌劇の生徒の寄宿舎のようになっていたはずだ。チェンポーン先生は、1979年にポルポト政権が倒れたあと、文化情報大臣(日本でいえば文部大臣)になった元芸術大学の先生である。先の首相選挙の際に名前が上ったこともあるが、現在は私財を投じて「クメール民族精神瞑想センター」を設立し、荒廃したカンボジア人の心の復興に努力されている。私の書いた本『スーはきっと踊りつづける』にも登場する。
それならば、あそこしかないといわんばかりに、コン君とドライバーは中央公園のロータリーを回って通りに入りすぐの場所にある大きな建物にクルマを寄せた。「先日火災があって、いまは使われているかどうかわかりません。入ってみますか」「ええ、できれば」そういうと、彼はドライバーに指示をし建物の門をくぐり正面玄関でクルマを止めた。
(ここが、あの練習所なんだ)私は、感激した。建物は縦長だと思っていたが、なかなか立派な横長の5階建てだった。ずいぶん傷んでいる。中に入ると、殺風景ななかに舞台の大道具のようなものが乱雑に置いてある。いまは使われている感じがない。中年の女性がいた。コン君が話しかけた。「確かにここがそうですね。前にチェンポーン先生がここにいたと言っています」。私は、なぜか懐かしい光景に再会したときのような胸苦しさをおぼえた。
そこからふたたび「ソテールー(Sotearos)通り」にクルマを進めた。左手が「スクゥォッター(不法占拠者)」のスラム街、転々と売春宿が並ぶ。そして右手に「サムダッチ・ソテールー(Somdech Sotearos)小学校」がある。この対比は、私にとって大きなショックだった。芸術大学に隣接する売春宿というのにも驚いたが、小学校の目の前の売街というのは脳天をかち割られるような衝撃だった。確かに、「聖と俗」はいつも隣り合わせにあるように思う。ミラノの教会の周りでは、麻薬の売人がうろうろしていたし、アムステルダムの旧教会の周りには世界中の人々に知られた「飾り窓」がある。しかし、それらが動き出すのは、日が落ちてからで、子供たちの目に触れることは少ない。大人たちの世界は、子供たちの世界と隔絶している。
しかし、プノンペンのそれは似て非なるものだ。子供たちへの精神的な配慮というものがまったくない。昼も夜もなく、子供の目を逃れる「仕切り」もない。いまのカンボジアの苦悩が、その悲惨な現実から読み取れる。中央市場でもチャンチャヤ王殿のまわりでも、人が集まるところには、浮浪者や乞食がうようよいる。彼らが危害を加えることはないが、日本人には内心穏やかでない。カンボジアのすべての矛盾が、蛆がわくようにゴソゴソとプノンペンに集まってくる。内戦の傷跡の悲惨さとはこういうことなのだろうか。
クルマはゆっくりと、ソテールー通りを往復した。私は、道の左右にレンズを向けて夢中でカメラのシャッターを切りまくった。
もうあとは、空港へ向かうばかりだった。
「最後に日本人のお墓に寄ってみますか。空港の近くですから」
コン君は、最後の最後まで私への気遣いを捨てなかった。(それにしても誰の墓だろう) クルマはやがてポチェントン空港のゲートに近づいた。道を左に曲がれば出国ターミナル。クルマをそれを素通りしてすぐ右に曲がった。程なく田舎道に入り、周りにはカンボジアの典型的な田園風景が広がった。家も高床式になっている。
「虎などの猛獣から身を守るためと、洪水の被害を防ぐためです」
高床式住居の起こりを、コン君はそう説明した。ほどなく、寺院にたどり着き、木の生い茂った境内の奥までクルマを進めた。黄色の僧衣を着たお坊さんが何人かいた。禁欲的な過酷な修行僧というより、失礼だがなんとなくひまを持て余してごろごろしている若いお坊さんのような印象だった。立ったまま私をじっと見ている僧がいる。右手をお尻のほうに隠している。何だろうよ良く見るとタバコを吸っているのだった。教師の目を盗んで吸っている中学生のようでおかしかった。お坊さんがタバコを吸うのは別に問題ではないらしいが、外国人に見られると気恥ずかしいのだといった。
ここがそうです、と案内された場所は、UNTAC軍に参加し武装勢力の襲撃で殉死した元自衛隊の「高田晴行さん」の慰霊碑だった。石の囲いがあり、立派なものだった。そこで手を合わせ、帰ってきた。
日はすでにだいぶ傾きかけていた。空気のきれいな田園風景は、目に焼きつくようにまぶしい。途中、沼があり少年がじっと水中をうかがって網を投じようとしている。それを沼の反対側で見物している子供が二、三人いる。魚取りの少年に私もジッとカメラを向けたままにした。右手を肩の上にかざしたまま、なかなか網を投げない。私も息を殺してシャッターチャンスを待っている。でも、じっと身動きせず、投げる様子がない。コン君が、ベトナム語で少年に何かささやいた。少年はニヤニヤしながら、えいっとばかりに網を沼の中央に向かって投げた。じっくりたぐり寄せたが獲物はゼロ。「観客」からため息が漏れた。コン君が飛行機の時間が間に合わないから、ちょっとサービスで投げてみてくれとでも言ったのであろう。彼としては、投げたくはなかったに違いない。申し訳ないことをした。でも最高の写真は撮れた。
私たちは、ポチェントン空港の出国ゲートの外で別れを告げた。旅の土産は何ひとつ買わなかったけれど、コン君との深い友情が何よりもかけがえのない「土産」だった。その彼とは、帰国後もインターネットの電子メールでやり取りしている。
プノンペンのポチェントン空港発ホーチミン行きの最終便。飛行機までは歩いて行く。私は30年ぶりに双発のプロペラ機(ATR)に乗った。振り返ると、真っ赤な太陽が地平線にゆっくり沈んでいく。昨日アンコールワットで見た落日とはまた違った迫力で西の方角を赤く染めている。飛行機の後部に機体から引き出した十数段のタラップを昇る。出発予定時刻は午後6時10分だったが、この飛行機も予定よりは早く離陸してしまった。
ホーチミンの「タンソンニャット空港」には7時近くに到着。トランジットの手続きをして、空港内に留まり深夜23時25分発関西空港行きの飛行機に乗り、日本に帰国した。 おわり。
●注意
他国から乗り継ぎ、ホーチミンのタンソンニャット空港経由で、関西空港に帰国する方はご注意を。ベトナム航空便もJAL便も23時25分、23時50分と出発時間がかなり遅いため、空港待合室でかなり長時間待たされることになります。待合室周辺の免税店やカフェなどは18時から22時頃まで閉まっているので、簡単な食事や飲料は自分で用意しておくほうが便利です。開店時間は、その日の都合で21時だったり22時だったりします。聞いてみると「あと30分」といいそれが「あと1時間」になり、それから「さらに1時間」待たされます(私の経験談)。「客がいるんだから早く開けてよ」と掛け合っても、まず無理。この国は社会主義の国だということを、こんなところで痛感させられます。実際搭乗開始までは、何時間も何もすることがない状態に置かれます。結局何か口寂しさを紛らわしながら時間を待つことになるわけですが、事情を知らないと「飢えと渇き」で苦しむことになります。事前に手提げかばんになどには「エビアン」「缶ビール」「つまみ」「サンドイッチ」「ハンバーガー」のようなものは買っておくほうがよいです。
第8話に戻る
トップに戻る
最新情報
プロフィール
遊佐へのメール
©Copyrights Yuza Taira,1999,2000,All rights reserved.
