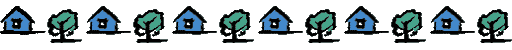
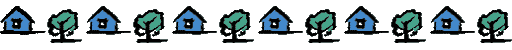
第8話 ついに来たアンコールトムとアンコールワット
翌朝4時モーニングコール。4時30分ホテルをチェックアウト。モニヴォン通りのホテルを出て、真っ暗な中を空港に向かった。早起きのカンボジア人だが、さすがにこの時間はまだ人々は寝静まっている。
コン君は、時間に関しては日本人以上に几帳面だ。カンボジアの飛行機は予約していても、込んでいると席がなくなることがあるので、国際線、国内線に関係なく常にリコンファームしておかないと危険だという。オーバーブッキングというより、スタンバイチケット(空席待ちチケット)を早めに売ってしまうことが多いようだ。予約しても来るか来ないかわからない客を待つより、目の前で待っている客にチケットを売りたがるというのは、考えてみれば当然のことだろう。だから、コン君飛行場だけは、早めに行ってゆっくり待っているほうがいいという考えだ。さすがに4時起きはつらいけど、責任感の強い彼の指示だから従うしかない。
搭乗の案内があってゲートをくぐろうとして客は少し待たされた。すると横から警備員に守られられたVIPの女性が先にゲートをくぐり飛行機に歩いて向かった。カンボジア人の間でひそひそと話声がする。コン君に聞いたら、カンボジアの文化大臣で有名な女性だそうである。背は小柄だ。
いつものようにゲートをくぐってから、私たちは歩いて飛行機に向かいタラップを昇った。タラップの下で、カンボジアの民族衣装の制服を着た女性係員が搭乗券の半券を切り取る。
乗った飛行機はボーイング737−400という小型ジェット機。便名はプノンペン発シエムリアップ行VJ320便。午前6時10分発。シエムリアップまで約45分ほどの飛行時間である。ホーチミンとプノンペンの間よりも距離は長い。離陸するとすぐ川幅の広いメコン川と、川幅の狭い(といっても広い)トンレサップ川の流れが、朝日を照り返して奇麗な光の筋となって見える。雨季が明けて間もないので、川筋以外の部分も広大な水溜まりが平原にいくつも光って見える。窓の外の景色を眺めながら、コン君は説明する。
トンレサップ(Tonle Sap)湖は生きている湖だ。カンボジアという国はちょうど中華鍋のような地形をした国土で、その鍋の底の部分がトンレサップ湖にあたる。湖の面積は、乾季で最大幅約70キロメートル。これが、雨季になるとその80倍の面積になる。また、深さも乾季では0.5メートルほどしかない。もっとも、そこは泥土だ。これが雨季になると14メートルを越える。雨季と乾季とでは、湖の表情がまるで違うのだ。鍋の底の例を思い出してみると分かりやすい。左右のいずれの窓にも、湖の表面が広がっているからその大きさは琵琶湖の比ではない。
人類誕生以前、カンボジアは海だった。その水が次第に引いて、カンボジアの国土が現れ、さらに水が引いてトンレサップ湖だけに水が残ったのである。かつて海だった証拠に、淡水に順応はしたがもともと海の魚の種類が三種類残っているという。「ふぐ」と「さより」だが、もう一種類はコン君思い出せなかった。
戦争以前、漁獲量は政府が管理し統計を取っていたため明らかだったが、世界一魚の取れる湖だった。乾季には、水が干上がって、魚が「なべ底」に追いやられるため、簡単に魚が取れた。トンレサップ川の河口は少し小高くなっているため、乾季が始まると湖に閉じ込められた魚が川に逃げ込むことができなくなる。鍋の底に追いやられるしかないのだ。
王宮前のチャンチャヤ殿の前に、メコン川とトンレサップ川の合流地点がある。5月から11月までの雨季にメコン川もトンレサップ川も水流は南に向かって流れるが、11月から5月までの乾季には、トンレサップ川の水流だけが北に逆流する。だから、合流地点でメコン川の流れの一部がU−ターンするようにトンレサップ川を上流に向かって流れる。席の前にある小さなテーブルを倒して、コン君がメモに川の流れを書いて説明してくれた。
収穫したばかりの水田が、赤白い大地の肌をさらしている。このあたり米は年二回取れる。いまは、収穫はおわり仕事から開放される時期だ。結婚式が急増する時期でもある。「あそこも結婚式があります」プノンペンの市内を回っているときコン君が家の軒先に吊るしたバナナの房を指差して言った。たわわに実をつけたバナナの房が二本垂れ下がっている。一本の房は自然のままの緑色。もう一本の房は全体を銀色に塗られていた。
シエムリアップに到着。要人を迎える人の群が三十人ほどタラップの下に待機している。文化大臣が降りたあと、私たち一般の乗客もおりた。シエムリアプは、田園の中の小さな空港だった。空港の回りには建物らしいものはない。ホテルまでは田舎道をクルマで約20分ほど走る。やがて道の左右に横幅の大きなホテルが転々と立ち並ぶ場所を通った。どれも、ヨーロッパのリゾートホテルのように洗練されている。行く手に見える建物らしきものは、すべてホテル。この町にいかに観光客が多いかを物語っている。これでもまだ足りないのだという。シエムリアップはプノンペンに次ぐカンボジア第二の都市。しかし、町自体は小さい。この町の住民は少ないが、訪れる観光客の数が年間を通して住民よりもはるかに多くいるものと思われる。
シエムリアップは少し小高い土地の上にある。だからその上に建てる建物には気を使う。アンコールワットの尖塔の最高が海抜65メートルで、どこにどんな建物を建てても、それがアンコールワット以上の高さになってはいけないという法律があるので、ホテルは高さのかわりに敷地をたっぷり取って幅で部屋数を増やす。だから、どのホテルも正面から見ると幅が巨大に見える。難点は高さがないから、ホテル内にエレベーターがないことである。だいたい平均すれば三階建てがホテルの標準である。そのかわり階段は急だ。アンコールトムやアンコールワットの石の階段が急なのとどこか通じている。ホテルの階段は、のちに寺院の石の階段を登るためのトレーニングにはもってこいだ。不思議なことだが、ホテルにチェックインした直後には、急な階段がしんどかったが、翌日アンコールトム、アンコールワットを観光して石段を昇り降りした後は、ホテルの階段が楽に昇れるのである。
宿泊するホテルはシエムリアップ川のほとりの「タプローム・ホテル(Ta Prohm Hotel)」。中の上といった感じのホテルだ。「タプローム」とは、アンコール・トムの城壁の外にある、自然ととけあった荒廃した趣きの寺院の名前。巨木の根が寺院の石にがっしりと絡み合っている場面をよく見かけるが、日本人には受けのいい有名な場所である。
チェックインのあと少しホテルの回りを散策してみた。シエムリアップにも川沿いに中央市場「プサーチャス市場」がある。「プサー」というのは市場という意味だそうだから「チャス市場」が正しいのだろうが、日本語のガイドブックなどには「プサーチャス市場」と書かれているものが多い。ここも背丈を気にしているのか、頭を低く体をちじ込めているように背の低い市場だ。観光地だから民芸品などの土産物屋が目立つが、食料品や衣類などもある。軒をかいくぐるようにして奥の方に入っていくと、そこにも中心に金などの貴金属商の一群があった。市場の構成はどこも似ているなと感じた。
各国の人間を瞬間に見抜いてその国の言葉で声をかけてくる。「おにいさん。おみやげいらない。安いよ」気持が悪いほど巧みな日本語だ。コン君に言わせると、日本人には特徴がある。頭が低いこと(つまり猫背ということか)と、カメラをぶら下げていることの二点からすぐに見分けがつくという。
いよいよ、アンコール・トムに向け出発することになった。シエムリアップの町の中心部を通る。シアヌークがここを訪れるときに泊る場所の前を通った。質素な建物に驚く。シエムリアップの最古で最高級ホテル「グランド・ホテル」が見える。ここでは、毎日観光客のために美しいアプサラの踊りをはじめとした宮廷舞踊が踊られる。スイスのNGOが管理運営しているシエムリアプ最大の病院が見える。正面の屋根の上にジャヤバルマン7世の石像が飾ってある。
プノンペンの雑踏とは裏腹に、この町の風景は穏やかで洗練されている。治安もかなりよく、観光客を保護する厳しい法律があるそうで、もし地元民と何か揉め事があると地元民が処罰されるケースが多いという。歓楽的施設はいっさいなく、サウナもマッサージもない文化的にはかなり上質な町だ。
アンンコールワットはシエムリアップの市街地から約7キロメートルの距離。地元の人々は、バイクや自転車で行く人も多い。クルマは北を差し参道に向う一本道に入った。途中に料金所のような場所がある。多数の警備員がものものしく料金徴収にあたっている。入場料は外国人一人一日につき20USドル。二日から三日間で40USドル、四日から七日間まで60ドル(2000年1月現在)という規定だ。これで何度も往復できる。最近クルマの運転手からも徴収するシステムに変わったらしい。小さい乗用車クラスは1ドル。12席以上のクルマは2ドル。15席以上は5ドルだそうだ。われわれの運転手も、全く知らなかったようで、不満の表情をあらわにしていた。制度変更は、その多くがお金の徴収にかかわることのようだが、なんの前触れもなく紙切れ一枚で突然言い渡され一方的に巻き上げられる。いまのカンボジアの問題と言っていい点である。
アンコールワットとアンコールトムに向う途中の料金所だから、当然政府の管轄だとばかり思っていたが、どうも違うらしい。ベトナム人が運営する民間の会社のものだというから驚いた。このベトナム人は今のフン・セン首相の親しい友人だという噂だ。政界や産業界の上層部、いわば表向きの顔はカンボジア人でも、実務面はベトナム人がかなり支配していることも、カンボジアという国の複雑さを物語っている。
ジャヤバルマン7世が建設した3キロメートル四方の一大都城「アンコールトム」の南門に到着した。荘厳な門だ。ここでいったんクルマを降り、歩いて門をくぐる。アンコールトムには五つの門がある。「北門」、「西門」、「南門」、そして東に二つ、「死者の門」と「勝利の門」である。
この都城の城壁の内部には有名ないくつかの寺院がある。目の前にそびえる最初の寺院は「バイヨン(Bayon)寺院」。ガイドのコン君は「Y」を「ジュ」と発音するので「Bayon」がどうしても「バージュオン」と聞こえる。どうしても「バイヨン」と発音できない。しかし、日本人の表記で単純に「バイヨン」と読ませてしまうほうにむしろ無理があるのかもしれない。寺院の壁画にはチャンパとの闘いの記録などが細密なレリーフで描かれている。兵士や庶民の当時の様子が分かって面白い。闘鶏や闘犬なども描かれている。船や魚のレリーフが彫られていることから、チャンパとの命運をかけた戦争は、トンレサップ湖を戦場に戦われたものであることがわかる。この辺のことについて詳しくは解説書をご覧いただきたい。
バイヨン寺院には、壁の素材である砂岩の石がくずれている部分がある。特に図書館として使われていた建物を中心にユネスコと日本政府の修復プロジェクトが進められている。
バイヨン寺院の次が、「バープーン寺院」。尖塔や外壁部分の傷みがひどくフランスを中心とした修復チームが活動している。修復予定の完成図はみごとに美しい。
このバープーン寺院のあたりに、子供の物売りがしつっこく纏わりついてくる。「おにいさん。1枚2ドル。買わない?」という日本語がどこからともなく飛んでくる。みると年の頃7、8歳の少女が目の前で絵葉書を差し出している。頼まれもしないのに扇子であおいでどこまでも横をついてくる男の子供もいる。ちょっとうるさい。
この、子供たち、近隣の家の子供だそうだ。学校をつくってやっても、「商売」のほうが面白いらしく、学校にいかない。身なりはみすぼらしいが乞食ではない。言葉も巧みだし、日本人の泣き所をよく知っているのだ。いよいよ駄目となると、計算づくで泣き出す子供もいるという。お年寄りの団体客が多いため、泣き出す子供を前にすると、たいてチップをあげてしまうのだそうだ。それを十分見抜いているのが、他ならぬこの子供たちなのだ。途中の小道で片足を失った男が3人民族楽器を弾いている。なかなか上手な演奏だったので、彼らにはこちらからチップを差し出した。ひとりの男の顔からうれしそうな表情がこぼれた。プノンペンでもそうだったが、目がどんよりと曇って絶望的な表情の物乞いもホームレスも、何かの拍子で笑うと、本当に心から喜んでいるように見える。笑顔を見る限り、人間としての希望を、彼らはまだ捨て去ってはいない。
しばらく行くと、「ピーミェンアーカス寺院」にたどり着く。寺院というより、急な階段がある小高い丘のような建物。皇帝は、毎日この建物の上に登って、眼下の池で女官たちが水浴びする光景を見て楽しんだという。もちろんそれ以外にも何か寺院建立の目的はあったはずだ。池は、男の池と女の池があり、女の池の方が寺院に近い場所にあり、男の池よりはるかに大きい。
それからわれわれは、勝利の門からいったんアンコール・トムの壁の外に出て、クルマでタ・プローム寺院に向かった。寺門をくぐってから、参道を1キロメートルほど歩いたところに寺院がある。自然と渾然一体となった建造物だが、このあたりの寺院の中では最も荒廃し傷みが激しい。この寺院の修復は、ほぼ絶望的と見られる。
スポーンというベージュ色の木肌をした背の高い木が、まるで獲物をつかんで空中に舞い上がらんとする鷲の爪のように、その強靭な根をがっしりと建造物の砂岩の石に食込ませている。日本の写真家は、好んでこの寺院の画像をしばしば紹介するので、日本人はタ・プローム寺院のことをアンコールワットと混同している人々も少なくないが、別物である。
この寺院は、アンコール・トムを建設したジャヤバルマン7世の母が亡くなったとき、慰霊のために建造したものである。当時はこの寺院の中でおよそ2万人ほどの人々が暮らしていたとされる。お坊さんや皇帝おかかえの宮廷舞踊の踊り子たちがここに住み、主にカンボジアの古い文化を継承する役目を果たしたいわば大学のような施設であったと聞く。
ちなみに、カンボジアは19世紀末から第二次世界大戦後までフランスの植民地であったが、その間フランス政府は公用語としてフランス語の使用を強制した。カンボジア語は仏教寺院の中で、死に絶えることなく保存されていた。
タ・プローム寺院を見学し終えてから昼食と休憩のため、われわれはいったんシエムリアップのホテルに帰ることにした。距離にして約7キロメートル。観光客は、いったんシエムリアップに引き上げるのが普通のようだ。
ホテルは「タ・プローム」ホテル。チェックインしたときには気づかなかったが、名前の由来がわかってから、ますますこのホテルが気に入った。次の約束は3時半。昼食を摂ったあと、私は部屋で少し体を休めた。
コン君は、約束の時間より少し前に、再びロビーに来ていた。それから私たちは、いよいよ「アンコール・ワット寺院」を目指し、朝と同じ道を北上した。アンコール・トムとアンコール・ワットとは近い。クルマで4、5分の距離である。
ホテルのあるシエムリアップからみると、アンコールワットは、アンコールトムの手前にある。例によって、物々しい警備員がいる料金所を抜けて、すぐに写真などで見覚えのある懐かしい石造寺院が現れた。まわりが広い濠で囲まれているため、寺院の正門までは長い石の橋を渡る感じだ。ナガ(大蛇)の形をした欄干を間を正門めざして歩く。途中で寺門をくぐる前に斎戒沐浴したという階段状の踊り場があった。西日を背中に浴びながら寺院の門をくぐると、ひときわ高くそびえる中央の塔が威容を放つ。
ついにここまでやってきたかという思いに感慨もひとしおだ。つい先日まで、アンコールワットとは、まるで険しいジャングルの奥深くにある遺跡で、そこにたどり着くには内戦や、地雷、それにひるやマラリア蚊など熱帯特有のいくつかの危険動物との遭遇を覚悟しなければならないと思い込んでいた。だから、体力のあるうちに一生に一度しか行けない場所だと思っていた。とんでもない勘違いだった。アンコールワットは、カンボジア第二の都市シエムリアップから近い場所にあり、天気がよければ軽装でハイキング気分で行けるのである。地元の家族連れなどは、アンコールワットの堀の周辺にビニールを敷き、簡単な弁当を持参してピクニックを楽しんでいる。まるでどこの町の郊外にもある公園の赴きである。
しかし、アンコールワットは12世紀前半に、スーリャバルマン2世によって建てられた。東西1.4キロメートル、南北1.3キロメートルの石の壁に囲まれた単一寺院だが、寺院の壁に刻まれた微細なレリーフは、好きな人にしてみれば飽きることがないだろう。「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」といったインドに発祥した一大叙事詩をモチーフとしたレリーフは、足元から頭上まで壁いっぱいに物語を刻んでいる。
ガイドのコン君が、壁の主要な部分について簡単に説明を加えてくれる。数百メートルも続く壁は、東西南北四方にある。とても見きれるものでゃないし、説明しきれるものでもない。おそらく、日本を離れる前にまず基礎的なことを勉強したうえで、レリーフを鑑賞すれば申し分がないといえる。
アンコールワットの詳細については、解説書をごらんください。旅行者は、寺の門をくぐってからは、中にトイレも休憩所もないので気をつけていただきたい。寺門をくぐれば、ただひたすら壁や塔を眺めながらゆっくりと歩く以外にない。寺門の外で、寺門に向かって左手に、休憩所のような場所があり、ここに数戸の男女共同の簡易トイレがあるが、利用するのにはやや勇気が要る。カギがちゃんとかからないし、閉め切ると昼でも中が真っ暗になる。いちおう「水洗」ということにはなっているが、その水洗というのは狭い便所の中に水桶のようなものがあり、自分で水を汲んで使用済みの便器に掛けて流すやり方である。なお、この水は「紙」のかわりに利用するものでもあることにも注意すること。ほっとして出てくると、チップをねだる近所の子供たちに囲まれてしまう。トイレだけは、出掛けにホテルでちゃんと済ませてきた方がよい。
もうひとつ、言っておきたいことがある。アンコールトムもアンコールワットも、ただ平地をゆっくり見てまわるというのではなく、随所に急な石の階段を昇り降りしながら移動するので、すべりにくい靴を用意すると同時に、足腰をある程度鍛えておいたほうが良いのではないかと思う。階段が急であるというのは、東南アジアの仏教寺院に共通して見られるように思うが、アンコールワット周辺の寺院は特に勾配が険しく、石の階段の出っ張りが少ない。登るのはいいが、後ろを振り返るとちょっと足がすくんでしまう。
石の階段を急にしているのは、天に近づく行為にふさわしい忍耐と勇気を試すために意図的にそうしたのだという。アンコールワットは、お年寄りの観光客が多い。見ていて危なくてしかたがなかった。ちょうど日本からきたお年寄りの団体客がいた。目の前の急な階段を登って向こう側に行かないと、次のスケジュールをこなせないとツアー・コンダクターは声を荒げて説明していた。激励なのか威嚇なのかわからないが、お年寄りたちは必至になって登っていた。
さて、ひととおりアンコールワットを見終えた人々は、5時頃から近くのバーカイン山の頂上に昇り、そこの寺院の西側の石段に腰掛けて5寺30分頃、遠くに沈む落日を見るのがお決まりのコースである。山といっても、アンコールワットのすぐ近くにある、小さな丘というべきか。ふもとから頂上まで、速い人で10分くらいで登り切る。そこから、さらに急な石段をいくつか昇り、荒れ果てた寺院の上にたどりつく。
ふもとから山の頂上までは、象にのってマハラジャ気分で登ることもできる。こちらは登り切るのに約15分かかり、ひとり15USドルである。わたしは、興味本位で象に乗って登ってみたが、急な山道の斜面を何度か折り返しながら進むので、背中の「客席」がけっこう左右に揺れて恐ろしい。歯を食いしばって15分(以上に思えた)間ただ体を突っ張っていた記憶だけが残っている。
頂上は、人でいっぱいだった。西に面した石段のどこかに席を見つけて腰をおろす。まるで、野外コンサートの風情だが、地方の野球場の外野席の芝生に腰を下ろしている風でもある。遠くで赤い火の玉が次第に地平線のかなたに沈んでいくさまが美しい。アンコールワットを見学した日の最後を締めくくるには最高に贅沢なクアイマックスだ。乾季で天候に恵まれたことを神様に感謝しなければならない。ここまで来て雨降りだったということも多いらしい。
日が沈むと、足元が危くなるので、薄あかりのなかをみんないっせいに下までくだる。あとは、ホテルに帰って夕食をとり体を休めるだけだ。
この夜運良く、タ・プロームホテルでは宿泊客を対象とした「民族舞踊」のショーの開催日にあたっていた。6USドルを払えば、道を渡り切ったとこに常設されているホテル専用のステージで、カンボジア特有の踊りを見た。素晴らしい踊りだった。漁師の踊り。ココナッツダンス。そして、アプサラ(天女)の踊りなどを楽しませてくれた。これは、ぜひ見ておきたい伝統芸能だ。シエムリアップでは、最高級ホテルとして知られるグランドホテルが、毎日ショーを開催し、踊りも最も格式が高いと聞く。それ外にはタ・プロームホテルが週3回ショーを見せるだけである。
第7話に戻る
第9話に続く
トップに戻る
最新情報
プロフィール
遊佐へのメール
©Copyrights Yuza Taira,1999,2000,All rights reserved.
