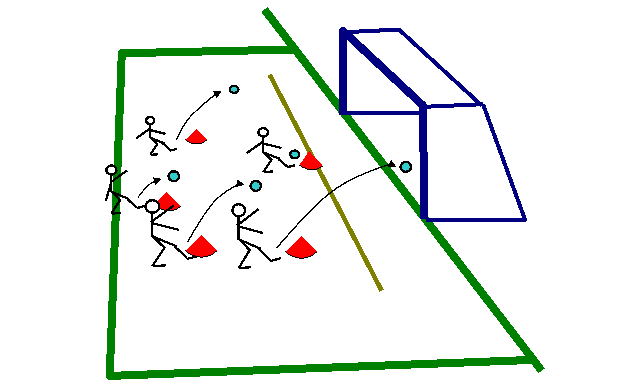|
1年生の練習内容 2001年6月号① 作成:平成13年6月23日(Rev.A) |
|
目 次 ●はじめに |
|
●はじめに スポーツは全般的にそうだが、特にサッカーは、少なくともやる気と元気さえあれば体力差や技術の差はカバーできるものだからだ。 |
|
ファミコンの技術習得のスピードは、大人では真似できないものが子供にはある。サッカーでも同じ様に無限の可能性を持っているはずだ。大人がやっている練習内容のコピーを、1年生に当てはめてうまくゆくだろうか?そんなはずはない。なにか1年生に適した練習内容があるはずだ。ここはひとつ自分で理想的な練習内容を追求していくしかなさそうだ。実際にコーチとして指導をしていく過程で、誰かに相談したいのは、やる気のない子をその気にさせる方法とか、出来ない子への適切なアドバイスの方法だ。しかし、そういうことが書かれている指導書は少ない。また、コーチは自分では簡単にできても、教え方のコツは案外わからないものだ。小生もそのうち、子供にどう教えたか忘れてしまうだろう。そこで、実際に悩んだ内容やその時どう指導したかを、できるだけ早めにドキュメンタリー・タッチで残しておくことにする。理想と現実のギャップを埋めるべく、まさに成長過程のスタート地点にいる1年生の子供達に対して、試しては修正していける絶好の機会でもあるからだ。 |
|
1年生を教えるのは初めてのことなので、何から何まで手探り状態である。サッカーの技術に関しては、無菌状態の子ばかりといってよい。教えたことがすぐに結果として表れてくる。指導を誤って悪い癖をつけさせてしまい、後で直しにくくなっては大変。技術に対してもそうだが、やる気とか自信に悪影響を与えてはならない。そういう意味ではいろいろなメニューをやらせてみて、「すぐに出来そうか/とても無理そうか」、あるいは「夢中になっているか/つまらなそうにしているか」等、反応を見ながら都度修正していくやり方で進めていこうと思う。 |
|
幼稚園に通っていた子がほとんどと思われ、「集合ー!」といったらすぐに集まってきた。これには正直、幼稚園の先生方に感謝というのが本音。次に「おはようございまーす!」といったら、全員が声を揃えて大きな声で反復してきた。『ウーン、やっぱり子供には、こうした素直な時期があるんだなー。すでに集団行動の基本が出来ているではないか。これなら、余計なエネルギーを使わなくて済むので指導に専念できる。』ただ、この純粋無垢な気持ちを、これから先どこまで引っ張っていけるだろうか?飴とムチをうまく使い分けながら、こちらも出来る限り素直に正直に対応していこうと思う。 |
|
まずは他の学年がやっているように、手始めにグランドをドリブルで一周させた。だれもさぼらず一生懸命ドリブルしていた。終わった子供達は皆、地面にへたり込んだことでそれが分かった。1年生にとっては、けっこうハードな内容かもしれないが、極めて大事な基本練習なので練習開始時には必ずやるようにする。 |
|
名前が分からないのでは、指導はうまくできない。 「それでは丸くなってください。ここから順番に、小学校名と名前を言ってください。」と言って全員に自己紹介をさせた。高学年の時は連絡網等全て苗字だったので、ファーストネームで呼ぶことはなかった。しかし、どうも親しみがわかないし、子供達同士もコーチの真似をして他人行儀の呼び方になってしまう。1年生に対しては、苗字は置いといて、名前で呼ぶことを徹底することにする。 「ゆうま」「ゆうた」「ゆいと」「いくと」「けんた」「たくみ」「りょうた」「しょうた」「そうたろう」「のぞむ」・・・。似たような名前が多い。最近物覚えが悪くなって、とっさには名前が出てこない。忘れたらその都度、子供自身に聞いて確認しているが、そのうち半年もすれば名前と顔が一致するようになるだろう。 |
|
リフティングはサッカーでは基本中の基本だ。正確に蹴ったりトラップしたりする技術の習得だけでなく、実は“片足でボールを扱う”ための“ボディバランスの養成”に役立つ(・・・と、何かの本に書いてあった)。1年生に対しての基本リフティングとしては、①もも、②足の甲(インステップ)、③頭、の3個所でボールを扱えるようにし、その他は機を見て応用編でやることにする。まずは、一番やりやすい“もも”から始めた。 ①“もも”のリフティング 「それでは自分のボールを両手で持ってください。手に持ったボールを軽く上に上げ、落ちてきたボールを“もも”で1回突き、それを両手で掴みます。これで1回です。」 と言って見本を見せる。「はーい。“もも”で突いたボールを掴めた人は手を上げてください。」と言って出来たかどうか確認する。だれでも出来ることを最初にやらせて、自信をつけさせてから次のステップへ進もうとしたが、以外やこれすらすぐに出来ない子がけっこういるではないか。大半は、ボールを“もも”に当てたはずなのに、なぜか前の方に飛んで行って掴めないのだ。さらには、“もも”に届かない所に手で投げてしまい、“もも”に当たらない子さえいる。 でも、練習しているうちに出来るようになったらすかさず、「そう、そう、よく出来ました。すごいねー。」と誉めてやると喜んで続ける。とにかく、今まで出来なかったことが出来るようになった、という喜びがあるので、“出来るの当たり前だよ、そんな簡単なこと。”と思っても顔に出さずに一緒になって感激したり、なにかしら激励の声を掛けて行くことが必要なようだ。 「さあ、次は同じことを続けて10回やってみよう。」と言って見本を見せ、再度出来た子の確認をする。 「次は、利き足ではない方の“もも”でやってみよう。」と言って同じように最初は1回、次に10回行わせる。 ここまでは、自信をつけるための導入部分である。これからが本番である。 「それでは、左右の“もも”で2回連続して突いてみよう。」と言って見本をみせる。この時右足でしか出来ない子には、「利き足で2回連続でもOK。」と言う。すぐに2回出来た子には、「連続3回できるかな?」と課題を少しずつ上げて、無理なくしかも飽きがこないようにやらせる。 ②足の甲(インステップ)のリフティング 手で投げ上げたボールを、足の(指に近い方の)甲に当てて手で掴ませる。これを1回とする。これはなかなか出来ないようだ。足の甲ではなく、つま先やすねやその他に当ててしまう子が大半である。そのため、蹴ったボールが前に飛んで行ってしまって、なかなか手で掴めない。 ももの場合と同じ様に、これを10回やったら、逆足でも10回やらせる。多分出来ない子がほとんどだが、途中で打ち切って、「それでは、左右の足で連続2回蹴ってから手で掴めるかなー?」と言って見本を見せる。利き足でしか出来ない子には「利き足で2回連続でもOK。」と言って、できるだけ連続で2回以上に挑戦させる。 ③頭のリフティング これはいきなりではうまくいかない。なぜなら、頭のどこに当ててよいか分からないからである。そこで、次の様にやる。「両手でボールを掴んでください。掴んだら、両手を引いて自分の頭にボールを当ててください。さあ、10回連続でやってみよう。」と言って見本をみせる。恐らく全員目をつぶってやっているはず。そこで、「次は目をあけて、ボールの縫い目を確認しながら10回やってみよう。」と言って再度見本をみせる。この時わざと力強く当てて、しかも目を“カーッと見開いて”、全然痛くないといった風にやる。ここまでやってもまだ変な所に当てている子には、おでこの髪の生え際に近い所を指で押さえて「ここ」と言う。 次に、上(空)を向いて同じことを10回やらせる。ここまでやると、頭にボールを当てるという恐怖感は相当取れているはず。「さあ、次はボールを手で頭の上に上げて、今まで当てていたところでついてからボールを掴んでください。これで1回です。」と言って見本を見せる。出来た子には、「じゃあ、2回連続で頭でついてから手で掴めるかなー。」とすかさず言って見本を見せる。 ここまで来れば、自分で投げ上げたボールを、比較的正確に額に当てて前に飛ばせるようになるはず。 とにかく、ヘディングというものは、最初に恐怖感みたいなものを持たせたらそれで終わり。一度ついてしまった恐怖感を後で取り除くのは至難の業となる。ちょっと面倒だが、導入時期は慎重に、全員が必ず出来る内容を心掛けた。 |
|
1年生のほとんどの子は、つま先(トー)でボールを蹴る。足の甲(インステップ)では蹴らないというより蹴れない。止まったボールや転がってきたボールならともかく、浮いたボールを強く遠くに蹴るにはトーキックでは無理。試合をやっていて、いつまでもボールを遠くに蹴れないのでは話にならない。子供達も遠くにボールを蹴れるようになったら、自慢になるし面白みも倍増するはず。 理屈をこねた反復練習では面白くないだろうと思い、ゲーム感覚でやらせることにした。既にインステップのリフティング練習は最初にやっているので、当てる所は分かっているはず。 まず全員をネットのあるゴールの前に集合させた。その後、ゴールから2~3m位の所にゴールラインと平行に線を引いた。一人一人に小さなコーンを渡し、各自のコーンを線上に置かせ、その後ろからゴールへ向かってパントキック(手で投げ上げたボールを地面に落とさないでインステップで蹴る)をさせる。「蹴ったボールが直接ゴールラインを越えたら、自分のコーンを大股で一歩分後ろに下げてください。ペナルティエリアの外まで行った人がチャンピオンです。」と言ってから、一斉に始めさせる。皆チャンピオンになろうと、夢中になってやり出す。ゴールへ入れるのはあくまでも目標で、ゴールの上を越えようが、横にはずれようが、ボールが直接ゴールラインを越えたらOKとした。せっかくインステップにまともに当たってボールが遠くに飛んだのに、ゴールに入らなかったということでやり直しでは目的が違ってくるからである。
しばらく見ていたら、どうしてもうまく蹴れない子が何人か出てきた。見ていてその原因が2つ分かった。1つは、足の甲ではなく、つま先の方に当ててしまうから。もう1つは、蹴るタイミングがずれている。つまり、手で投げ上げたボールがまだ上がっている途中か、上がりきった高い所で蹴ろうとしているからである。しかも、足だけ出して取りあえず当てている感じである。強く蹴るには、ボールが落ちて来た所を蹴るのがよいが、まだ難しいようだ。そこで、うまくいかない子には静止したボールで特訓をするようにした。 「うまくいかなかった子はコーチの所に来て特訓です。」と言って、一人一人呼んでコーチが低い位置で持ったボールを蹴らせる。注意する点は2つ。1つはインステップに当てること。もう1つは勢い良く蹴らせること。「もっと強く蹴って。もっと。もっと。」と言ってやると、手に相当の衝撃が来るようになる。しかし、せっかく感触を覚えたはずなのに、自分で投げたボールになると、また元の悪いクセが出てきて失敗する。失敗したら、またコーチの所で特訓、というのを繰り返しているうちに、半数は大体うまく出来るようになった。始めてから10分位経過したところで、ようやくペナルティエリアを越えた所まで行って直接ゴールラインを割る子が出てきた。「はーい。***がチャンピオンでーす。終わりー。」と言って、ゲームを一旦終了させた。 |
|
前のパントキック勝負が終了したので、再度全員をゴール前に引いたラインの所に集め、同じ様にライン上にコーンを置かせた。 「さあ、今度は手で投げ上げたボールをワンバウンドさせてから、同じ様にインステップに当てて遠くへ飛ばします。今度はノーバウンドで蹴っては駄目です。また、2回バウンドしてから蹴るのも駄目です。必ず、バウンドは1回だけにしてください。ボールが直接ラインを越えたら、さっきと同じ様に大股で一歩分コーンを下げてください。最後にペナルティエリアの外まで行って、そこから蹴ってラインを越えたら優勝です。」 ワンバウンドしたボールを蹴る方が、より実戦的である。この方がなぜかうまくいく子もいる。ちょっとした違いで、さっきの練習に飽きた子も、気持ちは振り出しに戻って一生懸命やっている。うまくいかない子には、先ほどと同じ特訓でコツを教えてやる。より親近感が沸くのか、毎回特訓を受けに来る子もいる。特訓で感触をつかんだ後でも、自分の手で投げ上げたボールだと何回やってもうまくいかない子がいた。よく見ていたら、手で投げる動作が影響してバランスをくずし、蹴るタイミングがずれてしまうようだ。これを直すには、やはり何回も何回も本人が一生懸命練習するしかないようだ。見ていると、何回かに1回はうまくいく時もあったので、そのうちにコツをつかむだろうということを実感した。 そうこうしているうちに、ペナルティエリアを越えたところから蹴って、ゴールラインまで飛ばした子が出てきてゲームは終了した。 |
|
今後は、技術の進歩に合わせて次々と課題を変えていく予定である。最終的には、昨年度の6年生の内容までもって行くようにしたい。 |